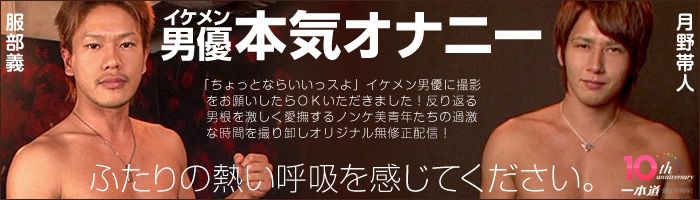�Ɍ��̋C���ԁI181�n �Ռ��̃^�[�{�T�E���h�@Vol.1
�L�n90�n����Ԃɂ������o�̓G���W���J���̐��ʂ܂��A���S�̗ʎY�C���ԂƂ��Ă͏���500PS��
��o�̓G���W�����ڎԂƂȂ����A����22�N11��6���Ƀ��X�g�������}������181�n�ɂ��Č���Ă����܂��傤�B
���肪�낤��
�L�V�T�Ƃ����H���Ԃ��������Ă��܂�
������>>5�͓S���P��̍r�炵�ɂ��X���[����
�Ȃɂ�������
����Ȍ������m������t����́H
������Ƃ��Ȃ�
���������ɂ���Ȍ������m������t����́H
�����\��ł�2�����B
�������A��ԉw�����Ȃ��B
�M�A��2���䂦�ɉ�������܂Ŏ��Ԃ������邩��d���Ȃ��B
�����ȓ�̒�ԉw���Ђ�E��܂Ƃ��ƌS�R�{2�`3�w�O��Ȃ̂ɑ�
���͌S�R�{�F�s�{������̂ǂ��炩�A�܂��͂��̗�����������
2�����Ƃ����̂͏������͂Ȃ��낤���ǁA485�n�Ɣ�ׂĂ����F�Ȃ����肾�����ƌ����������ˁB
�Ԃ����Ⴏ583�n�����āA�Ȑ��ʉߑ��x�̖���485�n���͒x���������ˁB
���Ȃ��Č��\�B
��聨�Ďq�����ʂ������ǁA58�n��������K���ɂ��Ȃ��Ă���������
���H����͒P����Ԃ������ē��ɓ~���͒x�ꂪ���B
����Ȓ��悤�₭�J���~��Ă��������̉^�]�͂����[�����E�E�E�B
�ȍ~�͎g�p��~�H
�B��S�ɒ��蒦�肵�Ă��邩�炾�낤���E�E�E�B
����Ⴀ�L�V�T�Ƃ������Ă����
ttp://kiha181.com/
���̓��C���R�z�����͐V�����̌�ǂ��ɂȂ�̂ł܂����葖�肾������B
������ăX�[�p�[�`���[�W���[����ˁH
DML30�̓^�[�{�`���[�W���[�����ǃC���^�[�N�[���[���������B
�C���^�[�N�[���[����������Əo�͏オ���Ă���ˁB
������4�o���u�^�[�{���ĉ���I�@�\���Ǝv�����ǁB
�x����T���i���Z�b�g���o�邩�Ȃ�
�����͓��}�p�ł����ʎԂɃ��N���C�j���O�V�[�g�̓[���̎��ゾ����
���̌�͒�������]���������B
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
���邹����A�o�J
���̓_�ł́A��N�̂͂��Ƃ┒�n�A���v�X�A�����₵�������A�����Â��̂ق������x�������̂ł͂Ȃ����ƁB
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
���Ƃ��_�̕t�߂Ƃ��Ǐ��I�ɂ�����
���S�F�������Ă���p���B��Ȃ������̂��c�O�B
�L�n187�n�Ȃ�A�͂�1.8km���x��120km/h�قǂ܂ŏ\���ɉ����ł��邼�B
����ɂ��Ă��A181�n�ȍ~�̷�65�66�47���Ĵݼ�݉���
�₩�܂��������Ȃ��B��o�͂̌��Ԃ�H
�K�X�^�[�r���Ԃ����
��40�͔��d�p�̃G���W�����g���Ƃ��A�Ԃ����Ⴏ�L�蓾�Ȃ��E�E�E�B
�G���W���̊����d�ʁi2,720kg�j�̊��ɂ́A�o�͂�220�n�͂������B
���܂��ɁA40�g���߂��̉ߑ�Ȏԏd�ƁA�ᑬ��ł͔�����ȕϑ��@�ݒ肪
�Ђ����A���͐��\�̓L�n20�Ɣ�r���ĂقƂ�nj��サ�Ă��Ȃ��B
�L�n40�̉t�̕ϑ��@�͋��^�Ԃ�3�i6�v�f�^�̕ϑ��@�Ɣ�r����
�N������͔��ɕs���ȓ�����1�i3�v�f�^�ł��邽�߁A
�G���W���̉�]�����������ɂ́A���i�͔��ɂ������Ƃ����������������B
�܂��A�g���N�͒i�Ⴂ�Ȃ낤���A����ł��Ȃ��E�E�E�B
�G�A�R�������Ȃ��������J���̂ł悩�����B
�L�n�W�Q�ɔ�ׂċ@�B���̒ʘH�������ĈÂ������̂Řg�t���̌u������
���܂��đD��̂悤�ȕ��͋C�������B
�Ԃ����Ⴏ�g���N�̑召���̂͂ǂ��ł������B
�Ԃ͍ō��o�́@�ԗ��͒�i�o��
�r�C�ǂ��������I�[�o�[�q�[�g�p�����邾�낤����
�w���łɊ����G���W�����������āA300�n�͂Ɍ��コ�����������܂��B�x
�w���t�o�C�N�̃{�A�A�b�v�Ɠ��l�A�G���W���̃V�����_�[�������̈��͂̑ς����邩���l����K�v������ˁB�x
�w�ϑ��i�ō�����܂ň������������A80km/h�ȏ�̑��x�ő�����Ԃ̕����y�������B�x
�w70�`85km/h���x�ł���ƒ����i�ɓ���悤�ȋC���Ԃ́A���x�����������A�������̑����^�]�����������Ԃ�
�g�����ɂȂ�܂���B���������ƁA��ÓS���̓��}�`�C���Ԃ������ł��B�I�����䂪�Ⴗ���āA�قƂ�ǒ����i�ɂ�
���炸�A�������̈����ϑ��i�Ő�߂���^�]�����|�I�ɑ����A�R�����낵���Ȃ������ł��傤�B�x
�L�n�P�W�P�n�u���Ȃ́v�Ō�̐킢
>>47
�m���ɁB
���\�ʐ^�c���Ă�����
�w�����ɁA�u���[�L����������ςȂ��ɂȂ��Ă��Ȃ����̓_�����s���B�x
�w������A�u���[�L��1��2�̒i�ł�������ςȂ��ɂȂ��Ă���A
�čs���s���ɋ}���ɑ��x��������̂ŕ�����Ƃ����B�x
�������A���̐F�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ���?
>>53.>>56
�I�C���E�V���b�N�̎Y���L�n391�n�A�g���u�������Ŏ��p������...
�Ȃǂ̋Z�p�I��肪�傫�������݂����ł��ˁB
�o�X�݂����ɂb�m�f�Ƃ����Ȃ瑼�ɐF�X�ł����������c
�Ă��A�܂����ւɉ�̑҂��Ŏc���Ă�́H
>�Ă��A�܂����ւɉ�̑҂��Ŏc���Ă�́H
�L�n391����Ȃ��āA���ւɂ����̂̓L�n181�n���Ď��B
�L�n391�́A�S�����肷��b����������...
�ʏ�͂�����x�]�T���������ē��}�^�d�Ԃ̏ꍇ160�L���܂ō��܂�Ă��邪�B
���}�^�d�Ԃ̍ō����e���x��160km/h�ł���
���ۂɂ͏o�����Ƃ͂Ȃ�����
���ŎR�x�}�Ȑ��̒���������181�n�������悭��������͂����
�J�������͐U��q���ȑO�̎���ł����āA
�����z��DMH���ڂ̋}�s�`�C���Ԃ�荂���œo��ł���p���[���Ђ����狁�߂�����
���̊��ɂ͎R�x�d�l�ł������悤�ȋC�������
���߂�Wikipedia�����āA�Q�l�ɂȂ����B
���É��H��Ɩ��É����@�悪�A���R����I�����ւ̉^�p��
���₵���A�Ƃ���������ɋ�����B
�ϑ��@���ϒ���ւ��������̂܂܂��ƕs�s�������������߁A
�̂��Ɏ蓮�Ő�ւ�����悤�ɉ������ꂽ�A�Ƃǂ����œǂ�
�悤�ȋC�����邪�A�Y�ꂽ�B
http://yuzuru.2ch.sc/test/read.cgi/jnr/1319900071/
�\�Z�Ǝ��Ԃ�������ł��ςݏグ�Ă����Ȃ�p�[�t�F�N�g�ȋ@�B�ɂ��o�������낤���ˁB
����������肶��Ȃ���
�������̈Ⴂ
�]������܂��Ă��Ȃ������̂��A�s��������Ƃ͏����ĂȂ������B
��ɁA�o�͂��ߑ�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂����������悤�ɂȂ���
���肵�ĉ^�p�ł���悤�ɂȂ����悤�� �AWikipedia �ɂ͏����Ă���B
��o�̓G���W���Ƃ���ɑg�ݍ��킹�\�ȕϑ��@�ɍ��킹�Ďԗ�����������������
���ʂƂ��Čォ�猩��Ε��R�����K���ɂȂ���������̂ŁA
�X�P�n�ł̃e�X�g�����������Ƀ����T���g�E�ɊԂɍ��킹�悤�Ƒ�}���ō���āu���Ȃ́v�ɓ˂�����������_�ł�
�ߓ����O�A������j�Ƃ����������̍��S�v�������̊����A�́A�����܂Ő[���v���ȂO���ɂȂ������Ǝv���
��ɋ�B�В��ɂȂ����Έ�K�F���͓����v�������ŊJ���ɓ���������l�̔������A
���̕ӂ�̃O�_�O�_�Ɏ������ڂ�������ɂ��Ă͌�������ł���
��̕��Ƃ������A�c�Ɣ����炩�Ȃ�̈��͂���������Ȃ����B
���Ƃ�43.10�ɊԂɍ��킹�Ăق����ƁB
�L�n91�Ŏ������Ȃ���A�Е��ŃL�n181�n�̐}�ʂ������悤�ȏ������낤�B
�Z�p�����炷��A�u�����A���ق��Ă���v�ƌ������������̂��낤�ȁB
�Ӗ����킩��Ȃ��B
�����̋Z�p�͂Ǝj���ʂ�̗\�Z�Ǝ��ԂŁA�R�x���p�̋C���Ԃ����S���J�������牽���ł��Ă����Ƃ����H
�Ӗ���������Ȃ����Ă��O�n���Ȃ́H
�����ł��Ă������ĈӖ��������
�Ӗ����킩�����Ă��O�n���Ȃ́H��
���O���n���Ȃ�
���l�ɂ킩��悤�Ȃ����Ƃ������͏�����
���X�A���a�R�O�N��㔼�̍��S�ŎR�x���ɓK���Ă����C���Ԃ�DMH�G���W���Q��ڂ̂T�O�ԑ�C���Ԃł�����
����ł��u�܂��܂��A�Q��G���W���Ԕ䗦���グ���Ґ��łȂ��Ƒ��x���łȂ��v�Ƃ������x��
����ŒP���ɁADMH���ꡂ��ɋ��͂ȃG���W������Ă݂��͂�������ǁA
�����̋Z�p���ƂP�i�����ϑ��@�������Ȃ�����A
�R�o��������^�]���A�Ɨ~�������ėp���܂ōl���Đv������A181�n�ɂȂ���������������낤�B
�����Ɍ��̂Q�O�O�OPS���́u�_�v�����o���āA����Ŕ�s�@������炦�炢�ڂɑ��������R��f�i�Ƃ�����ȁB
���{�@���������Q�O�O�O�n�͋��́u�_�v��������ǁA�ߋ���1�i2��������A
�r�C�ߋ��@������B29�ɔ�ׂč����x���\�������Ȃ������̂��霂�����
�u�_�v�ɂ��Ă͋Z�p�҂����肷������B�����̓��{�̋Z�p�����ł͋���
���x���ŏI���B�_����
�S���Ō����ΐ��\�𗎂Ƃ����g�p�����L�n66/67���x�����x�ǂ������Ƃ������Ƃ�
�霂������ĉ�����
�ŁA�ǂ݂ɂ�������ςȏ��ʼn��s�����
�t�B�[�h�o�b�N����ɂ����g�D������?
�����d���ŗ\�萔�I�����āA�ς�?
�ŁA�ǂ����悤���Ȃ��������낤�B�@�^�����������Ƃ��������悤������
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
������EF81�̐v�҂ł���Γc���A���̎��O�������Ȃ�181�n�g���u���̎��Ԏ��E�ɕ��荞�܂�Ă��܂���
���̏�ԂőO�C�҂���̈����p���Ȃ��Ƃ����̂��Ђǂ�����
�m���Ƀn�P�P�Q�|�U�͍����x���Ńo�����X�����Ă����낤�ˁB
����n�S�T�B�͌��Ō������ǁA��V�O�N�O�̓��{�l����������Ƃɋ�������������B
�ޗ��̎��Ɛ��x�����ǂ���A�ԈႢ�Ȃ����E�g�b�v���x���̋�┭���@�B
>>102
�\�葬�x�̘b�͗ǂ�������Ȃ����ǁA�ō����x�Ȃ�A�R�z�{���ł̋����������Ȗ\�͓I�ȑ���Ɖ����Y����Ȃ��B
�͂܂����̍Ō�̑��[�P�H�Ԃł̂P�Q�OKm�^�]�ł́A���\�����Ă��銴�����������A�͎̂�������ȏ�o���Ă����̂��H
��E�E�E
�����P�O�N�W���R�O���̂��ƂȂ��ǂˁB
���̓��͗��j�I���J�ɂ�蒆���n�悪��^���ŁA�͂܂���������p�����V�����ň�Ӗ������������������ǁA����ȍ��J�̒��̌����������B
�������x��Ă�����ŁA���߂����Ƃ��Ă����̂��ȁE�E�E
���̌�A�P�����S���p�~�ԋ߂ɏ�����Ƃ��́A�S�R�Ⴄ�Â��ȑ���Ŕ��q����������B
���̎��̂̑O�ʼn��ł��L�肾������ł͂Ȃ����낤�ƐM���������ǁA�P�Q�O�����I�[�o�[�������̂��Ȃ��H
����Ȃɏo��̂��ȁH
JR�ɂȂ��Ă���́A�ߋ��ɔ̔����ꂽ�^�S�����Ţ�͂��ƣ��Ұ����U����đ��s���Ă��Ƃ̋L�q�B�ӔN�̢�͂܂������181�n����^�s�ŏI�̢�͂܂����6����6���x������߂��ׂ��唚��
���̍��͑��|�P�H�ł��ő�68��(�ō����x100km/h)���������ȁB
JR�ɂȂ��Ă���͐V�����̑呝���E�X�s�[�h�A�b�v������A
�ō����x120km/h�̃t�����\�ŗ]�T��������l�߂�ꂽ����ȁB
183�n�������ɃL�T�V��]�p����Ă͂������݂����B
������͂�183�n���ᑫ�g�ɂȂ邾���Ȃ̂Ŏ������Ȃ��������B
http://www.westjr.co.jp/press/article/2012/02/page_1386.html
�������ň��������̂�?
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1328103259/
��������O�̎������Ă�́H
�L�n181�n�̃g���R���́A���ԑ��x��ł̉����͒ቺ��}���邽�߁A
�ϑ��^�]�ō�����܂ň������邱�Ƃ̂ł���^�C�v���̗p���Ă��܂��B
����A�L�n58�n�A�L�n80�n�̃g���R����3�i6�v�f�^�ł���A�ᑬ�g���N��
�������̂̑��x�Ɣ��ɋ}���Ƀg���N���ቺ����^�C�v���̗p����Ă��܂����B
�g���N�R���o�[�^�̍\����1�i3�v�f�ł��B�G���W���̍ō���]��ł�
�g���N�������o���鐫���������Ă��܂��B���̂��߁A�L�n181�n�����C�悭
���i����ۂɂ́A�G���W���̉�]��������Ȃ�ɍ����Ȃ�܂��B
�X�g�[���g���N��̓L�n58�n��5�`6�{�Ȃ�A�L�n181�n��3�`4�{�ł��B
�^�[�r������H
>>118�ȊO�݂�Ȃ킩���ĂĂ��炩���Ă悗
��肪�Ƃ��������܂��B
4�̓t���b�g������ƕ����Ă��܂����B
�ŏI���̉^�p�ɂ��Ă���12��13�ł͂Ȃ������ɂ�ł��܂����B
�u����������A�^�[�{��t����7���߂��n�͂��グ�Ă�̂ɃC���^�[�N�[���[��t���ĂȂ��B
�iDMH17�����b�^�[10ps���ADML30�����b�^�[16.666....ps�j
����v�����z�͎ԂƂ��S���Ƃ������ȑO�ɃG���W���̊�{��m��Ȃ��̂��B
�͂����茾���ƃA�z�v�ƌ����Ă��B
�܂����ꂪ�s��̌����ɂ��q�����Ă�̂���
���Ԃɂ͐����̍H�ƌ����ҁA�Z�p�҂����ĉȊw�Z�p�A�H�ƋZ�p�͓��X�i�����Ă��
���͓�����O�̏펯�Ń`���[�j���O�V���b�v�̐e������ł��m���Ăē��R�Ȃ��Ƃł����Ă�
�����͂�������Ȃ��������Ƃ������ς�����
>>133
181�n�̎���Ԃ̃L�n91���o�ꂷ��ȑO�ɃC���^�[�N�[���[�^�[�{���G���W�����ڂ���DD51�����ɗʎY����Ă���B
�������A�l���ٓ��Œ��C���X181�n�̃g���u���̌�n������������ꂽ�Γc�[��J���E�v�����L�n66�E67��
���̂��Ɠo�ꂵ�����S�̐V�`���̃f�B�[�[���J�[���V�����ɂ̓C���^�[�N�[���[�����ĂȂ��B
���_�Ƃ��ĉ�������������?
�R�x���d�l�Ȃ畽�R���̍����^�]�Ŗ����������Ăł��A
60�A80km/h�ōł������ǂ��^�]�ł���Z�b�e�B���O�ɂ��ׂ����������ƁB
���S����̏c����̕��Q����Ȃ����H
�����@�t���ĂĂ��M�e�ʕs���������Ƃ����
�����@�Ȃ��E�L�T�V�g�ݍ���
�����������B
181�n�͂��Ƃ́A120km/h��Ԃ́A���s�E�V���|��S�ԂŒ���������
�A���|�P�H��58������������A120km/h�o�Ă���Ԃ����Ȃ肠���������B
���Ȃ��āA����|�Ďq�Ԃ̂��ƁH���R�|����Ԃ̂��ƁH
120km/h��Ԃ͏�S�|���R�Ԃ����ŁA���������Ԃɂ����5�����炢�̍�
�����������ǁA�Ȑ����ȊO�ɑ����̂�120km/h�o�Ă���Ԃ���������
�ǂ����͔����������B
�ō��^�]���x�ƃ��[�^�[�̍ō��ڐ��������Ȃ̂͒������B
�ڈ�t�w���đ��s���Ă����̂��B
�E�e�V�̃`�������W���_���������Ă��܂�����Ȃ����B
�X�s�[�h�I�[�o�[�̏؋��B�łׂ̈��H
���S���}�ɕ����ĂȂ镨���A�݂����ȉ��V���������炵������˂��B
�悭�x�����������������_�C�����M���M�������������
�����Ӗ��ł́A���@�����Ƃ��B
���ۂɑ̌������ǂ��Ӗ��ł́A���H���́u��������v����P���Ԓx��Ŕ��قɒ�����
�A�������X��40���x��Őڊ݁A�ڑ�����u�䂤�Â�v�����ɐ����̒x��œ����Ƃ��B
���k����������Ȃ���BJR�l���ł����傢���傢���[�^�[
�U����������B
�����ɂ悭�������A8���Ґ��ŃL�n181��4�������Ă�����������
��7���Ґ��ŃL�n181��3�������Ă������������E�����Â��Ȃł́A
���Ԃł悭���Ă������̂��B
���������ȉ^�]�������Ǝv�킹��ɏ\���c�B
���̃L�n281�i283�j�n�ʂ̃p���[���Ȃ��ᖳ����������Ȃ��낤���H
���߂ĐH���Ԃ��u�L�V180�v��������A�Ƃ��v�����ǁc�B
��183�̘b�����AJR�k�̓}�W��135�L���Ƃ��o���Ă���
�܂����������O�̃m�[�}���̎��̘b��
�L�n181�n�͕��R���������^�]����̂ɍœK�Ȏԗ��Ő��\�I�ɂ��\���]�T���L��B
���͂������R�x�H���ɓ������ĘA���ߕ��^�]���Ă��܂������ƁB
�R�z�E��B���}��k�C���e���ɓ�������Ă�����]��������Ă������ƁB
(�܂��k�C����80�n�ȏ�Ɉ��艻�ɋꂵ�ނ��ƂɂȂ邾�낤���B)
130�܂ł������������600m�Œ�܂肫��Ȃ��E�E�E
>>157
���ꂾ���p���[�L��]���Ă����̂��B
�L�n�P�W�P�n�̊ђʃu���[�L�͂悭��������A
�P�Q�O���ĂP�R�O�߂��ł��A�U�O�O���ߕӂł͒�܂ꂽ��B
20���̏����z�ɍ����|��������A�}�ɃX�s�[�h�������Ĕ@���ɂ��b���b�����s���Ă�
�悤�Ɋ����������������B281�i283�j�n�̏o�͂��ȂĂ��Ă������Ȃ̂��Ƌ����āA
�Ȃ�ق�80�n�̍����́u�k�l�v�u�����Ƃ�v���n�������o�R�������肵���킯����
�v�����������B
������181�n��38��̔J���z���́A����ς薳�������������Ď��Ȃ낤�c�B
��U�p�~������@����������Ȃ��Ȃ��āA�J���S���҂͂������O�������Ǝv�����c�B
�R����Ԃł͂R�O����/�����������Ńm���m���Ɠo���Ă�����B
�u�U���x��v�Ȃ�Č����Ă��̂ǂ��ȕ��͋C�ŁA�u����͂����ŃL�c�l������ł����v�Ƃ��Ȃ�Ƃ������Ȃ���A
���ǁA���邱�ƂȂ��A���M�łP�O�������B
�P�W�P�n�ł��E�E�E���ȁH
����ς蕽�R�̂������肵�����ňЗ͂��ł����ˁH
���݂ɁA���̖k�C�P���ł́A�J���`����u�����Ă��Ă�����v�Ȃ�Č����ăO���[���Ȃ��̌��ł����B
�Q�l�������Ȃ���q�̘V�v�w�́u�����Ɠ|����O�O�v�Ȃ�Č����Ă��ꂽ���A
�����炩�Ȏ���ł����B
�d�Ԃł͂Ƃ��Ă��B���o���Ȃ���������Ă�Ƃ�
�̏Ⴕ���̂͂قƂ�ǂ����ԎԁB
�X�s�[�h��������Ɖ��㎩�R���M�킪���蓯�R�Ŗ��ɗ����Ȃ������B
�d���G���W���ƃ��W�G�^�[�����p���Ă��擪�ԂƃL�n65�ł͂��������b�͏o�ĂȂ��ˁB
���R���͂�����Ɩ�������Ȃ�
�X�����̓o����z�ŃX�s�[�h������̂�R=300�ׂ̈��Ǝv���B
������281��25��ύt���x��100km/h�߂������Ǝv���B
�܂�����Ƃ��Ă͊i�D�������ǂˁB
wiki����ƃG���W����ϑ��@�n�Ƃ̎�荇�킹���������s��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邯�ǁA
�R�X�g�͒Ⴂ�̂ŁA���Ƃ��Ό���嗬�̑��i���ϑ��@�Ƒg�ݍ��킹�Ă͂ǂ��Ȃ�
�������͎R�x�������ɕ��R�����������ɗD�ꂽ�ԗ���������̂��B
�v���d�l�Ɛv�d�l�����{�I�Ƀ~�X�}�b�`���Ă�Ƃ����v����̂����B
2) �L�n�U�O�@�@�ʖڂ����
3) DMH17�ŃL�n�W�O
4) ������x���킾�I�@�L�n�X�P�o����
5) �ǂ��������@���}���I�@�����Ȃ肶��Ȃ�Ȃ�Œ������ŗl�q���Ȃ���@�X�P�������Ă邵
6) �L�n�X�P�@�ʖڂ����@�ǂ��Ƃ��͗ǂ�����ǁB�B�B
7) �������@����������@�P�W�P
8) �������������牽�Ƃ����点�悤�A�F�K���o����
����Ȃ���Ȃ��H
���܂�R�x�������ɂ�������ƁA���̓��k�{�����ŋ}�s���x���Ȃ肻�������B
����łȂ��A�����ɋ�����p�̃��W�G�[�^�[���Ԃ牺����퓹���u�����v�̂����[���ł��Ȃ������B
������ɂ͗�[��������Ώ\������B�ł���@��ނ͏����ɏW�߂���������������e���y�����B
���������Ȃ�����łȂ��̂���
�ł��{���̓��W�G�[�^�̈ʒu�͏�����艮��܂��͑O�ʂ⑤�ʂ̕��������Ă���
�����Ƀ��W�G�[�^������ƃS�~�ȂNJ�������Ђ̌����ɂ��Ȃ�₷��
�G���W���̋쓮���Ńt�@������]������s����A�d���Ȃ������ɒu���Ă���Ɨ���
���܂������Ȃ玩�R��p���̂ق������R�ǂ��B���ۂ̌��ʂ͂����̗L�l���������B
>>168
�̏�p���̍ő�̌����͉ߑ�ɒ������ꂽ�R�����ˋ@�̐ݒ�̂��������Ȃ��B
����ɔJ�Ɋւ��Ă����A�������͂����̎R�x������Ȃ��A���{�ł����w�̎R�x���i���z�ƒ����̗����Łj������Ȃ��B
�{���͘A����i��1-2��������30����i�Ŏg���O����A
�A����i�ȏ���o����R�����ˋ@�̐ݒ�͓K���ł��傤�B
���R���Ȃ�ő�o�͉͂������ƈꕔ�̌��z��Ԃ��������炻��Ŗ�薳�����A
���z�H���ł͍��������d���Ō����̒Ⴂ�ϑ��i���甲���o�����A
�Ђ�����ő�o�͉^�]���������邱�ƂɂȂ�͓̂��R���ƁB
�ǂ��݂Ă��v�d�l�Ǝ��g�p�����̃~�X�}�b�`�ł��B
������������Ƃɐv�̃g�b�v�͓ƍَ҂ƂȂ��Ď��p�������u�ڂ��̂��ڂ��v��D��B
��s����Ԃ̃L�n91�n��̎����͉^�s�\��̂Ȃ��[�����a����ł���āu���i�v�Ƃ����Ė��É��Ɉ����n�����B
�u���v�Ɠ����g���u���́u�}�s���Ȃ́v�̂��납�炠�������ĕ��ł��Ƃ������牽�����₾�B
�L�n82�n���l�Ɂu�k�C�������B�܂Ŏg���v�v�悪��������ƊJ���̒i�K�ŏn�������낤�ɁB
�a�B�[�[���Ԃ̊J���i�����J�[�u��d�ԕ��݂ɉ��ǂ���Ƃ��j�a���ɂ����̂��ˁH
�d�Ԃ̋Z�p�v�V�i�������j�͓��C���ɐV�������o�������_�łЂƒi���ł悩�����Ƃ��v���̂ɁE�E�E�B
���k�E�k���̗��{���͖ܘ_����ɕt������H����
��B�����̓d�����i�߂��Ă���������Ă��ȁc
�Ă�1960�N��㔼�̍��S�ԗ��͑�Ȃ菬�Ȃ�����������̂��肾������
�Ō�̈�s�͈Ⴄ�Ǝv����
�L�n80�̎������������������
�K�X�^�[�r������Ă�����Ȃ��B
�Ȃ̂ŁA>>169�ɕt�������Ƃ���A
9)�@�O�x�ڂ̐����A���x�����d�Ԃɕ����Ȃ��C���Ԃ��I
10)�@�|���R�c�̃L�n07�Ɏ����ɃK�X�^�[�r���ڂ����Ă݂��B���点����A���܂�̑����Ɉ��R�I
11)�@��R���C�ɂȂ��ăL�n391���J���B����͐������A�����ƔR������̕������ɂ����R�E�E�E
12)�@�����փI�C���V���b�N�������B�K�X�^�[�r���H�@����ȃg���f���~�߂�I�E�E�E�����Ȃ��I���B
13)�@���ꂩ��̂P�O�N�A���S�����̑�Ԏ��ƘJ�g�Η��ɂ��E��r�p�ŁA�����\�Ԃ̊J���͕s�тɁE�E�E
����Ȋ������ȁB
�L�n80�E81�̎��s������������L�n82�́A���̒��x�̃g���u���ōς̂ł́H
�����Ȃ��ǁA���ǃL�n81�Ńg���u�����o��x�ɂ��̓s�x�Ή��������ǂ��t�B�[�h�o�b�N����������
�n�l�͂��ĂȂ��Ǝv�����
�l�ԍH�w�Ǝ�����肾��
�ԔԂ͕ς��Ȃ������B����͎��ɕs�v�c�B
����A�L��180�̈ꕔ�͌��X�������m���g�C����P�����ĎԔ̏�������������
�i�H���Ԗ��́u������U�v�̂��肾�Ƃ��j�A��������150�ԑ�ɉ��Ԃ��Ă�c�B
���̎��_�ŃL��180��100�ԑ䂪�������̂�
��ʂ���K�v�������������B
>>186����Ȃ���>>185�������B
�T��481�̏ꍇ�͊m���ɂ��������ǁA�������������Ă�K�C�h�u�b�N�ɂ́A
�L��180-150�Ɋւ��Ắu�o�������̗m���֏���P�����āc�v���ċL�ڂ�����B
������A0�ԑ�̏ꍇ�͓d�Ԃ̃O���[���ԂƋt�ŁA�h�A�̕����m���ŋt�����a��
�����낤�Ǝv���Ă��B
�����������Ă݂���A�����̎v���Ⴂ�ł����\����Ȃ�
���Ԃ����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Y��Ă��܂����̂��E�E�E
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�g���l�����ŗ₦�Ȃ��Ƃ�����_���L�����炵��
�M�C�͏�ɗ��܂邩��
�v�҂����s����H���̓�����S�R�m��Ȃ��A�Ƃ������l���ĂȂ��ȁB
����������ɐ������邱�Ƃ����ᒆ�ɂȂ������i�ƌ����Ĉ������A������ŗD�悵���j�Ƃ��B
���̌�̓]�p�悶��ǂ����݂�����ȍ����ő��点�邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���āc�B
�����k�C���Ƃ��ɓ���������肾������A�����Ɗ挒�Ȑv�ɂȂ��Ă��悤�ȋC�����Ă����B
�܂����������v�҂������Ǝv���Ă鎞�_�œ��������B
���ł����Ȃ�G���W��?
�J���ŃG���W���ȊO�ɂȂ��o�����H
�g���u���ɂȂ����̂͗�p�n�������
�������Ŏ��������Ȃ��Ȃ��ē����o����DC�~�[��
���H��ʊ�ł����ɏo���肵�Ă���͗l�B
���ƂȂ������Ă镪�ɂ͂܂��������ǁB
���������Ă��O��������̍r�炵��?
�������L�n66�E67��440PS�Ƀf�`���[�����Ă�
�g���u���͗�p�n����Ȃ���B
�r�C�n�̉��M���B
�R���ł���
�������肠�Ԃ�o�����Ȃ�B
�����J���S���҂��A���点��O����u����ς蕟�Ă̎��͑��s�͖����v�ƋC�t���āA
���������@�p�~�̕��j��P�Ă��A���Ă�Ȃ�u�v�҂ɔv��F�߂悤�B
���ʓI�ɂ���A���ꂾ���g���u�����o��������A
���O�ɉ��̖����Ȃ��Ǝv���Ă��v�҂������Ȃ����Ȃ��B
��ԂЂǂ��Ǝv�����̂��ЂƂ������ށB
�u�G���W���A�R���o�[�^���q���S���p��̔j���ł����A�S������ϖ����̃S���Ɏ�芷�����̂�
���v�ƕ�������܂������A�^�]�ǂ̉ے�����Ďq�@��ŃS���p��̎�芷����Ƃ���������ςȍ�Ƃ��ƕ�������܂����B
�s�v�c�Ɏv���Đ}�ʂ��J���Ă݂�ƌp���h�U�S���Ƃ��Ă͌�����g���������Ă��ċ����܂����v
��C�̐v�҂͂���ȕs�Ǖi�̌�n���������t�����Ă悭�䖝�����ȁA�Ɗ��S���܂����B
�Ȃ����ł���
���k�ɂ̓L�n65���z�u����Ȃ������̂��A181�n�ł���ۂǒ��肽�Ƃ������ƂȂ̂���
�}�s�͖������ė�[������A�܂Ƃ��ɑ��������������ł���A�݂�����
�L�n58�͎��͂œo���Ă���20�L�����x�����o�Ȃ�����
70�N��܂ł͓��k�̃f�B�[�[���J�[�͗�[�@���t���ĂȂ��̂����ʂ������̂�
�o��p�͂Ƃ������A��[�d���t�����q�Ƃ��ẴL�n65�͕K�v�Ȃ������B
��O�͋}�s�u�������݁v�u����䂫�v�̊�{�Ґ����炢���B
�u���v��181�n�͔��v�q�ԋ�̏��������A�Ԃ���ꂽ��ԂŏH�c�ɓ�������̂�����
���S�H�c�̐l�������������f���������Ƃ��낤�B
�t�ɏ��u���v�̏ꍇ�́A�q�ԋ�̐l�����v�w��ʉ߂��鏊���ώ@�����B
�u�����͑����������_�����Ă邩�ȁH�v
�̏�Ԃ͑����i���j���_������B
3���ȉ��Ȃ�D�G�A5���ȏ�͂��߂Ƃ������Ă����������B
�ŁA�܂��Ȃ���삩�����Ă���ԗ��́A�����̍�Ƃ̗\�z������킯���B
�L�n183N�n��DML30HSJ�����i�o�́��ő�o�͂Ƃ����i��i�͈͓̔��ōō����x���o����悤�ɂ����j�̂Ńg���u�������Ȃ��Ȃ����Ƃ�
���̏�485�n���̒��O�ɂ͔��Ԃ�������̏������E��
���̏ソ���̌o�R�n�̎R�`�Ɂu���v�̖��𓐂��c�B
�H�c�̊W�҂���������������낤�ˁB
�~�c>>215
�������B�X�}�\�B
�ŋ߂̋C���Ԃ͏Ռ������Ȃ����炩�ɕϑ����邪
�����Ȑv�������̂ł͂Ȃ��A�R�����ԗ����ɂ��Ƃ��������s�ǂ�
�����ŁA�������������R�����o�ʂ��ߑ�ɂȂ��Ă���A500PS�G���W����
590PS���x�܂ʼn���Ă��܂��ԗ���������������I�[�o�[�q�[�g��r�C�ǂ�
�ߔM�������N�������B
���̌シ�ׂĂ̎ԗ��ŔR�����i��A�^�[�{�������܂蕷�����Ȃ��Ȃ����B
�L�n66�E67�⏉��183�n�͓���DML30HS�����A����Ɉ��S��������ŏo�͂�
440PS�ɗ��Ƃ��Ă���B
�u�V���b
�����̐v�v�z�ł͘A����i��2��������30����i�Ƃ��Ďg���O����A
590PS�o��̂͐����s�ǂ���Ȃ��ł���B
���͂�����p�������Ȃ��R�x�H���ŘA���Ŏg���Ă��܂��^�p���@���ƁB
�ԈႦ�Ă��܂����B
590PS�łȂ��A620PS�ł����B
�R���ɖ�肪�邽�ߎR�x�H���Ńg���u�������݉������̂ł���A�����͉^�p
���@�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�h�[���ƕϑ����Ă���̂́A���q�������ԗ����B
�{���́A�V���b�N�Ȃ������ϑ�����̂����A���x���m��
���܂������Ȃ��Ȃ�����A�ϒ��ؑւ����܂�������������
�肷�邵���̂ŁA�����������ĕϑ�����悤�ɂȂ�����
�������B
DMH�ł��{���A����i�̂͂���180PS���T�������ێ��ł��Ȃ������������B
�v�A�^�p�A�ǂ��������������������A
�����66�E67�p��30HSI�ŁA�ݒ��̃`���[�j���O�ǂ��납�u�f�B�[�[���@�֎��̂̈��k�䗎�Ƃ��v�Ƃ���
�����Z�p���̔����グ�ʼn��Ƃ��j�]����ɉ�����ł���B
�g������������ł͂Ȃ�����O�̂��߁B
66�E67�p��30HSH�B30HSI��183�n�p�B
���ƁA���k��͕ς��Ă��Ȃ��āA�u���ϗL�����v�𗎂Ƃ����̂ł���B
�T���X���܂Ȃ����A
���̐F�̓A�[�o�����ɗǂ����������Ǝv����
�h�肷�����X�}�[�g�ȓs��h�L�n181�Ƃ���������
�L�n91�̒i�K�Ō������炳��Ȃ������낤�B
���߂Ď����������Ĕ�r����ˁB
�d�q����ɂ���Đ����ɉ�]�������킹�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����̂Ŏ����ł����Ƃ�
���p�������s���Ă��܂����˂��B���̌�ADW14�^�͐����ɂȂ�܂������B
�e�[�u�����������ٓ��Ȃ�e���p�m�[�g�p�\�R�����u���Ȃ�����
�́g���������h�ɏ�������̂�́A�}�s�^��ߍx�^�̂f�Ԃ݂����ȃZ�R�����������ˁB
����������ł͂Ȃ�������ˁH�̂�������20�N���炢�O�̂��Ƃł�����w
�ۈ�ЃJ���[�u�b�N�X�Ɏʐ^�o�Ă��̂��Ēm���ĂȂ��H
746 �f�B�[�[���J�[�i2�jJR�ɏo�Ă���c
�o�ꎞ�́u���Ȃ́v�A���Ďʐ^��5���ڂ��L�n91
���ꂪ�����Ƃ��́A�d���̈����ʂ����ǂ����Ă��̂��C�ɂȂ�
�d���ނ͗��ԑS�������B�t�ɃL�n91���ݗ��ԂƘA���ł���悤�ɕϊ��p�W�����p�𓋍ڂ��Ă����B
���_��͉\�ł��邪
������Ē��ԎԂ��S���O���[���ԂƂ����邾�낤��?
����͊ԈႢ�Ȃ�
���ꂨ����������?
�Ȃ��Ȃ��̏r�����������ǁA�g�C�����^�L�n180��1�ӏ������Ƃ����̂̓L�c�������B
���ʏ����c�u���Ēj�q���p�ɉ�������A�g�C���s���������Ȃ���P�ł����̂ł͂Ǝv���B
3������J���̃g�C���ʼn��ł����́H��ʌ^��肸���Ƒ����Ǝv�����ǁB
���܂��ɒ���̏��Ȃ�181�n3��������A�g�C�����g���l���́A�ő��ɂ��Ȃ�
�悤�ȋC�����邪�B
3���Ґ����ƈꃖ���ɂȂ����܂��ƌ�������������ˁH
�������}�͂���Ȃ�ɋ������邵��Ԏ��Ԃ����߂�������
���������ɷ�120�Ƀg�C���������ƃe���r�Ŏ��グ��ꎖ��������
�R�A�͘V�l����������A�斱�����q���F�X�ƍ����Ă���
�����\�̕Ґ��\��ł́A�����S�N�R�����畽���T�N�R���̊ԂɎl���̂P�W�P�n�̂��܂�ƁE���������
�L�n181-�L���n180-�L�n181�ɂȂ��Ă������ƂɂȂ��Ă��邪�A���ۂ̓L�n�P�W�O�����������
�S���Ґ��ɂȂ��Ă�������A���̕Ґ��͑��݂��Ă��Ȃ��B
���낵����
�O���ł͒ʋΓd�Ԃł���g�C���t�����ӂ��A�g�C����1����2��������q�Ԃ�����
��������~����1���Ԃ���Ԃ����Ȃ��悤�ȃ��[�J�����ł��g�C���Ȃ��̎ԗ���������{�ُ͈�
�Ⴄ��B�ϑ�1�i�A����1�i�ŁA�g���N�R���o�[�^��3�v�f1�i�`�̃��X�z�����E�X�~�X����B
�ϑ��i�ɂ����āA������܂ň������邱�Ƃ̂ł���^�C�v�̃g���R���ŁA
���ʁA�N���g���N�͎キ�Ȃ��B
�ϒ��ؑւ̖ڈ����x��85km/h�ł��邪�A�t���m�b�`�Ȃ�50km/h���x�Ŏ����I�ɐ�ւ��B
��]�������m���āA�����I�ɃM�A���ւ��邩��ɂ�B
���̎R����Ȃ��Ă��瓌���ł͑S���l�����Ȃ��B
�ʂɂ��������Ӗ��ł͓`���̎ԗ����Ă��Ƃ͂Ȃ���
���}�����̎��ォ��f�B�[�[���œ����w�܂ŏ�����Ă���
���}�������ăL�n181�n����Ɏn�܂������Ƃ���Ȃ�
�L�n82�̎����������Ă�
�����ߋ��̘b������
���C�����ʈȊO�f�B�[�[���}�s�������Ă�����
������Ō�܂Ŏc������
http://www.youtube.com/watch?v=cc0y3LC0H2s
http://www.youtube.com/watch?v=-k7ekRgZtbw&feature=related
���͂���@���x��
�[�r�������Ĕ����Ă��邯�ǁH
���X�z�����͏[�r�����Ȃ����
�R�x�H���Ȃ̂ŃL�n82�ł͎R�o�肪��ς������͂�
���Ȃ̂ŎU�X��J������ꂽ����������ق��Ă��Ƃ�������
��������Ίό������ɂȂ����͂�
���w��
�^�s���
�n���w�@�@������w
�o�R�@���C���E�R�z���`�d�A���`�R�A�{��
�I���w�@�@����s�w
�Ґ�
�E1���ԁ@�L�N���n�l���n�V���j181
�@�G���W���P��
�@�^�]�Ȍ���̋@�펺��X�ցE�ו�����
�@���̌���A�Q����~1�AB�Q���(2�l�p)�~1
�@����ɁA�O���[���ԍ��� 1��@���ʎԍ��ȁ@2��
�@�d�q�����W�������ȈՃr���b�t�F
�E2���ԁ@�L�T���l��180
�@�G���W���P��
�@A�Q��~4(�㉺�i/�v���}����)
�@�O���[���ԍ��ȁ~6��
�E3���ԁ@�L�n�l�n�^ 180
�G���W����2000ps�ɑ������������C���W�F�N�V�����^�[�{
�@B�Q��~4(�㒆���i/�v���}����)
�@���ʎԍ��ȁ@4��
�@��ʑ��ԓ��ɐΖ��^���p�^���N
�E4���ԁ@
�@�L�N���V181
�@�O���[�����ȁ~4
�@�H����
�@�^�]�䑕������
�E5����
�@�G���W��������
�@�L�n�l180
�@�㉺2�i�G���Q�X�^�C��
�E6����
�@�L�N���l�e181
�@A�Q����~8
�@�Ԓ[���ɂ͓W�]��
2013.1���`�^�s�\��ł���B
�ʔ����Ȃ���ɃL����
�ÎR�w�ɕۑ�����Ă����͔������ɍ��S�F�ɖ߂�����
���������S�J�g�͂ނ��Ⴍ���Ⴞ��
60-70�N��̍��S�Ƃ������璷�����A�����ʋΗA�����A���q���ݕ����p���N���āA
���܂��ɐԎ������ݎn�߂āA����Ȃ͂���MT54�n�d�Ԃ�DMH17�n�C���Ԃł���
��������Ԃ̕���^�s�m�ۂɋ�J���Ă�����A���J����Ȃ��Ă����ۂ��ē��R���ƁB
��̌����Ă����u�₭���v�ȊO�̃L�n181�[�]�p��Ƃ�������
�t���p���[�̕K�v���Ȃ��H�������肾�������B
���Ȃ蒦��Ă�����DML30
���̓L�n65�����܂�g�������Ȃ������Ƃ̂��ƁB
53.10�ł̓]���́A�d���Ȃ�������B
�J�g�W�Ȃ��A�㕔�����ۂ��Ă����B
�厖�ȂƂ���̎��ȗ�����̎~�߂�����������
���S�o�X�ł��X�|�[�c�J�[�݂����Ȑ��\�̃o�X�����[�J�[�ɖ�����������Ă���
���R�����̂�
���邹������ē{����
�������̂��̂��Ƌ��n���Ă��C���[�W
�J�X�x�Ə�Ԃ�������ɃL�n189�n�ł͔p�~�ɂȂ�����
�������Ō�܂Ŏc���Ă������������S����̂܂܂̃O���[���Ԃ�����
���F�̂܂ܑ����Ă�낤����
���╺�Ɍ��̏o���K��ŃO���[���Ԃ���߂��Ă�������N���K�v�ł͂�����
�������O���[��������������ĕ��ʎԎw��Ȃɏ��̂ŏ�q�͂��Ȃ�����
�p�Ԕ����i��2+1��V�[�g�Ɍ������Ă��ǂ������̂�
DML30�̐����Ɏ���Ă��āA�G���W����P������Ă��܂��A�����̋q�ԂɂȂ�Ƃ��F�낤�B
������Ȃ�Ɗm�M���Ă����A��ɍs�����L�n183�������S���`�V��s�Ԃ̋}�s�ɓ������ꂽ���
�Ƃ肠�����͂����ƋC���ԗ�ԂƂ��đ��肻��
181�͑�Ԃ�����Ȃ̂ŁA���O�ŋ�J����\���͂���B
1067mm��1000mm�̉��O�͎ԗւ̃t�����W��������邾���ŗǂ�
���^�̃��N���C�j���O�Ȃ����Ȃ͔w�ʂɃ��P�b�g���\���ĂȂ��������A�J�[�e�����������ł͂Ȃ����[���J�[�e���i�O���[���Ԃ͉������J�[�e���j����
�C���Ԃׂ͖����H���̑㖼��
�ł��L�n181�n�͑������������Ă�Ǝv����
�C���Ԃ��������邩��R�X�g�_�E�����Ă���̂ł́B
HOT7000�͉������J�[�e�������j���[�A���Ń��[���J�[�e���ɂ�����
�h��̖���
�L�n80�n�̕��ʎԍ��Ȃ̔w�ʂɂ̓��P�b�g���\���ĂȂ��������A
�L�n181�n�̕��ʎԍ��Ȃ̔w�ʂɂ͓\���Ă������B
���������̏��a62�N3�������ō����|���R�Ԃ�110����/h�ɂȂ��Ă��瑬���Ȃ����B
���R�����ɂȂ��Ă���ł́A�������|�����|�F���ÊԂ�110����/h�Ƃ�120����/h����������
�������|�����Ԃ͕��ʗ�Ԃ̑��s�������肵�đ����Ƃ����C���[�W�͂Ȃ��B
�啪�ȓ�̒P����Ԃł͂ɂ���g���g�����肾������
���a61�N11���܂ł́A�\�]�������|���x�Ê�95����/h�A���x�Á|�F�a����85����/h�B
���a61�N11������́A�\�]�������|���R��95����/h�B
���a62�N3������́A�\�]�������|���R��110����/h�B
����2�N11������́A�\�]�������|�F�a����120����/h�B
����5�N3������́A�\�]����o�|���R��130����/h�B
����7�N���납��́A�\�]�������|���R��130����/h�B
�L�n181�̂��������ł����ΓI�Ƀ}�V�Ɏv�����B
�������A���a36�N10�������̃L�n58/55�ɂ��}�s�u�l���v��
�����|���R�R���Ԑ�E�\��66km/h����債�đ����Ȃ��ĂȂ���������˂��B
���P���ꂽ�̂͏��S�n���炢���H
>>�����|���R�R���Ԑ�E�\��66km/h����債�đ����Ȃ��ĂȂ���������˂��B
���a�R�U�N�����͂R���Ԑ�ĂȂ��i�R���ԂT���j�A�R���Ԑ�͏��a�S�O�N�ŁA�\��66km/h
�͏��a�S�R�N����Ȃ����������H
�ǂ��Ƃ邩�����ǁA���a�S�V�N�R�������ł̂��������̍����|���R�Ԃ�
�ő��Q���ԂS�P���B���̌�͂��炭��ԉw�������Ēx���Ȃ��Ă��������A
���a�U�Q�N�R���ɍő��Q���ԂR�S���ɁB�����T�N���ɂQ���ԂQ�O���ɂȂ���
�������B
ttp://rail.hobidas.com/rmn/archives/2013/01/jr181_17.html
���̎ԔԔ���l����H
���������A�g���l���a���������ēd���ł��Ȃ������k����Œ���^�p�����Ă��ԗ������H
�ÎR���ő��s�s�\�ɂȂ�Ƃ͍l���Â炢�B
��Q��u�L�n181�@�`�����S���Ԃ�S���Ɋ�������`�v
BS�t�W�@ 2013�N1��19���i�y�j23:30�`24:00
http://www.bsfuji.tv/top/pub/tetsudo_densetsu.html
�L�n183�n0�ԑ�̓L�n82�Ƒ債�Đ��\���ς�炸����ڂ�����
�܌˂ɐႪ��������ł����Ƃ����ԂɎg�p�s�\�ɂȂ��ďI���B
��Ԃ̍\������˂ւ̉����͍���Ȃ͂��B
�k�C���ւ�181�n�z���A���Ȃ̂�₭�����d�ԉ����ꂽ�ۂɖϑz���Ă����ȁB
�܂�˂̖����N���A�[���A���ف|�D�y�Ԃ̊C����120km/h�œ˂�����A
�����̍��S�ő����}�ɂȂ��Ă�����������Ȃ��B
�������݂́A�������܌˂�583�n�䂤�Â�Ōo���������ǁA
����ł����N�撣���Ă����ȁB
�k�C���Ő܌˂�711�n����Ԃł���Ă�
������4���܌�
�ˑ܂ɐႪ�l�܂��ĊJ���Ȃ��Ȃ�̂����O�����炵�������ԕ����������ߌ��Lj����ˉ����ꂽ
���܂�Ɏ����o���Ă邪��
�������Ⴄ���H
�S���Ɍ����Ė�肪�N������L�̗��R������낤�ȁB
�w�S���`���x��Q��u�L�n181�@�`�����S���Ԃ�S���Ɋ�������`�v
bs�t�W�@2013�N1��19���i�y�j23:30�`24:00
ttp://www.bsfuji.tv/top/pub/tetsudo_densetsu.html
ttp://www.bsfuji.tv/tetsudo_densetsu/
80�n������j��H��݂�����
�o���B
�������M�d�ȉf���͊������������A�����Ԃ������ȓ��e�B
�L�n81�n�͊e�Ԃɔ��d�G���W����ς�ł邩���͂Ƃ��A
��ɃL�V80�͑��s�p�Ɣ��d�p�̃G���W����ςƂ��B
����Ɨ�̂͂���Ђ́A�����@��ɗ��܂�������
�u���[�L�̉ΉԂ����������̂����A�ȂI�[�o�[�q�[�g��
�����Ə���ɉ��߂���Ă邵�B
>�L�n81�n�͊e�Ԃɔ��d�G���W����ς�ł邩���͂Ƃ��A
����͂����͌����ĂȂ��ȁB
�u��[��ԓ��Ɩ��Ȃǂ̃T�[�r�X�Ɏg�����d�p�G���W�������s�̑傫�ȕ��S�ɂȂ����B
�@�G���W���͊e�ԗ��P�@�������ς߂Ȃ��������߁A�H���ԂȂǂɂ͑��s�p�G���W����
�@���ڂł��Ȃ������̂��B�v
������J���m�炸���}�������莖�̂�������Ȃ��V�����B
�w�͉��P�����Ȃ��^�C�}���ȍs������̕���@���ׂ�����B
�}�X�S�~���ēz�́B
�ݎK���K���@����Ă��킯����
�L�n80�̃g���u���͑傫�������Ă������A181�̃g���u���̌��̓X���[�B
�摜���u�͂܂����v����Łu�₭���v��u���������v�A�����^�p��������Əo�������B
�ꉞ�u���Ȃ́v�ɂ��G��Ă͂������A�A�A�A
B787��������������Ԃ���
�������J���Ă�݂��������A���傤���Ȃ���ˁA�݂����ȏ����悤������Ƃ��낪�������Ƃ�����
����͂���ł܂����Ƃ͎v�����ǂˁB
�L�n181�n��������Ȃ�
ttp://v.youku.com/v_show/id_XMzA1MjQyMzcy.html
����^����L�n66�E67�݂����������⎮���^���W�G�[�^�ɕύX����悩�����̂�
�ϑ���ᑬ�����ɕ������Ȃ��������̂�
�����Ō�̃L�n�P�W�O�����ɉ�̂���Ă��܂����݂������ȁB
���̗�Ԃ̒��ň�ԃC���p�N�g�̂��钆�ԎԂ������B
�l���J���[�̃��c
�ŋ߂̌y���C���Ԃ��ƕϑ��i��2�i�t���Ă�̂���ȁi�L�n40��JR�����{�̃G���W�������ԂȂǁj
�����i�ł̕ϑ��͐����Ȑ��䂪�K�v�ŃL�n60�ł�낤�Ƃ��Ď��s�����p����1989�N�̃L�n85�܂ő҂��Ȃ�������Ȃ�����
���R���݂ɂł���悤�ɂȂ��Ă���̋Z�p����ȁB
�̂̓��J�d�|��������ƂĂ�����Ȃ�������ȃf���P�[�g�Ȑ���͖����B
���s���Ԃ��Z�������Ƃ����̂����邾�낤����
DD51���[�r�����ϑ�3�i�Œ����i���Ȃ���
�L�n90�A91�̍�����S�����Ă����v�̃g�b�v���ٓ��ł��Ȃ��Ȃ�
��n���������t����ꂽ�V�����g�b�v�̐l�͏��Ȃ��\�Z�ƒZ���ł̉��C��������ꂽ�̂�
���z�I�ȉ��ǂ͖����������B
2nd Life Train�@�j�b�|����Ԉٍ��I�s�`�~�����}�[�ҁ`
����4��u�V���Ȃ闷����!�@�~�����}�[�ҁ`�e�B�����x���̗��`�v
�܂��́A�~�����}�[�ő�̓s�s�����S���̒����w�ʼn^�]�i�ߎ�����ʂɌ��w�ł��邱�ƂɁI
���̌�A�ԗ��H���K���ƁA�����ɂ͓��{����A�����ꂽ����̍ŐV�̎ԗ�����������Ă��܂����I
������Ԃ����̂́A�L�n�T�Q�ƘA�����ꂽ�����}�L�S���̋C���ԁB
�l�X�ȏo��┭�����J��Ԃ��Ȃ���A�~�����}�[�̔��W��������ʌo�ϓ���ցB
���̎ԑ��Ɋ��������i���c�B
�A�����ꂽ����̍ŐV�̎ԗ����L�n181���ۂ��E�E�E�\���f���ɂ��������ǃ��W�G�^�[�͂Ȃ��Ȃ��Ă�
���Njq�ԉ��Ȃ�?
�쓮�n�ڂ��ւ�?
���z���E�̊W�ŁA�����ド�W�G�[�^��P�����Ēቮ�������Ă���B
�����ɕ��ʂ̗�p�t�@���t���W�G�[�^�����Ă���͂��Ȃ̂Ŗ��Ȃ��B
�������A�g����͂��������ό��q������Ԃ������ɂȂ����Ƃ��ŁA�^�s�J�n�͖���B
���[���o�X��������DL�����������A���ǃ~�����}�[�̏ꍇ��
�S�����ǂ������r�W���������ĂȂ��܂܂�
�i���Ŏ�ɓ��钆�ÎԂ��Ă͏ꓖ����ɉ������A�g���̂ĂĂ������ŁA
�m�E�n�E�~�ςœ��{�̒��Îԗ��̑̌n�I�ȉ^�p�Ɏ��g��ł���C���h�l�V�A�̂悤�ȃ��x���ɂ�
���ꓞ�B���ĂȂ����Ă��Ƃ���
�G�A�R�������͉����ꕔ���蔲���Ďԓ��ɉ����Ă����������
���̒Ⴓ�͓��Ԃ��邼�E�E�E�o�b�g��ɂȂ��Ă邩�琅���܂��ĕ��H�ƉJ�R��̉\�����B
�������ɉJ��ւ̐��������������Ă���
�ٍ��̕��y�ɓ���߂������ɋq�ԉ��Ƃ����p�^�[������
�L�n181�擪�Ԃ̕ۑ��͖��É��ƒÎR�ɂ��邭�炢?
�~�����}�[�Ɏ����čs���߂�����
����������JKT48�ɑ���YGN48��������
�����ɂ���L�n181�n���̂���2���݂̂ɂȂ��Ă��
�~�����}�[�ɂ����čs�������Ƃ������A���̘b���Ȃ���Α��X�ɔ�����(ry
��������Ԃ̍\�����Ђ����āA�q�ԉ����Ă���͒����Ȃ������Ȃ̂��E�E�E
100 �F��z774��ԁF2012/02/18(�y) 23:56:54.19 ID:jiMwjxxE
�L�n181�́u���Ȃ́v��u���v���ܘ_�����ǁA
�u�����߁v��u�Ȃ́E�����v�ɓ�������̂����肾������Ȃ�?
�^�C�̃L�n58�݂����ɓ��͌n�͑S�ĉ��낵�ċq�ԉ����Ďg�p����ȊO�ɂȂ����낤�ȁB
�L�n82�ł͍��R�{����I���{���̋}���z���h�������̂ł́H
JR���C�͌��݂ł��C���Ԃ�2���`���ɌŎ����Ă邪
�L�n181�n�͍��S����3���`���̋C���Ԃł���
���̋}���z�����w���e�R�Ȏ��R��p���W�G�^�[�ێ���������h�������炵���B
�L�n65�͈ێ����Ă�����DML30�n�͂����܂Ō����ł͂Ȃ������낤�B
��p�\�͕s���͐��������݂������ˁB
���܂���DML30�n���Đ����Ό��̕��G�ȃG���W������Ȃ���������(����ӂ�)�H
����Ȃ�A�����͌͂�ė���DMH17�n�œZ�߂����Ȃ�̂��������ƁB
DML30�n�̃G���W���́A���Ȃ���܂݂������l�q�B
Wikipedia�uDML30�n�G���W���v�Q�Ƃ���B
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/DML30H
���W�G�[�^�ȊO�ɂ��@�ւ̐v���Ԃ��̖���A
�R�Ď���V�����_�w�b�h�⏁���n���牽���牽�܂ŋɌ��̈ȉ����E�E
������Ƃ����āA�D��Ŏg���Ă�����ł��Ȃ����������ȁ����S��
�������c�����ɁA�V�S�ǂ���4������������̂ɂ͈ꐡ�ȊO�������B
�Ȃ̂ɉ��̐擪�Ԃɂ͉�����̗�p�킪�t���Ė��������낤�B
�d���G���W���������Ă邩��A�܂Ƃ߂ċ�����p�ɂ����B
�������͑債���g���u�����Ȃ������̂ŁA�ŏ��̎d�l�̂܂ܑ������ꂽ�B
���������������̂��A�[�����@�ǂ������肪�Ƃ��B
����B�V���\�z�����Ă��A�S�~���p�����n���������˓앗�E�E
�X�ɂ̓����G�A�ɗ��������W�G�^�[��p�ȂǂƂ����唎�łɏo���B�ی����|������
��
�M�͊w�̐_�l���瓖�R�̕���
�Ƃ�������
���G���W���ɂƂ����Ď��s�����{�c�@��Y�Ɏ��Ă����
�����BϼނŁB
�����}�W����B
���̕ӂ��C���Ԃ̉��[���A���Ƃ��v������ǁE�E
�L�n181�n�͐v�v�z�I�ɕ��R���������s�d�l�����A
���̏������Ȃ��薳���^�p�ł��Ă����B
���͗v�����ꂽ�^�]�����ƌ����̎d�l���~�X�}�b�`���Ă��邱�ƂŁA
�Z�p�I�����g�D�I��肪�傫�����ƁB
���L�n181�n�͐v�v�z�I�ɕ��R���������s�d�l�����A
����[�v���d�l�͐^�t�������Ǝv����ł���
http://www.katomodels.com/n/kiha181/
���L�n181�n�́A��d����ԂŊ��Ă����L�n82�n����{�Ƃ��A����Ɍ��z����ɑΉ�����ׂ���o�̓G���W���𓋍ڂ��ď��a43�N�i1968�j�Ƀf�r���[�B
�v���ꂽ�̂��A���Ă̂����Ȃ��B
�������挈�܂��Ă���炻���ɍ����̍��̂�������O�Ȃ̂�
���̐��\���L�n80�n�������ɓ������ꂽ��d����v�����ŒB���ł��Ă���A
�d���͈͂��ς������������炢�̃C���p�N�g�������Ǝv���B
�L�n80�n�̍��܂����z���Ă���ׂ��p�������������̂́A
�����ɒx���A���������m�̓o�R�����p�r�����������̂ł͂Ȃ����ƁB
���̕ӂ̍d�������g�D�I���Ȃ̂��ȁB
���ǂ��ł�炩���킯�����
�������������������
���͓o������҂��ꂽ���`�đ�Ńg���u�������������͔̂������
����ł��A���̎ԗ����ʂ����������͑傫����
��삩�畟���܂őS�͎������Ă����Ȃ�J�z���B
485�n�ł��g���u�����o������M�Ԃ𑝂₵���B
���l����
�ƂׂȂ������Ė��悾��
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%B9%E3%81%AA%E3%81%84%E7%BF%BC
�J�����@�t���œo�₷��p�́A�܂��������̒ʂ肾��
��肢
>>418
�Ȃ�ق�
��l���ܑ̌㖾(�������E�߂�)�́A�w�Ƃ͗D�G�����A������݂��ĕs�ǂɃ����`�����
�N���X���C�g�����ĕ@�ŏ��l�Ȑ��i�̎����傾�����B
����Ȃ���Ƃł��镃�e����ʎ��̂Ŏ��S�������߁A����̃o�[�Ńh�A�{�[�C�̃A���o�C�g������
�w����҂����ɂȂ������́A���̋����ɕs��������Ă����B
������A�q����a�������㒅�̒��ɑ���̓��������z���c����Ă������ɋC���������́A
�g�C���ɍs���ӂ�����Ē��g�̋����A���z�𑋂̊O(���̓h�u�삪����Ă���Ǝv���Ă���)�Ɏ̂Ă��B
���������ɂ͐l�����āA�����Ă������z���E���ēX�ɓ͂������ł��̏��Ƃ��������A
���͌x�@�ɑߕ߂��ꂽ�B
���n�̏��N�ӕʏ�(�l���J��)�A����ɎR�����̗������ʏ��N�@�ɑ��v���ꂽ���́A
�����ŏ��߂āA���N�B�̊Ԃʼn��s���郊���`��B��ċz���^�o�R�Ƃ����������̐��E�ɐڂ����B
���͂��̎��Ă�@�m�ƍ��d�\�͂ŗ�����낤�Ƃ���B
�����A���������u����Ă������N�⏭���A�����͋��������Ɛڂ��Ă��邤���ɁA
���̐S�ɂ͂���ω����N�����Ă����c
80km/h�����o���Ȃ����E�E�E�E�B
����ł����x�Á`���R�Ԃ͍��S���ォ�����X���[�����i��ł�����ȁB
��̂̉w�́A100km/h���������B�C�ݎ��A�l�ԁA�����A�{�R�A�L�l�A���Y�A��V�]�A�ɗ\����A�ɗ\�y���A��A�����A�ΒȎR�A�ɗ\�����A�ɗ\�O�F�A�ɗ\�x�c�A�吼�A����A�ɗ\�a�C�A�O�Õl�A��ɔg���A�e�ԁA��C�A��Y�A�ɗ\�k��
�m���ɂ��̉w�͒ʉߐ��̗����ɑޔ�������邯�ǁB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���\���\
�@�������@�@�^�@�@�@�@�@�@�@�@�_�@�@�F�a����
�@�\�\�\�\�\�\���\���\�\�\�\�\�\�\�\�\
�@�@�@�@�@�_�@�@�@�@�@�@�@�@�^
�@�@�@�@�@�@�@�\�\���\�\�@
�@�@�@�@�@�@�@�ɗ\�T���w
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\���\���\
�@�������@�@�^�@�@�@�@�@�@�@�@�_�@�@�F�a����
�@�\�\�\�\�\�\�\���\���\�\�\�\�\�\�\�\
�@�\�]�����x�ÈȐ��̈�ʓI�ȓ��}�ʉ߉w�i�����Ȃǂ͏ȗ��j
�i���c������{�e�r�O�w�R�z��l��920�w�x���w�فA1993�N�j
���̐́A�h�C�c���펞�����ŃC�X���G���ɂ������f�B�[�[���J�[�������q�ԂɂȂ����������B
�������B
�ɗ\�T���̍�����1�Ԑ��E2�Ԑ��̕���Y�|�C���g�ɂȂ��Ă��邩��B
�w�̌`��O��̑��x�����̊W�i���R�����|�C���g��������������90km/h�̐����j
�ŁB
�@�@ �@�@�@�@�@/��_��
�@�@/��_,�� �q�i�@߄t߁j
�@�@|�i�@߄t߁j �R ���j) �܂��������I
�@�@�R__��/�P�P�P/ |
�@ �P�_/�Q�Q�Q/
�T�n�����̃L�n58��
���肾���ŁA�������R�A��Ԃ܂ŏ��i�߂Ȃ��ƈ��މ��o���L�O���z�z������Ȃ����Ă��E�E
���6���Ȃ�đ��I���O�̕����ł���ؐG�ꂸ�ɂ��̂܂I����
��荞��ł��ԏ������Ȃ��܂ܑ��ɒ��������A�ǂ���
���߂ċL�O���؋��Ɏԓ����D������炨���ƁA��㓞����ɋq�o�������܂ł̋͂��ȊԂ�
�K���Ɏԏ���{�����Ăđ��˗�������A�X�^���p�[������Ɏ����Ă��̂�
�B�ꃌ�`GJ���������ǂ�
�ԏ�������Ȃ��ăh�A�t�߂ɗ����ĂĂ���Ȏp�������悗
�������|����O�ɂ�����Ă��l�������B�Ō�̍Ō�ɋ�C�ǂ�ł���ėL����`����
����ȑ傰���ȃC�x���g�����҂���̂��r���������Ⴂ���B
���̂��������ʂ肪�ǂ������̂��ȁE�E�E
�����̂킪�܂܂������߂ɁA�j�������G����D/�K�i���牓���Ȃ�s�ւ��������t�����Ă��܂���
�@���̉f���ō��G���̋��������܂���
http://www.youtube.com/watch?v=cPWYZ0qm6FU&feature=channel&list=UL
�@�@�I�����s�b�N�ŗ��������C�O�̒j���ɂ܂ł��y�Ԓj���ւ̕��J
�@�@���̂킪�܂܂����e���Ă��܂������{�̒p
�@
�j�������ʂ��������ȏ��̂킪�܂܂ł��鏗����p�ԗ�����p�~�����悤
www3.nhk.or.jp/news/html/20130907/k10014366821000.html
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/femnewsplus/1378538181/
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�������̃G���W�����͕����Ȃ���Ȃ��E�E�E�B
���ʂ��Č�����_�́A�M�A���オ��Ƃ��A��u�����G���W�������r��邱�ƁB
���̓_���o���Ă����A�ϑ��i�A����1�i�A����2�i�̈Ⴂ���킩��B
���x�v�����Ȃ���̕����ǂ̑��x��ŃM�A���オ��̂��킩��B
�܂��́A5�m�b�`�ł߂����ς���������^�]�m����������܂��傤�B
�������Ȃ��ƁA�C���Ԃ͌��C�悭�������Ă���܂���B
�ϑ��i��0�`50km/h
����1�i��50�`70km/h
����2�i��70�`120km/h
�Ԏ�ɋ����āA����2�i��75km/h�ȍ~�œ�����̂�����܂��B
�d�ԓ��}��110km/h�����o���Ȃ���Ԃ�
120km/h���F�߂��Ă����P�[�X������
���ăz���g?
�����ۂɂ�70km/h�t�߂܂ŕϑ��i�ň��������B
���̂��߁A1�i3�v�f�^�̂�͏�p���x��̑唼�������̈����ϑ��i�Ő�߂���B
�L�n181�n��80km/h��ŕϒ��ؑւȂ̂͂킩����ǁA
��Ƀ��[�J�����ݍs�����̃L�n40�n��͉��ł����Ȃ�B
���̃^�C�v�̕ϑ��@�͓`�B�������̂��ᑬ�^�C�v��舫����ˁB
4,50km/h�ŐؑւȂ炾���Ԍo�ω^�]���o�������Ȃ����ǁB
���k�{����120km/h�ŋ삯�������181�E�E�E�j�Ė��f�̃^�[�{�T�E���h�B
�S�������Ƃ��ɂ������u�͂��Ɓv���\�葬�x�̍ō�����Ȃ���������
�������Ǝv���Ă���A���̓L�n185�ł��卷�Ȃ������͂��B
�u�X�[�p�[�͂��Ɓv�͒q���}�s�ł͍ō��^�]���x��130km/h�������B
�u�͂��Ɓv�͒q���}�s�ł͍ō��^�]���x��110km/h���������B
�u�͂��Ɓv�͓��C���{���E�R�z�{���ł͍ō��^�]���x��120km/h���������ǂˁB
58/28�̋}�s�Ō����҂��̂Ƃ��A���̍���������Ă����B
�V����0�n�Ŗ��ɂȂ����悤��
���������ATC����쓮����Ƃ��Ŗ��ɂȂ葬�x���m�������u���[�L�͂�50%�ɂ���H���{���Ă�
�ŋ߂̎ԗ��͒��ԎԂɑ��x���m����݂���悤�ɂȂ���
E233�Ɏ����ẮA�擪�ԗ��Ȃ��瑬�x���m�p�̎ԗւɂ̓u���[�L����������Ă��Ȃ��B
��o�͂��������肾����
�I
�R���R���R���R���R���R��
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�₭���ŒÎR���I��^�]�������C���Ă��܂����炵��
�\���ԂƃL�n�P�W�P�n�u���������v�u�͂܂����v�ɘA���\��̃L�n180���A�������
���u����Ă���̂��悭���������B
�O�ς͕��}�Ȃ̂ɂ��̉^�]��f�U�C���������Ƃ��Ă͑�_��������
���̌�c�^�}�X�R����201�n�܂łȂ��������A���̌��203�n���]���^������
�^�]�䂾���݂�ƍ���E�u���b�N���C�g�̗p�ȂǂƂĂ�1970�N��̎ԂƂ͎v���Ȃ�
�^�]��̎a�V������������ƍ��S�ł�EF66�ƂƂ��ɑo�����Ǝv��
�i�ł������E�e�V�Ȃ��Ή^�]�������Ƃ͎v��Ȃ����g���������Ȃ���ꂽ�Ǝv���j
���ԎԂɃT�[�r�X�d���p�̃L�n�P�W�P������Ȃ��P�O���Ґ����������A
���[�擪�Ԃ���̋��d�̖��͂Ȃ������̂��낤��
�L�n�P�W�P�n�͂W���Ґ��ȏ�̕Ґ���g�ނƂ��͒��ԂɃL�n181��A�����Ȃ����
�Ȃ�Ȃ��͂���������
�u���Ȃ́v��10���̎����d���Ԃ͗��[2���������i47.10�̍��S�̉^�p�}�\�Ŋm�F�j�B
10���܂ł̓Z�[�t����Ȃ��������ȁB
�h�A�̈ʒu���������Ԃ͕Ďq���A�Ďq�Ԃ͑����ƂȂ��Ă������A
�Ȃ��ԗ��̌����ƃh�A�ʒu���قȂ��Ă����̂��낤��
�L�n�W�O�n�́u���������v�Ȃǂ̒u�������̂��߂ɃL�n�P�W�P�n���Ďq�����������
�]�������Ƃ��ɁA�h�A�̈ʒu�Ǝԗ��̌������������^�]���̃L�n�W�O�n�Ƒ��������߂��낤��
�����Ԃ͔��d�G���W���̗e�ʂ�������8���ђʂ����E
�ʎY��s�Ԃ�1�`4�ˁB
���É����擪�Ԃ��̏�Ő藣���ꂽ���߁A�c�c51�̏d�A�ɂ��������Ă���ʐ^���ڂ��Ă����B
����Ԃ͖��É��w�ɂT�R���x��œ��������Ƃ����B
����Ԃ͖��É��ʼn^�]��ł��������A���É�����\���̃L�n181���A������āA��������������
�s������
�u���Ȃ́v�o�ꎞ��9���������͂��B
�S���W���[�i��1968�N�i���a43�N)10�����ɂ��ƁA�L�n181�̋��d�\�͂�5���A
�A���H���Ԃ��܂ޏꍇ��4���Ƃ���B
�܂��A�L�n181�n�̏Љ�L����9���Z�b�g�Ő}�ʂ��ڂ��Ă���B
���̋L���̒��҂͒J��v���i���S�ԗ��v�������j
���������Ƃ������A�u�₭���v��u�앗�v�Ȃǂł͂����������Ƃ����Ȃ������̂́A
���v���Ԃ����������Ȃ��Ă��G���W���ɕ��S�������Ȃ��悤�ȑ��s��A�ߍ��ȉ^�p�����Ȃ�����
����ł͂Ȃ���
�L�n�W�O�n����̃_�C���Ƒ��x�ʼn^�]����Ă����悤��
���ʋ}���z�ł��Ȃ��H�����ł�181�n�̐��\�����ɂ����B
����ł����v���ԉ������ɒ�ԉw���₹���̂�181�̂��������ƁB
�ԓ��͂��Ȃ�r��Ă����悤�Ȋ���������
���a62�N3�������ō����|���R�Ԃ�110km/h�ɂȂ�����́A����������
�G���W���J�b�g�����o�������ǂˁB
����ȏ�ɃL�n185�n�̂ق����ԗ��̏Ⴊ�Ђǂ��đ�ς������炵�����ǁB
��̂���ēS�N�Y�ɂȂ��Č������Ă��Ȃ��Ǝv����
�L�n126�����������������H�����������������̂Ńm�b�`�X�g�b�p�[�Ńm�b�`�������ăt���p���[���o���Ȃ��悤�ɂ��Ă�����
�l���̂͐V�i�ł��������Ȃ�
�L�͈͂ɂ킽���ĉ^�p����邱�Ƃ������āA�G���W�������Ȃ荓�g�����
����悤�Ɏv����
���̃V�[�g�Ȃ�185�n�̓]���N���X�V�[�g�Ƒ卷�Ȃ��Ɗ��������B
�R�A��l���ł͉��ɃL�n80�n�ʼn^�s���Ă��]�T�̂���_�C���ʼn^�]����Ă�����B
�����y�]�����t���m�b�`�Ȃő����Ă��璆�������≜�H���Ɠ����悤�ȃg���u�����������Ă����낤�B
����Ɏl���ɂ̓L�n65�����ɓ�������Ă�����DML30�n�G���W���̈����Ɋ���Ă����ȁB
�L�n�W�O�n�̃V�[�g�����|���S�n���ǂ��A�����݂�������
���S����̎l�����}�͍ō����x85�L���Ƃ��ƂĂ��Ȃ��x������
���������ꂽ�̂�JR���ȍ~
����Ă���ƁA�����A���|�A�_���A�Ґ����ԁA�����Ȃǂ̍�Ƃ��s���Ă������A
�e��ԂɎg�p�����L�n�P�W�P�n�͗����ȍ~�������Ґ����u���������v�Ȃǂʼn^�p�����
�����̂��낤���B
�L�n65�݂����ɋ������⎮�������ɐݒu����I�[�o�[�q�[�g�����͖��������̂�
�擪�Ԃ̃L�n181�����͖ő��Ɍ̏Ⴕ�Ȃ������Ƃ�
����h�~�̂��߂ɕĎq�Ԃ̓}�[�N�̎~�߃l�W���싞���Ɍ������ꂽ���A�������Ԃ�
�}�[�N��t�����Ƀ��b�N���̏d���ȋ����g�����t���ă}�[�N�����̒��Ɏ��[����
�e�ՂɊO���Ȃ��悤�ɉ�������Ă���
HM�����Ɋђʔ����J���Ȃ��Ƃ����Ȃ��\���ɂȂ��Ĉꌩ�h�Ɛ������܂����悤�Ɍ�������
��ԗ��u���Ɍ��Ǔ���ɂ����Ƃ����E�E�E���܂�Ă����l�i�I�ɍ����g�܂Ŏ����Ă������̂�����邽�߂̑Ή����������H
�d���̋��̂悤�����A
�����|���x�ÊԂ�95km/h�������B
���a61�N11�������ő��x�Á|���R�Ԃ�95km/h�ɂȂ����B
���a62�N3�������ō����|���R�Ԃ�110km/h�ɂȂ����B
�ꉞ�̍������͂i�q�������O����B
���ېݒu���Ă���B
���ڂ͕⏕��p���u��������������p�������C���ɂȂ��ĂĎ�]�t�]���Ă�
�����x��邱�Ƃ����������B�P����Ԃł̑Ό���Ԃ̒x���A
�L�n�P�W�P�n�̐��\�ʂ�R�A�{���̐��`�̈������������̂��낤��
�Ďq�@��̃L�n�P�W�P�n�̈ꕔ���ꑫ�����������^�]���֓]�����A
�R�z�{����R�A�{���A���ߐ��Ȃǂŏ斱���P�����s���Ă����B
�k�l��120�L���^�]�Ƃ��Ζk�{���̏�䓻�������ʼnz����Ƃ��唗�͂ɂȂ��Ă��͂�
�������܌˂���Ⴊ���荞�ތ��O������悤��
711�n����Ԃ��ŏ�4���܌˂����������Ԃ���Ⴊ���荞�ނ��߂Ɍ��Lj����˂ɂȂ���
���q���̑������͓����̃L�n�P�W�O�̗������������^�]���ɔ�ׂď��Ȃ����Ƃ������āA
�L�n�P�W�P���Ďq���擪�Ԃ̎��ʂ�1�A2���A������邱�Ƃ����������A���̕Ґ��͌����ڂ�
�����ėǂ��Ґ��Ƃ͌���������B�L�n�P�W�P�𒆊Ԃɑg�ݍ���ł���Ό����ڂ͗ǂ�������
����܂łW���Ґ��ʼn^�]����Ă����������^�]���S���́u���������v�S��ԂƑq�g�u�͂܂����v�P������
��{�V���Ɍ��Ԃ��ꂽ���A�u�܂����P�E�S���v�p�̂��߂̃L�n�P�W�O��P�o���邽�߂̌��Ԃ������̂��낤��
�܂����̎��_�ŁA�������^�]���ł̓L�n�P�W�P���s���������߂ɃL�n180��擪�ԉ������L�n�P�W�P-�P�O�P���������^�]���ɔz�u���ꂽ���A
���̎ԗ��͓����̃L�n�P�W�P���������ꎞ��Վ���ԂɎg�p���ꂽ�Ƃ��̗\���擪�Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɔz�u���ꂽ�̂��낤��
�_�����Ă��Ȃ����Ƃ��悭���������A�i�L�n�T�W�n�̋}�s�u�O��v�����l�j
���ꂩ�A�����s�ǂ������̂��낤��
���S����͂悭�Б��_�������������ǒP����Ԃ̂��߂������̂�
���œ���ւ��W���ȂƎv�������ǂ���ƃi�]��������
�����ȗ�Ԃ���Ȃ��݂����ŁB
���V���N�V����������a�c�����̃I�n64�n��
�Г_���Ȃ̂𗼓_���ɂ���������
�ԏ����C�Â��ĕГ_���֖߂��₪������
����ɂނ�����
�^�u���b�g��Ԃ͂P��OK���Ă��Ƃ��H�H
����2�ȏ�K�{�Ƃ������Ƃ��B
�P���ł��ǐM��������ƑʖڂȂȁB
�R�A�{���͕ǐM���������悤�ȋC�����邯�ǁA
>>509�̗�͈����Ő�ւ��Ă��낤��?
�u�����̓����������Ɂu�͂܂����v�ȂǂƏ����ꂽ�X�e�b�J�[����������\���Ă��邱�Ƃ�����A
�}�[�N���������Ȃ��Č����ɂ������Ƃ�������
������āA�w�b�h�}�[�N������ɂ����ď��v��������Ȃ��Ȃ����ׂ̏��u����Ȃ��́H
���\�\�������Ȃ������炵����
�����j��������Ƒ�ς������݂�����
�u�܂����v�P�����u�����v�Q�����x�����ĕĎq�ɓ�������ꍇ�́A�ǂ����Ă����̂��낤��
�u�����v�T����u�܂����v�S�����x��ĕĎq���o���������A�Ďq�@��̗\���̃L�n�P�W�P�n�Łu�����v�T�����d���Ă���A
�܂��͗\���̃L�n�P�W�P�n���u�܂����v�P���̕Ďq��]�ԂɘA�������肵�ď��u�܂����v�S�����d���Ă��肵�Ă����̂��낤��
���̌���ł́A���Ȃ��Ƃ����S����̈�����(�ʕ[���)�̒P�s��Ԃ͕Г_���������B
�u���}�͂܂����@�l��̑��v�ƂȂ����܂܁A���C���A�R�z�{���𑖍s���Ă��邱�Ƃ�
�悭����������q�͌˘f��Ȃ������̂��낤��
����֍s���l���ԈႦ�ď��Ȃ��l�ɂ����\�����Ă���
�L�n�P�W�P�n�g�p�̖L���E���`�Ďq�Ԃ̉����A���}�u��������6�E7�v����
����`�Ďq�Ԃ͉����Ƃ��ĉ^�]�A�L�n�P�W�P�n�g�p�̕Ďq�`���R�A���s�Ԃ̕��ʗ�Ԃ�
�L�n�T�W�n�g�p��Ԃ����K�ŏ�蓾�ȗ�Ԃ�����
�i�q��B�ő����Ă����ȐF���Ȃ�
�����N�悪�ςɂȂ����B
���̃T�C�g����B
�����Ŏ֍s���ɗ͍s����Ƃ��ɃG���W���̉�]�������킹��ׂ�
�Q��A�u�[���u�[���Ƌ�Ԃ��������Ă����B
���̌セ��ȉ^�]�͌o���������Ƃ��Ȃ��B
�����̏����g���u�������̂��ȁH
���̗�Ԃ͎R�A�{���ɓ����Ă���Ō���T���Ԃ̃L�n�P�W�P���}�ɃG���W���������Ȃ��Ȃ�A
�Â��ɂȂ������A�G���W������~����Ă������A�j���[�g�����ɂȂ��Ă����̂��낤��
�L�n�P�W�P�̓T�[�r�X�d���̉������邩��ƂR���̐^�̃L�n�P�W�O�ɏ�����B
�Ƃ��낪�S��ԕ��R�n�ŃG���W���͓����Ă��Ȃ������B�T�n�P�W�O�ɂȂ��Ă����B
���~�x�݂Ŗ��ȂŐȂ�ς���킯�ɂ��������A
�g�C���ɍs�������łɃL�n�P�W�P�ŗ����ăG���W�������Ă����B
�A�����x�v��120�L���\���Ȃ̂ŐU���Ă��܂���
�k�C���̃L�n183�n0�ԑ�݂����Ɏԗւ𑁂߂Ɍ�������Ή��Ƃ��Ȃ�͂�
���Ȃ݂Ɏԓ��ł͏�ԏ��z��ꂽ�B
�����̂͂܂����ł́A�����̗͍s����čs�ɂȂ鎞�ɋ�Ԃ������鎖���������B
�쓮���̃G���W�����傫�ȉ��𗧂ĂĐg�k�������u�ԁA�}�ɃG���W�����~�܂����悤�Ȋ����ŐÂ��ɂȂ邱�Ƃ�������
�F�X�ȉ^�]���@���������݂������ˁB
�����̃E�e�V�ɕ����Ă݂����B
��]���N���C�j���O�V�[�g�Ɍ������ꂽ�����A�V�[�g�̐F�͔��Ɣ����̃X�g���C�v���������A
�����̃L�n�P�W�P�n�u�͂܂����v�̃V�[�g�̓��P�b�g�̐F�����ƃu���[�̃X�g���C�v�Ȃǂɕς���Ă����B
�V���ɃV�[�g���������ꂽ���A���P�b�g����������ւ���ꂽ�̂��낤��
�e�[�u�������������߂Ƀm�[�g�p�\�R�����u���Ȃ�����
���߂ė����̃O���[���Ԃ݂�����1+2�ɂ���悩�����̂�
�]����Ƃ������Ƃ����Ă���Ƃ��A�L�n�P�W�P�n�̓h�A���J�����܂܂c�k��
���i���ꂽ�肵�Ă������A�L�n�P�W�P�n�̃M�A���j���[�g�����ŃG���W�����������Ă��Ȃ���������
�h�A���J�����܂܂ł����������Ƃ��ł����̂��낤��
���|�Ƃ���D�R�b�N������Ă���������Ȃ����H
�Ƃ������ǁA�h�A���ԑ̂̊O���i�֏����j�ɊJ���悤�ɂ���Ή��Ƃ��Ȃ��Ȃ����Ǝv��
���Ԃ����ۂ̐v�}�ƌ��Ȃ��ƂȂ�Ƃ������Ȃ����A���ۂ̂Ƃ�������ˉ��͌������Ȃ������̂��낤���H
�����˂ɕύX����Ζk�C���ɂ������ł����C������
��p�n�͌������Ȃ��Ƃ����Ȃ���
�L�n181�͔��̈ʒu�I�Ɉ����˂ɂ���̂͊ȒP���낤��
���ۂɂ����������̂��L�n183�n��㩁B
�L�n183�n�̑�Ԃ͂��������I�[�\�h�b�N�X�ȃ_�C���N�g�}�E���g�����A
����ł���Ԃ��ɃX�e�b�v���������獢��̂͂��܂�ς��B
> ����1�h�A�Ȃ�h�A�ƃg�C���Α��̎Ԓ[�ɐ݂���ςޘb�������������B
���̔z�u�͋q�����Ԓ[�������d���Ŋu���ł��郁���b�g������ˁB
�Q��Ԃ����̔z�u�B�����ǒ��s��ԂɊւ��Ă͋q���ƕ֏��X�y�[�X��
�f�b�L�Ŋu�����邱�Ƃ�D�悵���悤���B
�^�[�{���a������Ɖߋ������グ���邪�^�[�{���O���傫���Ȃ�Ƃ����g���[�h�I�t������������
�̂̃g���^�E�}�[�NII�Ńc�C���^�[�{�d�l�Ƃ��Q�e���m�݂����Ȃ̂�����
���݂��������肵�Ă����̂͒������^�p�������������Ƃ�A�C�݉����𑖂��Ԃ�����������A
�܂��R�A�n���̋C��Ȃǂ��e�����Ă�������ł͂Ȃ���
>>542
�Ȃ�ق�
���S�ɂ��������]�T������������{����181���������Ă��̂�����
�k�C���p�ɂ̓L�n181-500�ԑ�@�Ƃ�����������
80�N�㏉�߂���ɁA�J�~���Y�G���W���̂悤�ȃG���W�����ڂ̓��}�C���Ԃ�����n�߂Ă�����
�L�n82�n�u�k�l�v�������N�C�����Ă����A�k�C���̃L�n181�n�́c
���̎ԗ��͂X�U�N�Ɉ��ނ���
���Ǖϑ��@�����`�̂܂܂ʼn������\������Ƃ��ōL�܂�Ȃ�������
������̋��僉�W�G�[�^���p�����ɂȂ�̂œP���\���������P�����Ȃ������̂��s�v�c
���܂�ɂ��傫������Ƃ����̂łi�q�l���ł͉��R�����́u�앗�v�Ȃǂ��L�n185�n�ɒu���������Ƃ���A�����A�U���͏����ɘa���ꂽ�Ƃ���
�ˑ܂�h�A�G���W���̐ݒu�ŕ֏��������Ȃ邵�֏��_���W���݂����Ȃ��̂œ���B
>>539>>545
���Ȃ��Ƃ��k�C���`�ł͎ԑ̂̒f�M���\�A��Ԃ�@��̖h��E�h�X���K�v�䂦181�n�̋敪�ԑ�Ȃ邱�Ƃ͗L�蓾�Ȃ��B
�܂�������1�G���W���ɑ���璷���̂Ȃ��ɕs�����������ƕ�������������B
���H�������x��Ă����k�C���œ~��̗��������͎����Ӗ�����B
>>543
���Y��p�Ԃł̓g���^�̂ق����Y�A�X�o���A�}�c�_�A�O�H�Ǝ�v���[�J�[�̍��o�̓G���W���ō̗p���Ă�����A�H�Ƃ������̂��̂ł͖����Ǝv�����B
��U�V���O���ɖ߂����̂̓R�X�g�ʂ�VG���ŃV���O���^�[�{�ł����X�|���X���ǂ��o����悤�ɂȂ�������ȁB
��^�Ԃł͎O�H�Ɠ��삪V8�c�C���^�[�{���o���Ă����A��6���ŏ����Ă��܂����B
�Ƃ͂������s�̂����U���^�o�X�E�g���b�N��6�C����4�C�����r�C�ʉ��ƕ����ăc�C���^�[�{�ɂ�������A
�ɒ��]����ߋ������A����]�ł͂���ʂ̋z�C������ɂ͂܂��܂��A�h�o���e�[�W������̂��낤�B
>181�n�̋敪�ԑ�Ȃ邱�Ƃ͗L�蓾�Ȃ�
�L�n82�̗��ꖳ����
����ŋ�J��������181�ɂ͎���o���Ȃ�������B
�G���W���A�G���W���I�C���̓_�������A��ԓ_���Ȃǎԗ��̃����e�͌������Ȃ������悤��
�L�n40�Ƃ����k�C�������Ɠ��n�����Ŕԑ�敪�������������
550�̍l�����炷��ƈႤ�`���ɂȂ肻�������ǂȂ��ĂȂ�
���Ǝl���ɗ��s�����Ƃ��L�n54���l���ɂ����邱�Ƃ�m�炸�ɏ���āA�ԍ������Ăт����肵���v���o������
������54�ƑS�R�Ⴄ�ԗ����Ɗ�������
�I
�R���R���R���R���R���R��
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
���^�]��A�q�ԗ�Ԃ̍Ō���ɘA������ĕĎq�ɖ߂��Ă��邱�Ƃ�������
���V�����Ղŗ��s�����ہA���։w�łӂ��߂����w�����ăK���K���̂��������ԓ��ŐH�ׂ��̂����������B
���V�����ՁA�ӂ��߂��A�����������X�݂�ȂȂ��Ȃ��Ă��܂����E�E�E
�L�n80�n���̂������\�G���W���̊J���Ɏ��s����DMH17�ł�������������݂�����A
�L�n80�n�̂���ׂ����\�����������̂��L�n181�n�Ƃ����Ă����������m���B
���R���ł̍����^�]�ɓ����������\�ݒ�Ȃ�Ă܂������B
�Ȃ�����œo�R�����悤�Ȃ�čl�����낤���c
�R�z�{���ȂǂŃL�n181�n3�A���g�p�����斱���P�����s���Ă������A����܂ŃL�n80�n���^�]���Ă����^�]�m��
�L�n181�n���^�]�����邽�߂̋��K�������̂��낤
�������^�]���ł��C���Ԍ��C�����ǂ����N7������������^�]���ɔz�u�ƂȂ�L�n181�n�̃G���W���̍\��������@�Ȃǂ�
���C���Ă����悤���B
���n�œ��}��Ԃ������ő���悤�ȘH���͂��Ƃ��Ƃ��d������āA
���ǁu�C���Ԃ̓��}�ԗ��v���g���ׂ��H���͎R�x�H���i�R�x��Ԃ�����H���j�����c���ĂȂ���������ł��傤��
�{����181���A�����̐��\�̎ԗ�(�ł����Ƃ�����183?)���k�C���ɗ���Ηǂ������Ǝv��
���������k�l�ɂ͂����Ă��̎ԗ���������
�R�x�H�������p�r���c���ĂȂ��Ȃ�R�p�̐ݒ�ɏo���Ȃ������̂��ˁB
�ᑬ�A�������^�]�K���̉^�p�Ȃ̂ɁA�����^�]���݂ŏd�ʂ̐��ގ��R���Ȃ�āc�B
�ō����x��100�[110���炢�ɂ������Ă��̕����[�M���ɂ���������������Ǝv���B
�y�]���͎R�x�H���ƌĂ�邪�A�k�C���̐Ζk���Ƃ��܂�ς��Ȃ��̂ł́H
�}�J�[�u���������B
����͎������Ȃ������B
������p�t�@�����������͂��P�`���ăG���W���o�͂��Ƃ��Ƃs�ɉ̂�ژ_�����R����120�L���ő���Ȃ�e���p�R�x�H���ł͗�p�s�����I�悵��
�ŏ����狭���ʕ����ɂ��Ă����p���[���X������������̂̌y�ʉ��o������ɃI�[�o�[�q�[�g�����͋N���Ȃ������͂�
��N�⏕���W�G�[�^�������ɕt��������]�t�]���Ă��܂���
�e�펎�����L�n180���̏�ŋ}篃L�n91���A�����ꂽ�̂��낤��
44�g������L�n181�̏d�ʂ�40�g��������x�i�L�n185�n���݁j�ƂȂ�A�o�͏d�ʔ�̌����}�邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ���
���͎ԑ̋��x�����A101�n�̔����Ƃ�����301�n��103�n1200��Ƌ��ɁA���G�x�̌�������Ԃ̉^�p��30�N�ȏ�ғ��ł����̂�������v�ł͂Ȃ����H
���a�S�R�N���͂܂��A���S�Ȏ��p��ɒB���ĂȂ�������������Ȃ��ȁB
���ƕ��ʍ|���ԂƔ�r���āA��T�g���̌y�ʌ��ʂ��������Ƃ���Ă邪
�h���ł̃��X��A�V�䃉�W�G�^�[��d�@��ˑ��͋��x�I�ɕs������
�̗p�͓�����ゾ�����̂����B
��Ԃ�����A�����Ԃ�0.15mm�ȏ�Ƃ�Ɩ������ቺ���ăG���W���̋��X�ɃI�C����
�s���͂��Ȃ��Ȃ�A�t�ɂ����Ԃ�0.15�o�������ƃG���W�����Ă��t���Ă��܂��B
�L�n�P�W�P�n�̑S�ʌ����ł̓I�C�����p���Ȃǂ̗��H�̐����A�z�ǂ̒��ߕt���ȂǓO�ꂵ���`�F�b�N���s���A
�P���̃I�[�o�[�z�[���ɂR�T�Ԃ�v�����Ƃ���
�V�����_�[�����ɐQ�������`���珁���Ɋւ��Ă͈ӊO�Ƀf���P�[�g�������ˁB
�����S���́u���������v�Ɓu�͂܂����v�̃O���[���Ԃ��Q���Ԃ���S���ԂɕύX���ꂽ���Ǝv����
��391�͂Ƃ��Ƃ�����ł��܂��́H
�~���H�ɑa�J���u����Ă���
�������̓d�Ԃ�C���Ԃ̃}�X�R���͏c���}�X�R���̎ԗ��������������炻���������̂��ȁB
�����ė͍s�A�����ăm�b�`�I�t�̕����g���₷���̂ɂˁc�B
�ЂƂ�łɃm�b�`�I�t�ɖ߂�悤�ɂȂ��Ă���B
���S�������قɂāA�}�X�R�����W�����Ă���R�[�i�[�ŐG��Ă킩�������ʁB
�����ʼn����ė͍s�͉c�ƎԂł͗B��
0�n���������̗p��1�������u�����ė͍s�v�ł���i�d�C�@�֎ԂƓ����A�ݗ����ň����ė͍s�̉����}�X�R����1����201�n�ʎY�ԁj
�����ė͍s�A�����ė͍s�A�ǂ��炪�l�ԍH�w�I�Ɏ��R�Ȃ̂��͂킩��Ȃ������݂͎��̂̌�
���̌�͌�҂ɓ��ꂳ�ꂽ�̂ŁA��͂�����������R�������ƌ������ƂȂ̂��낤��
��s�@�̃X���b�g���������͉��������B
�u���[�L�Ɋւ��Ă͔�펞�ɉ����`�����A
���������l�Ԃ͓��삪�����B
���u���[�L���Ƀ}�X�R���A�u���[�L�������������A
�둀�쏭�Ȃ��Ǝv���Ă����̂ł͂Ȃ����ƁB
���ł���ȑ厖�Ȃ��Ƒ��������Ă���Ȃ�
�����������ǂ�
�N�����O���m��Ȃ������Ȃ�ĕ�����Ȃ�����
�����i�D�ł������h���ł��Ȃ����ǂ�
103�n1000�ԑ�̓f�b�h�}�����u�����邽�ߖ߂��o�l�������Ă��Ȃ�
�V����0�n���߂��o�l��������������m�b�`����ꂽ�܂܉^�]��𗣂�˂��݂����������Ԃ�����ɓ����o�����Ƃ�������
���ǁA�t�ɗ���������ȁB
���������̏�f�����ō�_�W�H�k�̍ۂɗ������Ŗ�肪�o���̂�
��f�������쒀���ꂽ�̂Ǝ��Ă�B
�݂��Ă���
2�����炢�͕t���ԘA�����Ă���������Ȃ��̂�H�H
�L�T��2���Ƃ�
�V�����̃}�X�R���͖߂��o�l���Ȃ��̂́A�E��ő��삷�邽�߁B
�����x�ő��s���A�}�X�R�������𗣂��āA�w�����m�F���邽�߂ɂ�����B
�ԗ��_�����s���ۂɂ́A�}�X�R�����m�b�`�I�t�̏�Ԃɖ߂��Ă��邩���m�F����K�v������B
1�A2�m�b�`�ł������Ă�����A�N���[�v���ۂœ����o�����Ⴄ����ȁB
�V�����͍����x�Œ��������𑖂邽�߁A�u���[�L�����}�X�R���̑��삪�d�v�������B
���̂��߁A������̉E��Ń}�X�R���𑀍삵�₷���悤�ɉE���ɂ���̂��B
�p���đ�o�͂̃L�n181�͐�Βj������ȁB
�g���Ȃ́h�ł͌̏�A���Ŏԗ�������Ȃ��Ȃ�̂ŃL�n91�����ɘA�������B
�����ł͂Ȃ����������������Ȃ������݂����B
�G���W���ɔ��͎��ƌĂ��G���W���Ƒ�Ԙg���Ȃ��V���t�g������A���̃V���t�g�ɂ����
�U�����Ԃ�`���ċO���ɓ����H�v�ƁA�G���W���̎ԑ̂Ƃ̌�������e�������Ƃ��ĐU�����ԑ̂�
�`���ɂ����悤�ɍH�v����Ă������炾�Ƃ���
�������͏����������⎮�ł�������
�L�n66�E67�͉����㋭�����⎮�ł���������p���p�C�v���ǂ����Ă������Ȃ��Ă��܂���p�\�͂��ቺ����Ƃ��ŃG���W���������ɓP�����ꂽ
�G���W�������ɂ���A���W�G�[�^�[���O�ɂ���̂ŁA
�������W�G�[�^�[�z�[�X���K�v�B��p���ʂ͈����B
���ƁA�}�j���A���Ԃ́A�g�����X�~�b�V�����ƃV�t�g���o�[�܂ł̊Ԃ�
�������b�h���K�v�Ȃ̂ŁA�M�A�̓���͈����B
1970�N��̘b�B
���̉^�]��͓d���H���ł��������S�^(115-1000)���嗬�̉��B�ɂ͏Ռ����˂�
�����̓�������̑g���͂悭����
�l�I�ɂ͂��̉^�]��Ƒ�n�̓G���W���𓋍ڂ���DC�������������Ǝv��
120�L���^�]��B���ł�������I�ȋC���Ԃ��������̏Ⴊ���������ꋃ����������
���R���⎮���W�G�[�^�̓��[�V���O�J�[�݂�������
�X���`�����ǂ��A���Ȃ������݂̃M���R����ˁH
�����Ɏԓ����X���A�H�ԔɓۂݓS�X���������
������&���X���X���Ă���Ȃ����H
���������݂ŋ�����ǂ����̃X�����U���Ȃ����
���ׂ�S����ԁi�قȂ钼�a�̎ԗւ��v���y���V���t�g�Ōq���S���W���𑪒肷��j�݂����Ȋ�����
�������͒��a����1%�ȓ��ɂȂ�悤�ɂ��Ă邪
http://bunken.rtri.or.jp/PDF/cdroms1/0004/2014/0004006092.pdf
���s�|����E�����ۊԂ́u�����߁v�Ȃɂ��������Ă��ǂ������悤�ȋC�����邯�ǂȁB
�R�z�{���ł͍������\�������ł��邵�A�Z�m�n�`�ȊO�ɂ���Ƃ��������z��Ԃ��Ȃ�����ȁB
HOT7000�Ȃ�V������葬����
��181�͒�ԉw��啝�ɍi������Ō݊p(�����ɂ͕���)������
�����^�����̓I���{�����V�Ԃ�������B
�i���ۋ��Ƃ̏����쌫���͐V�ԓ����őg����ق点�Ă������������j
�������̓J���x�����낤����
���`�P�H�Ԃ͑O���V�����ɋ��܂�ċꂵ�����ɉ^�]���Ă���
�L�n189�n�ɂȂ��ĉ��P���ꂽ
�����Ɛ��������̂��}�s������܂�95�L�������o���}�s�̂����ɐV�����ɒǂ���������Ă�
���݂ɃL�n80�n�̂����߁E�����͓���Ԃ�65���ő��j���Ă�����ȁB
����Ԃł͗����������킷��X�s�[�h�Ŕ���Ă����ǁA���|�P�H�ł͓��}�ɉ������Ă��悤�ȃ_�C�����������B
�L�n�P�W�P�n�̏斱���P�����R�z�{���Ȃǂōs���Ă������A�����͕Ďq�@���������^�]���ɂ́A
�L�n�W�O�n�ƃL�n�P�W�P�n�𗼕��^�]�ł���^�]�m�͂��Ȃ������̂��낤��
���������}�ɉ�������͓̂��R����
�m���S���Ȃ��A�K���Ȃ��Ə����Ă��܂A50.3�܂Łu���Ȃ́v��181�n�ŁA
��ԗ��u���������������i����͊m���j����A�����炩�͋�����Ȃ����B
�܂��A�Ďq�͔������u�₭���v�������Ă���Ȃ����H
��481�Ƃ��L�����p���Ă��̂Ɂc
�i�グ��́u�����v��181�n�ŋ��s����o�Ă܂������ȁB
�c�c�T�P�̏d�A�Ɍ��������Ƃ������Ԃ������������A���̎��A��q�͋��낭�ɗ����Ȃ��Ȃ����������C�̂悤�Ȏԗ���
���É��܂ŏ悹��ꂽ�̂��낤��
�V�������}�s�����������
�}�s������܂��L�n181�n�ɂ���悩�����̂�
����ɂ����̏Z�l�Ȃ�Ƃ����̐̂ɑ����Ă邩��
�k�C���ɓ]�p���ăL�n183�n�̐H���ԂƂ��Ċ��p����\�z���������炵��
�L�n80�n��3�i6�v�f��DF115A�A�L�n181�n��1�i3�v�f��DW4����������ˁB
�������A�ŏI�����䂪�Ⴉ�����̂ŁA�V�t�g�A�b�v���x�͑O�҂�70�L���A��҂�85�L���������Ɓc�B
�L�n80�n�̓L�n58�Ɠ��l�ɕϒ��ؑւ͎蓮�ؑւ������悤�ȁc�B
�L�n58��2.976
�L�n80��2.613
�^�[�r����3�i�i3���j�A�X�e�[�^�[��2���A�|���v�C���y���[��1���Ƃ����\���̃g���N�R���o�[�^�̎��B
���v6�̗v�f���琬�藧���Ă���B
�����ԗp�̃g���N�R���o�[�^��1�i3�v�f�^���嗬�A
���ꕔ�ɂ�1�i4�v�f�����݂���B
�g���N�R���o�[�^��1�i3�v�f�A3�i6�v�f�̑��ɁA1�i4�v�f�A1�i5�v�f�A
2�i4�v�f�A2�i5�v�f�A4�i8�v�f�����݂���B
1�i3�v�f�ɂ��A�O�����^�[�r���^�����݂���B
���̌p��̏ꍇ�́A�X�e�[�^�[���������߁A�\���I�ɂ�1�i2�v�f�ł���B
�L�n85�n���C�h�r���[�Ђ���10���A�����Ă���̂�����Ɠd�����Ă��ǂ������Ǝv���B
�u���Ȃ́v�u���v�u�₭���v�u���������v�L�n181�n���������ǁA�d�ԓ��}�ɂ�����v�͂������ȁB
�u�Ђ��v�u�k�l�v���d�ԓ��}�ɂ���v��͗L�����炵���B
��E�\�B�ԗ����E�ɒ�G���錚�z���E��������炢��������B
���r���[�ȃW���C�t���g���C���ɂW�R�𖼏�点�����Ȃ������D�D�D�D�D
180�xV�^�G���W���́A���E�̃s�X�g�����N�����N�s�������L���Ă��܂��B���̂��߁A���E�s�X�g������̂ƂȂ������̂悤�ɁA�ЂƂ̓����Ƃ��ĉ������܂��B
�o�����X�ʂł́A�����Ό��G���W�����s���ɂȂ�A�U�����N���₷���Ȃ�܂��B���ʁA�N�����N�V���t�g�̒�����Z���ł���̂ō������グ�₷���A
�܂��A�N�����N�P�[�X�̈��͂̊W���獂��]�ɗL���Ƃ������ʂ�����܂��B�������X�|�[�c���f���A�X�[�p�[�J�[�̗ނ����S�ł��B
����܂ł̗̍p���R�[����12�C�����f���i�e�X�^���b�T�A365BB�A365GT/4BB�A512BB�A512TR�AF512M�A�x�����l�b�^�{�N�T�[�j�������Ƃ��L���ł��B
�g���[���[�̃N�Z�ɂ��̕ϑԑ�Ԃ𗚂������_�ŁA�ፑ�̎g�p�͋p������Ă����c�B
�L�n80�n�����菊�v���Ԃ�10���قlj��L���ꂽ���A�Ȃ��X�s�[�h�_�E�������̂��낤��
�L�n80�n��苭�͂ȃL�n181�n�Ȃ�A�L�n80�n����̃_�C���̂܂܂ł�����������������āA
�t�ɑq�g�A�Ďq����2�A3���͑����Ȃ��Ă����̂ł�
���J���݂Ƃ��H
���s���P�Q���P�W���ƂR�������Ȃ������A��̉����ŋ��s�����P�Q���Q�Q������
�Ăђx���Ȃ��Ă���
�����H�̓d�����A���̋C���ԂƈႤ�̂ŁA�V�n��Ƃ���100��̌`���ԍ����^����ꂽ�B
��o�͋@�ւ����炩�Ǝv���Ă���
�������c�����ł���Ȃ���u�����ė͍s�v�ł���i�V����0�n��201�n�́u�����ė͍s�v�j
�}�X�R�����ꂽ�܂܉^�]�Ȃ𗣂ꏟ��ɓ����o�������Ⴀ���������H
�V����0�n�Ń}�X�R��������ςȂ��\���������Ă��܂�����Ă��ꖱ�ԏ�����������Ԃ������Ȃ����Ƃ�
�ԈႦ��
�c��������Ȃ��ĉ�����
JR�l���̃L�n181�n���Ĕ�r�I�V�����ăA�R�����P�����č���b���g���\�肾�����̂ɁA
���ˑ勴�u�[���̏I���ƍ������H�̋}������2000�n�ɒu���������ꂽ�B
���ˑ勴�ő������N��������
���̊���ɷ�181-1���180-1�݂����ȌÂ����p���ݐЂ��Ă��݂����ł��������{���Â����p�̊��������Ȃ������H
�l�I�ɂͷ�126�̕���������ۂ�����B
�����ő����Ă���
���x�v�����̂�120�܂ł����Ȃ����琦������
�k���{����ΐ������ł͂S�W�T�n�́u�����v���l�ɂP�Q�O�L�����s���Ă����̂��낤��
�����Ȃ̗p�̓]���ԂƎl���ɐV���z�u�����ԗ�����������ɂ��čl���Ă��ˁB
�܂��A�����Ȃ̎Ԃ͍����ɂ��Ďq�ɂ��������A��181�̃��X�g�i���o�[�͕Ďq���������B
�R�z�����͂��Ȃ�h�ꂪ���������B�����c�t�����������]������蕨�����ŃQ���f�����ʂ������B
�V����(������117�n)�͂����܂ō����Ȃ������Ǝv�����A����͋O�����ɋN��������̂ł͂Ȃ�
�L�n181�n�̑��̖�肾�����̂��ȁH
�ߎS�ȃL�n181�n���}�u���Ȃ́v�A����ł����Ɂi�^�ӂ�Q�Ɓj
��������N�͂��Ȃ̂͋@�֎Ԍ������Ǝv���Ă��悤����
����^�ł�����ȍׂ������������̂������c
�ł��V�^�ԗ�(185)�͌y������Â��Ȃ͂����ė^���Z���͊��҂��Ă��݂���������
�n���e���r���n��Ōv�������Ƃ���181��185�œ��ɍ��͂Ȃ������Ƃ����I�`
�q���������ꏏ���ǂ����Ƃ����������ǂ��Ƃ��܂ł͂����
���Ԃ��Ă���120km/h�ɂȂ�܂Ŗ�3km������������ˁB
�����ɂ���邪�A���Ԃ�1��30�b�A������1.5km���炢�B
�L�n40�̏ꍇ�́A���R�ȋ�Ԃł����Ă�3���ȏォ���邪�c�B
https://www.youtube.com/watch?v=dzPCw16TO9Y
��𗣂��Ă��m�b�`������ςȂ���
��Ȃ���Ȃ���
�߂��o�l�Ȃ��͓d�C�@�֎Ԃ�V����0�n�Ō���ꂽ
�g�@�^�]�͈������ݐ��ɂ����āA�����悤�ȑ��x�ő���Ȃ���s���Ƃ����B
���{�ł͒�ԏ�ԂŒg�@������̂����ʂ����c�B
�L�n181�̃}�X�R����211�n�A205�n�A�L�n110�n�Ɍ�����u�����ė͍s�v�ł͂Ȃ��A�u�����ė͍s�v�ȂȁB
�ׂ�ɂ���L�b�N�_�E���{�^���̓}�X�R����K�X�悭���삵�Ȃ���A����̐e�w�ʼn�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�t�]�n���h�����O����̏�ԂŃ}�X�R�����ق�̏����ł����ꂽ��N���[�v���ۂő��肾���Ă��܂��܂���ˁB
������L���āA������Ƃł͋t�]�n���h���̈ʒu���悭�m�F����K�v������B
�t�]�n���h���������̏�ԂȂ�A�G���W�����K�[�K�[�ƚX�邾���œ����Ȃ����c�B
�L�n110�n�̋�Ԃ������t�]�n���h���������̏�Ԃōs���Ƃ����B
https://www.youtube.com/watch?v=O1HRbHpBK9k
https://www.youtube.com/watch?v=O1HRbHpBK9k
https://www.youtube.com/watch?v=O1HRbHpBK9k(�͖k�Ȃ����l�w�A�J�������o���N�h�[�n�̔ߌ��r�W�l�X
(��Ƃ�s���Y������ߕ����|�C���g�����X���p�F����ēJ�N�e���i�C�g
kwsk!
�������ϑ��@�����`�̂܂܂ŏo�͂��ቺ�����̂�1�������ŏI�����
DMF18HZ��p����Ή�����������i600PS���ւ邪���X�D���p�����v�������̂ŃL�n182�]200�ԑ�ł����g���Ȃ�����
�b�S��̃J�o�l���̍b�S��Ō����A����ʖ����𑖂点�āA�H�Ղݔ����̂ɋ߂��ˁB
�d�ʋ��̋C���Ԃ��ȈH���ւ̓������ł��Ȃ��̂́A�H�Ղ̎コ�̖��B
�X���u�O���ł���A�L�n181�n�Ȃ�30kg���[���ł�����95�L���قǂő��点���Ƃ���łȂ�Ƃ��Ȃ����c�B
�L�n�P�W�P�n�Ɠ����G���W�����ڂŁA�L�n�P�W�P�n���d�ʂ̏d���L�n�U�T��
�A�������L�n�T�W�n�̕��ʗ�Ԃ́A�����̕��R��Ԃł̓X�s�[�h���o�Ă��悤������
�U�����Ԃ���O���ɓ������ĐU����}����H�v�Ȃǂ��{����Ă������߁A
���s���͐U�������Ȃ��A�ԓ����h���{�s����Ă��悤�ő��s���͉��K������
�L�n40�n�ł܂��h���邱�Ƃ��\�����ǁA
��o�͂̂��͉̂ߋ��̂��̂ɂȂ����̂��c�O
�L�n65������ւ�
�R�A�n��ł̍��S�^�C���Ԃ̓L�n�S�V�n�����ɂȂ�����
���������Ǔт͑S�Ċ����Ԃ����
���^�G���W���́A�k�̈ꕔ�A��̈ꕔ�A�l����(40�n)�S�Ԃ���
�P�O�R�n�d�Ԃ̂悤�Ƀ��j���[�A���H���≄���H�����{����Ă邪�A
�V�������i��ł�����A�L�n�P�Q�U�n�ɒu���������Ĕp�Ԃ���邩��
�A���J�[��>>�t������
����̓K�Z�A�L�n80�n�̕����m���ɐÂ���������B
DML30�n�g�p�Ԃł�65�����̃G�[�f���Ԃ����i�ɐÂ��A4VK����ĂĂ�
�C�ɂȂ�Ȃ��ʁB
�����◯�u���Ȃǂɂ悭�|�c���Ɨ��u����Ă������A�L�n�P�W�P�n�̊e���}�̑g����Ƃ�
�Ґ��g�݊����Ȃǂ͗[�������Ԃɂ����ĉ^�]���ɋA�悵�Ă���u�����v��u���������v�Ȃǂ̓����ɍs���Ă����悤�ŁA
���Ԃ̓L�n�P�W�P�n�̎ԗ��ړ���g����Ƃ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�D���p����13���b�^�[��900PS�Ƃ������̂����邪����͊C����W�����p���Ƃ��Ė��s���Ɏg���邽�߂œD�����z������̏�̌����ɂȂ�
��ԋ�������JR���ɂ́A�܂��܂��I���W�i���n�̓L�n40�n�����������c���Ă邺
���̉������\�̃N�\�����̓}�W�ŋ�����Ȃ��
���̋Z�p�����肷��܂� ��q�� ���K�v�Ȗ��
��]���ɕ����Ƃ��낪�傫���ł��傤
�D�̃G���W���ł͉�]�����n�͂ɑ傫����^���邪�ADML30�́A2000��]�܂ōs���̖Y��Ă��B
DML30�͑S�R���߂��ˁB�M�ʂɔ��������āA�g�킸�Ɏ̂ĂĂ銴�����ȁB
����DMH17��1200�n�́i�[���؎̂āj
http://www.mtu-online.com/mtu/products/diesel-engines-overview/general-purpose-diesel-engines/2000/
���ŁA�v�҂͋C�t���Ȃ�������H
���W�G�[�^�[��p�t�@���������͂܂ŃP�`�������Ă����������낗
���d�Z�b�g������̈ꕔ��苒���Ă��Ėʓ|����w
�������A���Ȉʒu�̈Ⴂ�͔F�����Ă��
���F �]���C���ԂɗႦ��ƁA�L�n66�n�ɂȂ�̂͂��̂����B
峎t�̃M���R�̓L�n40�n�ɂȂ邵�c�B
�Ƃ��閂�p�̋֏��ژ^�̈���ʍs�͓��RJR�����{�L�nE140�n�C���Ԃ����c�B
���W�G�[�^�̗�p�t�@���܂ŏȗ����ĂƂ��Ƃ�P�`���ē��͂ɉ����Ă�
F1�}�V���̃��W�G�[�^�����R��p�Œ����ԃe�[���E�g�D�[�E�m�[�Y����ƕ���������Ȃ����߃I�[�o�[�q�[�g���Ă��܂�
�Ñԕۑ��L�n181�������Ƃ��A�I���͒��������������̂��Ǝv������
>�O�}�S�����H�ŋu�ɏオ�����J�b�p��Ԃ̐Ñԕۑ��L�n181
�O�}�S�������Ėk�C������ˁH�Ȃ�L�n181�ł͂Ȃ��L�n82�Ȃ��B
���n�r������
�v�����ă��W�G�[�^�[��P�����Ă����Ȃ������̂ł́H
�L�n65�͌����狭�����₪�����ɂ����ĉ��ɂ����J���ŏ[�����Ă��I�[�o�[�q�[�g�͋N���Ȃ������H
�����̋Z�p�ł͒���2�i(�@�ρ���1����2)���ł��Ȃ��̂͑O��Ƃ��āA
{ �ρ���1�@�܂��́@�ρ���2 }
�Ƃ����ϑ��V�X�e��
���R�n�ł́A�v������181�n�̕ϑ���ŕρ���2
���z��Ԃł́A�L�n65�̕ϑ���̕ρ���1
�\���I�ɂ͍ŏI�����@�t�߂ɕ��ϑ��@������A�^�]�ɉ����ďI��������ւ��邱�Ƃ��ł���B
���s���͐�ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂Œ��Ӂi���������ƃK���K���ƂȂ��Ď��Ԃ��j�����錴���ɂȂ�j�B
���̕��ϑ��@�̓X���C�f�B���O���b�V�����i�����������j�ł���A�V���N���@�\��������Ă��Ȃ��B
�{�����[�h��85�L���œ������[�h��45�L��
�u6�N�O�ɂ͂܂����̎ԗ����̏Ⴕ�A�o�X�ɐ�ւ����v
���̏Ⴕ�Ƃ�����
�c�b�̒m�����Ȃ��Ă��̕ӂ��S���������ĂȂ���
https://www.youtube.com/watch?v=uWLnfkOLmfk���s����ڂ������������i
�_�C�G�b�g�j���[�X (�A���o�o�_�C�G�b�g�S�O��U�������v��������(���t�[�W���p���^�C�������(40��u���b�N�o���G�e�B���H���c�k���j
��@������D���ݓ������l�����ԃ��R�[��������p������s�@���
���t�[�l�b�g�_�C�G�b�g�R�[�q�[�j���[�X�^�E�����[�N�T�[�r�X�s���܂������}�C�J�[�ޓ���
�����h���}���E���r�[���ڂ�������̔����K�����i
�K���r�W�l�X�j���[�X�v��������V�Љ�TRUMPTOWER���J�u���v40��Ď��J�����g�p�R���v���C�A���X���ԏ� (������}���R����TPP��聚��
�g�����v�W���[�J�[��(������w���h���R�X�g�J�b�g�A�C�h���}�X�^�[�A�b�v������Ѓe���r�r�W�l�X�X�F�w���p�`���R�K���@�I�[�N�V�����̔�����j
NHK�����l�p�g�����v�哝�̃e���r�j���[�X�i���t�[�W���p����@�Ј����ʐ�����x�����s���ꉘ�����X�L���P�A�e���r���������M�����u���ˑ��njږ�E���j
���t�[�W���|���}�C�m���e�B�Ј��u���{�ƃ��V�A�͒��ǂ������Ă͂����Ȃ��[hondasouichirou�[�v(�ݓ������l3�����Z�j
�������z�̕x�T�w���q�J�W�m�ʂ��A���A��I�[��TRUMP�p�[�e�B�[�}�X�N�����w���}�X�N�I��NACNN���������_�r���`�����i�j�b�J���j�����t���a�J��̗t�����j���[�X7��5�疜
�u���Ȃ́v�Ґ��i8M1T�j�Ŗ��É��[����Ԃ��V�~�����[�g����ƁA��1,700���b�g������A1���ɂ��Č����
���b�^�[������1.3�L�����x���邱�ƂɂȂ�A�ԑ̂̑傫�����炷��ƈȊO�ɔR������Ƃ��v���܂��B
�ގ��̏�����85�n���g���ăV�~�����[�V����������Ă݂�ƃ��b�^�[�������1.8�L���ƂȂ�A
�������A����2�i�ϑ��ɂ���R��̌��ʂ����Ȃ茻��܂��B
�L�n35�n�ƃL�n110�n�ŃV�~�����[�V����������Ă݂Ă��A���l�Ȍ��ɂȂ�B
��Ԃ̓��b�^�[������350���[�g����������Ȃ��ƌ����Ă������A�L�n20�n�͒�R�̏��Ȃ��S�H�𑖂�̂ŁA
�������ǂ���A���b�^�[������2�L������̂ŁA��Ԃ�萏���R������Ɗ����܂��B
�ρ�����ւ��̓t���m�b�`��85�L���������}�����邭���ɍō����x65�L���Ƃ��ُ킾����
�ϑ��i�������Ǝg�����ςȂ��ɂ���ƕϑ��@�I�C�����x���ُ�㏸���邽�߂ɉ�ÓS���L�n8500�Ŗ��ɂȂ���
�ɗ\�s�`���q�ȊO�͍ō����x�ɓ��B����O�ɃJ�[�u�Ō������K�v�������Ǝv����
��̓����ƐႪ�ς����Ă߂���₦���������낤��
��������������Ėc�������W�G�[�^�[���j������댯�����������͂�
https://www.youtube.com/watch?v=kcQnYK84Pms
�ƌ������A�A�L���̋��c�̃o�C�N�ɋ߂����\�������ˁB
�L�n181�n�͉ˋ�̃L�����N�^�[�ɗႦ��Ȃ�A�߂����{�b�N�X�̍��_�߂����A����V���[�Y�̐�ꃖ���Ђ����ɋ߂��B
�[���_�̓`���̃����N�́A�L�n110�n�ɋ߂�����ˁB
�o�ϐ��̓����N�̕�����ł���B
���y�ʉ��ƒ����G���W���ƒ������i���Ɠd�q���䂪�K�����Ă���B
�g�����v�W���[�J�[��(�n����w���h���R�X�g�J�b�g�A�C�h���}�X�^�[�p�C�i�b�v��������Ёj30��D�]�l�C�A�ږ���u�q�J���̌邨�O�牽��v
NHK�g�����v�哝�̃j���[�X�i���t�[�W���p����@�Ј����ʐ�����x�����s���ꉘ�����X�L���P�A�e���r�����M�����u���ˑ��njږ�E����c�Ēr�L�c
40��Љ�l�W�c�X�g�[�J�[��[hondasouichirou�[ ���l���A�i�v���X�y�C���㐼�t���C���O�t�@�C�A�[�E�H�[�^�[�T�[�o�[�_�C�r���O�h���C�u�V���[�g�쒆
�������z�̕x�T�w���q�J�W�m�ʂ��A���A��I�[��TRUMP�p�[�e�B�[(������s�@�_�_��U�z�}�X�N�����j�w���}�X�N�I��NACNN���������}�}�j���[�X
2���̎ԗa�͌����ɍ��킹�Ȃ���Ȃ炸�덷1�~���ȉ��ƌ������ݒ肳��Ă���
�ԗa���قȂ�Ƃ��ׂ�S����Ԃ̂悤�ɂǂ������Е��������Ĉُ햀�Ղ��Ă��܂�
�~�ԗ֓]��Ղ��g����
�Z�ԗ֓]��Ղ��g����
SL�̎���͐��֎q�Ƀo�C�g��t���č\�����u���[�L���|���Ȃ���]�������}�I�Ƀt���b�g����菜���r�Ƃ����݂���
�u�����N�A50�~���̃o�C�g������Ă��Ă���邩�ˁH�v
�����N
�u50�~���̃o�C�g�H�����H���ՂŎg��50�~���̐ؐn�ˁB�v
����n�̋D�J�ł́A�����C�̏d�����̌o��������̂ŁA
�������H�@�B���g�����Ƃ��K�����Ǝv���B
��Ԓ��̓J���J���ƃf�B�[�[�������������邯�ǁA�������i����Ƌ쓮�n���̑��́u�L���C�[���v�Ƃ������������C���œd�Ԃ̃��[�^�[���݂���
�^�]���ł̘^���ŁA�L�n181�n�͂��̌�납��̋쓮�����傫������d���Ȃ��낯�ǁA�q�Ȃŕ�������S�n�ǂ��G���W�������y���݂ɂ��Ă������ɃK�b�J��
181�n�ȊO�ł��W�]�\�t�g�ŋO���Ԃ̎ԓ��G���W�����y���߂�Blu-ray or DVD�̃I�X�X�����ĉ����Ȃ����ȁH
�ŏI������ς��Čΐ����Ɏ��������160�L���^�]�̎�������ė~��������
JR�k�C�����L�n183NN��153�L���o���Ă邪�C���Ԃ̍������͂ǂ������ɓI
��p�Ό��ʂ̖�肪��
���`�I�ɍ����^�]�\�Ȕ�d���H�����v�����Ȃ��̂��
���������d������ō�160km/h�ł̉^�]�͗e�Ղȏꍇ
�����ċ�������Ńf�B�[�[���ō���������Ӗ�����̂����Ęb�ɂȂ�
��i�ł�500PS/1600��]����100�L�������o�Ȃ�
�K������470PS�ɂȂ����ԗ����o�Ă�
���Ƀg���u�����o�Œ��肽�̂����̋C���Ԃ͒�i�͈͓̔��ōō����x���o��悤�ɂ��Ă�
�Ώ��A�k�z�k�A�q���A�����A�����A�h�сA�����
�Ƃ����Ă��Ώ��ȊO�͕��R��Y���|�C���g�ō���Ă�����
�����ʕ��{440PS�f�`���[���̃L�n182�ŕs�����N�����ĂȂ�����
���ꂮ�炢���K���������낤��
�t���X�s�[�h�ő���ƁA���[�^�[�̐j���U��ꂽ��ԂɂȂ�B
�����ۂɂ́A�ڈ�t�o���Ă�110�L���قǂɂƂǂ܂�^�]�������̂ŕs�s���͂Ȃ������B
�L�n58�n�͎���95�L���܂łȂ̂ɁA���x�v��120�܂ł���̂́A
������z����\���������ɉ��L���o�Ă���̂����킩��Ȃ��Ȃ邽�߂̑[�u�ƌ����悤�B
�����JR�k�C�����쒀�ɓ��ݐ���
DMF13�n�ł��u�[�X�g���v��������グ���600PS�ʏo��
���D�p�G���W���ȂC�����p���Ƃ��Ė��s���Ɏg����̂�DMF13�n�̃T�C�Y��900PS�o��̂���
�d�Ԃ�183�nATC�Ԃ��ڐ��肪120�L���܂�
103�n��ATC�Ή����[�^�[�𗬗p�������߂݂�������
���R���⎮���W�G�[�^�[���R�x�H���ō����ׂł�����葖��Ɨ₦�Ȃ�
����F1�}�V���݂����ȋC���Ԃ�������
�ō����x��65�L�������Ȃ��������S����̗\�]�����R�Ȑ��Ƃ����H�K�i�̒Ⴂ�H�����ƕϑ��i�݂̂ő��s���邱�ƂɂȂ�R���������������
�ꕔ�͖��c����Ɏ���������
�L�n65�͏����ɓ��ꂽ�����W�G�[�^�[������Ȃ��߂Ƀg�C���^���N�������Ɏ��܂炸�g�C���ݒu��f�O����
�f�B�[�[���G���W���̓K�\�����G���W���ƈ���ăm�b�L���O�̐S�z���Ȃ��s�X�g����V�����_�̋��x���E�܂ʼnߋ����グ����
80�N���F1�͗\�I�Z�b�e�B���O�ʼnߋ���6.5bar��1500cc��1500ps�Ƃ����ٓI�Ȃ̂��������w�ǃg���G���Ƃ����L�łȔR�����g���K�v�������ăs�b�g�N���[���K�X�}�X�N�𒅗p����n��������
�����N�́A�N�ł������₷���悤�Ɍo�ϐ����d�������ݒ�ŁA
�X�R�[���E���I���n�[�g�ł́A�����x���d�������s�[�L�[�Ȑݒ肾�Ɓc�B
�����s���\�͖ڈ��ł��B
���ۂɂ́A�����N���X�R�[���E���I���n�[�g�ɔ��鐫�\���o���܂��B
�n�`�S�[���L�n82�n�ŁA�n�`���N���L�n181�n
�����ăG���W���u���[�������L�n181��
��p�̃L�n183�̒����^�[�{�G���W����
�ڂ�����660PS�̃L�n181���a��
�L�n183N�ł͒��������ĉ��P����
�L�n181�n�ŃV�����_�u���b�N�����Œ������`���[�������̂�������ǂ��Ȃ��Ă�����
�L�n40�ł͎��݂���
>����ȃ��W�G�[�^�[���v��قǔr�M���傫�������̂���肾������
�ʂɂ���ȏ㏬�������W�G�[�^�[����ʖڂ��������Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ�
���R�ʕ����ɍS�����܂��������̂���
���ۃL�n181�`�̎��R�ʕ������W�G�[�^�[�͖��N�����ĂȂ�����
DML30HSH�G���W�����������āA530�n�͂ɏグ��Ƃ��A���ɖ��������c�B
DMF15HSA�G���W���̒��������ł́A�����I��265�n�͎�̐��\�ɂ����߂��Ȃ��B
���̎���̓S���Z�p�҂͐�O�̍q��Y�Əo�g�҂��܂�������������
�{���@��Y�݂����ȋ��M���������̂��ȁB
����G���W�����₷�ׂ̐������邾��
���̐��̓G���W�����₷�ƍ����ɂȂ邾��H
������₷�̂����W�G�^�[�̖���
��p����₷�̂܂Ő���ɂ����炢�����p���ς�ł�����Ȃ��Ȃ���
���ǂ͕��ʂ��ė�₷�����Ȃ�
���̕������R���i���R���s�ɂ�蔭�����鑊�ΓI�ȕ����܂ށj�ɔC����̂����R�ʕ������W�G�^�[
�t�@����t���Ă��̕��ŗ�₷�̂������ʕ������W�G�^�[
����������i��1500��]�������ꂾ��100�L�������o���Ȃ�
�L�n183N�����i�͈͓̔��ōō����x���o��悤�ɂ���
���R���W�G�^�[���g�����Ƃ��ړI�����Ă����悤�ɂ��v���邪�B
���V�v���G���W���ł����������W�G�^�[���đ��̏�蕨�Ő�����͂���́H
738�Ɣ����ɕς��Ă�����
�����Ƌ��ɓ������Ă���L�n181���ŏ������Ƃ���
���Ȃ��炸�Ռ������������̂�B
�L�n120��50�L���ŃL�n47��30�L���Ƃ���̑��x�����|�����Ă�g���l�������邪�����ŎC�����H
EF71���S����15�������Ȃ��A�����ŏI�`3���͎R�`��ɏo�����Ă����B
���d��������13~15�͕ߋ@�ɕt�������Ƃ��Ȃ������B
72�N�Ɉꎞ��ED78���ߋ@�ɕt�������Ƃ����������S���d�ʕs���Œf�O�����B
�������901�ȊO11���S�@�B
EF71���R�`��3���o���Ă����A������12���A�ߗp��1���c����11����4����ߋ@�ɉȂ���Ȃ�Ȃ���������A���̗�Ԍ����̉^�p�ʂɎx����������悤�ɂȂ��Ă����킯�B
EF16��64���z�u���������Ȃ���������ˁB
�O�X����EF63�݂�����葤�Ɉ��ɘA����������킯�ł͂Ȃ���������
�}�j���A���ǂ���ōςޖ��ł��Ȃ������B
�A���J���܂߂ĉw��5���͒�Ԃ��Ȃ���Ȃ炸�A���Ԉ��̘J�͓I�Ȗ����������B
���̎��̂ŃL�n181-13�35�ƃL�n180-8���p�ԂɂȂ����B
�L�n��35�Ȃԗ�킸��3�N��..
�C���ł��Ȃ������ł͂Ȃ��������������A��͂荓�g�ŃK�^�����āA�܂��A�]������肩�łȂ��������炵���B
�p�ԓ��t���͗��N1��17���B
���ꂪ�L�n181�n�B
���O���Ŏ����Ŏ��₵�Ď����œ����o���Ă�́H
�L�n80�́u�����v���������d�ʓI��7���Ґ������E������
�L�n181�n�͋�����12�A�^�]�\�ɂ��Ă���7�A�ȉ���������u�����v�ɂ��Ă��͂�
�G���W�����A�C�h�����O�ɂ��Ă����̂Ȃ�u�����^�]�v�Ƃ͌���Ȃ����낤���B
�Ƃ���l�b�g�̋L���ŁA�ׂ�������͂����A�L�n181�̕��͂������������ɂ��Ă����Ƃ����b�����邪�A����̓G���W���u���[�L�����邾���ɂ��Ƃ����̂��낤���H
�����A�d�Ԃ�DC�Ƃ̖{�i�I�ȋ����^�]�̃e�X�g���s��ꂽ���A���p���ɂ͎���Ȃ������킯�����B
����������ɂ��邽�߃L�n181�n��菬�^�Ŏ�}�V�Ƃ͂�����p���̗ʂ����ɑ����Ȃ�͔̂������Ȃ�����
��������Ƌ����^�]�͈Ⴄ����ˁB���@�̏d�A�Ȃ͋����^�]����B
�����Ƃ��A�d�Ԃ̕��̏o�͈͂����x�ɗ}�����Ă��邻���ŁB
�J���̏ꍇ�͗��j�I�o�܂���DC���������͂ł͂Ȃ��AEL�͂����܂ŕ⏕���Ă̂����������������̂�������Ȃ���
���[���A��������DC�̃G���W���A�A�N�Z�����߂ɁA�ƘA���������悤�ȁB
������JR�k�C���L�n201�̋����^�]�ɔ�ׂ�ƁA�����A���n�I�Ȃ��̂ł͂��邪�B
�L�n181�n���͋����^�]����Ă��Ă��A�^�p���Ս����������ƂⓌ�k�{���ł�
120�L���^�]���邱�Ƃ������āA�Ƃ��ɉď�͎ԗ��̏Ⴊ���o���Ă����
����Ă���b��ɂȂ������낤���I�[�o�[�q�[�g����������
���v�ɔz�����̂���L�n181�̃}�X�R���ɂ͒ʏ�̉^�]�ʒu�ȊO�Ɂu�����v�̈ʒu�ƕ\������������
��{�I�ɃL�n181�n�̑���}���C���ɉ^�]������i�M����u���[�L���̈�����EF71���j���߂̈ʒu����
�L�n181�Ŕ��v���珬�S��Ďq�֓]�������L�n181�̂��̕\�����Ȃǂ́A
�]����œP�����ꂽ���A�����͓h��Ԃ��ꂽ�́H
�ԓ��d�b�Ƃ��A���u�U�[�p�̈����ʂ����Ă������낤���H
�ً}��Ԃ��炢�Ȃ�D�J�ő���邩
����w�ʼn��肠����(189�n)�����Ԃ���Ƃ��A63�Ƃ̘A���ʂ����Ă���
�d�Ԃ���ɓ����o���āA63����������o���Ĕ��Ԃ����B
�������ꂪ�u�����^�]�v���Č����ڂŃn�b�L���킩�����B
181�n�������^�]�ĊJ�����Ƃ͂����AEF71�̕�@�̓s�����t�����A���邢�͉^�]�x���������Ȃ�Ȃ������B
1���Ԓx�ꂮ�炢�̓U���ŁA�����̕ꂪ�H�c�̑c���̑��V�ɍs�����Ƃ����]�T�ł��̂��炢�x�ꂽ���Č����Ă��B
�����ƍ��������͖̂�s�u���g���u�����ڂ́v
�J�∫�V��ȂǂŔJ����EF71����]���ēo��ł����A1~2���ԓ�����O�ɒx��āA�����������邭�Ȃ��Ă�����4�A5�����ɂȂ��Ă��B
�J���͉^�]�\�Ȏԗ��`�������肳��Ă����߂ɒ����킸�A�x���ƃ_�C���̗���Ƃ̐킢�������Ȃ��B
�O�X����o��Ƃ��̂P�W�X�n��S�W�X�n�̉^�]�m�̓u���[�L�ق��O���A�}�X�R���̃L�[�����b�N���A
�^�]�͍Ō����EF�U�R�̋@�֎m���^�]���Ă���������
�L�n�P�W�P�n���͒u�����������͔J�������͂ő��s���Ă������A�̂���
�I�[�o�[�q�[�g���������āA�����������o�ē����Ȃ��Ȃ��ďH�c�ɂ͂R���Ԓx���
�����������Ƃ�������
����Ƃ��s��͏��m�̏�ŗʎY�̐��̃n���R�����������??
>181�n��
�L�n�t����
>>772
�����d���@�֎Ԃ��y���d�Ԃ̕�����ɓ����o���͓̂�����O����ˁH
�J���ł̋��P���炩�A�u�₭���v��u�앗�v�Ȃǂʼn^�p����Ă����L�n181�n�́A
��������y�]���ł̓G���W���ɕ��S�����Ȃ��悤�ɃX�s�[�h�𗎂Ƃ��ĉ^�]�����
�������߁A�ԗ��̏��I�[�o�[�q�[�g�́u���v�����菭�Ȃ������B
�u�₭���v��u���Ȃ́v���ď�ɂȂ�ƁA�擪�Ԍ̏�̂��߂c�c51��c51�Ɍ�������邱�Ƃ���������
Wikipedia�Ƃ��Q�Ƃ���Ƃ킩�邯��
�L�n91���̏Ⴊ��������Ȃlj���������Ȃ���肪���������B
�Ⴆ�A���̉��ド�W�G�[�^�[�͖��炩�Ɏ��s���������ċL�q���Ă���B
������x���x���o�ĂȂ��ƌ����ڂ��Ȃ���
���ƁA�L�n91-8�̂ݗ���������N�[���[�����t���ēo�ꂵ������
���d��45�g�����z���Ă��܂����̂ŁA�y�ʉ��̉ۑ���o���B
���ǃL�n91���̏ᑽ���ɋ�������āA76�N�ɑS�Ԕp�ԂɂȂ����B
�ʎY�Ԍ`���ƂȂ����L�n65�̓L�n181�Ɠ������A���W�G�[�^�[�������z�u�ɂ������߁A���^���N��֏��A���ʏ��ݒu�X�y�[�X���m�ۂł��������ƂȂ����B
�L�n181�n�̔J���̃g���u�����d���������S�̓L�n65�̓��k�ւ̓�����f�O�����B
���É��@�揊���̃L�n180�̕������ɂ́u���}�Ђ��@���R�v�������Ă������
�u�Ђ��v�ɂ��L�n181�n�g�p�\�肪�������悤�����A�u���Ȃ́v�̃L�n181�n�ԗ��̏�ɔY�܂��ꂽ�o������A���É��@��̓L�n181�n���������炵��
�L�n82�ł����R���͊Ԃɍ������̂ɁH
����82�n�́u������ǁv�Ȃ�Ĕ�F����30�p�[�~���z���ɒ��̂ɁH
���āA�d����D51�v�b�V���v���Ń��[�v���o�邱�ƂŗL�����������..
�L�n181�Ȃ�]�T���Ǝv�����ǁB
�t�ɔJ���ɃL�n85�n���������ꂽ��]�T�œo�ꂽ�����B
�e�ԗ�30�g���O���Ōy�ʁA�G���W����700�n�͂Ƌ��͂����B
���M�ʂ��n���݂����ɑ傫�����W�G�[�^�[�����傷���ď����Ɏ��߂�ƍ��x�̓g�C���^���N�̏ꏊ�������Ȃ�
�Ďq�@��ł̃L�n181�n���}�̑g����Ƃ�Ґ��g�݊�����Ƃł́A�c�c51��c�d10���L�n180��L��180�����������萄�i�������肵�Ă�����
�ϑ��i��80Km�߂��܂ň�������v�������B
���̂��ߑ�n�͂ɂ�������炸���z��Ԃ����
�L�n65�͍ō����x��95Km�ɗ}����ЂƂŁA
65Km���x�Œ����i�Ɉڍs����v�ɂ�������
�]���L�n5828�ȂǂƂ̍������ė�[�����\�Ƃ����B
�����A���v���Ԃ��L�n181�n�u�����v�����u�����߁v�̕����Z������
�����߂���㒩8���䔭�ł���̂ɑ��A������11����o���B�_�C���̍�����Ⴄ���Ƃ������ł́H
�V�������R�J�ƑO�̑��ߑO11�����́A�V�����ڑ��Œ����E��B���ʂɌ��������}�A�}�s����������o�Ă������ԑт���B
http://blog.livedoor.jp/railart/archives/cat_133009.html
1971�N�A���}�����A���A����
https://inacafe.exblog.jp/iv/detail/?s=2124989&i=200605%2F11%2F55%2Ff0027355_20225814.jpg
���R�E���ԏ�肾�ƁA�����߂�2����13���A������2����6���B�P�H�ł̒�Ԏ��Ԃ͋���1���B�������A�����߂�21�����㒅�Ȃ̂ɑ��A������17���䒅�B�_�C���̉ߖ��x�̈Ⴂ�ł͂Ȃ����ƁB
���Ȃ݂ɁA���̋�ԁA�d�ԓ��}���C���ԓ��}�����v���Ԃ͂قƂ�Ǎ����Ȃ��B���s�_�C���ő����Ă�낤�B
���}�u����5�E2�v���Ƌ��ʉ^�p����Ă������A�V���E���`�Ďq�`���S�Ԃ�
���C���{���A���m�R���A�R�A�{���A�R�����o�R�Œ������^�p����邱�Ƃ������Ă��A
�Ƃ�����ԗ��̏���N���Ēx�����邱�Ƃ�����A���}�u�����v2�����x�����ĕĎq�ɓ�������ƁA
���̒x�ꂪ�u�܂���4���v�ɂ܂ŋy�Ԃ��Ƃ������������B
�L�n66.67�͒}�L�ŏ�������ǂ��邳�������ȁB
�ԓ����S�~�ŎU�炩���Ă��̂������ăJ�I�X�������B
�������b�ł́A�����Ƃ���z�㓒��Ƃ��A�Վ���Ԃ�z�肵���ʏ�̉^�p�ȊO�̉w�̃R�}�������Ă����Ƃ��H�H
�������181�P�s�̖{���ł���
>>789
4VK�d�g�������̂��傫������
�Ȃ��}�L�̋q�w�ɂ��Ă͂��@��
�S�ʌ����Ō㓡�ԗ������o�ꂵ���L�n181��1�������Œ���܂��͏o�_�s�܂�
���^�]���Ă���ADD51�����̋q�ԗ�Ԃ̍Ō���ɘA������ĕĎq�܂Ŗ߂��Ă������ƁA
�Ďq�@��ɓ���A���炭���u�̂̂��^�p���A���Ă�����
�����̕Ďq�@��\���ɂ͗\���Ԃ̃L�n180�A�L���P�W�O�������A�܂���
�\���̊O��ɂP���A�Ƃ��ɂ͐����ȂǂɃL�n�T�W�ȂǂƘA������ė��u����Ă������A���@��ł͎ԗ��̈ړ��J�n���Ԃ�����J�n���ԂȂǂ�����炵���A
���ԌW�⑀�ԌW�����̎��Ԃ܂ŒN���ԗ��ɋ߂Â����肵�Ă��Ȃ������ȁB
�����ł��Ƃ�����A�Ґ��g�ݑւ���ƂȂǂɔ����āA�L�n�P�W�O�Ȃǂ̑O�ɃL�n�T�W�Ȃǂ��A������邱�Ƃ͂��������B
�[���ȍ~�A�u�����v��u�͂܂����v�Ȃǂ����悵�Ă��āA���ԁA������ƂȂǂ�
�J�n�����Ƃ���܂ŕ��U���u����Ă����L�n�P�W�O��L���P�W�O�Ȃǂ��A
�L�n�T�W��c�c�T�P�ȂǂɘA������Ĉړ��J�n����āA�Ďq�w�z�[�����炻�̍�ƌ��Ă���ƃz�[�����痣����Ȃ��Ȃ����ȁB
���Ȃ̂Ƃ₭�������Ȃ̂ɂȂ�
���������d������A��㔭���́u���Ȃ́v�P���������͂��炭�̊ԁA�L�n�P�W�P�n�ʼn^�]����Ă�����
��㔭���́u���Ȃ́v�P������������Ȃ��āA���É������̂��P���������L�n181�n�ʼn^�]����Ă���
�L�n�P�W�P�n�u���Ȃ́v�͉ď�A�擪�Ԍ̏�Ȃǂ��������āADD51������
���É��ɓ��������肵�Ă����ǁA���É�����A���É��ʼn^�]���ł���ꂽ���A
�܂��͖��É�����͐���Ȑ擪�Ԃ����߂ĘA������āA���Ɍ��������肵�Ă��낤��
�L�n181�n�̃g���u�����ăL�n181����Ȃ��Ē��ԎԂ̃L�n180�ƃL��180�Ŕ������Ă���
�L�n181�n�u�͂܂����v�Ȃǂł́A�L�n180�̃h�A���̌̏�����������v�̔������v��
�������܂ܑ��s���Ă��邱�Ƃ����������A�L�n180��1���s���ł����s�ɖ��Ȃ������̂��낤���B
����Ƃ����̕s���ԗ������G���W���J�b�g����Ă����̂��낤��
�������^�]�͐��їǍD�c�������낤��w
�L�T�V180�͏����ɃG���W����ς�ł��Ȃ���������
���ꂱ����̑O��ʂ�u���v�Ŕ������v�̓_������������o����������H�ڂɂȂ����̂����v��H�c�̒S����
�R�A�̃L�n181�͕Ђ��ۂ̐擪�Ԃ̔��d�G���W����P�����ăg�C���ݒu�Ƌq���g��H�����Ă��悩�����̂�
3���Ґ����ƃg�C�����Ґ�����1���������Ȃ�����
���̏������݂̑O��
>�L�n�P�W�P�n�u���Ȃ́v�͉ď�A�擪�Ԍ̏�Ȃǂ��������āADD51�����Ŗ��É��ɓ��������肵�Ă�����
�̌��ɂ��Ĕ��_��������
����ɂ��ď�������ł���
http://www.asahi-net.or.jp/~se1t-imi/tw_fhi.htm
���a46�N���̓S���t�@���ɃL�n181�n�u���Ȃ́v���ԗ��̏�ő��s�s�\�ƂȂ�A
�c�c51�����ō�������ʉ߂���ʐ^��c51�����Ŗؑ]��S����n��ʐ^���f�ڂ���Ă���
����͐擪�Ԃ̌̏�Ȃ̂��H
���Ȃ���
>�L�n�P�W�P�n�u���Ȃ́v�͉ď�A�擪�Ԍ̏�Ȃǂ���������
�Ə����Ă�킯����
�����̎ʐ^�̉���ɂ́A���É����擪�Ԍ̏�ɂ��c�c51�Ɍ��������
�L�n181�n���Ȃ�2���ȂǂƂ�����
���ꂤp�ł���H
�Ö{���ł��̌Â��u�S���t�@���v�𗧂��ǂ݂��Ă鎞�ɂ��̎ʐ^���āA
���̉���ǂ��������炤p�͖���
�����A�L�n181�n���Ȃ�DD51�����Ō���������A�ԗ��̏�ɂ��DD51������
��������������S����n���Ă���L�n181�n���Ȃ̂̉摜������
�厖�Ȃ̂͐擪�Ԍ̏Ⴉ�ǂ���������
����ᓖ�ĂɂȂ���
���́u���Ȃ́v�������́u���v���l�L�T�V���O����10���Ґ��ɂȂ��Ă�����ˁB
�d�����O�̒E�����̂ŃL�n���Ԃ͏o�������E�����͍ŏI���܂ŐH���ԘA��
��䓞������v�։��ꂽ�ŏI�����̕Ґ��i�t���Ґ�������Ԃ��s��10���Ґ��ŏH�c�����𑖂����j�܂ł����L�T�V����
�L�n180�̑�ԂƂ��āA�L�n91�n�̒��ԎԂ��Ґ��ɑg�ݍ��܂�Ă��鎖�����������A
�L�n91�n�̃V�[�g�̓{�b�N�X�V�[�g���������߁A���̎ԗ��ɏ�Ԃ���q�͂��̎ԗ���
�w��ȂȂ���}������100�~�ł������ꂽ���A���R�ȂƂ��Ďg�p�����Ȃ痿���͂��̂܂܂������̂��낤��
�L�n183�n�ŃI�[�\�h�b�N�X�Ȏ�����C�u���[�L�ɋt�߂肵�Ă�
�c�����}�X�R��������I��������201�n��205�n�́u�����ė͍s�v�����L�n181�n�́u�����ė͍s�v�ł���
�u�����ė͍s�v�̕���������}�a�ʼn^�]�m���|�ꂽ���Ƀ}�X�R����������ăm�b�`�I�t�ɂȂ�̂ň��S�Ȃ͂������u�����ė͍s�v���Ɨ͍s�����ςȂ��ɂȂ��Ċ댯�Ȏ��ԂɂȂ肻��
�H��l�c�������l�c�����Ŕp�Ԃ��o�������H
���̎��̂ł͒E�������L�n181-13�A35�A�L�n180-11�͏C��������g�������ȑ������������A�u���v�̂S�W�T�n�d�ԉ����߂��Ƃ����āA�C������邱�ƂȂ��p�ԂƂȂ����B
75�N9��5���̏���2���̂��Ƃ��ˁB
���̎��ӂ̓����O���[�����H������������
�O���̎c���Ń��[����������߂ɁA�ԗ����E�������B
181�n�C���Ԃ����v���疼�É��ɓ]�����āu�Ђ��v�ɓ��������\�肾�����݂������������A�O�q�u���Ȃ́v�̃g���u���p���ɒ��肽���炩�A������ꂽ�B
���ǁA�����ƕĎq�̑����ƂȂ����B
�u���v��485�n�d�ԉ����}�����܂�A1000�ԑ�̗������Ԃɍ��킸
�b��I�ɐX��́u���Ȃفv�p�ԗ������75�N11��26������^�]�J�n�����B
181�n�C���Ԃ��A���v���疼�É��֓]�����āA�u�Ђ��v�ɓ��������\�肾����
���b��I�ɐX��́u���Ȃفv�p�ԗ������
�X���`�ɂȂ�̂ł��܂A�ꎞ�I�ɐX�Ԃ��������H
���荲���ۓd���p�̖��̎Ԃ��ꎞ�I�ɏH�c�ɓ��ꂽ�̂͒m���Ă��邪�B
�L�n183��CLE�����ȓ_��181�Ɠ��������A�k�C���̋@�֎m�͂����ƃL�n82���^�]���Ă������Ƃ������ă}�X�R���͍��E�ɓ����������Ȃ��̂ɖ߂��ꂽ�B
�N���b�`���L�n181�̓t���V���N���ڑ��^�����A183�͔��}�j���A���ڑ��^�ɂȂ��Ă�B
�f�B�X�N�u���[�L��82�n�ɂ��W���������������A�������Ƀs�b�`���O��b�N���N�����₷���̂ŁA183�n�ł͋����ȃV���[�u���[�L�ɖ߂����B
�앟���悪���S��������?
���A�I�Ԃ���������..
�X��485�n�͂����ȋ�̎ԗ����o���肵�Ă������..
�u�����v�͑僀�R��������Ȃ��u�����v�Ɠ������T���Ԃ�������B
�d�ԉ����}����Ȃ��A�{�i�I�ɐႪ�~��O�ɓd���H�����I��点������A�d�Ԃ𑖂点�悤���Ă��ƂŁA�Ƃ肠�����g�p�\��̂Ȃ��A�����߁E�݂ǂ�p�̓앟����485���g�������Ă��Ƃ���Ȃ������H
485��1000�ԑ�́A���X�A���N��3�������ɍ��킹�Đ������Ă��̂ł́H
�R�A�E�l���ł͍��S����͂����ăL�n80�n�̐��\�ɍ��킹�ă_�C����ݒ肵�Ă�����ȁB
�ȑO�̂��Ȃ̂���݂����ɃL�n181�n�{���̐��\�ʼn^�s����悤�ɂȂ����̂�JR�����O��1986�N11���ȍ~�B
�L�n�P�W�P�n�����ꂽ�����̕Ďq�����s�s�����}�u���������v�Q���́A�L�n�W�O�n����Ɠ����Ďq�V�����A�q�g�V��47�����A���S7�����A���s�P�Q���Q1�������������A
���s�����L�n�W�O�n������A�P�������A
���a�U�O�N�R�������ŗ�Ԕԍ����u���������v�S���ɕύX����Ă���A
�Ďq�V�����A�q�g�V���S�R�����A�q�g���S�S�����A���s�P�Q���P�W�����ƁA
�L�n�P�W�P�n�̐��\�ɂ��X�s�[�h�A�b�v���킸���Ȃ���s���Ă����ȁB
���X�A���J�[���炢�o���Ă�
���k�V�����̖��̂������Đ����ǂ��u�͂�āv�������悤���S�{�Ђ֒���b�Ǝ��Ă���
�����H���ɷ�66/67�g�p�̋}�s�𑖂点������}�̖ʖڊےׂꂾ�����낤�ȁc
�L�n181�n�u���Ȃ́v�̎ԗ��g���u���ɔY�܂��ꂽ���É��@��́A����ȏ�A
�����Â炢�L�n181�n�̐�����C���͂������Ȃ��Ƃ������R�������ȁB
���̂��߁A�u�Ђ��v�ɂ́u�����v�̃L�n181�n���ŗ]��ƂȂ����L�n80�n���]�p���ꂽ��
���̃G�s�\�[�h�L�������
�]�����܂�Ă�����
�L�n65�͋@�ւ�ϑ��@�A��Ԃ̓L�n91�n��L�n181�n�Ƃقړ����Ȃ̂ɕs�v�c�ȋC������B
�f��ꂽ�L�n181�n��Ďq�A�����Ȃǂ֓]�z���悤�Ƃ��Ă��A�ԗ���������Ă���Ȃǂ�
���R�łǂ��̋@���^�]���ł���������ۂ��ꂽ�B
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
95�L���A�u�G�[�f������v�Ɓu�G�[�f���k�ߋE�v�p�͑��z�u�͎�Ԏ���̂܂܁A
���ԎԂ͉^�]�䂪�c����A���ԎԂ̑O�ʂ̓L�n65�̂܂܂ŁA�W�]�ԃL�n65��
���ꂵ���Ƃ��Ȃǂ́A�Ƃ����肻�̒��ԎԂ��擪�ɏo�邱�Ƃ��������B
����Ȃ�ł��Ȃ������B
�ŏ��i46.4�����j�ɒ��삩��������2���͋C���ԁu�����v�̎w��ȗ�[���Ŏd���Ȃ��i�z�u2���g�p1���j�A
���i48.7�����j�ɂ������1���́u�����v�S�ԗ�[���̂��߁i�z�u3���g�p2���j�B
50.3�����ōX��2�����{������炤���A����́u�̂肭��v�̃n���n�Ґ��̗�[���̂��߁B
53.10�Œ���̗]���3�������炤���A����̓L�n57�]����f�����㏞�i�����̒��̐l�̒k�j�B
���̂��߃L�n57�̈ꕔ�͗�[���������Ȃ����C���֍��J�B
���É��̃L�n65�͂����8���ɂȂ������A�������ė]���C���������Ƃ������B
������JR���̍ہA���z�u��4��������������̂͂�����ƈӊO�������B
���ǖv�ɂȂ���1���Œ��~���ꂽ
���L�g�̃L�n181�n���ΐ����E�k���{���o�R�ŕx�R���獂�R�{���ɉz�������܂œ������A
�L�n85�n���}�u�Ђ��v�Ƃ̌���������ꂽ�ȁB
��I�ɂ͂����Ƃ��Ă��A�q�Ƃ��Ă͉���������
>>824
�k�C���̓��ʐ����͐��̈Ӗ����傫����
����L�n82����Ȃ����H
�����������Ă�����T�Ԃɂ͖��p�̕ϑԑ�Ԃ������܂��������낤�ȁc
�L�T�V80-1�����͓n�����Ă��̂܂܉^�p�𑱂������nj�ɃG���W��2��𓋍ڂ��A�q����1���Ԃ��Đ��^���N����u���ăL�V��903�ɉ�������Ă�����
����5�N�قǂŔp�ԂƂȂ����B
181�n��80�n�͒f�ʂ�ԍ����Ⴄ���獬���s���Ǝv����B
�E�u�X�|�[�c�J�[�݂����ȁv
�E�u�R�z�����}�́w�����߁x�ɓ��������E�E�E�v
�E�u�i�����j�`�̂��낤���v
�E�u�ÎR���̃g���l���Ń��W�G�[�^�[���������v
�E�u���͎��ɂ���ĐU�����Ȃ������v
�E�u���D�p�G���W���͊C���s���ɗ�p�Ɂv
�E���Ƃ̓M���R�̒ɂ��������݂����
�������������ŏ����Ă�����ۂ�����������
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�I�[�o�[�q�[�g�N�����ăG���W���J�b�g���F���_���Ŗ����B
���}�C���Ԃ͂��ꂱ��P�`���Ă���
�L�n80�����P�b�g���w�ʂɒ����ĂȂ�
�L�n�W�O�n�̃V�[�g�͔w���肪���p�ɋ߂��p�x�ɐݒ肳��Ă������߁A
�����ԍ��|���Ă���Ƃ�����Ă���
�L�n�P�W�P�n�̃V�[�g�͉��ǂ���ăL�n�W�O�n�̃V�[�g���|���S�n���ǂ��Ȃ�A
�����ԍ��|���Ă��Ă���J�����Ȃ��Ȃ�A�w����̗����ɂ����P�b�g������t�����āA�g���݂����������Ă��ꂽ��
�ڋq�ݔ��ɂ�����s���͎̂d�����Ȃ���
������I�ɂ̓L�n80�Ƃ��L�n181>181�n�d�Ԃ���Ȃ��́H
��������6�C���E���r�C��14���b�g���̏��^�G���W���ɂȂ������A����͂��Ȃ�t�]���Ă���B
������A�y�ʎԑ̂ƁA�������i���̂������ł��ȁc�B
�Ⴆ�b�ł����A��ꃖ�� �Ђ����A���_ �߂����ɂ�����DML30HSE�G���W����
�x�X�g�}�b�`����ŋ߂̒������i���̕ϑ��@���J������A�g�s���s���\�͌��シ��ł��傤�B
�������A12�C��������G���W�����̂��ȃG�l���M�[�̐��i���̎���ɂ͂�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��ˁB
DMH17H�Ƃ�NA�G���W���͕W���������Əo�͒ቺ���N�������^�[�{�G���W���͏o�͂��ቺ���Ȃ�����Ƀ^�[�r���̉�]�����㏸����̂ō����x�����߂���
�����ド�W�G�[�^�[����C�������ƌ������ቺ���ĉď�ɃI�[�o�[�q�[�g������������
�����������ۂ��B
�}�s���d�Ԃ͋�C�o�l�B�C���Ԃ̓R�C���o�l�B�O���[���Ԃ̑�Ԃ�
�R�C���o�l�B�����B
��[�Ɋւ��Ă͌��킸�����ȁB
�}�s�����Ȃ�čŌ�܂ŕ��ʎԂɗ�[�����Ȃ������B
1960�N�����A��[���̓�Փx
���ȒP�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����
�d�ԁ������q�ԁ����������������������������������C����
�ʏ�̉������}�X�R�����u�����ė͍s�v�ł���̂ɑ��L�n181�n�����u�����ė͍s�v�ɂȂ��Ă�̂Ŗ�����^�]�m���O���ɓ|�ꂱ�ނ悤�Ɏ��_������}�X�R���ƃu���[�L������ON�ɂȂ��Ă��܂��댯�����������̂ł́H
���}�Ƃ��̗��胏���n���h���}�X�R���̓t�F�C���Z�[�t�ɗD��ĂđO���ɓ|�ꂱ�ނ悤�Ɏ��_�����玩�R�Ɣ��u���[�L���|����
JR�����{�͑S�ăp�l���ɖ��ߍ���ł�
�L�b�N�_�E���v�b�V���X�C�b�`�͏����Ԃɂ͕t���ĂȂ�����
���̋L�q����������A�T�V�N�V���P���̓��}���������Q���͋��s������A�L�n�W�O�n�Ɏԗ�����������Đ܂�Ԃ����������T�����s�ƂȂ����̂��A
�q�g���������Ə�肠�������̓L�n�W�O�n�A���ߐ��E�{�Ð��o�R���s�̂��������̓L�n�W�O�n�ŏ�蓞����A�܂�Ԃ��ċ��s������A�L�n�P�W�P�n�Ɏԗ���������āA
�܂�Ԃ����������V���Ďq�s�ƂȂ����̂��낤��
�V���P�����炠������2�E5�����V���P�����炠������2�E7���̂P�������L�n�P�W�P�n��
http://www.railstation.net/duke/ressha/ltdexp_asasio.html
>�P�X�W�Q�i���a�T�V�j�N�ɂ͔������̓d���ɂ��P�o���ꂽ�L�n�P�W�P�n�ɑS��Ԃ��u��������ꂽ�B
>���Ȃ݂ɓ��N�V���P������u��������ꂽ�̂͂Q��V���̂P�����݂̂������悤���B
http://cyuouline.la.coocan.jp/newpage47.html
�L�n�W�Q�n�ɂ��u�͂܂����v�Ɓu�܂���3�E2�v���͏��a�T�V�N�U���R�O������Ŏp�������A
�u�͂܂����v�Q�����Ɓu�܂���3�E2�v���͂V���P������L�n�P�W�P�n�ʼn^�]�����悤�ɂȂ����B
�����牽�H
�L�n181�n�̃}�X�R���́A����������211�n�d�ԂƓ��l�Ȃ��̂��Ǝv������A
�����ė͍s�A�����ăm�b�`�I�t�Ƃ������t�z�u�������c�B
���܂��ɁA�}�X�R���ɂ͂˂������Ă��Ȃ��̂ŁA�m�b�`����ꂽ���𗣂��Ă��m�b�`���߂�Ȃ��B
211�n�d�ԁA�L�n110�n�C���Ԃ̃}�X�R���͂˂������Ă���i�S�������قŎ����ɐG��Ċm�F�ς݁j�B
�L�n82�̉^�]��̓L�n�T�W��d�ԂȂǂƓ��l�A�E���u���[�L�n���h���A�����}�X�R����
�ʏ�^�C�v�������B
�L�n�P�W�P�̉^�]����͎����Ԃł����Ƃ`�s�Ԃ̉^�]�ɑ�������
�������^�]���̃L�n�W�Q�n���}�u�͂܂����v�Ȃǂ��L�n�P�W�P�n�ɒu����������Q�����قǑO����A
�R�z�{���║�ߐ��ȂǂŃL�n�P�W�P�n�̏斱���P�����s���Ă����B
���s�S�������قŃV�~�����[�^�ɂ���Ƃ�
�\���Ԃ̃L�n�P�W�O�������A�����ɗ��u����Ă�����A�Ƃ���������߂���
���u���ɃL�n�P�W�P���P���|�c���Ɨ��u����Ă���̂����ꂽ��������B
�ŋ߂̋��s�����^�]���͂Q�S�n�A�P�S�n�A�S�W�T�n�A�T�W�R�n�A�L�n�P�W�P�n�A�L�n�U�T�n�̔z�u�������Ȃ��Ă���A�̂ɔ���C�͖����Ȃ��Ă���B
���o�[���J�������S�ď�f���ɂȂ����̂͌��\���オ�������Ă��炾����ȁB
��_��k�Ђŏォ�畨�������Ă��ďo�������ɂȂ鎖�Ⴊ���������Ƃ��������邪�ǂ��Ȃ�
�����t�@���g���́A�L�n181�n���G���W���S�J�Ŏ���95�L���قǂő���̂ɋ߂�����ȁB
�L�n181�n�Ə��S����u�����v2���ŕĎq��14��08���ɓ�����A���}�u�܂���4���v�ƂȂ�L�n181�n�͕Ďq��30���`1���ԋ߂����x�~���Ă������A
��͂蒷�����^�p�Ƃ����āA�G���W���������x�߂Ȃ��ƃG���W���ɕ��S������������̏�ɂȂ��鋰����������̂��낤�B
�Ďq�w��Ԓ���A���S�@��Ȃǂł��L�n181�n���}�u�����v�̎ԗ��_���A�d�ƌ����͍s���Ă����B
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�ϑ��i�����g��Ȃ������H
���Ƃ����ăL�n82���l���]�p�����獡�x�͓y�]���̋}���z������
�L�n80�n���}��L�n65��g�ݍ��L�n58�n�}�s�́A�I���{����y�]���̌��z��Ԃł́A�������鍑���𑖂�j�q���w���̎��]�Ԃɂ܂Œǂ������ꂽ���Ƃ����邭�炢�������
�m���^�[�{�̃u�[�X�g�������ĔR��������400�n�͂��炢�܂ŗ��Ƃ��Ă���Ȃ����������H
�L�n58�n�A�L�n52�n�A�L�n54�n�Ȃǂ�2�G���W���ԂŁA�Е��̃G���W�������ő��s���邱�ƁB
�d�ԂŌ����Ȃ�A���j�b�g�J�b�g�ɂ��Дx���s�ɊY������B
���R�Ȃ���A���\�͖����x�ɂȂ�A�����I�ɃL�n28�n�Ɠ����ɂȂ�B
�r����DD51�ɂ�������B
12�N�ɂȂ�̂��B
14��181��51���S�ł�B
���V�ؕ��k�ߋE�]�[���łT���Ԗ����a�c�R�̕l������x�����������B�i�����ƍŏI���͕P�H�̕l��܂ŏ�����B�j
���ӁA�l��w�̑ҍ����ʼnw�Q���đ����̂͂܂����Q���ɏ�����B�������͉w�Q�Ƃ��Ă͍ō��̏ꏊ��������B
�Q�Q�����̂͂܂����T���ŕl��ɖ߂��Ă��ĉw�Q�B������T�����R�����A
�r���łP���́A�L���̉w�߂��̈��h�ɔ��܂�p�C��{���̂��킾�����B
�i�L�����̓��͑����ɂP�W�R�n�k�ߋE�ŎR���܂ŏ��A�^���S�G�N�X�v���[���[��
�L���ɖ߂��Ă��āA��������o�X�ŏo�֍s���̂��P�Ⴞ�����B�k�ߋE�]�[���́A
�o�X�ŏo�ɂ��s�����B�j
���q���́u���������v�̑�����Ƃ͂��̊Ԃɍs���Ă����悤�����A�u�����v��
�ċx�݊��Ԓ��Ȃǂ̑��q���ł�3���Ґ��ʼn^�]����邱�Ƃ������A�ċx�ݒ��ł�
�R�������ł̓��}�u�����v�̎��R�ȎԂ�3���Ґ��ł���Ȃ��`���z���ڗ��قǂ�
��ԗ��������B
�A�t�^�[�t�@�C�A�[�Ń^�[�r�����Ă��Ƃ��ُ�
�W�F�b�g�G���W�����悗
�R�₵�ĉĂ�킯�ł͂Ȃ��B�_�f�Ȃ�����R���Ȃ��B�r�C���ł���ƔR���邩�炻��������
�J���̏����z�ő��s�s�\�ƂȂ��ė��������������Ƃ��������B���̎��̔r�C�́A
�O�������Ȃ����炢�̂��̂����������ŁA�H�c��3���Ԉȏ�x��ē����������Ƃ��������B
>>773
�I
�O���b�K�b�K�b�K�b�K�b�E�E�E
�O���I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
�N�I�I�I�I�I�I�I�I�[�[�[�[�[�[���I
���ァ�����������������[�[�[�[��I
�L�n40���ԑ̏d�ʂƃG���W���o�͂̃~�X�}�b�`�ňٗl�ɔR���������
�\�R�Ď����Ȃɂ��������𑁊�����̗p���Ă���悩�����̂�
���S�ł̒����f�B�[�[���̗̍p�͂����Ԏ��オ������1983�N�̃L�n37�����DML30�n���������̂�1986�N�̃L�n183-500�ԑ䂩��
���É��Ɍ����Ă�������Ђ��ɓ]�p�o���Ȃ��������R�A�Ǝl�����}�ɓ]�p�o�����͂��B
���ƍŌ�܂Ŕ��v�Ɏc�����L�n180�27�Ə��S�̃L�n180�8�A28�A29��
�L�n181-100�ԑ�ƃL��180-200�ԑ�]�p�Ȃł����Ă�L�T�V180�ȊO�S��JR�������}���Ă����Ǝv���B
���̕��L�n185�n�̗����������Ă����ȁB
�����A�U�����傫�����邱�ƂȂǂ����ɂȂ����ȁB
���̂��߁A�L�n181�n���L�n185�n�ɒu��������Ɛ��ˑ勴�ʉߎ��̑����A�U����
��⏬�����Ȃ����B
�L�n185�n�͐����R�X�g�팸�̂��߁A�L�n58�n�Ȃǂ̒��Õ��i��20�_���g�p������A
�o�X�p���i���g�p���Đ������ꂽ
�v���������]�����܂��X�J�C�E�H�[�h�\�[�h�̃����N�B
�悭����ƁA�ꎲ�쓮�̋쓮��Ԃ��J���J���Ƌ�������āA
�ΉԂ��U�炵�Ȃ����]���Ă��܂��B
���̗E�҂Ȃ����ɁA���������u���t���Ă˂��̂��H
�W���ō��������u�𓋍ڂ��Ă���B
���܂��ɁA��]���N�����ƁA�ĔS��������悤�ɁA
�����I�ɃG���W���̉�]��������CCS���u��ς�ł��܂��B
��BotW�����N�̋쓮��Ԃ͓쓮�B
�t18�����ՂŋC�y��181�n�ɏ�ꂽ�̂́A�ō����������I
��蔭�Ďq�s�����̓L�n181�n3���Ґ��������ȁB
�V�[�g�ɂ̓��l���̓Z�b�g����Ă��Ȃ��������A���̗�Ԃ͕Ďq������A
���}�u�����v5���ƂȂ��ď��S�܂Œ��ʂ��Ă�����
���������Ȃ̂ɂ͂܂����h���Ƃ�����̂킩���g�ݍ��킹
1���Ԃ̃L�n181�͕ă��i�̏����A2���ԁ`5���Ԃ������R�̎ԗ��ȂǂƂ����Ґ��ɂȂ����肵�Ă����B
�}���J�Ȃ����ɁA�J���J�������̐��H�𑖂�̂��H