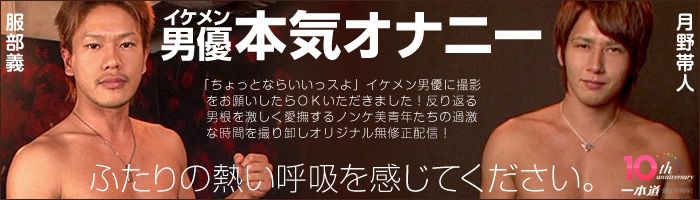�n�C�h�������X���b�h14
����̕s�ł̃n�C�h���B�n���ɕ��G�ȋZ�p�����t�҂ɗv�����Ă���Ȃ̐��X�B
���������ǂ����I
�ߋ��X��
�n�C�h�������X���b�h
http://music4.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1051959029/
�n�C�h�������X���b�h�Q
http://music4.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1109992690/
�n�C�h�������X���b�h�R
http://music8.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1148045313/
�n�C�h�������X���b�h�S
http://mamono.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1192631048/
�n�C�h�������X���b�h�T
http://mamono.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1220256360/
�n�C�h�������X���b�h�U
http://jfk.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1235036812/
�n�C�h�������X���b�h�V
http://jfk.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1249303062/
�n�C�h�������X���b�h�W
http://toki.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1262193269/
�n�C�h�������X���b�h�X
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1288948728/
�n�C�h�������X���b�h10
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1336219256/
�n�C�h�������X���b�h11
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1360661102/
�n�C�h�������X���b�h12
http://yomogi.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1392118450/
�n�C�h�������X���b�h13
http://lavender.2ch.sc/test/read.cgi/classical/1456015977/
��ɂ���ĕ@�ɂ����t�ŁA��ł��C�ɓ����CD�ł�����
�n�C�h�������͑t�҂�I�ԂƁA���炽�߂Ďv����
���ł�
�n�C�h���̋ȂȂ̂͊ԈႢ����܂���
�����Ȋ����ł�
�_�[���[�[���[���[���[�[���i�Ⴂ���A�����j�A���[�������[���[���[�[�i�����������j�A
�_�[���[�[���[���[���[�[���i�Ⴂ���A�����j�A���[�������[���[���[�[���[�i�����������j�A
���[�������[���A���[�������[���A���[�������[���[���[�[�����[�[�i�����������j
�����[�������[���[���[�������[
���[���[�[���[���[���[�������[�����[�i�����̍s�͐��������킩��Ȃ��j
������܂����狳���ĉ�����
�ܖ��������Ƃ����ɐ�Ă���CD�ł��������ɂȂ���
�͂�܂����Ă����
����ɑI���v�z�������t����Ȃ您�܂���
��ɂ���ċC�����������t�ŁA��ł��C�ɓ���̃R�����E�f�C���B�X�ł�����
�n�C�h�������͉��t�҂�I�ԂƁA���炽�߂Ďv����
�R�����E�f�C���B�X�ƃR���Z���g�w�{�[�̃n�C�h���������͂Ȃ���
�ł��邾���V�����^���Œ���������������
�f�C���B�X�Ȃ�ӔN��LSOLive�Ń����[�X���Ă�ɃU�������I�W�A
������LSOLive�́w�z����̃I�[�P�X�g���̗��x �T�C�����E���g��
�w�{�[�ɂ��T�[�R�����Ƙ^������������ɃA�[�m���N�[���Ƙ^������
�U�������Z�b�g�i�e���f�b�N�j������̂Ŋ��o���A�b�v�f�[�g�������ق��������B
�t�@�C�̂悤�ȉ��t��
����Ȃɂ͂Ȃ��B
���A�A�[�m���N�[���Ƃ��Ă͐S�O�ɈႢ�Ȃ�
�ł��A�[�m���N�[��/�E�B�[���t�B���͉̂��̋��ȌÊy�h�̃��_���I�P�̖炵���Ń_��������
�w���҂̗͗ʂ�����킯�����A�����ɂ�
�I�P�̃s���I�h�t�@�̗���x�A���p�́A�w���҂ւ̐M���W�����邾�낤�B
���������̂��Ĉ�x���x���킹����x�ł͓�����Ȃ낤���A
�A�[�m���ƃw�{�[�̎��݂�
��ՓI�ȑ�����ʂ������炵���H�ȗ�Ȃ�܂���
���[���b�p�����ǂƂ̈�A�̘^�������̈�܂łɂ͎����ĂȂ��Ǝv���B
�t�@�C�̏ꍇ�̓o���b�N�̓s���I�h�y��A
�n�C�h���ȍ~�̓��_���y��ł���Ă��邪
���N��������N�������c�B�X�����W�J�G�e���i��
�o���b�N������܂ł̌Êy�̓s���I�h�y��Ƒt�@�Ř^�����Ă邪
�ÓT�h��}���h�ȍ~�̓��_���y��ł���Ă��ł���H
�u���_���I�P�̌Êy�h�̉��t�v��u���_���I�P�̌Êy�h�̖炵���v���B
�܂����̂������u�Êy�h�v�Ƃ����̂����������킩���w
1.�Êy����g���Ă��Ă����߂�t�@�ɂ���قǍl�����ĂȂ���B
�Q�D���_���y��g�p�ł������̎d�����}�i�[�Ȃǂ𗝉����Ă���ҁB
�傫���Ⴄ�B��������ʂ��̂ł��˂�B
���݂ɃA�[�m���N�[���ƃt�@�C�͑S�R�^�C�v�Ⴄ�悤�ɒ������邪
��ʂ���Ȃ��҂ɑ�����B
���߂�t�@�ɍl�����Ă鉉�t�Ƃ́A�ǂ��������t��������ł����H
�����̎d�����}�i�[�Ƃ́H
���̎���͂��Ȃ苻�������邩�琥���Ăق�����B
�܂������l���Ńm���r�u���[�g�ȂȂ�O.K�Ƃ�����Ȃ����낤�Ȃ�
�r�u���[�g�����Ɖ��t��������������ꍇ������B
������_���y��ł��悤�ȉ��̂̂��Ԃ��̂悤�ȉ��i�ȃr�u���[�g��NG�����ǂˁB
�i���̂̂��Ԃ��͉��i�ł͂���܂��j
������Ȃ��s���I�h�y�킩���_���y�킩�ł���ȋɒ[�Șb�����Ă��܂��̂��ƁB
�Ђƌ��Ɍ����A�S�[�M�N�B
���_���v�l�͊y���ɋL����Ă�ȏ�̎��͂��Ȃ��A�ł��Ȃ��B
�y�������ׂĂ����炾�B
�Êy����g�p���Ă��Ă����������ׂă}���J�[�g�ŏ������Ă鉉�t������B
�y���ɂ͍Œ���̏��������Ă��Ȃ��Ɠǂݎ��̂��s���I�h��
���g���b�N���d�v������B
�w�����Ȃ��Ă����������������ł̓e���|�𗎂Ƃ�
�Ȃǂ������̎d�����}�i�[�̂����ł��邩�ƁB
�h�����[�W���̊��Ɋ��҂��Ă�����
���t�͇@�^�C�v�ŌJ��Ԃ����ȗ����Ă�悤��
�������肱�̏�Ȃ��B
> �w�����Ȃ��Ă����������������ł̓e���|�𗎂Ƃ�
�����ł͂Ȃ��āA���������Ȃ������ł̓e���|�𗎂Ƃ��A���Ǝv���Ă�
16����������̕����͑��߂ɁA4����������Ȃ�������߂Ƃ�
995 �������̓J�̗x�� 2018/10/24(��) 20:06:19.82 ID:SxXPTYer
������50�Ԃ���81�Ԃ܂ł̘^���ł����̂͂���H
�Êy��͔�����
996 �������̓J�̗x�� sage 2018/10/25(��) 21:11:06.85 ID:NKrBRsPP
>>995
�A�_���E�t�B�b�V���[
����C�܂܂̎v�����Ƃ������
�������������Ƃ��l�A���߂̂����Ȃ�ˁB�����猙�Ȃ낤���ǁB
�������̂킹���
�������ɂȂ郂�c�ƃn�C�h���̈Ⴂ��
�����Ƃ��̑����͔����ĂȂ��Ǝv���B
>>30
�����������B��肢�B
���x�𗎂Ƃ��l����������A�����
��������ɁA�A�A�B
����Ȃ͎̂w���҂≉�t�҂ɂ���ĈႤ����B
�Êy�퉉�t�݂͂ȓ����Ȃ킯�Ȃ������
�ǂ�������ƕ��������˂��ˁH
�h���e�B�������g�D���x�g�ł͂��Ȃ�A�O���b�V�u�ɍU�߂�̂ɑ���
�n�C�h�����Ƌɒ[�ɂʂ�ܓ��݂����ȉ��t�����Ă�B
���������̂��ĒP�ɂU�O�[�V�O�N��ɂ�����ÓT�h�̉��߂��Ă�����
����ȏ���ȉ������݂��Ȃ������B
LPO�̌���BPO��VPO�ƈ���đS�R�����������Ȃ��̂��t�ɗǂ�
���ƂȂ��Ă͂�͂�nj��ł̃o�����X��
���y�풆�S�̃��}���h�T�E���h
�Ȃ�ˁB���߂ė����ł���c
�ƌ����Ă����܂藝�����Ă��炦�����Ƃ͂Ȃ�
�ςɊNJy��⋭��炳���Ă��w���҂�������
�������܂Ƃ܂��Ă邹�����낤���B
�n�C�h���̌����Ȃ́A106�ȑS�������삾�ȁB
���j�I�ɂ͕]���Ⴉ������ˁB
�ŋߍĕ]�������悤�ɂȂ����킯�ŁB
�N���A�ڂ����l���Ȃ��H�����Ă��������B
���l���ł��邱�Ƃƃr�u���[�g�i�t�@�j�͂��ꂼ��s���I�h�̂����v���ł�����
��ɃZ�b�g�ŃN���A����Ă�Ƃ�����Ȃ��B
���Ƃ��Ύ��ۂɃG�X�e���n�[�U�o���h�̌��̐l���i�R�C�R�C�P�C�P�C�P�j��
�^�����Ă���̂̓\�������X�Ձi�W�O�N��j�ƃz�O�E�b�h�Ձi�X�O�N��j�̂�
���Ǝv���B
�h�����[�W����U�������̃I�P���Ƌt�ɐl�������Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ�B
�ǂ����ɂ��낻��炵�������Ă���Ηǂ�������x����������ˁB
�ĕ]������Ă�́H
�X�J�����b�e�B�A�����[�A�N�[�v����
�Ȃǂ��Ƃ��`�F���o���p�̃o�b�n�ȊO�̉��y��
�s�A�j�X�g���炠�܂藝������ĂȂ��̂ł�
�^���[�Ƃ��q���[�C�b�g�A�n�C�h�����ƃA���h���E�A���������
�^�����ڐV�������ǁB
�I�y�͂̃e���|�v���X�g���t�@�C�̔{���炢�̑��̂���( �E�́E)=b �ޯ�ޮ��
�W���P���D�݂Ȃ̂�( �E�́E)=b �ޯ�ޮ��
�ڂ����l�ł͂Ȃ����ǁA�n�C�h���͂����������Պy�킪���ӂȐl�ł͂Ȃ�����
�n�C�h���ƌ����R���T�[�g�}�X�^�[�i��1���@�C�I�����̎�ȁj
�X�J�����b�e�B�͂�����Ɛl�C�����
�`�b�R���[�j�ȊO��
���q�e���Ȃ̓n�C�h���̃\�i�^�������]�����Ă��B
�O�[���h�͕]���͂ǂ����������m��ǎ��ʒ��O�̘^���̒��ł̓n�C�h���̌��6�ȃ\�i�^���`���C�X���Ă�B
��������̃\�i�^�͂ǂ̋Ȃ��D�����ȁB
����I�Ɋ��S�Ƀs�A�m�̂��߂ɏ�����Ă邵�A�Ƃ���ǂ���x�[�g�[���F���̎���Ɍq���鋿��������B
�u�u�����f���Ǝ��͑����̃n�C�h����i��^�����Ă��܂����A�n�C�h���̖��͂𐢂̒��ɍL�߂�Ƃ����Ӗ��ł́A���܂�v�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B
�@�n�C�h�����̑�ȍ�ȉƂł��邱�Ƃ͒N�����F�߂Ă��܂����A�ނ̕��O�ꂽ�n���́A�L���ȃC�}�W�l�[�V�����A���[���A�̃Z���X��^�ɗ������Ă���l�͑�������܂���B
���Ƃ��Δނ̍Ō�̃\�i�^(Hob.XVI:52)�ł����A�σz�����̋ȂȂ̂ɁA��2�y�͂̓z�����ŏ�����A���ԕ��̓z�Z���ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ�Ƒ�_�Ŋ�Ȕ��z�ł��傤�I
�@�ނ̓p�p�E�n�C�h���ƌĂ�A�����ȘV�l�Ƃ����C���[�W�Ō���邱�Ƃ������ł����A�ނ̍�ȏ��@�͂��̃C���[�W�Ƃ͂܂������Ⴂ�܂��B
�ނ̊y���ɂ͂܂��������ʂ��Ȃ��A�ł����Ȃ������Ŏ��ɑ����̂��Ƃ�����Ă��܂��B
�f�G�ȃs�A�m�O�d�t�ȂȂǁA�ނ̍�i��e�����тɁA���͂��̏���Ȃ��K���ȋC�����ɂȂ�A�ނ��������̐��ōł��̑�ȍ�ȉƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�v
�u�Ō�̃\�i�^(Hob.XVI:52)�ł����A�σz�����ƃz�����̊Ԃ̋������O���������Ă��Ȃ���A�n�C�h���̃��j�[�N�Ȕ��z�A�����ԈႦ���Ǝv�킹�郆�[���A�ɋC�Â����Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B
�����悤�ɁA��3�y�̖͂`����G���̘A���́u��k�v�c�c�A���������������ł́A��2�y�͂̌������̃z�Z���̑����̂悤�ł����A�����E������āA�x����Ă������ƂɋC�Â��A���̌�ŕσz�����ɖ߂�܂��B
�@�������A�n�C�h���͂������[���A�ɂ��ӂ�Ă��������ł͂���܂���B���̍�i�́A�����ȃ��e�B�[�t�ő傫�ȍ\������g�ݗ��Ă�悤�ȋZ�@���g���Ă��܂��B
��2�y�͂̎��̃����f�B�[�͑�1�y�͂̓W�J�����琶�܂�A��i�S�̂��z���A�n�C�h���̌��o�����˔\�����������܂��B���ꂪ�x�[�g�[���F���ɑ傫�ȉe����^�������Ƃ͊ԈႢ����܂���B�v
>�u�����f���Ǝ��͑����̃n�C�h����i��^�����Ă��܂����A
>�n�C�h���̖��͂𐢂̒��ɍL�߂�Ƃ����Ӗ��ł́A
>���܂�v�����Ă���Ƃ͌����Ȃ��ł��傤
����͌����ł��傤
�Ă��A�u�����f���̊����Y�����̂̂悤�Ȃ�
�V�t��u�����f���͗]�v
�悩�����̂����I
���݂Ɍ����Ȃł̓A�[�m���N�[���̏��o�R���ADG�I���t�F�E�X�����ǂ̐����A
������DG�J�������̃p�������Ȃ�LP�o���Ə��oCD��
�ٍʂ���|�p�I�ȃJ�o�[�t�H�g������ł��B
�\�[�X�̓n�C�h���̃s�A�m�\�i�^�W�̃��C�i�[�m�[�g
�o�b�n�̋Ȃ͌��X�`�F���o����N���r�R�[�h�����ɏ�����Ăăo�b�n�{�l�����߂̒e�������Ă��炵�����獇���Ă낤���ǁB
�n�C�h���̃s�A�m�\�i�^�͌���̂̓s�A�m�����ɏ�����Ă邵�ȁ[
���y�l�d�t�Ȃł́A�����X���[�Y�ɂ͒����Ȃ��������낤�B
���y�l�d�t�́A�����I�ɁA�ǂ����O����C������B
�z�[�{�[�P���ԍ���83�܂ł����ǃz�t�V���e�b�^�[�̃Z���i�[�f���\�ɋU�삠�邵�\���ˏ�̃L���X�g�̍Ō�̎��̌��t�̌��y�l�d�t�łʼn��̂���y�͂��ԍ��t���Ă邵���ʂɐ��������Ȃ��Ă���
Op.�X���犨�肷��Ⴂ���̂ł��B
�ŋ߂̘^���͂ǂ���Op.�X����n�߂Ă���܂��B
��Ȏ����ɂ���ăI�P���g�������Ă�킯�ł��Ȃ���ѐ��̊Â��S�W�ɂȂ肻���ȗ\�����c
����ɂ��̌�A���g�j�[�j�̒�Ăɂ��x�[�g�[���F���̘^���ō�ȓ����̊y����g���n�߁A���݂ł͑S�t�҂����_���y��ƃs���I�h�y����g�������鐢�E�I�ɂ��������I�[�P�X�g���ƂȂ����B
�����Ŋm�F���ĂȂ����ǁA�n�C�h���̉��t�͂����炭�S���s���I�h�y����g���Ċ��S�Ƀs���I�h�y��I�[�P�X�g���ɂȂ��Ă�̂ł͂Ȃ����낤���B
���Ȃ݂Ƀz�O�E�b�h�̓}���e�B�k�[�̌��Ђł�����A�}���e�B�k�[��X�g�����B���X�L�[�����o�[�[�������nj��y�c�Ƙ^�����Ă��ˁB
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41ZG6297QXL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41RZ339NRBL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51U4iCOtxwL.jpg
���{�ł��S�ȉ��t
����悭�ΑS��CD�����˂���Ă�y�c������
���ɂ̎�q�����Ƃ�������
����ސ搶�͎蕺�ƑS�Ȃ�����͂�������
���ꂱ���^���c���Ƃ��ė~��������
����悭�ΑS�W�ȂǂƂ͈Ⴄ�Q�O�R�Q�̐��a�R�O�O�N�������A����
����������Ƃ��������̑�^�v���W�F�N�g�ł����B
�N���V�b�N���[�x���̒P�Ɗ��łȂ�
�X�C�X�̃��[�[�t�E�n�C�h�����c���o�b�N�A�b�v���Ă��邱�Ƃ�
����܂ł̑S�W���Ƃ͈�����C���̓��������̂�
�܂蔄��グ�ɂ��r���œ����o�����Ƃ͂��܂���Ɩ���悤�Ȍ`�B
�o�[�[���ǂ͏����P�X�Ԃł͌��̐l���������Ă���Ă�ˁB
�C��JAL��4-4-2-2-1�̒ʏ�ɑ���
�����Ȃł�5-4-3-2-1�ł���Ă�悤�ł��B
��̃J�L�R�ŊԈႦ�Ă܂���
�\�������X�{�l�����[�_�[�Œe���Ȃ���w���Ȃ̂�
4-3-...
�z�O�E�b�h�Ղ�4-4-...�ł������������l�т��܂�
CD�̃u�b�N���{���ł��܂��̂�
�Q�l�ɂ��ĂˁB�g�p�y����Ȃǂ��L�ڂ���Ƃ�܂�
25�N�Ԃ蕜���I
(߄D߁�߄D�)?
https://www.suruga-ya.jp/database/pics/game/129000764.jpg
���b�t���̃����h���Z�b�g�͒x���d�������Ă���B
�w���r�b�q�͒��x�����B
���[�c�@���g�̌����ȑS�W�̕���
�O���邹���Œ����ɂ����B
�Ȃ����j�I�ɂ����[�c�@���g�̕���
����I�Ɉ�����Ă����̂��A
�悭�킩��Ȃ��B
���O���A�����ɂ��V�ˍ�ȉƊ��o�Ă邵
�n�C�h���ł��Ⴆ�p���Z�b�g�����1�N�������Ă�����O���邺��B
���S�ȑS�W�̓i�N�\�X�܂߂Ďl��ވʂ��Ǝv������
��ԌÂ��̂ɁA����ϖ����ō��ŃI�[�\�h�b�N�X�ȑS�W���Ǝv��
NAXOS�̃~�����[=�u�����[���Ȃ̃��^���^�����X���[�e���|�Ƃ͈Ⴄ
�S�W����Ȃ��čŌ�̐��Ȃ��������ĕ]�����߂��Ă��܂��Ă�
�n�C�h���̓U�������Z�b�g���̃j�b�N�l�[���t��(�����A��ՁA�R���A���v�A���ۘA�ŁA�����h��)�U��
���[�c�@���g�̓n�t�i�[����W���s�^�[�܂ł̂U��
�`���C�R�ƃh���H�͂��ꂼ��Ō�̂R��
�z�[�{�[�P���ԍ���胉���h���ł̔ԍ��̕���
��ȏ��ɒ����݂���������A
�������ɕ��בւ��Ē����Ă݂悤���ȁB
�F����͂ǂ����Œ����Ă܂��H
�����́A�����Ȃ̓f�C���B�X�Ղ̏�����
���בւ��Ē����Ă�B
�e���|���I�[�\�h�b�N�X����
>>82
���c��`���C�R�͂���ł��イ�Ԃ�Ȃ��
�������n�C�h���͏����A�����A�����
���ꂼ�������ʔ��݂�����B
�h���C�u�̎��Ɍ����Ȃ̏I�y�͂���(���ɑ��߂̋�)���V���b�t���Đ�
��ՁA99�ԁA���ۘA�ł̏I�y�͂͏G��Ǝv���B
���ɑ��ۘA�ł̏I�y�͂̓t�B�i�[���������đf���炵���B
60�ˉ߂����炢�̎��̍�Ȃ̂�
���c�͂��͂�k�G�b�g����Ȃ��X�P���c�H�Ƃ��̎��㊴�₳�����B
����38�Ԃ̏I�y�͂���D����
���̓��[�c�@���g��20�ԑ�̌����Ȃ�`���C�R�t�X�L�[�̓~�̓��̌��z�A�����V�A�A�|�[�����h����D�������ǂȂ�
�n�C�h���̏ꍇ�A���f�ޗ����U�������Z�b�g��������
�U�������łP�_�[�X�����邵�A�K������������Ȑl����
�Ïk�E���f���ꂽ������̂��Ă킯�ł��Ȃ�����ˁB
�n�C�h���͍�ȑΏۂ̏�⒮�O�A�I�P�̋K�͂ɍ��킹�Ă�
��Ȃ䂦�c
100�Ȉȏ�̑S�W�̓n�[�h���������猋�ǃU�������Z�b�g���������Ĕ��f���ꂿ�Ⴄ
�A���ՂɂȂ��Ȃ����L���ɂ��������N���V�b�N���S�҂̍��̎����ɂ͖��m�̋Ȃ�����
���N�O�Ƀh�C�c�E�O�����t�H���̃U�E�x�X�g1200�Ńo�����{�C���w���C�M���Xco�́u�߂��݁v�u���ʁv�u�}���A�E�e���W�A�v�̂P�����o�Ă�̂��������炢
https://content-jp.umgi.net/products/uc/uccg-5216_WoP_extralarge.jpg
����Ȋ����̃J�b�v�����O�łȂ������H
�z�[�{�\�P���ԍ����̑S�W��������
��ȔN����킩��ɂ����A���̒�����
�����Ńh���C�u�p�ɃZ���N�g����̂����������ˁB
�z�O�E�b�hAAM�Ղ͂��ꂾ���ł��L�Ӌ`�ȑS�W�ł����B
���Ƃ������킯����
���ꂾ�ƃ����c�B���i���j���͏�Ɂu�����Ӂv�����
���ꂪ���܂ЂƂs���Ƃ��Ȃ������B
���Ԃ�S�Ԃ̂ق����X�b�L�����ĂčD�܂����B
���_���̏��Ґ����ƃI���t�F�E�X�����ǂ̉��t���\�D����������
�J�b�v�����O�����ƂƓ������Ⴄ���͕ʂɂ���
>>93��DG��SONY��DECCA��Warner��Philips��EMI���̍����̗������Պ��Ƀ}���A�e���W�A��CD���I�o����Ă�̂��܂茩�Ȃ��Ȃ��Ęb�������������̂�
http://pbs.twimg.com/media/CDHH0-3VEAA6SRv.jpg
https://img.hmv.co.jp/news/image/12/1226/title-0078.jpg
https://tower.jp/article/feature_item/2016/03/10/~/media/387941004D1D48DE91FD31FBDB1C1D8D.jpg
https://tower.jp/images/40/58840.jpg
http://file.blog-kichijyouji-classic.diskunion.net/Img/1473144661/index.jpg
�����ɍڂ��Ă��Ȏ����̕��ނ����Ȃ��班���I��ł݂�
https://www.kanzaki.com/music/mw/sym/haydn
�����ȗl���ւ̖͍��F1757�`65
�V���g�����E�E���g�E�h�����N�F1766�`73
���O�ւ̌}���Ǝ����F1774�`84
�ÓT�I�����F1785�`89
�~�n�F1791�`95
��1�ԁA��3�ԁA��22�ԁu�N�w�ҁv
��44�ԁu�߂��݁v�A��45�ԁu���ʁv�A��48�ԁu�}���A�E�e���W�A�v�A��49�ԁu���v
��53�ԁu�鍑�v�A��60�ԁu�I舎ҁv�A��73�ԁu��v
��82�ԁu�F�v�A��88�ԁu�u���v
��94�ԁu�����v�A��104�ԁu�����h���v
����Ńx�[�g�[���F�������ȑS�W�Ɠ������炢�̖����Ŏ��܂邨��y�ȃn�C�h�������Ȑ�W�ɂȂ邩
��3�Ԃ͌l�I�ȍD�ݑS�J�őI�̂ň�ʌ����ɂ͑�6�ԁu���v�̕����ǂ�����
�s���I�h�y��g�p�̃A���g�j�[�j���ǂ��B
�m�����g�����s���I�h�y��g�p�Ř^�����Ă����͍D�����������A���_���y��g�p����悤�ɂȂ��Ă�����ɂȂ����B
�����X�b�L�������Ă����ċ��ǂ�e�B���p�j�����N�Z�̂���s���I�h�y��g�p�����肷��̂̓o�����X�����Ȃ��čX�ɍ����B
���Ɗǂ̗Z�����s���I�h�t�@�ŗǂ������ɍ�����낤����
�e�y��̌����o�Ă郂�_���y��ł�����Ⴄ�Ƌp���ĕ��������Ⴄ����������
�Ȃ��Ȃ��ǂ�����
���̎w���҂͑��t�B���Ō����ȑ�39�Ԃ�U�������Ƃ�����
���_���y��ƃs���I�h�y��ł�
��͂艹�F�E���ʂ�����ʂ��̂Ȃ�
�Ƃ������ƂŊJ�������Ē������Ƃɂ�����
�m�����g���̃p�������ȁi�U�������Z�b�g�͊����̂悤�Ŗ����j��
�t�@�C�Ղ��ꂼ��ɊѓO�������߂���������ɂȂ�
�h�ӂ�\����܂łɂȂ����B
�n�C�h�����g�̋L�q�i�ቹ���̐l���ɂ��Č��y�j���l������܂ł��Ȃ�
�e�p�[�g���n�b�L���ƕ������Ē����Ƃ�邱�Ƃ�
�n�C�h�������Ȃł̓v���X�ł���Ƃ����ėǂ����ƁB
�������X�e���I���ʂō�Ȃ��ꂽ���̂͗����z�u�ŁB
�����ۂ����҂����Ă����A���g�j�[�j�Ղ���
���̍�ȉƂɂ܂Řg���L�������̂�
���̃R���T�[�g�A����CD�Ƃ��ĂȂ璮�������������邩������Ȃ���
�n�C�h���������W�����Ē��������҂ɂƂ��Ă�
������Ɣ����ɂȂ��Ă�C���c
���܂̓f�[�^�ŕ����l�̕����������A���l������f���Ă���Ƃ͌�����B
�������_���I�P�̎w���҂ɂȂ��ăs���I�h�I�P�ɖ߂����悤�ɂ������邯��
�n���ɑ����Ă����낤�ˁB
�z�O�E�b�h��AAM���ތ���R���T�[�g���ɂ͊��
�o���Ă����悤�����B
�m�����g���ƃQ�[�x���͋������s���I�P�����S�ɉ��U���Ă܂������
�Ƃ肠������肽�����Ƃ͂�������Ď��ȂȁB
�����ăs���I�h�̃I�P��U��Ȃ��ϋɓI�ȗ��R�͕�����Ȃ����ǁB
�s���I�h�y��I�[�P�X�g���ł��Ȃ�A�傫�ȃz�[���ł͂ł��Ȃ����炻�ꂾ���ł��W�q�͌�����B
�N���V�b�N�̏��ƃ��f���́A�傫�ȃz�[���ő����̒��O���W�߂�Ƃ����R���Z�v�g�łł��Ă��邩��A
������}���h���y������ɓK���Ă���̂͊m�����B
�Ȃ������Ă��N���V�b�N���y���̂́A��I�[�P�X�g���Œ�Ԃ̋Ȃ��Đ����I���������l���������S������ˁB
�^�������邭�炢������
�ے�I�ɂȂ����Ƃ������Ƃł͂Ȃ�
���낤��
OAE�̂悤�ȏ�C��u����
�O����w���҂��Ăԃ^�C�v��
�s���I�P�͋ɂ߂ċH����
���ɂ̓J�y�R�����炢���ȁH
��������E�e��(N��)�������h����
�I������Ƃ�����\����������w
�A���g�j�[�j�̓o�[�[�������ǂƂ̃x�[�g�[���F���ł́A�i�`�������E�g�����y�b�g�A�i�`�������E�z�����A�P�g���E�h�������̗p���āA���y��ɂ̓K�b�g�����g�p�A�؊NJy��̓��_���y����g�p���Ă�
���̐�A��K�͊nj��y�Ȃ����p����O���Ă���ł��낤
�����ǂł����
�Êy��������ꂽ�������p���k���_�Ŗڗ����낤�ˁB
�n�C�h���܂łȂ�3-3-1-1-1��
�ǑŊy��͐_�c�y�킩��A����ex�g�����Ăׂ����B
���݂Ɍ�����̂ӂƂ��郍���h���E�V���t�H�j�G�b�^��
��{�����o�[�͊e�y��P�l�������Ǝv���B
�p���Ɠ��{�ł͎���Ⴄ��Ǝv����������Ȃ����A
�Ԃ����Ⴏ���y�l�d�t�Ƀt���[�g�ƃs�A�m�𑫂���
�n�C�h���̌����ȂȂ牉�t�ł���B
�T���̃u�b�N�ɍڂ��Ă�W���ʐ^���܂��ɂ��̎��̎ʐ^�̂悤��
����H�Ǝv��������
�g�p�y��̓O�����U�[�̃R�s�[��
A.�x���i���f�B�[��ɂ��P�W���I�y��̃R�s�[��
�g���Ă�Ə����Ă���B
�A���f�B�A�E�o���b�N������
�T���}���e�B�[�j�i��j�̌����ȂȂǂ�naxos�ɘ^�����Ă�
�n�C�h���������������ł��肢�����������B
naxos���ČÓT�h�̓��_���y��ł����j���ł�
�{�w�~�A�̗r�����̃~�T �g����
�����~�T�� �n����
�A���f�B�A�E�A���T���u��
�E�[���F�E�O���b�g(�w��)
http://ml.naxos.jp/album/8.555080
naxos�̃��@���n���� �j�R���E�X��G�X�e���n�[�W��V���t�H�j�A / �E�[���F�E�O���b�g (�w��) �̂������
�Ƃ������Anaxos�̃}���� /�@�g�����g�����ǂ͂����V������3�W�ȍ~
�m�����
���g�L���\��/�V�e�B�E�I�u�E�����h���E �V���t�H�j�A�������Ă邵
�g�����g�`�ƃA���f�B�A�`�̘b�����Ă��Ȃ������̂�
����ȕ�����Y�����t����Ă��Ȃ������Ȃ�āA
�܂��܂�������Ă閼�Ȃ�����̂����ȁB
���炢�������B
���}���e�B�b�N�����낤�ȁB
���Ƃ͕����ĂȂ��C��������B
���}���h����Ȃ�����ȁB
���c�̏D�������т�����������
�����炭�؋��ꂩ��N���������̂��낤����
�������}���h�̐��_�a�I�Ȃ��̂̐�삯�Ƃ����Ă悢����
�n�C�h���͂��̐l�ƂȂ�����y�����Q���N�����N���̂��́B
���_�ł͂Ȃ��B
���[�c�@���g��x�[�g�[���F���Ƃ͐����ɋ߂�����
�����������̂Ő��̑��ɓ����ꂽ�Ƃ�����
���c�̂悤�ɕ��e�����t�Ƃō�ȉƂł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�
�傫�ȍ����ˁB
��̃~�q���G�����˔\���������B
���݂ł͌Z��[�c�@���g�̉A�ɉB��Ă�̂������������ǁB
> 1749�N�A�ϐ��̂��ߐ��̑��ō��������̂��̂��s�\�ɂȂ���ق���A
> ���̌�F�l�̉ƂɏZ�ݒ����悤�ɂȂ�A�t���[�̉��y�ƂƂ��Ă̊������n�߂��B
> ���̐�����10�N�ԂقǑ����A���̊Ԃɕ��L���d���ɏ]�����Ă���B
�u���L���d���ɏ]���v�Ƃ����ƕ������͂������ǁA�����ׂ̈ɉ��y�Ɩ��W�̃t���[�^�[�I�Ȏd�������Ă���Ă��Ƃ����
�䂸���������ꂽ�����ŐH�ו��S�̂䂸�����ɂ��Ă��܂��Ă���������������
�����o�����Ƃ��A���ۂ��Ēǂ��o���ꂽ
�������悤����
���y�ƂɂȂ낤�ƁA���Q�����R��
��Ȃ�Ɗw�������B
��ׂ悤���Ȃ��ȁB
�������A���y�I�����[�̍�ȉƂ́A
�����ɂ͉��y�ƂƂ͌���Ȃ��B
�o���b�N�`�ÓT�h�̍��̗̉w�ȁE�̎���Ă悤�m���
��\�I��ȉƒB�́A�{�l�͂ǂ̊y�킪���ӂ���������������ꂼ��̓��ӕ��삪�킩���Ėʔ����ˁB
���B���@���f�B�����@�C�I����
�e���}�������R�[�_�[
�o�b�n�����ՑS�ʂƃ��@�C�I����
���[�c�@���g���N�����B�A�ƃ��@�C�I����
�x�[�g�[���F�����t�H���e�s�A�m
�ȑO�̓��[�c�@���g�̘^���ɕ���Č��Պy�������̂��嗬��������
�G�X�e���n�[�W��j�R���E�X�̃I�P�ɂ͏�݂̌��Պy��t�҂����Ȃ��������Ƃ���
���݂ł́A���̎���̌����Ȃɂ͌��Պy��������Ȃ��̂��嗬�ɂȂ��Ă���
���ǂ͐��܂�炿�Ōb�܂ꂽ��ȉƂ��D���Ȃ�
���������X�e���I�^�����H
�C�s����ɓV�䗠���Ԏ肷��قǂ̍�ȉƂȂ��
���ɂ���̂��H
�{��y���ɂȂ����Ƃ����̂�����
���Ȃ�v�̂�������������ɈႢ�Ȃ�
�n�C�h���@�����ȑS�W�@�G�����X�g�E�����c�F���h���t�@�[���E�B�[�������nj��y�c�i33CD�j
https://www.hmv.co.jp/product/detail/9374167
60�N��̃X�e���I��������
����͑S���m��Ȃ��������A�q���̍������c�F���h���t�@�[��N���ɋq�������̂������Ƃ�����
�g�����y�b�g�̃��B�Y�b�e�B�Ƌ����ŃW���Y���ۂ��Ȃ��U���Ă����A�ǂ�Ȏw�����������͊o���ĂȂ�
�����c�F���h���t�@�[2009�N�܂Ő����Ăăn�C�h���̑S�W�^���̈������ǂ��v���Ă���
�S�[�o�[�}���̑I�W�ɂ��Ă���������
��قǔ����ƌ��Ȃ���Ȃ����
LP��CD���Ȃ�ă��W���[���[�x���ł�
�����ɂȂ���ĂȂ���킯����Ȃ���Ȏ��ہB
���̃y�[�W�A���ʂ��n���p�Ȃ�
�ǂ��Ȃ��Ă�̂�
�Ȃŋ߂����������ߏ�ȃy�[�W��������
��肪�ǂ������������A�����A���Ǝ҂�����Ă�낤
���܂ŃX�N���[��������A���ނ̃����N�����������邩�猩�Ă݂�Ƃ�����
�N�����l�b�g�Ţ�q���C�b�q���C�b�q���C�b����ē���́B
�Ȃ�̂��ƂȂ̂�
�q�[�����O�̂��Ƃ��Ƃ��v�������A�N�����l�b�g�̉ӏ��Ƃ͍���Ȃ��C�����邵
����ƋC�ɂȂ�S�W���˂�
�ӊO�ƃn�C�h���̕������ϓI�ɗǂ���ȁB
����͉��C�ɂ��������Ƃ��Ǝv���̂����B
���[�c�@���g�̓s�A�m�\�i�^�������Ă��Ȃ�
�����������Ȃ��Ȃ�����
https://www.youtube.com/watch?v=CbQkyOlYCmM
��1��
https://youtu.be/7L8S1SYEf38
��38��
https://youtu.be/Mq2M5Y_Slyo
��61��
https://youtu.be/opm_3GPomsY
�ǂ������̂�����̂��悭�m��Ȃ�
���\�A�N�Z���g���߂̔e�C�̂��鉉�t���̂�
�啪�ǂ���������
��͂�Ό��z�u�����ʓI��
https://www.youtube.com/watch?v=wdX9qqbHN-E
���[�_�[�͓��{�l�����Ȃ˃o�[�[���J���}�\
�n�C�h���̓��[�c�@���g���e���炢�N��Ȃ̂ɋt�Ƀ��[�c�@���g��蒷�������������������āA����̍�i�͊��S�Ƀs�A�m�̂��߂ɏ����Ă��ˁB
���ۂ̓t�H���e�s�A�m�ʼn��t���ꂽ�悤�Ȃ̂�
�n�C�h���ɂƂ��ă`�F���o���ƃs�A�m��
����̐l���v���قǂ͈ӎ�����ĂȂ��Ǝv�����B
�t�H���e�s�A�m��z�肵�Ă������Ƃ͖��炩���Ƃ����
���̃\�i�^�̓x�[�g�[���F���Ɍq���鋿�������ˁB
���������̔N��l����������Ǝv���B
�����ɉ��N�����邩�킩��Ȃ���
�Q�O�O�X�N�����\��Ƃ����v�悾�������啝�ɒx��Ă���
�������Ƀt�@�C�̑����Ō��݂͊y�c�̃��[�_�[��
�w�����Ƃ��Ă����ŁA�x�X�Ƃ��Đi��ł��Ȃ��B
�����ɂ��ăX�N���x���_���̃q�b�g�Ȃ邩
�����ȑ�98�Ԃ͑����������c�ւ̎v���A����ׂ��x�g�ւ̋���������B
����Ӗ��A����͖͎ʂł���̂�������Ȃ��B
�Ⴂ���ɕӋ��n�ŊO�I�e�������Ȃ��Ƒn�I�ɂȂ炴��Ȃ���������
���Ƃ��Ă���͊O����̉���ۉ��Ȃ��ɋz��������łȂ����B
�ʑt�ቹ�e�����炢�Ȃ��傶��Ȃ��Ă������������Ƃ����Ȃ�N�ł��ł����������ǂ�
�Ȃ�ƂȂ��u�Ђ傢���Ђ傢���v�������������Ă����̂�
�X�R�A���J�����灔�W�W�̖؊ǂ�
�t���E�g�P�A�I�[�{�[�Q�A�t�@�S�b�g�Q�@�ł����B
���܂������������t�͂ǂ����͂킩��Ȃ��ł���
���Ԃ̃p�[�g�̓I�[�{�G�ł��B�������Z�J���h�E�I�[�{�G�ł����B
�Z�J���h�p�[�g�͒ʏ�t�@�[�X�g���n���Ƃ�����
���ŏ���x����p�[�g�Ȃ̂ŁA
�t�@�[�X�g�ƃZ�J���h�E���@�C�I�����̊|�������Ƃ�
�S�Ẵp�[�g�ɋC�z�肵�Ă�Ȃ���
���������ł͂�����Ƃ킩��Ȃ������Ȃ�ˁB
�n�C�h���������N������Ă��珑���n�߂�ꂽ�������A
�[��������i�������B
�V���X�^�R�[���B�`�̌��l�Ɠ����ŁA
���������͍̂K�^�Ȃ��Ƃ��B
�O������̉e�������Ȃ��W��
�o�C�^���e�B������I���W�i���e�B���ӂ��
���X�����n�쎞���ł���Ƃ�����B
�N���V�b�N���y�Ƃ����Ƃǂ����[���ł��������Ԃ���
�d���������߂������������킯����
�n�C�h���̉��y�͂ƂĂ��C�y�ł����̂��B
�����R���g���i�J�t�F�[�c�B���}�[�}���c���j�ɂ��
�o���g���g���I�̌��y�O�d�t�łɂ�
���y�l�d�t�ȂƂ͂܂�������ǂ��������B
�n�C�h��������ɒ����Ă݂����l�͂��������Ă݂Ăˁ[�m�V
�����Ă݂����Ȃ����B
����ɂ��Ă��A�n�C�h���̎d���̗ʂ́A���������̂�����ȁB
�ł�����Ƃ����A�e���}���Ƃ͂��������E�E�E�B
�e���}����12���炢�����Ȏn�߂���ɁA86�˂ŖS���Ȃ钼�O�܂ō�Ȃ������Ă邵�ˁB
�e���}����1767�N�܂Ő����Ă邵�A���̍��n�C�h���͊���35�˂ɂȂ��Ă�ˁB
�p���i�b�V���W�`�icpo�j�ɂ��S�Q�A�S�R�n�̋Ȃ�
���B���@���f�B�ۂ��Ă��������B
��o�b�n�����B���@���f�B����̉e���͂��邪
�e���}���̏ꍇ�͉��y���̂��̂��o���b�N�炵�����͋C�Ōy���B
�n�C�h�������������[���ɒ����Ƃ������C�y�Ɋy���݂����B
�n�C�h���E���[�c�@���g���ɁA�o�b�n����ނ��Ă���Ǝv���B
���y�j�Ō�ނ����Ȃ�āA���ɗႪ�Ȃ���Ȃ����낤���B
>�o�b�n����ނ��Ă���Ǝv��
��ނƂ������A��������
�o�b�n�����z�����i�ƒf��ł���j��ȉƂ���́H
�悭�ł��������y�̑����ɂ��y�Ȃ��B
���̓_�A���܂�O���Ȃ��s�A�m�Ȃ���Ȃł���
�x�[�g�[���F���́A�債�����̂����B
�o�b�n�̑��q�B�̍�i�͂ǂ��Ȃ�H
�ÓT�h�Ƃ͉��y�̕~����
�Ⴍ�Ȃ��đ�O�����Ă�������B
�o�����牺��݂����ɏ��z�����畽�n�ɂȂ������Ⴄ��
�����[�g�Ƃ����y����ނ̉��y���G�����Ȃ肷����
�s���Ƃ��܂ōs���Ĕp�ꂿ������Ƃ����B
����Ǝ����悤�ȂȂ�䂫�Ƃ��Ⴄ���ȁc
�A���X�m���@��A���X�E�X�u�e�B���I���̎���ɔ�ׂ���
����l�ɂ�������Ƃ��������̂��Ƃł͂Ȃ��̂��H
���y����ނ��Ă�Ɗ����邾����
�����������Ƃ�����`�F���o���ƃs�A�m��
���Ղ�����
�L�[�ɂȂ��Ă��܂����H
�o���g�����Č��̐����₽�瑽����������ςȂ̂Ŕp�ꂽ���
���Պy��̌����Ă���قNj���Ȃ��̂���
���_���s�A�m���炢���낤�����������Ă����Ă����v�Ȃ̂́B
���y��̒����͉��t�Ҏ��g���s�����Ƃ�����
�s�v�c�����
�]�����R���Ԃ̂��鉤�炢������������Ȃ��y�킾�����̂��낤�B
����̊y�탔�B�I�[���i�K���o�j�ɔ�ׂ���A�p���Ƃ����قǗ��s������Ȃ������B
�V���[�x���g�̃A���y�W���[�l�݂����ɋȂ��c���Ă��邪�y��̕���
�����g���ĂȂ��Ƃ����čD�����ȁB
�g���Ă������C�e�[�v��������Ɏc���Ă��Ă��v���[���[�͂�����������ĂȂ�
�݂����Ȃ��̂Ŋ��S�[���B
�y��̉p��instruments�͉��y�́u����v�ɉ߂��Ȃ��B
>�y��̉p��instruments�͉��y�́u����v�ɉ߂��Ȃ��B
���₢��Ainstruments�́u�y��v�Ɩ�ł�
�ǂ�ȃV���{�C�����ł��u�u����v�Ɓu�y��v�͕ʂɋL�ڂ���Ă܂�
���Ȃ݂ɁAinstrument�̌��`�́u�g�ݗ��Ă���́v�ł�
�u����v�ł͂���܂���
���`�u�g�ݗ��Ă���́v����h�����āA�u����v��u�y��v�ɂȂ�킯�ŁA
�u����v�Ɓu�y��v�͕ʂ̊T�O�ł���
�����ɕs���a�����o�Ă���Ƃ��날�邶���H
��(50-51����) / �Č���(225-226����)�ʼn��������ƁA
��1���@�C�I������F / C�A��2���@�C�I������C / F#�A���B�I����B / E�A�`�F����E / A
������2. Vn��Va�̉�������2�x�ɂȂ�̂��ȁA����������D��
��(50-51����)/�W�J��(189-190����)/����(225-226����)
1. vn: G/D/C
2. vn: C#/G/F#
�@va: B/F#/E
�@vc: E/B/A
�Ȃ̂ŁA���E�Č����ł�2. vn��va����2�x�A�W�J���ł͒Z2�x�i���Ǝv���j
���Ƃ��̓W�J���̕����͑���2�ƑΉ��������ĂȂ���
�u�R�[�v�}����PHILIPS�ւ̏��^���Ղ��܂ށA
���A��1976-81�N���^�̃`�F���o���^������C��5�앪����!
�S�Đ��E��CD��!�v���Ă��ꂽ����
�t�B���b�v�X���f�b�J�ɓ�������Ă���
���������W���P�f�U�C���ɖ��W�ȃf�b�J�}�[�N������̂�
���������̂ŁA������m��҂ɂ͈�a�������肷����������
����͂������N���A���Ă���đ�ς��肪�����B
�I���W�i���W���P�͋��̔�����������������
�����܂ł̍Č��̓��V�Ƃ��悤�B
�����u�n�C�h���̃\�i�^�v�̂݁uphilips�_�b�`�}�X�^�[�Y�v�Ƃ���
�I�����_���[�J�����̂Q���g�ŏo�Ă����͂��Ȃ̂Ő��E���ł͂Ȃ��B
�_�b�`�}�X�^�[�Y�̓��[�J���ՂƂ������Ƃ�
���炭���{�ɂ͐��K���[�g�ł̗A��������Ȃ������̂ł͂Ȃ����B
�s�A�m�O�d�t�Ȃ⌷�y�l�d�t�Ȃ��͂܂�Ȃ��ȁB
YouTube�Œ����ĂĂ����v�����B
�Êy�킾���A�����͔����̂�߂���B
�A�}�]����6��~�Ŕ�����ɂ�1��������݂����B
�~�����l�͂ǂ����B
�o���g���g���I�͈ȑO�͑ދ��������A�������Ȃ����Ƌ����[�������邩��
����ς蒮���Ȃ�����
���Ԃ�u���Ă��A����ۂ̂܂I�����Ă悭���邱�Ƃ�����
�t�҂�����ĂȂ��B
���Ɏv������Ȃ��t�҂�
�S�Ȉ�C�ɘ^������
���̂ɂ͌��E���L��͂��B
�n�C�h���̉��y�Ɏ����͉������߂Ă���̂�
�Ƃ������Ƃ��Y�ꂽ�炢���Ȃ��B
��i�ȉ��t�Ń_�C�i�~�N�X�̕��������Ɗ�����������邪�A���Y���A�A���T���u���̖ʔ����͐\�����Ȃ��B
���炭�ʂ̍�ȉƂ��Ă������A�܂��n�C�h���̎l�d�t�ɖ߂��Ă����B
�V���[�}���̌��y�l�d�t�ȏW���������ĂȂ������ȁc
�n�C�h�����T���Ă݂邩�c
���Ȃ݂�youtube�őS�Ȓ�����B
�����Ȃ��璮���̂́A����ώ����y�����Ȃ���ȁB
����A�����������A�܂�Ń��_���y��݂����Ō����B
�Ȃ̂ŁA���_���y��D���Ȑl�͂��̔Ղ������߁B
�V�����^����������
�ǂ����P�����̂���ŗʓI�ɂ��̑���Ȃ��B
����ƂđS�Ȃł͑�������B
���̓_��ASV��hus�Ղ̂Q���͊������ʂ������B
�x�߂̃e���|�ɂ��ւ�炸�����炭���s�[�g�����ׂĒ����ɂ���Ă鏊�͕]���ł���
�n�C�h����ϋɓI�ɘ^���E�Љ�Ă������̌��J��
�^�ɒl���邪
�s�A�m�\�i�^�S�W�̃W���P�ɂ�
��ȌÓT�s�A�m�̎ʐ^���g���Ă��邪
���g�̓��_���`�F���o����_���s�A�m�̉��t�ł��������
�t�H���e�s�A�m��N�����B�R�[�h���������Ȃ��Ȃ������ƂȂ��Ă�
��⌨�����������炤��������Ȃ��B
�p���̃s���I�h�w���҂Ƃ��Ă͂����Ƃ��n���ȑ��݂ł��낤
�j�R���X�E�}�b�M�K����
�����ȂV�X�A�W�O�A�W�P��^�������B
����܂Ńo�������[�X�ł͘^�������Ȃ������ԍ���
�A���g�j�j�̘^���Ƃňꎞ�ɑ��������ƂɂȂ�B����������ł���B
������ׂĂ���ƁA
����y��ƌÊy��A�ǂ���ɂ�
����������Ƃ������Ƃ��킩��B
�ł��t�H���e�s�A�m������
�H���Ȃ����Ȃ��E�E�E�B
�c�ƖړI�̊w��~���킩�Ȃ��ĕ��a���ȁB
�p��ɂ��Ƃ�ł��Ȃ��̂킭���B
�p����[�}�́A�ό��q�������ĉ������ǁA
�E�B�[���̊X���������̂́A
�N���V�b�N���y�̈Ќ��ɂ���Ď���Ă��邩��B
�n�C�h���X�����A�n�C�h���̈Ќ��ɂ���Ď���Ă���̂��낤�B
CPE�A�n�C�h���Ȃ�N�����B�R���h�̕���
�X�ɑ@�ׂŗǂ��B
���X�g���e���Ɗy�킪�߂���N�`���ɂȂ�Ă͖̂{���̘b�ȂƎv�����B
�u���X�g���e���Ă����Ȃ��s�A�m�v�������Ƃ����b���ǂ����œǂ�
���悪�킩������܂��H
�N�����l�b�g�ő�p�ł��邩�m�肽����ł��B
At the Prince's court, the baryton was always tuned with bowed
strings of D-G-c-e-a-d, and sympathetic, plucked strings of A-d-
e-f sharp-g-a-b-c sharp-d. Haydn scored both parts in the treble
clef, an octave higher than they sounded.
Haydn indicated which plucked strings to use by numbering them
l to 9 under the notes.
The tuning of these strings also decided the keys inthe works.
Most of them are in D major, or more rarely in A major and G major.
Flat keys scarcely ever occur.
�ǂ��J�o�[���邩���e�[�}�ł͂Ȃ����Ȃ���
�V�����N���G�[�g����Ƃ������Ƃ��d�v�Ȃ�܂���
�P�Ɉڒ�����Ƃ������ƂłȂ�
���ꂱ���I���W�i���̋ȂȂ�Ȃ��̂Ǝv�킷�悤��
���y�l�d�t�Ȃ����C�y�ɒ����āA�܂�ōÖ��p�ɂ�����ꂽ�悤���B
����̓n�C�h�����L�̊��o�B
�Ԃɍ���Ȃ������낤�B
�N���V�b�N�͂̂�т�y�[�X��������B
���̃X�����{���̂������y�[�X�ɖ߂��Ă悩�����B
https://youtu.be/aieNUMWiT7Q
http://nico.ms/sm1142226
http://nico.ms/sm1102026
�I�[�X�g���A�鍑���́uGott erhalte Franz den Kaiser�v
http://nico.ms/sm3508062
�����삩�炱�̃N�I���e�B�A�Ȃ�đf���炵���낤�B
�����Ȃ͍ŏI�ԍ����Ȃɂ�炻�̍�ȉƂ̑����Z�I�ȋȂ�
�݂����Ȉ�ۂ��܂܂��邶��Ȃ�����
�ł́u�����h���v�̏o���������̂��Ƃ����A�����ł͂Ȃ���
���ꂾ���Ńn�C�h�������Ȃ̂��ׂĂ͌������Ȃ��Ƃ������ȁB
���R�Q�n�����Ɓ��R�V�n�����ł͓������Ȃ̂ɕ��͋C���Ⴄ�ȁB
�U�������͘^�����Ȃ����A�p���͘^������
�Ƃ����w���҂�������������
������āA���̃��[�x���Ɋ��ɃU���������̘^��������Ƃ���
���ƂłȂ��H
��قǂ̗L���w���҂łȂ���c�f�ł��������Ȃ�
�Ⴄ�w���҂ʼn��x���^������Ȃ�Ă��Ƃ�
�͖̂\���ƍl����ꂽ�ˁB���狣���Ղ����邱�ƂɂȂ邩��B
�ʂɃp���Z�b�g�͈ӊO����Ȃ�����
�����19�Ȃ���������
�唼�͂����ŋ���
�������ʔ����āA����60�A70�A90�Ԃ�������
���̂����肩��A���������Ȃ⌷�y�l�d�t�Ȃ̑S�W���Ē��������Ǝv���悤�ɂȂ���
�͉̂��N�̃��[�x���e�ЁA���t�ґ������ȁB
�I���t�F�E�X�����ǁA�J���e�B���[�i�A
�����ă��g���̍��ɂȂ�ƒ�ԍ�
�͖��Ӗ�
�ɂȂ�B
���܂ł����N�̘^���������l��
�Ƃ��ẮA�����I�ɃU���A�p���AV�����Ȃ��B
�I�b�N�X�t�H�[�h�������20�Ȃɂ��Ƃ���
44�ԁu�߂��݁v��48�ԁu�}���A�E�e���W�A�v�������ȂƂ��Ĉ���ꂸ�A�n�C�h���������ƒ����Ă݂����Ƌ��������Ă���Ƃ��ǂ蒅����ԂȂ̂͂ǂ��ɂ��Ȃ�낤��
����̌����Ȃ��Ƃ����₷�����Ȃ̂�
�����A�ǂ��炩�ƌ����Ί�l�ϐl��������Ă���
�Ƃ������^���j�Ȃǂ��������Ȃ����낤�B
���̂���l�C�E�̐l�w���҂��^��������̂������ȂƂ����ˁB
>�u����Ȃ�V���t�H�j�[�v��^�����Ă�V�F���w���Ȃǂ�
>�����A�ǂ��炩�ƌ����Ί�l�ϐl��������Ă���
�^�����Ă��炦��Ε����邪�A�f�G�ȃm�C�Y���������Ă���
�������������u���o�v�����R�[�h�ł�邱�Ƃ��A��l�ϐl��������
�䂦�낤�@�������w���҂͂����������Ƃ͂��Ȃ�
�ł��A�a�V�Ŏ������肵�Ă���@���ꂪ�V�F���w��
�f�G���Ǝv��
�y�V�F���w���̍��ʁz
https://youtu.be/VO4omSklXdI?t=1076
�W�X�A�X�O�A�X�P�̂R�Ȃ�
�Ƃ�킯�N�I���e�B���Ⴂ�Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂�
�P�Ƀj�b�N�l�[�����Ȃ������ŃX���[����Ă���Ȃ�
�����������Ƃ��낪�[�������Ȃ���Ȃ��E�E�E
�A���m���͎���ł܂�����
�m�����g���ɂ͂��̂W�W����X�Q�܂ł́A�Ȃ�Ƃ��^�����Ăق����ȁB
https://auctions.c.yimg.jp/images.auctions.yahoo.co.jp/image/dr000/auc0406/users/1a579b6f69196956e1fb3f1b087bd847e23bee7b/i-img1200x1200-1529140110mvqz9g13089.jpg
�x�[���̃n�C�h�������͖���
�����ȃ^�C�v�̉��t�������Ă����Ƃ͎v������
�����A����ƃ����^�[�̌R�������͊��ق��Ăق����ȁc
�o�[�~���K���̘^���͗ǂ������̂�
�Ŏ����Ă�Ƃ���������ɂ��Ă�Ƃ��낪������
�w���҂ł��ꂪ�K�����ƕς���Ē����l��
�����ƌ��킹����Ă��Ƃ́A���܂�Ȃ����
�ǂ������������҂𗠐邱�Ƃ��Ȃ�����
�N���U���Ă�����N�I���e�B�B���g���͎��߂Đ����������Ǝv����B
op20�������َ��ŁA��������op33�Ƃ͑S���������i�ƂȂ邪�Aop17��33�ɂ͌q���肪��������B
Op9�͂��邯��op17����̓Z���N�g����ĂȂ���
���l�Ɋւ��ẮA�S�R�Ӑ�����Ȃ��ȁB
�G���f�[�f�B�l�d�t�Ȃ��A������̕�����o���ȋC��������B
��Ȏ������Ⴄ�Ȃ�g�ݍ��킹�Ĉꖇ�ŏ����������
���t�҂̃Z���N�g�A�C��������Ėʔ����B
�Ⴆ���t�L���Ȃǂ́u�z�����V�O�i���v��
���̃v���g�^�C�v�I�ȁ��V�Q���J�b�v�����O���Ă�B
�Ґ��Ƃ����Ă��t���[�g�ƍŌ�̍Ō�ŃN�����l�b�g����������
����Ȃ���������x����B
���}���h�ƈ���ČÓT�h�͊��͂����鎞���̂ق���
�Ȃ��V�N�ł�����B
��Ȏ������Ⴄ�Ȃ�g�ݍ��킹
�ƌ���������ɍ�Ȏ���������31�ԃz�����M��(1765�N)��72��(1764�N��)�̑g�ݍ��킹������̂��c
���Ȃ݂ɃY���F�[�f���͂��̂Q�Ȃ�73�Ԏ��(1781�N)�𑫂��Ĕԍ����߂������������ȂƎ����������ԍ����߂��Ȃ̃J�b�v�����O�ɂ���
https://img.hmv.co.jp/image/jacket/400/28/1/7/078.jpg
�~�ԍ����߂������������ȂƎ����������ԍ����߂���
���ԍ����߂������������ȂƔԍ��������������߂���
�u�}���A�E�e���W�A�v�{�u�鍑�v�{�u���܁v�Ƃ����J�b�v�����O�D��������
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516x-sFGHQL._SL1500_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51usXFOPW2L._SL1500_.jpg
���[�c�@���g����Ղ̂悤�Ȍ���R������Ȃ������Ă���
������āA���܂��N�̈˗��ŏ������̂��A�����͂��Ȃ̂��A�ڂ������Ƃ�
�܂�ŕ������Ă��Ȃ��炵���@�����ɐG�����ꂽ�悤�ɒZ���Ԃŏ����ꂽ�̂�
�͂����肵�Ă���@���y�j�̃~�X�e���[�@�����A�������̂́A���������ɁA
�n�C�h�����p���E�Z�b�g�������đ�ςȕ]�����Ƃ��Ă���@�y���̓E�B�[���ł�
��������A������������[�c�@���g�������̂͊m���ŁA�G�����ꂽ�̂�
�z���ɓ�Ȃ��@�ł���A����R������Ȃ̒a���ɂ́A��͂�n�C�h����
�傫���e�����Ă���Ɓ@���[�c�@���g�̓n�C�h����ʂ��Č����Ȃ̉\����
�C�Â��Č�����������@���ہA�n�C�h���͂��̌�A���x�̓����h������˗���
�āA�U�������E�Z�b�g�̌���������āA�����ȍ�ȉƂƂ��Ă̖�����
�s�łɂ���@�������A����̃��[�c�@���g�͊�Ղ̂悤�Ȍ����ȂR�Ȃ́A
�ǂ��ŏ������ꂽ�������������Ă��Ȃ��@�����炭�o�ϓI�ɂ͎��s������
�Ǝv����@���[�c�@���g�͂���ȍ~�A���������n�C�h���Ƃ͑ΏƓI�ɁA
�����Ȃ��������Ƃ͂Ȃ�����
�Ȃ��n�C�h���̓U�������Z�b�g��͎��ʂ܂ł�14�N�������������Ȃ��������Ƃ͂Ȃ�����
�_���̊y�m�����炩���Ă�悤�ȍ�i�u���y�̏�k�v��
�����N���̈˗��ō�Ȃ��Ă����炱�̏�Ȃ����炾���ȁB
�����Ȃ͊�y�ȂłȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����������͂������悤����
�܂��x�[�g�[���F���̑�9�ԈȑO��
�t�H�[�O���[(1749-1814)��1806�N�A���B���^�[(1754-1825)��1813�N�ɐ��y�����������ȍ���Ă��炵������
�����Ȃɐ��y����Ȃ��̂��u�������v���Ă킯�ł��Ȃ��̂ł�
�����̌`�����ł̘b��
�Ⴆ���t�����ȕ��Ȍ����Ȃ͐������
�������L���č�Ȃ��ꂽ�̂�105�ԂP�Ȃ݂����₵�B
�܂�uSinfonia�v�͊�y�Ȃ����uSymphony�v��uSinfonie�v����{�I�ɓ���
���̑��ʼn̂��Ă����킯����
�̂Ɗ�y�Ȃ͈Ⴄ���̂�
�����ď��������Ă����Ƃ��������ł́H
�n�C�h���̌����Ȃ͌����I�̋Ȃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ���B
�ǂ�قǂ̂��̂��o�������낤�Ǝc�O�łȂ�Ȃ��B
�l�G�̏��t���Ă���ƁA���̂܂܌����Ȃ��n�܂�悤�ȋC�����Ă��܂��B
������肶��Ȃ��ď펯����������
�x�g�̑�X�̓V���[�̎��������f�B�ɂ̂��ĉ̎�⍇���ʼn̂킹�Ă��邪
���Ƃ��ƃo���b�N�̏��ȁi�g�ȁj�ɂ�
�A���}���h�A�N�[�����g�A�T���o���h�A�W�[�O�Ƃ��������Ȃ̂ق���
�u����v�Ƃ�����ɏ����������Ȃǂ̊�т̕���
�������Ă����肷��̂�
���k�G�b�g�y�͂����n�C�h���̌����Ȃ�
���̗�����p�����̂ƌ����Ă����̂�������Ȃ����A
���c��������Ȃ����Z���i�[�h�i���Ƃ͔��O�ŗ��l�ɉ̂��ȁj�ɑ���
�n�C�h���̖�O���y�A��O�g�Ȃ̓t�F���g�p���e�B�Ƃ��Ă��邱�Ƃ�
����I�Ȃ�����Ƃ����Ⴂ����������B
�@�@His melodies make you want to sing.
�@�@His rhythms make you want to dance.
�@�@His good humor make you want to laugh
�@�@�@- even in the middle of a concert.
�@�@He is constantly entertaining, uplifting, life-enhancing.
�@�@Even in the enlightened 21st century
he is still underrated by some music lovers.
�@�@But just listen to his amazing music.
�@�@�@�@�@�@�@by Roger Norrington
�����Ă݂���ق�ƂɃN�\������
�Ⴆ�g���l�����̂悤�ȍL����Ԃ�
�����y���Ă��܂肠�肦�Ȃ��Ƃ������B
�I�P�ɂ������đ�z�[���̍Ō��Œ������ꍇ�A
������āA�������Ȃ��ōD�܂����͂Ȃ��Ǝv����
����ȃJ���I�P��������킯����Ȃ����ȁc�B
�x�g�̃R���I�������ȁH�̂悤�ȃt���[�Y���o�Ă��ăj����(�E�́E)����
HMV�Œ��������̓��גx��ɂȂ��Ƃ�
���������������
������ : 2019/01/31 (�\��)
�Ə�����Ă����
HMV
�������@2019�N01��20��
�����@���[�J�[����
�^���[���R�[�h
������ :�@2019/01/31 (�\��)
�������ȍ~�ɂ��͂��������܂�
Amazon
���݂������������Ă���܂���
�D���ōD���ł��܂�Ȃ��Ƃ������̂�
�������̂��낤�H
������������ȂƂ���̕s����̑��l�Ƃ��܂��̍D�݂���v����킯�Ȃ����B
��Ԃ̂��E�߂́A�Í��W��������킸
�u�W���P�����v�Ƃ����K�E�Z�������āA�������������Ń��[�x����A�[�`�X�g��
�R���Z�v�g�����������m�邱�Ƃ�
�ł������̂Ȃ���
���܂͂����R�X�g��}���邾����
�ǂ��ł������悤�Ȃ̂������ł�
�N���V�b�N�͓��ɁB
angeles
http://www.e-onkyo.com/music/album/a378/
�c���ߑ��Ȃ̂C��^���ƌ������肷�邪�g���l�����ɂ��Ƃ���̂͏��߂Č���
�I�P�͋���ł̘^�����Ǝc���ߑ��Ȃ��Ƒ����C������
�S�W����Ȃ����ǃV���i�C�_�[SQ
����1930�N���sp�����Ƃ��͕��ʂɊy���߂邵�A�t���x�����x�g2�ȊO�͑��y���߂�̂ɁA
�V���i�C�_�[��ars nova�͕��߂��Ă��������B
�قڑS�ʓI�ɉ����ꂪ���Ă�B
���}�X�^�[�ŁA�������߂邽�߂ɉ������s�ł������Ƃ����v���Ȃ��B
�������͈�x�������Ă��Ȃ���Ȃ����Ǝv�����x���B
https://tower.jp/item/3735647/The-String-Quartets-of-Haydn
�������Ȃ特���͂��Ȃ肢����
���肪�Ƃ��B
�ł��A������K�����̑��݂͒m���Ă��B
���K�����Ŏ������ėǂ���������A
ars nova�ł�����Ȃɍ����͂��͖����Ǝv���ă|�`�b���������B
�悤����ɁA�����Ԕ����Ȃ������B
>�V���i�C�_�[sq ��ars nova�̂���ŋߔ��������ǁA
>�����ň��œ����̂Ă����Ȃ���
�����A��Q�҂�������
�����ɂ��āA�����������蔃���Ă��܂����������̍����ɕ��ꂽ��
�����͍����Ȃ�Ă���Ȃ��@�ŏ�����Ō�܂ʼn�������Ă���
�}�W���肦�Ȃ�
�@
���̎�̃{�b�N�X�́A�ǂ��������Ղ̈��Ղȃf�W�^���R�s�[���낤�Ǝv����
���S���Ă������A�f���Ƀf�W�^���R�s�[����\�͂��Ȃ��ƌ�����
ars nova�A�{���ɕ��ꂽ
���Ȃ݂ɉ��t���̂��̂́i�����ȊO�́j���ɗǂ����̂ł�
�ŋ߁A�N�������Ȃ����畁�ʂɂ������������������B
2�����O�قǂɁAhmv�̃����L���O��ʂɏオ���Ă�����A����ȊO�ɂ������������������Ǝv�����ǁA
�܂��A�����ĂȂ��z������A��ɐ��K�����ɂ��Ƃ��ׂ��B
���ł�����M&A�̎O���̈�̉��i�����A�����肳��Ɉ����ƂȂ����瓖�R�������������낤
50�N��̃��m�����Z�b�V�����ŁA�����܂ō����������Ă���܂�Ȃ���
���^�Ȃ����ԕ��Ă��
�ŏ��͂������������āA���̒l�i�ɉ��������Ƀ����L���O��ʂɂȂ������Ƃ�����́B
�ł������Ƀ����L���O����������B
�P�Ƀ��m�����̃n�C�h�����s�l�C�Ȃ������Ǝv������A�܂����̕������B
https://www.hmv.co.jp/product/detail/8586167
������������l�������������ă��r���[�����Ă����Ȃ�
�n�C�h���������c���J�b�v�����O������
�����l���ĂB
���c�̌��l�Ȃ�ă��m�ł��X�e�ł�������ł��L�x���낤��
�v���R�t�B�G�t�Ƃ̃J�b�v�����O�Ȃ�
�n�C�h���̂ق����Ȃ����瑊�������Ǝv�����ȁB
���h�r���b�V�[�{�����F���{�n�C�h���u�_���v
���v���R�t�B�G�t�Q�ԁ{���[�Z���{���[�c�@���g�u���v
�̓���o�Ă��
�ǂ�����ɂ���Ŕ�����
https://tower.jp/item/3170305
https://tower.jp/item/3842871
�h�r���b�V�[�{�����F���̌��Ղɂ��v���R�t�B�G�t�Q�ԁ{���[�Z���̌��Ղɂ��n�C�h����[�c�@���g�͓����ĂȂ��̂Ń^�����R�œƎ��ɒlj��J�b�v�����O�����悤��
https://www.lpshop-b-platte.com/smp/item/271530.html
https://www.bakuendo.com/products/detail/2438
https://eterna-trading.jp/html/upload/save_image/1016/a/1016-026.jpg
�v����ɂR�����Q���ɍĕ҂��ĕ��������̂��^�����R����
���ꂽ���͖̂����悤�Ɏv����
�h���e�B���݂̉����������炢����
>���y�l�d�t�Ȃŏ��t����������t���Ă�̂�op.71-2�����Ȃ̂��ȁH�@���̋Ȃ��Ȃ�D��
����������Ă���Ƃ����ƁA�������Ɏv��������Ȃ��ł��ˁB
���̋ȁA���������Ȃ肷���Ȉ�Ȃł��B
���l�́A���_���D��ł���̂������̂ł����A����́A�U������SQ����Ԉ��D�ł��B
�G���f�[�f�B���������Ă���̂����������Ȃ��B
�p���l�A�[�`�X�g���Ė����̔����d�邽�߂��A���������̂Ƃ͈Ⴄ��
����ɃN�C�P��SQ�����̌����߂��ӎ������̂����Ȃ��ł�
�n�C�h���̏��^���̓G���f�[�f�B�������B
>>308
�h�r���b�V�[�{�����F���ɐU���Ă�����
���炢�������B�ł��n�C�h���̓��[�Z���E�v���q�̑���
����U���Ăق��������@orz
http://www.amazon.com/dp/B00KGUETBU
https://www.discogs.com/release/9665778
����Ɍ��炸�A����܂Ōy�����ꂪ��������
���������̂Ȃ����i�̃��m�����^������
���W���[�ȃ^�C�g��CD�Ƀt�B���A�b�v����Ă�\�������邩������
�����A������ŁA�ǂ����ЂƂA�I���W�i���t�H�[�}�b�g��CD���Ƃ���
�I���W���P�ŗ]�v�ȍ������i�V�œ��̖�CD�����Ăق������̂Ȃ���c
������2012�N��2015�N������n�C�h���̕������[�c�@���g���R�N�����������Ă��ꂽ��
���肪�������Ƃ�
�悭���邯��
���̏ꍇ�I���W�i���Ղ̃R���Z�v�g��
�����Ă��܂��킯������
�ǂ����Ȃ�A�h�r���b�V�[�ƃv���R��
�ʁX�ɑg�ݒ����ĂR�ȓ����CD�Ƃ���
���ꂼ��V�������v���f���[�X���������ʔ����̂ɂȂ��B
���ꂾ�ƃn�C�h���ƃ��c�����S��
���[�ȃI�}�P�����݂����ł�
�厖�Ȏd������Ȃ����Ǝv���B
���̓{�b�N�X���S�W���̂Ɗ��S��
�����Ă��ȁB
���ꂵ�����@���Ȃ��݂����ȁB
����ɂ͂����ЂƍH�v���Ȃ���ˁB
�^�[�g���C
����z�O�E�b�h/AAM�͋���ł̘^���������ɂ�������炸
�c�������Ȃ�����ƕs�]
����̓I���]���[���̃G���W�j�A�̂������낤
�c�����Ԃ̒����p�̃Z���g�|�[���吹����9.3�b������܂����A�I���K�����t��O���S���[���̂ɓK��������̎c�����Ԃ�6�b�O��ƌ����܂��B
�N���b�V�b�N�̏ꍇ��2�b�O��̎c�����Ԃ̂���z�[���ł̉��t���œK���ƌ����Ă���A�����̃T���g���[�z�[���A�I����z�[���̎c���͖��Ȏ�2.1�b�A
���E3��L���z�[���i�E�B�[���w�F�����z�[���A�A���X�e���_���E�R���Z���g�w�{�E�A�{�X�g���E�V���t�H�j�[�z�[���j�̎c��������������Ȃ�2�b���x�ł��B
https://yoko-tada1946.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_603/yoko-tada1946/E3839BE383BCE383ABE5AEB9E7A98DE381A8E6AE8BE99FBFE69982E99693.gif
�}�̓z�[���̗e�ςƎc�����Ԃ̊W�ׂ����̂ł��B
�v���e�X�^���g���J�g���b�N�̋���̕����c�����Ԃ��������ƁA�A�����J��胈�[���b�p�̃z�[���̕����c�����Ԃ��������Ɠ��A�����[�����̂�����܂��B
����ł̃I���K���R���T�[�g�͘N�X�Ƌ����đf���炵���ł����A�����Ńs�A�m�̃R���T�[�g������Ƃ����苿���ĕ��C���ԂɂȂ��Ă��܂��܂��B
���C��̃f�[�^����������
��ʓI�ȉƒ�̕��C��ƑK���̔�r������
�z�[���Ƃ��E�ߏ�ł�邾�땁�ʁB
����A�G���W�j�A�ЂƂ�̎�E�ӌ��Ƃ����킯�łȂ�
�v���f���[�T�[��w���҂��������Ńv���C�o�b�N���Ă���ʐ^��
���܂Ƀu�b�N���b�g�ȂǂɌf�ڂ���Ă邶��Ȃ��ł���
�F�ʼn����߂�����B
�Ⴆ�A�Â����̂ł�
�V�F���w���͎w����Œ����Ă鎞�Ɠ������R�[�f�B���O�o�����X�c�@
�Ƃ����悤�Ȏ�ӂ��n�C�h���R���E���ʂ�CD�ɋL�ڂ���Ă���Ă���B
�����h���̃E�H���T���X�g�E�E�A�Z���u���[�E�z�[���B
�o�[���X�^�C��LSO�̃}���Q�̘^�����ɂ��Ȃ��Ă���
�����V��̍�����z�[���Ǝv������
�������Ă݂�Ə����w�Z�̑̈�ق��炢�̋�Ԃ�
�X�e�[�W�����Ǝ��Ŏg���邭�炢�̋K�́B
�����炭�^���̓X�e�[�W�łȂ��̈�قʼn^�����镔����
�L���X�y�[�X���g���Ă���̂��낤�B
�P�O���̍Ō���̘^���Ńw�����[�E�b�h�z�[����
�P���̓A�r�[���[�h���ł��������
�ނ���S�W�̂悤�Ș^���ł͖����悤�ȉ���ɕۂ��߂�
�Ȃ�ׂ��Ԑډ�������Ȃ��悤�ɃI���}�C�N�Ŏ��^����
���Ƃ��炢��������ł́B�t�F�[�Y�S�����������f�b�J�͂��̕�����
���C���Ȃ�܂����ƁB
�c������߂��Ă�^�������C��Ƃ悭�����Ă邩����ۂɕ��C��ʼn��t������ǂ��Ȃ�̂����Ă��炢�̘b�Ȃ��A�E�ߏ����w
���j��������悤�Ȑ̂Ȃ���̑K������
�Α���̑���Ƀ^�C������A
�V�䂪�����ď�ɂ̓X�e���h�O���X�Ȃ�ʃK���X���B
���Ƃ͍L���̖�肾��...
���A�Ⴄ���B
�������ނ��Ƃɂ���B
����ɂ��Ă��A�o���g���O�d�t�ȑS�W�͂Ђǂ������ȁB
�ቹ�ɉ����W���������B
���ƌ����āA�����R���g���̃��@�C�I�����ł́A
����ς�ǂ����������肱�Ȃ��̂ȁB
�����n�C�h�����o���g���O�d�t�Ȃł͂Ȃ��A
4��\�i�^�ł��ʎY���Ă�����A
���j������Ƃ��̑�ȍ�ȉƂƂ��Ă̕]����
���������낤�ɁA�c�O�łȂ�Ȃ��B
�ጷ�̂��߂̎l�d�t�ȏW
�` �\�i�^��3�� �n���� �u���i�̑g�ȁv
https://youtu.be/NHQ-GF475dM
���̎���͂��̎�̎����y�͂��ƃ��W���[
����Ȃ�CD�Ɠ��ꉉ�t���Ǝv�����ǁACD�Ƃ͈���Ďc���������ꏊ�ł���̂�������B
https://www.youtube.com/watch?v=wvRGH8s1X6g
�Гc�ɂ̎ԑ�H�̑��q��20/21���I�܂Ŗ����₷��ȉƂɂȂ낤�Ƃ�
���̕s����������̂��B
�^�����R�̕\����
�������@2019�N02��10��(�\��)
�ɍX�V���ꂽ�悤��
��9�E�U�T�E�U�V
�Ƃ������Ƃ���
�z�O�E�b�h/�E�F�u�X�^�[��CD�ł́��X�͂R��
���U�T��5���A��67�͂X�����^�Ȃ̂�
���́��X�ƂU�T�̕�����Ȏ������߂��B
�������玾���{�����̍��܂ł͊y�����s�̂���ĂȂ������W��������
�n�C�h�����g�����`�����̍�ȏ��ɂ��Ă͂ǂ��ł����������������悤���ˁB
�����̎�͒P���Ƀz�[�{�\�P���̃~�X�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ����B
��Ԃ����o���Ȃ�Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ����B
���Ȃ����͖�ǂłЂ肪�������Ă��B
�����Ƃ����ȂƂ��Ńn�C�h�������ė~�����ȁB
�Z�b�g�Ƃ��Ă͂n���T�O����ԍD��ł���i���łn���Q�O�j�B
���̌���A��Ȃ��ł́A�D���ȋȂ͂��������邯���(�n�C�h���̂r�p�Ō����ȋȂ͂Ȃ��j�B
�n���T�O���t�ł́A���Ȃ�\���傫�������V���i�C�_�[�r�p�����͓I�B
�����I�ȃ^�[�g���C�r�p�����킢�[���B
�ቹ�̐搶�������̐��k���^������Ȃ����A
�Ȃ��܂������ȁB
�n�C�h���Ƃ��ẮA�ō��̃��[���A�������낤���ǁA
����܂��������̋C�ɂ��Ȃ��ŋȂɂ��Ăق��������ȁB
�n�C�h���̃s�A�m�\�i�^�i�E�B�[�����T�ł̂T�U��)���������Ă����B
6�̃\�i�^op.30
Hob.XVI:35(�E�B�[�����T��48��)�n����
Hob.XVI:36(�E�B�[�����T��49��)�d�n�Z��
Hob.XVI:37(�E�B�[�����T��50��)�j����
Hob.XVI:38(�E�B�[�����T��51��)�σz����
Hob.XVI:39(�E�B�[�����T��52��)�g����
Hob.XVI:20(�E�B�[�����T��33��)�n�Z��
�G�X�e���n�[�W��܂̂��߂�3�̃\�i�^op.37
Hob.XVI:40(�E�B�[�����T��54��)�g����
Hob.XVI:41(�E�B�[�����T��55��)����
Hob.XVI:42(�E�B�[�����T��56��)�j����
����������2��5������
�悩�����A���|�u������
�ׂŒ����Ƃ悳��������A���Ȃ胊�}�X�^���s�Ƃ��łȂ���Η~����
�}�X�^�[�e�[�v�ɋN������m�C�Y�͏�ɓ����Ă��邪
�O�ɏo�Ă���̂͂Ȃ����B
�ʑt�ቹ���h���ĂȂ��ɁH��
�܂����`�F���o���A���Պy�킾�����ʑt�ቹ�Ƃ��Ďg�p�����y��Ƃł��v���Ă�́H
����ɑ��āA�u�z�O�E�b�h�̓`�F���o������ĂȂ�����B�ʑt�ቹ����ĂȂ���B�v�Ɣ�������l�͂��Ȃ�p���������o�J�B
http://classicalcd.la.coocan.jp/etcetera/201902.htm#201902121
�����c�F���h���t�@�[�w���C�E�B�[�������ǂ̎j�㏉�̃n�C�h�������ȑS�W
�pSCRIBENDUM����C���̃����c�F���h���t�@�[�w���C�E�B�[�������ǂ̃n�C�h���̌����ȑS�W���b�c�R�R���g�̃{�b�N�X�Ŕ����ɂȂ�܂����B
�������̂b�c�{�b�N�X�̔����͉���I�Ȃ��Ƃ��Ǝv���C�����������肵���̂ł����C����������ƁC
�����ɂ��ẮeDigitally remasterd from vinyl. Original tapes missing and cannot be found�f�ƋL�ڂ���Ă���C�k�o����̕����̂悤�ł��B
���ۂɉ����Ă݂�ƁC�k�o�Đ����̃X�N���b�`�m�C�Y��s�`�E�p�c�E�m�C�Y�����������C��r�I��������̗ǂ����ł͂���̂ł����C
�P�X�U�O�N��ɘ^�����ꂽ�k�o�̕����ɂ��ẮC���̌��݂��Ȃ��C�����≹�F�����قƂ�ǎ����Ă���Cmp3���݂Ƃ������C
�啔�ȑS�W�{�b�N�X�����Ń����[�X���Ă���VENIAS���[�x�����݂̉����Ȃ̂ŁC���̓_�͑����ɕ�����܂��C
����܂ŃC�A���E�W���[���Y�ɂ�鍂�����}�X�^�����O�Ȃǂ��s���Ă���SCRIBENDUM�̉����Ƃ͎v���Ȃ����x���Ȃ̂ł��B
�@���Ȃ݂ɁC���̃����c�F���h���t�@�[�̃n�C�h���̌����ȑS�W�͂b�c���͍����߂Ăł����C
���̓A�����J��THE HAYDN HOUSE���C�S�Ȃ�����mp3�t�@�C����1���̂c�u�c�Ɏ��^����$129.95�Ŕ̔����Ă���̂ł��B
���̃T�C�g�ł͑S�����Ȃ����ꂼ��P�����x�������邱�Ƃ��ł��C�����192kHz��mp3�Ȃ̂ł����C�����ɒ����Ă݂��Ƃ���C���������Ƃɍ�����SCRIBENDUM�̂b�c�̉����Ƃ���ȂɈ��Ȃ��̂ł��B
�Ƃ������Ƃ�THE HAYDN HOUSE�̉������g�p���Ăb�c�������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă��܂��̂ł����C���ۂ͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
SAGA��CBS�^���̃\�������X�Ղ̖�CD��������CDR(?)���ȂŔ̔����Ă��ȁB
�����ƋC�ɂȂ��Ă��
��������80�N��̘^���Ȃ̂�
�\�j�[���ٔF���Ă�Ƃ������Ƃ�
�}�X�^�[��j�����Ă����Ȃ��Ƃ��A�̔����������Ȃ��Ƃ�
�Ȃ��납�H
https://youtu.be/yPGHJLdjMZo
https://youtu.be/uJB0W3uPBIY
�A�^�b�J�l�d�t�c��YouTube�ɏグ�Ă鉉�t���C�ɓ������̂�CD�͏o���ĂȂ��̂��ƒT���Ă݂����ǁA�n�C�h����CD�́u�\���ˏ�̃L���X�g�̎��̌��t�v�����Ȃ�����
�����Ă��ꂪ�܂��n�C�h�����g�ɂ�錷�y�l�d�t�ҋȔłł͂Ȃ��ăA�^�b�J�l�d�t�c���I���g���I�ł��猷�y�l�d�t�ɕҋȂ��������Ƃ������������̂�����
https://youtu.be/PN2uo62a5O0
82�ԁu�F�v�̃t�B�i�[��4��5�b�̏��ʼn�����u�r��Ă�
���肪��
���̃v���[���[�ł��m���߂������������
�ǂ̃v���[���[�ł������ɉ���т�r�ꂪ����ꍇ
�͂��߂ĕs��Ƃ����Ă悢�̂ł�����
�f�W�^�����Ă��ꂪ���邩�璮���Ȃ��Őς�ł����l�͗v���ӁB
���[���A�h���e�B�̃g�r�A�̋A�ҁA�ǂ����ɔ����ĂȂ����Ȃ��B
�i�N�\�X���t�ȑS�W�A�ŋ߁A�₽��ƒ��ÂŌ��|����B
�������ʂɂł����B
���[�Y���[�X�Ř^�����n�C�h���̌����Ȃ̘^��Ȃ����͂��Ă���Ȃ��̂�
�s���I�h�y��ł�邯��
�n�C�h�������̓��_���y���
��������Ă�ˁB
�s���I�h�y��ł��^�����Ăق���
�s�A�m�g���I�łł�����ꖇ���������͂�����
�s�A�m�����t�H���e�s�A�m�g�p����
���y��̓��_���d�l�������B
�ςȊ����B
���t�Ҏ��悾�Ƃ͎v����
�i�N�\�X�ĉ��ցA���f�����b�g�[�Ƃ�
���Ƃ������N�͔��������ӂ��Ɍ��邪
�n�C�h���͂��ꂾ�ƃC�}�C�`�����낭�Ȃ��B
���[�Y���[�X/�J�y���C�X�g���|���^�[�i��X�����@�[�N/�X�����@�L�A�������݂����ɉ��肭���Ȃ̂͑ʖڂ���
�ނ���E�B�[���t�B��������͕̂@�ɂ�
���}���h�̂悤�ȃs���~�b�h�`��
�����Ղ肵�����y��Q���S�ł��Ƃ̓o�b�N�O�����h�݂����ȉ����B
���̎��_�Ńn�C�h���𗝉��ł��ĂȂ���
���Ďv���Ă��܂��B
�A�[�m���A�w�{�[�����Ƃ�����������肾���ǁA�����͌v�Z����Ă��Đ����ˁB
�E�B�[���t�B���̋������n�C�h���ƍ���Ȃ����炩����
94�u�����v101�u���v�v83�u�����v
82�u�F�v96�u��ցv100�ԁu�R���v
44�u�߂��݁v88�u�u���v104�u�����h���v
45�u���ʁv48�u�}���A�E�e���W�A�v102
85�u���܁v92�u�I�b�N�X�t�H�[�h�v103�u���ۘA�Łv
���ē��ɗL���Ŕ�r�����^���̑����Ȃ��肾����Ȃ�����ʉ��ɕ���������
�j�b�N�l�[���̗L���Ńn�C�h���̌����Ȃ�I�Ԃ̂�
�Q�O���I�ŏI���ɂ���B
�x�[�g�[���F����7�Ԃ͑�ςɐl�C�̂���ȂɂȂ���
�n�C�h�����Ԃ��Ȃ������Ȃ�͂�
20���I���ƁA7�Ԃ͂����ȂȂ̂Ƀj�b�N�l�[���������̂͂��������A
�V�����l���ĕt���悤�ȂǂƂ����������������͂�
����ȃj�b�N�l�[�����肫�A�݂����Ȃ��ƌ����l�͂�����ł����̂ł͂Ȃ���
���X�ɂł͂��邪�ω��͂��Ă���
�i�N�\�X�̃n�C�h���^���̈�ԍŏ��ɂȂ�T���Ƃ������ƂŎ���t���₷�����ȃj�b�N�l�[���t�����W�߂��낤����
�܂��z�����M���Ƃ����E�p�b�V�I�[�l�Ƃ����������̂ɂ��肰�Ȃ�102�Ԃ�I��œ���Ă�̖ʔ�����
�u�c�������ȁv�Ȃǂ͒��������藒������̕W�艹�y������
�n�C�h���̃j�b�N�l�[���̒��ɂ́u���v�v�u�R���v�̂悤��
�W��ɉߓx�Ȋ��҂������Ē������ꍇ��
�r�M�i�[�Ȃ���҂𗠐�ꂽ�Ǝv���l�������܂����H
����Ɂu���̈ڂ낢�v�Ƃ��ȂƊW����̂��Ȃ��̂��Ӗ��s���Ȃ��̂��炠�邵
�uV���v�ɉ������҂���Ƃ����̂��A������ăj�b�N�l�[����Ȃ��Ƃ�����
�t���ĂȂ��ꍇ���炠�邗
�u���̈ڂ낢�v�́A�ɏ��y�͂ŏI�~�`���o�Ă��Ȃ��Ƃ��납�痈�Ă�ƕ�����
��ԍD���Ȏw���҂������̂ɁB
���������A�v�����B���̃n�C�h�����������Ƃ���B
����͗ǂ����̂�
�Ǔ��ŋv���Ԃ�ɒ�����
�n�C�h���ƃx�g�����͍D���ɂȂ�Ȃ��B
���c��`���C�R�͑f���炵���Ǝv���B
���̎w���҂̉��y���ƍ����Ă鉹�y�Ƃ����łȂ����y��������
������܂����Ǝv���ȁB�����łȂ���o�P��������B�@�Ǔ��c
�u���̈ڂ낢�v�̓p�[�g���𑩂˂��т�
�������܂�Ă����Ƃ������e����̊i���炵�����A
�n�C�h���{�l�ɂ����̂��ǂ����͕s����
������Ƃ����^�C�g���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��炵���B
�u���v�v�̂悤�ȓ�������̖{���̈��̂������
���炭��t���ł��낤�u�v�Ȃ�Ă�������ꂽ���̂����邩��
�Ȃ�Ƃ������Ȃ��B
�����Ȃ́A�Ȃʍ���ۂ��̂����\����B
�N���̌����ȂƔ�ׂČ����Ă��
�v���g�^�C�v�I�Ȍ����Ȃ̑��݂͂���Ƃ��Ă�
��Ƀ��x���W���Ă�������Ƃ����\���̋ȂɎd�グ�Ă邵�B
���������Ԃ������č�Ȃ��ꂽ�㐢�̌����ȂƂ͈Ⴄ�B
���S�I���W�i���ȍ�Ȃ����Ă����Ƃ���
�؋��Ƃ����Ă�������Ȃ���
�J�y�R���^���t�L�� ��CD
�n�C�h���F�����ȑ�31��, ��72�ԁ@���ˁB
��72�Ȃ�ăg���`���J���Ȕԍ����ӂ��Ă��邪
���R�P�z�����V�O�i�����ق�̏����O�̍�Ȃ��B
���ɂ��������������݂��ςݏd�˂���
�n�C�h���̌����Ȃ͌��z���̂悤�ɍ\�z����Ă������B
�z�O�E�b�h�̌����ȏW�̏��o�J�o�[�f�U�C����
���z�}�ʂ��g���Ă�̂͂�������������\�����Ă��Ȃ����Ɓc�B
����Ƒʍ�Ƃ��C�R�[���ɑ����Ȃ��ŗ~�����B
����Ɍ��߂�Ȃ�
������A�����肪���m������d���Ȃ��B
CD����������Ȃ�łˁB
20���I�̉��t�ƒB������
�z�[�{�[�P���̂�����d�����B
>��ɍ��ꂽ���̂̕��������x�����Ƃ����v������
����Ȃ�ɒ�������ł�����肾���A
�U�������͔�����łĂ���C�͂��邪�Ȃ��c
����ώv�����݂Ȃ̂��ȁ@�@
�����i�ɐl�C���W������͓̂�����O����
�n�C�h���͏����A�G�X�e���n�[�U���A
�t���[�ɂȂ��Ă���Ƃ��ꂼ���
��������B
���̍�ȉƂ���̕�����
���}�C���h�Ɋ����x�����������邩������Ȃ���
�G�L�Z���g���b�N�Ȃ܂łɃI���W�i���e�B�Ȃ̂̓n�C�h�����^��p�b�N����Ă�
�G�X�e���n�[�U�����낤�B
�ォ�痈�郂�c�A�x�g�ɂ͋y�Ȃ�
���݂ɂȂ�B
���ꂪ20���I�����܂ł̕]���Ƃ������Ƃ���܂����B
�U�������Z�b�g����Ԉ����|����₷�������A���Ă��Ƃł́H
�����������Ƃ����_���A���₷���Ȃ������Ƃ����邩������Ȃ��B
���@�C���Ղł���#46�̓I�N�^�[�u����
����Ă��ĈӊO�������B
���������O����ǂ�ŁB
�ʍ���ۂ��ɑ��ăv���g�^�C�v�I��
�����Ă邾���B
�n�C�h�������Ȃ̎������ł������Ƃ���
�w�҂�����B
�������Ƃ����w�҂ɂ����ӂł��Ȃ�
�Ƃɂ����G�X�e���n�[�U����
�Ƒn�I�ł��邱�ƂɊԈႢ�Ȃ���
�����Ȃ炴��Ȃ����ɂ������B
�Ƒn���ƌ������t���B��Ă��
�v���
���B���@���f�B�̂Ȃ��̎��݂Ƃ������Ȃ͂��������Ƃł����������̂��H
�ŏ��Ɏ������������w�҂Ƃ��́A���炭�I����肢�����������Ǝv���Ă��邩���B
�����Ă����������t��L�����Ďg���A�z�N�����^�����邵��
�I�[�P�X�g���ƈ���āA���������łɊ�������Ă������炾�낤�ȁB
�v���g�^�C�v�́u���^�v�Ƃ����Ӗ��������A �f�����X�g���[�V������Z�p�̌��A �R���y�e�B�V�����ւ̏o�i�Ȃǂ�ړI�Ƃ����ʎY�O�̎���̂��Ƃł���B
�v���g�^�C�v�́A�f�����X�g���[�V�����ړI��V�Z�p�E�V�@�\�̌��A�����A�ʎY�O�ł̖��_�̐o���̂��߂�
�v�E���g�݁E�������ꂽ���^�@�E���^��H�E�R���s���[�^�v���O�����̂��Ƃ��w���B
20/21���I�̐l�ԂɂƂ���
�N���V�b�N���y�͉ߋ��Ɋ������ꂽ���y������
������I�Ȋ��o�ɂ͓���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁB
�V���[�}���ł���n�C�h����J�߂Ă͂��Ȃ��悤��
����ʼn��ÓI�ȃu���[���X�̓n�C�h���������]������
���܂���̓n�C�h���𗝉��ł��ĂȂ��Ƃ��������Ƃ��ŁB
�����N�����^�Ńn�C�h���D���̐l���Ă���̂��ˁH
�N�����^�����c�E�x�g���݂ɒ����Ă���Ă�������̂����c
�^�������猾���Ă����������U���Z�b�g�A���y�l�d�t��������Ă���x���낤
����͉��t����łǂ��ɂ��Ȃ鍷�ł͂Ȃ��C������B
�n�C�h���D���̃N�����^�Ȃ�ĕ��ʂɂ��邾��
�U�������ƌ��l���x�̔F����
100�Ȉȏ゠��o���g���g���I�Ȃǂ�
�m��Ȃ����A���l�Ŏ������Ǝv���Ă�̂ł́H
�ŋ߂̃��R�[�h�ƊE�Ȃ�n�C�h����
���E�K�͂ʼn������炢���v�����邩
�o�Ă���̂ł́B�S�[�o�[�}���Ƃ�
�����\�[���h�A�E�g�������́B
����̗��ꂾ�ˁB
����������������#2�̖`����
#104�����h���̖`���Ǝ����悤�ȉ��`�Ȃ�ȁB
���c���ꎞ���C�o���������N�������e�B�̐�����
���J���ȂŎg�p�����̂Ɠ����悤��
���ۂ��H
�x�[�g�[���F���̌����Ȃ��U�������Z�b�g����Ƃ������Ă��鎞�_�ŁA�n�C�h���t�@������Ȃ�����A
���ƂȂ����x�[�g���F���]�����Ă�������̂ɁB
���̂��̃X���ɂ̓N�����^�����Ȃ��Ǝv���Ă�̂���
���x�[�g�[���F���̌����Ȃ��U�������Z�b�g����
���I�H��������Ȃ��́H��
�����A����ƌl�I�ȍD�݂������Ƃ͌���Ȃ��ł��傤���ǁB
���̃X���ł������h�Ǝv���B
�������U�������Z�b�g�̕����x�[�g�[���F�������D�����Ǝv���Ă��͑����h���Ǝv�����B
���̌����߂̂悤�ȎG���͂�����ł�����ł��傤��
���y���̂��̂̏㉺�Ƃ���ȉƂ̗D��Ƃ�
�_���Ă��Ȃ�ɂ��n�܂�Ȃ��Ǝv�����E�E�E
�N�����^�Ȃ玩���̍D���ȍ�ȉƂȂ艉�t�Ƃ͕��ʂ͂������H
���ꂪ�����ŋ߂̉ߑa���Ă闝�R��Ȃ��́B
�Ȃ�قǂ����ˁI
�������牽�̃��^�Ȃ���Ęb
�ÓT�h�E���}���h�̉��l�ƁA���㉹�y�̉��l�͓������Ƃ��ق����Ă�B
�x�g��c�Ɣ�ׂĐl�C�E����グ���ォ����
�����Ȃ����y�l�d�t�̂ǂ������o�����ǂ���
�Ƃ��A�n�C�h�����D���Ȑl�ɂƂ��Ă̓z���g�ɕs�����Ȃ����Ȃ���
�܂��悭�킩��Ȃ��l���猩��Ό��܂��肵�Ă�悤�Ɍ����邩������Ȃ���
����Ȏq���ȉ��Ȍ��܂�����قǃN�����^�������т��Ă�����Ă��̂���������
�܂������Ӗ��s��
�ÓT�h�̃t�@�����Č��㉹�y�قǂ���Ȃ��̂��i���
�����Ə����h������
�����Ȃɑʍ���ۂ��Ƃ��̂�����Ƃ����������݂ɑ��āA���������̓I�Șb��W�J���Ă����̂ł͂Ȃ��A�����������������ݎ��̂����������ƂȂ�Ήߑa�錴���ƂȂ�B
�E�B���h�E�K���X�ɑ傫�ȕ�����HAYDN�ƃv�����g����Ă���
������BGM�̓n�C�h���ł͂Ȃ�����
���j���[���L�x�ň������͕��ʂ�����
���͓��e���画�f����ƁA���������āu�N�����^�v���u���C�g�ȃN���V�b�N���X�i�[�v���炢�̈Ӗ��Ŏg���Ă��̂�
�����Ȃ�88�A�U�������Z�b�g���琔��
�Ȃ�Ƃ��x�X�g100�Ȃ痎�I�A���c����n�܂��Ă�ꍇ��
����Ȑ��E�Ŏ��̃N�����^�𖼏���l���Ă���̂�
�����Ƃ��邱�Ƃ�
�Ⴆ�h���e�B�S�W����I�Ȃ���Ȃ�
����Ԃ������J�b�v�������łȂ�
�����A�����A�������1�Ȃ��݂����̂������� �����B
�ނ���n�C�h���E���[�c�@���g�E�x�[�g�[���F�������{�b�P���[�j�E���@���n���E�f�B�b�^�[�X�h���t������ł��܂��̂��N�����^
13�ԁA57�ԁA90�Ԃ݂����ȃJ�b�v�����O�ŏo����y������
���̐l��CD�Ɍ�3000�~�����g���Ȃ���
���肵�悤�B
�o���̏��������Ȃ�
���c�̓o������ꖇ3000�~�B
�n�C�h����3���g���������ĂȂ���9000�~�������B
�����ǂ������B��������Ȃ���w
���Ƀz�O�E�b�h�̍����Ղ̃��c�����Ȃ͑S�ȃo�����肵�����ǃn�C�h���͈�x��
�o�����肵�Ȃ������ȁB
��N�ɂȂ��Ē����[�����o�������ǂˁB
�h���e�B�̃n�C�h�������ȑS�WCD����8����
���Ȑ�p���b�N�ɓ����Ă�
���ƂȂ��Ă͕��ʂ̃��b�N�Ɏ��܂�Ȃ��Ă����Ƃ�������
��������ł������f�����B
���āA���x�́A�V���X�^�R�[���B�`�̌��l���A
�o���g�[�N�̌��l�Ɣ�ׂĂǂ����A
��������ł݂Ȃ��ƁB
CD1�������������ĂȂ����ǁA�������ނ��߂ɂ��A
�p��̃��X�j���O���߂悤���Ǝv���Ă��B
���y�Ƃ�����������{�ɂ����ƍL�߂��Ă��A
�p��͂�������Ƃ������Q������ƁA�ŋߋC�Â����B
�l�����܂镪�����v���P�[�X
���̓g���[�̗��ɂ����[�ł��邩��6�����[�ł���^�C�v�ł�����ˁB
�S�����l���Z�b�g�Ȃ̂��A�p���͓g�Ƃ������őg�������Ⴄ����...�H
�I���W�i���pCD�S�W�i�v���X�̓h�C�c�j����
���̕������P�[�X�i�g���[�j�̂S���g���W�Z�b�g��
�{�b�N�X�ɓ��������̂������B
�L���O�̏�CD���i�p�Ղ͂X�O�N��ɂȂ��Ă���j�������悤��
�Z�b�g���e���Ƃ͎v������
���ؖؐ����b�N�Ƃ����Ɠ������Ȃ�Ȗ����Ɋ������ˁB
�J��Ԃ������I�ɏȗ����Ă邾�낤��
���̓N�����V�F���{�b�N�X�ŕ��ʂ̔��T�C�Y�Ɏ��܂鐔�ʂȂˁB
�e���}���̃��R�[�_�[��i�W���A��BOX�̔��i���Q�b�g�I�I
��BOX�̔��i����ɓ���Ƃ��ꂵ���I�I
�e���}���X�����Ȃ��̂ŁA�����ɏ������ށI�I
�B�������ʼnp��v��Ȃ��l���B
���A���������3h���炢�A�d�Ԃ̈ړ����ɕ����Ă��B
�}�b�^�����y�����悤�Ȋ��łȂ����B
�s�A�m�\�i�^�S�W�ł����߂͉�������ł��傤���H
�����Ă�������Ɗ������ł��B
Tom Beghin (NAXOS) Blu-ray audio
Christine Schornsheim (Capriccio) CD
���@���^�[�E�I���x���c
����̂�op55��71�A74�̉��t�B
op55�̓p�m�n�A71�̓`�M���A���A74�̓^�J�[�`�ŗ��������Ă��邪�A�܂����ɂ��ǂ����t�����肻�����B
>>462
�S�W�ł���I���x���c�B
�S�������[�C���D���B
�s�A�m��z�肵�č�Ȃ��Ă��̂͌����10�Ȃ��Ȃ��B
�]��l�C���Ȃ�����ǂ��A�}�b�P�C�u�̑S�W�͖O���Ȃ��Č��\�D���B
YouTube�őS��������̂ȁB
�ł�������Ɨ��\�ȉ��t���ȁB
����Ȃ�A���̉��t�̕����������ȁB
�����Ă݂����ǁA�}�b�P�C�u�����ˁB
�D�݂���B
������̈ȊO�A���オ�y���݂Ȋ������ˁB
���̂Ƃ��A�����h�[����ԍD���Ȃ��ǂˁB
����ɂ��Ă��A�ǂ���T���Ă��A�n�C�h���̃\�i�^
�S65�Ȃ𑵂����Ȃ��B
�N����������@�A�킩��l���܂��H
���l�Ȃ�A�R�_�[�C�����ő����̂ɁB
�ƂĂ����ɗD����
���A�ǂ��Ŕ������̂��L���ɂȂ��A�����ɂ������łƌ������͋C�́i����j�P�|�R���������b�c���o�Ă����B
���҂��Ȃ��ŕ����Ă݂��Ƃ���A�ӊO�Ȃ��ƂɁA�ƂĂ��ǂ������i���̂Ƃ���A�U�S�|�P�𒆐S�ɕ�����ׁj�B
���t�c�̂́ucaspar da salo�v�i�J�X�p���_�@�T���A�Ȃǁj�ƂȂ��Ă��āA���������Ƃ��Ȃ��c�̂ł��B
�������Ă��A�c�̂��̂��̂͂悭�킩�炸�A
���t�c�̂��B���ĕʖ��Ŕ���o���u�H��c�́v�炵���Ƃ����L���Ȃǂ��������i���A���̋L�����������Ă��܂����j�B
�C�ɓ����Ă��鉉�t�Ȃ̂ŁA�ǂ̂悤�Ȓc�̂Ȃ̂��m�肽���Ǝv���Ă��܂��B
���̒c�̂ɂ��āA�m���Ă����������A�����Ă�����������肪�����ł��B
PILZ�n���ł���ˁB
���̎�̊C���Ղ͌��\�D���ł����A���̘^���̉��t�͖����ɉ𖾂���ĂȂ������Ǝv���܂��B
�I�P��\���X�g���ƃX���o�L�A�A�X�����F�j�A�̉��y�Ƃ����̂̎����������ǁA�J���e�b�g�͏�w�ǂȂ��ł��B
�����̉A���肪�Ƃ��������܂��B
�܂��������Ă��Ȃ��̂ł����B
�c�O�ł����A���̉��t�͊y����ł䂱���Ǝv���܂��B
��ӂł��B
���̕s���c�̂����ǂ��Ɨǂ����t�����
https://i.imgur.com/Ut8j16r.jpg
https://i.imgur.com/3OmHCia.jpg
�t�B���n�[���j�A�E�X�����H�j�J�����
�ǂ̃o�[�W�����H
���삾�Ƃ������Ƃ͕������Ă��Ă��A�I�[���ɏ��y�͂̍\���ɁA�ǂ����Ă��r���ňӎ��������Ă��܂��B
�C�t������u�n�k�v�ɂȂ��Ă�����
�nj��y�o�[�V�����A�����y�o�[�W�����A�I���g���I�E�o�[�W����
����ɂ���ɘN�ǁi���j�̗L���̃I�v�V�����܂ł�����
������ւʓ|�Ȃ̂ŁA���܂葼�l�Ƙb���Ȃ�����
�����ł̓��[�e�B���D��ŐU���Ă����ۂ������āA
�E�B�[���ƃx�������Ő��K�^�����������悤��
��S�\�i�^�Ƒ�T�\�i�^�̊Ԃ̌��y�l�d�t�łɂ͖������������y�l�d�t�ʼn��t���Ă�
�n�[�Q���������Ĉ����������A��ɓ���ɂ�����l�i���l����ƃE���u���q�������Ă���Ί����Ĕ����K�v�͂Ȃ��������ȁB����Ɍ����n�[�Q����1994�N�f�W�^���^���Ȃ��ǁA������Ƃ�����C���̉����Ř^���̗D�ʐ����]�芴�����Ȃ��B
�W�J�����s�[�g���Ȃ����t�ő��ɗǂ����t�m���Ă���l�͂��܂��H
�����v������ł��āA���y�̗F�Ђ̖��Ȋӏ܂�ǂ�ł����Ƃ���A�������A��{�^�Վ����A
�\���˂̏��t�ɂ��āA�u����܂Ńn�C�h���́A����ȉ��y�����������Ƃ��Ȃ������v�ƌ����Ă��镶��ڂɂ����i�L���Ⴂ�łȂ���j�B
�������y��O�ɏ����Ă���̂ɁE�E�E�Ǝv�����̂����A�ǂ������Γ����ł͂Ȃ������B
�Ƃ͂����A���ɂ��Ă��S�̂̕��͋C�ɂ��Ă������ԂĂ���B
�u����ȉ��y�����������Ƃ��Ȃ������v�Ƃ����]�́A��͂菭���������������B
�ǂ��ȂȂ̂����A���A���t�������āA
���̌�ɉ��t���邱�Ƃ�O��ɍ�Ȃ���Ă��銴�����������B
���̂悤�Ȕł�I���g���I�łȂǂŕ�����
���Ȃ�������ۂ���̂�������Ȃ��B
�s�A�m���t�ł��Ɖ��y�݂̂������Ǝv��
���N�͂Ȃ����قƂ�nj������Ȃ��c
�����j���Ȃ̂�Bellotti��Salerno��2��I���K���ŕ����Ă�B
�n�C�h���̌��y�l�d�t�Ȃɕ߂���āA���W�����������������Ǝv���Ȃ�����Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ��Ă���B
�n�C�h���̌��l�̒��ŁA�Z�b�g�ł́A��i�Q�O�ƍ�i�T�O�Ɉ�����Ă���B
�X�̋Ȃł́A�D���Ȃ��͕̂ʂɂ��������邪�A��i�Q�O���i�T�O�́A�Z�b�g�S�̂ŋ�C�A
���͋C�ȂNj��ʂ̖��킢���������A���̏�ŁA�X�̋Ȃ��Ƒn�I�Ȃ̂ŁA
�������āA���ꂼ����I�ł��邱�Ƃ��D�܂������������Ă���悤�Ɋ����Ă���B
��i�Q�O�ɂ́A�̂ǂ�����i�u���z�v�̖��̂Ƃ͗����Ɂj�u�����v�̂悤�ȕ��͋C��������̂���
�i����͊����鋤�ʐ��̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ�����ǂ��j�A
�Q�O�|�P���A������Ȗ��ɕ\�����Ă���悤�Ɋ����āA�Z�b�g�̒��ł͕����������B
�������A�Q�O�|�P�́A���t�ɂ��Ⴂ���ɒ[�ɑ傫���B
���y�͖`���̌J��Ԃ����O�����A�X�^�b�J�[�g�C���ɂ��邩�A
�u���ʁv�Ɂi���邢�̓��K�[�g�C���Ɂj���t���邩�ŁA��ۂ��܂���������Ă��܂��B
�E���u���q�͑O�҂ŁA���̋ɂ̓R�_�[�C�Ǝv�����A����͉��t���Ԃ��E���u���q�̓�{�ȏ゠��
�i�R�_�[�C�́A�����n�߂����A�_�C�i�~�Y���A�e���|�Ƃ����f�̉��t�Ǝv�����̂ŁA
��i�Q�O�̒��X���[���t�ɂ͋������j�B
�R�_�[�C�قNjɒ[�ł͂Ȃ����A�����X���ɂ́A�^�[�g���C�͂��߁A���������̉��t������B
�����̍�i�Q�O�̃C���[�W����́A�Q�O�|�P�̓^�[�g���C�Ȃǂ̉��t���������߁A
���̋Ȃ����S���Ē�����^�[�g���C�𒆐S�ɕ������Ƃ������B
�������A����A�E���u���q���Ă݂āA�����͏����Ⴄ���A��������ɗǂ����t�Ǝv�����B
���̕����ŁA�����x���̉��t�͂Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂ł́B
�S�W�ł́A���ɃG���W�F���X�A�u�b�t�x���K�[���Ă݂��B�G���W�F���X�́A����Ȃ�̉��t�Ȃ̂��낤���A
�����Ƀn�C�h���ƈႤ�悤�Ȋ�����@���Ȃ��B�G���W�F���X�ŕ��������n�C�h�����v�������Ȃ��B
�u�b�t�x���K�[�́A���t�̊����x�͂Ƃ������A�\���ӗ~����������
�i������O����傫�����j�ʔ�������������B�������A�t�@�[�X�g�`���C�X�ɂ͌��������B
�E���u���q�ƈႤ�����Ȃ�A���̈�Ƃ��āA�^����ʂɂ���^�[�g���C�͈����Ȃ��Ǝv�����A
�������A�ꕔ�l�y�͂ł̃��s�[�g������B���s�[�g�͎�������肾���A����͉䖝���ĕ����Ă���i�j�B
�����A�����Ȃł����������A����̃��s�[�g�͂��܂�Ȃ����A
���̎����̋Ȃ́A��ɂȂ�x��������r�I���������̂������B
���ɌÂ����t�ŁA�V���i�C�_�[�A�v���E�A���e�̍�i�Q�O���y����ł���B
�P�b�P���g�͗ǂ����t�Ǝv�������܂蕷���Ȃ��B
���̑��̐��E���t������l�́A�������ė~�����B
Op9����͂��܂�悤�����Op 64�܂ŗ����Ƃ��낾��
���j�I���S�W���^�C�����[�ɑ̊����邱�Ƃ�
�ő��ɏo���邱�Ƃł͂Ȃ����낤�B
488�����A�ꉞ�A�E����Q��op20�������Ă���B
���t���Y��Ȃ̂����A�S�̓I�ɂ������Ƃ������͋C�ƓW�J�����s�[�g�̂��߂ɂ��܂蒮���Ȃ����t�ɂȂ��Ă��܂����B
�W�J�����s�[�g�̂����Ă�op17�C33�A50�A71�A74�A76�͂�����C�ɂȂ�Ȃ����A20�A54�A55�A64�̓��s�[�g����Ƃ��ꂾ���ŕ����p�x�������Ă��܂��B�Ȃ̑���Ƃ��Ĉ�x���������Ǝv������܂����������J��Ԃ��A�Ƃ�����ۂ����邩���낤�B
���Ȃ��N���ɂ����y�̓����Ƃ������̂��낤
���Ƀn�C�h���͋U�I�n�A�U�Č��Ȃǂ��D��ł��l�Ƃ������Ƃ�
�^��������ے肵�Ă���悤�Ȃ��̂��ƁB
���Ƃ��X�e�B�[���E���C�q�̉��y���ŏ�����
�Ŋ��܂Œʂ��Ē����̂��ދ��Ɋ�����Ƃ����Ă�悤�Ȃ��̂��B
���s�[�g�ȗ���SP��LP����̎��^���Ԃ̓s���ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ�
�P�Ȃ�s������̃��s�[�g���Ȃ��ЂƂ̉��y�Ɋ������Ă��鉹�y
�̂悤�Ɍ��������Ă��邾���̍s�ׂȂ̂��B
�n�C�h���̓��[�c�@���g��x�[�g�[���F�����Z���̂ŁA
���r�[�g����Ƃ��傤�Ǘǂ������ƂȂ�A���[�c�@���g��x�[�g�[���F���ɂЂ����Ƃ�Ȃ��Ȃ�B
�Ȓ��ɃA���R�[��������݂�����
�^�����肫�̎���A���邢�͂��Ƃ��璷��ȉ��y�Ƃł�
�܂�������������ē��R���낤�ˁB
�Ȃ�ΑS�Ẵ��s�[�g�����Ȃ��Ƃǂ����낤��
��ԃJ�b�R�A��ԃJ�b�R������悤�ȍ�i�̏ꍇ
��ԃJ�b�R�̉��`�͂Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B
�܂�s���S�ȉ��t���Ⴀ��܂��Ƃ��������̘b��
�Ⴆ�X�g�R�t�X�L�[���`���C�T�̂��ǂ�������
�����߃J�b�g���ĉ��t�E�^�������悤��
���t�҂ɂ�锻�f�E�ȗ��Ƃ��������̘b�ˁB
�p�������Ȃ̂悤�ɑS���J��Ԃ����s���ƈ�ȂR�O���O��ɂȂ�ꍇ
�S�����ق������|�I�ɏ��Ȃ��Ȃ�BLP����Ƀn�C�h����c�̌����Ȃ�
���ʂłP�Ȃɂ��郌�[�x���͂قƂ�ǂȂ������Ǝv����
CD�ɂȂ��Ă����̂܂܂̊��o�Ƃ��������ł́B
�A�[�m���N�[����z�O�E�b�h�̂悤�ɂ�قǂ̎咣���Ȃ�������
�S�����ق����܂����������ނł���̂��ȁE�E�E
�[���}�C���̒~���@�Ȃ犪���Ȃ����K�v��������
�����l����f�W�^���z�M����������
���y�Y�ƂƂ��ĂȂ�P�ȁA��y�́A�R�`�S�����Ó��Ƃ������Ƃ�
�������ɖ���������̂ł́B
��̋Ȃ����x���������Ƃ��Ȃ��Ȃ��o���Ȃ����������ł́A
96�Ԃ̏����ł́A�O�̊y�͂܂ł��A���R�[�����t���Ă���B
���A����Ȃ��Ƃ��������A�ꍇ�ɂ���Ă̓u�[�C���O���ł邩������Ȃ���
���������T�[�r�X�ʂƃ��s�[�g�����W�Ƃ͎v���Ȃ��B
����Ȃ�n�C�h�������Ă�����ł�
�����̂ł́H
�킯�킩���
�Ȃ�Ȃ�
������ƃn�C�h���̕��������Ă邩���E�E�E�Ǝv�����B
���l���A�����Ȃ��A�I���g���I���A�~�T�Ȃ��A
�s�A�m�O�d�t���A��������A
���̂��炢�������Ă����Ă�������ȁB
�ǂ�ȂɍD���ȋȂł����B
���x������������ΒP���ɂ���CD�₻�̋Ȃ��ŏ�����J��Ԃ��ĕ����Ηǂ��B
�₽��Z���Ȃ�Ȃ����邪
�����̖��ŌJ��Ԃ��l������B�C�����Ȃ������ŁB
���邢�́A�x�g�̂悤�ɉ��y���̂��̂����ǂ��ꍇ�A�J��Ԃ��Ȃ��Ƌt�ɏȗ����ꂽ��������B
���c�ɂ̓I�y�������邪
���͓����̃C�^���A�I�y����i��m���
�����܂ł̂��̂łȂ������B
�R���`�F���g�̓h���O����������
��ɋ�������s�A�m�����̂��������B
�܂��o���b�N�̖��c�肪���鍠�̍�i�Ȃ��������āA�o���b�N�ƌÓT�h�̂����Ƃ��ǂ肵���Ȓ������
�u�����b�w���̃��R�[�_�[�^����
��CD���͓��{������悪��s�������B
������A. �N���t�g�̃R���`�F���g�Ɠ������炢�D���B
�m���Ɉ�Ԃ͂��������X���̋Ȃ����ǁA2�Ԃ͌ÓT�h�炵���Ȃł���B
�������A94�Ԃ�96�Ԃ́i��y�́j�̃��s�[�g�́A�I�����𖡂�����Ǝv������܂��n�܂����Ƃ��������B
�i94�́A�J�������ƃw���r�b�q�A96�Ԃ͖Y�ꂽ�j�B
�Ō�Ɍ������N���C�}�b�N�X�̗��ꂪ�����I�����̋����y�͂ł̃��s�[�g��
���ʂɕ����Ă��āA���������Ă����C�������B
�ǂ�Ȃɖʔ��������A�܂��͊����������e�ł����Ă��B
����������u���ĉ��߂Č���̂͗L�肾���ǁB
���r���X�����h���łŊm�F�������ł�#93�ȍ~
������U�������Z�b�g�̋Ȃ̍Ō�Ƀ��s�[�g�̂Ă�Ă�}�[�N�͕t���ĂȂ�
���������ȑO�̃��s�[�g�t���Ă�Ȃł�
���̒ʂ�J��Ԃ����U�����������ɕ���ČJ��Ԃ����ɏI��邩�̈Ⴂ�B
���ƃ��r���Y�����h���Z�����̊e�X�̋Ȃɂ͊y��Ґ��̈ꗗ���t���Ă���
�`�F���o���������Ă���B���_���y��I�P�ł킴�킴����Ă���l��
��������炵�Ă�Ƃ������Ƃ����B
��͂�U�������Z�b�g�̃R���T�[�g�Ńn�C�h�����e�����Ƃ���������
�����h���͑��̋Ȃł�����邱�Ƃ�z�肵�Ă�킯����
�ߔN�̓G�X�e���n�[�W�y�c�ɂ͌��Ցt�҂����Ȃ���
�t�@�S�b�g���Ɨ������p�[�g�łȂ��ʑt�ቹ�y��Ƃ����킦���Ă���
�Ƃ������ƂɂȂ��Ă�B����������ꂽ�炢���Ȃ��J��Ԃ����炢���Ȃ�
�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B
�u�I�����𖡂�����Ǝv������܂��n�܂�v
������u�U�I�~�v�̓n�C�h�����D�ގ�@�E���炩���̂����̂ЂƂB
�������ԁ��X�O�ł̓z�O�E�b�h�iCD�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��j��g���ɂ��
���C�u�{�Ԃł�
���̕����Ŕ��肪�N�����Ă���A�u�����v�̈�łł͋����Ȃ�����l��
���̃g���b�N�ɂ͓��ʂ̊Ԃ��Ă���邱�Ƃ��낤�B
���̃X���ɂX�O�Ԃ̌J��Ԃ��ɕ���������Ă���l�Ԃ͋��炭��l�����Ȃ���B
�n�C�h���̏ꍇ�A��i�ɂ���Ă�
��ɂȂ�قǂ����^�ʖڂɒ����Ă�ق���
���X�������˂��Ƃ������Ƃ��B
�n�C�h�������ƂɒN����ɂȂ��Ă��Ȃ��͂����B
��ɂȂ�̂́A�n�C�h���ł��낤�ƁA�ǂ�Ȗ���A���y�A�f�悻�̂ق��ł��낤�ƁA
�K�łȂ����s�[�g���A���ǂ��A��ɂȂ�Ƃ������Ƃ��B
�ނ���A�Ƃ��ɁA���\���̊����x�������قǁA�s�K�ȃ��s�[�g����ɂȂ邱�Ƃ������B
�p�������Ȓ��ɍŌナ�s�[�g����Ȃ�
���Ȃ��ŏI���Ȃ�������������ȁB
�����łȂ��ėǂ��Ƃ���܂�
���c�̋Ȃ̂悤�ɁA���[�c�@���g���ɂȂ߂炩�ɉ��t���悤�Ƃ��Ă鉉�t�̂ق����s���R��
�͂Ȃɂ��ȁB��قǂ��ǂ�������B
�������������t�͓��Ă��ČJ��Ԃ��ĂȂ��Ă����������ċC���������B
�ƂĂ��炢�Ƃ������Ƃɂ͓��ӁB
�N�����肭�����b�Ȃ�Ă��ĂȂ��̂���B
���o�J����B
���ăn�C�h���Ɍ��ܔ����Ă�A�z����}�V
�P�ԃJ�b�R�A�Q�ԃJ�b�R�Ƃ����m����
���y���Ă�̂��ˁ@�������B
�̎����Ȃ�������̂���
�ŋߔ������ꂽ�}�N�X�E�F���l�d�t�c��op71�͓W�J�����s�[�g���Ȃ��悤�ŁA�l�I�ɂ͊��}����B
��������Ă��Ƃ��
���Œ����ėǂ����y���ǂ������d�v�B
�ܘ_���t�Ǝ��g�����s�[�g����̕����ǂ����y���Ǝv���Ȃ炻����������B�����͊��}�͂��Ȃ����B
���ہA�����������𗘂�����Ƃ܂�Ȃ����t��������B
����A�܂�Ȃ����t�𐳂����ŌГh���Ă���Ƃ����������������B
�ǂ��Ȃ낤�ˁB
�����A��Ȏ҂����s�[�g�܂Ŏw�����Ă����̂��B
����Ƃ��Ӑ}�͈Ӑ}�ł����s�[�g�͏o�ŎЂ̈Ӑ}�������Ƃ����\���͂����ˁH
���̓_�ŕM�ʕ����d�v�������킯�ŁB
���s�[�g������ˑR�V������A�܂�Ȃ��Ȃ�
�Ȃ�Ċ����邱�ƂȂ��ȉ���
�W�J���̃��s�[�g��5�炢���ō��Ƃ��H��
�̂̋Ȃ�����I�ɍ����I�ɂƂ炦����A��邩��ɂ͂����Ƃ�����
����Ȃ���
�O�ɃJ���I�P�̃t���R�[���X���o�����̂�
�̎��╨�ꂪ���Ă����
���������f�B�𐔉��Ă邱�Ƃɕς��͂Ȃ�����
�l����A���s�[�g�͌�y�Ƃ��Ă̎��ԑт̉����ł���A���邢�͏��߂�
�����l�̂��߂ɋȂ̂��o���Ă��炤��i�̂ЂƂB
���ۂ̓��s�[�g���Ȃ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�����̕�����������s�[�g���Ă��ǂ��ł���B���炢�̂���ł���B
���邩��ˁB
�O�������Ȃ珮�X�B
CD���炢�y���ʂ�ɌJ��Ԃ��Ă�
�悩��ׂ��H
����͂���Ǝv���B
�n�C�h���̌����Ȃ̓u���b�N�i�[����̎���̍�i�ł͂Ȃ�
�o���b�N�̏�����̎���A
�܂�����ȂƂ����Ă��܂��O�̎����
���c�Ȃǂ͂���͂�...
�n�C�h���̓o���b�N�̍��ɏ����ꂽ
�����ⓖ���܂�O�ÓT�h�̊y����
��Ȃ�Ɗw���Ă�B
��1�A2�y�͂Ń��s�[�g�����ƁA���܂ő����ݓ��������f�B�[�J��Ԃ��Ă��I�Ƃ��ƂƐ�ɐi��ł���I
�Ƃ����C���ɂȂ�B
����ς��4�y�͂̃��s�[�g����߂Ă��ꂗ
SP�̍��̘^���Ȃ���^���Ԃ̊W�ŋɗ͂��ĂȂ��Ǝv����̂�
���������Â��^����I�ׂ�������B
�ŋ߂̃}�N�X�E�F��Q�͕ʂ̋Ȃ�����ł���̂œW�J���̃��s�[�g��
���ĂȂ��̂ł�
�����n�C�h���͈�ԍD�������ǂ�
�S�̓I�ɂ͈Ⴂ�������Ă��A�����I�Ɍ��\���ʂ������͋C�̉��y�ɂȂ��Ă���̂͐����c�O�ł���B
����́ASP���^���ԂȂǂ��W���Ă���H
�Жʖ�4��������ˁB
�����^�[�̓X�e���I���ɂȂ��Ă����̓��s�[�g���Ȃ��ˁB
������ˁB�Ă������ƌJ��Ԃ��Ă���Ă�ق������Ȃ��̂ł́c
>>558
�����͒������̂��̂ɈӖ���������
�n�C�h���̏ꍇ�A�n�����͏j�T��\���Ă���
�σ������̓~�T�̒��Ƃ������Ƃł�
���������̂ɑ��Ė����Ƃ����\���@���o�Ă���
�ց[����Ȃ��̂Ȃ̂��B
�~�T�̒��H���߂ĕ������B
�����Ē������L��������ړI���������̂����B
�Ⴆ�Ύ��Ɏg��ꂽ�n���e�B���O�z�����A�ޗǂ̎��W�߃z�����ł�������
�킴�킴���ɂ���Ē���ς����肵�Ȃ��悤��...
�σ������̓~�T�̒��Ƃ������Ƃł́����������u�����̈Ӗ��v�Ƃ��āu�~�T�v�Ƃ����̂��悭������Ȃ��B����́u�Ӗ��v����Ȃ��B
�Ȃ̂�>>561�͏��������������ǂ��B
�s��Ȓ� �V�����p���e�B�G�A�}�b�e�]���ˁB
��ԍŏ������b�t���̃����h�������Ȃ����Ă������ɂ͂������肭�鉉�t�B
570����̃R�����g�����ă����c�F���h���t�@�[�����Ē����Ă݂����Ȃ����B
�ȑO�A�ŏ��̑S�W��ڎw�����Ƃ����S�o�[�}�����b��ɏ��A
���������Ȃ�T�U�ԂȂǂ̍��]���R�����g�����Ċ��҂��čw�������B
痂�����ۂň����Ȃ������X������Ȃ������B
�����c�F���h���t�@�[�̕������҂ł������B
����ɂ��Ă��A�����c�F���h���t�@�[�̑��݂�m���āA�A
�h���e�B�����炭���E���Ƃ���ꑱ�������Ƃ��s�v�c�łȂ�Ȃ��B
������}�C�i�[���[�x�����Ƃ����Ă��A
�w���҂����łȂ��A�I�P�c�����҂ȂǑ������u���E���v��m���Ă����͂����B
������ł��`�B�E���M��i�̂��錻�݁A���ꂪ���炭�`���Ȃ������Ƃ́B
���̒��q�ŁA���x�́A�P�O�S�Ԉȍ~�̌����Ȃ��������ꂽ�Ƃ��_(^^)�^
����͂Ȃ����i�s�s�j�B
�A�����J�ł͎嗬�̉��N���u�z�z�̂悤�Ȃ��̂炵�����
�Ȃ̂Łu�n�C�h���n�E�X�v�̂悤�ȃ}�j�A�b�N�Ȑl�݂̂��m��
�^���������Ƃ����ˁB
���ɂ�CBS�̃S�o�[�}���̓ڍ����Ẵh���e�B������
���ƃ��[�x���I�ɂ����Ƃ������ƂȂ낤�ˁB
���ƈꉞ�A������A�AB�Ƃ�������̂̓h������i������
�P�O�V�A�P�O�W�ԂƂ������ƂȂ��E�E�E
�h���e�B�̑S�W���u���E���I�v�Ƃ������
�n�C�h���̌����ȑS�W�͂��ꂵ�������ĂȂ��I�@���炢�̔F�m�x��
�����炩�Ȏ��ゾ������ˁB
���ɂȂ��Č���z�O�E�b�h�����ċ}���Œ��~���Ȃ����
�����Ă��邤���ɂ͊������Ă��Ǝv���B
postponed�������킯�ʼn������Ă��邤���Ƀf�b�J�Ƃ̌_��I��
AAM�ɂ͋q������Ƃ����X�^���X�ɂȂ��Ă��܂����̂�
���߂Ă��ƂS�Ȏ��^���Ă����Ăق��������Ƃ��ꂪ�z���g�̒ɍ��̋ɂ�
�ƌ����ƁA�����������Ƃ����������ė���l�������Ȃ�
�ǂ������̖��ł͂Ȃ��̂̃��W�J�Z�^���}�C�N�̂悤�Ȏ������~�b�^�[���́H
�����������Ȃ�Ɖ��m�C�Y�܂ŏE�����Ⴄ�قǂɃA�b�v���x�������
�Ƃ�����ƃM���b�ƃ��x�����i����
���܂�ɂ������܂���Ȏ��^�Ȃ�ŁB
�܂������Ă��܂��܂�����
1���ɂȂ��Ă��܂����������邾�낤��
1�Z�b�g�Â�Ȏ����Ƃ���ɂƂ��Ȃ��e�[�}�ł܂Ƃ߂����߂Ă̑S�W�ɂȂ�\�肾�����B
�㔼�œg�ɂȂ�̂��������͂��B
�n�C�h�����R�[�h�j�ɂ�����
�P���ɏ��̃s���I�h�y��ɂ�鉉�t�E�^���Ȃ�Ă������Ղ�������łȂ������B
�V�V�Ԃ܂Ř^���������_�őł��茈��
�X���������ăV���[�Y�I����\���A
���U�Q���灔�V�V�͂������肳������肾�����悤����B
�P�O�����o���̂͋��炭���E���̃t�@�������
�u�[�C���O�ɉ������̂��A���̎��_�ŃV���[�Y�ĊJ���Ƃ���
�ۂ����܂������̂��c�B
BBC�̕t�^�͍ĊJ����l�q�����Ǝv�����������������̂�
�G���̂ق���ǂ�łȂ��̂Ő^���͂悭�킩��Ȃ��B
76��77�Ԃ��Đ��K��previous��������Ȃ�����
BBC�t�^��ɔ������ꂽ�C�^���A���j�o�[�T���̃��[�J�����BOX���ɂ�
�����ĂȂ������Ƃ����̂��ˁB���������Ȃ��Ƃ������A�Ȃɂ�肽�����ŁB
�W�߃s���I�h�S�̃{�[�i�X�g���b�N���Ĉ����Ȃ킯����ˁB
����AAM����h���E�N���V�J���E�v���[���[�Y�̃��[�_�[������
����
�\���X�g�̒��ł̓p�[�Z��Q�̃L���T�����E�}�b�L���g�b�V����
ecm���[�x���̃W�����E�z���E�F�C��
�c�������n�C�����Y�Ƃĉ���ŋ��ځB
����Ȃ���������
���C���� �J���b�W �I�u �~���[�W�b�N����
�Y�K�^�J�C�A�T���T��
���炵�܂����B
�@�z���E�F�C�A�}�b�L���B�o���[�C�n�C�����Y
�z�O�E�b�h�Ƃ͋��m�̒��Ƃ������Ƃ��낾�낤��
�h��ȃ\���X�g�ł͂Ȃ���������Ȃ���
���݂����܂ł̏d�ӂ��Ƃ߂Ă����Ƃ͒m��ȂȁB
�㔭�g�ɂȂ�Ǝv����
�ďC�����r���X �����h�����ˁB
���r���X�����h���̓z�[�{�[�P���̒��n�̂悤��40�`60�ԑ�̍�ȔN���
�ߔN�̃w�����łƂ͂��Ȃ���������B
���̑��ɂ��z�����ƃg�����y�b�g�̈����ɂ��Ȃ�̎咣��������B
�Ȃ��A�\�������X&���X�g���Ղ��ȉ���̓����h����������l��Dr�}�C�P�� �g�[���o�b�g�ɂ��B�y�c�̐l���Ȃǂ��ȁB
�n�C�h�����āA�ǂ������Ƃ����Ǝ����y�̐l���Ǝv��Ȃ��H
�����Ȃ��O������ǁB
����Ă�Q�[����BGM�ɂ���̂ɁA�s�A�m�Ȃƌ��l���g�����A
���l�ƌ����Ȃ��g�����Ŗ����Ă�B
�n�C�h���ɂ����ł��Ȃ����͂��l�܂��Ă�̂́A
�ǂ������Ǝv�����A�ӌ������Ăق����B
Wizardry�V�Ԃ̂ɉH�c�����Y��BGM���āA�n�C�h���̌����Ȃ������Ă������Ƃ��������B
�����͋����Ǝ��v���������ĂȂ������B
�n�C�h���ɂ��Ă̓��R�R�ȍ앗�̋ȁB
�����6�Ȃ��邤����2�ԁB
https://www.youtube.com/watch?v=p-mhgPvBOCs
�����Ȃ������y���u���[���X�I�ȉ��t�����܂�ɂ������������Ƃɂ��
���n�C�h���ɂ����ł��Ȃ����͂��l�܂��Ă�̂́A
�N�����ƌ�������
�u�J���v�̉��y�v�S�ȁ@�ł���B
�����炵�Ċ��Ƀ��g���ȃQ�[�����邢�̗͐̂V���n���̂��́B�����Ă��̉����E�ł���B
�I���W�i���̓J���v�i�Ō�͉�ꂻ���ɂȂ���̂��j�ɂ��^��
���E�B�[���́u�I�[�X�g���A�Ȋw�A�J�f�~�[�v�o�ł���
�P�O�N�O��CD���o�Ă����Ƃ́E�E�E
�u�b�N�ɏ��������J���v�e��̃J���[�ʐ^�܂ł��Ă̊�����
����̉��y�r�W�l�X�Ƃ��܂������������������n�C�h�������ꂳ�������
�Ƃ��ւ�ӁB
���������P������Ⴊ�L��������������������
����ł��A�����Ȃ��悢���t�ŕ����ƁA�����V�N�Ɋ�����B
�Ƃ���ŁA�u���[���X�I�ȉ��t�Ƃ́H
�����́A�����ς�x�g�ȍ~���Ă��āA�����Ȃ̔�d���傫���Ȃ�A
�ŏI�I�ɁA�u���[���X�𒆐S�ɕ����悤�ɂȂ����B
�������A�ǂ������̂��肸�A���c�ɖ߂��Ă݂����A���܂ЂƂ������B
���̂��炭��A�U�������Z�b�g���āi����܂ŕ����Ă����Ȃ������j���̓��e�A���l���ɋ������B
�x�g��u���[���X�̃G�b�Z���X�͂قƂ�ǂ���B�����āA���}�����ꂽ�[��������
�i�O�҂́A�ǂ����A�u����ł����A����ł����v�Ƃ����Ƃ��������������j�B
�n�C�h���́A���ł͂Ȃ��W�J���Ȃ���\�����鑤�ʂ������ȂǁA�[�݂�������Ƃ��낪�����B
�����A���ꂾ���ɁA���t����ŁA���݂ɂ������Ȃ�B
�܂��A�Ȃ̑�����u����ł����v�Ɖ����t���Ă��Ȃ��̂ŁA���R�ƕ����Ă���Ɗj�S�����Ƃ��B
�n�C�h���ɖO����A�Ƃ������A�n�C�h�����u�Ⴍ�v�]�����ꂽ����́A
��������̌����Ȃɑ�\�����i�j�A���[���A�Ƃ��e���݂₳�Ƃ����n�C�h���ɉ����t�����Ƃ��낪�傫���̂ł́B
�������A�n�C�h���́A���������v�f���L�x�����A
��������߂ăn�C�h��������A���]���邩�A�܂�Ȃ��Ƃ���Ŗ������邱�ƂɂȂ�B
�n�C�h���̍\�����A���Â����[���ȂǁA�u���[���X�ȏ�Ƀu���[���X�I�ȉ��t�����K�v�Ǝv���Ă���B
����hyperion�̃V�F���[�w���̔Ղ́A�̂�����Ƃ����d�������肿�傤�Ǘǂ��̂ł́B
�u�b�N���b�g�Ń��r���X�E�����h�����A�J�������͖������ꂪ���̃n�C�h����dignity��
�\���\�����Ă���A�݂����Ȃ��Ƃ������Ă�
���b�t���A�J�������A�o�[���X�^�C���A�}���i�[�A�h���z�V���A���@�C���A�O�b�h�}���̃n�C�h�����������Ă�]�I
�̂����肵���n�C�h�����t�₷�����肵���u���[���X���t(�m�����g����x���O�����h)���D���Ƃ����̂͂܂��Ⴄ�b������
������ĒP���ɃJ�������w���̃n�C�h�����D���Ƃ��������Ȃ̂�
����Ƃ��t�@�C�̂悤�ȃp���V����
�n�C�h��������Ȃ̂��H
�A�[�m���N�[��������dignity���Ǝv����
�ꌩ�p���V���ł������肵�Ă�t�@�C��m�����g�����������������łȂ�����������������͓̂��݂���dignity���Ȃ낤��
�U�������ł͊������Ȃ���������Ȃ���
�Ⴆ�Ύ����{�����ɂ͂��Ȃ�
����ł������������B
����͒P�Ȃ郁���f�B�̌J��Ԃ�
�ł͂Ȃ��A�����t���[�Y�ˁB
�}���A�e���W�A�̑�j�y�͂Ȃǂ�
�������蒮���Ăق����ȁB
�Q�O���I��18���I���y���������
�s���I�h��`�ȑO�ɂ͂P�X���I���̉��Î�`�҂�����
�u���[���X�Ɏ������������������Ȃ������̂ł�
�Ƃ��������̈�
CBS�̎���DG�̃E�B�[���t�B���ՂƂł͂��Ȃ�\�����@���Ⴄ�Ǝv���B
CBS����̂͂܂��Ƀu���[���X���ȋ��������ł���Ǝv���̂����B
�ǂ����낤��
19���I�I�ȕ��������ł���Ă�
�Ⴆ�J�������̃u�����f���u���O��
�Ȃǂ��A�����ƒ��������čĘ^�����Ă�����
�A�o�h�̃u�����f�����炢�ɂ͂Ȃ��������ȁB
�Ⴄ�Ǝv���B
���R�Ƃ������t���Ɓh
�ł́H
��������������
���m���̘^���⌻�ݐi�s���̑S�W��
�G���A�Z���`�����[�A�A���g�j�[�j����������
�V���|�A�́A�������ɔ��������������邯��ǂ��B
�������A�V���|�A�ɏW���n�C�h���ƃu���[���X�Ƃ́A
��������̌����ȓI�ȃn�C�h���ƁA���������d�ꂵ���ƌ�����u���[���X�́A
�ǂ�����A���܂�Ɉ�ʓI�ȁu�n�C�h���v�Ɓu�u���[���X�v�ł́B
�����́A�u���[���X���r�I�D������������ǂ��A�n�C�h���ɌX�|���Ă���͂قƂ�Ǖ����Ă��Ȃ��B
�n�C�h���͂r�x�͑S���ɓn���čD�������A�U�������̖��͂͂�͂�ˏo���Ă���B
�����u�����b�w���̎q������ĂȂ�
�Ɗ����邪�A���葱���邱�Ƃ�
�Ӌ`������Ǝv���B
�^�����ꂽ���t�͕ς��Ȃ���
�����l�̊������͂��ꂼ��Ⴄ��
�܂��ڂ낢�䂭����
�s���I�h�y��̃n�C�h����[�c�@���g�͍D���Ȃ��ǂˁB
�������������o�J���ۂ����ǁB
���[�O�i�[�Ƃ��n�C�h���̐��y��i�͑f���炵���̂ɁB
�Ȃ�Ń��[�c�@���g�̑�\�숵���Ȃ̂����킩��Ȃ��B
�Ƃ���ŁAFF7�̃����C�N�Ŕ����l����H
���쓖�����Z������������A���������Ĕ������������肷��B
�������炢�̃q�b�g��Q�[��������āA
����Ƀn�C�h���̋Ȃ��g���Ƃ�����]�������́A
�ŋ߂̃Q�[���̌����̂��߂ɂ��A���������ǂ��������Ă�B
���Ȃ݂ɁAFF7�ł́A�`���C�R�t�X�L�[�̂���݊���l�`�̋Ȃ��A
�Y�z�̒��̋ȂƂ��āA���̂܂g���Ă����B
�n�C�h���̋Ȃ́A�s�A�m�\�i�^���A�V���B���C�[�[�V�����Ƃ����Q�[����
�g���Ă��肵�����ǁA���͂����ƁA��X�I�ɁACD10�������炢�A
�Q�[�����Ŏg�������B�������A�n�C�h���̖��͕����邯�ǂȁB
�N���V�b�N���Ă����ŁA������������邩�����B
�O�̃��X�Ń��[�c�@���g�̖����o�Ă��邩��A��������ċ}�Ƀ��[�c�@���g�̘b���������Ȃ����̂��H
�{�P�V�l�͑����Ԃ̖Ƌ��Ԕ[���Ă����I
�I�[�{�G��z�����ȂNJNJy��ɂ�
�܂�ŗ����̂Ȃ����m�ȃv���O���~���O
���_���y��Ȃ�O���ɏt�ՁA�㔼�}�[���[��邭�炢�̖������Ղ�B
���_���Ō��y��o�g�̎w���҂Ă�������H
�܂Ƃ��Ȃ�O�����y���t�A�㔼������1�Ȃ���ȁB
����ȂƂ���ɌÓT�h�����Ȃ�
�Â��Ⴍ���Ă��������̂���..
����
���͂����������Ƃ���Ȃ��ˁB
�G�X�e���n�[�U�ɂ̓g�����y�b�^�[��
���Ȃ������̂ő���Ƀz�������₽��
�������Ńt�@���t�@�[���𐁂������
�Ȃ�����B
���_�����b�p�Ȃ�ȒP�ɐ����鉹�悾��
�i�`�������Ȃ�1�I�N�^�[�u�オ��̂�
��͂�u�����f���u���O#2�݂����ȉ���ɂȂ�̂œ������ƁB
�v���Ƃ����ǃ��C�u�ō�������
���x��100%���Ă�Ȃ�Ă��Ԃy��̐l�Ԃ�S�Ȃ��w���҂ɂ�
�����o���Ȃ������낤�B
�Ȃ܂�����𑵂��Ă�ΐ����ĂȂ��
����̂ȁB
���b�Z���f�[�r�X�̌Êy��łɂȂ��Ă��܂��̂��ȁB
���b�Z���̑S�W���āA�A�}�]���̃��r���[�Ő�^����Ă͂��邯�ǂˁB
�e�n�ł̉��t��ł悩�������
CD�ɂ��Ă��Ǝv����
����ł��n�C�h���͓�����n�Y��������
���炭���c��x�g�ɔ�ׂĉ��t���
�Ƃ肠���������Ȃ������̂��Ȃ���
�v���B
�m�����{�ɂ͎����Ă��ĂȂ������悤�ȁB
�R���T�[�g�����̂܂�CD�ɂ���`���͑f�l���ۂ����B
�G���Ɍ��������Ƃł͂Ȃ���
���͐̂ƈ���ĉ��t�Ƃ̃��x���������̂ł���Ȃ�Ɍ`�ɂ͂Ȃ邪
�����Ƃ܂ł͂����ĂȂ������ĂȂ����t�������Ȃ邾���ł́B
�s���I�h�ɗ����������w���҂��琬���邽�߂ɂ�
�G���͑t�҂ɓO���ĕʂɎw���҂����Ă������y�c�̂��߂��Ǝv����
�ł���Q�l���炢��ւł�邤���ɂ͖������o��Ƃ�������
�O�ɂ������������̃u�����b�w���ł���O���Ă��܂��̂��n�C�h����
����Ƃ���B�G����������킩���Ă�̂��ǂ����B
���������ɋl�߂܂����ď������Ă���悤��
�Ƃ��郌�R�[�h���[�x���̂���
�ѐX�̃n�C�h���͌��Ǔ`���I�ȃ��_���I�[�P�X�g���ɂ��n�C�h���̏Ă������ɕ�������B
�ǂ�������Œ�������ۂł͂ˁB
����I�ɐ����̍����Êy�퉉�t�̃n�C�h����������Ƃ����Ӗ��ł�OLC�͓��{�B��B
�Ȃ��Ȃ������ɋM�d���������邾�낤�B
���{�l�̓��_���I�[�P�X�g���̋ώ��I�ȉ��I�������D��������i���y��������l�قǂ����Ȃ�j�A
�Êy��͍��t���Ȃ��̂��낤���B
��؉떾�̃o�b�n�E�R���M�E���E �W���p��
��؏G���̃I�[�P�X�g���E���x���E�N���V�J
�������t�̃R���M�E���E���W�N���E�e���}��
���_�˗��̃��E�{���A�[�h
�Ԉ�N�Y�̃R���g���|���g
�ێR��̃��E���W�J�E�R�b���[�i
���̂ւ�
���l�T���X�̒c�̂Ȃ�����Ƃ���悤�ȁB�܂��������Ă邩�ǂ����m���
�܂����������͎̂d���Ȃ��̂���
�R���T�[�g�łȂ����R�[�h���S�̉��y�t�@���̒��ɂ́A���̔ɂ����邪
�R�A�S�O�N�O�̘^�������܂��ɃX�^���_�[�h���t���Ǝv���Ă�l�����Ȃ��Ȃ��̂�����
�n�C�h�����ăU�������Z�b�g�̍��͂܂�����
���E�����͂܂��ʑt�ቹ�̎����
�n�C�h�����Ⴂ�{�b�P���[�j�Ȃ͋Ȃɂ���ăo���b�N��������Ă�B
���A���T���u���̃��E�^���u���Ƃ�
�o�[�[�������̃g�b�v�͓��{�l�����������肷�邵
���{�ł����b���������Ă��Ƃ��Ǝv����B
>>629
�R���M�E���E���W�N���E�e���}�� ����
�T�C�����E�X�^���f�[�W���q�������Ƃ��낾�����H
���{�e���}������Ȃ�Ƃ��������悤�ȁE�E�E
�^�u��g�D�[���̂悤�ȃ��l�T���X�o���h�̓P���g�Ƃ�
�������y�̒��Ԃɂ���Ă��Ȃ�
������R�e�b�R�e�̃N���V�b�N�t�@����̃^�C�v�̉��t�Ƃɂ�
���c��x�g�قǂǂ��Ղ�S���ł��Ȃ������������ē��R��
�n�C�h�����P�Ȃ����^�����Ă邯��
Franui�͊�{�I�ɉ̂��̂��ꖖ�o���h�ł��Ƃ������R���Z�v�g�₵��
�D�������̖��łȂ�
��������ׂ��Ɖp�ˋ��炷�鑤�������Ȃ���
���̂悤�ɂ����炽�Ȃ��B
�Ƃ�킯������������n�߂�o�C�I�����ƃs�A�m�ɂ����Ă�
�Êy��Ƃَ͈��Ȃ��̂Ȃ�ł��傤�B�s�b�`����Ⴄ�̂�����
�����͐��m�̃N���V�b�N���y�Ɠ��{�̓`���|�\�ƈႤ�Ƃ���ł�����킯��
���������t���x���Ȃ�J�������̉��t����Ԕ��ꂽ���̂�����
������ӂ�{�Ɩ{���݂����ȃC���[�W�Ŕ��荞�߂�
�����������t�������h�ȂȂƂ܂�߂��ނ��Ƃ����Ăł��悤�B
�������炢�̔N��̐l�����Ȃ낤�ȁH
�܂�60�ȏ�H
�݂�Ȃ�������Đl���ۂ߂������Ƃ��ċ����Ă�킯����ˁH
��Ɏ��@�����������Đ��@�Ȃ�
������Ď�����ɒʗp����D�ꂽ���t���ǂ������ߋ��ɂǂ����ꂽ��
�����������肷���ˁB
�Ȃɂ���Ă͂����܂ŌÂ����t���킴�킴�����ʂ��K�v������̂���
�Ƃ��v�����B
�o�b�n��BOX�̒��ň�Ԃ�����Ȃ����H
�`�F���o���ƃI���K������A�V�ƒn�قLjႤ�ȁB
�u2�̃����̂��߂̋��t�ȏW�v��
�i�|�����t�F���f�B�i���h4�������ӂƂ��������E�I���K�j�U�[�^�Ƃ����y�킪
���ꂷ�������߃o���g���p�̉��y��肳��ɉ��t���^�������Ȃ��B
�킴�킴�y���p�ӂ����N���X�g�t�E�R�����Ղ�
�������T�Ȃ����Ȃ��̂ɑS�Ș^���ɂ͂������ĂȂ��B
�J���v�ł��o�Ă��邯��
�ǂ�������Ƃ��ǂ�����]�p����Ă�Ƃ��悤�킩���B
���߂Ē����̂ɂ�����m���Ă�Ȃ�����
�Ƃ����ɔ���Ȃ��̂������B
amazon prime music�Œ�����ˁB
���ƃ��b�t�����B
���̃Z�b�g�̌����ȑ�90�ԏI�y�͂�91�ԑ��y�͂ɂȂ��Ă�̒����Ă���A�}�]���̉��y�z�M�͐M���ĂȂ���
�J�X�^�}�[�T�[�r�X�Ƀ��[���������lj��N���C���Ȃ��܂ܕ��u����Ă邵
�A���o���R���Z�v�g�̂��鉹�y���䖳���Ȃ̂ł�
�o������Ŕ����Ȃ����Ƃ����邵
�n�C�h���̈�Ԃ̌���Ƃ������ƂɂȂ��Ă�炵���B
�����݂̂�Ȃ������v���̂��ȁH
���͂����͎v��Ȃ��̂����E�E�E�B
���O�A�z�M���y�̃y�[�W�悭���Ȃ��őz���Ō����Ă邾��
�A���o������̋ȔԂ����Č��ǃA���o���Ŕ��������Ȃ��p�^�[�������肾��
�A���o���P�ʂŔ�����1500�~
�����̂��s���|�C���g�ɐ��Ȃ����Ƃ��łȂ���A���o���P�ʂōw�����Ȃ��z�͂����̃o�J
���Ă̂�������
�����͎v��Ȃ��̂Ȃ�A�ǂ��v���Ă��ł����H
�n�C�h���͂��������ɉ��y�̂��Ƃ������l���č�Ȃ����Ƃ����B
���Ƀ����f�B�Ƙa�������邾���Ȃ瑼�ɂ�����ł����邪��
�V�n�n����l�G�ɕC�G��������Ȃ̂ǂꂩ1�ȁA���y�l�d�t�Ȃ̂ǂꂩ1�ȂȂ�ĂȂ��ł���B
����Ȃ�G���f�B�[�f�C�l�d�t�̕������삾�ƌ����Ă������悤�ȋC������B
mono�����40�ԑ�����ɘ^������Ă���
�X�e���ɂȂ��ăU�������Z�b�g�ɕ��Ă��܂����̂́A���R�[�h�Y�ƂƂ��Ă̖��ȑI�Ȋ�Ƃ������̂Ɍ������������̂ł͂Ȃ�����
�ǂ̋Ȃ����삩�Ȃǃn�C�h���Ɍ��炸�D���ɂȂ�Ȃ�قǂ�
�܂������Ӗ����Ȃ����ʂÂ����B
�p���Z�b�g�E�E�E�B
�V�n�n���E�l�G��CD2���������A
�܂Ƃ܂肪�������A
�p���Z�b�g��1�Ȉ����ł�������B
���E�p�b�V���[�l�̓\�������Y/���X�g���E�A�����j�R��CD�ŏ��߂Ē����čD���ɂȂ�����
90�N��ȍ~�͌���ɕ�߂����Ƃ͎v���܂�
�Ƃ��ɓ����̃n�C�h���̉e���͍l�����
�i�����n�C�h���̓G�X�e���n�[�W�ƂɌǗ����Ă������̂́A�y���o�ł̎��R�͔F�߂Ă�����Ă�����
�t�����X�̃t�����\�����W���[�t�E�S�Z�b�N���͂��߂Ƃ��鑽���̒�����ȉƂ���^�����j
�n�C�h�����g����Ȏ��������Ȃ�
���ɂȂ��Ă��āA�ԍ�����ȏ��łȂ��̂�
���ꂪ�����B
����1�Ԃ����͍ŏ��̌����ȂƂ����L�����������炵���̂�
#37�͍�ȔN��̊ԈႢ�炵���B
�������� (���\�łȂ�)
�� �p�b�V�H�[�l�͍ŋ߃O�b�h�}���Ղ�
�O�b�Ƃ��Ă邪�B
�����A�����J��������#39�g�Z����p�b�V�H�[�l�������^����������
�n�C�h���̌����ȕ]�������Ȃ�ς���Ă����Ǝv����B
���O�����́u�R���v��u�����v��
�^�ʖڂȊ炵�Ă���Ă�
�M���O��������������邾������̂�...
�����A�R���ɂ��āA�Ȃ��炭�����v���Ă��āA�قƂ�Ǖ������A
����́A��U�������̂������������ς畷���Ă����B
�������A���N������A���t�̒�����ׂ�����Ă����āA�����ɂȂ����Ƃ���A
���t�ɂ���āA���̑��ʂȖʂ����͓I�Ɍ���Ă������Ƃɂт�����B
�����Ԃ�A�O�̖{�����A���䐽�̌����ȉ��t�����N�����̖{�ŁA
���̂Ƃ��́A�n�C�h���ȂǕ����Ă��Ȃ��Ƃ����������A
�������\�Ȃƕ]�����A���ׂẲ��t���y���݂����A�ȂǂƏ����Ă���̂����A
����قǂ��낢��ȉ��t���悤�ȋȂ��낤���ƁA�܂��������������������B
�������A��������ł݂āA�Ȃ��ݕ����܂������ς���Ă��܂����B
�Ȃ��A49�Ԃ́A�n�C�h�����n�߂�����A�n�C�h���ɂ���ȋȂ�����̂��ƃC���p�N�g�����������B
���܂ł��A�ǂ��ȂƎv���Ă��邪�B
�n�C�h���f�r���[�Ղ͂�����
#90&93�Ŏ��̎���#86&88������
�U����93���90�AV�����86�����炭�C�ɓ����Ă��܂����̂���
�܂�80�N��ŋC�����������Ă������Ƃ͂���
���̎��A�n�C�h�������Ȃ̓Z�b�g���j���[�ł���K�v�͑S���Ȃ��Ǝv�����ˁB
46�A47�A48�̎O�Ȃ������[�D����
��3�y�̓��k�G�b�g�̕s�v�c�ȃ����f�B��
�I�y�͂ł܂��o�Ă���Ƃ����B
���y�͂̎�肪�I�y�͂Ɍ���ďI���
�u�z�����M���v�̂悤�Ȍ��I�Ȋ����Ƃ͋t��
�����Ȃ��G���h���X��������B
�S�̓I�ɗ������������͋C�ɂȂ邪
�I�y�͂ő�3�y�͂̃����f�B���o�Ă���
�ςȊ����͎�܂�
�A�}�]���ŁA�A�������O�̃n�C�h���̉̋ȑS�W�������A
�V�i��5��~�o�����̂ɁA�����Ă����̂͂ڂ�ڂ�̒��Â������B
�Ȃ��A���[�c�@���g�̉̋Ȃɔ�ׂĂ��܂������������ȁB
���匾���ĕԕi���������A�����̂����ŁA�����Q���肵���B
�n�C�h��������킯�Ȃ�����
���c����Ȏ���䂦�B�����Ȃ����̘b��˂��́B
�ʔ̂��鎑�i�Ȃ����B
���𑗂�t�����Ă�����ЂƂ�������
������l������ȂƂ��ł�������
���ɂȂ�B
�q���ł��킩�郂�c�ł������Ĕ��Ȃ���
����93−99�܂ł̍�i�͎����{������p���Z�b�g���������Ǝv���B
������100-104�͋t�ɂ��܂�ʔ����Ȃ��B(104�͂܂�������)
�U�������̌㔼����Ȃ��đ薼���t���Ă��Ȃ��Ȃ������ƃv�b�V������Β����l��������Ǝv���̂����B
�Z�����ĊJ�����Ȃ��ł��邤���ɕԕi�������߂��������
�Ƃ��Ȃ낤����
����ɃU�������ȊO�̌����Ș^�������Ȃ��Ƃ���������
�U�����������Ȃ����Ɉ����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�ςȊ��Ⴂ���Ȃ��łق���
���t�����܂��������l�̎�ƈ������
�܂�Ń_���Ȏ����{������p���Z�b�g�ɓ�����
�m���������Ȃ���Ă킯����ˁB
���c�x�g�̌����Ȃɔ�ׂ��特�y���̂��̂��ǂ����������錻��ɂ͂Ȃ��B
100�ȏ�����钆����~���E���7�Ȃ�I��Ă��˂��A
�s�A�m�\�i�^�ƌ��y�l�d�t�Ȃƌ����Ȃ�
�S�b�h�n���h���B
�٘_�͔F�߂�B
�e���݂₷���j�b�N�l�[�����肪�����
����o���Ă݂��肷��l�����邩������Ȃ���
�����Ȃ������y���{�b�N�X����̓I�X�X���o���Ȃ���ȁB
���Ȃ��ɂƂ��Ă��ꂪ���܂����ȉ��t��������
���܂�����CD����x�ɉ��������킳���
�n�C�h���Ȃ�Ă��܂����I�Ǝv����
�n�C����܂ł惓�B
�K���Ƀs�b�N�����ȂŃn�C�h���ɖڊo�߂Ȃ���A�n�C�h���ɂ͉��̖��������l�ł�����Ȃ��납�B
�n�C�h���̏ꍇ�܂�������Ă�����
�Ƃ����Ȃ�1�E2�ȑI�Ԃ̂�������A
���t����ʐl���v��������Ǝv���B
�ςσn�C�h���̃C���[�W������ƓݏL�����t�������̂������B
�Ƃɂ����I�X�X����
���[�c�@���g⇄���}���h�`�B
�n�C�h��⇄�O�ÓT�h�A�o���b�N���y
���̗���͈ӎ����ė~������ȁB
���c⇄�n�C�h���̕ǂ͈ӊO�Ɍ��������B
> �n�C�h���̏ꍇ�܂�������Ă�����
> �Ƃ����Ȃ�1�E2�ȑI�Ԃ̂�������A
��ԃt�c�[�Ȃ̂́A�����A���v�AV��������B
�h���e�B�̑S�W�o��O����̃X�^���_�[�h�i���o�[�B
> ���t����ʐl���v��������Ǝv���B
������t�c�[�ɃJ�������Ƃ��o�[���X�^�C���Ƃ��ŁB
> ���c⇄�n�C�h���̕ǂ͈ӊO�Ɍ��������B
�n�C�h���ɔ�ׂă��c�͊ɏ��y�͂��ދ����ȁB
�w������ɗF�l�Ƀ��b�t���̋�������������A�ǂ��ƌ����Ă��ꂽ�B�����ɃN�����y���[�̃��c�z�������t�Ȃ�����������A������ǂ��ƌ����Ă��ꂽ�B
�n�C�h���̂ق����f���炵���B
�������Ȃ��牉�t���ȒP�ō�ȉƂƂ��Ă�
�m���x���c�����|�I��CD�������B
���ƃ��c�����Ȃ̓��k�G�b�g�y�͂��ދ�����
�����������牉�t�̂�����������Ȃ�
�^�����c�����Ƃ����e��������
�j�b�N�l�[���Ȃ���#89��90��蔲����o�Ă��Ȃ����
�����I�H
�g�X�J�j�[�j������ˁB
�n�C�h���̌����Ȃ͑S�Č���ƌ������̂̓h���e�B�����ǁA�ǂ������Ȃ�L���ǂ���ł������B
���Ɗ�Ղ����S�҂ɂ����Ȃ蒮�����Ȃ���������
���K�^���������
20���I�^�C�v�̃��_���I�P�Ȃ�p�������Ȃ܂ł��Ȃ��B
�o���X�^��v���r���̂悤�Ƀx�g�̌��l�����y���t�ł��悤�Ȋ��o�ɂȂ����
�d�S���Ⴄ���A�ǂ����Ă��������݂��Ȃ�ˁB
�X�Q��芮���x�������Ǝv���B
�����̎w���҂����グ���̂����R�ł͂Ȃ����B
�������A�\�ʓI�ȕω��ȂǁA�ꌩ���Ȃ��Ƃ���������āA
�������ɁA���S�҂ɂƂ��Ă͂Ȃ��݂ɂ����Ƃ�������邩������Ȃ��B
�ŋ߁i�ł��Ȃ����ǁj�̊��ł�
�C���|���h�[���́u�߂�ǂ�v�Ƌ��t�Ȃ��J�b�v�����O�����Q���gCD���ʔ����Ǝv�����B
�^���͊Ԑډ������߂ōD�݂���Ȃ����B
�����Ƃ��̂�DAW��AAM�̂悤��
�J���J���Ɋ��������悤�ȉ����D���ȉ�����������悤��
���[�x���E�^���͂����o�Ă��Ȃ���Ȃ�
���������Ƃ����Ȃ���
�����̎w���҂����グ�Ă邩�炻��Ȃ�̉��t�ɂԂ�������邾���̂��ƁB
�h���e�B�ł͂Ȃ����ǂ��ꂼ��̋Ȃɂ��ꂼ�ꖣ�͂�����B
���Ȃ킿�Ȃł͂Ȃ����t�̊����x�̖��Ȃ�B
�s���Ƃ��Ȃ��Ȃ����邯�ǁA����͉��t���s���Ƃ��ĂȂ��������Ǝv���B
�n�C�h���Ɍ��炸�����ȑS�Ș^���Ƃ������̂͐������
��l�̎w���ҁE�I�P�����ׂĂ̋ȂŖ��S�ł��鉉�t�E�^���Ȃ�����B
������Ƌɘ_�ł��傤�B
�m���ɁA�Ȃ��Ƃɗǂ����t�A�����̎w���ҁA�I�P�͂��ꂼ���
�U�������Z�b�g�����Ƃ��Ă��A��ȁA��ȁA����Ă���B
�n�C�h���̋Ȃ��ׂĂɖ��͂�����Ƃ����̂����ӁB
������Ƃ����āA���ׂĂ����t�̑��ɂ���Ƃ����̂͂��܂�Ɉ�ʓI�ł́B
�y������ł��A���Ȃ��ǂ����A����Ȃ�̔��f�ł�����̂͏��Ȃ��Ȃ��B
�i�������A�y���Œm���Ă��Ă��A���̃C���[�W���閼���Ƃ������̂͂��邪�j
���t�ɂ���āA�Ȃ̃A�s�[���x�Ȃǂ�����I�Ɉ���Ă��邪�A
�������A������܂��̂��Ƃ����A���t�����ł͒������Ȃ��͈͂�����B
�o�����Ƃ��Ă��A�t���x���ƃn���m���N�[���ł͓����ɂ͖�Ȃ��Ǝv�����ǁH
�ɒ[�Șb��������Ȃ�����
�Ȃ�ƂȂ��������Ă�l�A�������Ⴂ���������v�f�Ȃ�Ă����ē��R����
�ʒi�u�߂�ǂ�v1�Ȃł����t���ǂ���p���Z�b�g�łȂ��Ă��悵�ƌ�������
�Ȃ�܂����ˁH
���y�l�d�t�Ȃ̍ō��̂��̂��B
�٘_�͔F�߂Ȃ��B
���c�A�x�g�A�n�C�h���Ƃ���������
�؈Ⴂ�ɂ��肪�������B
21���I�̓n�C�h���ƃo���g�[�N��g�ނ܂łɂȂ��Ă����ȁB����͗ǂ��X���B
�n�C�h���ƃo���g�[�N
�N���V�b�N��������ĂȂ��q�ɂ����Ȃ�u���������Ė��͗����ł���Ȃ獡�������Ɛl�C��ȉƂɂȂ��Ă��c
�킩��₷�������f�B�[�����Ē��������킩��Ȃ��Ȃ��Ƃ��t�B�i�[��������オ��Ȃ��ŏI���ςȋȂ��Ƃ������Ȕ������肾������
���y�l�d�t�̘b�����c
�n�C�h���̉��y�ɂ͂��������N���V�b�N�̏��S�҂�
�嗬�i�����j�̉��y�����m��Ȃ��҂ɂ͂�����Ɖ���Ȃ����͂�����B
�Q�O���I�̂��Ɩ����ʂ����w���҂ł���i�L���ȃI�P��U���Ă�l�قǁj�肱����̂��n�C�h������
�e���}���i�܂��j�ACPE�o�b�n�i�m���j�Ƃ����l�������n�C�h�����^��������V���n���
���B���@���f�B�A��o�b�n�ƃ��[�c�@���g�Ŗ����Ȑl�͎���o���K�v�Ȃ���B
�V�i�𒍕����Ē��Â�����悤�Ȃ���i��肢��肢�j
�N���V�b�N�������Ȃ�ɂ��ꂱ�꒮���Ă����l�Ȃ�Ȃ�����
�Ǝv������Ȃ����肵��
����������łȂ��e���|��Y���������I�m�Ŋy��Ԃ̎����Ȃǂ�
�o�����X�悭���Ă鉉�t�E�^���Ȃ�y���߂�͂��B
�Q�O���I�ɂ͂܂₩���̖��ՂƂ�炪���܂�ɂ������̂ł�
�n�C�h����������̘^���Ɋ��҂����ق��������B�������ŏ����������Ȃ�
�n�C�h���͗v���ӂł�����B
���KCD������ĂȂ��T�[�R������#86&88�Ƃ�...
���r���[�Ȑ��̃{�b�N�X�ɂ��邭�炢�Ȃ�
�����Ղ����Ȃ��ԍ���o�����ǂ��ԍ�������P�i�ŏo���Ă݂�Ƃ�
�Ȃ�ł��Ȃ��낤�ˁB
���܂̓{�b�N�X�łȂ�ڂȂ�����Ȃ���
CD1���ŏo�����͂��Ȃ������Ȃ�ˁ[�̂��H
�٘_���F�߂Ȃ��B
�t�@�C�A�A���g�j�[�j�ōŒ�C���B
�Ƃ������A�S�ʂɌÓT���ĂƂɂ������s�[�g������u���H�����������������B�]���������ē������I����Ȃ�Ŏ��ԉ҂����Ă��[�̂�H�v���Ďv���Ă��܂���
https://twitter.com/daifujikura/status/1126374627557691393?s=19
(deleted an unsolicited ad)
���̑O�ɂ��̂���������t���₷���A�N���V�b�N�����Ȃ��Ă�����߂�L���Ȃ��邩�炱���̐l�C�Ȃ�ȁc
�u�g���R�}�[�`�v�Ƃ��u�A�C�l�N���C�l�����q���W�N�v�Ƃ��u�Z�����������R���v�Ƃ�
��͂������₷���������߂�悤�ȃ����f�B���C���������l�͏��Ȃ��Ȃ��ł��傤
��o�b�n�ɂ��Ă��uG���̃A���A�v�Ƃ����X�̃J���^�[�^�A
�܂�u�́v�̃������R���b�N�ȃ����f�B���C���ɖ�������A
�ō����삪�u�t�[�Z�v�ł������Ƃ��Ă����������͍̂D���ɂȂ��Ă���p
�ł��傤
�����Ŗl�̂Ȃ���Ď��_
���[�c�@���g⇄���}���h�`�B
�n�C�h��⇄�O�ÓT�h�A�o���b�N���y
�����܂����ǎv���N�����Ăق�����
�ǂ̃��C�������Ƃ����Ώォ�牺�܂ł̑S���̃p�[�g�����B������Ƒ�ς��Ȃ�
�v������u�Q��Duo�v�u�R��Trio�v�̋Ȃ��璮���Ă݂���ǂ���
���Ƀ��@�C�I�������t�Ȃ�4�Ȃ��炢����̂ɂǂ��������� ?���ĂȂ�B
�����A�T���Ă݂�Ƙ^���͂���Ȃ�̐�����̂�����w
�J���~�j���[�����ŋ�DG�Ř^���������A�Â��̓X�^���f�[�W�A�c�F�[�g�}�C���[�A�E�H���t�B�b�V�����^�����Ă���B
HMF�Ńt�H���E�f���E�S���c����Ȃ����^�����Ă邪����͒���I�ɂ܂�Ȃ��B
�S�~�Ɏ̂Ă�̂��ܑ̂Ȃ��̂Ő��������܂Ƃ��Ċ��p���邵���Ȃ����E�E�E
������c�E�x�g����Ȃ��Ă��邪�@�N���V�b�N�̒�Ԓ��̒�ԋȂ�ˁB
�ÓT�h��Vn���t�Ȃ͂��̂Ȃ��ł���ԁu���������܁v�I��������Ȃ���
�n�C�h���́u���������܁v�͑��ɂ��o���g���g���I�����邪
����̊y��Ґ��Ƃ̓s���Ń��������l�ɘ^���͂����Ə��Ȃ��Ȃ�B
����p�̐S�z���Ȃ��̂ł��������p���������B
�g�����y�b�g���t�Ȃ�������Ȃ�
�o���b�N����̋Ȃ��~�q���G���̃i�`������������𐁂�����鋦�t�Ȃɔ�ׂ�
���|�I�ɘ^������Ă���̂͌������b�p��Ώۂɍ�Ȃ���Ă���
����ɂ��̃o���u�����b�p�Ɠ�������ʼn��t�����悤��Ȃ���Ă��邩��
�����ł͂Ȃ����B
����|���h�[���������P�����炢�n�C�h���^�����Ăق����̂���
�`�F�����Ɋւ��Ă̓W���P���ςȂ�ŃC���|���łȂ�
�����Ƃ̃J�b�v�����O���ǂ����߃P���X���t���C�u���K�[�Ȃ��ǂˁc
����von der Goltz��van�𗪂���͖̂����B
�W���[�t�E�n�C�h���Ȃ�
����ɂ��Ă��r�[�o�[�͖��O������
https://de.wikipedia.org/wiki/Goltz_(Adelsgeschlecht)
�t�H���E�J������
�f�E���[���g
�t�����[�x�b�N�E�f�E�u���S�X
�ȑO�A�S���c�Ɨ����̂͂��������ƌ����Ă����l�������ȁB
�{�l��������Meer�ƃT�C�����Ă邯��
����͈Ⴄ����w
���q�e�E�t�@���E�f�A�E���[�� �́@���q�e
���[�V�[�E�t�@���E�_�[���@�̓��[�V�[
���t�@�[�X�g�ł���ȊO�̓t�@�~���[�l�[���Ƃ������ƂȂ�
���������u�E�v�����Ȃ��Ă��ǂ���
���݈ʂ̃t�H���Ȃ�f�A�S���c�ł��悢�̂ł́E�E�H
���{�l�̂��Ȃ܂����I�ł���K���Ȃ��
�x���M�[����vanden�Z�Z�ɂȂ�P�[�X������̂ŁA�J�i�\�L�ł��������u�E�v�����Ȃ��Ă��ǂ����ǂ����͂�����Ɠ���B
von der Goltz��von�������u���݈ʁv�̋L�����Ƃ�����A���Ⴀder�͉��Ȃ́H�Ƃ����^��͂����Ȃ����Ȃ�w
���N�O�A�S���c�����ȁI�Ɠ{���Ă���l����������ŁB
�Ƃ�����ꂩ�˂Ȃ������
�� �p�b�V�I�[�l�����ꂾ���܂�Ȃ�
���t���邵�B
H�����f�B�����̂Ƃ���
�A�}���f�B�[�k�E�x�C�G��C���E�|����
�������荞��ł���̂�����C����
�����̍D���Ȃ낤�B
���w�҂��ĕ��������ƂȂ��H
�����������t�ł��Ȃ��̂�
���ꂢ�����I�ƌ����Ƃ��܂苻�����Ȃ��Ă��`���Ŕ����Ă����
����ȓ��{�l�B
�u���V���g���G�̖@���v
�ŋ߂ɂȂ��ĊJ�Ⴕ���B
��́A����ȃG�r���ǂ��ɂ���́H
�N�̑S�W�����Ă�́H
����Beaux Arts Trio�̃n�C�h���̃s�A�m�O�d�t�S�W���܂����B�������͂߂��Ⴍ����C�ɓ���܂����B
���t�ҁA��Җ�킸�A�n�C�h���̃s�A�m�O�d�t�݂����ȕ��͋C�̋Ȃ͑��ɂ�����܂����H
BGM�Ƃ��Ă��������̂őS�W�̂悤�ɂ�����������Ă���̂����ꂵ���ł�
���W�J �A���^ ���p�̃e���}���W �ܖ��g
(MDG)�ō��v10CD���炢�̋C�̗�����BGM�W�ɂȂ邾�낤�B
���p�̓s���I�h�y��g�p����
���_���y�퉉�t�Ɋ��ꂽ�l�ɂ��������
������̂ł͂Ǝv��������B
�f���炵�����̂�����ȁB
�C�ɓ���Ȃ��̂́A70�Ԃ̑�4�y�͂��炢���B
���[�c�@���g�̕����������Ă���ǁA
�Ȃ��g���Ȃ���ȁB
> �C�ɓ���Ȃ��̂́A70�Ԃ̑�4�y�͂��炢���B
�G�����s���|�C���g���ȁB
�����܂����̂��悭������B
�x�[�g�[���F���̌��y�l�d�t�ȑ�7�Ԃ�
��2�y�͂̓����A�łƂ悭���Ă���B
�x�[�g�[���F���̕��́A�����s�]�������Ƃ��ėL�������A
�������A������Ƃ܂�Ȃ����邩�Ȃ��Ǝv���B
�^��������#50�͂��ƕ��ʂȋȂ��Ǝv������
#70�Ȃ�Ę^�����Ȃ����������Ō��_���邱�Ƃ��Ȃ���B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂�
�s�A�m�O�d�t�������A�s�A�m�ƌ��̑g�ݍ��킹���f�G��������ł����A���߂Ă����������Ȃ����ɂ��s�A�m���g���Ă��܂����H
���ȃ��X
�n�C�h������O��Ă��܂��܂����c
�s�A�m����Ȃ���ł����ŋߔ������u�N�X�e�t�[�f�̃g���I�\�i�^��i1��BGM�Ƃ��Ĉ�ԋC�ɓ����Ă܂�
https://ml.naxos.jp/sharedfiles/images/cds/hires/HMA1951746DI.jpg
�u�N�X�e�t�[�f�̓I���K���̘b����ł��̋Ȃ̏�قƂ�ǖ����A�O���[�v�������o�Ă��Ȃ����ACD��1���g�Ȃ̂ł����Ƃ������������̋Ȃ�������Ǝv���Ă��܂�
�e���}�����ƁAMAK�̃t���[�g�J���e�b�g�W���C�ɓ���܂���
�g���I�\�i�^���o����CD3�������炢�̗ʂɎ��܂��Ă܂�
�o���b�N����̎����y�͗ʓI�ɂ��ق�
�����Ȃ��Ǝv���܂��B
���B���@���f�B�̃`�F���\�i�^��CD�ɂ��ē��炢�ł����B
�قڃg���I�\�i�^����Ȏ���Ńn�C�h���̃s�A�m�g���I�͂�����ւN���łȂ����ƁB
�Ȃ�CPE�o�b�n�ɂ��ʂ͏��Ȃ��Ȃ���
�s�A�m�ʼn��t���Ă���g���I������܂��B���ꂪ��ԃn�C�h���ɋ߂�����
����w�i������܂���ˁB
�L���Ȃ̂�
�ʑt�ቹ�C�R�[���o���b�N�Ƃ������Ƃ�
�����o���b�N���y�Ɍ��Ȃ���Ă����肵�܂���
�`�F���o���̂����Ƀt�H���e�s�A�m��
�g���Ă���^��������܂��B
�n�C�h���̊��Ă��������
���}���h�̎�����A�o���b�N����O�ÓT�h���g�߂ɂ������ƌ����ėǂ����ƁB
�������c�͑����ɂ��ċt�Ƀn�C�h����
�����������Ƃ������Ƃ��Ȃ�ƂȂ�
���o���܂��ˁB
�f�B�b�^�[�X�h���t���n�C�h�����Ⴂ���ǁA�u�O�ÓT�h���E�B�[���ÓT�h�v
�݂����Ȏ����}�������ɂ��т���Ă�Ɗ��Ⴂ������
�q��肵�Ă����Ȃ�Ă�����Ə����
��o�b�n�A�x�g�A�u����3��B�ȂǂƂ���̂����t��̌���E�����������Ă������ɖ��W����Ȃ����낤
�h�C�c���y�Ȃ�3S���璮���ׂ�
���ȃ��X
���_�A�M�l�X�I�Ƀe���}���͗�O
�ׂɃn�C�h���A���[�c�@���g�Ɠ�����̉��y�Ƃ��Ē������W����������Ȃ�����B
���ƁA�h���B�G���k�Ȃ̓t�@�S�b�g�ƒʑt�ቹ�̂��߂̃\�i�^�����邵�B
��������o���b�N�͏I����āA�ÓT�h�ł��B���Ȃ�ċ��̔N��͖�������A�o���b�N��
�W�����������炭�����Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��ł���B
�����ł͕������Ă��Ă����t�l����t�@�Ȃǂ͂P�X���I���̃u���[���X�̎����
���A���݂��猩���炸���Ԃ�ƈႤ�����ł������ɈႢ�Ȃ��B
�Ƃ����_�͒��ӂ��ׂ��ł��傤�B
�s�A�m���ǂ�ǂ͂ɂȂ�ƃ`�F�����炢��Ȃ��Ȃ�B�Ƃ��B
���͂Ȃ��Ƃ�����͗���Ă���̂�����c
�Ƃ������Ƃł͂Ȃ���B�ʑt�ቹ�Ƃ��Ắ@�Ƃ�����
���ƁA���[�c�@���g�̃t�@�S�b�g�ƃ`�F���̂��߂̃\�i�^K.292�Ƃ����Ȃ����邯�ǁA���̋Ȃ͎��ۂɂ�
�t�@�S�b�g�ƒʑt�ቹ�̂��߂̃\�i�^���ˁB
���݂̏o�ŕ��ł̓t�@�S�b�g�ƃ`�F���̂��߂̃\�i�^�Ƃ����y��w��ɂȂ��Ă邯�ǁB
�n�C�h�����オ���ՂƂ����܂�
�`�F���o���������ɈႢ�Ȃ��B�n�C�h�������y��łȂ����Ղ̒B�l�������Ȃ�b�͕ʂ����B
������Ƃ����ăs�A�m�Ńn�C�h����e�����炢���Ȃ��Ƃ��A�`�F���o���ł��ׂ�
�ȂǂƂ��������Ō����Ă�킯����Ȃ��B
�n�C�h����ǂ݉��������ł͏d�v�������ƁB
���₻�̕ӂ͕ʂɊ��Ⴂ���Ȃ�����
����͂ǂ��Ȃ낤�ˁB
���͂����͌�����Ȃ��Ǝv�����ǂˁB
��̂b�o�d�̋Ȃ�����悤�ɁA�܂��A�s�A�m�ƃ`�F���o�������݂��Ă����������Ǝv����B
�m���Ɍ��݂̃s���I�h�y�퉉�t�̓��c�ӔN�̋Ȃ̓t�H���e�s�A�m���g�p����Ă��邩��A
�u�s�A�m���`�F���o���Ɏ���đ��Ă����v�Ɗ��Ⴂ����̂��d���Ȃ����B
�����`�F���o�����X�ɏ�����
���̊y��ƍ��t����Ȃ�Ė�������ˁB
��l�łԂԂ����Ȃ���e������
�������肷��̂ɂ͑ł��Ă��B
���݂Ƃ������Ƃ͗����Ƃ��g���킯���ꂽ�Ƃ������A����͔p��Ă����ߒ��ɂ������Ƃ���������
CPE�̋Ȃ͌��Ղ������ڐ���
�H�Ȉ������ł�
���ꂩ��A1788�N�ɂ́u�N�����B�[�A�E�\�i�^����Ȃ��邽�߂Ƀs�A�m��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v�ƁA
�n�C�h���͎莆�ɏ����Ă���B
�����āA�V�����c�̃s�A�m���w�������������B
����ȊO�̍�ȉƂ̌��Պy����Ȃ̏o�ŕ��Ȃł��s�A�m�ł��`�F���o���ł����t�\�Ȃ�ċL�ڂ���Ă���Ⴊ�����݂������ˁB
���̂��Ƃ�����ƒ�i�������M�����������̂Łj�ł̓s�A�m�ƃ`�F���o�������݂��Ă����Ƃ���̂͐M�҂傤���������ł��ˁB
50������������H50��͂Ȃ��ł���B
�N���X�g�t�H���̂悤�Ƀt�H���e�s�A�m���̂��̂͂����ƑO���炠�����炵���̂�
�N�������e�B�̕��̓`�F���o�������C���Ŗw�ǃs�A�m��e�������Ƃ����������Ƃ����d�v�ȗ��b�B
���ꂾ�����̓����̃s�A�m�͋M�d�Ȋy�킾�������Ƃ��f����B
�N���u�T���卑�̂��t�����X�ł̓G���[�����o�Ă���܂ʼn��y���ǂ����ڂ������A�Ƃ�
�����h���ł�JC�o�b�n���X�N�G�A�s�A�m��e�����Ƃ��A
�E�C�[�����A�N�V�������ǂ�����ȂǁA�A
�ɂ��Ă��A
���y�j�I�ɕK�{�y�킾�����`�F���o�����猩����A���Ƒ������y�����y�킶��Ȃ��낤���B
��������ł��邱�Ƃ͍��̃s�A�m�ł��������Ƃ�
�`�F���o�����܂������������̂Ȃ�A�Êy���t�ł��`�F���o���ł����Ǝv�����B
�t�H���e�s�A�m�̉��F����邭�Ȃ����ǂˁB
�U�����������ȂX�W��4�y�͂̍Ō�߂��̓Ƒt�y���
�`�F���o�����w�肳��Ă���A�s�A�m�ł������̂�
�킴�킴�`�F���o����p�ӂ���B
���ۂ̃U�������R���T�[�g�ł̓t�H���e�s�A�m��
�p�ӂ���Ă����Ƃ����f�[�^���܂��āA���̎���₻�̌�ɍ�Ȃ��ꂽ�Ȃł�
�t�H���e�s�A�m��p�����肷�邪�A����͉��t�҂̔��f�ɂ��B
���݂Ƀ��C�E�O�b�h�}����hyperion�����Ș^���ł͒ʑt�ቹ�̊y��Ƃ��ā��X�Q�܂ł��`�F���o���A
���X�R�ȍ~�Ƃ����Ă�CD�Q�������������P�W���I���̃u���[�h�E�b�h�E�s�A�m���g�p���Ă�B
���ꂪ�܂����t�ɂقǗǂ��A�N�Z���g�������Ă���B
�ƒ�ł̉��y�ƍ�ȉƂ��͂���ꂽ�ł��낤�Ȃ̃R���T�[�g�Ɠ���ɂ͌��Ȃ�����B
�ł��V�n�n����1798�N�̋Ȃł���B�������ɂ��̍��͌��X�`�F���o�����������悤�ȗT���ȉƒ�₨���~�A�ꏊ�ł�
�قƂ�ǃs�A�m�����y���Ă����Ǝv�����ǂˁB
��������1798�N��15�N���炢�O�ƈꏏ�����炢�����B
>>775�Ƀn�C�h����1788�N�Ƀs�A�m���w�������Ƃ��邪�A�ƒ뉹�y�ł�1790�N�O��Ń`�F���o���ƃs�A�m�̍��݂̎��ォ��
�s�A�m�̕����D���ɂȂ��Ă������ƌl�I�ɂ͎v���B
�`�F���o�����������ƒ�₨���~�ł��ŋ߂̐V�Ȃ̓s�A�m��z�肵���ȂɂȂ��Ă������玩�R�Ƀs�A�m��e���݂����ȃC���[�W���ȁB
���オ���܂�����Ȃ��y��
���l�T���X���̃N�����z�����Ƃ��V���[���̂悤�ȃ_�u�����[�h�y��
�͂Ƃ����ɓ�������Ă������
�����Ċy��͂ǂ�ǂ�傫�ȉ����o��悤�ɉ��ǂ���
�I�P�̌��y��͑�������Ă䂭�Ɓ@�ǂ������悩�͂Ƃ��������y���ς���Ă䂭��
mono�Ղ���X�e���I�Ղɐ�ւ���킯����Ȃ��킯��
5�`15�N�̃^�C�����O�ȂǂȂ��ɓ�����
�Ƃ����I�[�_�[���������؋���
����܂ł͉��悷�Ȃ킿���Ր����N���A
�ł���Ίy��͔C�ӂł悵
�̐��E��������H
���ÂŔ���������i�������B
����Ȃ������Ƃ�����ȁB�����ɋL�O�������B
1788�N�Ƃ����̂͂��傤�ǂ��̍�����܂Ƃ��Ȑ��x�̃s�A�m�����ʂ��n�߂��Ƃ������Ƃ��낤�B
����܂ł͂������������ł����x�̈����e���Ȍ��Պy������܂Ŏg�p���Ă����`�F���o���ɑ��镨�Ƃ���
�w������̂��S�O���Ă����l���������낤���B
�����݂̂Ȃ�����������Ă���Ƃ͎v�����A�s�A�m�ƌ����y��͊��Ƀo�b�n�̔ӔN�ɂ͂������킯�����A
���̍����炵�炭���\�N�͌��݉�X��CD�^���Ŏ��ɂ���t�H���e�s�A�m�Ɠ����̐��x�̊y��ł͖w�ǂ��Ȃ�������B
�����A���[�c�@���g��n�C�h���̃t�H���e�s�A�m���t�Ŏg�p����Ă���t�H���e�s�A�m�͂܂���1780�N��㔼����
����ȍ~�̃s�A�m�̕����y�킪�w�ǂ����B
�����������Œ��ڂ��ׂ��_��
���c��1780�N��O���Ƀs�A�m���}�X�^�[���Ă����Ƃ��������ȁB
�ꑫ����������ׂ�������̊y��������̂��̂ɂ��Ă����Ƃ����ėǂ��̂ł�
�y�펟��ʼn��y�̎��A�\�����@���ς���đR��ׂ����Ǝv���B
�v�N��1788�ɍ�Ȃ����Ƃ����͎̂����Ȃ�
���ȉƂ̎��j�V�Ƃ��ă`�F���o���ƃs�A�m�����t�Ȃɂ��Ă���������Ȃ��
�o���߂����b������
�J�U���XQ��肢���ł����H
�p���Z�b�g��肾���Ԑi�����Ă�B
�Ȃ�Ō����Ȃ���葱���Ă���Ȃ������낤�B
�l�ގj��ő�̑�������ȁB
�N�����Ă����j��ō��̍�ȉƂɂȂ����Ⴄ����ȁB
�n�C�h���Ƃ��ẮA�����Ȃ������̂���߂邱�ƂŁA
�o�b�n�E���[�c�@���g�E�x�[�g�[���F���ɁA
���̒n�ʂ��������Ƃ������ƂȂ낤�B
�������n�C�h���D���Ƃ������Ƃ����邪�A
�����ʂɂ��āA���[�c�@���g�A�x�[�g�[�x���A�u���[���X�Ȃ�
���ꂼ�ꏭ�����Ӗ����Ⴄ��
���̌�̌����ȂɁA����قǐV���͊��҂ł��Ȃ�����������B
�n�C�h���Ƃ͂�͂菭���Ⴄ�Ӗ��ŁA�V���[�x���g�́A���̌�̍�ɋ����͈�����邪�B
�U�������Z�b�g�́A�\�ʓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ�
���e�������قǑ��ʂŁA�i�����Ă���B
���̌����Ă�������A�ǂ̂悤�ȂƂ���܂ōs�������낤���B
����́A�����Ȃ��ꎩ�g����łĂ��邱�ƂŁA
�ǂ���Ȃ̂��Ɣ�r��R������悤�Ȃ܂�Ȃ����ł͂Ȃ��B
�����ɂǂ��炩�ƑΗ��I�ɂƂ炦�āA
���ʂȐ��i�̂��ꂼ����u�ǂ�����v�ƍl�����Ȃ��l�͋C�̓ł��B
���킹�ĂP���~��ŃQ�b�g���܂����B
CD�S�O�����łP���~���Ȃ�ċ��ٓI�Ȃ��������B
��߂R�S�N�O���CD�����������䂪�Ƃɗ���B
������Ȑl���̒��ʼn�������v�����̂��������̂����m��Ȃ��B
�N�C�P���ƃo���X�^�������Ă��܂����A���ɐ��E�ł�����ΏЉ�肢���܂��B
���̋Ȃ��Ă��낢�늴�z�A�]���Ȃǂ�����l���������ȃX���ŁA
����������˂ĎQ�l�ɂ��邱�Ƃ��A������ŒT������Ƃ̈�ƍl����ꂸ�A
�����t���鋷�ʂ����ǂ��l����悢�ł��傤���B
���̕��@�ł��ނ��T���܂��B
���Ȃ��̂悤�Ȑl�ɓ����Ă���ƌ����Ă���킯�ł͂���܂���B
�n�����j�[�~�T�̉��炩�̉��t�Ɋ����Đ��E�ł�����l������Ȃ�
�����Ă��炢�����Ƃ������Ƃł��B
����A�����}���K�Ȃ��ǂ��B
���͋���������ˁB
https://www.youtube.com/watch?v=RFiDuobjVfg
�s�A�m�\�i�^���s�A�m���t�Ȃ��A�s�A�m�̈����ɕs�����c��B
���[�c�@���g���x�[�g�[���F�����A�s�A�m�̈����͐_�B
�o�b�n�̓I���K���Ȃɔ�ׂāA�`�F���o���Ȃ͂��܂����B
�s�A�m���y�̋����ƐV�����āA
���ʂɃx�[�g�[���F���ƃV���p���̂��Ƃ��낤�ƁB
�I���g���I�́A�����ł��Ȃ��Ǝv�����ǁB
����́A�V�n�n�������l�G�̕�����邩��
����ȋC������̂�������Ȃ��B
�o�b�n�̃`�F���o���Ȃ��C�}�C�`���ēz���������w
�����Ɋ��S���Ă��A���y��̐l�ƌ�����ۂ͈ȑO��邪�Ȃ��B
���܂������Ă��Ƃ͂Ȃ����B
�ł��s�A�m�Œe���Ȃ��ƁA���͂��\����������Ȃ��C������B
�o�b�n�́A�d������Ɣg���������C�����āA
���ꂪ���͂�1�Ȃ낤�ȁB
�������̈ӌ��ɍ��킹���������B
����σo�b�n�̃`�F���o���ȁA��܂�Ȃ���B
�܂Ƃ��Ȋ����̐l�́A�݂�Ȃ���Ȉӌ������Ǝv�����ǂˁB
�n�C�h���ɂ��Č��Ƃ��Ńo�b�n�ɂ��Č���Ă�z����������
CD�v���C���[���d�r�����d����������ɉ~�Ղ��l�܂����������������Ƃ��āH
�ߕ���H���␅�����������Ă������Ƀn�C�h���̌����ȑS�W�������Ō�܂ŗ������Ɏ���ł����̂��낤�B
���߂Ē������̂̓w���q�F��/CPE�o�b�n�����ǂ̘^��������
����͂��Ƃ������̔������ɂ��\��Ă���B
�C�O�ł͉��t�@����Ƃ���낤��
�ȑO�A�����J�̃A�}�I�P���O�v���Łu���l���v���ȍ̂�グ�Ă�
���܂��ܒ������̂�������������������
�����ꂽ���Ƃ��ɁA���������Ă��܂��B
�܂��������Ȃ��������悤�ɂȂ낤�Ƃ́B
������A�����B
����ގU�I�I
���O�́A����t�Ɠ����������B
�_�Ɏ��ꂽ�N���V�b�N���y�ł������Ă݂���H
�����ł����������̂������炳�܂ȏ��A
���܂蓪�������킯����Ȃ��낤�ˁB
�S�R��������Ȃ�����H
�㏬��������ƂɏZ�ݒ����Ȃ�āA�����������B
�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��̂��ˁB
�ʂɂȂ��Ă�����Ă����Ȃ��́H
���}���h���班�������������Ȃ��Ă��������B
�}�[���[��R�V���g���E�X�ӂ肩��́A�������Ԉ���Ă��銴������B
�����m���Ă�l�Ԃ������Ԏ肵�Ă邾��������A
�C�ɂ��Ȃ��̂����ʁB���܂ɂ͂����������Ƃ�����B
���ꂪ�n�C�h���̌��y�l�d�t�ȁI
������������Ȃ����Ƃ����L�^���c��������
�ǂ��������܂�Ȃ������Ȃ��肾
���̕��́A
���B���@���f�B���n�C�h��
���t�ȁ�������
�ɑւ����������˂�
�[�ÓT�l���B
���̂��߂ɍ�����낤�H
���邩��ɂ͏�����Ă��炤���A���[�c�@���g��n�C�h���ł͑���Ȃ������̂��H
�^���Ƃ��c��́A�����������Ċ����B
������A���́A�x�[�g�[���F���̋Ȃ́A���ɐ���������Ǝv���B
���y�E���y�j�̉��l���A���̎���ɍ��킹�Ă�����x�l�������Ȃ���A
�N���V�b�N�𑽂��̐l���������ƂȂǂ������肦�Ȃ��B
���ЁA����̃n�C�h���ɁA�����ƕ\�ɏo�Ă��������Ȃ���B
���t���ʂ̒Nj������y���A���Ă̂��ȃC�f�I���M�[�B
�ʂɌ��Ȃ���Ⴞ�߂�
���Ȃ��������ʂԂ��Ă���悤�ɒʂԂ��Č����Ă�B
�N�����l�b�g�E�`�F���ȏォ������Ȃ��B
���킸�ɂ͂����Ȃ����炢�D���Ȃ��A����Ȏ�����
�Ɏ��I�ɕΈ����Ă�܂Ȃ��ꖇ������
���C�g�i�[�̌����ȑ�U�E�V�E�W��
�o�C�G���������@profil
���ʂقǖ������
�����Ȃ��������ĂȂ��̂ɁH
���̉��t�������
���܂��ܓ���ň����Ȃ��Ă��̂ōw�����Ă�����
�o���g���O�d�t���S�n�悭�Ė�����Ă�
�ǂ�����g�̂Ȃ��ʍ����Ȃ̂�
�ɏ��y�͂ɑ����ދ��ȕ��������邩�ȂƂ͎v���B
�G�\�̃u�����b�w�����w�����ċv���U��ɒ�������A�C�ɓ��肷���ČJ��Ԃ������Ă��܂��Ă���B
�^�����R�ł�Amazon�ł����s�\�ƌ���ꂽ�B
�N�����Â�AMAZON�Ŕ����Ă���
�܂�y��́A�l�i������������قǂ��������o����Ă��Ƃ��ȁB
https://item.rakuten.co.jp/miyaji-onlineshop/kg21-1172
https://item.rakuten.co.jp/gandg-o/aulos-moeck-0083
�R���g���o�X���R�[�_�[�Ȃ�����ƍ����Ȃ邩
https://item.rakuten.co.jp/auc-gakkidonya/5741b
�A�}�f�E�X�̃f�B�X�N������
�ډ��̈����Ղ̓N�C�P��Q��Op.76, 77
1�x�ł�������R���T�[�g�s������������
�s��������Ȃ��ł����H
�|�s�����[�̃R���T�[�g�݂����ɗ����Ē����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�łȂ��B
�ނ�H
���A�|���[�j�̃X���ƊԈႦ�Ă�
���܂�
�|���[�j�̃X���ł��̐l�������{���{�����痈�������قڂȂ����낤�Ȃ��݂����Ȃ��ƌ����Ă����
����ʼn��n���������牼�ɗ������Ă��s���Ȃ����낤�ȃ@���Ă��Ƃ�������������
�X���`�ł�R
���N��22�̑ゾ����I����I👍
Petersen quartet��CD���͂������B
�ɏ��y�͂̓}�W�ł��
�����ƃn�C�h���^�����Ăق���������
�߂���
�v���O�����㔼�́A���߂ĂS�O�����炢�̊y�Ȃ�
�K�b�c�����������C�����́A�q�Ƃ��ĕ�����
�q���̎�����LP�Ƃɂ���B
���ʂ̓��C�i�[�̃W���s�^�[�B
�������o���g�[�N�Ƒg�ݍ��킹��Ƃ����f���炵���Z���X�̃v���O���~���O
���Ă����l�����ȂI
�����ȉ��t�ōD���Ƃ������Ă����ǁB
�}���i�[�̃n�C�h����CD�ł͖��������Ȃ͂�
�ŔӔN��95&101�́A�܂Ȃ��ɂ͒����Ȃ�
�����Ɛ��ɏo�Ăق���
�E���̈ʑ����]������ƒ������ł͂��邯�NJ����������L����B
AudioDirector�ŃX�e���I�g��(�H)�݂����Ȃ̂�MAX�ɍL�����炾���Ԏ��R�ɂȂ�����B
���}���h�ƈ���ČÓT�h���āA�ꗬ�Ȃ̂���2�l�������Ȃ�����ȁB
�n�C�h���́A���y�j�ɂ����āA���d�v�ȍ�ȉƂƂ������Ƃ��ȁB
�x�[�g�[�x���̓��}���h�����Ɓc�c
�x�[�g�[���F���͓����Ɓc�c
�{��̂�������ȉƂł��Ȃ��S�g���ɕa��ł�����A
���}���h�̂͂���݂����Ȃ���
���̓_�Ńn�C�h���̓t���[�ɂȂ��Ă�������S����ÓT�h�Ƃ����Ă悩�낤
���y�̋��ȏ��Ȃ�艹�y���̂��̂��悭�����Δ��鎖�B
��o�b�n�͂��łɃo���b�N����̍�ȉƂł���
���jcpe�͑O���ÓT�h�Ƃ��Ă�
�n�C�h���Ƃقڋ߂��N��̖����qJC�͊��S�ɌÓT�h�̍앗�ł���B
�����Ĕނ�̑��q�قǂ̃��c�A����Ƀ��c�̑��q�قǂ̃x�g�ƂȂ��
����ÓT�h���邢�͏������}���h�ł���Ƃ����č����x���Ȃ����낤�B
�x�[�g�[�x��������A�V���[�x���g������B
�����������}���h�Ȃ�Ă����s���_�ɂ܂�Ȃ����莩�̎g�������Ȃ��B
�J�[���E�V���~�b�g
�n�C�h�������܂�ɂ����N�Ō��N�I�ȍ앗�Ȃ�Ŏv������������
�t�����X�����Ƃ������Ƃ��ӎ����Ă����낤��
�������٘_�͂��낤
�M�����u���ˑ��ǂɂ��؋�����ŕa�I�ȔӔN�������������c�Ƃ�
���������Ȃ��Ă䂭�Ƃ������y�ƂƂ��Đ؉H�l�܂����x�g
�ȍ~�̐��_�I�ɕa���}���h��ȉƂ̉��y��
����ɉ��t������l���Ȃ��ق������ǂ��Ǝv������B
�Y�ݑ�������l�ɂ͌��N�I�ȃn�C�h���̉��y���
��͂薾�邢�Ȃ��ɂ��ǂ����a�I�Â������悤���c�ӔN�̋Ȃ̕���
���������̂悤�������
���邳���������������邵�B
�x�[�g�[���F�����ʍ�����������肨�낷���Ƃ́A
���y�E�̉��v�̂��߂ɁA��ɕK�v�Ȃ��ƁB
�����ł��Ȃ���A
�N���V�b�N���y�E�͂����łԂ������Ǝv����B
���}�n�Ƃ�����Ƃ�������Ȃ��g�D��
�����������Ă邩����v���i�܂Ȃ���B
���{�̔N���̑�9�Ȃ�āA�I�y�͂̎�肪���������ŁA
�������Ă����Ȃł��Ȃ�����H
����ɔ�ׂāA�N�n�̃E�B�[���ł̓V�n�n���A
�N���̉��Ăł̂���݊���l�`�́A�{���ɑf���炵���ȁB
�ȋȂł��u�x�[�g�[���F��������v�Ŏ����グ�Ă邩��A
�N���V�b�N���y�E�͂����܂ŔߎS�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂�����B
�h���H���U�[�N���{���f�B�����`���C�R�t�X�L�[���O���[�O���V�x���E�X���j�[���Z�����A�b�e���x�������H�[���E�B���A���Y���v���R�t�B�G�t���V���X�^�R�[���B�`���n�`���g�D���A����
�݂�ȍD�����������̍�ȉƎ����グ�邽�߂ɂ킴�킴���̍�ȉƂ��Ȃވӌ��ɂ͓��ӂ����˂��
> �x�[�g�[���F�����ʍ�����������肨�낷���Ƃ́A
�����B
"Roll over Beethoben"
���ċȂ�����B
Beetles���Ȃ����Ȃ��������̂�N��������������H
�薼���A�[�e�B�X�g�����X�y����������
https://yamakamu.net/wp-content/uploads/2019/10/4-6.gif
����ɔ�ׂāA�l�G�͍\���������B���������Ȃ��B
�S�R�N���]���Ƃ��ł��ĂȂ�����ȁB
�N����Ă��璮���ƁA���ꂪ�C�ɂȂ�B
�u���[�c�@���g�̉��y�͎q���ɂ͂₳�����A
�@�������A��l�����ɂ͓���v
�@
�@�@�@�V���i�|�x��������������
���ꂪ���R������
��l���q���ƈႤ�悤�ɐ[�ǂ݂���
���t���������Ă�����͗e�Ղł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ����������낤�B
����n�C�h���͎��g�����y��D���Ŏd���Ȃ����Ċ���
�������͋t�Ɏq���ł͂��̉��̋Y���������邱�Ƃ͓�����낤�B
�f�B�b�^�[�X�h���t�̋Ȃ͒����₷���͂��邯�ǂ�����ƍ\�����Â����ȁ[���Ċ�����
�n�C�h���̌��y�l�d�t�ȁu�c��v��u�Ђ�v�͎q�ǂ��̍��ɒ����Ă���Ȃ����߂���
���́A���M�̃e���}����V���[�x���g�������ŁA
�x�M�̃V���p����u���[���X����F���͂ǂ������Ƃ�����
�D���Ȃ��A���炭�C�ɂȂ��B
���̎���̐l�����͊�{�I�ɂ݂�ȕM������
�N���Ɉ˗����ꂽ��i�Ȃ���ߐ�ɊԂɍ��킹�Ȃ��Ƃ����Ȃ�����Ȃ��̂���
�����烍�}���h�ȍ~�̂�������d�グ��l������z�肵�Ē����Ƃ������肷��Ǝv��
�ł��C�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͍D���ɂȂ�Ƃ����v�f������Ƃ�����
�H�킸�������������Ƃ�����
(���M���ۂ��ōD����������܂�Ƃ��Ȃ��Ȃ������[���n�D�ł����������)
��ȉƂ̕M�������낤���x���낤���A�K�b�J������悤�ȉ��y��������
�N�����Ȃ���
�l�̍D�݂⎋�_�͕ʖ��B
�N�\�����ɁA
�E���Q���[�[�B
���z�c�����H
op.51�͈�Ȃ��Ƃɔԍ��ӂ���Hob.III:50~56��7�ȕ��߂Ă���̂����
Op.9���疢���̂P�O�R���ȕ��ʁB
1922�N�A���D�A�l�}���[�E�U�C�f���ƌ����B1932�N�ɗ����B
1957�N�A�t�����c�E���[�[�t�E�n�C�h���̍�i�ژ^�������B
�n�C�h���̍�i�́A���̖ژ^�ɂ��Ȃ�Ńz�[�{�[�P���ԍ��ŌĂ�邱�Ƃ������B
�z�[�{�[�P���ɂ��n�C�h����i�ژ^�́A��i�̌`���Ɋ�Â��ĕ��ނ�����@�Ɋ�Â��Ă���A���Ƃ��Ό����Ȃ͑S�ăJ�e�S��1�Ɏ��߁A���y�l�d�t�Ȃ͑S�ăJ�e�S��3�Ɏ��߁A�s�A�m�\�i�^�͑S�ăJ�e�S��16�Ɏ��߂�Ƃ�������ł���B
���̋Ȃ����ƈ�ʔF�m�x�����Ȃ��ĂĂ����������Ȃ�����B
���ނ͂Ƃ������A�ԍ��Ɏ����Ă�
���炾���ǂقƂ�LjӖ��Ȃ����
�o�ŎЂ��X������ł��낤op.�ԍ���
�����Ȃ͓��������ȏ������ɂȂ��Ă����ԍ���
�قƂ�ǂ��̂܂g�p���Ă邭����
�Ȃ��Ă��N������Ȃ����A�ނ��덬���𗈂��Ȃ���ł͂ł�...
�����ȃo�[�W���������邩��
��ۂ����܂��Ă��ˁH
�R���b���S�W�̕����S�R�ゾ��ȁB
�ǂ��Ȃ���Ȃ��̂Ɍ��z�����Ȃ��L�����Ƃ��A
���y�E�ł́A���������t�]���ۂ��悭����B
�Ȃ�����̃n�C�h�����{�X�ɂȂ�Ȃ��̂��A
�����͂悭�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����A�ǂ��l���Ă����O�����݂��邩�炾��B
�������B���@���f�B���u�l�G�v�݂̂̍�ȉƂ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�āA�n�C�h����ދ����ƕ]����V�Q�ǂ��Ɠ������W�b�N�Ɋׂ��Ă邼
�c���ĉ������B���@���f�B����܋����Ȃ�����w
��Ȃ����ʂ͑����Ƃ͌����Ȃ���
�����x�g��h�{�������Ȃ��P�O�O�Ȉȏ��Ȃ��Ă���
�㐢�̃A�z����́u�����悤�Ȍ����Ȃ�100�ȏ����������� �v���Č�����̂��I�`
���B���@���f�B�̃}���h�������t�Ȃ͗ǂ��Ȃ���
�Ȑ����������Ă����œ����悤�Ȃ���
�ƌ��߂��邢���̂Ƃ�ł��Ȃ��B
�n�C�h���قǑn�ӍH�v�����鉹�y�Ȃ��
���肻���łȂ�
����������Ȏ������o���o���ɂ�������p�̑I�W������Α���ەς��Ǝv��
> �U�������Z�b�g������҂ɂƂ��Ă͓����`������Ɋ�������̂��}�C�i�X
��肠���H
�u���b�N�i�[�A�u���[���X�����Č`���͓����Ɏv����B
�x�[�g�[�x���A�}�[���[�A�V���X�^�R�[���B�`�͈�Ȃ��ƂɈႤ���ǁB
�O�҂̌Q����҂̌Q���}�C�i�[�Ȃ킯�ł��Ȃ��B
�����Ȃ͂������������y�Ƃ̔F���E�e����^�����̂�
�n�C�h�������Ȃ̓����̑�q�b�g�������Ȃ肠��Ƃ������ƂȂ̂ł�
�V���z�j�A���̂��̂̓��B���@���f�B�����č�Ȃ��Ă�B
����҂ɗ^�����ۂ̘b���
��������ł�n�C�h���}�j�A�ɂƂ��Ă͖��Ȃ�
�s��E�d���E�����I�A�Ђ�����������A�L���b�`�[�ȃ����f�B�A�A�A
�����������ʂƂ͕ʎ����ȒP���łȂ��y����������E�E�E�B
�l�d�t�Ȃ珉�߃f�B���F���e�B�����g�Ƃ��č�Ȃ��ꂽ�̂�
����M�������ɖ�����蕪�ނ��Ă݂��
�Ȑ��̑��������Ȃ̓p�������Ȃ������
���ɑO���̓t�H�[�}���ȉ���������y�E ���o�̓����ʂɎg����(��)�悤��
�₩�Ȃ܂���C���ȋȂ��܂�
��
�㔼�̓J�W���A���ȑ�O���y(�ɏ��y�͂łł��������o���ăn�b�Ƃ�����. �U�I�~�Ŕ�������A)�ɂȂ낤��
���[�c�@���g�̌��y�l�d�t�Ȃ͑ʍ�A
����͏펯����B
���[�c�@���g�̌����Ȃ��āA�y�������ǂǂ�������ۂ��Ċ����B
�����A�n�C�h���̃p���Z�b�g�ȍ~��23�Ȃ̌����Ȃ́A
�u���[���X��4�Ȃ�23�ȂɊg�傳�ꂽ�ꍇ�Ɠ������l������B
�܂���������́A�Ƃ�ł��Ȃ���Y�Ȃ�B
�Ȃ��w�Z�̎��ƂŕK�C�łȂ��̂��������ł��Ȃ���B
�㉺�ɂ��������Ď��삪�����̂Ɂu�����v�̂悤�Ɏ���傫�����߂���X���������
���͈ӌ��Ɏ��M���Ȃ��̂ł��������������ɂȂ�낤
��l�̈�ӌ��ȂƊJ���������ق���������
������Ă����߂������N�Y��Y�B