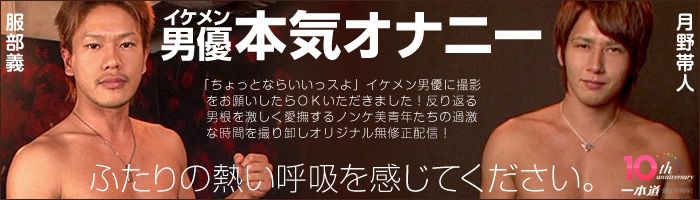�Y�@�̕��@��44
�Y�@�̕��@��43
http://kohada.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1377519587/
��(߁[�*���܁M�߁߁߁߁߁߁߁߁߁�
�P�@���ʊW
�Q�@���d��������
�R�@����
�S�@���Ƃ̏�������
�T�@���s�̒���
�U�@�����ɂ����Ď��R�ȍs��
�V�@�s�ז����l�E���ʖ����l
�W�@�s�K�́E�ٔ��K�́E���ًK��
�X�@�s�ӎv
10�@�\���v���_�`�\���v���I�̈ӂ̈ʒu�Â���������
�����ɑ��_�ɕ��Ă��邗
����ȊO�̃e�[�}�͒n��������Ȃ����A��������̂͊y������Ȃ�
�w�҂��킴�킴�Q�����܂ŗ��Ēp���炳�Ȃ��Ă�����H��
�����N�����˂���
�ԈႦ�Ă��Ă��̂��O������w
�����i�@�����ɋ��ꏊ�Ȃ��Ȃ���������ˁi�j
�Y�@�w�҂��ĕςȂ̂����������Ȃ�
����ȓz��ɕ������̂��Ǝv���Ə�Ȃ��Ȃ�
�͂�
�A�z�Ȃ���B
�u�������̂ق��v���ĉ����H
���肢������
���₵���̂�����
>>1�͐ӔC�����č폜�˗��o���Ƃ���
���{�̐^�̎x�z�҂ł��钆�����Y�}���p�~���ĂȂ����炾��
���{�����ɑI�����Ȃǂ���܂���
�������������A�j������Ƃ����x�@�Ɍ�����Ƃ���ϗL�߂ɂȂ邩�ȁH
�u�����F�e�̌Y�@�w�����v�Ɖ��߂āA��ɌY�@�w���ɂ��Ă�
������t���܂��B
�I�C���̑f���̑F���E�l�U���͌��ւł��B
���w�ҁE�㋉�҂ɂ������Ȃ���������҂����Ă��܂��B
���Ⴀ�A���ʊW�Łu�댯�̌��������v�ɗ�������ŁA
�s�\�Ƃŋ�̓I�댯���ɗ����Ƃ̘_���I�������������B
����ƁA���ʊW�̍���ł́u�댯�̌������͈͓̔��v�̕������l���邱�ƂɂȂ�́H
�̂������������₾�ȁB
�����]���Ă����ς蕪����Ȃ��B����グ���B
�t�ɋ����Ăق����B�B
�N�͓����������Ă�낤�H
�l�I�ɂ́A�댯�̌��������͍s���̔F������b�Ƃ���̂ł͂Ȃ���
�S������l�����邩��A��̓I�댯���Ƃ͐������Ȃ��ƍl���Đ����ł���B
���������ʊW�̍���́A�s���̔F������ɂ���������Ȃ��̂ŁA
���̏ꍇ�ɂǂ����������F������Ό̈ӂ�F�߂���̂����킩��Ȃ��B
���̕ӂ����܂���������l�����͂Ȃ����̂��Ǝv���āB
���_�I�ɂ́u�댯�̌��������m�肵���鎖���F��������Ό�����
���������댯�����̌o�߂ƈ�v����K�v�͂Ȃ��A�܂��A���̎����F���̒��x�Ƃ��Ă�
�댯�̌������̔��f�ɂ͋K�͓I�]�����̂ŁA��ʐl���댯�����̊W�R������������x��
�F���ő����v�Ƃ����悤�ɂȂ邩�Ǝv�����̂����ǁB�ǂ��H
���ʊW�͔����������ʂ��s�ׂɋA���ł��邩�Ƃ������
�������Ⴄ���痼������ΓI�ɐ������Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł�?
�ȑO���碋�̓I�댯�ࣂ��̂�A��S������l�������q�ϓI���������̂�_�҂͂��邵(�q)
�ɓ����ࢋ�̓I�댯�ࣂ��̂�A���ʊW�ɂ��Ắu�댯�����ʂɎ��������v���Ƃ��K�v���Ƃ��Ă�����
���ʊW�̍���ɂ��ẮA�]���̒ʐ���O��Ɍ��t��u��������Ȃ�A
�s�҂̗\���ƌ����̈��ʌo�߂Ƃ���댯�̌�������͈͓̔��ŕ������邩�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ�낤����
���ʊW�̍���͌̈ӂ�j�p���Ȃ��Ƃ������݂̑�����(?)���炷��A�����������Ƃ��l����K�v���Ȃ��낤��
(���ۂ̂Ƃ��뢊댯�̌�������I�ȍl�������̂��Ă���l�͌̈ӑj�p�ے�����̂��Ă���悤�ɂ��v������)
���ʕs�����ƌ��ʔ����ŏ�ʂ��Ⴄ���Ă������ǁA�s�\�Ƃ̏ꍇ��
�u���������댯�v�̋A���̖�肾����A�����ȒP�ɈႤ�Ƃ͌����ɂ����Ǝv���B
���ɂ����l����Ƃ��Ă��A���_�I�ɂǂ��Ⴄ�����b������قɂ���̂���
��������K�v�������ˁB
���ƁA���ʊW�̔F���s�v�����ė��_�I�ɂ͎x�����ɂ�����Ȃ��̂��ȁB
�Ȃ��A�q�ϓI�\���v���̂����̈��ʊW�����S���F���s�v�ɂȂ�̂���
���_�I�������Ȃ����Ă����̂͂����ƌ����Ă邵�A�s�v�_�҂���
��̓I�ȍ����̒��Ȃ���Ȃ��́B
�M���̉]���������Ƃ��O�C�Ȃ��猩���Ă����B�u���C�N�X���[�܂ł����ꑧ��
�������Ƃ���ł��ˁB
���ʊW�_�ƕs�\�Ƙ_�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�ܒ��I�������ʊW���Ƌ�̓I
�댯�����A�q�ϓI�������ʊW���Ƌq�ϓI�댯�����A���ꂼ��Ή����邱�Ƃ�
�ȑO����w�E����Ă����i�O�c�P�X�O�łȂǁj�B�O�҂͎��O���f�ł���A���
�͎��㔻�f�ł���B
�������u�댯�̌��������v������ł���A���A�߂������̒ʐ��ł���Ƃ���
�Ȃ�A�ܒ���vs�q�ϐ��̋c�_�͈Ӌ`�������ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���w�E��
�Ƃ���u�댯�̌��������v�͎��㔻�f�ł���A�ܒ����͋��ꏊ����������ł���B
����ł́A���̂悤�ȍl�������s�\�Ƙ_�ɂǂ��e�����邩�B�s�\�Ƃ́u�댯��
�������v�u���Ȃ������v�ꍇ�ł��邩����ʊW�_�Ƃ̑Ή��W�͂Ȃ��A�Ƃ�
�P���ɂ͉]���Ȃ��B>>31���w�E����Ƃ���A�s�\�Ƃ̏ꍇ���u���������댯�v
�̋A���̖�肾����ł���B�������A�����ł��u�댯�̌��������v�����㔻�f
�ł��邱�Ƃ��d������ƁA�q�ϓI�댯���ɌX������Ȃ��ł��낤�B���Ⴊ
�q�ϓI�댯������̓I�댯�����ɂ��Ă͎�̋c�_�����邪�A���Ȃ��Ƃ�
���̎E�l�����i�L�����ُ��a�R�U�N�V���P�O���j�ɂ͔�������Ȃ��B
�i����͒���E����Y�@�u���A�����ĎR���E�֖@�A����ɑO�c�A�O�c�Ƃ̑Βk
�ʼn���������J�j�A�x�����L���邱�Ƃ͂Ȃ������B
���݂ɁA�R���搶�̘_�͎��̂Ƃ���B
�@���ʊW�̍���̏ꍇ�A���͍���_�͖��ł͂Ȃ��A�q�ϓI�A���_�i��������
�@�W�_�j�Ŗ��͉�������B
�A�Ȃ��Ȃ�A�����E���������߂�̂͋q�ϓI�A���ł����āA���ʌo�߂̍����
�@�ꍇ�A�������ʂɑ���̈ӂ����݂��邱�Ƃ͋^�����Ȃ�����ł���B
�B�Ⴆ�A�u�M���v�̈��ʊW�ɂ��ė\��������A�̈ӂƂ��ď\���ł���B
�C�q�ϓI�ɔ����������ʌo�߂��A�q�ϓI�ɋA��������͈͓��ɂ������A�s��
�@�́A�̈ӁE�����̐ӔC���B
�ǐL
�M���̂��Ƃ͈ȑO���瑶���グ�Ă��܂���
�I�C�����m���ɗ���X���������̂ɑ��āA�M���͂��������̓��ōl����
�̂ŁA���S���Ă܂����B
���̃X���́A�����ז�������Ȃ��Ȃ����̂ŁA����Ƃ����݂����Y�I�ȋc�_
�𑱂��܂��傤�B
�܂œǂ�
>>32
>�s�\�Ƃ̏ꍇ���������댯��̋A���̖�肾����
���̕����͈����������
�s�\�Ƃ͢�댯������������Ƃ����邩�ǂ����̖��Ȃ̂ł�?
�댯�̢�A�������Ƃ���̂ł���A����͂�͂袈��ʊW��̘b���Ǝv����
(�����ʂȋc�_�ƍ������ĂȂ�?)
����>>30�̌㔼�́A����ʊW�̔F���s�v�ࣂł͂Ȃ���
����ʊW���̈ӂ̔F���Ώۣ��������ʊW�̍��낪�̈ӂ�j�p���邱�Ƃ͂Ȃ���Ƃ�������
(���Ȃ݂ɍ������_�Q��(�茳�ɖ���)�ɢ�댯�̎������O��Ɍ̈ӑj�p��F�߂�L�q���������̂ł��Q�l�܂�)
��댯�̌������ࣂƢ�q�ϓI�댯�ࣂ��e�a�I�Ȃ̂͂��̒ʂ�Ȃ̂ł��傤
�����A���Ƃ���>>26�̖���N����_���I��������Ƃ������Ƃ�����
��댯�̌������ࣂƢ��̓I�댯�ࣂ̗������̂�Ƙ_���I�ɔj�]����̂��Ƃ������Ƃ��Ǝv�����
(���Ȃ��Ƃ������͂����F������)
����Ȃ��ʂ��Ⴄ�ȏ�A���ɐ������Ȃ���ƍl���闝�R���Ȃ��Ǝv�������ǂ�
�ǂ����Ă�������K�v�Ȃ�A���̂悤�ɍl����̂͂ǂ�����(�v���t������)
���ݢ��̓I�댯�ࣂ��̂�l��(������K�R�ł͂Ȃ��ɂ���)�s�ז����l�_��O��Ƃ�����
�����Ė����̏��������ࢍs�ׂ̊댯��ɋ��߂�킯�ŁA����͈�ʐl�𖼈��l�Ƃ��颍s�K�ͣ�Ɉᔽ����s�ׂƂ������ƂɂȂ�
����䂦�A��ʐl����ɍs�����f������͎̂��R�Ȃ��ƂƂ�����
�����A����ʌo�ߣ�͐l���R���g���[���ł�����̂łȂ��ȏ�A
��ٔ��K�ͣ�����d�����Ď���I�ɔ��������S������l�����邱�Ƃ͂��������Ȃ��E�E�E�Ƃ�
���ɢ�q�ϓI�댯�ࣂ��̂�ƌ����Ă��A���݂̎嗬�́A
����I�ɔ��������S�������b�Ɉ��ʖ@���Ɋ�Â����f����Ƃ������̂ł͂Ȃ���
���ۉ����ꂽ����I�Ȏ�������b�Ƃ��Ĉ�ʐl�̊댯���Ŕ��f���颏C���ࣂȂ̂ł���
���̈Ӗ��ł́A���̐������ĕK�����ࢊ댯�̌������ࣂƃp�������Ȃ킯�ł��Ȃ��̂ł�?
���_�I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����ǁA����͈�ʂɁu�L�߂ɂ��₷�������v�ʼn��߂���X��������悤�ȋC������B
�Ȃ̂ŁA���ʊW�ŋq�ϐ��ɌX���Ă��A�s�\�Ƃœ��l�ɋq�ϓI�댯���ɌX���邩�͋^�₩�ƁB
��̓I�댯�����̂邩�ǂ����͕ʂƂ��āA������F�߂₷���l�������̂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
����>>36�̎w�E�͐����ŁA�u�댯�������������v�Ɓu���������댯���A�����ׂ����v�͕ʂ̋c�_���ˁB
�m���ɁA�������Ă����Ǝv���B�����A���҂͊w�������ʂ���Ă��Ȃ������C������B
��҂̋c�_�͌����ɂ͈��ʊW�ƃp�������̋c�_�����ǁA�����̂Ƃ����
���ʊW�������o���̂͂�����������A�����ɋq�ϓI�A���̖��Ɛ������邵���Ȃ��̂��ȁB
�܂������ł��ĂȂ��ĊȒP�Ɋ��z�߂������Ƃ��������ǁA�����c���Ă����܂��B
�����̏��������_�ɂ��āA��c�搶�̂悤�ɋK�͈ᔽ�̍s�ז����l���݂̂ł�
�Œ���̏�����������b�t������ƍl����A�s�\�Ƃ̏ꍇ�͌����ȈӖ��ł�
�q�ϓI�Ȋ댯������v���Ȃ��ƍl����]�n������A����͈��ʊW�ƈႤ���f��ɂ��
�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�����A���ʖ����l�ꌳ�_������A�댯�Ƃ������̂��{���I�Ɉ�ʐl�̊��o�i�댯���j��
�W���Ƃ�����Ȃ��Ƃ݂�A��͂�@�v�N�Q���ʂ��̂��̂Ƃ́u�����v�y�т��́u�A���v�ɂ���
�ʌɍl����ׂ��ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��v���������ǁA�ǂ��ł��傤�H
��c��������ɔ��W�����āA�u�q�ϓI�ɋK�͈ᔽ���������v�ƔF�߂�����薢���Ƃ͐�������
�Ƃ����Ӗ��ł̊댯�s�v���A�q�ϓI�K�͈ᔽ���Ƃł������ׂ��l�����͐������Ȃ����낤���B
�i�E�ӂ������č��������܂��鎖��́A�q�ϓI�ɋK�͈ᔽ�s�ׂ��������Ƃ����Ȃ�����A���̐�������s�\�ƂƂȂ�B�j
���ɐ�������Ƃ���A�s�\�ƂƂ��ĕs�����ɂȂ�]�n�͂��Ȃ菭�Ȃ��Ȃ邩��A���������₷���̂ł͂Ȃ����ƁB
���ȃ��X�B
���ǁA�u�K�͈ᔽ�s�ׂ����邩�v�Ŕ��f����̂͌`���I�q�ϐ��ŁA
�u�E�l�̋K�͈ᔽ�s�ׂ����邩�v�������I�ɍl�����
�u�l��R�댯�̂���s�ׂ��������v���l���邱�ƂɂȂ�i�����I�q�ϐ��j����A
����ς�댯�̗L�������ɂȂ����Ⴄ�ˁB���炵�܂����B
�s�\�Ƙ_�ƈ��ʊW�_�Ƃ̊W�ɂ��ẮA�O�c��p���ʔ������Ƃ��]���Ă���B�H���A
�@�@�s�\�Ƙ_�ƈ��ʊW�_���d�Ȃ荇���̂́A����Ȃ�̗��R������B�����@
�@�@���ʊW�_�̊e�����Η������u�]�~�ł̐l�����邱�Ƃ̊댯����]������
�@�@�ɍۂ��čs���̎�����ǂ��܂œ����̂��v�Ƃ������́A�s�\�Ƙ_��
�@�@������u���A�a���҂ɍ��������܂��ĎE�����Ƃ��鎖��v�ƘA����������
�@�@���ƂɋC�Â��ł��낤�i�O�c�P�X�O�Œ��Q�X�j
�s�\�Ƙ_�̎����́A�s�ׂ̗L����댯�������Y�\���v���̗\�肷����̂ł��邩
�ۂ��Ƃ������ł���A�L�`�̑������Ɠ��������܂ނ̂ł���B���������Ӗ���
������q�ׂ��Ƃ���A���ʊW�_�ɂ����Ď��㔻�f�ł���u�댯�̌��������v
���ʐ��ƂȂ�A�s�\�Ƙ_�ɂ��e�����y�ڂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�s�\�Ƃ�F
�߂�����͏��Ȃ����A���a�R�V�N�R���Q�R���̋�C���ˎ����ȗ��A�ō��ٔ���
���o�Ă��Ȃ��̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł���B
�O�c��p�Ɖ]���A���ʊW�̔F���s�v�������ʊW�̍��떳�p�_���咣����
�w�E�̖Ҕ��������B�Ⴆ�A�R�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���i���T���P�R�Q�Łj
�@�@���ʊW���ꗂ��\���v���I�]���̓_�ŏd�v�łȂ�����Ƃ����Ă��A����
�@�@�W�̔F�����s�v�ł���킯�ł͂Ȃ��B����ɑ��A�O�c�́A���ʊW��
�@�@�F���͕s�v�ł���Ƃ��邪�A����͌����߂��ł���A���Ɂu���s�s�א���
�@�@�F���v�œ������Ƃ���Ƃ��Ă���B
���̂悤�Ȕᔻ�́A�������ʊW�����R�ɍ\���v���v�f�ł���A�]���āA�̈�
�̔F���ΏۂɊ܂܂��Ƃ������O�Ɏx�����Ă��邪�A���ʊW�̍���͖���
�ł���Ƃ���̂Ȃ�Ƃ������A���ǂ͌̈ӂ͑j�p���ꂸ�̈ӊ����Ƃ���������
�Ƃ����̂ł���A�Ƃ肽�Ăāu���ʊW�̍���v��_����Ӗ�������̂���
�����^�₪�@���Ȃ��B���̓_�ɂ��ẮA���ɂP�X�W�Q�N�ɁA���R���m��
�@�@���ʊW�̍���̖��Ƃ́A���ǁA���̌o�߂��������ʊW�͈͓̔���
�@�@�ǂ����Ƃ������ƁA���������Ĉ��ʊW�_�Ɠ���ɋA���A����_�Ƃ���
�@�@���ʂɘ_��������̂͑����Ȃ�
�Ɗ��j���Ă������Ƃ��z�N�����ׂ��ł���B
�ȏ�A�G���ł����B
�����ʊW�ɂ��ĕ��͂���悤�ɁA�R�y���j�N�X�I�W�J�Ƃ������A
�s�\�Ƃ̏����������ʕ��͉\�Ȗ@�v�N�Q�̊댯��Y������ɒu�����A
�����I���ς��挩�I�ɂ����āA��ނ������댯���Ђ��ς肾���Ă���̂���Ȃ����B
����ǂ�ł���̂͊w�҂������Ȃ�����Ȃ���
�����P�ɕs�\�Ƃɂ�����댯�ƁA���ʊW�ɂ�����댯���������Ă��邾�����悗
�Y�@�w�҂�������˂�
�i�@�����̂ق��Ń����N�������Ă�����ǂ�ł݂��B
http://www.rikkyo.ac.jp/law/output/rituhou/081.htm
�����N�������̂����O���낤����
2ch���ƈ��ʊW�̘b��Ŋ��Ƃ͂���_�����Ǝv��
�ʂɢ�@�w�£�Ȃ��炢����Ȃ�
���͂������ł͢�@�w�ł�ꣂƌ����Ă���
�������͊w��I�Șb�ł����킯����
���̎ז��ɂ��Ȃ�Ȃ�����
�����A�q�ϓI�������ʊW���́A�A�Ӕ͈͂��L������Ƃ����ᔻ�ɑ��āA
��ϓI�A���i�̈Ӊߎ��j�Ō��肷�邩��s�s���ł͂Ȃ��Ɣ��_����̂����A
���ʊW�̍����s��ɕt���ꍇ�A�����Ƃ͂����Ȃ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����B
�Ⴆ�A�u�i�C�t�Ől���h���E�����Ƃ������A�y���Ȑ菝�����^�����Ȃ������Ƃ���A
���܂��ܔ�Q�҂����F�a�ŏo�����~�܂炸���S�����v����ɂ����ẮA
�E�l������ے�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�I�C���́A���F�a����ł��̈ӁE�����Ƃ�F�߂č\��Ȃ��Ǝv���Ă���B
���ۂɔ���Ɍ��ꂽ���F�a����́A�n�ُ��a�S�T�N�P�O���P�T����������
�v�����A�n�ق͏o�����������̎��Ăɑ��A���S�ɂ��Ă͈��ʊW��
�ے肵���Q�߂݂̂�F�߂��B
�������u��Q�҂ɐg�̂ɂ��鍂�x�̕a�ςƖ\�s�Ƃ����ւ��Ď��S�̌��ʂ�
���ꍇ�ł����Ă��A���ʊW���m�肷��]�n������v�i���n�ٕ����Q�O�N
�U���R���Ȃǁj�Ƃ����̂��A�ߎ��̉����R�̎嗬�ł���A�n�ق̎����
�ނ���ْ[�ɑ�����B
�q�ϐ��Ȃ����u�댯�̌��������v���̂�A���A���ʊW�̍��떳�p�_���̗p
���Ă����̕s�s���������Ȃ��B
�O�c��������N���̔s�ފm�肗
169 ���O�F�����ٔ�[sage�@�@] ���e���F2013/09/14(�y) 16:25:17.62 ID:???
�O�c���ł́A�C����N���ƍ�����N���̈Ⴂ�����m�łȂ���ˁB
���̓_�A�R���ƈ�c�͗��҂͖��m�ɈقȂ���̂ƒ�`���Ă���B
170 ���O�F�����F�e�Q�� ��JEhW0nJ.FE [sage�@�@] ���e���F2013/09/14(�y) 17:07:07.41 ID:???
>>169
���������_�̊w���̕��ގ��́A���܂��m�肵�Ă��Ȃ��B
���̖��̃p�C�I�j�A�ł����z�����́A�@�ӔC���Ɛ��A�A�Љ�I���S���N�Q���A
�B�s�ז����l��N���A�C��N���i�����Ȏ�N���E�C�����ꂽ��N���j�ɕ��ނ��Ă������A
���������́w���Ƒ̌n�Ƌ��Ɨ��@�x�ɂ����āA�@�ӔC���Ɛ��A�A�s�@���Ɛ��A
�B�Ɨ����u����N���i������N���j�A�C�]�����u����N���i�C����N���j
�D�]���I�@�v�N�Q���i������N���j�̌܂��ނ����B
���݁A�ł��L�͂ȕ��ނ́A���������Ɏ������āA�R���E��c�������ɂ����
�咣����Ă���@�ӔC���Ƙ_�A�A��@���Ƙ_�i�s�@���Ƙ_�j�A�B������N���A
�C�C����N���A�D������N���̂T���ނł���B
�������Ƃ��A�B�͑Ó��łȂ��A�C�͇A�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ��āA�D���x�����Ă���B
174 ���O�F�����ٔ�[sage�@�@] ���e���F2013/09/14(�y) 18:25:12.15 ID:???
���F�e���̓o��ŋc�_�����������邱�Ƃ͂������Ƃ��B
2013/06/01(�y) 14:37:42 ID:???
�P�@���̍ߐ�
�i�P�j�E�l�߂̐���
�@���́A�`���g�����N���ɂ��邱�ƂɋC�Â��A�`�̌����K���e�[�v�ōǂ�
�g�����N����Ă���i��P�s�ׁj�B�܂��A�`���Ă��E�����ƌ��ӂ��Ă���
�i�̈ӂ̑��݁j�B�����āA�`���܂������Ă���Ǝv���A�a�Ԃ�R�₵�Ă`��
�E�Q�����i��Q�s�ׁj
������
�@�������A���́A�`�̌����K���e�[�v�ōǂ������_�ł`�����S����Ƃ�
�v���Ă��Ȃ��������ƁA�g�����N����čĂё��s���{�����ԏ�ɒ����܂ł́A
���Ԃɂ��ĂP���ԁA�����ɂ��Ė�Q�O�L�����[�g���ł���A���ԓI�E�ꏊ�I�ߐڐ���
�F�߂���Ƃ͌�������Ƃ���A��P�s�ׂɎ��s�̒���͔F�߂�ꂸ�A
��Q�s�ׂ����s�s�ׂł���B
�@����āA���ɂ́A��Q�s�ׂɂ��Ă`�ɑ���E�l�߂���������B
147 �����ٔ�
2013/06/01(�y) 15:24:16 ID:???
>>145
��Q�s�ׂ��E�l�߂̎��s�s�ׂƂ���́H
���̎��_�ł`�͎���ł邯�ǁB
��ʐl�ł���`�������Ă�ƔF������ł��낤����A�Ƃ������ƁH
���̓_�̐����͕s���̂悤�Ɏv���邪�B�B�B
���1�s�ׂ����s�s�ׂł͂Ȃ�����A��2�s�ׂ����s�s�ׂ���Ƃ��������ł͑�
���̂ł͂Ȃ����ȁB
2013/06/01(�y) 15:13:47 ID:???
�i�R�j���������ȊO���߂̐���
�@�a�Ԃ�{�����ԏ�ɒ��Ԃ������_�ŁA�{�����ԏ�ɂ͂b�ԁA�c�ԁA�d�Ԃ�
���Ԃ��Ă����B���́A�u���̎ԂɔR���ڂ邱�Ƃ��Ȃ����낤�v�Ƃ����F����
���ƂɁA�a�Ԃ����コ���Ă���B
�@������110��1���́u�����̊댯�v��108�������109��1�������ւ̉��Ă�
������̂��ǂ��������ƂȂ�B
������
�@����ĉ��ɂ͕��߂͐������Ȃ��B�����A�b�Ԃ̍����ʂ��ꕔ�������Ă���
���Ƃ���A�함����߂���������B
149 �����ٔ�
2013/06/01(�y) 17:21:09 ID:???
>>146
���͢���̎ԂɔR���ڂ邱�Ƃ��Ȃ����낤��ƔF�����Ă邪�A��함����ߣ��
�̈ӂ��F�߂��邩�ȁB
���ƁA110��1������Ȃ���2�����ˁB���L�ҍb�ɗ��܂�ĔR�₵������B
�q�ϓI�������ʊW������������Ó��Ƃ����͈̂�̕K�R�I�ȋA�������ǁA
�댯�̌�����������͌��F�a����Ŋ����ɂ���̂��K�R�Ƃ͂����Ȃ��C������B
�u�����菝��^������x�̐���s�ׁv�̊댯�́A�����܂Łu�����菝��^������x�̊댯�v
�ł����Ȃ�����A���Ɏ��������ʂ́A���Y�s�ׂ̊댯�ł͂Ȃ��A���F�a�Ƃ����a��
���Ȃ킿�u�����菝���Ă��܂��Ǝ��Ɏ��肩�˂Ȃ��댯�ȕa�ԁv�̊댯��
�����������ɉ߂��Ȃ��ƍl������̂ł͂Ȃ����낤���B
���̒��x���y�x���i�����菝�j���d�傩�i�d���j���ɖ�肪����킯�ł͂Ȃ��A
�u���ꂪ���S�̗B��̌������͒��ڂ̌����ł��邱�Ƃ�v������̂ł͂Ȃ��A
��Q�҂̐g�̂ɂ��鍂�x�̕a�ςƖ\�s�Ƃ������܂��Ď��S�̌��ʂ����ꍇ
�ł����Ă��A���ʊW���m�肷��]�n������v�i���n�فj
���ꂪ���݂̔���̎嗬����B
���������āA���������F�a���Ⴊ�ٔ��ɂȂ�����A�ٔ����͂����炭���ʊW
���m�肷��Ǝv���B
���Q�҂̍s�ׂ���̈��ʊW���m�肷��ɂ��A
���̓���A�d�v�A�傫���ƌ����Ȃ��Ƃ����Ȃ����낤�B
�����������댯�͌��ʎ�N�ɂǂ�قǏd�v�Ȗ������ʂ��������B
��Q�҂ɒʏ픭������댯�Ɣ�ׂĂǂ�قǑ傫�����B
�u���ʊW���m�肷��]�n������v�Ƃ������n�ق̌����́A
�댯�̌���������q�ϐ��͂������A�ܒ����Ƃ��������Ȃ��Ǝv���B
�u��Q�҂̐g�̂ɂ��鍂�x�̕a�ρv���s�҂��F�����邩�A��ʐl�ɔF���\�Ȃ�
���ʊW���m�肷�邩��A�u�]�n������v���Ƃɕς�肪�Ȃ��B
����������̂́A�댯�̌��������́u�댯�v�Ƃ́A�s�ׂɓ��݂���댯����ǂ�ق�
����Ă��m��ł���̂��Ƃ������ƁB�����菝��^������x�̊댯�n�o�������āA
�Ȃ��A�����������������̊댯���A���ł���̂��A����̌��_�͂Ƃ������A
���_�I�ɐ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
���Ȃ݂ɁA�h�C�c�̋q�ϓI�A���_���ƁA���F�a�͂ǂ����������́H
�ʏ�̎Љ���𑗂��Ă���҂����Ȃ��炸���݂��Ă���C
�{���̂悤�Ȗ\�s�y�т��̌�̓����s�ׂ����̎��a���ɍ�p���Ď��S�̌��ʂ�
�����邱�Ƃ����蓾��v���Ƃ���A
�u�{���\�s�ɂ��c��Q�҂̊����ُ�ɍ�p���ċ}���z�s�S��U�������v�ƔF�肵�Ă���B
�]���āA�ܒ����������ʐl�ɔF���\�ł������ƔF�肵���鎖�Ăł���A
�u�U���v�Ƃ͐ܒ�������b����Ɏ�荞�߂�ꍇ���w������ܒ����Ƃ͖������Ȃ��Ƃ���
�l�����i�]�������̎w�E�������Ǝv�������M���Ȃ��j�Ɛ�������B
������A���F�a����ł��]������Ŕے�����蓾��Ǝv���B
�͂̎ア�����ł����Q�҂ɑ��C�w�ォ��R��t������C������͂�ŋ�����
�h�A�ɕ�����ł��t���C�������܂Ɏ茝�ŗ��j�╠�������ł���ȂǂƂ������X
�ő����ɋ��x�̊댯�Ȃ��́v�Ƃ����F��̏�ŁA��L�̂悤�Ș_�����Ă��邩��A
�P�ɂ����菝�킹��y���Œʏ펀�̊댯�̂Ȃ��s�ׂɂ��Ă܂Ŏ˒����y�Ԃ���
���������ł��邱�Ƃ��t�����܂��B
�u�퍐�l�́C�O�L�̂Ƃ���C��Q�҂������j���O���ɓ|��Ĉӎ������������Ƃ����邱�Ƃ�C
���ɗ��Ă���������������ēd�Ԃɏ�����ۂɐS�����ꂵ�������Ƙb���̂���
�m���Ă����̂ł��邩��C�{���\�s�ɋy���_�ŁC�������������^���C
���ɑ��邱�ƂɐƎ�ȑ̎��ł��邱�Ƃ�F�����Ă����ƔF�߂��C��Q�҂̐Ǝ�ȑ̎���
�����܂��Đ����Ɋւ��悤�ȏd�ĂȏǏ���������邱�Ƃ��\���ł��Ȃ������Ƃ͂���
�Ȃ��v�Ƃ��F�肵�Ă��鎖�Ăł��邱�Ƃ����ӂ��ׂ����Ƃ��Ǝv����B
���_�����L���ƁA���F�a�Ƃ����d�ĂȎ����Ǝ��X�Ȗ\�s�Ƃ����ւ��āA
��Q�҂͎��Ɏ������A�܂�
�o������Ύ��Ɏ��邩������Ȃ��댯���������������A�ƌ�����̂ł͂Ȃ����B
�]���ЕF�́u�U���v�T�O�ɂ��Ắw�Y�@�ɂ����錋�ʋA���̗��_�x�i�P�P�V��
�`�P�Q�R�Łj�Q�Ƃˁi�Q�O�P�Q�N�j
�Ƃ���ŁA�]���́u��ݎ���\���s�\�ł���Ƃ��Ĕ��f��ꂩ��r�������
�ꍇ�́A�s�ׂ̊댯���̒��x�Ɖ�ݎ���̊�^�x�Ƃ̑��֊W�ő������̗L����
���܂邱�ƂɂȂ�v�Ƃ���B
�������A�������f��ꂩ��r�����ꂽ�͂��̉�ݎ���̊�^�x���ēx����
����͉̂��̂ł��낤���B�������R��ǂ�ł�����Ȃ������B
��ݎ���\���\�ȏꍇ��
�s�ׂ̊댯���̎����ɉ�ݎ������荞�܂��(�`�{��)
�����A��ݎ���\���s�\�ȏꍇ��
�s�ׂ̊댯��(�`)�݂̂����������Ƃ����邩�����ƂȂ邪
(�܂袁{����ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŕ��f��ꂩ��r������邪)
�`�����ƂȂ�Ƃ��́A���������̂͂��̊댯�ł����Ă`�Ƃ͂����Ȃ�
�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ�ł��傤
�Y�@�̏d�v���k���_�l����
�s�҂��r������˂����Ƃ�����Q�҂�
�������ɑ�O�҂��ˎE�����Ⴊ�������Ă���
>�s�ׂ̊댯��(�`)�݂̂����������Ƃ����邩�����ƂȂ邪
>(�܂袁{����ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ŕ��f��ꂩ��r������邪)
>�`�����ƂȂ�Ƃ��́A���������̂͂��̊댯�ł����Ă`�Ƃ͂����Ȃ�
>�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ�ł��傤
�Ƃ������Ƃ́A�`�����ƂȂ�Ƃ��́A���������Ȃ����ƂɂȂ�킯�ˁB
�����A�s�������g�����̂������ȈӖ��Ő��������͕�����Ȃ�
���ȏ����琳�m�Ɉ��p���Ă����ƁE�E�E
�@��ݎ���̌��ʂɑ���e����(��^�x)���傫���ꍇ�́A
���ʌo�߂̑������̘g���Ă��܂��A�������ʊW���ے肳��邪�A
�A��^�x���������ꍇ�́A
�ˑR�Ƃ��đ������̘g���Ɏ��܂��Ă���A�������ʊW���m�肳��邱�ƂɂȂ�B
�s�ׂ̊댯������ݎ���̊댯���̂Ƃ��́A�\���\�����l�����邱�ƂȂ��A
�s�ׂ̊댯�����������������ǂ����𑊓����̖��Ƃ��Ĕ��f���A
�s�ׂ̊댯������ݎ���̊댯���̂Ƃ��́A�\���\�ł����Ă͂��߂āA
���f���ɑg�ݓ���Ĕ��f���̖��Ƃ��Ĕ��f����A���Ă��Ƃł��傤�B
�ȂA�R�����Ɓ����������l����_�͓������ˁB
�悸���ݎ���\���\����f����
�\���s�\�ȏꍇ�Ɂu��ݎ���̊�^�x�v���l������
�Ƃ������Ƃ݂��������ǂ�
����͕�����B
�@��ݎ���̊�^�x���傫���ꍇ��
�A��ݎ���̊�^�x���������ꍇ�̈Ⴂ���ˁB
�ł��]�����w���ʋA���̗��_�x�Ŗ��Ƃ��Ă���̂�
�B��ݎ���������������f��ꂩ��r�����Ă�ꍇ�ȂB
�����ɉ]����>>68>>69�̐����ł͕�����Ȃ��B
�Ȃ��A���씎�m�́u�s�҂��r������˂����Ƃ�����Q�҂𗎉����ɑ�O�҂�
�ˎE������v�ŁA�s�҂Ɉ��ʊW��F�߂Ă���i�w�����i��j�x�i�P�X�W�P�N�j�S�Q��
�s�ׂ̊댯���݂̂ő��������f���s���ׂ��ł͂Ȃ���
�Ƃ������ӎ��Ȃ̂��ȁE�E�E
�����A��ݎ���f���ɓ���邩�Ƃ������Ƃ�
�s�ׂ��猋�ʂ������邱�Ƃ̑�������W���鎖��Ƃ��čl������Ƃ������Ƃ�
�ʖ��Ƃ�����̂ł͂Ȃ�����(�������Ƃ��ēx���ɂ��Ă����ł͂Ȃ�)
���炭�]�����̖{���Ƃ��ẮA�Y�@�̏d�v����ǂތ���
���̢�˂����Ƃ�����(?)�̕�����̌��_�����������ƍl����
(�ܘ_���ꂾ���ł͂Ȃ���������Ȃ���)
���ݎ�����ʂɋy�ڂ�����^�x���l�������������Ȃ�
�Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ��̂���
�������悤�����u��ݎ�����ʂɋy�ڂ�����^�x���l������������Ȃ��v
�̂ł���u��ݎ���\���s�\�ł���Ƃ��Ĕ��f��ꂩ��r������v�Ƃ���
�~�X���[�f�B���O�ȕ\���i���ʋA���̗��_�R�V�Łj�͎~�߂����������Ǝv���B
���ʋA���̗��_�v�i�Q�O�P�Q�N�A�������A�U�T�O�O�~�j�͑S�R�P�X�ł�����
�R���Ԃ�����Γǂ߂�B
�I�C���͔��ʋ��t�Ƃ��ēǂ�ł���̂����A�]�����̏W�听������A�]����
�̐l�ɂ������łȂ��l�ɂ���ǂ�E�߂�B
�\�s�̒��x�����X�łȂ��āA�P�ɂӂ����ăJ�b�^�[�i�C�t�Ōy�������悤��
�ꍇ�ɂ��A�u���F�a�ɂ��o���ߑ���U�����Ď��̊댯�������������v�Ƃ�����H
���_�����łȂ��āA�����Ɏ��闝�_�ߒ���m�肽���B
�\�s�̒��x�Ǝ����̏d�Ă��Ƃ̑��֊W�ōl����̂��A����Ƃ��A
���҂������܂��Č��ʂ���������Ώ�ɋA�ӂł���̂��A���̔��f�g�g�݂��C�ɂȂ�B
�]���͔��f���ɓ����ꍇ�͊�^�x����ɂ�����
���̎�����O��ɔ��f����i����ΐ�ΓI�l�����R�j�B
����ɑ��A���f��ꂩ��r������ꍇ�ɂ́A��^�x���l������
���̗\���s�\�Ȏ�����܂߂��ꎖ��Ƃ��čl������i����Α��ΓI�l�����R�j����
���Ƃ��Ǝv���B
�u���f��ꂩ��r���v�Ƃ����\�����~�X���[�f�B���O�Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ��B
�I�C���͍ŏ��Ɍ��F�a������o����>>53�A�܂�
>�i�C�t�Ől���h���E�����Ƃ������A�y���Ȑ菝�����^�����Ȃ������Ƃ���A
>���܂��ܔ�Q�҂����F�a�ŏo�����~�܂炸���S����
�Ƃ��������O��ɋc�_�����Ă����̂����B�܂�E�ӂ�����ꍇ����B
���ʊW��ے肵���Q�߂̂ݔF�߂��n�ُ��a�S�T�N�P�O���P�T�����E�ӂ�
���݂͓��R�̑O��Ƃ��Ă���B
>>76��
>�\�s�̒��x�����X�łȂ��āA�P�ɂӂ����ăJ�b�^�[�i�C�t�Ōy�������悤�ȏꍇ
���A���̊댯�͌��������Ă��邪�A�E�ӂ��Ȃ��̂ŁA���Q�v���߂ɂƂǂ܂�ƍl����B
�i�z���g�ɗV�є�����������ߎ��v���߁j
�Ƃ���ŁA�I�C���̘_�G�͂����������l����H�Q�l������Ƃ��R�l���H
�ǂ����P�l�̂悤�ȋC�����邯�ǂ�
HN�Ƃ͉]��Ȃ�����AA�ł�B�ł���������L�������Ă����Ə�������B
>>75
�]���搶�̘_���͓ǂ�ł��Ȃ��̂ŕ�����Ȃ����ǁC
>>68�Ȃǂ�ǂނƁC���f����O��ɂ����s�ׂ̊댯����
���f��ꂩ��r�����ꂽ����̂�����ɋA�ӂ��ׂ�����
��^�x�Ō��߂�Ƃ������f�g�g�݂ł͂Ȃ��́H
>>75���]���搶�̘_���̓ǂݕ���������Ȃ��ƌ������̂����[������C
���̐l�ɘ_����ǂ�ŋ����Ă���C�Ƃ����ԓx�ł͂Ȃ��āC
���̐l�̂����悤�ɘ_�����ǂ߂邩�ǂ����������Ŋm���߂�ׂ��ł́B
���̏�ŁC�m���ɂ����ǂ߂��ʂ邪�C
���f����O��ɏ����W�Ŕ��f���āC��^�x����ɂ��Ȃ�
�Ƃ����]���̔��f���̎g�����ƈႤ����~�X���[�f�B���O���C�Ƃ��C
�ʂ̉ӏ��Ł`�Ə����Ă��邩�炻���͓ǂ߂Ȃ��C�Ƃ��C
�������������łȂ��Ƌc�_�ɂȂ�Ȃ��B
���������u���ʋ��t�v�Ƃ��C�]���u���v�̏W�听�Ƃ��C
�ŏ��������ςŁC�]�����̌��_�Ɨ��������݂ėg��������낤�Ƃ��ĂȂ��H
�{���Ɏi�@����������Ȃ�C���̊w�҂̌��_�Ȃ�{�ǂ��ł�������B
�����҂̗��Ȃ�C�]���搶�Ƃ������h�Ȋw�҂����\�N�������āC
�ǂ��������ӎ��ŁC�ǂ�����������ǂ�ŁC�ǂ����āC������������̂��C
�Ƃ��������́u�W�听�v�����u���t�v�ɂ��ׂ��ł��傤�H
�Ȃ̂����Ȃ��Ƃ������Đ\����Ȃ����ǁC
���̂܂܂��Ɠ��X����ɂȂ肻�������C
���ʋ��t�Ƃ����̂��������C�ɂȂ����̂ŗ]�v�Ȃ��Ƃ��������Ă�������B
��������B
���N�V���A�R���h�ꂾ���łȂ��A���h���t�B�[�A���H���^�[�A�t���b�V���Ȃ�
�̌�����������������ł̔ᔻ�����Ɏn����������
�T�^�I�Ȕᔻ���Q�����Љ�Ă����B
�E�q�ϓI�A���_�ɂ́A�����I�v�f�ƋK�͓I�v�f�����݂����A����ɂ͎�ϓI�v�f
�����q�ϓI�\���v���Ɏ�荞�ނ��Ƃɂ���āA�u�{�������I�Ɂv���̉�����
�}�낤�Ƃ���v�z�̌X���������i�P�T�Q�Łj
�E�i�R���ɂ��j�q�ϓI�A���_�ɂƂ��ĕs���ȗތ^���̍�Ƃɂ���āA�͂�����
�u�@�I���萫�Ɩ��m�����l���v���A�u�K�ȋA�����Nj������邱�Ƃ��ۏ�
���ꂽ�v�Ƃ����邩�A�^��Ȃ��Ƃ��Ȃ��B�ނ���A���_���̂��̂̔���H����
���炩�ɂ����Ƃ݂�͕̂M�҂̎v���߂����ł��낤���i�Q�O�R�Łj
>>80�������Ă�Œ���>>79����ɏ������݂���Ă��܂����̂ł����A>>80��
�ǂ�ł��炦�Ε�����Ƃ���A�q�ϓI�A���_���̂鎄�ɂƂ��āu���ʋ��t�v
�Ƃ����̂́u�q�ϓI�A���_�ᔻ�ҁv�Ƃ����Ӗ��ő��ӂ͂���܂���B
���t���炸���������Ƃ͂��l�т��܂��B
�d�v���⌻��Y�@�_���i�]������[�������j�͍��ł��苖�ɒu���Ă���A
�]���搶�͎��̑��h����搶�̈�l�ł��B
�d�������B�Q�����˂���r�炳�Ȃ��ŁA�������Ǝd�������B
�i�@���������������̂��悭�킩��
�n�b�X����
�������ꂾ��
�_�G�Ƃ������킯����Ȃ��āA�����ɋ����ė~�������ǁA
�u�댯�̌��������v�̋�̓I�Ȕ��f�ߒ����Ăǂ��Ȃ��Ă���́H
�M���̃��X��ǂތ���q�ϓI�������ʊW���Ɖ���ς��Ȃ��悤��
���������̂ŁB
�ǂ��������^���Ă��܂����悤���B
�I�C�����g�́A>>81�ŏq�ׂ��悤�ɋq�ϓI�A���_���̂�[�u�̂�v�Ƃ������
�u�͍����v�Ɖ]�����������m�B
>>32�ȉ��ŏq�ׂ��u�댯�̌��������v�́A�����܂ł�����͂��̂悤�ɍl����
����̂��낤�Ƃ������Ƃ��I�C���Ȃ�ɕ~���������肾�����̂����A���ꂪ
�u�q�ϓI�������ʊW���Ɖ���ς��Ȃ��v�Ɣᔻ�����̂ł���A��
�I�C���̕��s�����Ƃ������Ƃ��낤�B
�������悤�Ő\����Ȃ����A�t��A����̍l�����������Ăق����B
���������āA�������悭�킩��Ȃ��B�킩��Ȃ��Ƃ������A
���������A�u�댯�̌��������v�Ȃ�w���͑��݂��Ȃ��̂�
�u�댯�̌����������ƁA�����Ȃ�v�ƈ�`�I�ɂ͌����Ȃ��Ƃ����F���B
�����炱���A���_��������Ȃ��āA���ꂼ��̎��Ăłǂ�����������
���_���������̂��A���̘_���\�����c�_���ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���B
��̓I�ɂ́A�K�͓I���_���ǂ̂��炢����邩�͖��ɂȂ蓾��̂ł͂Ȃ����B
���Ȃ킿�A���F�a����ł���A�q�ϐ��͘_���K�R�m�肾���ǁA
�A���_�I�ɂ́u�K�͓I�ɂ݂ċA��������ɒl���Ȃ��v�ƍl���Ĕے肷��]�n�͂��肤��̂ł͂Ȃ����B
����ƁA���ӎ��Ƃ��ẮA����̂����u�댯�̌������v�́A�������ʊW����
�������̔��f�ɓ����锻���ɉ߂��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ�����B
������A���f���_�Ƃ��Ă̐ܒ����Ƌq�ϐ��̑Η��Ƃ͒��ڊW�������̂ł͂Ȃ����ƁB
�����炱���A�ܒ����̘_�҂��댯�̌������ōl���锻��ɔ����Ă��Ȃ��̂��낤�B
���F�a���҂����S���ׂ��댯�Ƒ�����̂��A�����菝��^������x�̊댯��
�n�o�����s�҂ɕ��S������ׂ��댯�Ƒ�����̂��A����͋K�͓I�Ȕ��f�ł���B
���̂悤�ȋK�͓I���f�ɂ����āA��L�댯�͍s�҂ɕ��S������ׂ��ł���Ƃ������f�̉���
�u�s�ׂ̊댯�������������v�Ƃ������_�Ɏ���̂��A�����ł͂Ȃ��āA�P�ɑS�Ă̎�����
�l������A�u���Ɏ���̂������v������u�댯�������������v�Ƃ������_�ɒB����̂��B
��҂ł���A�q�ϓI�������ʊW���Ɠ����Ƃ������ƂɂȂ�B
���ɑO�҂ł���A���̔��f�̑O��Ƃ��āA��b�����ܒ����I�Ɏ��O���f�ōl���A
���O���f�̘g���ŋK�͓I�ɋA�ӂ��l���邱�Ƃ��������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�Ƃ������ƁB
��J�E�Y�@�u�`���_�ƁA��ˁE�Y�@���_�̎v�l���@�����邪
������S�������b��Ƃ����(�v�͎R����)���w���Ă���
������A�����O��Ƃ���A���F�a���ᓙ�͋q�ϐ��Ɠ����Ƃ������Ƃł悢�͂�
�����ŁA
���s�ׂ̊댯�������ʂɌ�������������Ƃ������f�g�g�݂��̗p����Ƃ��Ă��E�E�E
��s�ׂ̊댯����A�q�ϐ��̂悤�ɁA�s���ɑ��݂���E�E�E���ׂĂ̎�����l�����Ĕ��f����̂��A
�ܒ����̂悤�ɁA��ʐl���F���\�Ȏ���ƍs�҂����ɔF�����Ă����������b�ɔ��f����̂��A
�Ƃ������́A���̂܂c����Ă���v
�Ƃ����w�E(�����E�Y�@���_�̍l�����E�y���ݕ�)���炷��A
(��댯�̌������ࣂƂ������O�ɍS��Ȃ��̂ł����)�`����̖��ӎ��͕�����
�����A���b�����ܒ����I��ɍl���A
��댯�̌������́E�E�E�������̔��f�ɓ�����v�ɉ߂��Ȃ��ƍl����̂ł����
�t�ɐܒ����Ƌ�̓I�ɂǂ��Ⴄ�咣�����悤�Ƃ��Ă���̂����悭������Ȃ��C�͂���
�������܂��ɖ��ӎ��ŁA�]���u�������v�Ƃ����͎̂����̖��̂悤�ł���Ȃ���
�����ɂ͑����ɋK�͓I�ȗv�f���܂܂�Ă����̂ŁA���̕����𐳖ʂ���
�K�͓I�ɑ����悤�ƌ����̂��A�u�댯�̌������v�̍l�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B
��s�@�������邩������Ȃ��ƔF�����A�E�ӂ������āA�u��s�@���֗��ł���v�Ɗ��߁A
�Ă̒��s�@���������Ƃ����ꍇ�ɁA����͔�s�@�������邱�Ƃ��Љ�ʔO�㑊���łȂ�
����Ȃ̂��B�u����I�����댯�v�ɉ߂��Ȃ��Ƃ��čs�҂ɋA��������ׂ��łȂ��Ƃ����̂�
�ŋ߂ł͗L�͂Ȃ͂��B���̔��z�̉�������ŁA���F�a����ł��u���߂�ꂽ����I�����댯�v
�������������ɉ߂��Ȃ��Ƃ��āA�s�҂ւ̋A����ے肷��w�����h�C�c�ɂ͂������͂�
�i���̓_�͌����F�e���ɕ⑫���Ă��炢�������j�B
���̂��Ƃ́A��b����_�Ƃ͕ʌ̋c�_������ܒ����{�댯�̌����������̂��āA
��ʐl�ɂ͌��F�a��F���\�ȏ�Ԃł������Ƃ��Ă��A
���S���ʂ̋A����ے肷�ׂ��ł���Ƃ������_���������邱�ƂɂȂ�B
�]���̑������ʊW������́A�i�q�ϐ��ł���ܒ����ł���j�o���@����̑���������
�l���ł��Ȃ��������̂��A�s�ד��ݓI�Ȋ댯�ł��邩�A�����ꂽ�댯�ł��邩���̍s�҂�
�A�����ׂ��댯���ۂ��Ƃ����K�͓I�Ȋϓ_�������ł���悤�ɂȂ�_�ɁA�u�댯�̌��������v��
�̗p������v������B
�P���������Ă��������̂�
>�ܒ����{�댯�̌����������̂��āA
>��ʐl�ɂ͌��F�a��F���\�ȏ�Ԃł������Ƃ��Ă��A
>���S���ʂ̋A����ے肷�ׂ��ł���Ƃ������_����������
�Ƃ����Ƃ���Ȃ�
��������飂Ƃ���������
������ׂ�����ƌ����Ă��ł͂Ȃ��̂�������Ȃ�����
�����������_���̂ł����
�Ȃ���ܒ��࣓I�Ȋ�b����_�ɍS��̂����s���Ɨ��Ȃ��C��������ǁE�E�E
�����Ċ�b��������肵�Ȃ��Ă��������_�͓���������
>���F�a����ł́A�u�����菝�Ŏ��Ɏ���댯�v��>���F�a���҂����S���ׂ�
>�댯�Ƒ�����̂��A�����菝��^������x�̊댯��n�o�����s�҂ɕ��S
>������ׂ��댯�Ƒ�����̂��A����͋K�͓I�Ȕ��f�ł���B
�]�������́u�q�ϓI�A���_�͎����I���f�ł���ׂ����ʊW�_�ɋK�͘_��
�������ݖ��p�ȍ����������Ă���v�i�����ËH�W�W�Łj�Ɣᔻ���Ă���B
�]�������ɂ����ẮA�\���v�������l�����I�ɒ藧���邱�Ƃ����㖽��ł���A
�K�͓I�v�f�̍��݂�������̂ł��낤���A�Y�@���ߊw���K�͊w�ł������A
�ƍߘ_�̌n�̂ǂ����ŋK�͓I�]��������Ȃ��B�\���v���_�����q�ϓI��
�Ȃ������Ƃ��Ă��A�Ⴆ�Έ�@�_�ɂ����ċK�͓I�]��������̂ł����
�Ӗ����Ȃ��B
�u�@�I���ʊW�̔��f�ɂ����ċK�͓I�l�����K�v�ł��邱�Ƃ͋^�����Ȃ��A
���̓_�m�Ɏw�E�����̂͋q�ϓI�A���_�̌��тł���v�i�����E�őO���Q�V�Łj
���������́u�s�҂ɂ���Q�҂ɂ��x�z�ł��Ȃ�����Ȏ����Q�҂̑f��
�i�Ⴆ�Ό��F�a�j�ł���ꍇ�ɂ́A��Q�҂Ɍ��ʂ��A���������邱�Ƃ�������
������ȏ�A�s�҂̍s�ׂɋA��������ׂ��ł���v�Ƃ���i�����E�őO���Q�T�Łj
���̓_�ɂ��ẮA��c�������u�����@�I�Ȕ��z�����ׂ��ł͂Ȃ��v��
�ᔻ���Ă���i��c�E�őO���T�S�Łj
���يۏo����������
�͂ł��Ȃ��ł��낤���B
�����A�Q�O���I�����A���ʊW�_�Ƃ͕ʂ́u�K�͓I�v�Ȋϓ_����A�����k�y��
������s�����_�����ꂽ�B���̂悤�Ȏ��݂́A�h�C�c�ł̓~�����[��
�u�K�͓K���I�댯�̗��_�v�Ɍ��������B
�~�����[�̊댯�T�O�̕��͂́A�P�X�R�O�N��ɃG���M�b�V���ɂ���āu����
���ʊW�ɍ̗p���ꂽ�v�B���ꂪ�u�s�ׂ̊댯���v�i�댯�n�o�j�Ɓu�댯�̎����v
�̋�ʂł���B
�R���������u�s�ׂ̊댯�������ʂւƌ������������v�i�댯�̌������j��
�]���Ƃ��A����̓~�����[�̘g�g�݂Ə������ς��Ȃ��B����ΐ�c�Ԃ肵��
�̂ł���B
�������āu���̂悤�ȗ���́A�K�͓I�l���Ɋ�Â����ʂ̍s�ׂւ̋A����₤
�q�ϓI�A���_�Ƃ��͂⍷�͂Ȃ��v�i�R���U�O�Łj
�܂�A�ŐV�̑������ʊW���Ƌq�ϓI�A���_�͗Z�����Ă��܂����̂ł���A
�Ƃ����͉̂]���߂��ł��낤���B�@
�q�ϓI�A���_�̍l����ƍߘ_�̌n�ɋy�ڂ��Ă������A���ʊW�ɂƂǂ߂邩
�ɂ����āA���������Ȃ��H
�������A�q�ϓI�A���_�͏]�����{�ł͎��s�s�א��Ŕ��f����Ă������́i����I�����댯�j��
��@���_�ŏ�������Ă������́i�����ꂽ�댯�j���܂�ł���B
�]���āA�u�Z���v���邱�Ƃ͐�����ł��Ȃ��Ǝv�����A�ǂ����B
>>97�����������̂͂����������Ƃł��傤�B
>>98
�I�C����<<87�ŏq�ׂ�
>�I�C�����g�́A�q�ϓI�A���_���̂�[�u�̂�v�Ƃ������u�͍����v�Ɖ]�����������m�B
�Ƃ����̂͂܂��ɂ��̓_�ɂ��Č��f�ł��Ă��Ȃ����炾�B
�q�ϓI�A���_�������܂ł����ʊW�_�̒��ɕ����߂�ׂ����A����Ƃ��A
���Ƃ��A�ē�������ؖΎk�̂悤�Ɉ�@�_�ɂ܂œ��ݏo���ׂ����A���f��
�ł��Ă��Ȃ��B
�܂��A�s��הƂ�ߎ��Ƃ́A�q�ϓI�A���_���̂邩�ǂ����ŁA���̍\�����傫��
�ς���Ă���B
�q�ϓI�A���_�ɑ���ł����͂Ȕᔻ�҂ł����J���́u�댯�����̗��_��
���Ă͊댯�̑n�o�Ȃ��������Ƃ����T�O�͎��s�s�ׂɓ�����s�ׂ�������
�ǂ����̖��ł���A�q�ϓI�A�ӂƂ����ׂ����ł͂Ȃ��v�u�K�͂̕ی�ړI
�̗��_����ыK�͂̕ی�͈̗͂��_�ɂ��ẮA�K�͂̕ی�̖ړI�Ȃ����͈�
�͋ɂ߂Ĕ��R�Ƃ��Ă��邽�s���m�ȏꍇ�������A�`���I�E�ތ^�I���f�ł���
�\���v���Y�����̔��f�̊�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ͕s�K���ł���v�i�Q�O�S�Łj
�Ǝ茵�����B
�ȑO����q�ϓI�A���_�ɍD�ӓI�ł������R�����́u�q�ϓI�A���_�̋A�����
�g�g�ݎ��̂͏\���̗p���邱�Ƃ��\�ł���v�Ƃ��Ȃ�����u�q�ϓI�A���_��
���ʂ���̗p���邱�Ƃɂ��߂炢��������邱�Ƃɂ́A�S�����R���Ȃ��킯��
�͂Ȃ��B����́A��������A���������ǂ̂悤�Ȋ����яo���Ă��邩�킩
��Ȃ��Ƃ���x���������邩��ł���v�ƌ��O�������Ă����i���T���Q�X�E�R�O�Łj
���̃I�C���ɂ́A�����̔ᔻ�ɏ\���ɉ�����\�͂͂Ȃ����A�ǂ��炩�Ƃ�����
�q�ϓI�A���_�͈��ʊW�ŗL�̗��_�ł���Ǝv���Ă���B
���ꂪ�G���ȋA���_�̊W�߂Ȃ�A����ɖ��O��^����Ӗ����Ȃ��Ƃ����w�E�����邵�B
�b���ς��Ăق����B
�i�s�ׁj�A�\���v���A��@�A�ӔC�ɕ��z���Ă��܂��̂����肩�ȁB
�ʐ��ł̈�@��ӔC�̈����Ɠ��l�ɁA��@��ӔC�ł͈��ʊW�ے�_�ɂȂ�B
�R���搶���q�ϓI�A���_�ɍD�ӓI�Ȃ̂́A�ނ����s�s�T�O��
�Ǝ��̈Ӌ`��F�߂Ă��Ȃ�����ł��傤�B����́A���s�s�T�O���d������
��J�搶�̔ᔻ�ƕ\�����Ȃ��W�ɂ���Ǝv���B
�u�댯�̌��������v�Ōł܂�Ƃ����ꍇ�A�s�\�Ƙ_�ł��q�ϐ��ɗ����낤��
�\���ł���Ƃ͂����A�q�ϐ��ɂ́u���q�ϓI�ɂ͖����͑S�ĕs�\�ƂɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ���
�v���I�Ȍ��ׂ�����B
�Ⴆ�A�m���ɂ݂���l�Ƀs�X�g���łƂǂ߂��h���s�ׂ������҂ɂ��āA
���͍s���̐����O�Ɏ��S���Ă������Ƃ��Ӓ�ɂ�薾�炩�ɂȂ����Ƃ��������
����͂ǂ��������_���̂�Ɨ\���ł���̂��낤���B
�u�댯�̌��������v�̍l��������͐l�̎��̊댯�͑n�o����Ă��Ȃ��Ƃ���
�s�\�ƂƂ���̂����_�I�����A���ꂾ�ƕs�\�Ƃ͈̔͂������g�傷�邱�ƂɂȂ�B
�o�����ܐ���������F�߂��Ō���35.10.18�ł��A�s�\�ƂƂ��ׂ����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
���ʊW�_�ɂ����āu�댯�̌��������v���ʐ�������A�s�\�Ƙ_�ɂ����Ă�
�q�ϓI�댯�����L�͉�����ł��낤���Ƃ͋�Ƃ���ł��傤�B
�q�ϓI�댯���ɑ��Ắu����I�ȗ��ꂩ��A�s���ɑ��݂������ׂĂ̎���
���l������Ȃ�A�����関������Εs�\�ƂȂ�A�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ�v�Ƃ���
�ᔻ���܂�Œ���ł��邩�̂悤�Ɍ���邱�Ƃ��������i��c�S�P�S�łȂ�
�Q�ƁB���̓_�ɂ��Ă͎R���Q�V�T�ł����F���Ă���j�ʂ����Ă��̂Ƃ����
���낤���B
�ނ���A����炷�ׂĂ̎��������������ɂ����A���ꂪ�q�̂��i�̌��ׂ�
��Â��̂��A����ȊO�̏�Q�Ɋ�Â��̂�����ʂ���A���̃Y���̎��Ɨʂ�
�����I�������\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�������A���ݗL�͂Ȍ����́A�����q�ϓI�댯���i����q�M�E����I�W�J�U�P�V�T�łȂǁj
�ł͂Ȃ��A�R�������w�댯�Ƃ̌����x�i�P�X�W�Q�N�j�Œ����u����I�����̑��݉\�����v
�i���c�T�V�̂����u����I�W�R�����v�A�����R�T�O�ł������j�ł���B���̐���
���Ă͏ڏq����X�y�[�X���Ȃ����A�����q�ϓI�댯�����������Ƃ�F�߂�
�͈͂��L���A��q�̔ᔻ��Ƃ�Ă���B
����͎R��������Ƃ��āA�s�\�Ƙ_�̍Č������Ȃ���邱�ƂɂȂ�Ǝv���B
�Ƃ���ŁA�����l���O���Ă���悤�Ȃ̂ł��A���낻��b��]�����܂��B
�Ⴆ�A���Ƙ_�Ƃ��B
���̗���́A�܂��ɋq�ϓI�A���_�I�Ȃ��̂Ƃ�����ł��傤�B
�댯�̌��������́A���ʊW�ɂ����đS������l�����������ŁA
�K�͓I�ϓ_����A�����������A��������ɒl���錋�ʂƁu�]���v�ł��邩����ɂ���B
�����A�s�\�Ƙ_�ɂ����Ă��A�S������l��������ŁA�����������ۂɂ���
�K�͓I�ϓ_����A�����������A��������ɒl���錋�ʂƁu�]���v�ł��邩��
���ɂ���Α����Ƃ������Ƃł���B�����ł́A��ʐl�̊댯����
�s�҂̔F�����l�����ꂤ�邪�A����͊�b����_�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A
�O���܂ŋK�͓I�ɋA�ӂ��ׂ����ۂ��̍l���v�f�̈�Ƃ����ɉ߂��Ȃ��ƍl���邱�ƂɂȂ�B
����́A���ʓI���Ƙ_�̎v�l�́A�����_�Ȃ̂��A���Ƙ_�̓K�p���ʂȂ̂��Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ킿�A��ʂɁA���Ƃɂ����ẮA�P�ƔƂƔ�ׂāA���ʊW���g�������Ɛ��������B
����ŁA���Ƃ���b�t����̂́A���ʂւ̈��ʓI��^�ɂ���Ƃ���B
�������A���Ƃ̓K�p�O��Ƃ��Č��ʂւ̈��ʓI��^���F�߂���̂ł���A
���Ƃ̓K�p���ʂƂ��Ĉ��ʊW���g���������v�͂Ȃ����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�Ⴆ�A�b�Ɖ����u���E�Q�����ꍇ�A�b���ɋ������ƊW������A���̍s�ׂ�
����Ď��̌��ʂ����������ꍇ�ł����Ă��A�b�͂u�̎��ɂ��ċA�ӂ����B
���̍����́A�b�͉�����Ău�̎�������������ł���A�ƁB
�������A�b���u�̎��ɑ��Ĉ��ʐ����y�ڂ����̂ł���A�������Ƙ_�ɂ��
���ʊW�̊g����v����܂ł��Ȃ��A�u�̎����A�ӂł���̂ł͂Ȃ����B
���̂悤�ɁA���ʓI���Ƙ_�́A���Ƃ̍����ƌ��ʂ��������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��ł��B
�Ƃ����̂́A���_�I���݂��s�\�ɏI��������Ă��Ƃ���ˁB
�Ӗ��s��
���ʊW�̊g���̈Ӗ��ƌ��ʂւ̈��ʓI��^�̈Ӗ��̈Ⴂ��
�����Ă͂���܂����H
���鍀�ڂ��A�g�����_���ɗ���B
�@�s�x�z��
�A���Ƃ̏��������i��N���j
�B�Ԑڐ��ƊT�O�̕K�v��
�C���ƂȂ����Ƃ͔F�߂��邩
�D���d�������Ƃ̍m��
�E�����Ƃ̌̈Ӂi�����̋����j
�F�̈��ʊW
�G�����I�i����I�j�s�ׂɂ���
�����ɂ��āAA����̍l�������������l���Ă���������ƗL��B
�������A�I�C�����\������菑�����ށB
�@
���ƓƗ����������ʓI���Ƙ_���̂��ĉ���������������܂��B
�Ƃ������A���ʓI���Ƙ_�͋��ƓƗ������̋A������B
�q��{���苖�ɂȂ����A�m���q��͈��ʓI���Ƙ_���̂��Ă����Ǝv���B
���ʓI���Ƙ_���̗p�����Ƃ��Ă����ƓƗ������Ɏ���킯�ł͂Ȃ��B
�b�����������Ău�ɖ\�s�������A���̖\�s�ɂ���Ău�����S�����B
���̏ꍇ�ɁA�b�͂U�O����K�p���ď��߂Ău�̎����A�ӂł����
��������邪�A�b�͉�����Ď��̌��ʂ��������ȏ�A
�U�O���̓K�p��҂܂ł��Ȃ����̌��ʂ��A�ӂł���悤�ɂ�
�v���邪�A�����Ȃ�Ȃ����R�͉����Ƃ������Ƃł��B
�l�����Ƃ������A�����̂���_���v�����܂܂ɊȒP�Ɏ����܂��B
�@�ړI�I�s�ט_�Ƃ̘_���K�R���͂��邩�B
�@���ʖ����l�̗��ꂩ���邱�Ƃ͉\���i�u���ƂƂ��Ă̈��ʓI��^�v�͍s�x�z��
�u�������邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ����j
�A�C�̊W�͘_���K�R�Ȃ̂�
�B�����́A�Ӗ��s���ƌ���ꂽ���ӎ��Ƌ��ʂŁA
�@�v����Ɍ��ʂɈ��ʐ����y�ڂ��Ό��ʂ��A�ӂł��A
�@�s�x�z������ΐ��Ɛ�����b�t�����邩��A
�@�Ԑڐ��Ƃ⋤�����ƂƂ������ނ͎��͕s�v��������Ȃ��Ƃ���
�@���ӎ��͂���B
�D�ے���������邱�Ƃ̌���I�Ӌ`��₤�i����ύX�̉\���͌���Ȃ��R�����j
�E�̌̈ӂ̕�������������i�E�B�j�[���������������Ƃ��āj
�@���̓W�J����ł�����ɂ��e�������邩���l�������B
�F�@�q�ϓI�A���_�̉e�����C�ɂȂ�B
�G�@�E�B�j�[�������̌̈Ӂi��ϓI�A���j�ōi�������ƂɈ�a��������
�b�Ɍ��ʂ��A�ӂł��邯��
60�����Ȃ��Ȃ狷�`�̋��Ƃ���ˁB
207���͉��ɂ����Ă������B
���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����狤�����Ă��Ă��ˁB
�P�Ɛ��ƂɂȂ�Ȃ��Ƃ����F���̂悤�ł����A
����͒P�Ɛ��Ɛ����ɕK�v�ȗv���̂�����
�ǂ̗v���������Ă��邩�炾�Ƃ��l���ł����H
60�����K�肳��ĂȂ��Ɖ��肵���ꍇ�A�܂����Ƃ�
���ۂ��������邪�A����̎�Ŏ��s���ĂȂ�����
���ڐ��Ƃł͂Ȃ��B�ł͊Ԑڐ��Ƃ͂ǂ����B
���̓�����m�肳��邩�Ƃ����Ƌ^�₾�ȁB
�K�͓I��Q������ł���B����łȂ��킯���B
������Ԑڐ��Ƃ��s�����B�ȏ�͎��S���ʂ�
�A���Ɋւ���c�_���B
�u�̎��S���ʂ͉��̖\�s�ɋA������̂ł���A
�b�̖\�s�ɂ͋A�����Ȃ��B
�b�̖\�s�߁i�܂��͏��Q�߁j�Ɖ��̏��Q�v���߂̓����ƂƂȂ�B
�b���ԐړI�Ɏ��S���ʂƈ��ʐ�������Ƃ����Ȃ�
�����Ƃ��ƂɂȂ�B
�b�ɖ\�s�߁i�܂��͏��Q�߁j�Ə��Q�v���߂̋����ƂȂ����Ƃ�
��������B�ł�������ӌ���������邩������Ȃ����A
�\�s�߁i�܂��͏��Q�߁j�͏��Q�v���߂̋����Ƃɋz�������
�����ƂƂȂ�B���ƂƋ����Ƃ͖@��Y������������ˁB
�{��̏ꍇ�A�����Ƃ̂ق����d���B
���݂����ȕ���̂ق������O�̕�����������₷���o�邾�낗
(118���ł͂Ȃ���)
����̖\�s�ɂ���Ău�����S�����̂ł����
�b�̍s�ׂ������Ă����S���ʂ���������̂�����
�����W���Ȃ���Ƃ����̂͂ǂ�?
���ڐ��Ƃ��Ԑڐ��Ƃ��������Ȃ�����P�Ɛ��ƂɂȂ�Ȃ��Ƃ���
�������Ǝv���܂����A����͗v����ɒP�ƔƐ����v���̂����A�u���s�s�ׁv��
�����Ă���Ƃ��������Ƃ������Ƃł����ł����H
>>123
�����W���Ȃ��Ƃ���A�b�͌��ʂɈ��ʐ����y�ڂ��Ă��Ȃ����ƂɂȂ�̂ŁA
���ʓI���Ƙ_����͋������Ƃ���b�t�����Ȃ�����Ƃ������ƂɂȂ�B
���̂悤�ȗ�������́A�U�O�������݂��Ă����ʂւ̈��ʐ����y�ڂ��Ă��Ȃ��ȏ�A
���Ƃ̏����������������߂ɋ������Ƃ͐������Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��ˁB
���S���ʔ����̊댯����L������s�s�ׂ́A
�b�ɂ͂Ȃ��ƍl����ׂ����ƁB
�܂�60�����Ȃ��Ȃ�
�d�v�Ȗ������ʂ����Ă����Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ�
�ł��傤�B
�����b�ɖ����̌��x�Ŏ��s�s�ׂ͂����
�����l����������l������ł��傤�B
���̂悤�ȍl��������́A�U�O�������ʊW���g������Ƃ����ʐ��̍l������
���ł���A���s�s�א����g��������̂ł���Ƃ��������ɗ����ƂɂȂ�܂����A
����ł�낵���ł��ˁH
���x���Ⴗ���ă����^w
�������ȁB���႟123�͓P�āB�B�B
�P�Ɛ��Ƃ�F�߂邽�߂ɂ́A���ʂɑ���100%�̈��ʐ����K�v�ł���
���A�ݗ�̏ꍇ�A�b�̍s�ׂ����ł͌��ʂ������邱�Ƃ��ł��Ȃ�
������A���̍s�ׂƍ��킹��100%�ɂ��邽�߂ɕK�v�Ȃ̂�60���ł���
����łǂ�?
���ʊW�̊T�O����l���āA�����I�ɂ͍l�����Ȃ��ł��傤�B
���ʊW�́A�u����v���u�Ȃ��v���ł��B
���ɂ����l������Ƃ��Ă��A���ʓI���Ƙ_����́A
�u���ƂƂ��Ă̈��ʐ��v���������Ƃ̗v���ł���B
�M���̂����P�O�O���̈��ʐ����F�߂��Ȃ��b�ɂ��āA
�ǂ����āu���ƂƂ��Ă̈��ʐ��v������Ƃ�����̂ł����H
���������ł͐��Ɛ����Ɛ�����b�Â����Ȃ��ƍl����B
���ʊW�͏����̊�b�ɂ͂Ȃ邪���Ƌ��Ƃ̋�ʂ̊�b�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���ǁA���ƁA���Ƃ��ǂ̂悤�ɍl���邩�B
���ڎ��s�`�Ԃ̒P�Ɛ��ƁA�������ƁA��
�Ԑڎ��s�`�Ԃ̋����A�Ԑڐ��ƁA�A���d��������
���������ꂼ��ϋɓI�ȍ����Â������Ȃ��Ɖ����ł��Ȃ��B
��������ƁA�U�O�����K�p����邽�߂ɂ́A
�u���ƂƂ��Ă̈��ʐ��v���Ȃ킿�M���̂����u�P�O�O���̈��ʐ��v��
�s�v�ł���Ƃ����l�����ł����H
����������ʂɑ���100%�̈��ʐ���Ƃ������̂́A�����I�Ȃ��Ƃł͂Ȃ���
(����I�Ȑl�͕ʂƂ���)���̐l��l�Ō��ʂ��������Ƃ����Ȃ����
�P�Ɛ��ƂƂ��Č��ʂ��A�ӂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�
(���ʊW����Ȃ��)�Ƃ����Ӗ��ł͂���������
������ƕ����Ă݂����̂�����
�Ⴆ�AX��A���E�����Ɠł����܂������v���ʂɏ�������Ȃ�����
Y��A���E�����Ɠł����܂������v���ʂɏ�������Ȃ�����
�������A���������Ƃ�A�͎��S�����A�Ƃ����悤�ȏꍇ
XY�ԂɈӎv�a�ʂ��Ȃ������Ƃ�����A���l�̍ߐӂ͂ǂ��Ȃ�ƍl�����?
(���ƕs���Ȃ̂ŋ����Ăق�����)
���ʓI���Ƙ_�����
�P�Ɛ��ƂɕK�v�Ȣ���ʐ���Ƌ������Ƃ̂����̈�l�ɕK�v�Ȣ���ʐ����
�����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��?
>>132
���́A����ƌ����Ȃ����I�L�Ӎs�ׂ̉�݂��l���邽�߁A
�P�Ɛ��Ƃł����Ă��A>>133�̂����u100%�̈��ʐ��v�͕s�v�ƍl���܂��B
60���͂��������Ɋg�傷����́A�]����60��K�p�ɍۂ��Ă��s�v�ł���ƁB
���肢���܂��B
����AC�ŁB
���b�����������Ău�ɖ\�s�������A���̖\�s�ɂ���Ău�����S�����B
�̈ӂ̓��e���s�������A�\�s�̌̈ӂ����Ȃ������Ƃ��悤�B
���ɏ��Q�v���߂��������A�b�ɏ��Q�߂���������B
�U�O������݂�����ƍb�Ɖ��͏��Q�v���߂̋������ƂƂȂ�B������A
���b�͂U�O����K�p���ď��߂Ău�̎����A�ӂł����
�Ƃ����_�͂��̂Ƃ���B������ǂ��A�Ȃ�
���b�͉�����Ď��̌��ʂ��������ȏ�A�U�O���̓K�p��҂܂ł��Ȃ����̌��ʂ��A�ӂł���
�Ƃ͒N���l���Ȃ��B�����l���Ȃ����R��m�肽���Ƃ̂��Ƃ����A
���ʊW�̊g���ƈ��ʓI��^�̈Ⴂ���������ĂȂ����Ƃ��������B
>>�Ⴆ�AX��A���E�����Ɠł����܂������v���ʂɏ�������Ȃ�����
>>Y��A���E�����Ɠł����܂������v���ʂɏ�������Ȃ�����
>>�������A���������Ƃ�A�͎��S����
����͎E�l�̓����Ƃł��B
>>���ʓI���Ƙ_�����
>>�P�Ɛ��ƂɕK�v�Ȣ���ʐ���Ƌ������Ƃ̂����̈�l�ɕK�v�Ȣ���ʐ����
>>�����łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��?
���ʓI���Ƙ_�́A���ƂƓ������ʐ����y�ڂ������琳�Ƃƕ]���ł���ƍl����ȏ�A
�P�Ɛ��Ƃ��������Ƃ����ʐ��ɂ����ē����ƍl���Ȃ��Ƌ��ʂ�Ȃ��ł��ˁB
�ł͉����Ȃ�P�Ɛ��ƂɂȂ�̂ł����H
���ꂩ��A�����I�ɍl���邱�Ƃ��ł���̂͏����W�ł����A
�������ʊW�ł����A����Ƃ��q�ϓI�A���ł����H
>>���ʊW�̊g���ƈ��ʓI��^�̈Ⴂ���������ĂȂ����Ƃ��������B
�ł́A���̈Ⴂ����̓I�ɓE�����ĉ������B
133�ł�
����͎E�l�������̓����ƂƂ�����|�����
(������Ƙ_�_�͈��邩������Ȃ�����)
���̏ꍇ�A���ɢ�������ʊW�ࣂɗ���
X�ɂƂ���Y�̍����s�ׂ͢�s��̎���
�ʏ�\�������Ȃ����낤����
���f���Ƃ��čl������Ȃ����
��������ƁAX�̢�v���ʂɑ���Ȃ��Ŗ��s�ף����
���S���ʂ��������邱�Ƃ͒ʏ�Ƃ͌�����
���ʊW�͔ے肳���Ǝv���̂���
��댯�̌������ࣂɂ���
X�̍s�ׂ�A�̎��S���ʂƂ̈��ʊW��
�m�肳��邱�ƂɂȂ�̂���?
�������ܒ�������\���\���Ȃ��Ƃ��Ĉ��ʊW��ے肷��]�n������܂����A
�q�ϓI�A���̗��ꂩ��A����ے肷��]�n���Ȃ��킯�ł͂���܂��A
�c�_����������̂ŏژ_�͔����܂��B
>���Ƃ̓K�p�O��Ƃ��Č��ʂւ̈��ʓI��^���F�߂���̂ł���A�c�@
>���Ƃ̓K�p���ʂƂ��Ĉ��ʊW���g���������v�͂Ȃ����ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�c�A
�@���F�߂�ꂽ�Ƃ��Ă��A���s�@��A�����ɂ����Ȃ�Ȃ��B
>�Ⴆ�A�b�Ɖ����u���E�Q�����ꍇ�A�b���ɋ������ƊW������A���̍s�ׂ�
>����Ď��̌��ʂ����������ꍇ�ł����Ă��A�b�͂u�̎��ɂ��ċA�ӂ����B
>���̍����́A�b�͉�����Ău�̎�������������ł���A�ƁB
�b�͉�����āi�ԐړI�Ɂj�u�̎����������̂ł��邩��A
���ʔ����Ɍ��������ʓI��^�������ł̐����ɓ��Ă�̂ł���A
�����̐��ۂ���Ƃ�����ʊW�̊Ԑڐ������ƂȂ�B
����𐳔ƂƂ���ɂ�60���̓K�p��ւ����Ȃ��B���̈Ӗ���
���Ƃ̓K�p���ʁi��60���̓K�p���ʁj�Ƃ��Ĉ��ʊW���g���������v�́u����v�B
���ƂƋ����Ƃł́A���ʊW�̒��ڐ��E�Ԑڐ��Ƃ������Ⴊ����B
�������Ɓi���ɋ��d�������Ɓj�͈��ʊW���ԐړI�ł����Ă�
����𐳔ƂƂ��������������ď��߂Đ��Ɛ����l���ł���B
���ꂪ60���̓Ǝ����Ƃ�����B
60����P�Ȃ�m�F���ӋK���Ƃ��đ����A
���s�������Ƃɂ��āA�e���͈ꕔ���s�҂��ꕔ�����҂ł���Ƃ��A
���d�������Ƃɂ��āA�S�����s�҂Ƌ����҂ł���Ƃ���̂ł���A
����͋������ƊT�O�̔p�������錾�����邱�ƂɂȂ�ł��낤�B
�Ȃɂ䂦�������ƂƂ���̂��ɂ��A�O�ꂵ�����ʓI���Ƙ_����͉�����̂ł��낤���B
���ʂƍ����̍����ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂́A�������Ƃ̐��Ɛ��Ƌ��Ɛ��̗��ʂ�����
�O�ꂵ�����ʓI���Ƙ_�̎˒�����������^��ł��낤�ȁB
�M���̎咣�́A�P�Ɛ��ƂɕK�v�ȗv���̂����A
�u���s�s�א��v�Ɓu���ʊW�v�̂ǂ���������Ƃ����咣�ł����H
�Ӗ����悭�킩��Ȃ����i��ꂪ�Ȃ����߁j
��̈Ӗ����킩�����悤�ȋC������B
60���̓K�p���Ȃ��i�K�莩�̂��Ȃ��j�Ɖ��肵���ꍇ�ɁA
�b�Ɖ����������Ău���E�Q���邱�Ƃ��v�悵�Ď��s�ɋy���A
���̎��s�s�ׂ����u���S���ʂ��������ꍇ�A�b�����ƂɂȂ�Ȃ�
���R�Ƃ��āA���s�s�ׂ��Ȃ��̂��A���ʊW���Ȃ��̂�����
���Ƃł��낤���B
���Ƃ�����A���Ɛ����ɕK�v�Ȉ��ʊW���Ȃ����Ă��ƂɂȂ낤���B
�s���m�����B
���ʊW�͂��邪�A�ԐړI�����琳�Ƃ��肦�Ȃ��Ƃ����ׂ����B
�U�O���̓K�p���Ȃ��Ă����s�s�א��͔F�߂���Ƃ������Ƃł����H
�ł���A���s�s�א����F�߂��鍪���������Ă��������B
����܂�����̎�|���킩��ɂ������A
��L�̗Ⴞ�ƁA�Ⴆ�A�b�������s�X�g���̈����������������A
���̋ʂ������������Ƃ����炩�ł������Ƃ���ƁA�b�̎��s�s�ׂ�
�F�߂���̂ł͂Ȃ����ȁH
���s�s�ׂ̍�����₤�����H�̈Ӗ����悭�킩��Ȃ��B
���邢�͍b�����s�ɂłȂ����d�����������Ƃ���ƁA
�b�Ɏ��s�s�ׂ͂Ȃ��Ǝv�����B�Ȃ���������Ă�
�������Ȃ��B�����炪����̎�|��������ĂȂ���B
60���́A���s�s�ׂ���ʊW��⊮����K��ł��傤�B
�ǂ��炩��⊮������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����B
60�����Ȃ���A���s�s�ׂ����Ȃ����d�҂͋����Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
������A���������Ӗ��Ŗ₢�����ɓ�����Ȃ�
60���̓K�p���Ȃ��̂ł���Ύ��s�s�א��͔F�߂��Ȃ�
�Ƃ������ƂɂȂ낤���B
�Ȃ�قǁA���s�������ƌ`�Ԃł͎��s�s�ׂ͓��R�F�߂���Ƃ�������ł��ˁB
����ň��ʊW���Ȃ��Ƃ������Ƃł����A
�F�߂��Ȃ��̂́A�����W�ł����H�������ʊW�ł����H
���d�������Ƃł͎��s�s�א����Ȃ��Ƃ������Ƃł����A
���̏ꍇ�A�w��҂ɂ��Ă͋������Ƃ̗v���ł���u�������s�̎����v�͕s�v�ł���B
���Ȃ킿�A�K�͓I�ɂ����s�s�ׂƕ]������鎖�������݂���K�v���͂Ȃ��B
������������ƍl���Ă����ł����B
���Ȃ킿�A���݂̋@�\�I�s�x�z�܂��͗��p��[�W�Ɋ�Â��Ď��s���Ƃ�
���p����s�ׂɎ��s�s�א�������Ƃ��A���s���Ƃɕ��S���ɉe�����y�ڂ���
�P�Ɛ��Ɠ��l�ɖ@�v�N�Q���ʂ���N����_�ɔw��҂̎��s�s�א������o���Ƃ����l�����ɂ�
�����Ȃ��B�w��҂ɂ͏�L�̂悤�ȋK�͓I�Ȏ��s�s�א�����S���s�v�ł���
�Ƃ�������Ƃ������Ƃł�낵���ł����H
�e�_�_�ɖԗ��I�Ɋ֘A���鍪�{���ł���ƍl���Ă��邩��ł��B
�͂��H���̗��ꂾ�Ƌ��d�������Ƃ͔ے���ɂȂ邾��B
���s�s�א��͕K�v����B���s�s�א����Ȃ���A���Ƃ���Ȃ��B
�S�����s�ł͂Ȃ��ꕔ���s�Ƃ����Ӗ��ł́A�F�߂��܂��ˁB
���ʊW�̒��ڐ��ƊԐڐ��̈Ⴂ�̖��ƁA
�����W���������ʊW���̈Ⴂ�̖��́A
�����̈قȂ���Ƃ����ׂ��ł��낤���B
�����Č����Ȃ�A���������f�̖��Ɉʒu�Â�����Ǝv�����B
>>153
���d�������Ƃ̋��d�҂͎��s�s�ׂ��Ȃ��A�������s�̎����̗v�����[�����Ȃ�
�Ƃ����̂��c�_�̏o���_�ł͂Ȃ��������H
�K�͓I�ɂ݂Ď��s�s�ׂ�F�߂�Ȃ�Ԑڐ��ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����H
���ؐ��ɂ��Ă��Ԑڐ��Ɓu�ގ��v���ƌ�����̂��A���s�s�א��͂Ȃ����Ƃ��O��
�ł͂Ȃ����Ǝv�����B
���������s�s�א��ł͂Ȃ����Ɛ����m�肷��q�ϓI������d�������Ƃ̗v����
�Ȃ��Ă��邱�Ƃ͍m������ʂ̔F���ł��낤�B�ǂ����_�\������̂��ɈႢ������Ƃ��Ă��ˁB
�����炭�A���Ȃ��͐����I���ƊT�O��O�ꂷ�邱�Ƃɂ��A
�Ԑڐ��ƊT�O�ے�A�������Ɣے�A�ɂ�肱���������ɗ��Ƃ����ނ��Ƃ�
���_�I�Ɉ�т���ƍl���Ă���̂ł��傤�B
�������Ƃ����ʐ���{�Ŋ�b�t���闧���O�ꂷ��A�\�ȍl�����ł��傤�B
����n�͊m���ތ^���T�O�ɂ��A�O��͂��Ă��Ȃ��Ɨ������Ă܂��B
�Ȃ����n�Y�@�w�҂̈ꕔ�̕��X�Ɠ����l�����ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB
�ʂɊԈႢ�Ƃ͎v���Ă܂��B
���ƍs�x�z���ɂ�鐳�Ɛ��̊�b�Â��͋��{�������݂����ł����A
�Ⴆ�A�������Ƃɐ��Ɛ��i�x�z���j�Ƌ��Ɛ��i���ʐ��j�̑��݊W��
�����������m�ɂ��Ă����A���n�Y�@�w�҂̈ꕔ�Ƃ͈قȂ�̂ł�
�Ȃ����Ɨ���������Ƃ��l���܂��B
�O�c���ɂ́A���ʐ������܂�Ɛ��Ɛ����l������Ƃ������������邪�A
����͑O�c���Ǝ��̂��̂��A���싳���̔F���Ȃ̂����C�}�C�`�������Ȃ��̂ŁA
�m���Ă���l��������A�o�T�������Ă��炦��Ƃ��肪�����B
���ʊW���u���ځv�ł��邩�u�Ԑځv�ł��邩�́A�P�Ɛ��Ɛ����̗v���ł͂���܂���ˁB
�M���̌����ł��Ԑڐ��Ƃ́u���ځv�̈��ʐ�������Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł����A
���ʊW�́u���ڐ��v�Ƃ͂ǂ�������`�Ŏg���Ă���̂ł����H
���ꂩ��A�������������Ƃ������Ƃł����A�b�����������Ău�����S������ꍇ�A
�b�͉��̍s�ׂ����ɔF�����Ă���킯�ł�����A���̍s�ׂ͐ܒ����ɗ����Ă�
��b����ɓ���킯�ŁA��������ے肵�������Ǝv���܂����A
����ɂ�������炸��������������ƍl���闝�R�������Ă��������B
�Ȃ��A���d�������Ƃ̋c�_�̏o���_�Ƃ��āu���s�s�ׁE�������s�̎������Ȃ��v��
���������̂́A�u�`���I�ȈӖ��ł́v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�����I���ƊT�O�E�����I�q�ϐ��ɗ��ʐ��̍l�������炷��A
���d�������ƂƂ́A�`���I�Ȏ��s�s�ׂ͂Ȃ����A�K�͓I�ɂ݂Ď��s�s�ׂƂ݂�ׂ��ꍇ�ł��B
�ł�����A>>�P�T�T����̎w�E�̂Ƃ���A�K�͓I�ɂ����s�s�א����Ȃ��ƍl�����
���d�������Ɣے���ɂȂ��Ă��܂��킯�ł��ˁB
�����m�F�����������̂́A�M�����U�O���̓K�p�O��Ƃ��Ď��s�s�א��������I�Ӗ��Ƃ��Ă�
�s�v�ƍl���Ă��邩�ǂ����ł����B����͈�ʓI�ȍl�����Ɩ��炩�ɈقȂ邩��ł��B
>>158
���ɂ��̂悤�Ȏ�|�ł͂���܂���B����́A�����̐^�ӂ�₤���߂̂��̂ŁA
�����̌����ɗU������Ƃ��A�ᔻ����Ӑ}�łȂ���Ă���킯�ł͂���܂���B
>���ʊW���u���ځv�ł��邩�u�Ԑځv�ł��邩�́A�P�Ɛ��Ɛ����̗v���ł͂���܂���ˁB
���ʊW�̒��ڐ��͋����̈��ʊW���ԐړI�ł��邱�Ƃ̗��Ԃ��̋c�_�ł���A
���ɂǂ̌Y�@�w�҂���`���邱�ƂȂ��Öق̑O��Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B
>�M���̌����ł��Ԑڐ��Ƃ́u���ځv�̈��ʐ�������Ƃ������ƂɂȂ�͂��ł����A
�Ԑڐ��Ƃ��험�p�҂͓��������ʊW�̒��ڐ����O��ƂȂ��Ă��܂��B
>���ʊW�́u���ڐ��v�Ƃ͂ǂ�������`�Ŏg���Ă���̂ł����H
���ڐ��Ƃ͐��Ƃƌ��ʂ̊Ԃ���ɂ���ꍇ�ł���
�Ԑڐ��Ƃ͋��Ƃƌ��ʂ̊Ԃ���ɂ���ꍇ���w���Ă��܂��B
>���ꂩ��A�������������Ƃ������Ƃł����A
�c�_�����ݍ����ĂȂ��悤�ȋC������̂ŁA�m�F���Ȃ���b��i�߂�ƁA
60�������݂��Ȃ��Ɖ��肷��Ƌ������Ƃ��������邱�Ƃ͂Ȃ��B�������ƊT�O�s���݂ƂȂ�B���ꂪ��O��B
����āA�������ƌ`�Ԃ̔ƍs���������ꍇ�A�������P�Ɛ��Ƃ̂ǂ��炩�ɂȂ�B
�P�Ɛ��Ƃ���������̂́A�����ƁA�Ԑڐ��Ƃ̂ǂ��炩�B
�����ƂȂ�A�b�ɎE�l���������B�u���S���ʂ͉��Ƃ̊Ԃň��ʊW���F�߂��A
�b�Ƃ̊Ԃł͈��ʊW�͂Ȃ��B���Ƃɂ͒��ڂ̈��ʊW���K�v������B
�ԐړI�Ɉ��ʐ����y�ڂ��Ă��A���ꂾ���ł͑���Ȃ��B
���Ƃ̊Ԃɋ������������Ă�60�����Ȃ��ȏ��ނ����Ȃ��B
�܂��A�b�Ɖ��ɓ���̋K�͂��^�����Ă���ȏ㉳������肦�Ȃ��̂ŁA
�b�͊Ԑڐ��Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���s�s�א��Ɍ�����B
�ȏ�̌��ʁA�b�͋������B���s�s�ׂɋy��ł������̕]�������^�����Ȃ��B
����͕ʂɂ������ȋc�_�ł͂Ȃ��B�������Ƃƛ̋�ʂ̘_�_��z�N����悢�B
>���d�������ƂƂ́A�`���I�Ȏ��s�s�ׂ͂Ȃ����A�K�͓I�ɂ݂Ď��s�s�ׂƂ݂�ׂ��ꍇ�ł��B
���d�������Ƃɂ��K�͓I�ɂ͎��s�s�ׂ͂���A�������s�̎����̗v�����[������Ƃ������Ƃł����H
�N������Ȃ��Ƃ������Ă���̂ł��傤���ˁH�Y�@�w�҂̖��O�������Ă���܂��B
��ʓI�Ƃ����̂ł���B�O�c�ł����H�R���ł����H��˂ł����H��J�ł����H����ȊO�̐l�ł����H
���ʂ́A���s�͂Ȃ������Ƃł���A�܂���s�����ƂƂ����O��ɗ����āA
���s�s�ׂ��Ȃ��Ă����Ɛ����m�肷��킯�ł��B
���s�s�ׂ��Ȃ���ΐ��Ƃł͂Ȃ��A�Ƃ����̂͒c���E��˂̂悤�ȗ���ł��B
���Ȃ��́A���s�����ƂƂ����O��ɗ����Ă��܂��ˁB�������Ƃ�����ꂱ����ʓI�ł͂���܂���B
���ɏ����܂������A���ؐ��ł����s�s�ׂ͋K�͓I�ɂ����d�҂͍s���Ă��Ȃ����Ƃ�O��Ƃ��Ă܂��B
�M���̂������ʊW�̒��ڐ��Ƃ́A���ƂƋ��`�̋��Ƃ�����̂Ƃ��Ďg���Ă���悤�ł��ˁB
�Ƃ���A�ԐړI�Ȉ��ʐ������Ȃ��ꍇ�ɂ́A���Ƃ��U�O���������Ă��A
�������Ƃł͂Ȃ��A���`�̋��Ƃ����������Ȃ��͂��ł����A
�ԐړI�Ȉ��ʊW��������U�O����K�p���邱�Ƃɂ���Đ��Ƃɂł���Ƃ��������ɂ���
�ǂ��l���܂����H
�������Ƃɂ�����C�����ꂽ�\���v���ɂ����Ă�
���s�s�א��͕s�v�ł����āA���Ɛ�����b�t���鎖���ő����
�Ƃ������ꂪ��ʓI�ł���Ƃ����F���ł��ˁB
����͌��t�̖��i���Ɛ�����b�t���鎖�����K�͓I���s�s�ׂƌĂԂ��ǂ����ɂ��j
�ł����A���̋c�_�Ƃ͒��ڊW���Ȃ��̂œ��ɑ����܂���B
�������Ă��炦��Ə�����܂��B
���Ȃ킿�A���ʓI���Ƙ_�Ɓu�U�O���͈��ʊW���g������K��ł���v�Ƃ�������͗������Ȃ��B
���̖��ɂ��Ă̎������A�ȉ��ɂ܂Ƃ߂ďq�ׂ�B
�u�b�����Ƌ��d���A�����u���E�Q�����v�Ƃ�������ɂ����āA�b�ɂu�̎��ɂ��Ă�
���ʊW���F�߂��邱�Ƃ́A���ʓI���Ƙ_����͂U�O���̓K�p�O��ł����āA�K�p�ɂ����ʂł͂Ȃ��B
�i�ԐړI�Ȉ��ʊW���A�U�O���ɂ���Ē��ړI�Ȉ��ʊW�Ɂu�i�グ�v����邱�Ƃ͂Ȃ��B�j
�U�O���́A�Y�@���_�セ�̎҂Ɍ��ʂւ̈��ʊW��F�߂���ꍇ�ɓK�p������̂ł���A
�Y�@���_����ʊW���Ȃ��ɂ�������炸�A�u���������̂Ƃ݂Ȃ��v���ʂ�L����
�Q�O�V���Ƃ́A����قɂ���K��Ȃ̂ł���B�����炱���A�Q�O�V���͊w����ᔻ�����邪�A���l�̔ᔻ��
�U�O���ɂ͌������Ă��Ȃ��B
�����ɁA�U�O�������ʊW�̊g���K��ł���Ƃ�����ʓI�Ȑ��������ł��邱�Ƃ����炩�ƂȂ�B
�ł́A�U�O���͖��p�̋K��ł���A�U�O�����Ȃ��Ă��b�ɂ͒P�Ɛ��Ƃ�����������̂��B
�����͔ۂł���B�Ȃ��Ȃ�A�̈Ӑ��Ƃ̔w��҂́A���̓��Y�̈Ӑ��Ǝ҂Ƌ��ƂƂȂ�Ȃ�����A
��������Ȃ��i�k�y�֎~�j����ł���B������Ƃ���A�U�O���́u���ׂĐ��ƂƂ���v�ƋK�肵�Ă���A
�k�y�֎~���K�p����Ȃ����������Ƃ͒P�Ɛ��Ƃ̏W���ł͂Ȃ��A���ƌ��ۂł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă���B
���̓_�ɁA�U�O���̑��݈Ӌ`������B
���Ȃ킿�A�U�O���́A�k�y�֎~��r�˂��Ĕw��҂��܂߂Đ��ƂƂ���_�ŁA
�u�q�ϓI�A�����g������v�K��ł���B���̂��Ƃ́A���`�̋��ƋK������l�ł���A
�������k�y�֎~��r�˂��Ĕw��̊֗^�҂������\�ɂ���K��ł���B
�ȏ�ł��B�ᔻ���}���܂��B
�������Y�@�w�҂̃N�I���e�B�͈�ʏ펯����E���Ă���ȁB
�Y�@���w�ԂƂ������Ƃ�̌����Ă���悤����
�ᔻ�������w���̗��t���̂Ȃ���l�悪��́u�ӌ��v�ȂǒN������ɂ��Ȃ���
�܂��60����P�ƔƂ̋K��Ƃ��ė������Ă���悤���ˁB
�ł��w�҂̈ӌ������瑸�d���ׂ������
�y�؍��z��緑�w�@�w��������e����������W�c�ɂ������A�����`��ʖڂɂ����E�k�҂̓z���S�����Y�ɂ��ׂ��[11/28]
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1385610063/
���͂�����h�f�l�Ȃ̂ŁA���̂悤�Ȏ��������̂͂ǂ����Ƃ��v�����̂ł����A
�Y�@�ɂ��ڂ������Ɏ��₪�ł��邱�Ƃ��H�L�ȋ@��ł�����܂����A�s�^�Ȃ��玿�₳���Ă������������Ǝv���܂��B
���Ȃ��̂��������k�y�֎~�ɂ��q�ϓI�ȋA�����g�������Ɏ���w��҂̋�̓I�s�ׂƂ����̂́A
�ǂ̂悤�Ȃ��̂�z�肳��Ă�����̂ł��傤���H
���ǁA�{�l�ȊO�̒N���A���ӎ������L�ł��Ȃ������킯���B
�������Ȃ̂������ł��Ȃ��̂�����B
>>168�̕������疾�炩�Ȓʂ�A�������Ƃ���������ꍇ�̍s��ʂ��w���܂�
�����A�����������Ƃł͂Ȃ��āA�Ⴆ�Ώ��p�I�������Ƃ̏ꍇ�ɁA
�����ɑk�y���F�߂�ꂽ�Ƃ��Ă��A���p�O�̑��҂̍s���ɉe����
��������Ƃ������Ƃ́A�����I�ɂł��Ȃ��킯�ł��āA���������
�����Ȃ�K�͓I�Ȕ��f�Ɋ�Â��Ă����Ȃ��̓I�ȍs�ׂ����҂�
���p�O�̍s�ׂ��A��������N�_�ɂȂ�̂��H�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��������������킯�ł��B
�����܂���B
���҂̏��p�O�̍s��
��
���҂̏��p�O�̍s�ׂɂ��@�v�N�Q�Ȃ������̊댯
�ȂɁA���̏ォ��ڐ�
�����܂���B���̕\�����ق����Ƃ��琶��������ł���܂��B
���̂悤�ȕ\���ƂȂ��Ă��܂������Ƃ͐\����Ȃ��v���܂��B
��L�̎�����e�ł��ƁA�������₵�������ƂƏ�������Ă����Ă���
�悤�ȋC�����܂����̂ŁA�����ƒ��B�I�Ȏ�����e�ɕς������Ǝv���܂��B
���̔\�͂ł́A��L�̂悤�ȕ��G�ȗ��_��W�J����܂��ƁA
��̓I�ɂ����Ȃ鎖����ςݏd�˂Ă������Ƃɂ��A�������Ƃ�
���ۂf���Ă������ƂɂȂ�̂��A�Ƃ����Ƃ���܂ŗ\���E�z��
���ł����˂܂��B�ł��̂ŁA�ł��邱�ƂȂ��L���_�ɂ���
�ǂ̂悤�ȋ�̓I�Ȏ����������ċ������Ƃ̐��ۂf���Ă���
���ƂɂȂ�̂��A�������͏]���̋������Ƃ̔��f��@�ɑ���
��L�̗��_�͂ǂ̂悤�ȃC���p�N�g��^���邱�ƂɂȂ邱�ƂɂȂ�
�̂��A�Ƃ����_��⑫���Ă��������Ȃ��ł��傤���B
��������������
�Ȃ�Ŏ��������́H
�����̈Ӗ��������Ă�H
�`�������H
������
��
�Ȃ���
���߂��`
���ꂪ�厖
�������肷��H
��{�I�ɂ͉��̃C���p�N�g���^���Ȃ��Ǝv���Ē����Č��\�ł��B
�ނ���A�]���̋������Ƃ̔��f��@��p�������A�U�O�������ʊW��
�g���K��Ƒ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�k�y�֎~�Ƃ̊W�ő�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���Ȃ킿�A���݂̒ʐ��ł�����ʓI���Ƙ_�́A���ʂւ̈��ʐ��Ɛ��Ɛ���
��b�t�����鎖���W������ꍇ�ɂU�O����K�p�ł���Ƃ��܂��B
���Ȃ킿�A���ʂւ̈��ʐ����������A���Ɛ��������ꍇ�ɁA�U�O����K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���������āA�U�O���̓K�p�ɂ���Č��ʂւ̈��ʐ����g�������Ƃ��A
���Ɛ����g�������i�������x�̊֗^�s�ׂ��������ƂɊi�グ�����j�Ƃ����悤��
���ʂ͂��蓾�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
������Ӗ�������Ƃ�����ł��傤�B
�Ⴆ�A>>162�̂悤�ɁA���Ƃ���b�t����ɑ���鎖���W���Ȃ��i���̕��́u�ԐړI�Ȉ��ʐ��v��
�\�����Ă��܂����j�ꍇ�ł��A�U�O����K�p����ΐ��Ƃɂł��Ă��܂��Ƃ�������ł��ˁB
���������āA�������Ƃ⋷�`�̋��Ƃ̐��ۂ́A�k�y�֎~�̓_�������A�Y�@���_��
���Ɛ��̗L���y�ь��ʂƂ̈��ʊW�������ׂ��ł���A���ƋK��̓K�p�ɂ����
�i�����I�Ɂj�����\�ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ́A�̈��ʐ���
�e�����Ă���ł��傤�B���Ƃ̎��s�Ƃ̊Ԃŏ����W������Ώ]�ƋK��̓K�p�ɂ��
�����ł���Ƃ�����́A���ʓI���Ƙ_�Ɛ����I�ł͂���܂���B
���ʓI���Ƙ_����́A�ł����Ă��@�v�N�Q���ʂƂ̈��ʊW���F�߂���K�v�����邩��ł��B
���肪�Ƃ��������܂��B����Ŏ��̂悤�Ȃ��̂ł�����ȗ��_�������o�����悤�Ɏv���܂��B
60���̌��ʂ����ʊW�̊g���ł���Ƃ����Ă��܂��ƁA�@�K�p�̂��߂̗v���ƌ���
��������܂��ɂȂ��Ă��܂��B�����͖��m�ɕ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����m�ɕ�������ƁA60��K�p�̌��ʂ́A�k�y�֎~���j���邱�Ƃɂ���Ƃ�����B
���̂悤�ȗ����ł�낵���ł��傤���H
���������Ɍ��������������Ƃł悢���Ǝv���܂��B
�@�@���@�@���@�@�@���@�@���@�@�@���@�@���@
�̑��݂̊֘A������������͂��܂�Ȃ��悤�Ɏv����B
�h�C�c�ɂ����ẮA�̈ӂ͇@�Ӑ}�iAbsicht)�A�A���ړI�̈Ӂidolus directus)�A�y�і��K�̌̈�
�idolus eventualis)�̎O�̌`�Ԃɋ敪�����B
�@�Ӑ}�Ƃ́u�s�҂��\���v���ɊY������s�ׂ��邢�͍\���v�����O��Ƃ��錋�ʂ��A�܂��͂��̗��҂�
�Nj����Ă���Ƃ������Ɓv�ł���B
�@���ړI�̈ӂƂ́u���̍\���v���v�f�����݂��邱�ƁA�܂��͍s�ג��ɍ\���v�����[�������Ƃ������Ƃ�
�s�҂��m���ɔF�����Ă���Ƃ������ƁA�Ƃ�킯�s�҂��\���v���ɊY�����錋�ʂ̔������m���Ȃ��̂Ƃ���
�\�����Ă���Ƃ������Ɓv���Ӗ�����B�����Œ��S�ƂȂ�̂͌̈ӂ̒m�I�v�f�ł���A�s�ׂ�
���肷��ڕW�\�ۂƂ����Ӑ}�ɂƂ��ē����I�ȗv�f�͌����Ă���B
�@���K�̌̈ӂƂ́u�s�҂��@����̍\���v���̎������\�Ȃ��̂Ɩ{�C�ɍl���A�����̖@����̍\���v��
�̎������ÎĂ���Ƃ������Ɓv���Ӗ�����B���������āA���K�̌̈ӂ͇@�\���v���I�̈ӂɊւ������
�ӎv�i�s�וs�@�̈ӎv�I�v�f�j�A�A���ʔ����̊댯��^���Ɏ���Ă���Ƃ������Ɓi�s�וs�@�̒m�I�v�f�j�A
�y�чB�ӔC�v�f�Ƃ��Ă̍\���v���ɊY�����錋�ʂ̔������ÎĂ���Ƃ������ƁA����\������Ă���B
�@�y�����z
�@�p�Ė@�ł́A�q�ϓI�ƍߐ����v���ł���actus reus�ƂƂ��ɔƍ߂𐬗�������v�f�Ƃ���mens rea�i��ϓI�ƍߗv�f�j������B
�����Y�E���A�ɂ́A�ʏ�A�@intention�i�Ӑ}�j�A�Arecklessnes�i���d�j,�y�чBnegligence���܂܂��B
�u�Ӑ}�v�Ƃ́u�S�̒��ɖڂ����ڕW�ɓ��B���邽�߂̊m��I�ȖړI�����������Ɓv�ł���A�u���d�v�Ƃ́u�\���͂��邪���Y����
�̔������ӗ~���Ă��Ȃ��ꍇ�v�������Ƃ��ꂽ�B�������A���݂̔���E�������́A���ʂ̗\����������Ƃ����̔������ӗ~
�idesire)���Ȃ��Ă��u�Ӑ}�v�����݂���Ƃ����������̂�B
�@negligence�́A�����͂��邪�A�킪���́u�F���Ȃ��ߎ��v�ɑ�������B�u�Ӑ}�v�́A�䂪���́u�m��I�̈Ӂv�ɑ������A
�u���d�v�́A�킪���́u���K�̌̈Ӂv�Ɓu�F������ߎ��v���܂���T�O���Ƃ����Ă悢�B
�i�䂪���̊w���[�ȗ��j
�@�h�C�c�@�Ƃ̑Ή��ł́AAbsicht��dolus directus����������䂪���̊m��I�̈ӂɑΉ����邱�ƂɂȂ�B
�C�F�V�F�b�N�ɂ��ƁAAbsicht���p������̂́A�Ƃ�킯�u�Ӑ}�v����ϓI�\���v���v�f�Ƃ��Č����Ƃ��ł���A
����ɑ��āAdolus directus�Œ��S�ƂȂ�̂͌̈ӂ́u�m�I�v�f�v�ł���B
�@��������ꂸ�ɉ]���A�ӎv��`�̂����̈ӂ�Absicht�ɋ߂��A�F����`�̂����̈ӂ�dolus directus���̂���
�ł͂Ȃ����낤���B
�@�y�I���z
�h�C�c�̗�Ȃǂ��g���ċ�̓I�ɐ������Ăق����B
�Y�@�w�҂��ăA�z����Ȃ�����
�q�ϓI�A���_�ɂ����ẮA�K�͓I�v�f���l������̂��펯�����A
��ϓI�A���ł���̈Ӊߎ��ɂ����ċK�͓I�ϓ_����F������ߎ���
���K�̌̈ӂ�������o�ꂵ�Ȃ��̂͂Ȃ��ł��낤���H
�F�����A�F�e���A�W�R�����̑Η��ł͉����ł��Ȃ����́A
�������̎��_�Ɋ�Â��`���I�ȕ��ނ���_���K�R�Ɍ��_�����Ƃ���
��{�I�ԓx���̂��̂ɂ���A�������I�E�K�͓I�ϓ_���炫�ߍׂ���
��ϓI�A����_����Α����Ƃ����l�����́A�������ʊW���̊�@�ɑ��鏈��Ⳃ�
���l�ł���B
���낻�낱�̖��ɂ��Ă��A�ʎ��Ă̗ތ^���̍�ƂɈڂ�ׂ��ł͂Ȃ����B
�u�������̎��_�ɗ��Ƃ��̏ꍇ�������ł��Ȃ��v�Ƃ����ᔻ�𑊌݂Ɍ��������͕̂s�тł���B
���i�ӔC���̌`���_�I�Ȕ������ɖ�������邱�Ƃ́A
�q�ϓI�A���_�̎������ւ̖����Ɨ������Ȃ��B
�q�ϓI�A���ɂ����ċK�͐��A�������A���ߍׂ��ȗތ^���Ƃ��������֑���̂ł���A
��ϓI�A���ɂ����Ă����l�ɂ���ׂ��ł͂Ȃ����B
��@���̍���̏����ɂ��Ă��A�u��@���̈ӎ��̉\���v��
�u����ɑ����ȗ��R�����邩�v�Ƃ����悤�Ȓ��ۓI�K�͂̒T���ł͂Ȃ��A
�ʎ��Ă��ƂɌ̈ӑj�p��F�߂�u�ׂ��v���ۂ��Ƃ����ϓ_����̋K�͓I�E�ʓI�c�_��
�ςݏd�˂ėތ^�������Ƃɓ���ׂ��ł��낤�B
�����ςݏd�˂ėތ^��������
�����������s����`�̓_�������Č���ꂽ����H����
�����ɂł��Ă��Ȃ��̂��낤�B
�{���I�ɂ��ꂷ���B���l�ɖ��߂�������������āA�_���o�������̂ɁB
�������A�����̐��e�[�}����Ȃ�����˂���
���邗��
�E��R�̐l�������ӌ�����т��Ďx������
�@�����ӌ��ł��A�W�c�̒��ł��̈ӌ����M�����Ă���A�����̍l�����͊Ԉ���Ă���̂��A���Ǝv�킹���@
�E�s���Ȏ���������Ȃ�������A�s���Ȏ���ɂ͓����Ȃ��A�X���[����
�@�N�ɂ�����┽�_�������Ȃ����Ƃɂ��A�N�����F�A�^���Ȃǖ����ƐM�����܂����@
���}�X�R�~��A�J���g�̃l�b�g�H���������Ă��邱��
TV�Ȃǂ��A�����v�z��l�����ɐ��܂��Ă���t����펯���ʂ��Ȃ��t��������l�Ԃ��悭�o��������̂́A
�J���g���L�`�K�C�Ɍ�����l��������邱�ƂŔᔻ�̖�����J���g�����炷���Ƃ��ړI�B
���A���ł��l�b�g�ł��A�U�������͎��������̎咣�ɗ����Ȃ����Ƃ��킩���Ă���̂ł܂Ƃ��ɋc�_�����悤�Ƃ��Ȃ��̂������B
��ϓI�v�������܂藝�_�I�ɂ��ߍׂ������ނ���Ă��܂��ƁA
������A���̂悤�Ȃ��߂ׂ̍��������F��ɑς�����̂��A
�Ƃ����^�₪�킭�̂ł����A���̕ӂ�Ɋւ��ẮA��̓I��
�ǂ̂悤�ȕ��ނ�z�肳��Ă���̂ł��傤���B
�ތ^���A�v���[�`�������ɑς��Ȃ��Ƃ�����咣�ł����A
�w�������ʊW�ɂ��Ė��m�Ȋ����Ă����ɂ�������炸�A
����E�����͂��̂悤�ȍd���I��ł͎����ɑς��Ȃ��Ƃ������Ƃ���A
�A�h�z�b�N�ȑΉ����������߂ɋ}���ɋq�ϓI�A���_���L�͉������Ƃ���
�o�܂��炷��A�����ɑς��Ȃ��̂͌`����ɂ�鏈���̕��ł���Ƃ���
���ƂɂȂ�܂��ˁB
��ϓI�v�������ߍׂ������ނ���̂͌��@����߂�Ƃ��藧�@�{�̎d���ł���A
����I��Ղ̂Ȃ��w�҂����߂�̂́A�����@�{�I�E�������`�E�ጛ�I���A�Ƃ����^�₪�킭�̂ł����A
���̕ӂ�Ɋւ��ẮA��̓I�ɂǂ̂悤�ȕى���p�ӂ���Ă���̂ł��傤��
�����A�����������Ƃł͂Ȃ��A��ϓI�v���ƂȂ�ƁA�ǂ����Ă�
�ԐړI�ȏ؋������ς𐄑����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������܂�
�̂ŁA�퍐�l������ӎv��L���Ă���Ηv�����[������Ƃ������_��
�ł����Ƃ��Ă��A���̗v���̗L�����O������ώ@���邾���ŗe�ՂɔF��
���邱�Ƃ��ł�����̂ł����ė~�����Ƃ������ɞB�����P���ȋ^�ⓙ��
�킢�Ă��܂����̂ŁA���̓_�ɂ��āA�ǂ̂悤�ȕ��ނ�z�肳��Ă�
��̂��A�Ƃ�������������Ă����������킯�ł��B
�Ⴆ�A���鎖����F�����Ă����������͔F���\�ł������Ƃ����قǂ�
�P����������F�肵�₷�����ނł���܂��Ɣ��ɂ킩��₷��������
�F�肪�\�ɂȂ肻���ł��̂ŁA���炵�����̂ɂȂ肻���Ȃ����v���܂����B
�P���ȋ^�₪�킢�Ă��܂����̂ŁA��̓I�ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ�����F�肵�Ă���
���ƂɂȂ�̂��낤���A�Ƃ�������������Ă����������̂ł��B
�Ȃςȕ��͂ɂȂ����Ⴂ�܂����B
�����܂���B�ȉ��͖�����������Ă��������B
�Y�@�̂��Ƃ킩���ĂȂ����w�҃X����
�P�@���ɌY���ٔ��𒆐S�Ɍo����ςo���̍ٔ����́A�Ⴆ�Ζ����ٔ����͍s���ٔ��𒆐S�Ɍo����ςo���̍ٔ��������A
�@�ٔ����̑g�D���͏W�c�ɂ����Ďw���I���͎x�z�I���������w�̍ٔ������͑I�ǂ̍ٔ����ł����B
�Q�@�܂��A��L�P�ɋL�ڂ������▔�͊ϓ_�Ɋւ��A�i�@�@�֖��͍ٔ����̑g�D���͏W�c�ɂ����āA�w���I���͎x�z�I�������ʂ���
�@����̍ٔ������ς�ł�����v�Ȍo���Ȃ����o���̓��v�́A���������܂����B
�@�@����ɁA�����▔�͊ϓ_�Ɋւ��A�@���E�̈�ʓI�Ȋ��o�́A���������Ă��܂����B
���w���̕��ł��傤���H
�P�E�E�Y���ٔ����������ٔ����i�s���ٔ����j���G���[�g�ł���Ƃ��������͖����Ǝv���܂��B
�@�Y���ٔ����̃G���[�g�R�[�X�A�����ٔ����̃G���[�g�R�[�X�͗������݂��܂��B
�@���Ƃ��A�ō��ْ������A�i�@���C�������A�@���ȋǕt�Ȃǂ��G���[�g�R�[�X�ł����A��������Y���E�����E�s����
�@�g�����݂��܂��i�i�@���C���ɂ͍s���̘g�͂Ȃ��ł����j�B
�Q�E�E��L�̂Ƃ���A�킪���̍ٔ�����������w���I�n�ʂɂ��邩�ǂ����́A�ō��ْ�������i�@���C�������A�@��
�@�ȋǕt�Ȃǂ��o�����Ă��邩�ǂ�����A���̍ٔ����̔z�������C�n�i�ꏊ�j�ɂ���Ă�����x�킩��܂��B
�@�G���[�g�R�[�X���ǂ������������������Ƃ��āA����L��w�ٔ��������l���̌����A�u�o��I�����v���肪����Ƃ��āx
�@�i�܌����[�j�Ƃ����{������܂��B
http://www.amazon.co.jp/dp/4772704876/
���ƁA�ٔ����̌o����ԗ������w�S�ٔ����o�𑍗��x�Ƃ����{������܂��B
����Website�ł́A�ٔ����̌o�����������邱�Ƃ��ł��܂��B
http://www.e-hoki.com/judge/
�u�i�@�����Ɏ�܂����B�ł��@�����R�����̂��D���B�v
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd373/
http://www.dmm.co.jp/mono/dvd/-/detail/=/cid=1svdvd387/
�u�B�ӔC�v�f�Ƃ��Ă̍\���v���ɊY�����錋�ʂ̔������ÎĂ���Ƃ������Ɓv�Ƃ��邪�A
����͉䂪���ł͔F�e���ɑΉ�������̂ł���A���̂悤�ɐӔC�v�f���̈ӂɊ܂܂��邱�Ƃɂ�
���ʖ����l�_����͂������A�̈ӂ���@�v�f�Ƃ���s�ז����l�_������ᔻ����邱�ƂɂȂ�B
�������A���̔ᔻ�͑Ó��ł��낤���B���́A��L�B�́u�ӔC�v�f�Ƃ��āv�Ƃ����_�͕s���ł���Ǝv���B
���̂��Ƃ́A���݂ł͐V�ߎ��_���ʐ��ł���ɂ�������炸�A���K�̌̈ӂƔF������ߎ��̋�ʂƂ���
�_�_�ɂ��ẮA�ˑR�Ƃ��Ă��Ă̋��ߎ��_�̍l�������Ђ������Ă������ƂɋN������Ǝv����B
���Ȃ킿�A�̈ӔƂƉߎ��Ƃ̍\���I���قɎv����v�����A�����ς��ϖʂ̍��ق݂̂�_���Ă����̂ł���B
�Ⴆ�A�G���̒��ɎԂ������x�Ői�������Đl�����S���������Ăɂ����āA
�s�҂��u�l���Ђ�R��������Ȃ����A����ł��\��Ȃ��v�Ǝv���ăA�N�Z���ݍ���
�ꍇ�ɎE�l�̌̈ӔƂ���������̂́A�u�l��R�ȁv�Ƃ����K�͂Ɉᔽ���Ă��邩��ł���B
�����A�s�҂��u�����̉^�]�Z�\���炷��A�l���Ђ����Ƃ͂Ȃ��v�ƌy�M���ăA�N�Z���݁A
�l���Ђ��Ă��܂����ꍇ�ɉߎ��Ƃ���������ɉ߂��Ȃ��̂́A�u�G���̒��ɎԂ�i��������Ƃ��ɂ�
�l������������댯�����邩��A���x�𗎂Ƃ��ׂ��ł���v�Ƃ����K�͂Ɉᔽ��������ł���B
���Ȃ킿�A�F�e���̍����́A�ӔC�v�f�Ƃ��ĔF�e��v�����Ă���̂ł͂Ȃ��A
��@�v�f�ł���K�͈ᔽ���̎����ɂ����āA�F�e�����邩�ۂ��Œ��ʂ���K�͂�
�قȂ�_�ɂ���̂ł���B�����ł���ȏ�A�̈ӂ���@�v�f�Ƃ���s�ז����l�_����F�e����
�ᔻ����邢���͂Ȃ��B
�Q�����˂�ɏ������݂��������A�_�������Ȃ�����B
�Y�@�w�҂��āA�_�������Ə����ׂ����낗
����ȂƂ���Ŗ������Ă�ꍇ����ˁ[����B�d�������B
���{�̖@�w�҂́A�i�@�@�֖��͍ٔ����̓���̋�̓I�Ȏ����ɁA
�{���I�ȉe����^�������e���������_�����L�q�����A���͒�o�������ƁB
���{�̖@�w�҂��L�q�����A���͒�o�����_�������������e�́A
�i�@�@�֖��͍ٔ����̓���̋�̓I�Ȏ����ɑ��A
�w���I�Ȗ��͎x�z�I�ȉe����^�������ƁB
����͎����ł��B
�ŋ߁A�����҂��w�҂̈ӌ��������Ƃ��Ē�o���邱�Ƃ��܂܍s���Ă��܂����A
�����́A�ٔ������ɂقƂ�lje����^���Ă��Ȃ��Ǝv���܂��B
�������A�ٔ���������̊w�����̗p�������Ƃ͐����Ȃ��ł����Ȃ��킯�ł͂���܂���B
���Ƃ��A������]�p���i���ɂ��āA�ō��ٔ����́A������M�����̗p�����ƌ����Ă��܂��B
�i�Ŕ�����7.9.19���W49��8��2805�Łj
�i�Ŕ�����10.1.30���W52��1��1�Łj
�Y�@�w�҂����̂Ƃ��w�C�̌������Ă���̂��H��
�܂Ƃ��ɔ��ᒲ���������ǂ�ł����
���Ⴊ�w������{���I�ȉe�����Ă��Ȃ��Ȃ�Ďv��Ȃ�
�������ɁA����������i�ō��ٔ����������j�ł́A�w��������������p���Ă��ˁB
�����A�ʐ����L�͐����Ƃ������x���Ȃ�ō��ق��w�����̗p���邱�Ƃ͂����Ă��A
����̊w�҂̓��ʂȊw������ɍ̗p���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��悤�ȋC������B
>����̊w�҂̓��ʂȊw������ɍ̗p���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��悤�ȋC������B
�������͏������Ȃ����̗��R�����邩���
���������Ƃ�����łς��Ǝv�������͕̂����ʂ����Ǘ�Ƃ��Ă��łɂ����Ă�����
�Ⴆ�A�Ӗ����e�y�ј_���̍\���̊ϓ_���猩�Ă݂ē��Y��@�씻���ƈႢ�͂Ȃ��A�����ŁA���Y�Ӗ����e�y�ј_���̍\������̓I�ɕ\�����͋L�ڂ�\�����邽�߂�
�L�ڕ����̕\����̍��ٖ��͔����Ɋ�Â��Ӗ����e���܂ޘ_�����A���{�̖@�w�҂��L�q�����A���͒�o������̓I�ȓ���̗��
���݂��܂����B
�u��[�̊i���v�����͉ߋ��̔���̐ςݏd�˂ɂ��Ƃ��낪�傫���Ǝv���܂��B
���̑�@�씻���ɓ���̊w�҂̎咣���������ꂽ�����͂Ȃ��ł��傤�B
��ʘ_�ł����A�ō��ٔ���W�Ɍf�ڂ����悤�ȏd�v�ȍō��ٔ����E����ɂ��ẮA
�ō��ْ������������������M����̂�����ł��i�ō��ٔ����������Ɏ��^�j�B
�����ǂ߂A���Y�����E����̌`���ߒ���������x�������邱�Ƃ��ł��܂��B
�����Ă����������肪�Ƃ��������܂��B
�ō��ٔ�����@�씻���Ɏ����ꂽ�ŐV�̔������ɂ�����A
������u��[�̊i���v�ɌW��ꖔ�͓�ȏ�̘_�_�́A
�Ȍ������m�ŁA���Ȃ��Ƃ��L���҂̗��ꂩ�猩�Ă݂Ď��m�ł����B
��L�����ō��ٔ�����@�씻���ɂ�����ŐV�̔����ɌW��
������u��[�̊i���v�ɌW��ꖔ�͓�ȏ�̘_�_�ɑ����̓I�ȑΉ��̕��������͉�����
��L�����ŐV�̍ō��ٔ�����@�씻���̔������̂悤�ɁA
��̓I�ȈӖ����e�y�ј_���̍\���̂��ꂼ��Ɋ�Â��L�ڕ����ɂ��A�������Ƃ́A
���{�̖@�w�҂��S���ׂ��A���͉ʂ����ׂ��d�����͖����ł��邱�ƁA�y�сA
���{�̖@�w�҂����݂���Ӌ`�ł��邱�ƂƁA���ꂼ�ꂢ���܂��B
���q�������Ƃ����̂ɁA���@�����v�ɂ����ߏ����ɂ����Ȃ��ꍇ��
�����̈����⎖�������ɂ͂ǂ̂悤�Ȏ���������̂ł��傤���B
�Ⴆ�A���Ɍx�@�̑{���i�K�ŁA�ʂɐ^�Ɛl���߂܂��Ĕ�^�҂̖���������������
���l�ɁA���Ɍx�@�̑{���i�K�ŁA��Q�͂�������Q�ґ��̏���Ȏv�����݂�
�e�^�������̂��Ȃ��������Ƃ������������������̏ꍇ�ȂǁB
�C�ӂ̎撲�ׂ̒����̏ꍇ��
�ߕߌ�̋����{���ł̒����̏ꍇ�Ƃł́A
�����ꂼ���舵���ɈႢ������̂ł��傤��
�@�I�ɂ́A���l�̌Y�������ɂ��ẮA���ߏ����ȊO�͌��@�����v�����
���ƂɂȂ��Ă��܂��i�Y�i�@246���j�B���������āA��{�I�ɂ��̂悤�Ȏ�����
����܂���B
�������A�����܂�Ɍx�@����Ŏ�����������I��������i���ݏ����j���Ƃ�����
�悤�ł����A����͈�@�ȏ����ł����A���̂悤�ȏꍇ�͋��q�������쐬����
���ł��傤�ˁB
���������āA�^�Ɛl���߂܂�����A�e�^�������Ȃ��ꍇ�A���������Ȃ��ꍇ
�ł��A���@�����v���Ȃ���Ȃ�܂���B
�⑫�ɂ���
��L�̂Ƃ���ł�����A�C�ӎ撲�ׂƑߕߌ�̎撲�ׂɂ���č��͂���܂���B
�������A�ߕߎ葱���o�����ƁA�������x�@����ł��ݏ������Ƃ͂قڕs�\
�ł��傤�ˁB
���Ƃ��ΐ^�Ɛl���߂܂�����A�e�^�������Ȃ�������A���������Ȃ��ꍇ�́A
���@�����v�Ƃ͕ʓr�A��^�҂̐g����������邱�Ɓi�ߕ߂��Ă���ꍇ�j�͉\�ł���B
�����J�ɉ��������L���������܂��B
�l�I�Șb�Ȃ̂ł����A
�m�荇��������e�^�ŔC�ӂ̎撲�ׂ������
�C�ӂł̒����i�w����������j�Ǝʐ^�B�e�Ə؋����̔C�Ӓ�o������
�g������l������ɌĂ�Ă��̍ۂɁA���ނ𑗌����܂��Ƃ������Ƃ�
���S������ߕ߂ł��Ƌ�����A���̓��͂��̂܂܋A���������Ȃ̂ł����A
���͔C�ӂƂ͖�����̋������v�̎撲�ׂł��莖�����
�����I�Ȏw��̎�Ɗ�B�e�Ə؋�����o�����������ŁA�{�l�͑����{�苶���Ă��܂���
���ꂩ��Q������ōĂьĂяo����A���̍ۂɔC�Ӓ�o��������Ԃ��Ă��炤�葱����
�y�����������ꂽ�����Ȃ̂ł����A�{�l�͗e�^�����͑S���ے肵�Ă���
���̍ہA���ߏ����葱��������؎�����Ȃ����������ł��B
����ɂ��̗����ɖ{�l�����@�����v�Ȃǂ́A���̌�̏��ނƐg���̎�舵�����ǂ��Ȃ�̂���
�d�b�Ōx�@�ɖ₢���킹���Ƃ���A���ݑ{�����܂����ޑ������邩�ǂ����킩��Ȃ��Ƃ���ꂽ�����ł��B
�܂����̓d�b�̍ۂɖ{�l���A������蒲�ׂ������x�����g�ɂ��̎撲�ׂ̈�@�����w�E�����Ƃ���A
�͂��߂͂����Ƃڂ��Ă��܂������A�x�����g�̋��q���Q�]�R�]���Ă��ǂ���ǂ�ƂȂ�Ō��
���炩�ɔ��I�Ȍ�����͂��܂������A��@�ȍs�ׂ����������ꎩ�͔̂F�߂������ł�
�i���݂ɂ��̍ۂ̇���b�͂��ׂĘ^���ς݁j
���̌�A�����ƂȂ�R�N���߂��܂��������lj��̉��������Ȃ����������ł��B
���̂悤�ȏꍇ�̉��߂Ƃ��ẮA�����O�̂��Âꂩ�̎�����
����Ɍ��@�����v�����Ă��̌�ɖ{�l�Ăяo���������A�s�N�i�Ŗ{�l�ɂ���ʒm�̂܂�
����Ɏ����͏I�����Ă����Ƃ������Ƃł��傤���H
�{�l���g�́A���@����Ăяo����������ł��o�����āA�����ł��邱�ƂƐ�̔閧�^�����܂߂�
�x���̈�@�{�����Ԃ��܂��镠�Â���ł����������ŁA�����������ǁA�{�l���g�͎��ێ����ɂȂ����킯��
�ǂ̂悤�ȏ����ƂȂ����̂������ɔ[�����Ă��Ȃ��悤�ł��B
���@�����v����Ă����̂Ȃ点�߂ĂP�炢�͖{�l���悪�����Ă��������Ȃ���
���ߏ����̏ꍇ�͎葱�����ɖ{�l�̏����Ȃǂ��K�v�Ȃ͂������A
�܂����x�@������ɏ������Ă����̂ł��傤���ˁB
���݂Ɏ��ꂽ�C�Ӂi���ۂ͋����j�̒����͔۔F�����i�߂�F�߂Ȃ����e�j�����������ł��B
���{�̖@�w�҂́A�_���ɂ����āA�i�@���͎Љ�ɂ����Ăł��邾���͂₭�������͑Ή������߂��Ă���A����̋�̓I�Ș_�_�ɑ��A�����ٔ������͍ō��ٔ����̍ٔ����������ł���Ύ������낤�������̂悤�ȁA��̓I�Ȗ��͋K�͓I�Ȗ��͐����I��
�������͑Ή��̕��������A��̓I�����m�ȋL�ڕ����y�ј_���̍\���Ɋ�Â��_�����L�q�ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�@���E�ɂ����āA���̂悤�ȓ��{�̖@�w�Җ��͖@�w�����Ȃŗ^�����锎�m����L����@�w�҂ɂ́A�ǂ�قǂ̑��݈Ӌ`�����邾�낤���B
�������ɁA����܂œ��{�̖@�w�E�ɂ����ẮA
���߁i�ڐ�j�̖����������邽�߂̒Z�˒��̗��_���A���s��Ȓ��˒��̗��_�̂ق���
�����ł���ƕ]������Ă�����������܂���ˁB
���[�X�N�[���ŗ��_�Ǝ����̉ˋ��Ƃ������Ƃ������Ă��܂��̂ŁA���̌X���͂��ꂩ��
�ς�邩������܂���B
���a�Ȑ��i���������l�Ԃ͖w�ǎE���ꂽ�B
�n�C�Z�p���Ȃ������Ñ�ɂ����āA���{�ɓ����邱�Ƃ͖w�ǂ̐l�Ԃɂ͖����������B
�����ꕔ�̗D�G�ȓ��]���������x�T�w���A
�D�G�ȓn�C�Z�p�ƍ��͂�p���āA�O�m�q�C�\�ȑD�����A�勓���āA���{�ɓn�����B
���ꂪ���{�l�̌��^�B
���{�l�����a��IQ���������͂�����͈̂�`�����B
�������N�l���U���I�Ńm�[�x����ꂸ�L���Ĉ�l������GDP�����{�l�̂P�O���̂P�Ƃ����ɒ[�ȕn�R�l�ł���̂���`�����B
�����ł���A���{�̖@�w�҂��L�q�����A���͒�o�����_�������������e�́A �i�@�@�֖��͍ٔ����̓���̋�̓I�Ȏ����ɑ��A �w���I�Ȗ��͂�����I�Ȃ����擱�I���͎x�z�I�ȉe����^���Ă������̋�̓I�ȗႪ�\������͂��ł��B
�킽���́A���Ȃ��̕ԓ��̎�|�ɕ����I�Ɏ^�����܂��B
�����A�킽���́A�u���߁i�ڐ�j�v�u�Z�˒��̗��_�v�u�s��Ȓ��˒��̗��_�v�u�����v�̊e�p��͗p���܂���B���Y�e�p���p����ƁA�Ⴄ��|�������N�����܂��B
���H�̖@���Ɩ@���̎��H�Ball purposes problem solver�B
�����A�c���d�����m�̒������������Ȃ̂ł�����
���Ȃ��͊w�҂���ł����H
�͂��B�ڂ����ς��ς��܂����B�@���ނ��ނ����܂����B�Ԃ��J�[�y�b�g�̊K�i�̏�ł����B
�@�w�̊�b�B�킽���́A�w�҂ł͂���܂���B
�uall purposes problem solver�v�́A�n�[�o�[�h�E���[�E�X�N�[���ŋ������Ă��Ƃ̈�������ł��B
���Ȃ��́A���{�̍ٔ��`���ɁA���{�̖@�w�҂��^����e���ɂ��Č�������Ă���̂ł����H
�����������Ƃ���A�킪���̃G���[�g�ٔ����̎v�l�ɂ��Ēm�邱�Ƃ��Ӗ�������Ǝv���܂��B
�����ŋߓǂ{�ł������납�����̂́A���ō��ٔ����̉�����v���̕����������ł��B
�����͂�����w�Ҙg�ōō��ٔ����ɏA�C���Ă��܂����A�L�����A�ٔ����̌o���������Ă��܂��B
�����́A��~�M�E�ҁu������v�I�[�����E�q�X�g���[�v�i�@�������Ёj�ł��B
����ǂ�ł݂Ă��������B
�ԓ����Ă��������A���肪�Ƃ��������܂����B
���Ȃ��Ɋւ�鉽������̂��Ƃɑ��ĕ]������\�͖��͎������A�킽���́A���������Ă��܂���B
�ȉ��ɋL�ڂ��邱�Ƃ́A���������Ă����ϓI�Ȋ���Ⴕ���͈�ۖ��͈ӌ��Ⴕ���͐S�ł��B
���ɁA�ȉ��̋L�ڂ����Ȃ��Ɂu���Ȃ��͉����܂ł����v�Ƃ̊���������N�������ꍇ�ɂ́A�킽�������������������B
�킽���́A�ƂĂ����������ƂƂ��ɁA��ϊ����������A�y�сA���Ȃ��̒m���Ȃ����C���e���W�F���X�������܂����A���Ȃ��̂��̂悤�Ȓ��J�ȋy�ь��S�ȕ��тɈ��Ӗ��͔ᔻ�����߂Ȃ��A�y�єz�����͎v�����̌��t�ɂ�莦���ꂽ�s���ɁB
�킽���́A�������Ă��������܂����u������~�M�E�ҁw������v�I�[�����E�q�X�g���[�x�i�@�������Ёj�v���AMyOpac�Œ��ׂĖ@�w�����͑����}���قɏ���������Γǂ݂����Ǝv���܂����B�킽���ɂ��̖{�������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B
�F�̛̈��ʐ��y�чH�̒����I�s�ׂ̛ɂ��āA
���ʂƂ̏����W�y�ыq�ϓI�A����v�����闧����咣�������B
�܂��A�̈��ʐ��ɂ��āA���ʂƂ̏����W��v��������͌��݂قƂ��
�x���҂����Ȃ��Ƃ���Ă���B���̎�ȗ��R�́A�ƍs�ɕs���ȏ��͂łȂ����
�ɂȂ�Ȃ����ƂɂȂ��ĕs�s�����Ƃ����_�ɂ���B�Ⴆ�A�`���a�Ƀi�C�t����A
�����p���Ăa���u���h���E�������A�`���i�C�t����Ȃ��Ă��A�a��
���X�Ńi�C�t���w�������ł��낤�A�ƌ����悤�ȏꍇ�A�`�̃i�C�t�Ƃu�̎��Ƃ�
�����W���Ȃ��Ƃ����̂ł���B
�������A����͑Ó��ł͂Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�����W�́u�t�������֎~�v�ɂ��A�a���i�C�t���w�������ł��낤������
�l���ł��Ȃ�����ł���B
�܂��A�`���a�Ƀi�C�t��������A�a�͓�������p�ӂ��Ă����s�X�g���łu�������E�����Ƃ���
�ꍇ�ɁA�`�̃i�C�t�ɂ���Ăa�̔ƍs�ԗl���ω������A���Ȃ킿�A�ڋߐ�Ȃ��
�i�C�t��p���邱�Ƃ��ł��邩���_�ɂu�ɗ������������Ƃ����������A
����͂`�̃i�C�t���Ȃ�����̂悤�Ȕƍs�ԗl�͎������Ȃ���������A
��͂茋�ʂƂ̏����W������i�قȂ�ƍs�ԗl�łu���E�Q�������낤�A�Ƃ����t��������
������Ȃ��j�B
�ȏ�̂Ƃ���A���ʂƂ̏����W��v�����Ă�����s�s���͂Ȃ��B
�̈ӂ��Ȃ킿��ϓI�A���ʼn��������B�������A����͑Ó��ł͂Ȃ��B
�u��O�I�Ƃ͂����Ȃ��͈͂̎҂��ƍs�ɗ��p����W�R���v�̔F����v�����鍪����
���ゾ����ł���B
�ނ���A�q�ϓI�A���̖��Ƃ��čl����ׂ��ł���B
���Ȃ킿�A��s�@��������悢�Ǝv���A�u�ɔ�s�@�ւ̓�������߂��Ƃ���A
�Ă̒��s�@�������Ău�����S�����ƌ�������ɂ����āA����͓���I�����댯�ł��邩��
�q�ϓI�A���������Ƃ����B
���l�ɁA�Ⴆ�A���̐l�͕�Ől���h�������m��Ȃ��Ǝv�����
�̔��������W�̃A���o�C�g�́A���ɂ��̎҂����ۂɂ��̕�ŎE�l��Ƃ��Ă��A
���̊댯�͓���I�����댯�ł����āA���Y�A���o�C�g�ɋA�������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A
�͐������Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�E�B�j�[�����͂ǂ����B����͂��悤�ȃ\�t�g���ʏ����Ă������ǂ����Ƃ����_�ɂ�����B
���Ȃ킿�A�\�t�g�J���҂�����I�ɃE�B�j�[�̂悤�ȃ\�t�g�����O�ɒ��Ă���A
���ꂪ�Љ��ʂɎ�����Ă����Ȃ�A���Y�\�t�g�ɂ�钘�쌠�ᔽ�́A
��͂����I�����댯�Ƃ����悤�i�����łȂ���Ayoutube�̎���������l��
���쌠�ᔽ�̛ƂȂ肩�˂Ȃ��ł��낤�B�j�B
���̂��Ƃ́A�J���҂̎�ςɂ���č��E�����ׂ��łȂ��B
�ȏ�̂Ƃ���A�̈��ʐ��������W�{�q�ϓI�A���Ɖ����邱�Ƃɂ��A
�F�y�чG�̖��͉����ł���B
>>246-247
���ɁA���Ȃ����ō��ٔ����̍ٔ����ł���Ƃ����ꍇ�A
���Ȃ����A>>246-247�Ɏ����ꂽ�����ŁA��̓I�����m�ȋL�ڕ����Ɋ�Â�
���m�����m�Ș_���̍\���y�ј_������ɂ�錋�_�y�ї��R�t�����A
�ꖔ�͓�ȏ�̘_�_�ɑ��^����ō��ٔ��������̔������ɌW���̓I�ȋN�Ă��������ƁA�y�э\�����邱�Ƃ́A
���̗��Ɏ����ꂽ�������̋c�_�ƁA�������A���͂��L�Ӌ`�ł���Ǝv���܂��B
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1387935359/
���{�̎�]���O����]�Ɖ�k���鎞�́A��T�A���S���~���x���̌o�ώx���\�����Ă邩���
������؍���]�Ƃ̉�k�ł������牭�~�̌o�ώx�����������ɗ^�����Ă���
����𐔔N����������ʂ͑傫��
���������łP���~�̓G���x�����팸�ł��邵�A�������{�̖h�q�⍑���\�Z�Ȃǂɉ�
4�Q�l�����F�ߐ��h�C�c�̋���Z�Z�Z�Z
http://www.data-max.co.jp/2013/12/09/100_66_dm1504_1.html
�n�Q�^�J�O���t�@���h�ɐH���s������鏤�Ǝ{�݃g���A�X�v�R
�o��팸�ŗ���҂̈��S�����m�ۂ���Ă��Ȃ�
���Ǝ{�݃g���A�X�v�R�@�O���t�@���h���T�[���ւ̋^�f
http://www.data-max.co.jp/2013/10/07/post_16455_dm1504_2.html
��@�����ƂƂ��ɐӔC���������Y�̌��Ƃ̍����Ƃ��錩���ɂ��A���p���\���ǂ����������������B
�܂��A��@������P�Ȃ�g�g�݂Ƒ����A���̊j�S�͐ӔC�����ɂ���Ƃ��錩������́A��z�ߏ�h�q�̏ꍇ
��@���̌����͂Ȃ�����A�R�U���Q���́u�K�p�v�͔F�߂�Ȃ����A�ӔC���������Ă���_�ŁA���́u���p�v��
�F�߂���i�����R�V�X�j
�������A��@���̌������S���F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ��A�Y�́u�Ə��v�܂ŔF�߂�ׂ��ł͂Ȃ�����A�Y�́u���y�v
�݂̂�F�߂�ׂ����Ƃ���i�O�c�S�S�V�j
����ɑ��āA��@�E�ӔC�������ɗ����Ȃ���A��@�������Ȃ����Ƃ��d�����āA�P�Ȃ��z�h�q�̏ꍇ�Ƃ�
�ύt���d�����錩������́A�u���p�v���ے肳��A���҉\���̗��_�ɂ���āA�ӔC�̌�����F�߂�]�n������
�ɂ����Ȃ��Ƃ����i�]���E�d�v���P�Q�Q�j
�������ɁA��z�ߏ�h�q�̏ꍇ�ɁA�R�U���Q���́u�K�p�v�Ȃ����u���p�v��F�߂�ƁA�P�Ȃ��z�h�q�̏ꍇ
�ɂ��̓K�p���Ȃ����ƂƔ�r���āA�ύt��������B
���������āA�����ɂ��A���p�����̂�Ƃ��Ă��A��z�ߏ�h�q�̏ꍇ�A�P�Ȃ��z�h�q�̏ꍇ�̉ߎ����Q
�̌Y���y���������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����͕��씎�m�̌����ƈ�v����i����Q�S�V�j
���ۓI�댯�Ƃɂ��ẮA�R�����w�댯�Ƃ̌����x�i�P�X�W�Q�N�j�Ō��s��
����Ă���A����ȗ��A�w���̐i���͂Ȃ��B
��̓I�댯�Ƃ̏ꍇ�ɂ́A�댯�̔����������ŗv������A��̓I�ɍ��x�Ȋ댯
�̔������Ɨ����Ĕ��f�̑ΏۂƂ����i�P�P�O���A�P�Q�T���Ȃǁj
����ɑ��āA���ۓI�댯�Ƃ̏ꍇ�ɂ́A���ꂪ�s����Βʏ�댯�̔�����
�m�肵����A��ʓI�E���ۓI�Ɋ댯�ȍs�ׂ̐��s���v���Ƃ��ċK�肳��Ă���
�i�P�O�W���Ȃǁj
�R���̐^�����͂��̗��҂̊ԂɁu�����ۓI�댯�Ɓv�Ƃ����̈��݂������Ƃ�
����i�Q�P�V���Ȃǁj
�u�����ł́A�\���v���s�ׂւ̂��Ă͂ߕ]���ɂ����āA���łɂ�����x�����I
�Ȋ댯���f���v������邱�ƂɂȂ�v�i�R���S�U��)
����̒��ۓI�댯�Ƃ́u���ʂł���댯�v�ɂ��Ăɂ��Ă̗����Ɋւ��ẮA
���a�T�T�N�P�Q���X���̒c���E�J�����ٔ����̕⑫�ӌ��Q�ƁB
�w���ۓI�댯�Ƙ_�̐V�W�J�x�ɂ���Ĉ�C�Ɋ댯�Ƙ_�����i���ꂽ��B
�N�͓���������ǂ��ƂȂ��낤�Ȃ�
��p�l�̕������Ǔ��{�̑�w�ŋ��ڂ��Ƃ邱�Ƃ��ł������炢���炵��
���m�O���t����B
�R���搶�̊댯�Ƃ̌����̋Ɛт͂����Ƃ��邩�炗
��̓I�댯���̔j�]���w�E���āA�C���q�ϓI�댯���̓����Ȃǂ��s�������ƂȂǂ��̃��m�O���t�ɂ�
��������̋Ɛт��l�܂��Ă��邻��ȈӖ��s���̂܂Ƃ߂ŏI���Ȃ��悤�ɂ�
���̘_�������\���ꂽ�̂́A���̘b���H
>��̓I�댯���̔j�]���w�E���āA�C���q�ϓI�댯���̓����Ȃǂ��s�������ƂȂǂ��̃��m�O���t�ɂ�
>��������̋Ɛт��l�܂��Ă���
����Ȃ��Ə펯�����珑���Ȃ������B����͂����܂ł����ۓI�댯�Ƃ�����B
�ŏI�͂̓Z�߂Ɛ}�\��ǂ߂Ή���Ƃ���A�����̎R�������������Ƃ��咣�����������̂�
�u�����ۓI�댯�Ɓv�̑��݂ł���A�C���q�ϓI�댯���͂���ΖT�_�ɂ����Ȃ������B
���ꂪ�R�������̎v�f�ƈقȂ�A�����ۓI�댯�Ƃ̎咣�͂��܂�x�������A�t��
�C���q�ϓI�댯���̕��ɒ��ڂ��W�܂�A���c�E�]���E���������̎x���Ă��邱�Ƃ͎��m�̂Ƃ���B
���n�ȗg�������͎~�߂Ă��炢�����B
2012�N3���B
�Y�@�w�҂�����A�ɂ��Ƃ�������Ăӂ��т���Ă����킯���E�E�E��
����Ƀv���C�h���������ǁA���x���̒Ⴂ��w�̋����ȂȁH
�����_���o���悗��
��J�̘_�����ᔻ�̑��ʂɂ������āA���Ȃ�u���ɂڂ�J�X�ɂ�������Ă����̂������Ȃ���
�b�͕ς�邪�A���ʊW�̍���ɂ��ẮA�ǂ��l����H
����͖��ł͂Ȃ��A�������ʊW�̖��ł���Ƃ���O�c����J���ɖ��͂�
�����Ă���̂����A�����̍���ł���Ƃ��鑽������_�j�ł��Ȃ��B
�o�����Ⴕ�傤���Ȃ��B
�Ƃ����>>266����A�ǂ������肪�Ƃ��B
�����A�����ǂ�ł݂�B
�����Ƃ��E�`�̐}�����ɂ��邩�ǂ���������Ȃ�����
������������炵�Ă��B�B�B�i����
>�Ȃ��}�ɘb��ς����̂�
�R�����ɉ����Ĉ��ʊW�̍��떳�p�_��������������������B
�킪���̑������́u���ʊW�̍���v���A�q�̂̍���A���@�̍���ƕ���
��̓I�����̍���Ƃ��Ĉ����Ă����B
�u�s�҂̗\���������ʂ̌o�߂ƌ����̈��ʂ̌o�߂Ƃ��������ʊW�͈͓̔�
�ŕ������Ă������A�\���v���I�̈ӂ͑j�p����Ȃ��v�i��˂P�X�R�Łj
�܂�A�킪���̑������́A�@�s���ɍ\���v�������Ƃ��Ă̑����Ȉ��ʊW
�̔F�������݂���Ό̈ӂ��F�߂��A�A���ɐ��������ʌo�߂��������ʊW��
�g���̂��̂ł���A�F���ƍ\���v���̘g���ŕ������Č̈ӂ͑j�p����Ȃ���
�������ƂɂȂ�B
�������u�d�v�ȍ��납�ۂ��́A���ǁA���ʌo�߂��������ʊW�͈͓̔��ɂ���
���ۂ��Ō��肳���ȏ�A���̔��f��͋q�ϓI�Ȉ��ʊW�_�Ɠ���ɋA���A
�Ɨ��ɘ_����Ӗ��͏��Ȃ��v�i�O�c�Q�V�S�Łj
���R���m�́A���ɂP�X�W�Q�N�A�u���ʊW�̍���̖��Ƃ́A���ǁA���̌o��
���������ʊW�͈͓̔����ǂ����Ƃ������ƁA���������Ĉ��ʊW�_�Ɠ����
�A���A����_�Ƃ��ē��ʂɘ_��������̂͑����Ȃ��v�Ɗ��j���Ă���ꂽ
�i���R�R�U�S�Łj
�@�@�y�����z
���̂悤�ɁA���ʊW�̍���̏ꍇ�A����_�͖��ł͂Ȃ��A�q�ϓI�A���_
�i�������ʊW�_�j�Ŗ��͉�������B
�Ⴆ�A���̏ォ��E�ӂ������Ĕ�Q�҂�˂��������҂ɓM���̈��ʊW��
���Ă̗\��������A�E�ӂƂ��ď\���ł���B�̈ӂ́A���ꂪ�����Ȃ��̂�
�������ŁA��ʓI�Ȍ��ʔ����Ɍ�������̓I�Ȉ��ʌo�߂�F�����Ă����
�����B�q�ϓI�Ȉ��ʌo�߂���̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤�ƁA���ꂪ�̈�
�Ɗ��S�Ɉ�v����K�v�͂Ȃ��B
�q�ϓI�ɔ����������ʌo�߂��A�q�ϓI�ɋA��������͈͓��ɂ������A�s��
�͌̈ӁE�����̐ӔC���B�˂��������҂Ɂu�M���v�Ɋւ���\�����������A
���r�ɓ����Ԃ������Ƃɂ��u���W�����܁v�Ƃ������ʂɑ���q�ϓI�A��
���m�肳���Ȃ�A���̈�v���m�F���Ȃ��Ă������ł���A�ے肳����
�����ł���B
�@�@�y�I���z
�@
�Ȃ�ȂB����ȊȒP�ɏ������K���������̂Ȃ̂��H�L���ȁB
���������܂��傤�B
�̈ӕs�@�i���͐ӔC�j����b�t���鍪���́A�s�ׂ��琶����@�v�N�Q���ʂ�F�������ɂ�������炸
�����čs�ׂɏo��_�ɂ���킯�ł���B
�]���āA���ɍs�҂̎�ςɂ����čs�ׂ��琶����@�v�N�Q���ʂƂ̌��т���
�q�ϓI�ɂ݂ĕs�����ł������Ƃ��Ă��A�̈ӕs�@�i���͐ӔC�j��ے肷�鍪���Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
�Ⴆ�A�s�҂������Ől���E����ƐM���A�������Ǝv���ĕ����������������R�[�q�[��
��Q�҂Ɉ��܂����Ƃ���A���͂��̕������_�J���ł���A��Q�҂����S�����Ƃ���
����ɂ����āA�s�҂̎�ςɂ���s�ׂƌ��ʂ̌��т��͋q�ϓI�ɕs�����ł��邪�A
�K�͂�ʂ����s�ׂ̐���i���Ȃ킿�A�l�����Ɏ��炵�߂�ƔF������Ȃ�A
���̍s�ׂ͎v���Ƃǂ܂�ׂ��ł���j�Ƃ����ϓ_����́A�����Ől�����Ɏ��炵�߂��
�F�������҂͐l�ɍ��������܂���s�ׂ��v���Ƃǂ܂�ׂ��Ƃ����K�͂��Ó����邩��A
����݉z�����ȏ�A�\���v���I�ɕ�������͈͂̌��ʂɂ��ċA�ӂ����
�W���͂Ȃ��̂ł���B
�����ł���ȏ�A���ʊW�̍���͖��ɂ���]�n�͂Ȃ��B
>>��ʓI�Ȍ��ʔ����Ɍ�������̓I�Ȉ��ʌo�߂�F�����Ă����
>>�����B�q�ϓI�Ȉ��ʌo�߂���̓I�ɂǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤�ƁA���ꂪ�̈�
>>�Ɗ��S�Ɉ�v����K�v�͂Ȃ��B
���̌����ł́A�u��ʓI�Ȍ��ʔ����Ɍ�������̓I�Ȉ��ʌo�߂̔F���v��K�v�Ƃ���ȏ�A
���̌��x�ň��ʊW�̍������ɂ�����Ȃ��̂ŁA�_�Ƃ��ĕs�\���ł��傤�B
���̂悤�Ȍ����ł�>>281�Ŏ������u�s�҂������Ől���E����ƐM���A�������Ǝv���ĕ���������������
�R�[�q�[���Q�҂Ɉ��܂����Ƃ���A���͂��̕������_�J���ł���A��Q�҂����S�����v
�ƌ�������ł́A�̈ӑj�p��F�߂���Ȃ��ł��傤�B
���������܂���ӎv���̈ӂƔF�߂��Ⴄ�́H
���������Ē��ۓI�댯���_�ҁH
���̌��_���s���ƍl����Ȃ�A���ʊW�F���K�v�����̂�Α���邱�Ƃł��B
�Ȃ��A���ۓI�댯���Ƃ́A�q�ϓI�Ȋ댯���Ɋւ���w���ł�����{�_�_�Ƃ͊W������܂���B
�O�q�̎���ł͐_�J�������܂���s�ׂɋ�̓I�댯�����邱�Ƃ͖��炩�ł��ˁB
�������Ԍ��͂悵�Ȃ����B���ׂĂ��o���o��
���떳�W������Ȃ��āA���ʊW�F���s�v���i�O�c�E��J���j���Ƃ�́H
�����ĔF���s�v����_����Ȃ炱���Ȃ�Ƃ������Ƃł��ˁB
���Ȃ݂ɁA���W���́u�W�����ʂ����_���Ȃ��v�ƌ������ł͂Ȃ��ł��ˁB
>>286
���Ȃ��̕ԓ����ɂ߂ĒZ���Ԃł����A���̓_���ǂ���������܂����H
���̃��X�͕ԓ��ł͂���܂���B
���쎩���Ȃ̂̓��X���e���炵�Ă����̃p�^�[���ł���B���łɂ��ׂĂ킩���Ă܂�����B
�L�������B�Q�����˂�S�̂��˂�
>>291
�ł́A���Ȃ��̃��X�����쎩���łȂ����Ƃ�
�ǂ�����Đ����\�Ȃ̂ł����H
�������A�O�q�̎���ŁA���s�s�א��̔F���������Ə�������悭�A���ʊW�̔F���͕s�v�ł���
���ƂƖ������Ȃ��Ƃ����咣�͂��蓾��Ǝv���܂��B
���Ȃ킿�A�u���������܂���s�ׁv�̔F���͎��̊댯����N����s�ׂł͂Ȃ�����A
���s�s�א���F�����Ă��Ȃ��ƌ����咣�ł��B
�����Ƃ��A���̎咣�́u�s�ׁv�̔F���������ƌ����Ӗ��ł̖{����
���s�s�ׂ̔F���̌�㞂ł͂Ȃ��A�u���ʊW�̋N�_�v�ƂȂ�Ƃ����F���i�댯�n�o�̔F���j�̌�㞂ƌ����Ӗ��ł�����A
���ǂ͈��ʊW�̔F���i�댯�����Ƃ��̎����̂����̑O�ҁj������
�Ƃ������ƂƓ��`�ł���Ƃ������_�͉\�ł��傤�B
���̓_���A�h�C�c�ƈقȂ���s�s�גi�K�Ŋ댯�n�o��D�荞��ł��܂��䂪����
���_�̌n�Ǝ��̖��_���Ǝv���܂��B
�h�C�c�Ƃ��Y�@�w�҂����m��낗
���ʊW�F���s�v���̘_���Ăǂ�H�����Ƃ���Ȃ����ǂˁB
>>293
���Ⴊ���������ˁB���������܂��鎖����ɏo���̂͌ÓT�I������㩂�
>���_�̌n�Ǝ��̖��_���Ǝv���܂��B
���̕������悭�킩��Ȃ���ł����A�v����ɁA�h�C�c�ł͋q�ϓI�A���_��
���ʊW�ɂ����Ċ댯�n�o�Ɗ댯�̌������f����Ƃ������Ƃł����H
>>293�����艟���ŁA���ʊW�̋N�_�̔F���ƈ��ʊW�̔F�����Ă��邵�ȁB
���������A���s�s�א��̔F���ƈ��ʊW�̔F���͕�����ׂ����̂��낤���B
�S�R�Ⴄ����ȁB������O�̂��Ƃ������ł�낵���B
���艟���ň��ʊW�̋N�_�̔F���ƁA���ʊW�̔F�����Ă��邾���B
���ʊW�̋N�_�̔F���͎��s�s�ׂ̔F���ł͂Ȃ��Ƃ��������������B
������������������܂����B�z���g�ɌY�@�w�҂��H��
���ʊW�͏����W�ł����đ����Ƃ��A
�ʂɋq�ϓI�A����_����Ƃ������Ƃł��B
���̑ԓx�������������Ă���Ǝv���܂����A���̓_�������g�ŕς��Ǝv��Ȃ��̂ł����H
A���̓h�C�c�Y�@�ɏڂ������Ȃ̂ŕ֏掿�₵�܂��B
���ۓI�댯�Ƃɂ����āA�h�C�c�ł͂�����������͏������Ȃ�ł��傤���H
�܂��A�h�C�c�ł͂ǂ������������L�͂Ȃ�ł��傤���H
>>286��O��ɂ���ƁA�Z���Ԃɕԓ��������Ȃ��̃��X�͎������Ƃ������Ƃ�
�Ȃ�܂����A����ł�낵���ł����H
�������Ƃ����Ă��F�X����܂��̂ň�T�ɂ͌����܂��A
���������h�C�c�̌X�̊w�����̂ɂ���قǏڂ����킯�ł�����܂��A
�����Ȍ`�������̂錩���͂��Ȃ菭�����Ƃ������Ƃ͌�����Ǝv���܂��B
�ǂ������肪�Ƃ��������܂��B
������w�Ō������u�`�ł����Ă�낤�Ȃ���
>���ʊW�F���s�v���̘_���Ăǂ�H�����Ƃ���Ȃ����ǂˁB
�I�C����>>277>>279�œW�J�������肾���ǂˁB
�܂����u���ۖ��v�̈Ӗ���m��Ȃ��Ƃ��E�E�E��
���ۖ��Ƃ��ǂ��ł���������A���ʊW�F���s�p���̘_�����肢�������B
>>277��>>279�͘_�ɂȂ��ĂȂ��B�_����Ȃ��Ă������A�����𑁂������Ă݂�B
���O��������s�Ȃ݂̂͂�Ȓm���Ă��邩��A������Ɠ�����B
>>���ƂƖ������Ȃ��Ƃ����咣�͂��蓾��Ǝv���܂��B
����ȓ�����O�̂��Ƃ͏����Ȃ��Ă���������A������Ɠ�����B
�R�������ĔF���s�v���Ȃ́H���떳�W���̊ԈႢ�ł͂Ȃ��́H
>���̌����ł́A�u��ʓI�Ȍ��ʔ����Ɍ�������̓I�Ȉ��ʌo�߂̔F���v��K�v�Ƃ���ȏ�A
>���̌��x�ň��ʊW�̍������ɂ�����Ȃ��̂ŁA�_�Ƃ��ĕs�\���ł��傤�B
���̔ᔻ�́A�O�c����J���̈��ʊW�̔F���u�s�v�v���ˈ��ʊW�̍��떳�p�_
��O��Ƃ��Ă�����̂Ǝv���邪�A�I�C���i�Ƃ������R���j�͈��ʊW��
�F���u�K�v�v�������ʊW�̍��떳�p�_�ƍl����̂ŁA������Ȃ��B
�ڂ�����
�R���h��u�ߎ��Ƃɂ�������ʌo�߂̗\���\���ɂ��ā[���ʊW�̍���̖����܂߂ā[�v�֖@�Q�X���P���Q�W��
�����}�W��������������������ȁB���ꂪ�Y�@�w�҂Ȃ̂��E�E�E�E�i����
�R���搶�Ƃ܂������W�Ȃ��̂ɁA�R���搶���J�肠���镠�����͏��邗
�I�C����>>306�Ŋ��Ⴂ���Ă��B>>309�̂����Ƃ��肾�B
�܂��A���ʊW�͌̈ӂ̑Ώۂł���F���͕K�v�B
�������ʊW�̍���͌̈ӂ�j�p����قǏd�v�łȂ��A�q�ϓI�A���_�ʼn���
�ł��邩��A���ʊW�̍��떳�p�_�ɗ��B
�����𖾂炩�ɂ���ƁA�����̐��̂���邗�A���r�o�����X���˂��B�邗
������Ƃ������Ⴂ���B��ڂɌ��Ă���B
�u�L�`�K�C�v�Ƃ��u�A���r�o�����X�v�Ƃ����l��ᔻ�������������肷��
���Ƃ͊ȒP���B
HN�𖼏���Ă���I�C����A���͂��̃��X�N��w�����Ă���B
HN�𖼏��Ƃ͉]��Ȃ����A���܂ɂ͎���b��������ǂ����B
�A�����āA�R�e�n����������B���̓o�J�ȃR�e�n����_�j���Ă����Ă��邾�������炗
>>316
�͂��͂��A�R�e�n���Ȃ���K�v�͂Ȃ��B�N�̂悤�ȃ��x�����Ⴂ�R�e�n����{�C�ő���ɂ������Ȃ�����ˁB
>>193>>194��_�j������B
>>193��>>194�́A�O���̌Y�@�̊T���I��������H�_�j����K�v�����Ȃ�����B
�{�l���ӔC�������ďЉ�Ă��邾���炗
�ǂ�������p���Ă����Ƃ�����A�����ӔC�d�傾���ǂˁB
�����ŖĐ������Ă��H����ł��������B
���p�_�̘_�Ƃ��ẮA�u�d�v�łȂ��v�̓����𖾂炩�ɂ���K�v������Ǝv����B
���Ȃ킿�A���Ɉ��ʊW�̔F����K�v�Ƃ���Ƃ����ꍇ�ɁA���ʊW�̔F����������
�F�߂���ꍇ�͑S�ċq�ϓI�A���������ƔF�߂��鎖��ł��邩��A
������d�˂Ę_����Ӗ��͂Ȃ��Ƃ����l�����ɗ��ꍇ�ɂ́A
��͂���ʊW�̔F���������ꍇ�Ƃ͂����Ȃ�ꍇ���i�]���Ɠ��l�u�������ʊW�v�͈̔͂̕����������đ����̂��A
�댯�n�o�Ɗ댯�����͈̔͂Ƃ����悤�ɕϗe�����Ĕ��f����̂��j�ɂ��āA���̔��f��������A���̏�ŁA
�q�ϓI�A���������ꍇ�ł����āA���ʊW�̔F���������ꍇ��S�ė]���Ƃ���Ȃ���܂��邱�Ƃ�
�_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̓_�̘_���K�������s������Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv����̂ł���B
�܂��A���ɂ��̓_���_�ł����Ƃ��Ă��A���ʊW�̗v�f�Ƃ��ċq�ϓI�A����v������Ƃ���A
����������ꍇ�ɂ͖����ƂȂ�͂��ł��邪�A�̈ӂ������ꍇ�ɂ�
���������ߎ��ƂƂȂ�ɉ߂��Ȃ��Ƃ���A�q�ϓI�A���������A
�����ʊW�̔F���������Č̈ӂ��ے肳���ꍇ�ɂ́A�����ŁA���A
�̈ӂ��������ƂɂȂ邩��s���ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪����B
���̓_�ɂ��āA�K�������������s������Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B
���ǂ͂�����ᔻ�������������낤�Ȃ���
>>312�͘_������菑���Ă���킯�ł͂Ȃ����낤�B�d�v�ł͂Ȃ��Ȃ�č����ɂ͂Ȃ��ȁB
������n���ł����O�̑��l�i�ł��A������ւ�͂�����Ɛ����t����B
���ʊW�������ꍇ�������Ȃ�ꍇ�̔��f��͖��炩�ɂ��Ȃ��Ă����͂Ȃ����낤�B
�����ł͂��������b�ł͂Ȃ��B�������A�q�ϓI�A���ƈ��ʊW����������ɍl���Ă���悤����
���s�����낤�B
��������������ꍇ�ɂ͖����ƂȂ�͂��ł��邪
���s���B
�����q�ϓI�A���������A
�������ʊW�̔F���������Č̈ӂ��ے肳���ꍇ�ɂ́A�����ŁA���A
���̈ӂ��������ƂɂȂ邩��s���ƂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��
���₻���͂Ȃ�Ȃ����낤��
�q�ϓI�A���_�ɑ��ĕ��s����I�悵����A�q�ϓI�A���_�̖{����S�������ł��Ă��Ȃ��悤�ł��ȁB
����ȃL�`�K�C�ł��Y�@�w�҂ɂȂ���ł���B�݂Ȃ���
>>322
�M���͊��Ɏ��̎����ł��邱�Ƃ������Ř_���Ă��܂�����A
�M���̃��X�͎��̃��X�ł��B
���ꂩ��A�咣������ɓ������ẮA�K�����R��t����Ƃ��납��A
�܂��͊撣���Ă݂Ă��������B�w�͂���ł���͂��ł��B
�������Ă��܂��B
���O����������Ƃ����B�����͂��Ȃ����ǂ�
�a�C�ɂȂ�ĂȂ�킯�Ȃ���ȁB�����������Ƃ��Q�����˂�Ō����邵�A
�l�ԊW�������ȓz������A��������Ⴂ���b�����A
�w���ɂ͓K���ɋ����Ă�����������ȁB
��w�@���͂ς��炵�āA���ׂ��B�Q�����˂�Ŏ��⎩���B
�����̎x�����Ă��锽�ΐ���ᔻ���邗�����y�ȏ�����ł���
���z�ȓz���ȁB�R�e�n���Ɋ��邵��������p��m��Ȃ��Ȃ�āB
�@�P���U���@�h�c���l�q���e�R�W�W���@�@�P�O��
�@�P���V���@�h�c���c�d�g�d�l�k�y�ke�@�@�P�R��@�@
�P���W���@�h�c���k�h�q�l�W�X���U�@�@�@�Q��
>>328
>�Y�@�w�҂́A�������̃X���ɗ���Ȃ悗
�����]���Ă�B�����͖@�w�����B
�N�����i�@�ɋA��B
���ꂩ��A�������Ƃ������Ă���B
�N�́A�I�C���Ƃ`��������l�����Ǝv���Ă���悤�����Ⴄ���B
�`���́A�ȑO���@�X���Ŋ����u�����̒�q�v����B
�@�w�ł��A�W�Ȃ��M�l�̂悤�ȃN�Y������̂͂��������B
�Y�@�w�҂Ƃ��Ēp��m��B
�ō��ق́u���s�ƂR���̎E�Q�v��́A�N�����t�H�������z�������Ă`�����_
��������A���̎��_��Ԃ𗘗p���Ă`���`�܂ʼn^�ю����Ԃ��ƊC���ɓ]��
�����Ăł���������Ƃ������̂ł����āA�E�E�E���Ƃ��A���s�ƂR���̔F����
�قȂ�A��Q�s�ׂ̑O�̎��_�ł`����P�s�ׂɂ�莀�S���Ă����Ƃ��Ă��A
�E�l�̌̈ӂɌ�����Ƃ���͂Ȃ��A���s�ƂR���ɂ��Ă͎E�l�����̋�������
����������v�Ɣ��������B
�������A�퍐�l�Ɂu�N�����t�H�����ł͎��ȂȂ��v�Ƃ����F�������Ȃ��̂�
����A�C�ɓ]�������Ď��S������Ƃ����̂́A�E�l�\���߂ɂ�����u�E�l��
�ړI�v�ł����āu�E�l�̌̈Ӂv�ł͂Ȃ��B
�����A�s�҂��K�ʂ̃N�����t�H�������z�������Ĉӎ������킹���i���ꂪ
�s�҂̂ɂ��ł���j���_�Ŕƍs�����o���A�s�҂��ߕ߂���Ĕ�Q�҂�
���ȂȂ������Ƃ���A������E�l�����Ƃ��邱�Ƃɂ͖���������A��������
�E�l�\���߂��F�߂���ɂ����Ȃ��Ǝv����B
�{���́A�s�҂̔F���ł͗\���]��s��
�{���́A�s�҂̔F���ł͗\���s�� ���猋�ʂ������������̂Ƃ��āA�E�l�\��
�Ə��Q�v���̂̊ϔO�I�����Ƃ��ׂ��ł������B
���_���|�F��c�a�Ɂu����Ɍ�����ߌY�@���`�̊�@�v�����ٖ@�w�Q�O�P�Q�N�T�E�U���P��
���_������ǂ����B
���O�͂��̐����x�����Ă���킯����Ȃ�����H��
���Ȃ�A���Ԃɂ���Ă݂�悗���L�`�K�C�Y�@�w�҂����B
�����玩�⎩��������Ă���̂͂`���i�����̒�q�j�����ĂB
�N�Ɂu�X�����r�炷�ȁv�Ƃ͉]��ꂽ���Ȃ��ˁB
���ꂩ��A���Ԃ͖{�E�̌����ŖZ��������N�̑��������ɂ͂Ȃ��B
�܂��Y�@�w�҂��Ǝ��������ˁB�����Ȃ��Ƃ��B
�������v�́A����ɐi��ŁA�̈ӂɂ́u�\���̌̈Ӂv�u�����̌̈Ӂv
�u�����̌̈Ӂv�̎O�킪����Ƃ��A���������\���v���̎����́A
�����̌̈ӂŊ������ʂ�����������A�����̌��x�ŐӔC����
�l����悤�ł���i�R�����������z�̂悤�ł���j���A����͏]���̌Y�@���_�̌n��������̂��A
��a�����ʂ����Ȃ��B�������ʔ�����F���i�y�єF�e�j���čs�ׂ��A
�������������ʔ����𐋂��Ȃ��������̂𖢐��ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ������̂��B
�u�댯�͔������邪���ʂ͔������Ȃ��v�Ƃ����F���́A���������F������ߎ��ł��낤�B
���يۏo����
�w�҂̕��y�Ȏd���̑ԗl���l����Εa�C�ɂȂȂ�킯�Ȃ�����ˁB
�����̍u�`�E�����撣���ĂȁB�����Ƙ_���o���悗
�������v�́A���_�Ƃ��āA�E�l�����߂Əd�ߎ��v���߂̊ϔO�I�����Ƃ���̂�
���邪�A����𗝉�����ɂ́A�����̍s�ט_�Ǝ��s�̒��莞���ɑ���l����
�i�ܒ����j�A����ɂ́A�����Ǝ��̌̈Ә_�E����_��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����́A�܂��u�s�א��̔��f�Ǝ��s�s�א��̔��f�Ƃ͋�ʂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�Ƌ�������B���Ƃ��A�N�����z�����E�l�����̂悤�ȕ����s�ׂ����ƂȂ�
�ꍇ�A�����ł́A�s�ט_���x���ōs�ׂ��Q�ł��邱�Ƃ��m�肳��A���̎��ɁA
�u��A�̎��s�s�ׁv�Ƃ����悤�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���i�܂��ɁA�ō��ق́A
���̂悤�ɔ��������B�������A�����́A��q�̂Ƃ���A���̂悤�ȍl�����ɂ�
���ł���j
�s�҂̕����s�ׂɂ���Ĕƍ߂��������ꂽ�ꍇ�A��Q�s�ׂ��A�v���I����
���ʂ̉�ݎ���ƈʒu�Â��邱�Ƃ͂ł����A���s�s�ׂ̓���̖����N���A
���Ȃ���Ȃ炸�A�����̎��s�s�ׂ����݂���ꍇ�ɂ͗��҂̊W����₢�A
��Q�s�ׂ���ݎ���ƕ]�������ꍇ�ɂ́A���ʂ̉�ݎ���̖��A���邢�́A
���ʊW�̍���̖�����������i���邢�͌������Ȃ��j�Ƃ����v�l�����ƂȂ�B
�@�@�y�����z
�N�����z�����E�l�����Ƃ���ɑ������É����ٕ����P�X�N�Q���P�U���́A
�@��P�s�ׂ̕s�����A�A��Q�ƂȂ���i�̎���̕s���݁A�B���ԓI�E�ꏊ�I
�ߐڐ��A�Ƃ����R�̊���̗p�����B
���̂悤�ɁA�����s�ׂɂ�������s�̒��莞���ɂ��ẮA��P�s�ׂƑ�Q�s��
�Ƃ̊W����Ƃ�������A���̍ہA�s�҂́u�s�ӎv�v�u�s�v��v��
�d�v�Ȕ��f�v�f�ƂȂ�̂ł���A����͂܂��Ɂu�ܒ����v�̓K�p�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�Ƃ���ŁA�̈ӂɂ́A�u�\���v���I���ʂ̔F���v�Ƃ����v�f�Ɓu���s�s�ׂ�
�����̔F���v�Ƃ����v�f�̂Q���K�v�ł���B��҂ɂ��ẮA�@���ۓI�댯
�Ɏ�����̂Ƃ̔F���i�\���̈Ӂj�A�A��̓I�댯�Ɏ�����̂Ƃ̔F���i�����̈Ӂj�A
�B�댯�̊����Ƃ��Ă̎����Ɏ�����̂Ƃ̔F���i�����̈Ӂj�Ƃ����悤�ɒi�K
������B
�N�����z�����E�l�����́A��L�̇@�ƇA�̔F�������Ȃ��Ƃ���A�B�̎�����
���������̂ł��邩��A�u�����̌̈ӂŊ������ʂ����������v�̂ł���A
�R�W���Q���ɂ��i�����\���v���Ɗ����\���v���Ƃ̊Ԃ̍���j�A�E�l������
�̐������F�߂��邱�ƂɂȂ�B
�@�@�y�I���z
������>>340-342�̂悤�ɂ����̓W�J��
��͂�Y�@�w�҂̉����[�̑�w�̊w�҂��Ɠ�������ȁB���Ԓm�炸����
�������ɑ����̋��ȏ��i���Ƃ��Α�J�U�Łj���u�s�K�́v�Ɓu�ٔ��K�́v��
�Βu�����钆�A�����́u�Y�@�̋@�\�́A���ǁA�s�K�͂Ɛ��ًK�͂̋@�\��
�������Ƃł���v�Ɩ�������i�����Q�O�Łj
�Y���@�K�́A�u�ٔ��K�́v�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�Y�@��́u�s�K�́v
������ƂƂ��ɁA���́u�s�K�́v�Ɉᔽ�����ꍇ�ɂ͌Y�����Ȃ��Ƃ���
�u���ًK�́v������̂ł���B���������āA�u�s�K�́v�Ɓu�ٔ��K�́v
�Ƃ����Βu�̓~�X���[�f�B���O�ł��낤�A�Ɓi���P�O�Łj
�s�K�͂Ɛ��ًK�͂̋�ʂ́A�K�̖͂����l�ɂ���ʂł����邪�A�ނ���
�K�͂́u�v���v�����Ɓu���ʁv�����̋@�\�ɏd�_��u������ʂł���B����
�悤�ȋ�ʂ́A���łɃr���f�B���O�́u�K�́v�Ɓu�Y���@�K�v�̋�ʂɂ݂�ꂽ�B
�s�K�́i�uehalten��norm)�́A�l�X�̍s�ׂɎw�j���������Ƃɂ���Ĕƍ߂�
�s���Ȃ��悤�Ɏ��O�I�ɗ\�h����@�\�ł���B�����ɂǂ̂悤�ȍs�ׂ��֎~
����Ă��邩�����m����̂��s�K�͂ł���B
�����āA���O���m�ɂ�������炸�A�s�K�͂��N�Q���ꂽ�Ƃ��ɁA���ق��Ȃ���
���Ƃɂ���āA����I�ɂ��̔ƍ߂̂����炵�����ʂ����E���A�Љ�̓��h��
���É�����K�v������B���̂��߂ɒ�߂�ꂽ�K�͂����ًK�́i�ranktionsnorm)
�ł���B
��J�͕ʂɑΒu���ĂȂ���B���������A��J�͂����܂ŋK�͘_���d�����Ă��Ȃ�����ˁB
�����łłǂ��Ȃ��Ă邩�͂����
�����́A�t�ŋK�͘_���d���������Ă��邩��ˁB�K�͘_�́A�Y���_�ɂ����Ȃ�����B
�ƍߘ_�ƌY���_�͕�����ׂ�����B���ʂ́B
�܂��N���N���X�}�X���琳���R�����͗]�ɂ��y����ł������Ƃ͖��炩�����A
���쎩�������܂����Ă���̂����炩�ł��傤�Ȃ��B
���̂悤�ȍl�����ɗ��ƁA�]���F������ߎ��Ƃ���Ă������̂܂ŁA�u�����̌̈Ӂv�ɕ�܂���Ă��܂�Ȃ����B
���Ȃ킿�A�u�������H�ɐl���吨����̂ŁA�����x�œ˂����߂ΐl�������������̓I�댯�͐����邪�A
�����̉^�]�Z�p�ł�����̊댯�͌��������Ȃ��ł��낤�v�Ƃ����F���́A
�]���F������ߎ��Ɛ�������Ă����͂��ł��邪�A
�����̌̈ӔƂ��������邱�ƂɂȂ肻���ł���B
�m���ɁA�O���܂ō\���v���I���ʂ̔F���i�y�єF�e�Ȃ����͎����ӎv�j��v���邩��A��͂�̈ӂ͂Ȃ��Ƃ����̂�������Ȃ����A
����Ȃ�A�\���v���I���ʂ̔F���Ƌ�̓I�댯�����F�����Ă��Ȃ������̈ӂƂ͖������Ȃ��̂��B
����������Ȃ悤�Ɏv����B
�����s�K�͂Ɛ��ًK�͂̋�ʂ́A�K�̖͂����l�ɂ���ʂł����邪�A�ނ���
�����K�͂́u�v���v�����Ɓu���ʁv�����̋@�\�ɏd�_��u������ʂł���B
��̓I�Ȏ���Ƌ�̓I�ȋ�ʂȂǂ���Ă݁B
�̂悤�ɁA��ɔᔻ���悤�Ǝ��쎩�����n�܂�B
�����̎x������w���́A�������ł��A�R�����ł��A�R�����ł��A�Ȃ�����˂�
>>346=>>348�͓���l���B�����o���o���B
�⑫���Ă���Ɛ錾���Ă��邤���ɁA�قƂ�Ǔ������́B
������ƁA>>349�ɓ����Ă݁B
���ł�ID(IP)��ς��Ă̏������݂͂Ȃ���Ă��邩��A
ID�ł͐����ł��Ȃ���
���ɂ������Ƃ���ƁA���Ȃ��Ǝ�������������ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂����A
�B�ꎩ�����ł����ɐ^��Ń��X���Ă�l�͂��Ȃ������ɂȂ�܂��ˁB
�B��ނ��Ă�l�ԂƂ��Ēp���������Ƃ͎v��Ȃ��̂ł����H
>���̂悤�ȍl�����ɗ��ƁA�]���F������ߎ��Ƃ���Ă������̂܂ŁA
>�u�����̌̈Ӂv�ɕ�܂���Ă��܂�Ȃ����B
������ɂȂ邪�A>>341�́A�����̎咣��v�����̂ł���A�I�C�����g��
�l���ł͂Ȃ��B
�u�������H�ɐl���吨����̂ŁA�����x�œ˂����߂ΐl�������������̓I
�댯��������ł��낤�v�Ƃ����F�����A��������͓��̒��̑��ɕ�����
�オ�������u�����̉^�]�Z�p�ł�����̊댯�͌��������Ȃ��ł��낤�v��
�����ł��������ꍇ���F������ߎ��ł���A�����ł��������u�l������
�������̓I�댯��������ł��낤�v�Ƃ�������ł������Ȃ������ꍇ��
���K�̌̈ӂł���i���R���j
�Ȃ��A>>193>>194���Q�Ƃ��Ă��������B
�������A������ƒ��삩����p����̂Ȃ�A����܂ŏ������ق���������B
�펯�����ǁB
���ꂪ����l������Ȃ��ƁA�L�`�K�C�Y�@�w�҂��Q�l�����邱�ƂɂȂ�ȁB
�Y�@�w����Ăǂ������w�����Ă���̂��낤���E�E�E�E�B
�������������Ă���悤�ɏ��������A���͑S�R���������Ⴂ�Ȃ���
�Ƃ��ɁA�P�O�O�ł́u�s�K�͈ᔽ�Ƃ��Ắw���s�s�ׁx�Ɛ��ًK�͔�������
�Ƃ��Ắw��̓I�댯�x�v�͓���B�v���
>���s�s�ׂɂ�����댯�̓��e�́A�u�s�ׂ̖@�v�ւ̒��ۓI�댯�v�ő�����
>����>���_�Ɏ���A�܂��A���s�s�ׂ̊J�n�ł�����s�̒�������l�̔��f���s��
>�K�v�����邩��u���s�s�ׂƎ��s�̒���Ƃ͓������݁v���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
>����ɑ��āA�����Ƃɂ�����댯�́A���ꂪ�������邱�Ƃɂ��A�����Ƃ�
>�������m�肳�����̂ł���A���̊댯�̔����͐��ًK�͂̔��������Ƃ���
>��������ׂ��ł���B�u���ًK�͂̔��������Ƃ��Ă̊댯�́A�s�q�́i�����
>�@�v�j�ɑ����̓I�댯�v�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
���̓_�Ɋւ���A����̈ӌ������肢�����B
>
>
>
���@��U�҂ɋ������肤���̖��������ԓx
���ɃA�z�ȌY�@�w�҂炵���Ă����˂�
�����X�����A�s�K�́��s�ז����l�A���ًK�́����ʖ����l�Ɠǂݑւ����
�킩��₷����Ȃ��낤���B
�s�ז����l�̊ϓ_����́A���ۓI�댯�ő����B
�������A�Y�����Ȃ��ɂ͌��ʖ����l���K�v���B
�����ł͋�̓I�댯�̌��ʔ������K�v�Ƃ����ƁB
�����悤�ȍ\�z���̑��c�������Ƃ��Ă���B
���c�����́A�s���K�́��s�ז����l�A���ًK�́����ʖ����l�Ɩ������Ă���B
�w��̏�C�����ɂ��������ᔻ�́A�G�z�����邯�Ǎ����́A����܂�Y�@�̂��Ƃ킩���ĂȂ���Ȃ��́H
���ۓI�댯���������Ă��A���������ƍߗތ^�͂����ˁB
>���ۓI�댯���������Ă��A���ق͂Ȃ��́H���������Ȃ��H
�����́u���s�s�ׂ͍s�K�͈ᔽ�̍s�ׂł���A���̊댯���̓��e�́A�@�v��
���钊�ۓI�댯�ő����v�Ɩ������Ă���i�R�U�Q�Łj
>>360�͊��S�Ȍ�ǁB
����悤�Ɏv����B
�u���s�s�ׁv�Ɓu���s�̒���v�Ɓu�����Ɛ����v�̊W�ɂ��Ă͎��̂R��
�p�^�[��������B
�@���s�s�ׁ����s�̒��聁�����Ɛ����i�ʐ��j
�A���s�s�ׁ����s�̒��聁�����Ɛ����i����Ȃǁj
���s�̒���Ƃ����T�O��P�Ɏ��Ԃ��悷��T�O�Ƒ����A��̓I�댯�̔����܂�
�͂��܂��\���s�ׂƂ���_�ɈӖ�������B
�B���s�s�ׁ����s�̒��聂�����Ɛ����i�����j
���s�̒���Ɠ����Ɏ��s�s�א��͍m�肳��邪�A����͖@�v�ɑ��钊�ۓI
�댯���ɂ���Ĕ��f����A���̌�A�@�v�ɑ����̓I�댯������������
�Ƃ��ɖ����Ƃ̐������F�߂���B
���s�s�ׂƓƗ����đ��݂���̂ł͂Ȃ����낤���B
���s�s�T�O�̒��ɍ\���v�����������������X�b�L������Ǝv��
�v�����܂܂ɏ����Ă݂�B�ԈႢ�͂��w�E�������������B
�s�K�͂Ƃ́A�����ɑ��A���̓��@�t���ɓ��������Ă��̍s���𐧌䂷��K�͂Ƃ��Ă̌Y�@�̈ꑤ�ʂł���A
���ًK�͂Ƃ́A�����Y����������v���Ƃ��ċ@�\����Y�@�̈ꑤ�ʂł����āA��ʂɂ͍ٔ��K�͂ƌĂ����̂Ɓi�{�l�͈Ⴄ�Ƃ������j���̂Ƃ��Ă͂قړ������B
�Y�@�ɂ��̂悤�ȂQ���ʂ����邱�Ƃ͈�ʂɔF�߂��Ă��邱�Ƃł���A�V���������Ƃ͂����Ȃ��B
�s�ז����l�_�҂͈�ʂɑO�҂��d�����A���ʖ����l�_�҂͈�ʂɌ�҂��d������B
�������_�́A����Η��҂�ܒ��I�Ɏ�荞�_�ɓ��F������B
�s�K�͂��d�����錩���ɗ��ĂA�K�͈ᔽ�s�ׂ����s�s�ׂł���A���ꂪ�������ȏ�A���������A���������\�ƂȂ�B
�����A���ًK�́i�ٔ��K�́j�݂̂��d�����錩���ɗ��ĂA�v����ɌY���������v���̏[�����݂̂��l�����������A
���s�s�ׂƂ����Ǝ��̊T�O�͕s�v�ł���i�R�����_���Łj�A�����Č����Ζ��������v���ł�����s�̒���Ɠ��`�Ƃ����A���ɂȂ�B
������ɂ���A���s�s�ׁ����s�̒��聁�������������藧�B
�܂����s�s�T�O�́A�Y�@�̋K�����铮�@�t���ɔ����Ă��ꂽ�_��
�{�������邩��A�s�K�͈ᔽ�s�ׂƂ��đ�������B
��������ƁA���s�s�ׂ͕K��������̓I�댯����������̂Ƃ͌���Ȃ����ƂɂȂ�B
�������A�\���v���͌��ʔ����̒��ۓI�댯�̂���s�ׂ�ތ^�����Ă���ȏ�A
���ۓI�댯�͏�ɔ�������i�t�Ɍ����Β��ۓI�댯���甭�����Ȃ��s�ׂ�
���s�s�ׁi�K�͈ᔽ�s�ׁj�ł���Ȃ��j�B
�����A���������̍����ƂȂ���s�̒���̊T�O�́A
���������̌Y���������v���ł��邩��A���ًK�́i�ٔ��K�́j�̖��ł���B
�]���āA�������������_���猋�_���������B
���Ȃ킿�A���������ɒl����댯�A�܂��̓I�댯�̔�����v����ƂȂ�B
�����āA���̗v�����[�����Ζ�������������B
�ȏ�̋A������A���s�s�ׁ����s�̒��聁���������̊W�ƂȂ�B
���������v���Ƃ��Ė����ɋK��̂Ȃ���̓I�댯��
�v����Ƃ��闧�ꂾ�����̂ŁA>>367�͓P��B
���ًK�͂Ƃ��ċ�̓I�댯��v����Ƃ���̂͗����ł��邪�A
���s�s�ׁ����s�̒���Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����R��
���������l����K�v�����邱�ƂɎv���������B
�P�@���̏���
�̈ӂ��铹��𗘗p�����ꍇ�́A���p�҂��Ԑڐ��ƂƂ���̂��킪���̒ʐ���
����i�ȉ��u�Ԑڐ��Ɛ��v�Ƃ����j�B����ɑ��āA���p�҂������ƂƂ�
�험�p�҂�ƂƂ�����i�ȉ��u�����Ɛ��v�Ƃ����j���L�͂Ɏ咣�����
����i���A���R�A�R���A�쑺�E�����Ƃ̌����A�ē��M���j�B���̓_�Ɋւ���
�����̑Η��́A�Ԑڐ��Ƃ��ǂ͈̔͂ŔF�߂邩�Ƃ������{�I�ȗ���̑����
����A�ȉ��ł݂�悤�ɗe�Ղɉ����������ɂȂ��B
�܂��A�g���Ȃ��̈ӂ��铹��𗘗p�����ꍇ�ɂ��ẮA������������Ƃ�
��������L�͂ł���i�����E�ƍߎ��s�s�ט_�A�]���E�d�v���A����E�O�c�A
�R���A���c�E���ƁE���Ƙ_�̊�b���_�j�B���d�߂�O���ɁA�[�I�ɒ��ڐ���
�ł���Ƃ����������i�����A���{�j
�̈ӂ���I����̏ꍇ�ɂ��ẮA�Ԑڐ��ƂƂ�����i�c���A��ˁA���q�A
���A����A��J�j�����邪�A�����Ɓi���c�A�쑺�A�R���j�܂��͋�������
�i�����A�]���A����j�Ƃ���̂��������ł���B����ɂ́A���d�������Ƃ�
�����������i�����A�O�c�j
�Ԑڐ��Ɛ��ɑ��ẮA�Ԑڐ��Ƃ͌����u�����̊Ԍ��v�߂邽�߂̕�[
�T�O�ł��������u���̕�[�I�����̗v�����A����_�̂悤�ȐϋɓI�_��
�g���āA�Ԑڐ��ƊT�O���剻�����v�Ă���Ƃ����ᔻ������i�R���j
�����A�����Ɛ��́u���Ǝ��̂����肷�邱�Ƃɖܘ_����Ȃ�̈Ӌ`��F�߂���
�Ƃ��Ă��A���Ƃ����肷�����ɋ��Ƃ��ɂ₩�ɍm�肷��̂ł́A���ۏ��
�Ӌ`�ɂ͖R�����v�Ɣᔻ����Ă���i�R���E���T��)�B�܂��A�����Ɛ���
�u���ƂȂ����Ɓv��F�߂���̂ł���s���ł���Ƃ����A��茴���I�Ȕᔻ��
����i��q�R�i�P�j�j
����ł́A�����̐��ۂ͖����ɏ����ꂴ���̓I�댯�Ō��܂邩��A
�u���s�̒���v�T�O�͓��ɕK�v�̂Ȃ��T�O�ɂȂ��Ă��܂�Ȃ����B
�S�R���̉��ߘ_�Ƃ��Ă͑傢�ɋ^��ł���B
�����ł���A���s�s�ׁ����s�̒��聁�����Ɛ����̐}���̕����Ó��Ȃ悤�Ɏv����B
���������A�m���ɂ��O�Y�@�w�҂���Ȃ�
�y�j���ɂȂ����炱��Ȃɒ��ԂɃX���L�т�Ȃ�Ă����������낗
�Y�@�w�����X�B�L�`�K�C�����X��
>>�s�K�͂��d�����錩���ɗ��ĂA�K�͈ᔽ�s�ׂ����s�s�ׂł���A���ꂪ�������ȏ�A���������A���������\
�N������Ȃ��Ə����Ă���́H
�������ًK�́i�ٔ��K�́j
���ꗼ�҂͈Ⴄ�T�O�Ȃ�ł���H�N������Ȃ��Ə����Ă���́H
���܂������������ނ̎��߂Ƃ���B
����
371���ǂ�Ȑ������Ă邩�m���
������Ă悭�l�����炨��������ˁB���ۓI�댯���������Ă��Ă��A��������Ȃ��\����������Ă��Ƃ���H
���ۓI�댯�͔������Ă����ٔ������Ȃ��\����������Ă��Ƃ���H
>>362�͉ɂȂ��ĂȂ��B���ǁA�������������Ă����Ȃ����B
>>373
���ʂ̉�Ј����Ɠy�j�����o�ł���B�Y�@�w�҂݂�����
�y���͊m���ɋx�݂Ȃ�Ă��Ƃ͂���܂���킗
�ނ���Y�@�w�҂̕��ɋ߂������X�^�C���Ƃ���������
���O�͌Y�@�w�҂����ăo���Ă���B
�w�������Ȃ̂������ɂ��Ă���悤����A���܂蔭�W���͂Ȃ��������Ȃ�
���Ⴀ���O�͂Ȃ�ŏo���ĂȂ��悗����
��������B���c�Ƃ����炗
�����̒��Ԃ��������݂ł���킯���B
�����̒��ԏ������݂ł��Ȃ��̂ɁA�y�j����j�A�j���ɂȂ�����Ȃ菑�����݂��܂���̂�
�Y�@�w�҈ȊO�l�����ȁB�y�j�x�݂̕��ʂ̉�Ј��͍����N���Ă��邾�낤���Ȃ�
�Y�@�̃X���Ȃɏ������݂����Ȃ����낤��
�����Ԃ����ȃ��m���������c�ƂȂ낤��
�i�P�j�Ԑڐ��Ƃ̐��Ɛ�
�Ԑڐ��Ƃ́A���j�I�ɂ́A���k�I���ƊT�O�Ƌɒ[�]���`���̑o�����̗p����
���߂ɐ������u�����̊Ԍ��v�߂邽�߂ɍl�Ă��ꂽ�Z�I�I�T�O�ł��邱��
�́A��ʂɏ��F����Ă���B�w���́A���̂悤�ȏo�������Ԑ�z���Ƃɉ��Ƃ�
���Ɛ���^���悤�Ɠw�͂��Ă����B
�@���p�҂̔험�p�҂ɑ���s�x�z���ɋ��߂錩���i��c�E�ƍߘ_�̌��݁j
��c�����́u�������E�̎��ۂ́A���ʓI����ƖړI�I����Ƃ�����̈قȂ���
����`���ɕ�����B���̖ړI�I����̑w�Ɉʒu�Â�����̂��s�x�z�̊ϔO
�ł���A�s�x�z���ړI�I����̒��j�ƂȂ�v�f�́A�w�����̎��ۂ��q�ϓI��
�`��������q�x�Ƃ��Ă̍s�ӎv�ł���̈ӂȂ̂ł���B�����炱���A�ߎ���
�ɂ��ẮA�댯���͂����Ă��s�x�z�͑��݂��Ȃ��Ƃ���邵�A���ʂɂ�����
���ʔ�����}���҂Ɍ̈ӂ����@���A�w��҂��S�̂����ʂ��Ă���Ƃ��́A
���̔w��҂Ɏx�z�����F�߂���v�Ƃ����B
�A�������ړI�I�s�x�z�ɋ��߂錩��(���c�j
���c���m�ɂ��ƁA�ړI�I�s�x�z�Ƃ́u�\���v���I���ʂ���������ӎv��
�����āA���̎����̂��߂ɁA�ړI�I�Ɏx�z�E���������O���I�s�ׂ𐋍s����
���Ɓv�ł���B�ړI�I�s�x�z�́u�s�ׂ���ρ��q�ς̑S�̍\����������
�ł���Ƃ���ړI�I�s�ט_�̗��ꂩ��A���ƊT�O�̈�ʓI�v�f�Ƃ��Ă̖ړI�I
�s�x�z����ρ��q�ς̍\���������̂Ƃ��Ĕc���v������̂ł���B
���Ԃ��k�߂ĘA���ŏ������݂��ĕʐl���̂�
�}�j���A���ʂ�炵���̂ŁA�S���H��ɂȂ��ĂȂ��B���͂�o���Ȃ�
�Y�@�قǓ���Ȃ��̂ł͂Ȃ��悗��
>>364-370�܂őS���̈Ӗ��̕�����Ȃ��������݂Ȃ̂ŁA
���߂ɍ폜�˗��ł��o���Ă���邩�H��
���Ⴀ�����w�҂��Ȃ�����
�͂��͂��A�����������炗�C�����������X��
���c�Ƃ����͖ق��Ă�悗��
�{���ɓ���l�Ǝv���Ă�Ȃ炻���L�������낤��
���̗����������A����l���Ƃ��������Ȃ���Ȃ���
����ȃA�z���Q�l������킯�Ȃ����炗
��^���Ԃɂ��ĘA������p�Ɛ��O�̎��c�Ɓi���j
�������m�́u�i���ƂƋ��Ƃ́j���E���悷���́A���p���悤�Ƃ��鑼�l��
�K�͓I�ɂ݂Ĕƍߎ����̏�Q�ƂȂ邩�ǂ����Ƃ������Ƃł���B�@�����́A
�ӔC�\�͂̂���҂ɑ��Ă͈�@�s�ׂ�����A�K�@�s�ׂɏo�邱�Ƃ����҂���
����B���̊��҂̉\�ȎҁA����������Έ������s�ד��@�ɑ��ėǂ��s��
���@���`����������쒀����\�͂������A���̔\�͂������Ԃɂ���҂�
��݂����ꍇ�A�@�����̗��ꂩ��́A����͔ƍߎ����̋K�͓I��Q�ƍl���Ȃ�
��Ȃ�Ȃ��B���̐l�Ԃł����Ă��A���ꂪ�K�͓I��Q���肦�Ȃ��ꍇ�A����
���p�݂͂�����̎�Ŕƍ߂���������̂Ɠ��l�ł���A�����ɐ��Ɛ����F�߂�
���v�Ƃ����B
�C���ڐ��ƂƈقȂ�Ȃ����s�s�א��ɋ��߂錩���i���c�j
���c���m�́u�������F���̂��Ƃł́A�Ԑڐ��Ƃ́A�܂��Ɂw���s�s�ׁx��
�s�������䂦�Ɂw���Ɓx�Ƃ����̂ł����āA�험�p�҂̖@�I�����ɍ��E
�����ׂ����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ����ׂ��Ȃ̂ł���B�Ԑڐ��Ƃ̐����v���́A
�܂��ɖ{�l�̎��s�s�ׂɋ��߂���ׂ��ł���v�Ƃ����B
�D�험�p�҂̗��p�Ɉ��̔ƍ߂��������錻���I�댯�������o����邱�Ƃɋ��߂錩���i��ˁj
��˔��m�́u�Ԑڐ��Ƃ̐��ƓI���i�̎��̂́A���̏ꍇ�ɁA���ڐ��ƂƎ��I��
�قȂ�Ȃ����s�s�א����F�߂��邱�ƁA���Ȃ킿�A�w��̗��p�҂̍s�ׂɂ́A
��ϓI�ɂ́A���s�̈ӎv���������A�q�ϓI�ɂ́A�험�p�҂̗��p�Ɉ���
�ƍ߂��������錻���I�Ȋ댯�������o����邱�Ƃɂ���Ƃ����ׂ��ł���v��
�����B
�L�`���Ƃ������p�����ق���������B�L�`�K�C�Ȃ̂�
�����ȊO�͂ǂ��ł������̂��H��
���c�����́u�@���ʔ����܂łɉ�݂������ׂĂ̐l�̍s�ׂ��w��҂̐��Ɛ���
�e������\��������A���A��݂����ҁi�s�ה}��ҁj�̍s�ׂ����̑���
��L���鎞�ɁA�w��҂̐��Ɛ����ے肳���B�����āA���̂悤�ɂ��Đ��Ƃ�
�������ے肳�ꂽ�ꍇ�ɋ��Ƃ̐��������ƂȂ�A�B���ƍs�ׂ�������ʂƂ�
���ʐ��Ɛ��ƍs�ׁE���ʂ̑��i�̗\�������Ɛ����̂��߂ɕs���ł���v��
�����B
�u�s�x�z�v�A�u�ړI�I�s�x�z�v�A�u�K�͓I��Q�v�A�u���s�s�א��v�A
�u�����I�댯���v�A�u�k�y�֎~�_�v�|������̊T�O����`�I�łȂ��A��Ƃ���
���e���s���m�ł���B
�Ԑڐ��Ƙ_�̐��I�����҂ł���i���a�R�R�N�A�w�Ԑڐ��Ƃ̌����x�j��˔��m���A
����_�A�������i�������j�A�������A���ʊW���f�_�A�k�y�֎~�_�A���k�I���Ƙ_�A
�g���I���Ƙ_�A�����Q�̐��Ƙ_�A�ړI�I�s�ט_�����������������ŁA
���_�Ƃ��āu�⊶�Ȃ���A�킽�����́A���܂����ɂ���i��薾�m�����
��̓I�Ȋ�j�������Ȃ��B�������āA���悤�Ȉ�ʓI�K���́A���邢��
���o�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ��������v�Əq�ׂĂ���T�U�N���o���A�Ԑ�
���Ƃ̗��_�I�����͖����m������Ă���Ƃ͂�����B
�Ƃ̏��ւɂ��ꂾ���̍��z�ȃ��m�O���t����������ˁB
���炵���ˁB�_���������ɂQ�����˂�ŃI�i�j�[����J�l��
�����͖O���ĕʂ̘b�肩�悗�@�Ђǂ��z���Ȃ�
�������i���o�[�����I��
���̂Ƃ���A���ӔC�����ǐ��ًK�͂Ȃǁ[�ł��悭�Ȃ����B
�K�͘_����т͐H���Ȃ����˂�
�Ƃ������ƂŊԐڐ��Ƙ_�̘A�������܂��B
���R���m�́A�u����_�v��u�s�x�z���v�Ȃǂ́A�u���s�s�ׂ́w��^���x
���܂߂ċK�͓I�Ȓ��x�T�O�Ƃ��Ă̕s���m�����܂ʂ��ꂪ�����Ƃ�����萫��
�������Ă���v�Ǝw�E���ꂽ�B
�u���s�s�ׂ́w��^���x���s���m�ł���v�Ƃ����w�E�́A�Ԑڐ��Ɛ������
���Ē�^���̘_�҂���咣����Ă��邱�Ƃ��l����Ǝ����I�ł���B
�u�w�K�͓I�x�Ȓ��x�T�O�v�Ƃ����\���ɂ͂����炭�ے�I�ȃj���A���X������
���Ă���̂ł��낤�B��˔��m�u�����́A�c�Ԑڐ��Ƃ̎��̂���b��
���A���s�s�T�O�́w�K�͓I�x�c����簐i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�i��ˁE
�Ԑڐ��Ɓj�Ƃ����p����ᔻ���Ă�����̂Ǝv����B�������A�Ԑڐ��Ƃ�
�K�͓I���i�̋����͑�˔��m�Ɍ���Ȃ��B�ނ���u���l�I�E�K�͓I�ȍl���v��
�\�Ƃ��邱�Ƃ��Ԑڐ��Ɛ��́u�����v�Ƃ���Ă���̂ł���i��c�E�ƍߘ_�j
�����ŁA�u�Ԑڐ��Ɛ����K�͓I�E���l�I�A�����Ɛ��������I�E���ؓI�v�Ƃ���
��������邱�Ƃ��������ł��낤�B
����Ⴛ������B���O�͍���������ˁ[���Ȃ�
�S�R�Ⴄ
�������s�s�T�O�́w�K�͓I�x
������O���낗
�����A���c�Ƃ�
���O�܂������̂��悗��
���R����O��ɁA�����̌̈ӂ��ϔO����ƁA���ʔ����̑���ł������Ă�
�댯�����̔F�����c���Ă���ȏ�A�����̌̈ӂ����邩��A
�F������ߎ��ł͂Ȃ��A�̈ӂ̖����Ƃ��������Ă��܂����Ƃ�
�ے�ł��Ȃ��B��͂�A�����̌̈ӂ��ϔO���邱�Ƃ�
�]���̗��_�̌n�Ɛ������Ȃ��B
�i�P�j�u���ƂȂ����Ɓv�ᔻ
�������ɁA�u�����Ɓ[�Ɓv�Ƃ����\�����Ƃ鋳���Ɛ��́A���Ƃ̂Ȃ�
�Ƃ���ɋ��Ƃ̐�����F�߂邱�ƂɂȂ�B
���씎�m�́u�T�O��A���Ƃ�\�肵�Ȃ�ky�����E�Ƃ������̂́A���s�@��
�\�肵�Ȃ��Ƃ��낾�Ǝv����v�Ƃ����B�O�c�������u�����̒ʏ�̉���
����́A���ƍs�ׂ���Ȃ�������F�߂邱�Ƃ͍���ł���v�Ƃ����B���ɂ��A
�����̘_�҂����R��s���Ȃ��܂܁u���ƂȂ����Ɓv��ᔻ���钆�ŁA�x��������
�u�w���Ƃ̂Ȃ����Ɓx��F�߂邱�Ƃ͑Ó��łȂ��B�험�p�҂̍s�ׂ��\���v��
�ɊY�����Ȃ��ɂ�������炸�A�w���s�s�ׁx�Ƃ��ė��p�҂ɋ����Ƃ̐�����
�₤���Ƃ͎��s�]�����̊ϓ_����^��ł���v�Əq�ׂ���B
�@���̘_�҂��A�Ƃ��ɗ��R�����Ȃ��܂܁u���ƂȂ����Ɓv��ᔻ�����
�������Ƃ́A�u���s�]�����v�͓��R�̑O��ł���Ƃ������ʂ�������������
����ł��낤�B�u���s�]�����v�ɂ��Ă͌�q����i�S�i�P�j�j
�i�Q�j�u���ƂȂ����Ɓv�̗��_�I�\��
�u���s�]�����v�����Ɛ����̐�ΕK�v�����ł���Ƃ���Ȃ�A�����Ɛ���
�̂�҂́A�u���ƂȂ����Ɓv���F�߂��邱�Ƃ�ϋɓI�ɘ_����`��������B
�������m�́A���łɐ�O���炱�̖����ӎ�����u�g���҂���g���҂𗘗p����
�g���Ƃ�Ƃ��A�܂��͖ړI�E�E�E�����҂����̂���������Ȃ��҂𗘗p����
�ꍇ�Ɂv�u���Ƃ��F�߂��邽�߂ɂ́A���S�҂�����@�v�f�Ƃ��Ă̐g��
�܂��͖ړI�ƒ��ڍs�҂̍s����@�s�ׂƂ���̌Y�@��̉��I��@�ތ^��
�܂ō������ꂳ��v�Ă���悢�Ƃ���Ă����i�����E���Ɨ��_�̌����j
�@���݂̊w���́A�s����������b������́i�@�A�A�j�A�U�T���P���̉���
���瓱�����́i�B�j�A���s�]���������������������́i�C�A�D�A�E�j�ɕ������B
�A�쑺�����̏����i�����Ƃ̌����A���j
�B�R�������̏���
�U�T���P���́u�Ɛl�̐g���ɂ���č\�����ׂ��ƍߍs�ׂɉ��������Ƃ��́A
���r�̂Ȃ��҂ł����Ă��A���ƂƂ���v�ƋK�肷��B����́A�^���g����
����w�ƍߍs�ׁx�Ɋ֗^�����҂͋��Ƃł���Ƃ����|�ł���B�u�ƍߍs�ׁv
�Ƃ́A���Ƃ݂̂łȂ����Ƃ����܂ށB�Y�@�́A�u���Ɓv�Ȃ����u���s�s�ׁv
��\���Ƃ��́A���̂悤�ȕ�����p����i�U�O���`�U�Q���Q�Ɓj�B�ɂ�������炸�A
�U�T���P�����u�ƍߍs�ׁv�Ƃ���������p���Ă���̂́A���Ƃ݂̂Ȃ炸�A
���Ƃ����܂܂����|������ł���B
���̂悤�ɂ��āA�^���g���Ƃɂ����Ĕ�g���҂𗘗p�����g���҂́A��g����
���u�v�Ƃ����u�ƍߍs�ׁv���s�����̂ŁA����ɏ]�����āw�����Ɓx��
��������B��g����Q�̕��́A���p�҂���g���҂̋����ɏ]�����ěƂ�
��������̂ł���B
�C�����m�́w�Ԑڐ��Ɓx�ɂ����鏊���i���j
�[������@�I�E���ݘ_�I���s�s��
�D���R���m�̏���
�������d��Ƃ���A�g����ړI�������s�ׂ��u�����I�Ȑ��Ɓv�i����
�ɂ͏]�Ƃ܂��͕s���j�Ƃ��āA����ւ̋������݂Ƃ߂邱�ƂɂȂ�ł��낤���A
���̕����`���I�ȊԐڐ��Ɛ������Â�������A�������ɑ�������������
�ł͂Ȃ����Ǝv����B
�E���c���m�̏���
�Ԑڐ��Ƃ�F�߂�ׂ��ꍇ�����肦�悤���A�ʏ�͋����Ƃɂ����Ȃ��ƍl����
�ׂ��ł͂���܂����B��g���҂́A�u�g���v�������Ƃ������Ƃ���A�@����
�u���Ɓv���肦�Ȃ��Ƃ��������ł����āA������u���ƂƂ��Ă̎��i���Ƃ��A
�������̍ȂƂ��Ă̌�������̌��j�j�������Ă���Ƃ����Ă��������Ȃ�
�ł��낤����A�u������̐��Ɓv�i�@����̛Ɓj�Ƌ����Ƃ̊W��F�߂�
���Ƃ́A�K�������A���s�@�ɔ�������̂ł͂Ȃ��Ǝv����B
�i���R�j�A�u������̐��Ɓv�i���c�j��K�v�Ƃ������ɂ����āA�����u���s
�]�����v�̎������瓦��Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
�����́A��ΓI�Ȍ����Ƃ����u���s�]�����v�Ȃ���̂���x�^���Ă݂�
�K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B
�S�@��̍l�@
�i�P�j�u���s�]�����v
�u���s�]�����v�Ƃ́A�u�w���Ɓx�������Ɏ��s�s�ׂ��������Ƃ��A���Ƃ̐���
�v���ɂȂ邩�A�Ƃ������ł���v�i����j�Ƃ���邪�A�����ŃA�v���I����
�u���Ɓv���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃɋ^�����������Ȃ��B
�悭�߂Ă݂�ƁA�U�P���P���́u�w�l�x���������Ĕƍ߂����s�������ҁv
�ł���A�u�w���Ɓx���������Ĕƍ߂����s�������ҁv�ł͂Ȃ��B�U�Q���P����
�u�w���Ɓx������ҁv�ł���A���@�҂́A���炩�Ɂu�l�v�Ɓu���Ɓv��
�Ӗ��̈Ⴂ���������Ă���ƍl������B�u�l�v�Ƃ͕K�������u���Ɓv�ł���
�K�v�͂Ȃ��B�i������́j�u�Ɓv�ł��悢���A���邢�͉��炩�̗��R��
�s���̎҂ł��悢�ꍇ������ł��낤�B
�u���ƂȂ����Ɓv�͔F�߂���B�ہA���̍\�������A�����Ɂu�K�͓I�v�ɊԐ�
���Ƃ�F�߂�������Ԃɑ����Ă���B
�i�Q�j�̈ӂ��铹��̍\��
�ȏ�̌�������A�̈ӂ��铹��𗘗p�����ꍇ�A���p�҂͋����Ƃł���A
�험�p�҂͕s���ƂȂ�B���̏ꍇ�A�험�p�҂�ƂƂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�ƂƂ́u�w���Ɓx������ҁv�ł��邩��ł���B
�����̂悤�ȍl�����ɂ͔ᔻ������B�u�ʐ��̔��Ύ҂����́A���s�s�T�O��
�������肷��㏞�Ƃ��āA�܂�����������ȁw�g���I���Ƙ_�x�Ɏ��炴���
���Ȃ��B�ނ�́A�ʐ��͊Ԑڐ��Ƃ��L���F�߂邱�Ƃɂ���Ď��s�s�T�O��
�o�ɂ����A�Ђ��Ă͍ߌY�@���`�̌�����h�邪�����̂ł���Ɣᔻ���Ȃ���A
���ʂɂ����āA�Y�@�U�P���P���̉��߂̌��E���Ė�����Ȍ`�ŋ����Ƃ�
������F�߂���Ȃ��̂ł���v�i��c�E�ƍߘ_�j�A�ƁB
����ɑ��Ắu�Ԑڐ��ƂƋ����ƂƂ̌��E�̔������ƌ����̕s��v���l��
����A�Ԑڐ��Ƃ̖��ɂ��K�͓I�ϓ_�̊g��X�����x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v
�i���R�E�����B�W�I���j�Ƃ������_���\�ł���B
�y�ȏ�z
���O�͂�����������A�X�g�[�J�[�N�͑��ɋA����R
>>402-406
�S�������Ⴂ�B�̈ӂɃA�z���Ă�̂��m���
�X���������ȁB�ŋ��D�_
����A���ʂɐ������͕ێ��ł���B���������ċM�l���]���̗��_�̌n�Ƃ��Ă���̂����킩���
������ΓI�Ȍ����Ƃ����u���s�]�����v�Ȃ���̂���x�^���Ă݂� �K�v������̂ł͂Ȃ����낤���B
�K�v�Ȃ��B�K�v����Ǝv���Ȃ�A�����_���o���Ă݂�B���O�̐�啪�삶��Ȃ����ǂȂ�
�Ȃɂ������Ȃ̂����S���s����
>>406
���s�s�T�O�̖��Ƃ͕ʖ�肾���Ȃ���
�����Ƃ��Ď��s�s�וK�v�Ȃ����낗
�ŋ������ĂȂ��̂͂��O���掩�c��
>>408
���s���B�ԈႢ���炯�B
>>409
���O���������Ă�̂��S���s���B���������B
�o�J�͂����������ނȂ悗
���_�ł��Ȃ����Ď����������B
��x�Ə������ނȁB
�ǂ���������Ă�H�����ƃ}�j���A���ǂ�ł�̂��H��
�����������甽�_���Ă݂���H����
�Ă��A�}�j���A�����ĂȂ悗��
�}�j���A�����Ȃ��瓊�e���Ă�̂���
��������˂���
�����Ă�̂͂��O�����s���Ȃ悗���ꂭ�炢�킩��悗��
�����ɐK�����o������ۂ킩�肾�Ȃ�
���_���Ă����̂́A�咣�ƍ������Ȃ��҂����ł��Ȃ���łˁB
�c�t�������蒼����BIP�{���N��
������F�߂�������
��x�Ɨ���Ȃ悗��
�A�z�H����ɁA���������̖�肶��Ȃ��B�^�����ǂ�������肾�B
�����炨�O���Ԉ�������Ƃ������Ă�̂����炩�ɂȂ������낗����
�ӂ��B�Ȃ��A�ӂ�B
�ԈႢ�H���͐^��������邱�Ƃ͂Ȃ��B
���̌�����͉R�͂łȂ����ƂɂȂ��Ă����B�c�O���ˁB
���ɏ����o���ė��蒼���I
�������炳�B
�u���c�Ƃ̂����ɐ��ӋC�Ȃ��ƌ����Ă����܂���ł����v���Ďӂ��B
�������狖���Ă�邩�炗
�ߎ��ɂ����ċ��Ƃ��ϔO�ł��邩�i�ߎ����Ə����K�肪�Ȃ��̂ŕs���ł��邱�Ƃ͑����͂Ȃ����j�H
�܂����̗��R�́H
>�ߎ��ɂ����ċ��Ƃ��ϔO�ł��邩?
�Ƃ����^��́A�ߎ����ƂƂ��ď����\���A���邢�͋t�ɕs�����Ƃ������
�ӎ��Ɋ�Â����̂ł��낤�B
�ߎ��̋������Ƃ͂��܂�ɂ��L���Ș_�_�Ȃ̂Ŋ������āA�����ł́A�ߎ��̋���
����щߎ��̛ɂ��Ă̂ݏq�ׂ�B
�y�ߎ��ɂ�鋳���Ɓz
�@�������Ђ̒�X�́A����Y�̑O�ŕs���ӂɂ����GA���u�����z�v�Ɣl�����A���V
�@����Y��A���E�Q�����B
���̐ݗ�ŁA��Ƃ��čs�������̗��ꂩ��AA�������ƂƂ���l����������
�i�q��E���{�Y�@�k��l�S�T�W�ŁA�{�{�E�w���S�O�X�ŁA�ؑ��S�P�Q�ŁA����
�R�T�S�ŁA�A�c�P�V�R�Łj
�������A���s�@��A�u�����v�Ƃ�����́A���ꎩ�̌̈ӂɂȂ��ꂽ�ꍇ�Ɍ���
���Ǝv����B�܂��A�R�W���P���̎�|�ɏƂ炵�Ă��A���ʂ̋K��Ȃ���
�ߎ��s�ׂ��܂߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
����Ƃ͋t�ɁA�ߎ��Ƃɂ́A���ƂƂ����Ƃ������Ƃ͂��肦���AX�́u���Ɓv
�ł���A�Ƃ����l���������_�I�ɂ͂���B���ʂɑ��Ĉ��ʊW������A�\��
�\�ł���A���ׂĉߎ��Ƃ̐��ƂƂ��ď�������A�Ƃ����̂ł���B�ߎ���
���ẮA�u���k�I���ƊT�O�v�ł͂Ȃ��A�u�g���I���ƊT�O�v���Ƃ���A��
�������ƂɂȂ�B
�������A�̈ӔƂƉߎ��ƂƂŐ��ƊT�O���قȂ��ė������闝�R�͖R�����A�ߎ���
�ɂ��A��͂���k�I���ƊT�O���Ó�����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ȏ�ɂ��AX�́A�����Ƃł����Ƃł��Ȃ��A�s���ł���B
�i���Q�S�P�A�c���S�O�R�A���q�S�S�U�A���c�Q�W�T�A��˂R�P�R�A��J�S�R�T�A
����R�X�R�A�R���W�X�R�j
�y�ߎ��ɂ��Ɓz
�A�x�@��X���s���ӂŌ�Ԃ̊��̏�Ɍ��e����u���Ă����Ƃ���A���������
�@�ʍs�lY�����e��ގ悵�A���˂Ă��獦�݂�����Ă���A���E�Q�����B
�ߎ��ɂ�鋳���ƂƓ��l�̗��R�ɂ��A�܂��A�����ߎ��ɂ��Ƃ�F�߂�
�ƁA�����͈͂��ς���g���邱�Ƃ���A�s�������Ó��ł���B
�T���N�X�B
����ς茋�ʖ����l���炷��A�̈ӂƉߎ��̋q�ϓI�v���͓���������A
�ߎ��ɂ����Ă����k�I���ƊT�O���Ó�����Ƃ����̂��ʐ��Ȃ낤�ˁB
�L�`�K�C�Y�@�w�җl�͂�������
����܂�A�����ɍׂ������Ă����ƁA�{�l���炫����ƔF���ł�
�Ă��Ȃ��悤�ȂƂ���܂ł��������Ȃ��ł����H
��������ƁA���������ő��A��؋����珟��ɍs�҂̓��S��
�s�����Ă邾���Ȃ�Ȃ��́H�Ƃ��v�����Ⴄ��ł����B
���{�̌Y�@�w�̗��j�i�Ƃ�킯���ʖ����l�_�j�́A
�ƍ߂���ϓI�v���ł͂Ȃ��A�ł��邾���q�ϓI�v���ŔF�肵�悤�Ƃ��Ă����Ƃ�����B
���̔w�i�ɂ́A���Ȃ��������悤�ɁA��ϓI�v�����d����������ƁA���ӓI�ȔF�肪
����邨���ꂪ����̂ł��傤�B
�̈ӔƂȂ̂�����A���Ȃ̍s�ׂ̊댯���������������Ƃ�����Ό����ƍߐ����B
���Ƃ́A�ӔC�̏��ŁA���҉\���̗L�����`�F�b�N���邭�炢���ȁB
���O�ɐl��Ȃ���
����������排����������݂͎��߂Ȃ���
��l���Ȃ�
�̈ӔƂɂ����鋤�d�������Ƃ͂ǂ��ʒu�Â�����낤���H
������̂Ŏg��Ȃ����Ƃɂ����i�S�I�͎g�p������肾�j
�����u�O������v�̊w���ɁA�����Ȃ�u�\���v���Ƃ͉����v��_���Ă���������
���ꂻ���ɂȂ����i����́A����E����ł������ł��낤�j�܂��A����������
���M���Ȃ��̂ŁA�w��������݈Ղ��Ǝv���鐳���h�q����n�߂邱�Ƃɂ����B
�����h�q�A�ً}���A��Q�҂̓��ӁA���ʊW�i�q�ϓI�A���j�A�s��ׁA�̈ӁA
�����̍���A�ߎ��A��@���̈ӎ��A�����ɂ����Ď��R�ȍs�ׁA�����ƁA���ƁA
�s�ז����l�ƌ��ʖ����l�A�����čŌ�ɍ\���v���̏��Ői�߂悤�Ǝv���Ă���B
�ق��ɉ��������A�C�f�A���������狳���Ăق����B
>>443
����ߎ��_���ĉ����H�@�s���ɂ��Ēm��Ȃ��B
�_�����������Ăق����B
�s�������邼��
�u�Y���ߎ��ƐM���̌����̌n���I�l�@�Ƃ��̌���I�Ӌ`�v
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/04/papers/v04part11(higuchi).pdf
���ߌY�@�ł��Љ��Ă�悤�Ȓ��L���_������m��Ȃ����F�e���̕��s�����Ƃ��߂Ă��B
�����猾���Ă������B�O�Ȃ�āA�����ٖ@�w�Ƃ�������p���܂����Ă�����
�V�����͓̂ǂ߂邯�ǁA�Â��͖̂������낤�Ȃ��B�������Ă��o�Ă��Ȃ����B
�T���N�X�B����_���ǂB
�Ȃ�قǔ������Ȃ�
���a�R�O�N��̐V���ߎ��Ƙ_�������āA��R�@����ɖ߂�A�Ƃ����̂�
�ǂ��ɂ����Ă����Ȃ��B
>>456
�N�A�����]���Ă�B�����͖@�w�����B
�@�w�̃g�b�v�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�u�����͖@�w�A���̑���w�@�w���Ō�������Ă���w�╪��̘b��ɂ���
�w�p�I�ɋc�_����ł��v
���@���m�肽����Ύi�@�ɍs���B
���̖@�w�Ȃ�X���^�C���h�Y�@�̕��h�ɂ���悩�����ȁB
�����̈ӌ��Ȃ���A�����Ɠ������t��A�Ă��Ȃ��Ă�낵���B�L�`�K�C�N�B
�����̋�̓I���R���A�ߋ��̔���ɖ߂�Ƃ������Ƃ��H�L�`�K�C�N�B�N�̗����͂��̒��x�Ȃ̂��H��
���������͖@�w�A���̑���w�@�w���Ō�������Ă���w�╪��̘b��ɂ���
�@�@�w�p�I�ɋc�_
�Ȃ��ĂȂ��B���ۓI�ȓI�O��̔�排������P�l���Q�l�̌Y�@�w�҂�
���쎩�����đ����Ă��邾���̃X���B�ɂ��Ȃ���
�ߎ����̈ӂƂ̃A�i���W�[�ōl���Ȃ��ƌ������Ƃ́A�̈ӂƉߎ��̋q�ϓI�v���͓������Ƃ���
���ʖ����l�_�̎咣�͕��ꋎ���Ă��܂��B
�ߎ��Ƃ̔ƍߌ���@�����̈ӔƂɂ��Ó�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ߔN�̗L�͂Ȍ����͂���
�O����������ƂɂȂ�B
����ɁA�ߎ��Ƃɂ����ė\���\����v�����Ȃ��Ȃ�A����͌��ʐӔC�ȊO�̉����ł��Ȃ���
�����ᔻ���\�ɂȂ�B
�ڐV�����咣�ɔ�т��̂͊ȒP�����ǁA����ɂ��㏞�͂ƂĂ��傫���B
�召���傫���̂͂��O�݂����Ȃ̂��Y�@���������Ă��邱�Ƃ��悗
�������ʖ����l�_�̎咣�͕��ꋎ���Ă��܂��B
���₻���ł��Ȃ��B��ʓI�Ɍ������Ă��邩�炻���l���邾��
�����ߎ��Ƃ̔ƍߌ���@�����̈ӔƂɂ��Ó�����̂ł͂Ȃ����Ƃ����ߔN�̗L�͂Ȍ����͂���
�����O����������ƂɂȂ�B
����������Ƃ͌���Ȃ��B
���� ���Ƃɂ����ė\���\����v�����Ȃ��Ȃ�A����͌��ʐӔC�ȊO�̉����ł��Ȃ���
���������ᔻ���\�ɂȂ�B
�悭�킩��Ȃ����ǁA�ϑz�Ō���Ă���́H
�����ڐV�����咣�ɔ�т��̂͊ȒP�����ǁA����ɂ��㏞�͂ƂĂ��傫���B
�ڐV�����H�ǂ����H
�u�A�i���W�[�ȂǂƂ����Ɠ��ʂ̈Ӗ�������悤�ł��邪�A�̈ӂ������Ă����x�̂���ތ^����
�̈ӂ������O�������ʌo�߂����x�Ƃ��ĉߎ����l���邱�Ƃ����ނƂ������ƂŁA�\���s�\��
���ʂ̎�N�ӔC��Njy����̂͌��ʐ��l�����ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��B�v
�ēc�זM�w�Ǘ��ēߎ������x�i�������j230�ŁB
���Ȃ݂ɂ�����͊w�҂ł����ł��Ȃ���B�����̌Y�@�D���B
�茳�ɂ��̖{�����鎞�_�ł��̌�����͖����B
>>467
�����ƈ��p����B
�����A>>450�̔���_���𗎂Ƃ��Ă����Ɠǂ�ł݂��B
�M���̌����̗A���o�H�ɂ���
�e���[�s�@�s�ׁi�����j����
�����Y���ɒʂ�����R�@�������Y�������ɉ��p�ƌ�����
�Ȃ��A���{�̖��������ł̐M���̌����̒莮�������͂���Ă��Ȃ��̂��낤�B
�吳 3�E3�E11����ł̘g�g�݂ɂ���
���Ӕ\�͂ɂ��čs�Ҋ�����Ƃ�Ȃ��Ȃ�A
��̓I��́A�E�����`���邩�������`���邩�̈Ⴂ�ɂȂ邾�낤�A
�t�Ɍ����ΐӔC��`���ǂ��l���邩�̖��ɋA�����B
�P�@�͂��߂�
����̍����͐����h�q���e�[�}�ł��B
�u�����h�q�v�Ƃ������t�́A�悭�Y���h���}�Ȃǂł����グ���A����p��
�Ƃ��Ă����y���Ă���A�F������C���[�W���₷���Ǝv���܂��B�������p����
������c�ꋞ���搶�́w�V�������ꎫ�T�x�ł́u�}�ɕs���Ȗ\�s��������ꂽ
���Ɏ����i���l�j�̐����⌠������낽�߂ɁA��ނ���������ɊQ��������
�s�ׁB�@����̐ӔC�͖���Ȃ��v�Ɛ�������Ă��܂��B
�Z�@���J���ĉ������B�ł́A��ԑO�̋M���A�R�U���P����ǂ�ʼn������B�ł́A
��Ԍ��̋M���A�R�V���P����ǂ�ʼn������B���ɂ��ׂ̗̋M���A�R�T����
�ǂ�ʼn������B�L��������܂����B
���āA�����C���t���܂��H�R�T�����R�U�����R�V�����u���X�̍s�ׂ͔����Ȃ��v
�Ə�����Ă���܂��ˁB����ɊQ�������Ă��A�Ƃ��ɂ͎E�������ꍇ�ł������A
���̗v�����[�����Δ������Ȃ��̂ł��B�R�T���́u�����s�ׁv�A�R�V����
�u�ً}���v�̋K��ł��B�����h�q�ƕ����āu��@���j�p���R�v�Ƃ����܂��B
�u�j�p�v�Ƃ�����͋��c��搶�̎��T�ɂ͍ڂ��Ă܂��A�{���Ȃ�Έ�@
�Ȃ̂����A���̗v�����[�����Ώ��߂����@�������������Ƃ����Ӗ��ł��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�_�������Ȃ��ŁA�܂��Q�����˂邵�Ă�̂���B�Y�@�w����X��
��ʂɁu�ƍ߂Ƃ́A�\���v���ɊY�������@���L�ӂȍs�ׂł���v�ƒ�`
����܂��B
�O�c�����́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�O�c�Q�X�Łj
�@�u�������ǂ̂悤�ȍs�ׂ�ƍ߂ƍl���邩�v�Ƃ������_��������I�ɍl�@
�@�@����ƁA�ƍ߂͊�{�I�Ɉȉ��̂Q�̗v�������s�ׂłȂ���Ȃ�Ȃ�
�@�@�Ƃ����悤�B
�@�@�@�q�ϓI�ɏ����ɒl���邾���̈����s�ׂł��邱��
�@�@�A�s�҂ɁA���̍s�ׂɂ����\�ł��邱��
�@���u��@���v�ł���A�A���u�ӔC�v�ł��B�ӔC�Ƃ́A���̒i�K�ł́A�̈ӁE
�ߎ������邱�ƂƗ������Ă����ĉ������B
�ł́u�\���v���v�Ƃ͉��ł��傤���B�[�I�ɂ����ΎE�l�߁i�P�X�X���j�̍\��
�v���́u�l���E�����ҁv�ł��B�O�c�����́u�����ɒl����悤�Ȉ�@�ȍs�ׂ�
�ӔC��������ꂽ�s�ׂ��A�@���ތ^�I�Ƀ��X�g�A�b�v�����̂��\���v��
�Ȃ̂ł���i��@�E�L�ӗތ^�Ƃ��Ă̍\���v���j�v�i�O�c�Q�X�Łj�Əq�ׂ�
���܂����A����͈�̗���ɂ������A�������X�Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�ŏI���
���߂ďq�ׂ����Ǝv���܂��B
�E�����łɁA�ƍߘ_�̌n�ɂ��ĐG��܂��B���A�q�ώ�`�Y�@�w���m������
�[�i�q�ώ�`�Ƃ́A�O���Ɍ��ꂽ�s�ׂƌ��ʂɊւ����@�����d�����闧��A
��ώ�`�Ƃ́A���S�̎���Ɋւ���ӔC���d�����闧��ł��j�|�c���d�����m
�i���ō��ٔ����j�̋��ȏ��[�w�Y�@�j�v���_�x[��O��]�i�P�X�X�O�N�j�[��
�ڎ����Ă͎��̂Ƃ���ł��B
�@�@��P�́@�@�ƍߘ_�̑̌n
�@�@��Q�́@�@�\���v��
�@�@��R�́@�@��@��
�@�@��S�́@�@�ӔC
�@�@��T�́@�@������
�@�@��U�́@�@����
�@�@��V�́@�@�ƍ߂̐����A������ы���
���݂̑��̑����̋��ȏ����A�ו��̈Ⴂ�͂�����̂̂��̏��q�����ɏ]���Ă��܂��B
�ł́A�������́A�\���v�������Ĉ�@������_���邩�Ƃ����ƁA��ɏq�ׂ�
�Ƃ���A�\���v���̗����͏������X�Ƃ��Ă���A�ŏ��̍u�`�ŊF���Y�@��
�T���̂����ꂽ����ł��B
�b�����ɖ߂��܂��傤�B
�����h�q�́A���l���E�����Ă���ɂ�������炸�A�Ȃ������������̂ł��傤���B
�������̉����蓾�܂��B
�i�P�j�@�v�����@��
���씎�m�́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i����Q�Q�W�Łj
�@�@�l�����炻�̌����̐N�Q�ɑ��ē����̂́A�����ł��邾���łȂ��`��
�@�@�ł�������A�Ƃ����̂��A�l��`�̊�{�v�z�ł���B���̌��ʁA�s����
�@�@�N�Q�҂̖@�v�́A�����Ȕ�N�Q�҂̖h�q�ɕK�v�Ȍ��x�ł́A���̖@�v����
�@�@�ے肳���B
�@�v�����ے肳���A�u�܂�A�U���ҁi��Q�ҁj�̖@�v���u�O�v�Ȃ̂�����
�h�q�҂̗��v���A��ɗD�z���邱�ƂɂȂ�킯�ł���v�i�O�c�R�T�V�Łj
��c�������A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i��c�Q�V�Q�Łj
�@�@�U���҂Ɂu�A�Ӑ��v���F�߂��邪�䂦�ɁA�U���ґ��̖@�v�i�ȉ��A����
�@�@���N�Q�@�v�Ƃ����j�̗v�ی쐫�����シ��A�܂��͔ے肳���Ƃ����
�@�@���߂邱�Ƃ��\�ł���B
�����ɑ��A�R�������́u���̌����́A�U���҂��w�s���x�A�h�q�҂��w���x
�Ƃ��������ŁA���͕s���ɗD�z����Ƃ��Ă���ɓ������A�s���O��̂������
�܂ʂ���Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă��܂��i�R���S�T�O�Łj
�@�v���Փ˂���ꍇ�ɉ��l�̏������@�v���]���ɂ��ĉ��l�̑傫���@�v���~��
�������u�D�z�I���v���v�Ƃ����܂��i�]���X�W�Łj
���c�����́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i���c�P�Q�T�Łj
�@�@�\���v���ɊY������Ƃ��A�����ł͖@�v���N�Q����Ă���Ƃ����Љ�I��
�@�@�L�Q�Ȍ��ʂ��������Ă���i�N�Q�@�vA�j�B�������A�����s�ׂ��A������
�@�@�ʂ̖@�v��ۑS����Ƃ����Љ�I�L�p����L����ꍇ������i�ۑS�@�vB)
�@�@�����A�N�Q�@�v�����ۑS�@�v�̕����D�z���Ă���ꍇ�ɂ́AB�|A���O
�@�@�ƂȂ邩��A�Љ�I������`�̌��n������A���̍s�ׂ͑S�̂Ƃ��Ă�
�@�@����������邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�����o������w�҂������������̂�������������܂��d���Ȃ�������
�c�����m�́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�c���Q�R�Q�Łj
�@�@�@�����̐N�Q�̗\�h�܂��͉����Ƌ@�ւ��s�����Ƃ܂̂Ȃ������ɁA
�@�@��[�I�Ɏ��l�ɂ�����s�����Ƃ��������̂ł���B
�]�k�ł����A�c�����m�̉����g���ɂ͓���������܂��B�u�ꍇ�v�́u�����v�A
�u�F�߂�v�́u�݂Ƃ߂�v�A�u����v�́u������v�B���������āu�F�߂邱��
���ł��Ȃ��ꍇ�Ɍ���v�́u�݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������ɂ�����v�ƂȂ�܂��B
�Ђ炪�Ȃ��P�O���ȏ㑱���ƃW���}�V�����o��̎��̎��ɂƂ��ẮA�c�����m
�̒����ǂނ͓̂�V�Ȃ��Ƃł��i�j
�܂��A���R���m���A���̂Ƃ���q�ׂĂ��܂��i���R�R�U�X�Łj
�@�@�����h�q���E�E�E�A���ȕۑS�̌����Ƃ��āA�@�v�N�Q�𐳓�������Ƃ���
�@�@���i�������Ƃ͖��炩�ł���A�E�E�E
�i�S�j�Љ�I��������
��J�����́A���̂Ƃ���q�ׂĂ��܂��i��J�Q�S�Q�Łj
�@�@�@�v�N�Q�s�ׂ��Љ�I�������͈͓̔��ɂ��邱�ƁA���Ȃ킿�A�s�ׂ��Љ��
�@�@�̂Ȃ��ŗ��j�I�ɐ��������Љ�ϗ������̘g���ɂ���Ƃ������Ƃ������Ƃ���B
�ȏ�A�i�P�j�@�v�����@���A�i�Q�j�D�z�I���v���A�i�R�j�@�m�̗��v���A
�i�S�j�Љ�I���������̏��ŏq�ׂ��킯�ł����A�����ăA�g�����_���ɏq�ׂ�
�킯�ł͂���܂���B��̓I�Ȃ��̂��璊�ۓI�Ȃ��̂ցA�����I�Ȃ��̂���K�͓I
�Ȃ��̂ւƏq�ׂ�����ł��B����́A�u���ʖ����l�_�v�Ɓu�s�ז����l�_�v��
�Η��̈��ʂł���킯�ł����A����ɂ��Ă��u�`�̍Ō�̕��ŐG��܂��B
�����h�q�́u�s���ΐ��v�A�ً}���́u���ΐ��v�̊W�ɂ���Ƃ����܂����A
����́A�����������Ƃł��B
�����h�q���ً}�����A�ً}���ŁA���ȁi�܂��͑��l�j�̌�����ۑS���邽�߂ɁA
���l�̖@�v���]���ɂ���s�ׂł��B�ً}���ł́A���I�ȋ~����҂u���Ƃ܁v��
�Ȃ����߁A���l�ɂ�鎩�͋~�ς����͈̔͂ŋ��e����Ă���̂ł��B
�Ƃ���ŁA�ً}���́A�B�����ȑ�O�҂̗��v���]���ɂ���Ƃ��납��A�@��[��
�i���s�ȊO�ɕ��@���Ȃ����Ɓj�ƁA�A�@�v�ύt���i�u����ɂ���Đ������Q��
�����悤�Ƃ����Q�̒��x���z���Ȃ������ꍇ�Ɍ���v�j���v������܂��B
����ɑ��āA�����h�q�́A�s���ȐN�Q�҂��琳���Ȗh�q�҂̗��v��h�~�������
�ł���̂ŁA�N�Q����ޔ����邱�Ƃ��ł���ꍇ�ł����Ă��A�܂��A�h�q�������v
�����闘�v���]���ɂ���ꍇ�ł����Ă����e����܂��B
���̈Ӗ��ł́u��ނ��ɂ����s�ׁv�́A�R�U���ƂR�V���Ƃł́A�قȂ�������
�����邱�ƂɂȂ�܂��B
���ꂪ�]���̋c�_�̘g�g�݂ł��B�Ƃ��낪�ŋ߁u�����h�q�̏ꍇ�ł����Ă��A����
�͈͂ŁA�ޔ��`����F�߂�ׂ��ł͂Ȃ����v�Ƃ����c�_���s���Ă��܂��B
����ɂ��ẮA��ɐG��܂��B
�i�P�j�}�����Ƃ�
�R�U���́u�}���v�Ƃ́u�@�v�N�Q�̊댯���ڑO�ɍ��������Ă��邱�Ɓv�������܂��B
�R�V���́u���݁v�����`�Ɖ�����̂��ʐ��ł����A���ݐ��̕����L���T�O�ł��B
�@�y����P�z
�@�@�����c������R�����ŋ�s���������d���Ă���̂����R�����̎�l���A
�@�@�����h�~���鑼�̕��@���Ȃ������̂ŁA����������܂��Ă����h�����B
�����ł́u�}�����v�͂Ȃ��̂Ő����h�q�Ƃ͂Ȃ�܂��A�u���ݐ��v�͍m��
�����̂ŋً}���Ƃ͂Ȃ蓾�܂��i�A���A�������ł��j
�}�����Ɗ֘A���āA�h�q�ґ��ɇ@�N�Q�̗\�����������ꍇ�ƇA�ϋɓI���Q�ӎv
���������ꍇ���A����Ŗ��Ƃ���Ă��܂��B
�i�Q�j�N�Q�̗\���Ƌ}����
���Ĕ���́A������̐N�Q�ɂ��\���̗\���������A�\���̗p�ӂ𐮂��đ����
�ɕ������ꍇ�A���̐N�Q�͋}���̂��̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��Ă��܂����i���a�Q�S�N
�P�P���P�V���A���a�R�O�N�P�O���Q�T���j
�����ł͔�����A�N�Q���\�������ꍇ�ɂ��A�����ɋ}�������ے肳�����̂ł�
�Ȃ����Ƃ�F�߂Ă��܂��i���a�S�U�N�P�P���P�U���j�B�}�����̗v���́A�q�ϓI��
�c�������ׂ��ł���܂����A�\�������Ƃ��͑ޔ��`�����ۂ����ƂɂȂ肩�˂Ȃ�����ł��B
�ߌY�@���`��ސ����߂̋֎~�������Ȃ��Ƃ܂�����ˁH
�_���������ɁA�V��ł��肵�Ă��ˁ[���H�����ɂ͐ŋ���
�����Ă��邱�Ƃ�Y���Ȃ�B���w�҂ǂ��B
A����A�y�Q�R�����z�̌���v�|��ǂ�ʼn������B
�L��������܂����B�S�I�̎g�����ł����A�܂��q���|�r�Ȃ����q����v�|�r
��ǂ�ʼn������B���ꂩ��i�����̊T�v�j��ǂ݁A������x�q���|�r�Ȃ���
�q����v�|�r��ǂ�ʼn������B�q����r�͓ǂ�ł��ǂ܂Ȃ��Ă��\���܂���B
�����ŏd�v�Ȃ̂́u�ϋɓI���Q�ӎv�v������ꍇ�ɂ́u�}�����v�̗v����������
�Ƃ������Ƃł��B�P�Ȃ�\�����z���ĐϋɓI���Q�ӎv����������ꍇ�ɂ́A���
���}�����T�O�Ƃ����q�ϖʂɉe����^���邱�Ƃ�F�߂Ă���̂ł��B
���L�����i�����j�́A�@�N�Q�̗\���Ɋ�Â��N�Q�O�̐S����Ԃ��}�����v���Ƃ��Ă�
�ϋɓI���Q�ӎv�̖��ł���A�A�h�q�s���̐S����Ԃ��u�h�q�̈ӎv�v�̖��ł���A
�Ɛ�������܂����B
����ɑ��āA��J�����͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i��J�Q�V�T�Łj
�@�u�}���v�͋q�ϓI���ԂƂ��Ċ댯�����������Ă��邱�Ƃ��Ӗ����邩��A
�@�@���Q�̈ӎv�̗L���ɂ���Ă��̑��ۂf���ׂ��ł͂Ȃ��A�ϋɓI��
�@�@���Q�ӎv�ŐN�Q�ɗՂƂ��ł��A���̂��Ƃ��璼���ɋ}������
�@�@������Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�@�ނ���A�u�h�q�̈ӎv�����@���Ă���v���̂Ƃ��Đ����h�q�̐�����
�@�@�ے肷��ׂ��ł���B�@�@
������������ǂ������ʒu�Â��ɂ��邩���ˁB
���ϋɓI���Q�ӎv�̖��ł���A�A�h�q�s���̐S����Ԃ��u�h�q�̈ӎv�v�̖��ł���A
���Ɛ�������܂����B
����悭������Ȃ����ǁA�N�Q�O�̐S����Ԃ��h�q�s���̐S����Ԃ��ǂ�����u�h�q�̈ӎv�v�̖��Ƃ��Ĉ�������_���Ȃ́H
����œ��ɕs�s���͂Ȃ��Ǝv������
�ϋɓI���Q�ӎv�����낤�ƂȂ��낤�ƁA�q�ϓI�Ɋ댯�����������Ă���Ƃ�����Ԃɉ���e�����y�ڂ��Ȃ��킯�����A��J�����̌����Ƃ���A
�ϋɓI���Q�ӎv���F�߂���ꍇ�ɂ́A�P�ɖh�q�̈ӎv�����@���Ă���Ƃ��āA�����h�q�̐�����ے肷��̂����ɂ��Ȃ��Ă�Ǝv�����ǁc�c
�����Ƃ������Ƃł��B�P�Ȃ�\�����z���ĐϋɓI���Q�ӎv����������ꍇ�ɂ́A���
�������}�����T�O�Ƃ����q�ϖʂɉe����^���邱�Ƃ�F�߂Ă���̂ł��B
���������A�ǂ��ɂ���Ȃ��Ƃ������Ă���H��
��������A�h�q�ӎv���S�����@���Ă���킯�ł͂���܂��B
��J�̌����͍̂�Ȃ��ȁB����̋�_�ɂ�����B�}�����̌��@�Ŗ��Ȃ��B
���ꂪ����̗��ꂩ�ǂ����͋^�₾�B
�ʂɋ}�������q�ϖʂ������������ċ������Ȃ��Ă��������ȁB
��J���̓z���g�Ӗ��s�����킗�����낢��ȑ�w�̃V���o�X�݂�Ƒ�J�̊�{�����w�肵�Ă����w����
�قƂ�NJF������ˁH���w�肵�Ă���̂͒�q�Ƃ�����q�����肾�Ƃ����킩�邗��
�������Ă��邩�����
�ϋɓI���Q�ӎv�̑��ۂ����ׂċ}�����̖��Ƃ�������ȂC���������B
�܂��ʖ�肾�낤�B
�s�𗝂ňӖ��s���Ȕ�排����܂����̔ᔻ������̂͂�����Ƃ��������ȂƊ�����ȁB
��J�̊�{����w����̌n�̂ق�������ۂǂ�����������Ȃ�
�P�Ȃ铌��R���v�Ȃ������H
���Ɖߋ��̔���ɖ߂�Ƃ��A���ӂ̔ᔻ�����킩���B
�Ȃ�ʼnߏ�h�q�ɂȂ�́H
�s���̐N�Q�̑O�ɐϋɓI���Q�ӎv�������Ă����A
�s���̐N�Q�������Č�A�����ɏo�鎞�ɐϋɓI���Q�ӎv�������A
�ɂ���Ĕ������ɗL���Ă����ӎv�͕ς���̂ɁA�Е��͉ߏ�Ȃ����
�h�q�ŕЕ��́A�h�q�ł���Ȃ��Ȃ�Ă��������Ȃ��H
������A�ߏ�h�q���Ƃ͌����ĂȂ��B�ނ���A�ߏ�h�q�̖��ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���
�Ӑ}�ŏ��������Ȃ��������Ƃ��������t�Ō���������H����
���Ⴀ�A�s���̐N�Q��\�����āA���O�ɐϋɓI�ɉ��Q���Ă�낤�Ƃ����ӎv(�ϋɓI���Q�ӎv)
���������ꍇ�́A�}�����̖��ƂȂ��āA�s���̐N�Q�������Ă���A����ɏ悶��
�ϋɓI�ɉ��Q���Ă�낤�Ƃ����ӎu���������ꍇ�́A�h�q�̈ӎv�̖��ɂȂ�́H
���Ⴀ���A�V�������c�l�b�K�[���U�����Ă��邱�Ƃ��\�����ꂽ����A�Z�K�[����
�X�^���[����̋����ȏ����l���ق��Ē��U������C�܂�܂�ő҂��\���Ă����ǁA
���́A�������Ǝv���Ă������l�͌����ڂ����ŁA�~�X�^�[�I�N���ƃG�X�p�[�ɓ��Ȃ݂�
�S�R���ɗ����Ȃ��z�������ꍇ�ɁA����Ⴤ���@�C�Ǝv���Đ��h�q�̂���(�h�q�̈ӎv��)�A
���������ꍇ�ł��A�}�����͔ے肳���́H
�@
�����������ꍇ�́A�}�����̖��ƂȂ��āA�s���̐N�Q�������Ă���A����ɏ悶��
���ϋɓI�ɉ��Q���Ă�낤�Ƃ����ӎu���������ꍇ�́A�h�q�̈ӎv�̖��ɂȂ�́H
����Ȃ��ƒN�������ĂȂ�����
�����Ⴀ���A�V�������c�l�b�K�[���U�����Ă��邱�Ƃ��\�����ꂽ����A�Z�K�[����
���X�^���[����̋����ȏ����l���ق��Ē��U������C�܂�܂�ő҂��\���Ă����ǁA
�����́A�������Ǝv���Ă������l�͌����ڂ����ŁA�~�X�^�[�I�N���ƃG�X�p�[�ɓ��Ȃ݂�
���S�R���ɗ����Ȃ��z�������ꍇ�ɁA����Ⴤ���@�C�Ǝv���Đ��h�q�̂���(�h�q�̈ӎv��)�A
�����������ꍇ�ł��A�}�����͔ے肳���́H
�@
�Y�@�w�҂�����������Ƃ܂Ƃ��ȗႾ���Ă�B
�����ɑ��������̂���Ȃ��ƂˁB���������̋�_����Ŋw�҂��đ��ݖ����l�����Č�����悗
�w�҂ł͂Ȃ����B
�Ă��A�����w�҃X���ł��Ȃ����B
�u����̋�_�v���Ă������A�A�N�V������삩�Ǝv������A
���̓R���f�B���������������Ċ���������
�ŁA���ǁA�ϋɓI���Q�ӎv���Ă�ŁA�����h�q���ے肳��邽�߂ɂ́A
�ǂ̎��_���炠���āA�ǂ̎��_�܂ňێ������K�v������ƍl���Ă�́H
����Ƃ��A�ϋɓI���Q�ӎv���L�邾���ł͐����h�q�͔ے肳��Ȃ��H
�i�P�j�ӔC�Ȃ��N�Q
�u�s���v�Ƃ́u��@�v���Ӗ����܂��B���āA��ϓI��@�_�́A�ӔC���\�͎҂ɂ�
���ߋK�͂������邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A�ӔC���\�͎҂̍s�ׂ͐����h�q�̑ΏۂƂ��Ă�
�u�s���̐N�Q�v�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ��܂����B
���݂ł́A�킪���ł́A�ӔC�������s�ׂ��u�s���̐N�Q�v�Ɋ܂܂�邱�Ƃɂ́u�قځv
�٘_�͂���܂���i�h�C�c�ł́A��⎖��قȂ�܂��j�B�u�قځv�Ƃ����͎̂���
�悤�Ȍ��������邩��ł��B
�@�@�N���҂�_��Q�҂̂悤�ɁA�ӔC���Ȃ������サ���҂ɂ��U���A����ɁA
�@�@��U���҂Ɠ��ʂȊW�ɂ���ҁi���Ƃ��ΐe�����j�ɂ��U���ɑ��Ă��A
�@�@����ɂ�蔽���͐��������ƍl����ׂ��ł���i��c�Q�V�R�Łj
�R�������́A���̂悤�ȁu�ӔC�Ȃ��s���ȐN�Q�v���A�����h�q�A�y���ȐN�Q��
�Ƃ��ɁA�u�h�q�s�ׂ̓��ݓI�����v�Ƒ����A�ޔ��`����F�߂Ă��܂��i�R���S�X�P�Łj
���̓_�ɂ��ẮA�u�h�q�s�ׂ̑������v�̂Ƃ���ōēx�_���܂��B
�B
�s���̐N�Q�����⓮���ɂ��N�Q���܂ނ������ƂȂ�܂��B
�@�y����Q�z
�@�@�P���Ă������l�̎������E������s�ׁi����ɂ͉ߎ����Ȃ����̂Ƃ���j
�@�@�́A�함����߁i�Q�U�P���j�̍\���v���ɊY�����邪�A�����h�q�Ƃ���
�@�@����������邩�B
��ώ�`�̗��ꂩ��́A�s�K�͂͐l�̍s�ׂɂ̂������܂�����A������
�K�͈ᔽ�Ƃ��Ă̕s���i��@�j��Ƃ����Ƃ͂ł��܂���B���������āA�@�m��
���l�ɑ��Ă݈̂Ӗ������̂ŁA�����h�q�͔F�߂�ꂸ�A��[���Ɩ@�v�ύt
���[��������ŋً}���F�߂���ɂ����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�������A�@�l�ɑ��Ă���E�����������������̂ɁA�����ɑ��Ă�
�ً}���̌��x�ł��������ł��Ȃ��͕̂s�����ł��邱�ƁA�A�����̍U����
����̌̈ӁE�ߎ��Ɋ�Â����ۂ��̔��f��h�q�҂ɕ��킹��̂̓A���t�F�A
�ł��邱�ƁA�B��ώ�`���̂��̂����ނ������Ƃ���A�����ł́A�Ε��h�q
�m��������|�I�ɗD���ł��B
�Ȃ��A�c�����m�́A���̂悤�ȗ��R�őΕ��h�q��ے肵�Ă����܂��i�c���Q�R�V�Œ��P�T�j
�@�@�s�ȊO�̎����ɂ��Ă��u��@�ȏ�ԁv�Ƃ����ϔO���݂Ƃ߂�Ƃ���A�����̐N�Q��
�@�u�s���v�Ƃ����v�����[�������ƂɂȂ�B�������A�����ɂ͐N�Q�s�ׂ͂Ȃ��B���������āA
�@�@�����ɑ��Ă͐����h�q�͋����ꂸ�A�ً}�������������Ɖ�����B
���̃X�����r�炷�ȁB������
��@���̖{����m��Ȃ������ɑΕ��h�q���F�߂��邩�ۂ��Ȃ����ł���͂����Ȃ��B
�i�P�j�h�q�̈ӎv�̓��e�E�v��
�R�U���́A���Ȗ��͑��l�̌������u�h�q���邽�߁v�ƋK�肵�Ă��܂��B�����ŁA
�ʐ��E����́A��т��āu�h�q�̈ӎv�v�𐳓��h�q�̗v���Ɖ����Ă��܂����B
�����A�h�q�̈ӎv�́A�@�h�q�̖ړI�i�Ӑ}�j�A�A�h�q�̔F���Ƃ����Q�̈قȂ���
�Ӗ��ŗp�����Ă��܂����B�@�O�҂́A�s�ׂ̓��@�E�ړI�������ς�h�q�̂���
�ł�����������ɂ��A�A��҂́A���̂悤�ȐϋɓI�Ȉӎv�͕s�v�ŁA���Ȃ�
�s�ׂ��h�q�s�ׂɌ������Ă��邱�Ƃ̔F��������Ώ\���ł���Ɖ����܂��B
�Ⴆ�A��˔��m�́A�A�̗��ꂩ��u�}���s���̐N�Q���ӎ����A�����
�����悤�Ƃ���P���ȐS����ԁv�ƒ�`���Ă��܂��i��˂R�X�O�Łj
�Ȃ��Ȃ�A�y�S�I�Q�S�����z�̈��c�y�����|�ȑO�́u�������v�ƌĂ�Ă��܂������A
���ł͑S��w�E�S�w���Łu�y�����v���蒅���Ă��܂��B����͒P�Ȃ閼�̂̕ύX�ł�
����܂���B�u�������v�͕����ǂ���u�����̌�����������v����ł������A
�u�y�����v�͌��O�Ƃ��Ă͋����̌����Ƃ������Ȃ��Ǝ��̌����ɐ�O���邱�Ƃ�
�ł��܂��|�̉���ɂ���Ƃ���A�����h�q���ً}�s�ׂŁA�����⋻���Ƃ���
�S����ԂłȂ���邱�Ƃ͂ނ���ʏ�Ȃ̂�����A�������Ĕ��������ꍇ�ł�
�Ȃ��h�q�̈ӎv�͍m�肳���ׂ�������ł��B��O�E���Âɖh�q�s�ׂ��s��
�����҂ȂǑz�����ɂ����̂ł��B����𖾂炩�ɂ����̂��y���a�S�U�N�P�P���P�U���z�ł��B
�ł́A�ϋɓI�ȉ��Q�s�ׂɏo���ꍇ�͂ǂ��ł��傤���B������������̂�
�y�Q�S�����z�i���a�T�O�N�P�P���Q�W���j�ł��BB����A�Q�S�����́q���|�r��
�ǂ�ʼn������B
�L��������܂����B����̉�������ɂ���̂��A��Ɉ������y�Q�R�����z
�i���a�T�Q�N�V���Q�P���[�ϋɓI���Q�ӎv�j�ł��B
���̂R�̔���́A��������Ɖ������Ă����ĉ������B
�y����R�z
X��Y���ˎE�������A��ŕ��������Ƃ���ł́A����Y��X���ˎE���悤�Ƃ��Ă����B
��u����X�̒e�ۂ�Y�ɖ��������̂ŁA���ʂƂ���X�͎��Ȃ̐�����h�q�����B
X�ɐ����h�q�͐������邩�B
�u����Ȕ��I�Ȏ�����l���ĉ��̖��ɗ��̂��v�Ǝv���������邩������܂���
�����m�u�����́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�����T�X�Łj
�@�@�w�҂́A�P�ɓ��̑̑������Ă���̂ł͂Ȃ��A�����̖����������悤��
�@�@���ėl�X�ȗ��_���l���Ă���B���ꂪ���ɍ����Ɏv��������I�Ɏv������
�@�@���Ă��A�V���������������邽�߂ɏd�v�ȈӖ��������Ă��邱�Ƃ͑����B
�@�@�V������肪�������Ƃ��ɐ^�ɖ��ɗ��̂́A���_�I�Ȋ�b�ł���A�����āA
�@�@�V�������͎��X�ɐ����Ă���̂ł���B
�y����R�z�ɖ߂�ƁA�{����͖h�q�̈ӎv�̗v�ۂ̖��́u�����v�Ȃ̂ł��B
X�͋q�ϓI�ɂ͐����h�q�̗v�����[�����Ă��܂����A��ϓI�ɂ́A�h�q�̈ӎv��
�Ȃ��ǂ��납�A�E�Q�̈ӎv��������܂���̂ŁA�h�q�̈ӎv�K�v������́AX��
�E�l�����߂ƂȂ�A�h�q�̈ӎv�s�v������́A�����h�q���������s���ƂȂ�܂��B
�u�E�l�Ƃ��s���ɂȂ�̂͂��������v�Ǝv���������邩������܂��A�A
���_�I�ɂ͂����Ȃ�܂��B
�]�ڋ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��H
�i�P�j�h�q�s�ׂ̑�����
�R�U���́A�����h�q�̗v���Ƃ��āu��ނ��ɂ����s�ׁv�ƋK�肵�Ă���A
��ʂɐ����h�q�́u�������v�ƌĂ�Ă��܂��B
����ɂ��u��ނ��ɂ����s�ׁv�Ƃ́u���Ȃ܂��͑��l�̌�����h�q
�����i�Ƃ��āy�K�v�ŏ����x�z�̂��̂ł��邱�ƁA���Ȃ킿�A�����s�ׂ�
�N�Q�ɑ���h�q��i�Ƃ��Ắy�������z��L������̂ł��邱�Ƃ��Ӗ��v���A
�u���̔����s�ׂɂ�萶�������ʂ����܂��ܐN�Q����悤�Ƃ����@�v�����
�����Ă��v�悢�Ƃ���܂��[�y���a�S�S�N�P�Q���S���z
�܂�A�@�h�q��i�́u�K�v�ŏ����x�v�̂��̂łȂ���Ȃ�Ȃ����ƁA
�A�ً}���ƈقȂ�u�Q�̋ύt�v�͗v������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�A�����J�̃��[�X�N�[���ł́A�O��I�ɔ����ǂݍ��܂���܂��B
����ɕ���āA�����R����𒆐S�Ɍ��Ă݂܂��傤�B
�i�Q�j�ύt��
�y����n�ُ��a�T�P�N�P�P���P�U���z
������̎����\�������悤�ȋ���Ȗh�q�s�ׂ�K�@�ƍl�����邽�߂ɂ́A����
�O��ƂȂ鑊����̍U���s�ׂɂ��Ă��A�������ɑ���d��ł��ɂ߂č��x
�̋}�������������N�Q�s�ׂ�K�v�Ƃ�����̂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��������A�����g���Ȃ��ˁB
�y���É��n�ٕ����V�N�V���P�P���z�i�E�l�̎��āj
�y�e�B�i�C�t�͐g�̂̐��v��������Ďg�p���邱�Ƃ��l����ׂ��ł���A���̌��
A�̔����ɑ��ẮA�y�e�B�i�C�t��S���t�N���u����ɂ���A���������Ȃǂ��āA
�y�����z���A���Ƃ͌x�@�̎�ɂ䂾�˂邱�Ƃ��\�����҂ł�������A�h�q�̒��x��
��������B
�y�������ُ��a�U�Q�N�W���P�V���z�i�\�͒c�R���̎E�l�̎��āj
�x�����_����Ƃ̉����ɂ킽��Ȃǂ��āy���z���邱�Ƃ́A�����č���Ƃ�
�����Ȃ��i�ߏ�h�q�j
�y��䍂�ُH�c�x�����a�T�T�N�P���Q�X���z�z�i�\�͒c�R���̎E�l�̎��āj
�e�ՂɁy�����o���āz�N�Q���������ɂ͂Ȃ������i�����h�q�����j
�i�S�j�K�v�ŏ����x
�y��t�n�ُ��a�U�Q�N�X���P�V���z�i���D�������j
�i�����̊T�v�j
�����Ď��X�ɂ����ł���j�����������˂���������ʁA�j�����R���ق�
�ジ���肵�Đ��H�ɓ]�����A�i�����Ă����d�Ԃƃz�[���̊Ԃɂ͂��܂�Ď��S�����B
�i���|�j
���̍s�ׂ��j���𗣂����߂Ɂu�K�v�ɂ��đ����Ȓ��x���z���Ă����Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��v
�i�����h�q�����j
�y�������ُ��a�U�R�N�P�P���R�O���z
�ǂ��z���ɕ��������҂��퍐�l�Ԃɏ�肩����A�^�]�Ȃ̑����������������Ȃ�
���č~�Ԃ����悤�Ƃ������߁A���Ԃi�����Ă����]�����������i�����h�q�����j
�y��㍂�ٕ����P�R�N�P���R�O���z�i�\�͒c�R���̎��āj
�N�Q���\������Ă���ꍇ�ɂ́A�\�����ꂽ�N�Q�ɑ��A���������邽�߂ɁA
[���I�~��]�����߂���A�y�ޔ��z�����肷�邱�Ƃ��\���ɉ\�ł���̂ɁA
����ɗՂނ̂ɐN�Q�Ɠ��퓯���̔�������ɉ����Ėh�q�s�ׂɋy�сA�ꍇ
�ɂ���Ă͖h�q�̒��x������͂��s�g���邱�Ƃ������Ȃ��Ƃ����ӎv��
������ɑ��ĉ��Q�s�ׂɋy�Ƃ����ꍇ�ɂ́A����Ζ@�����Ƃɂ�����
���e����Ȃ��y�����z���s�������ƂɂȂ�̂ł����āA���̂悤�ȍs�ׂ́A
����������@�ł���Ƃ����ׂ��ł���B
��|�͕�����܂����A�\�͒c�ɑ��āu���I�~���v�����߂�[�܂�x�@��
����Ă��炦�[�Ƃ����͔̂��I���Ǝv���܂����A�F����A�ǂ����l���ł��傤���H
�i�U�j���������̌���
���������́A�]���̊w���̈�ʓI�X���ƈقȂ�A�ޔ��`���Ɋւ��Ď��̂悤��
�������Ă��܂��i�����P�S�X�Łj
�@�@�h�q�s�ׂ��@�����ɑ���댯�̍����s�ׂƇA�����łȂ��s�ׂɕ�����
�@�@�@�O�҂ɂ��Ă͕�[���Ƒ�܂��Ȗ@�v�ύt����v������B���Ȃ킿�A
�@�@�@�����ɑ���댯�̍����h�q�s�ׂ́A�d��Ȗ@�v����邽�߂ŁA���A
�@�@���ɕ��@���Ȃ��ꍇ�Ɍ����ċ��e���ׂ��ł���B
�@�@���������āA�}���s���̐N�Q�����҂��A�N�Q������S�m���ɓ�����
�@�@���Ƃ��\�ł���A�N�Q�҂̐����ɑ��Ċ댯�̍����h�q�s�ׂ��s��
�@�@�K�v������ꍇ�ɂ́A��N�Q�҂́y�����Ȃ���Ȃ炸�z�A11�������ɁA
�@�@�����ɑ���댯�̍����h�q�s�ׂɏo���ꍇ�ɂ́A�h�q�s�ׂ̑�������
�@�@�ے肳���B
�R�������́A���������̌����͐����h�q���𐧌���������Ƃ��āA���̂悤��
�ᔻ���Ă��܂��i�R�����u�����h�q�_�̐V�W�J�v�@������U�P���Q���R�Q�ŁE�Q�O�O�X�N�j
�@�@�����h�q�́A�@�I�ɔF�߂�ꂽ�����ȁu�����v�̖h�q��i�ł���A�N�Q��
�@�@�r�������邱�Ƃ͂��������u�����v�̓��e���̂��̂ł��邩��A�s����
�@�@�N�Q����҂ɂ͂��̐N�Q����y�ޔ��z���邱�Ƃ͌����Ƃ��ċ��߂��Ȃ��B
�R�������̂��������ᔻ�̔w�i�ɂ́A�����̎��̂悤�Ȑ����h�q�ς�����悤��
�v���܂��i�R�����w���T���Y�@���_�x�T�R�Łj
�@�@�N�Q�ɑ���y�ޔ��`���z�Ȃ�������`�����ۂ����Ƃ́A�u�s�������Ƃ���
�@�@�ɍs�����R�v���邢�́u�����̉ƂɂƂǂ܂鎩�R�v�Ƃ����悤�Ȑ����ȗ��v
�@�@���Q���邱�Ƃ̎�E���������邱�ƂɂȂ�B
�܂��A���ы��������̂悤�ɔᔻ���Ă��܂��i���ь����Y�u��@���Ƃ��̑j�p�[������D�z���v�����𒆐S�Ɂv
��t��w�@�w�_�W�Q�R���P���R�X�T�ŁE�Q�O�O�W�N�j
�@�@�s���̐N�Q�Ƃ͖@�����̐��ɂȂ������悢�Ɣ��f�������̂ł���A�s����
�@�@�N�Q�̉������@�Ƃ��āA�@�N�Q����߂����邱�ƁA�A��N�Q�҂�
�@�@�y�����܂ǂ킹�邱�Ɓz���l������ꍇ�ɂ́B�@�O�҂��̗p���邱�Ƃ�
�@�@���`�ɂ��Ȃ��B
���W�����ɂ��̓��e�荞�ނ̂͂����Ǝv�����ǁA
�u�`�ł��̓��e����N�����Ă����Ȃ���B
�����h�q�̑�������_���邱�Ƃ́A�˂��l�߂�Ɓu�����h�q�ɂ͑ޔ��`���͂Ȃ��v
�Ƃ����]���̃e�[�[�i���Ƃ��A�R���P�P�R�Łj��F�߂邩�ۂ��ɂ��܂��B
�����ŁA���̑��̊w�����ȒP�Ɍ��Ă݂܂��傤�B
�@���c�����̌����i���c�E���łP�Q�T�Łj
���c�����́A��@�j�p�̈�ʌ����Ƃ��āA��P������D�z�I���v�ی�̌����Ƃ��A
��P�����̏C���Ƃ��āy����`���̌����z��F�߂Ă��܂��B
�@�@�ՓˏɎ���O�ɁA�����I�ȍs���ɂ��Փˏ��y����z�ł���̂�
�@�@����A����s�ׂ��Ƃ邱�Ƃɂ���ė����̖@�v���ێ����邱�Ƃ��v��
�@�@�����ׂ��ł���B
�A��c�����̌����i��c�Q�V�R�Łj
�N���҂�_��Q�҂̂̂悤�ɁA�ӔC���Ȃ������サ���҂ɂ��U���A����ɁA
��U���҂Ɠ��ʂȊW�ɂ���ҁi���Ƃ��ΉƑ����j�ɂ��U���ɑ��Ă��A
����ɂ��y�����͐��������z�ƍl����ׂ��ł���B
�B�R�������̌���
�u��ނ��ɂ����s�ׁv�Ƃ́A�h�q�̂��߂Ɂu�K�v�ŏ����x�́v�Ƃ����Ӗ�
�ł���B���������āA������A�Ƃ肤�邳�܂��܂Ȗh�q��i�̂��������Ƃ�
���₩�ȁi�@���ΓI�ŏ�����i���j�A�������h�q�̂��߂ɓK�����i�A�h�q�K�����j
�s�ׂ��Ӗ�����i�R���S�V�O�Łj
�u��ނ��ɂ����s�ׁv�́A�h�q�s�ׂ́u�K�v���v�݂̂��Ӗ�����Ɖ����ׂ�
�ł���B�����āA�ʐ����A�u�������v�̗v���̂��Ƃɘ_���Ă�����́A
�u�����h�q�̓��ݓI�����v�Ƃ��āA�R�U���P������тQ���̎�|���瓱�����
���̂Ɖ����ׂ��ł���i�R���S�W�Q�Łj
�ӔC�̂Ȃ��҂̈�@�ȐN�Q�ɑ��Ă��A�������A�����h�q���s�����Ƃ͂ł���B
�������A�q���A���_�a�ҁA�D���ҁA�d��ȍ���Ɋׂ��Ď҂Ȃǂ̈�@�ȐN�Q��
���ẮA�K�v���������Ă��A�����ɐ����h�q�����s�g���ׂ��ł͂Ȃ��B
��U���҂́A�y�ޔ��z������Ƃ��͑ޔ����ׂ��ł���A�����̏��������߂�
���Ƃ��ł���ꍇ�ɂ́A�������ĂԂׂ��ł���B�����̉\���̂Ȃ��ꍇ���A
��������ł��邾���z�����Ėh�q�s�ׂ��s���ׂ��ł���B�����Ȃ���A
�ߏ�h�q�ƂȂ�B
�����ł��A�ӔC�̂Ȃ��҂ɑ��Ă͖@�m�̗��v�����Ȃ����Ƃ��A�����̍���
�ł���i�R���S�X�P�Łj
���́A�R�����Ɏ^�����܂��B
����ŁA��P��̍u�`���I���܂��B
�������A���x���͍����Ȃ��B�����̓\��t��������ȁB���쌠�N�Q�r�������B
�Y�@�w�҂̗ϗ��ς�@�I�m���E�\�́A�Љ�펯���Ă̂͂��̒��x�Ȃ낤�Ȃ�
�����A�\�K�E���Q�O��Ői�߂Ă����Ȃ炻���܂Ŗ����ł��Ȃ��Ƃ��v���܂��B
����ρA���ȏ��̎w��͕K�v�Ȃ̂ł́H
�܂��A���ǂ��́A�l�b�g�Ŗ{�Ȃ�Ă�����ł�������̂ŁA�Q�l�}�����w�肵��
�ǂꂩ��������Ƃ��Ⴂ������Ă̂ł�����ł��傤���ǁB
�E�ߌY�@���`��ސ����߂̋֎~���w���ɂ����Ȃ���ߘ_�ɓ����đ��v�Ȃ̂��H
�E������d�����Ă���悤�����A���p�͔��|�݂̂Ŏ��Ăɂ��Ẳ�����قƂ�ǂȂ��ł����̂��H
�E����̓ǂݕ��A����Ƃ͂Ȃɂ��ɂ��Ẳ�����Ȃ��Ă����v�Ȃ̂��H
�������O��Ɉ��������A�����h�q���e�[�}�ł��B
����́A�@�����N�Q�ƇA�ߏ�h�q�A���ꂩ��B��z(�ߏ�j�h�q�������܂��B
�P�@�����N�Q�i�����h�q�j�|���珵���������h�q��
�i�P�j�����N�Q�Ƃ�
�}���̐N�Q�ɔ��������ꍇ�ł��A���̐N�Q���h�q�҂ɂ���Č̈ӂɒ������ꂽ
�ꍇ�i�����h�q�j�A���邢�́A���炩�̗��R�Ŏ��珵�������̂ł���ꍇ
�i�����N�Q�j�́A�ʏ�Ɠ����͈͂Ő����h�q�ɂ���@���j�p��F�߂�ׂ�
�ł͂Ȃ��A�Ƃ������_�����ɂ��ẮA�w���͈�v���Ă��܂����A���͂���
���_�\���ł��B
�w�������ڂ������Ă݂����Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�������珜�����̂́A�u�����v�s�ׂ����łɍU���ł���A�풧���҂�
�u�U���v������ɑ���h�q�s�ׂƂ��čs���B���ꎩ�̂������h�q�ƂȂ�
�ꍇ�ł��B���̏ꍇ�ɂ́A�����ȐN�Q�ɑ���U���ł����āA��������������
����܂���B
���Ȃ݂ɁA�w�҂ɂ���Ď����N�Q�ƌ�������A�����h�q�ƌ������肵�܂����A
�u���珵���������h�q�v�Ƃ����ł��I�m�ȕ\���́A�R��������
�w�@�w����S���N�L�O�_���W�x�i�P�X�W�R�N�j�Ɋ��_�����ɗR�����܂��B
�u�@�w����v�Ƃ����ƑS���̖@�w�҂̏W�܂肩�Ǝv����������Ǝv���܂���
����@�w���̊w�҂̏W�܂�ɂ����܂���i�j
�S���̌Y�@�w�҂̑g�D�Ƃ��Ắu���{�Y�@�w��v������܂��B�i�炭�c�����m��
���������߂Ă��܂������A���݂̗������͎R�������ł��B
�{��ɖ߂�܂��B
���O�͓���o�g����ˁ[���낗����
���Ȃ��������������Ƃ�����Ȃ��Ȃ�ƁA�قځu�X���̑薼�v�ʂ��
�b�̗���ɂȂ���ǂȂ��B
���Ȃ��́A���쌠�@�Ɋւ��Ă��A���������������ق����ǂ��̂ł́A�Ǝv���܂���B
���쌠�@32��1�������35��1���B
���쌠�@�H�������ނƂ��ɒ��쌠���������|�̓��ӂ������Ǝv�����B
�����͂Q�����˂邾��B���Ȃ��̃u���O����Ȃ���ˁB
���쌠�@�R�Q���̌����Ȋ��s�ɂQ�����˂�ւ̏������݁A���p���Y�����邩�^��ł��ˁB
�u�A��]�A�������̑��̈��p�̖ړI�㐳���Ȕ͈͓��v�ǂ���Q�����˂�ւ̈��p���Y������Ƃ͎v���܂���B
���쌠�@�R�T���̑薼�u�w�Z���̑��̋���@�ւɂ����镡�����v���炵��
�Q�����˂�ւ̈��p���Y������Ƃ͎v���܂���B����ɉ��x�������悤�ɁA�������݃{�^���������Ƃ���
���쌠�̕����̓��ӂ�����悤�Ɏv���̂ł����A������]�ڈ��p�����K�v�ł͂Ȃ����Ƃ��������ł��B
�����͂Q�����˂�ł��B�C��t���܂��傤�B
����A�����킩���ĂĂ���ĂȂ��Ȃ�A�F�X����������������B
�Ƃ肠�����A�����ŌY�@�̕��@���w�ڂ���B
������Ƃ������_�����Ă݂��B���x���x�������ςȂ��œ�����Ȃ�B
���̖@���ᔽ�҂̂����ɁB
>>537����͂ǂ����������@����Ԍ��ʓI���Ǝv���܂����H
�@�}������ے肷�錩���i����j
�}�������ے肳���̂́A�����炭�A���������s�ׂ��邢�͍U����\�z
���Ȃ��瑊��ɋ߂Â��s�ׂ��A����̍U���𗘗p���Ă���������悤�Ƃ���
�Ƃ݂�ꂤ��ꍇ�Ɍ�����ł��낤�i����Q�R�T�Łj
��̃R�����g��t�������܂��ƁA�O�ɏq�ׂ܂����Ƃ���A�N�Q��\������
���Ă��A�N�Q�Ɍ�����^���Ă��Ă��A�}�������̂ɂ͉e�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��B
�A�h�q�̈ӎv�ے���i�c���Q�R�W�A���P�V�U�j
�h�q�������ɂ��đ��̖ړI�̂��߂ɍs���s�ׂ́A���͂�h�q�̂��߂̍s�ׂƂ�
�����Ȃ��B���������āA�͂��߂��甽����������Ӑ}�Ō̈ӂɐN�Q�s�ׂ�
�����悤�ȏꍇ�́A�����h�q���݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��i�c���Q�R�W�j
�h�q�̈ӎv�s�v������́A�����������̐����̂邱�Ƃ͂ł��܂���B
�B�������ے���i�����瘿�Q�O�R�ŁA���R�Q�V�V�Łj
�����N�Q�ɂ��ẮA�݂�����N�Q�������p�����悤�ȏꍇ�������āA
�����h�q�̉\���͌`���I�ɂ͔ے肳�ꂸ�A�����̓_�͐N�Q�E�h�q�s�ׂ�
�召�E�y�d�Ȃǂ̑��������f�̒��ōl�������i���R�Q�V�V�Łj
�����h�q���s���Ƃ�����|�́A�}���s���̐N�Q�ɑ�������F�߂邱�Ƃ�
����Ė@�̑��݂��m�F���A�����ĎЉ���̈ێ���}�邱�Ƃɂ��邩��A�h�q
�s�ׂ̎��_�ɂ����Đ����h�q�̗v�������Ă����Ƃ��Ă��A���̖h�q�s�ׂ�
�@�m�̗��v�ɔ����Љ�I���������������̂ł���Ƃ��́A�����I�Ɉ�@����
�L����i��J�Q�W�U�Łj
���̐�����b�Ƃ���u�Љ�I�������v�Ƃ����T�O�͕s���m�Ɖ]�킴��܂���B
�D�v�ی쐫�ے���i��c�j
�����ł́A�����ɐN�Q�̋}�������ے肳��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����A���̎҂�
�@�v��ی삷��K�v���͌������A�t�ɁA������̖@�v�̕ی�̕K�v����
����قnj������Ȃ��ꍇ������i��c�Q�W�W�Łj
�E�������p���i��˂R�W�T�ŁA��[�R�S�U�ŁA�����R�W�W�Łj
�����h�q��蒨�����đ������N�Q���悤�Ƃ��A�̈ӂɒ�������悤�ȏꍇ�́A
�����̗��p�ł����āA�����h�q�Ƃ͉�����i��˂R�W�T�Łj
�u�����̗��p�v�Ƃ����̂́A���@�̎��Ƃł������Ǝv���܂����A���܂�ɂ�
��ʓI�Ȗ@�����ł���A���ߘ_�Ƃ��Ă͖��ɗ����Ȃ��Ɖ]���ׂ��ł��傤�B
���̐��́A�����Ȃ̂ł����A�R���P�Q�P�ł̐����͎��̂Ƃ���ł��B
�@�@�N�Q�̎��O�̉�����v������邱�Ƃ���A�u�}���s���̐N�Q�v�ɑ���
�@�@�����h�q�̐����͍m�肵����ŁA�����Ė@�v�N�Q����N�������Ƃ�
�@�@���R�ɔƍ߂̐������m�肷��B
�h�q�s���͓̂K�@�Ƃ��Ȃ���A����ɐ�s����N�Q�����������s�ׂƖh�q
�s�ׂ̌��ʂƂ��Ĕ���������ꂽ�@�v�̐N�Q�Ƃ����т��ČY���ӔC��₨��
�Ƃ��邱�Ƃ͋^��ł��B
�G���ݓI�������i�R���j
�@�m�،�������́A�@�m�́A����N���[���n���h�̌����ɏ]���̂ł�����
�݂�����Ӑ}�I�Ɉ�@�Ȓ������Ȃ����҂ɂ́A�u�@�v�̗���ɗ����Ė@������
�i����s�Ȃ����Ƃ͋�����Ȃ��̂ł���B���̂悤�Ȑ����h�q�̐����́A����
�h�q�K��ɓ��݂��鐧���ł���i�R���S�W�W�Łj
�ȏ�A�W�̊w�����삯���Ō����킯�ł����A���́A�B���A�D���A�G����
��r�I�Ó��ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
�F����́A�ǂ��l������ł��傤���H�@
������̋������ƂQ�����˂�ɏ������݂���̂��ւ̎R���ȁH��
�ŋ߁A��ŏq�ׂ�[�����Q�O�N�U���Q�T��]��[�����Q�P�N�Q���Q�S��]���_�@��
���āA�ߏ�h�q���N���[�Y�A�b�v����Ă��܂��B
�i�P�j�ߏ�h�q�̈Ӌ`
�ߏ�h�q�Ƃ́A�}���s���̐N�Q�ɑ��Ĕ����s�ׂ��s�������A���̔����s�ׂ�
�u�h�q�̒��x�����v�ꍇ���]���܂��B�����h�q�̑��̗v���͏[�����Ă���
���A�h�q�s�ׂ̑������[���Ȃ킿�u���ΓI�K�v�ŏ�����i���v����сu�h�q
�K�����v�|�������Ă���ꍇ���ߏ�h�q�ł��B
�i�Q�j�ߏ�h�q�̖@�I���i
�ߏ�h�q�́u���ɂ��A���̌Y�����y���A���͖Ə����邱�Ƃ��ł��v�܂���
�i�R�U���Q���j�A���̔C�ӓI���Ƃ̍����ɂ��ẮA�@�ӔC�������ƇA��@
�������̑���������A���̗����̋�̓I�A���́A��ɏq�ׂ��z�ߏ�h�q��
�����Ė��ƂȂ�܂��B
�܂��A��@�����ӔC����������Ƃ����B��@�E�ӔC������������܂��i����
�����́A��@�E�ӔC�������Ƃ����Ă��A�o�����K�v���Ɖ����錩���Ȃ̂��[
�d���I���p���A�ǂ��炩������Α����Ƃ��錩���Ȃ̂��[����I���p���A
�͂����肵�Ȃ��Ɣᔻ���Ă��܂��[�����P�U�S�Łj
�y���c�P�U�T�z
�R�U���Q���́A���肩��U�������Ƃ����ً}��ԁA�@�v�Փˏ�Ԃłً̋}
��Ԃł̋��|�E�����E�����E�T���Ƃ����S���I���h�ɂ��u���҉\���v��
���������Ƃ������Ƃ��l�����āA�Y�̌��Ƃ̉\����F�߂���̂ł���B
�@���s�҂���邷��ɂ́A�s���ɑ��݂����̓I����̉��ōs�҂�
�@�@��@�s�ׂł͂Ȃ��A���̓K�@�s�ׂ��s������ł��낤�Ɗ��҂�����\��
�@�@���Ȃ���Ȃ�܂���B���̉\���̂��Ƃ��u���҉\���v�ƌĂт܂��B
�A��@�������i�����u��z�h�q�E�ߏ�h�q�v�x�@�����T�O���X���i�P�X�V�X�N�j�T�Q�ňȉ��A�O�c�R�X�T�Łj
�y�O�c�R�X�T�z
���ɁA���ΓI�@�v���t�������T�^�I�ȉߏ�h�q�͈�@�̌����Ő������₷���B
�܂��A�h�q�̈ӎv��s�v�Ƃ��闧��́A��@�����Ɛe�ߐ���L����B���R�h�q
�ʼnߏ�Ȍ��ʂ����߂����ĂɌY�̌��Ƃ�F�߂悤�Ƃ���ƁA���҉\����
���Ȃ��Ȃ����Ƃ͐��������Ȃ�����ł���B
�B��@�E�ӔC�������i�c���Q�S�P�A��˂R�X�T�A���P�V�P�A�����R�T�P�A���R�Q�W�S�A
��J�Q�X�U�A�]���P�O�U,��[�R�T�U�A�ъ��l�Q�O�P�A�R���P�R�S�A�ɓ��P�V�O�A��c�Q�X�S�j
�y��J�Q�X�P�z
�ߏ�h�q�ɂ����Ă��A�@�̊m�̌��ʂ͑S�ʓI�ɔے�ł���킯�ł͂Ȃ�����
��@���̌����̖ʂ����邱�Ƃ͔ے�ł����A�܂��A�}���s���̐N�Q�ɑ���
�����҂̐S���I���h���l�������ׂ��ł���B
�ʐ��E����́A�h�q�s�ׂ�����������E�����Ƃ����u���I�ߏ�v�̂ق��ɁA
�N�Q�̏I����ɔ����s�����Ƃ����u�ʓI�ߏ�v���ߏ�h�q�Ƃ��ĔF�߂Ă��܂��B
�y����S�z�i���a�R�S�N�Q���T���j
x�́A�`���������ōU�����Ă����̂ŁA�g����邽�߂���ł`�����A
�`�����|���ɂ������A����ɂ`�����Ď��S�������B
�ō��ق́A���̎��Ăɂ��A�u�{����A�̍s�ׁv���u�S�̂Ƃ��āv�݂�Ȃ�
�ߏ�h�q�ɂȂ�Ƃ��܂����B
�y����T�z�i�����Q�O�N�U���Q�T���j
x�́A�`����A���~���D�M�𓊂�����ꂽ�̂ŁA�`�̊�ʂ����ł���ƁA
�`�͓]�|���ē����Ȃ��Ȃ����i��P�\�s�j���A����ɕ����𑫂��ɂ�����
���݂����肵�ď��Q�킹���i��Q�\�s�j�Ƃ���A��P�\�s�������Ŏ��S�����B
�ō��ق́A���̎��Ăɂ��A��P�\�s�Ƒ�Q�\�s�Ƃ̊Ԃɂ͒f�₪���邩��A
���\�s��S�̓I�Ɋώ@���ĂP�̉ߏ�h�q�Ƃ��邱�Ƃ͂ł����A��Q�\�s��
�����S�ȏ��Q�߂�F�߂�ׂ��ł���Ƃ��܂����i��P�\�s�͐����h�q�j
�y����U�z�i�����Q�P�N�Q���Q�S���j
x�́A�`��x�Ɍ����Đ܂��݊��������|���Ă������߁A���̊��𓊂����i��P�\�s�j�A
���̊�ʂ��肯��Ő��ł��邵���i��Q�\�s�j���ʁA�`�����������B
�ō��ق́A���̎��Ăɂ��A���̂悤�ɔ������܂����B
�u�O�L�����W�̂��Ƃł́A�퍐�l����Q�҂ɑ��ĉ������\�s�́A�}���s���̐N�Q�ɑ����A��̂̂��̂ł���A
����̖h�q�̈ӎv�Ɋ�Â��P�̍s�ׂƔF�߂邱�Ƃ��ł��邩��A�S�̓I�ɍl�@���ĂP�̉ߏ�h�q�Ƃ��ď��Q�߂�
������F�߂�̂������ł���v
�ꌩ�A�������邩�̂悤�ȂQ�O�N����ƂQ�P�N����ɂ��āA���������͎��̂悤�ɂ悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�����Q�W�P�Łj
�@�@�Q�O�N����ɂ����ē�̍s�ׂ����f���ꂽ�̂́A�N�Q�̌p�����̕s���݂Ɩh�q�̈ӎv�̕s���݂Ƃ����_���l�����ꂽ
�@�@���ʂł���A����ɑ��āA�Q�P�N����ɂ����ẮA�N�Q�̌p�����͂Ȃ����݂��A���A����̖h�q�̈ӎv�Ɋ�Â�
�@�@�s�ׂł��������Ƃ���A��̍s�ׂ͂P�̍s�ׂƔF�߂�ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�܂��A���������͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�����P�U�X�Łj
�@�@�Q�̌��肩��A���Ⴊ�u�h�q�s�ׁv�̈�̐���F�߂��́A�u�h�q�s�ׁv���u�}���s���̐N�Q�ɑ����A���
�@�@�̂��̂ł���A����̖h�q�̈ӎv�Ɋ�Â��P�̍s�ׂƔF�߂邱�Ƃ��ł��邩�v�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ��킩��B
�@�@���ԓI�ꏊ�I�A�����Ɩh�q�̈ӎv�̘A�����Ƃ����q�ϖʂƎ�ϖʂ̂Q�̗v�f�ɂ���ĉߏ�h�q�̐��ۂ����f�����
�@�@���邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�������q�ׂ܂��ƁA�P�̍s�ׁi�ߏ�h�q�j�Ɖ]���邩�ۂ��́A��{�I�ɂ́A
�s�ׂ̋q�ϓI�P�Ɓu�}���s���̐N�Q�v�Ƃ̑Ή��W�ɂ���Č��܂�̂ł�
�Ȃ��ł��傤���B
�}���s���̐N�Q�����S�ɏI��������̔����s�ׂ́A�����ɖh�q�̈ӎv��
���낤�Ƃ��A�h�q�s�ׁi�ߏ�h�q�j�Ƃ͔F�߂��Ȃ��̂ł��B
>>�s�ׂ̋q�ϓI�P�Ɓu�}���s���̐N�Q�v�Ƃ̑Ή��W�ɂ���Č��܂�̂ł�
>>�Ȃ��ł��傤���B
>>�}���s���̐N�Q�����S�ɏI��������̔����s�ׂ́A�����ɖh�q�̈ӎv��
>>���낤�Ƃ��A�h�q�s�ׁi�ߏ�h�q�j�Ƃ͔F�߂��Ȃ��̂ł��B
�悭�킩���B�A�z�H
�܂��Ƃɂ������߂ɑS���̕���ɂ��Ď������q�ׂĂ����ȁB
�o�όY�@��㎖�Y�@�݂����ȕ��݂����ȕ�������肢�����B
�N�݂����ȓ��������̂͌o�όY�@�Ƃ��㎖�Y�@�̂ق��������Ă��B
����ȍu�`�͐�Ɏ����Ȃ�
�������ɂ��ꂪ���W�����Ȃ�o���͂������ǁA
�u�`�ł��̂܂�܂��̓��e�����ƁA�ꗬ�吶�ł����čs���Ȃ��Ǝv����B
���F�e������Ȃ����ǁA
�s�ז����l�ƁA��@���̖{���_�ɂ�����Љ�ϗ��K�͈ᔽ����Љ�I���������Ƃ̌��т��͕K�R����Ȃ��B
�s�ז����l�̗���ɂ����Ă��A�@�v�ی��ړI�ɂ��̖@�v�N�Q���u������s�ׁi�y�ь��ʁj����@���̖{��
�Ƃ��闧��͂��蓾��B
��c�����͂��̂悤�ȗ�����̗p���Ă���B���������āA�@�v���d�����邱�ƂɂȂ�B
�P��̎��掩�^��w
�����������H������ƈႤ�悤�ȋC������B�ǂ��炩�Ƃ����ƋK�͈ᔽ���d����������������悤�ȁE�E�E�E
�撣���A�����F�e�N��
���̋K�͂��@�v�ی�̂��߂ɒ藧���ꂽ����
������s�ז����l���@�v�֘A�I�ȕX�قłȂ�������Ȃ��Ƃ��Ă����
�R�R��ւ�̋L�q���Ƃ����炩���Ă��č�������
������Ƃ��̋L�q�����p���Ă���B���܂ł�����p���Ă�������
���̎w�E�����p�ł��Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B
����Ɍ�����P���Ȃ��Ȃ��悤�ɁB���������A�K�͈ᔽ�_�Ɩ@�v�N�Q�_��
���v������͖̂����B
�s��Ȃ킯����ˁB
��ΌY�@�����ɂȂ��
�悭�ǂނƕX�ق��ĉ��H��
�@�v�֘A�����Ă��ƂȂ���肩�ˁB�ی�@�v���u������E�E�E�E�܂��ʂɂǂ��������Ə��肾��
��c���͍s��ł���A�s�K�͈ᔽ�_���d������͖̂����B
�ی�@�v���u������Ƃ������Ă��Љ�I�������������Ă��������A
�ی�@�v���u�����Ă��Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��B
�܁A�֘A���ł����̂ł���A�N�̔����͓�����O�̂��ƌ����Ă��邾�������ǂˁB
�����������������o�J�������킗����
80�ł�����ȂLj�@���ɐG��Ă���Ƃ����ǂ�ł݂���
���ƖړI���Љ�ϗ����Љ�I���������ɂ������Ắu�Y�@�̑��ݗ��R�ł���@�v�ی�Ƃ������_����������i����ɂ́C�@�Ɨϗ��̋ߓ��������N�����j�����ꂪ����v�i256�Łj�Ƃ��Ă���
�Љ�I���������ɑ���ᔻ�͐����ł͂Ȃ��ˁB
�Љ�I�������̖��_�́A���̒��g�̋�̐����Ȃ����Ƃ�����ˁB
�@�v�ی���u������Ȃ�ē��R���낤�B
�܁A��c�����s��Ȃ̂ŁA�@�v�ی�ƃ����N���Ă��邩�Ƃ�����
��������Ȃ��B�����Ă��邱�Ƃ͊G�ɕ`�����݂Ȃ�ʂ��̂Ȃ肯��B
���g���������Ƃ��w�E���Ă��邯�ǂ�
������ی��ړI�Ƃ��闧����s�ז����l�ƌĂ�Ŕᔻ����͎̂����Ƃ���Ƃ������Ƃ�
�Y�@�̗��j�̒��ł͓�����O�ł͂Ȃ��悤����
�P�O�O�N����s���Ă���̂͊m���B�s�ז����l�_�́A�x������w�҂̃��x�����Ⴂ����d���Ȃ��B
���A�����A��c�����肪���Ȃ���፡���s�ז����l�_�͏I����Ă��B
��J��ǂ�łȂ���ˁH
����Ɠ����悤�Ȕ��f�g�g�݂���B���̑������͂ˁB
�s�בԗl���Љ�I����������E���Ă��邩�ǂ����f����킯�����A
���̍ۂɁA��i���@�̒��x�A�@�v�N�Q�̒��x�A�ۑS�@�w�̒��x�A���̑���
�l���v�f�Ƃ��ċ����Ă邾��B
���̑����l���Ƃ����킯���B
���ʖ����l�͗D�z�I�@�v�N�Q����{�Ŕ��f���邩��A�ȒP�Ɍ����邾���B
���̂������̕��ł��ˁB
���{�̖@�w�����҂̂قƂ�ǂ͎��Y�p�~�_�܂��͑Q���I�p�~�_�҂Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�킪���̎��Y���u�_�҂͎����Əo�g�����҂��炢�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̑��u�_�҂̎咣�́A���Y���u�̐��_�������ʂ�A�ƍߔ�Q�ҁE�⑰�̏���������d��������̂���
�v���܂��B
�킪���ł͐��_�����̂��тɎ��Y���u�_�����_�̑������߂�Ƃ����������ʂ��łĂ��܂��B
�����A����ɂ��ẮA���_�����̕��@�����ł���Ƃ̔ᔻ���L�͂ɂȂ���Ă��܂��B
���킵���́A�킪���ł����Ƃ������Ȏ��Y�p�~�_�҂ł���c���d�����m�́w���Y�p�~�_�x�i��6�ŁE�L��t�j
���Q�Ƃ��Ă��������B
�킪���ō����Y�p�~�ɂ�������ƂȂ��Ă���̂́A�ƍߔ�Q�҂̏�������ł͂Ȃ��ł��傤���B
���s��q�E�Q�����Ŏ��Y�������o���̂́A��Q�҈⑰�̏�������ɂ߂ďs��ł��������Ƃ�����߂�
�d�v�ȈӖ����߂Ă����Ǝv���܂��B
�c�����m�́w���Y�p�~�_�x�ł́A���̓_�i��Q�ҁE�⑰�̏�������j�Ɋւ���L�q�������_����U��Ԃ���
�݂�Ƃ��ア�Ǝv���܂��B
�Y���葱�@����������A��Q�҂̌Y���ٔ��Q���������������݁A��Q�ҁE�⑰�̏���������ǂ������̂��A
�́A����߂ē����肾�Ǝv���܂��B
�܂�A�Љ�I�������Ŕ��f������Ă킯�˂�����
������A�B���Ȃ�ˁB�A�z���Ȃ��B
���∫�ӂ̂Ȃ����J�Ȑ����ƑΉ��Ƃ��Ċ��ӂ������܂��i���@�����B�{���ɕ��ɂȂ�܂��B���肪�Ƃ������܂��B
�ȉ��ɂ������āA�������̎���A�m�F���͈ӌ����L�ڂ����Ă��������B
�L�ڂ���Ă���u���{�̖@�w�����ҁv�y�сu�����Əo�g�����ҁv�́A���ꂼ��A�@�w���y�і@�w�����w�����Ȃɏ������鋳���̂����A
�i�@�������͎i�@�C�K���l���ɍ��i���Ă���Җ��͍ٔ����A�����Ⴕ���ٌ͕�m�̌o����L���Ă���҂ł����B
�ō��ٔ����Ɋ�Â��i�@�@�ւȂ����i�@�{�ƁA���@�{�ƂɁA���Y�̐��x��p�~���邱�ƁA���͔p�~���Ȃ����Ƃ̂��ꂼ��̌��_�ɌW�閽������E����ɑ����\���Ȏ������́A���܂��A���݂��Ȃ��Ǝv���܂����B
���Y�̐��x��p�~���Ȃ����ƁA�y�єp�~���邱�Ƃ̂��ꂼ��ɍł����͗D�悳���e����^����ꖔ�͓�ȏ�̗v�f���͓����@�\�Ȃ�����p�̌���m�邱�Ƃ��ł����̂ŁA�ƂĂ����ɂȂ�܂����B
��i���A�Ⴆ�f�W�ɂ����āA���Y�̐��x�����݂��鍑�A���͑��݂��Ȃ����́A���ꂼ�ꉽ�ł����B
���Ɏ��Y�ɌW��i�@�̔��f�◧�@�{�̍s�ׂ́A���f����҂ɌW�鑸���A���݂��̑��̑S�Ă��o�Ă���ƁA�킽���͎v���܂����B
�킽���́A���̂��Ƃ��v���܂����B���{�ɑ��݂��鐧��@�́A�������̊ϓ_����݂ĉ��Ăɑ��݂���_���Ɋ�Â��@���܂ނƎv���܂��B
���ꂩ�玀�Y�̐��x��p�~���邩�ۂ��̔��f�ɌW��O��ɂ́A���Ăɑ��݂���悤�Ȗ��m�Ș_�����K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�����āA�_���Ř_�����邱�ƁA���ꂪ�K�v���Ǝv���܂��B����ɁA���̘_�������������䂷�邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�ɌW������I�Ș_���̍\�����A�킽���͍l���邱�Ƃ����܂��ł��Ă��܂���B
�����Ă������������ƂɊ�Â��v�l�Ȃ��������Ȃǂ��A���������s���Ă݂܂��B
�킽���͓���Ƃ������܂����B���_�̑I���͌��܂��Ă��邯��ǂ��A���̌��_���@�ɌW������I�Ș_�����\���ł��܂���B
���̈Ӗ��ł́A�ō��ٔ����̎d���́A�\���ł��邵�A�����_�ł͂킽���������̂��Ǝv���܂����B
�����_�ɂ�����A�킽���̗���́A���̂Ƃ���ł��B
���Ɂu���Y�̐��x��p�~���邩�ۂ��v�ɂ��č������[���������ꍇ�ɁA�킽���́A�u���Y�̐��x��p�~���邱�Ɓv�ɂ͓��[���܂���B
����߂��ő���ɖh�~����悤�Ȏ葱���̎������̊m�ۂ����邱�Ƃɓ��[���܂��B
���̌������{�̖@�w�����҂Ƃ́A�����錤����̌����҂��Ӗ����܂��B
���̒��ɂ́A�i�@�����ɍ��i���������҂�����ł��傤���A�����o���͂Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B
���̌��������Əo�g�����҂Ƃ́A��ɁA���@���E�ٔ����̌o����L���錤���҂ł��B
���������@�������o�g�̌����҂̒��ɂ́A���Y���u�_�҂���萔���݂���悤�Ɏv���܂��B
�������A�ٔ����o���Ҍ����҂̒��ɂ͖��m�Ȏ��Y�p�~�_�ҁi�ؒJ�����Ȃǁj�������Ȃ��炢�܂��B
���@���o�g�҂́A���Y���u�_�҂���r�I�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���Ȃ��̂��ӌ��ɂ��āA���̊��z���q�ׂ����Ă��������B
���Y���p���ɂ����āA�u����߁v�̖��͊m���ɍŏd�v�̉ۑ�̈�ł͂���܂����A
����ɂ���߂̉\�����F���Ȏ��Y�������Ăł����Ă����Y���������̂��ǂ����A
���ꂪ���Y���p���̖{���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�z�Z�E�����p���g�w�Y�@�̎��s�v�c�x�Q�ƁB
�u���Ȃ��̂��ӌ��ɂ��āA���̊��z���q�ׂ����Ă��������B
���Y���p���ɂ����āA�w����߁x�̖��͊m���ɍŏd�v�̉ۑ�̈�ł͂���܂����A
����ɂ���߂̉\�����F���Ȏ��Y�������Ăł����Ă����Y���������̂��ǂ����A
���ꂪ���Y���p���̖{���Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�z�Z�E�����p���g�w�Y�@�̎��s�v�c�x�Q�ƁB �v
�@�����_�ɂ����āA���{���̐���@�́A���Y�̐��x��L���Ă��܂��B
���̑O��ɂ����āA���̑��l�����ׂ�����͓��i�̎���Ȃ�����A
����߂̉\�����F���ł��鎖�Ăł����āA���A���̎��Ă͎��Y�ɑ������鎖�Ăł���ꍇ�ɂ́A
�ō��ٔ����́A���̎��ĂɁA���Y�̌��_���͌��ʂ�^���邱�ƂɁA��@�͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�@>>580�̂悤�ɍl���Ă݂܂����B�������A�����ł́A�u�������̂��ǂ����v�Ɏ����ꂽ��|���e���A�u���{���ɂ�����@�Ȃ����@�ߓ��̈�@�����邩�ǂ����v�Ɍ��肵�Ă݂܂����B
�����Ƃ��A���{���ɂ����鎀�Y�Ɋւ�鐧��@�������_�ő��݂��Ă���ɂ�������炸�A���̎��Y�Ɋւ�鐧��@�ɂ����āA���Y�̐��x��p�~���邽�߂ɂ́A
���@�{�������Ɏ��Y��p�~����s�ׂ�����̂ɏ\���Ȏ����A���R�����K�v���Ǝv���܂����B���̏\���Ȏ����A���R���̋�̓I�ȗ���A�킽���͍\���ł��܂���ł����B
�@���Y�̐��x�����݂��邱�ƁA�y�ю��Y�̐��x��p�~���邱�Ƃ̂��ꂼ��𐳓�������_���̍\�����̑��̗��R�t�����A
�������̊ϓ_����݂ĉ��Ăɑ��݂���_���Ɋ�Â��@�̊�b�Ȃ��������̂悤�ɁA���m����̓I�ɍl����K�v������Ǝv���܂����B
�Q���I���Č��t���g�������Ă��傤���Ȃ��悤�����A
�i�K�I�p�~�_�҂̊ԈႢ�B�g�������Ԉ���Ă����B
�ǂ����悤���Ȃ��Y�@�w�҂��Ȃ�����
���������[���낻������̎����ł����[�K����lj����^����锻��ł�����A
��������ƕ��K���Ă��������B
�����̂�����́A�Q�O�N����ɂ��ẮA�ō��ٔ����Y������W�U�Q���U��
�P�W�T�X�ŁA�Q�P�N����ɂ����ẮA�������U�R���Q���P�ł�}���ق�
�ǂ�ł��������B
�R�@��z�i�ߏ�j�h�q
�i�P�j��z�h�q
C����A�y�S�I�Q�V�����z��(�����̊T�v)��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B���̂����A�ٌ�l�̎咣�A���Ȃ킿�uX�̍s�ׂ́A�q�ϓI
�ɉߏ�ł���Ƃ��Ă��AX�͒P�Ȃ�_�Ŕ������Ă���Ǝv���Ă����̂ʼnߏ莖��
�̔F���������Ă���A�ߏ�h�q�ł͂Ȃ���z�h�q�Ƃ��Č̈ӐӔC���j�p���ꖳ��
�ƂȂ�v�|���ꂪ�A��z�h�q�̂��ׂĂ��]���\���Ă��܂��B
���������Đ������܂��傤�B
��P�u�Łu�ƍ߂Ƃ́A�\���v���ɊY�������@���L�ӂȍs�ׂł���v�Ɛ���
���܂����ˁB�u�L�Ӂv�Ƃ́A�̈ӁE�ߎ������邱�Ƃ��Ƃ��������܂����B
�����āA��@����j�p���鎖�R������Δƍ߂͐������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����
���܂����i�����h�q�j
�����悤�ɁA�ӔC���j�p�����Ƃ����A�ƍ߂͐������Ȃ��̂ł��B
�܂�A�̈ӂ��Ȃ��Ƃ��́A�ӔC���j�p���ꖳ�߂ƂȂ�̂ł��B
X�́A�s����A�����|�P�b�g���烉�C�^�[�����o�����̂����āA�i�C�t�����
�o�������̂ƌ�M���A���Q�̌̈ӂ������ċ����R��グ�����������B
���̏ꍇ�AA�����ۂɃi�C�t�����o�����̂ł���AX�ɐ����h�q���������܂��B
�������A���o�����̂̓i�C�t�ł͂Ȃ����C�^�[�ł�����A�����h�q�͐������܂���B
���̂悤�ɁA�q�ϓI�ɐ����h�q�̗v�����[�����Ă��Ȃ��̂ɁA�s�҂������h�q
�ɓ����鎖��������ƌ�M���čs�ׂɏo���ꍇ���u��z�h�q��Ɖ]���܂��B
��z�h�q�ɂ́A���̂悤�ȁu�N�Q�̌�z�v�̂ق��ɁA�u�s���̌�z�v������܂��B
���������̐ݗ�ł��i�Q�Q�X�Łj
�y����W�z
X�́A�钆�ɗƂ̉Ύ��ő��ɕ��@���Ȃ���ނ���������ł���A��s�@
�N���҂��Ǝv���ē˂��Ԃ��ď��킹���B
���̏ꍇ�AX�̍s�ׂ͏��Q�߁i�Q�O�S���j�̍\���v���ɊY�����܂����AA��s�@
�N���҂��ƌ�M���Ă����[X�̔F���Ƃ��Ă͐����h�q���s���Ă������ł�����
�[�̂ł�����A�̈ӂ͔ے肳��A�ߎ����F�߂������ŁA�ߎ����Q�߁i�Q�O�X���j
���������܂��B
�ȏ�̐����͒ʐ��I�����ł���A���ɇ@�ӔC�ł͂Ȃ���@���j�p��F�߂闧��A
�t�ɁA�A�̈ӂ��m�肷�闧��i���i�ӔC���j������̂ł����A�ȗ������\���v���_
���������Ă��Ȃ��Ɨ����ł��܂���̂ŁA�����ł̐����͊������܂��B
��z�h�q�́u�������̌�z�v�̃p�^�[�����u��z�ߏ�h�q�v�ł��B
�y����X�z�i���a�Q�S�N�S���T�����C���j
X�́AA�Ɋp�ނŏP��ꂽ�̂ŁA�茳�ɂ������_��̂��̂Ŕ��������Ƃ���A
����͕��ł���AA�����S�������B
X�̍s�ׂ́A���Q�v���߁i�Q�O�T���j�̍\���v���ɊY�����܂����AX�́A����
�_��̂��̂ƌ�z���Ă���A�̈ӂ��ے肳��܂��̂ŁA�ߎ����������ŁA
�ߎ����Q�߁i�Q�O�X���j���������܂��B
D����A�y�S�I�Q�W�����z�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�Q�W�����́A�ߏ萫����b�Â��鎖����F�����Ă�����
�F�肳�ꂽ�킯�ł�����A�s�҂̔F�����Ă��������́A�ߏ�h�q�Ƃ�����@
�Ȏ����ł���A�̈ӂ��m�肳��܂��B
�ō��ق́A���̂����Ō�z�ߏ�h�q�ɓ�����Ƃ��ĂR�U���Q����K�p���Ă��܂��B
�ǂ̂悤�ȃp�^�[���ɂR�U���Q�����K�p�����̂��Ƃ�����������̂ł����A
�{�u�`�ł͊������܂��B
������ɂ���������������܂���B
�����̂�����́A����A�O�c�搶�̋��ȏ��𗧂��ǂ݂ł������ł�����A
�ǂ�ł��������B
��z�h�q�ƌ�z�ߏ�h�q�̃p�^�[���������S�S�R�ł̐}�\�A�ӔC��������
��@�������ƂłR�U���Q���̓K�p�͈͂��قȂ邱�Ƃ���������S�S�W�ł̐}�\
�͐�i�ł��B
���́A�w������A�ǂ����Ă���z�ߏ�h�q�������炸�A�S�S�R�łƂS�S�W�ł�
�R�s�[���Đ蒣�肵�ĂȂ��Ă݂āA����Ɨ����ł��A�ڂ����J���ꂽ
�Ƃ����L��������܂��B
�O�c�搶�̋��ȏ��́A��σr�W���A���ō��ł��w������ɐl�C������܂����A
���̌��_�͏o����ł��鏕��_���w���I��@���_�̌����x�i�P�X�W�Q�N�j
�ɂ���܂��B�I���W�i���Ȑ}�\���ӂ�ɎU��߂��咘�ŁA�w��������
���������씎�m�͂܂����������ł��Ȃ������̂ł����A���肪�u�����A�����v
�Ƃ����̂ō��i�_��^���Ă��܂����Ƃ�����b������܂��i�j
�����h�q���ɂ߂Ď��H�I�Ŕ���������̂ɑ��āA�ً}���͔���͏��Ȃ�
��ɗ��_�ʁi�@�N�w��̍��{���j���c�_����Ă��܂��B
�y����P�O�z�i�J���l�A�f�X�̔j
�D����j���ĊC�ɓ����o���ꂽX��Y�̂Q�l�����āA�C�ɂP���̔��������
�������A���̔͂P�l���̏d�������x�����Ȃ����̂������̂ŁAX�́AY��
�M�����������������������B
�y����P�P�z�i�~�j���l�b�g�������j
�C�M���X�D�u�~�j���l�b�g���v����j���A��g��X,Y,A���C�ɓ����o����A�{�[�g
�ŐH�����Ȃ��Y�����AX��Y�͍ł�����Ă������NA���E�Q���A���̓���H�ׁA
��������Ő����Ȃ��炦���B
����P�P�́A���ۂɁA�P�W�W�S�N�A�C�M���X�ŋN�����������ł��B������AX��
Y�͋��R�ʂ肩�������D�ɋ~������܂����B
�C�M���X�̍ٔ����́A�Q�l�̔퍐�l�ɑ���������͎��Y�����������܂������A
��ɉ��͂ɂ��U�J���̎��R�Y�ɕύX���܂����B
�ł́AE����A�Z�@��ĂR�V���P����ǂ�ł��������B
�L��������܂����E���ꂪ�ً}���̐����v���ł��B
�i�P�j���݂̊��
�u���݁v�������h�q�́u�}���v���L���T�O�ł��邱�Ƃ́A��P�u�Ő������܂����B
�i�Q�j�ۑS�@�v
�ً}���́u���Ȗ��͑��l�̐����A�g�́A���R���͍��Y�v�ɑ�����s�ׂ�
���邱�Ƃ�v���܂��B�����ł͂Ȃ��A���_��呀�Ȃǂ��܂܂�܂��B
�i�R�j���s��
�ً}���ɂ́A�@���Ȃ̗��v�ɑ����������邽�߁A���W�̑�O�҂�
�����ȗ��v��N�Q����Ƃ����u�]�Ō^�v�݂̂Ȃ炸�A�A���̊��̗R������
���̐����ȗ��v��N�Q����Ƃ����u�����^�v���܂܂�܂��B
�i�S�j��ނ��ɂ����s��
�u��ނ��ɂ����s�ׁv�Ƃ́A�����h�q�Ɠ������u�ŏ����x��i���v��
�u��i�K�����v���Ӗ�����u�K�v���v�ɉ����āA���ɕ��@���Ȃ��Ƃ���
�u��[���v���Ӗ����܂��B
�i�T�j�������Q�������悤�Ƃ����Q�̒��x���Ȃ������ꍇ
�@�v�ύt�̌����i�Q�̍t�ʁj�Ƃ����܂��B���v�t�ʂɂ���āA�ۑS�@�v���N�Q
�@�v�Ɠ��������A�������ł���ꍇ�ɁA�@�v�ύt�̌������[������܂��B
�����h�q����@���j�p���R�ł��邱�Ƃɂ��Ă͑����͂���܂��A
�ً}���́u���ΐ��v�̊W�ł��邱�Ƃ���A���̖@�I���i�ɂ��Č�����
���G�ɕ�����Ă��܂��B�z�z�������W���������Ă��������B
�i�P�j��@�j�p�ꌳ���i�ʐ��B�c���Q�S�T�A����Q�Q�W�A��˂S�O�P�A���c�P�U�R�A
�@�@�@���P�V�W�A��J�R�O�Q�A�O�c�R�U�O�A�x���P�U�U�A�����Q�W�X�j
�i�Q�j�ӔC�j�p�ꌳ���i���P�T�S�A�A���Q�O�W�j
�i�R�j��@�j�p����{�Ƃ��Ȃ���@�v�����l�̏ꍇ�͐ӔC�j�p�Ƃ��錩��
�@�@�i�����瘿�Q�O�T�A���R�Q�U�X�A�����S�O�T�A�R���T�P�W�j
�i�S�j��@�j�p����{�Ƃ��Ȃ��琶���ΐ����A�g�̑ΐg�̂̏ꍇ�͐ӔC�j�p�Ƃ��錩��
�@�@�i�ؑ��T��Q�U�T�A��������u�ً}���v�w�Y�@�u���Q���x�i�P�X�U�R�N�j�P�T�W�Łj
�i�T�j��@�j�p�ꌳ�����̂������g�̂̐��v���̐N�Q�ɂً͋}���͔F�߂�ꂸ���@�K�I�ӔC�j�p�̖��Ƃ��錩��
�@�@�i�R���P�R�X�j
�i�U�j�ӔC�j�p�ꌳ�����̂�ۑS�@�v���N�Q�@�v�ɒ������D�z����ꍇ�ɂ͈�@�j�p�Ƃ��錩��
�@�@�i�X�����w�ً}���̌����x�i�P�X�U�O�N�j�Q�Q�W�ŁA��c�R�O�Q�j
�i�V�j���I��@���̑j�p�Ƃ��錩���i���c���`�w�s�����ƌY����@�_�x�i�Q�O�O�Q�N�j�Q�W�R�ŁA�ъ��l�Q�O�V�j
�i�W�j�ۑS�@�v���D�z����ꍇ�ɂ́A��@�j�p�Ȃ����i���̔�Y���@�߂ɂ����Ĉ�@�Ƃ���Ă���ꍇ�ɂ́j���I��@�j�p�A���v�����̏ꍇ�ɂ́A���I�ӔC�j�p�Ƃ��錩��
�@�@�i�R���T�P�W�j
�i�X�j���Q�����ӔC��ǂ�Ȃ��ꍇ�͈�@�j�p�A�����ꍇ�͉��I��@���j�p�Ƃ��錩���i�]���P�P�Q�j
�i�P�O�j�Y�@�ً̋}���́A��Q�҂ɑ��Q�������Ȃ���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ĉ�@���j�p��F�߂����x�Ƃ��ė������錩��
�@�@�@�i���{�P�T�S�A�����m�u�P�W�Q�A�����P�V�R�j
�ɑ������h�q���\�ł��邩�A�A���ƂƂ��Ċ֗^�����҂̍s�ׂ����I��
�Ȃ邩�A���̓_�̉����ɍ��ق������܂��B
�@�����A�ӔC���j�p�����ɂ����Ȃ��̂ł���A�ً}���s�ׂ͈�@�s�ׂł���A
����ɑ��Ă͐����h�q�������đR�ł��܂����A�A�����A�ً}���s�ׂ���@
�Ȃ̂ł���A����ɋ��ƂƂ��Ċ֗^�����҂͏������꓾�邱�ƂɂȂ�܂��B
�y�����z���q�ׂ܂��ƁA�u�l�̐l�i�́A�������Ȃ�ꍇ�ɂ������ɖړI��
���Ďg�p���A�����ĒP�Ȃ��i�Ƃ��Ďg�p���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����L����
�J���g�̌��t������܂��B
�ŋ߂ł�,�R���������u�l�̐����y�ѐ����ɏ�����g�̂̏d�v�����́A���ꎩ��
���ȖړI�Ƃ��Ĉ����Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�{�l�̈ӎv�Ɩ��W�ɑ��l�̋]����
������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂��i�R���P�R�W�Łj
���������ł��B
���������āA�i�S�j���Ȃ����i�T�j���Ɏ^�����܂��B
�����X�B�ς����Ȃ��Ȃ���������
�m���ɌY�@�w�ҁB�����������m��B
�y����P�Q�z
����̗����x�ʼnЂ��������҂��A���Ȃ̐�������邽�߂̍Ō�̎�i��
���āA���l�̌��������B
�������͎����N�Q�ƃp�������ɍl���邱�Ƃ��ł��܂��̂ŁA�����N�Q���v��
�o���āA�e���l���Ă݂Ă��������B
�S�@���v�ً}���
�y����P�R�z
A��X�̎q��B��U�����AX�ɑ��ċ�s����P���~�𓐂܂Ȃ���B��R�Ƌ���
�������߁AX�͋�s����P���~�𓐂B
�ꌩ����ƁAX�̍s�ׂ́A�ً}���̐����v�������ׂď[�����Ă���悤��
�v���܂��B�������A������萶���̕����厖������Ƃ����āA����P�R��
�悤�ȋ�s������F�߂Ă��ẮA�Ƃ��ɒʐ��ł͊��S�Ȉ�@�j�p�ƂȂ�܂�
����A�P��ꂽ���i��s�j�͐����h�q���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
��������Ɓu���̂悢�ƍߎ҂͊F�A���̕��@�ŗ��v�������߂邱�ƂɂȂ낤�v
�i���{�P�T�X�Łj
����́A�ނ���A�ً}���ɂ�����u�@�v�Փˁv�Ȃ����u�������v�̖���
�l����ׂ��ł��傤�B
���ہA�����n�ٕ����W�N�U���Q�U���́A���v����ĎE�l���s�������Ăɂ���
�g�̂̎��R�ɑ��錻�݂̊���F�߁A�ߏ���̐������m�肵�Ă��܂��B
�i�I�E���^���������`�E�l�����j
�ȏ�ŁA��R�u[�ً}���]���I���܂��B
�P�u�@�v�v�Ɩ@�v�ی��`
�i�P�j�u�@�v�v�Ƃ�
�ŐV�̋��ȏ��ł���i�Q�O�P�R�N�R���P�W���j���������̋��ȏ��́A�ʏ�u��Q�҂̓��Ӂv�Ɖ]���Ƃ�����u�@�v��̂̓��Ӂv�ƌĂ�ł��܂��̂�
�܂��A�u�@�v�v�Ƃ͉�����������Ȃ���Ȃ�܂���B��ʂɁA�@�v�Ƃ́u�@�ɂ���ĕی삳��闘�v�������v�u�Ⴆ�A�E�l�߂̕ی�@�v�͐l��
�����ł���v�Ɛ�������܂��i�Ⴆ�A��J�V�Łj
�u�@�v�v�̌���́u�@�I�ȍ��݁v�iRechtsgut�j�ł��B�����ŁA���������́A�u�@�v�v�Ƃ́u�o���I�ɔc���\�Ȏ��̂�L���i�o���I���ݐ��j�A�l��
�ɂƂ��Ă̗L�p���i�l�ԊW�I�L�p���j�𗝗R�ɖ@�I�ی삪�K�v�Ƃ����Ώہv�ƒ�`���Ă��܂��i�����P�U�Łj
�i�Q�j�@�v�ی��`
�ȏ�̂悤�ȈӖ��ł́u�@�v�v�̕ی�ɖ𗧂���ŁA�Y�����@�͐���������܂��B���̂悤�ȍl�������u�@�v�ی��`�v�ƌĂт܂��B
�u�@�v�ی��`�v�́A�u�ߌY�@���`�v��u�ӔC��`�v�ƂƂ��ɁA���ȏ��̖`���ŐG�����d�v�Ȍ����ł��B
�u�ƍ߂Ƃ́A�\���v���ɊY�������@���L�ӂȍs�ׂł���v�ƒ�`���܂������A�u�@�v�ی��`�v���͈�@���́A�u�ӔC��`�v�͐ӔC�_�̎w��
�����ł��B�܂��A�u�ߌY�@���`�v�͍\���v���_���x����d�v�ȗ��O�ł���Ɖ]�����Ƃ��ł��܂��i�R���S�ŎQ�Ɓj
�ł́A���̂悤�ȈӖ��ł́u�@�v�ی��`�v�́A�킪���̔���œO�ꂳ��Ă���ł��傤���H
�킢�����Еz�߁i�P�V�T���j�́u���S�Ȑ������v��ی삵�i���a�T�Q�N�P�Q���Q�Q���j�A�q���߁i�P�W�T���j�́u�ΘJ�̔����v��ی삷��i���a
�Q�T�N�P�P���Q�Q���j���̂Ƃ���Ă��܂��B
�����́u�Љ�ϗ��v�̌��������ɂ������A�u�@�v�v�ƌĂѓ�����̂�����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�{��ɖ߂�܂��B
�@�v��̂��@�v�̏����ɓ��ӂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�@�v�̌��p�̋����������Ă���킯�ł�����A���͂�@�v�͑��݂����A���̐N�Q�����݂��܂���B
�܂��A�@�v��̂ɓ��ӂ�����ꍇ�ɂ́A���̐l�̂��߂ɓ��Y�@�v��ی삷��K�v�����F�߂��܂���B�������āA�@�v��̂̓��ӂ́A�u�@�v�̕s���݁v
�܂��́u�@�v�̗v�ی쐫�̕s���݁v�𗝗R�ɔƍ߂̕s�������A�����܂��[�u���v��&#32572;�̌����v
�i�����u��Q�҂̏����v�w����Y�@�����Q�x�i�P�X�W�P�N�j�P�U�W�ŁA�����T�W�V�A�O�c�R�S�V�A�R���Q�O�Q�A��J�Q�T�R�A�x���P�W�O�A
�@���R���ގq�u���Ȍ���Ƃ��̌��E�i��j�v�@�w�����Q�W�S���i�Q�O�O�S�N�j�T�U�ŁA�R���P�T�O�A�����R�O�O�A�����P�P�Q�j
����ɑ��āA�@�@�v��̂ɓ��ӂ�����Љ�I�ɑ����ȍs�ׂƔF�߂��t��ꍇ�Ɉ�@�����j�p�����Ƃ��錩���i�c���Q�Q�Q�D��˂P�S�V�A���v��
�P�X�V�A���c�P�W�P�j�A�A�@�v�����R�ɏ�������Ƃ������Ȍ���̗��v���@�v�ی�̗��v�ɗD�z����Ƃ��������i�]���ЕF�w�Y�@�ɂ����鐳������
���_�x�i�P�X�W�O�N�j�P�S�X�ŁA���J�B�w��Q�҂̏����Ǝ��ȓ��Ӑ��x�i�Q�O�O�S�N�j�U�Łj������܂��B
�@���́A���ǒP�Ȃ�u�s�ז����l�v�[��Ő������܂��[�݂̂������ď������m�肷�邱�ƂɂȂ�Ó��łȂ��ł��傤�i�������s�ז����l�_�ɗ���
��J�Q�T�R�ł́A�u�@�v�N�Q�s���̌����v�ɂ��A�ʐ��̗���ɗ����܂��j
�A���́A�u���ʖ����l�v�[��Ő������܂��[�_�I���ꂩ��A�������@�v�N�Q�Ɠ��ӂɂ����������u�l�̎��R�v���t�ʂ��邱�Ƃɂ��A��@��
�j�p���������錩���ł����A�@�v�����̏����Ɋւ���u�l�̎��R�v����藣���āA�u�l�̎��R�v�Ƃ͖��W�Ȗ@�v�̕ی���Y�@�̔C����
�l���邱�Ǝ��̂Ɋ�{�I�ȋ^�₪����܂��B�@�v�����Ɋւ���u�l�̎��R�v�͖@�v�̓��e���̂��̂ł���A�@�v�ƕʕ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��ł��傤�B
�����ٖ@�w�ł����J�_���o���Ă�����H������
��J�̗��R�Â��͔����B���O���⑫���Ă݁B
���S�I�����������[���낻������̎����ł����[
���̌Y�@�w�҂Ƃ��𗬂̂���A�܂Ƃ��ȌY�@�w�҂Ȃ�4���ɕS�I�̉������邭�炢�m���Ă�͂�
�����ŕۗ����Ă������A�u�s�ז����l�v�Ɓu���ʖ����l�v�ɂ��ĐG�ꂽ���Ǝv���܂��B
�s�ז����l�iHandlungsunwert�j�_�ƌ��ʖ����l�iErfolgsunwert�j�_�̑Η��́A���F���c�F�����A����܂ł̃��X�g���x�[�����O�̌n�Ɂu���ʖ����l�_�v�Ƃ���
���x����\��A�����ᔻ�������ƂɎn�܂�܂��B
�킪���ł́A���a�S�O�N��̌Y�@����������_���̒��ŁA�Η��������m�����Ă����܂����B
�@��{�I�ɌY�@�`�������ێ�������̂Ƒ�����̂��A�A�����̋�̓I�ȗ��v��N�Q����s�ׂ��������邾���ɂƂǂ߂�ׂ����̑����ł��B
�@�O�ҁi�s�ז����l�_�j���\����̂��c���d�����m�i�P�X�P�R�|�Q�O�P�Q�j�A�A��ҁi���ʖ����l�_�j���\����̂����열�ꔎ�m�i�P�X�Q�O�|�Q�O�O�S�j�ł��B
�ȒP�ɉ]���܂��ƁA�@��@���̖{�����K�͈ᔽ�́u�s�ׁv�ɋ��߂�̂��A�A�@�v�N�Q�́u���ʁv�ɋ��߂�̂��̑Η��ł��B
�u�s�ז����l�_�v�́A�s�҂̓����I�E��ϓI�Ȉӎv�̕������A�K�͈ᔽ�Ɍ������Ă��邱�Ƃ���@�̖{���ł���Ƃ��܂��B
�u���ʖ����l�_�v�́A�O���I�E�q�ϓI�Ȗ@�v�N�Q�̑��݁A�܂��@�ȏ�Ԃ̔�������@�ł���Ƃ��܂��B
�������āA�u�s�ז����l�_�v����́A�s�҂̎�ςȂ����ӎv����@���̔��f�ɂƂ��ďd�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B
�������A�u���ʖ����l�_�v����́A���ʂ̔������̂��̂Ȃ������̊댯���q�ϓI�ɑ��݂��邱�Ƃ��A��@�����f�ɂƂ��ďd�v�ł���A�s�҂̈ӎv�͏d�v�łȂ����ƂɂȂ�܂��B
�h�C�c�ł́A���̂悤�ȍs�ז����l�ꌳ�_���ʐ��ł����O�h�C�c�ł͕s�\�Ƃ���������܂��[�킪���Ŏ咣����Ă���s�ז����l�_�́A�s�ז����l�����ʖ����l���K�v���Ƃ�����@�_�ł��i��˂R�U�W�A��J�Q�R�V�A��c�W�P�j
�������A���̌��O�Ǝ��ۂ̋A�����������Ă��邩�^��Ȃ��Ƃ��܂���B���ʖ����l�����@���Ă��Ă��s�ז����l�����ŏ�������ׂ����Ǝ咣�����ʂ���������ł��B
�Ȃ��A��J�R�X�ł́A�s�ז����l�_���Љ�ϗ���`�A���ʖ����l�_���@�v�ی��`�Ƃ����}������Ă��܂����A�u�ƍ߂Ƃ͖@�v��N�Q���A�܂��͋������s�ׂ̂��Ƃł���v�Ɩ��������c���i�P�T�Łj�̏o���ŁA���̐}���͕��ꋎ��܂����B
�{��ɖ߂�܂��B
>>�u�ƍ߂Ƃ͖@�v��N�Q���A�܂��͋������s�ׂ̂��Ƃł���v�Ɩ��������c���i�P�T�Łj�̏o���ŁA���̐}���͕��ꋎ��܂����B
���̕��͂͒��쌠�͂Q�����˂�ɂȂ�炵���̂ň��p�����Ă��炤�ˁB
��c�̐��������邩��A��J�̎咣�������Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ���ˁB
�N�̓����Ȃ舫���ˁB���쎩�����Ă���ꍇ���H��
�����̐�啪��ȊO������ˁB�Ђ��炩���Ă���Ȃ��B
�u�N���v�ƋK�肷��Z���N���߁i�P�R�O���j�A�u�ގ�v�ƋK�肷��ޓ��߁i�Q�R�T���j�Ȃǂł́A�\���v�����̂�������̈ӎv�ɔ����邱�Ƃ��܈ӂ��Ă��܂�����A���ӂ́A�\���v���Y������r�����邱�Ƃ͖��炩�ł��B
�t�ɁA�u�l���E�����v�ƋK�肷��E�l�߁i�P�X�X���j�ɂ��ẮA�u�����ĎE�����v�ƋK�肷�铯�ӎE�l�߁i�Q�O�Q���j�Ƃ�������K�肪����܂��B
�ł́A���̂悤�Ȑ���K��̂Ȃ��u�l�̐g�̂����Q�����v�ƋK�肷�鏝�Q�߁i�Q�O�S���j�ɂ��ẮA�L���ȓ��ӂ��������ꍇ�A�ƍ߂̐����͔ے肳���̂ł��傤���A����Ƃ��ƍ߂̐�����F�ߓ���̂ł��傤���B
�i�P�j���@��
�ł́AF����A�y�S�I�Q�Q�����z�́q�����̊T�v�z�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������E
�L��������܂����B�]�k�ł����A�q����v�|�r�̉����g�����u�����v�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A��@��̍ٔ����͒c�����m�ł��������Ƃ�������܂��B
���̌���ɂ��ẮA���s�@��s���ȍ��\�߂̗\��������̂��Ƃ����������ᔻ������܂��i���ɁA�퍐�l��͍��\�߂ŗL�ߔ������Ă��܂��j
���ɁAG����A�z�z�������W�����́y����P�S�z�i���n�ِΊ��x�����a�U�Q�N�Q���P�W���j��ǂ�ł��������B
�q�����̊T�v�r
X�i���N�U�̎q���r���AA�i�e���j����s�`���̂����߂�����悤�ɉ]���Ďw���߂邱�Ƃ����ӂ���B�i�ᓪ�j�̏��w�̍�����ނ莅�Ŕ����Ď~�����A�o�n��ċ��ƂŒ@���Ă��̏��w�̖��߂�ؒf�����B
�q���@�|�j
B�̏������������Ƃ��Ă��AX�̍s�ׂ́A�y�����Ǒ��ɔ�����z�Ƃ��������悤�̂Ȃ��w�߂ɂ��������̂ł���A���̕��@����w�I�Ȓm���ɗ��t�����ꂽ���œ��K�ȑ[�u���u���������ōs��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A
�S����Ŗ��c�ȕ��@�ł���A���̂悤�ȑԗl�̍s�ׂ��y�Љ�I�ɑ����ȁz�s�ׂƂ��Ĉ�@����������Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i���Q�ߐ����j
�i�Q�j�w�@��
�w���́A�傫���S�ɕ�����܂��B
�@��Q�҂̓��ӂ́A�y�Љ�I�������z�f�����v�f�ɂ������A�Љ�I�������������ꍇ�ɂ͈�@�j�p���ے肳���Ƃ��錩���i��˂S�Q�P�A���c�P�V�X�A���v�ԂP�V�X�j
�A�����Ƃ��Ĉ�@�����j�p����邪�A�d��ȏ��Q�ɂ��Ă͈�@�j�p���ے肳���Ƃ��錩��
�B�����Ƃ��Ĉ�@�����j�p����邪�A�����Ɋ댯�̂��鏝�Q�̏ꍇ�ɂ͈�@�j�p���ے肳���Ƃ��錩��
�i�A�ƇB�́A�Ƃ��ɋ�ʂȂ��咣����邱�Ƃ�����B����Q�T�S�A�����T�W�W�A�R���P�U�Q�A���c�P�W�X�A�R���Q�O�T�j
�C��Q�҂̓��ӂ�����A��ɏ��Q�߂̐������ے肳���Ƃ��錩���i�O�c�R�S�W�A��c�Q�O�U�j
�y�����z�@�����A�Љ�I�������̓��e�Ƃ��āA���Q�߂̖@�v�ł���g�̈ȊO�̗��v���l������̂ł���B�Ó��ł͂���܂���B�C���͖����ł����A�ǂ̂悤�ȏ��Q��^���Ă��A�ɒ[�ɉ]���A��Q�҂�A�����
�ɂ��Ă��܂��Ă��A���Q�߂����������s���ɂȂ��Ă��܂��Ƃ������_�͎����Ǝv���܂��B
���������āA���́A�A���Ȃ����B�����x�����܂��B�@
��J�Y�@�݂������Ȃ�����
�i�P)���@��
H����A���W�����́y����P�T�z�i���a�R�R�N�P�P���Q�P���j��ǂ�ł��������B
�q�����̊T�v�r
X���A�S����\���o��A�ɑ��A���̈ӎv���Ȃ��̂ɒǎ�����悤�ɑ����Đ_�\�[�_�����܂��Ď��S�������B
�q���@�|�r
A��X�̋\㦂̋\㦂̌���X�̒ǎ���\�����Ď������ӂ������̂ł���A���̌��ӂ͐^�ӂɓY��Ȃ��d������r����ӎv�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�����Ă��̂悤��X�ɒǎ��̈ӎv���Ȃ��ɍS�炸A���\㦂�X�̒ǎ�����M�����Ď��E������X�̏��ׂ͒ʏ�̎E�l�߂ɊY������B
�i�Q�j�w�@��
�@�{���I�����
�{���I�����ɂ��č��낪����A����������Ɋׂ��Ă��Ȃ�������Γ��ӂ��Ȃ������ł��낤�Ƃ����ꍇ�A���Ȃ킿�A���̓��ӂ��^�ӂɓY��Ȃ�
�ꍇ�ɂ́A���ς͖����ł���Ƃ�����ł��i��˂S�Q�P�A��c�R�Q�S�j
�A�@�v�W�I�����
���Ԃ����܂����̂Łu�@�v�W�I������v�͎���ɂ��܂��B
>�u�ƍ߂Ƃ͖@�v��N�Q���A�܂��͋������s�ׂ̂��Ƃł���v�Ɩ��������c���i�P�T�Łj�̏o���ŁA���̐}���͕��ꋎ��܂����B
�쑺�������l�̂��Ƃ������Ă��Ȃ�������
���Ⴀ�N�̃p�N�����ˁB���p�Ȃ��ŁA����_������B
�����̗p��Ŏ����ꂽ�T�O�y�шӖ����e�Ƃ����ɌW�鎖���A�ٔ����̑��̕����Ȃ��������ƂɌW��@�����f�y�ь��_�Ⴕ���͌��ʂ́A�ŏI�I�ɁA�Ⴆ�ō��ٔ����A�ō��ٔ����y�эō��ٔ������^���܂��B
�ȂˁA�S�����Ă�l���ĕ������銴��������B
�O�̎��c�Ƃ̐l�Ƃ͕ʐl������B
�����킳�����悤�Ȃ���Ȃ̂��ȁH
����A�����C�ɋ��Ȃ��̂��A�w�҂��ۂ��H�R�e�����X�����
�قƂ�Njc�_����ł��Ȃ��A���쌠�����Ƃ����ꂾ����w�҂͂��Ƃ�
���肾���l�̂��ƁB
���X���݂Ă��A�w��̎i��ǂ��̂����̌����Ă邩��
�Q�����˂�ɌY�@�w�҂̕����������݂��ɗ��Ă��邱�Ƃ�
���炩���낤�Ȃ�
�ŋ߂̗L�͂Ȍ����́i����Ƃ��āA�R���h��u��Q�҂̓��ӂɂ�����ӎv�̌�&#32572;�v����w�@�w�_�W�R�R���R���S���T���i�P�X�W�R�N�j�Q�V�P�ňȉ��A
�����m�u�u��Q�҂̍���ɂ��āv�_�ˑ�w�N��P���i�P�X�W�T�N�j�T�P�ňȉ��j�A�\㦂ɂ���ē���ꂽ���ӂ́A���ꂪ�u�@�v�W�I����v�Ɋ�Â�
�ꍇ�����A�����ł���Ƃ��Ă��܂��B���̌����ɂ��A�y����P�T�z�ł́A���Ȃ̐����̐N�Q�Ƃ����_�ɍ��낪�Ȃ��ȏ�A�L���ȓ��ӂ͂���������
�ɂȂ�A�E�l�߂͐������Ȃ����ƂɂȂ�܂��i�����������E�֗^�߁j
�y����P�U�z
����������x���ē������邱�Ƃ̓��ӂāA�������ɂ�������炸�A����Ȃ������B
���̎���ɂ����ẮA�g�̂ɑ���L�`�͂̍s�g�Ƃ����\�s�߂ɂ�����@�v�N�Q�̓_�ɂ����Ă͍��낪�Ȃ������ȏ�A�������炦�Ȃ�����Ƃ����āA�\�s��
���������邱�Ƃɂ͂Ȃ�܂���B�����������\�߂̐��������ɂȂ�ɂƂǂ܂�܂��B
�ł́A���̂悤�Ȏ���ł͂ǂ��ł��傤���B
�y����P�V�z�i�ً}��ԂɊւ������j
�����̉Ƃ����サ�Ă���Ƃ��ɁA�ʍs�l�ɑ��āA�����ƉΏ��̊댯������ɂ�������炸�A���ɍȂ������߂��Ă���̂Ńh�A���J����̂���`����
�ق����Ɨ��݁A����ɉ������ʍs�l������ɂ���ĉΏ��������A���ۂ͒��ɂ͎q�������������ł������B
���̎���ɂ��ẮA�R�������́A�u�@�v�W�I����v���Ȃ��ɂ�������炸�A���ӂ��Ƃ��錩�����咣���Ă��܂����i�R���E�O�o�R�S�T�Łj
���̍����́u���ӎ҂��D�z����@�v�ɔ���N�Q�̋�������댯������ƍ��낵�Ď���̖@�v�̕��������ӂ����悤�ȏꍇ�ɂ́A���̌��ӂ͉��l�I�Ɏ��R�ɂȂ��ꂽ
�Ƃ͌������Ȃ��̂ł���A���ӂ͖����Ƃ��ׂ��ł���v�Ƃ������̂ł��B
�i�R�j��̌���
�܂��A�����{���I��������̂�A���낪�Ȃ������瓯�ӂ��Ȃ���Ȃ������ł��낤�Ƃ����ꍇ�ɂ́A���̍���͖����ł���Ƃ��������͑Ó��łȂ��Ǝv���܂��B
�@�v�W�I��������ᔻ����悤�ɁA���Y�̖@�v�N�Q�ɂ��Đ������F���������A����ɑ��ē��ӂ��Ă���ꍇ�ɂ́A�N�Q�̑ΏۂƂȂ�@�v�̖@�v���͎���ꂽ
�ƍl���邱�Ƃ��ł��邩��ł��B���Y�@�v�Ɩ��W�Ȏ���ɂ��Ă̋\㦁E����ɂ�蓯�ӂ��Ƃ��ď�������̂ł́A���ƂȂ�ƍ߂��A���Y�@�v�Ɩ��W��
�\㦂��������邽�߂ɓ]�p����邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�@�y�����z
���̈Ӗ��ŁA�@�v�W�I���������{�I�ɑÓ��ł���Ǝv���܂��B
���Y�̖@�v�N�Q�𐳂����F�������A���R�Ȉӎv�ɂ�铯�ӂ̑��݂ɂ���Ĉ�@���͑j�p�����Ɖ�����܂��B
����́A���̌���ɂ����āA�@�v�N�Q�͖@�v��̂̈ӎv�ɍ��v���Ă���̂ł���A�@�v�N�Q�����ے肳��A
�Y�@���ی삷��K�v�����F�߂��Ȃ�����ł��B���Y�@�v�ɊW���Ȃ�����ɂ��Ă̋\㦂́A�ꍇ�ɂ����
���̔ƍ߂̐��ۂ���ɂ�����ɂ����Ȃ��ƍl�����܂��B
�y����P�W�z
�����̎����Ă���ҏb�������o���Đl�Ɋ�Q�������Ă���Ɠd�b���x����A�����R���Ƃɓ��ӂ�^�����B
�y����P�X�z
�K�@�ȑ{���ߏ���āA�U�̗ߏ�������āA���l�̉Ƃɗ����������B
������ɂ��ẮA�@�v�W�I�����������L���ȓ��ӂ�ے肷�邱�Ƃ͉\�ł��B
����́A�����̏ꍇ�ɂ́A�\㦂ɌW�鎖���������ɑ��݂��Ă����Ƃ���A�@�v��̂̓��ӂɂ�����炸�A
���Ȃ킿���ӂ��Ȃ��Ă��A�ҏb�̎E�Q��Ƃւ̗�������́A���ꂼ��ً}���Ȃ��������h�q�i����P�W�j�A�@�ߍs��
�i����P�X�j�Ƃ��Ĉ�@�����j�p����邩��ł��B���̈Ӗ��ŁA�@�v��͖̂@�v�N�Q���Î�ł�������䓾�Ȃ������
����A�@�v�̗v�ی쐫�����̌��x�Ŕ۔F����܂��B
���̂悤�Ȏ���ɂ��Ă̋\㦁E����́A�ی삳���ׂ��@�v�̗v�ی쐫�Ɋւ���\㦁E����ł���܂�����A������
�u�@�v�W�I����v�Ɖ]��������̂ł���A���̌���ɂ����āA�L���ȓ��ӂ̑��݂�ے肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
�������āA�@�v�W�I���낪�Ó��ł���Ɖ]�����Ƃ��ł��܂��B
�ȏ�ő�S�u[��Q�҂̓���]���I���܂��B
�@�v�W�I����͏������������������܂���B�����̂�����͍����搶�̋��ȏ���ǂ�ł݂Ă��������B
�u����I���Ӂv�́A���Ԃ̊W��A�ȗ����܂��B�e���A�����ɋ��ȏ��ŕ����Ă����Ă��������B
����́A���悢����ʊW�_�ł��E
�����A���̎��_�œ��ӎ҂̓��@�܂œ����Ă܂���ˁB����������鍪���Ɏ��B
���̑��̗p��ŕ\��������ȏ�̊T�O�y�шӖ����e�ɂ��āA���m����̓I�ɁA���������Ă��܂����B
�Ⴆ�u�@�v�v�u�{���I�v�u����v�u���ʊW�v�u����v�u����I�v�u���Ӂv���̑��̗p��Ŏ����ꂽ�T�O�y�шӖ����e��
�����ɌW�鎖���A�ٔ����̑��̕����Ȃ��������ƂɌW��@�����f�y�ь��_�Ⴕ���͌��ʂ́A�ŏI�I�ɁA�Ⴆ�ō��ٔ����A�ō��ٔ����y�эō��ٔ������^���܂��B
�����牽�ł��\�_�������ȁB���@�͓��@�A����͍���B���{��̈Ӗ���
�����`�ʼn��߂����ׂ�����ȁB���ق���
�Ȃ��̔S���L�`�K�C�͌����F�e����Ƃ�R
�����Ƃ��A�����̗p�ꖔ�͕������L����ʏ�̈Ӗ����e�i�Ⴆ�u�L�����@��ܔŁv�Ɏ������Ӗ����e�j�ƁA�@�̉��ߓK�p�Ɋ�Â��p�ꖔ�͕����̈Ӗ����e�Ƃ��A���Ȃ��Ƃ������l����ƂƂ��ɁA
>>627�͋�̓I�Ȏ����W�Ȃ������O��ɂ����āA�����̗Ⴆ�u�@�v�v�u�{���I�v�u����v�u���ʊW�v�u����v�u����I�v�u���Ӂv ���̑��̗p��ŕ\��������ȏ�̊T�O�y�шӖ����e��
�����ɌW�鎖���A�ٔ����̑��̕����Ȃ��������ƂɌW��@�����f�y�ь��_�Ⴕ���͌��ʂɂ����āA�����A���m����̓I�ɁA�ō��ٔ����A�ō��ٔ����y�эō��ٔ����́A���ꂼ�ꎦ���Ă��܂����B
>>627�͑�O��y�ы�̓I�Ȏ����W�Ⴕ���͏��O����тɘ_������y�і@�̉��ߓK�p�ɂ����āA�����̗Ⴆ�u�@�v�v�u�{���I�v�u����v�u���ʊW�v�u����v�u����I�v�u���Ӂv ���̑��̗p��ŕ\��������ȏ�̊T�O�y�шӖ����e��
�����ɌW�鎖���A�ٔ����̑��̕����Ȃ��������ƂɌW��@�����f�y�ь��_�Ⴕ���͌��ʂɂ����āA�����A���m����̓I�ɁA�ō��ٔ����A�ō��ٔ����y�эō��ٔ����́A���ꂼ�ꎦ���Ă��܂���
�����p���OK�A���{��ɂ������������C�����Ă����B
�����ԓ����邩�͕ʂ����ǁA�N�������������B
��ʐl���p������{��̓���p���ƁA�@���Ɓi���ɓI�ɂ͍ō��فj�̗p������p���̈Ⴂ
�ɂ��Ď��₳��Ă����ł��傤���H
�Y�@��̈��ʊW�Ƃ́A�s�ׂƌ��ʂƂ̊ԂɕK�v�Ƃ����u�����[���ʁv�̊W���]���܂��B
���̈��ʊW�����݂��Ȃ���A�����Ƃ͐��������A�����Ə����K�肪�������Ŗ����Ɓi�S�R���j�ƂȂ�܂��B
���ʊW�̔��f�́A�@�����W�A�A�q�ϓI�A���̂Q�i�K�ōs���܂��B
�P�@����I���������ƍ��@���I��������
�����W�Ƃ́A���̐�s�������Ȃ�������A���̌�s�����͂Ȃ������ł��낤�A�܂�u���̍s�ׂ��Ȃ������Ȃ�A���ʂ͔������Ȃ������ł��낤�v
�Ƃ����W�ł��iconditio sine qua non Formel�j�B����u����I�����@�v�ł���A�u����I���������v�i�R���f�B�`�I�����j�Ƃ��Ă�܂��B
�������A���̂悤�Ɂu�`�Ȃ���a�Ȃ��v�Ƃ�������I�����@�Ƃ��Ă̏��������́A���ʖ@����O��Ƃ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�Ȃ��Ȃ�A
�������͂����čl����ꍇ�ɐ����錋�ʂ́A�l���O�����Ă��̏����������ł��邱�Ƃ�m���Ă���ꍇ�ɂ̂݊m���߂��邩��ł��B
���������āA���������Ƃ��ẮA���Y�s�ׂ����@���I�W�Ɋ�Â��āA��̓I���ʂɎ��ۂɎ����������ۂ����A��ʓI�E���I�Ȍo���ɂ���Ĕ��f����
�u���@���I���������v�iFormel von der gesetzmasigen Bedingung�j���Ó����Ǝv���܂��B�u���@���I���������v�Ƃ́u����s�ׂɎ��ԓI�Ɍ㑱����O�E��
������ω����A���m�̎��R�@���Ɋ�Â��Ă��̍s�ׂƕK�R�I�Ɍ������Ă���A�\���v���Y�����ʂƂ��Ď�����邩�ۂ��v�Ƃ������f�����ł��i�C�F�V�F�b�N�j
���̖@�����̒��ɂ́A���R�@���݂̂Ȃ炸�A�o���@�����܂܂�܂��B
���@���I���������̒҂̓G���M�b�V���ł���A�킪���ł�����x��������̂Ƃ��āA���{���u�w���ۓI��w�Ɓx�̖�萫�v�@�w�R�W���Q���i�P�W�V�S�N�j�Q�X�ŁA
�їz��w�Y�@�ɂ�������ʊW�̗��_�x�i�Q�O�O�O�N�j�V�Q�ŁE�Q�S�Q�ŁA�R���Q�T�X�ŁA���ь����Y�w���ʊW�Ƌq�ϓI�A���x�i�Q�O�O�R�N�j�P�X�P�ŁA���c�X�P�ŁA
�����K�T�u�����W�ɂ��āv���Ê�P�Q�U�ŁA�k��ʐ��u�����W�̈Ӌ`�v���c���Ê�P�P�X�ŁA�����P�P�S�ŁB
�u����I�����v�Ɓu����I���ʌo�߁v�ɂ��ẮA�e���A�����̋��ȏ��ŕ����Ă����Ă��������B
�Ƃ��ɁA����I�����́u�ꊇ�������v�Ɖ���I���ʌo�߂́u�t�������֎~���v�̖�萫���ӎ����Ă��������B
�Q�@�_���I�������E���ʉ���\����
���̌����́A���ʊW�͎����W�ł͂Ȃ��Ƃ��āA�����܂ʼn���I�E�_���I�Ȍ����W�ł���Ƃ݂܂��i�����w�ƍߘ_�̓W�J�T�x�i�P�X�W�X�N�j�P�S�V�ŁA
�R�����u���ʊW�_�v�w�Y�@���_�̌���I�W�J���_[�P]�x�i�P�X�W�W�N�j�S�W�Łj
���̌����́A����I�����@�̌����ɓƎ��̈Ӌ`��F�߁A�s�ׂ��Ȃ��Ă����ʂ��ˑR�Ƃ��Ĕ������Ă����ł��낤�Ƃ����ꍇ�ɂ́A���Y���ʂ͉��s�\�ł������̂ł���A
���̂悤�ȍs�ׂ��������Ă��A�����ɂ�����@�v�N�Q�̗}�~�Ƃ����Y���ړI�̊ϓ_���珈���𐳓����ł��Ȃ��Ƃ��܂��B�܂�A���̌����̊�b�ɂ���̂́A��ʗ\�h�ł��B
���̌����́A�u���ʉ���\���v���Ȃ��ꍇ�ɂ͏�����ے肷��Ƃ������̂ł����A���ʉ���\���̔��f�������ɍs�����Ƃ�������Ȗ�肪������݂̂Ȃ炸�i���ɁA�_��
�̒��ł�������������Ă��܂��j�A�����W�ƌ��ʉ���\���Ƃl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ]���ׂ��ł��傤�B���̌�������́A����I�����̎���ɂ��Ă��A����I���ʊW
�̎���ɂ��Ă��A���ʊW���ے肳��܂��B
����Ƃ�����I�Ȃ��̂ł���̂��A�ɂ��Đ������ׂ����낤�B
���ۂɍ��ق��o��̂́A����I�����Ȃǂ̃��A�P�[�X�݂̂��낤����B
�P�@�������ʊW��
�i�P�j�͂��߂�
�����W�����ŌY�@��̈��ʊW���f�͐s����ƍl���錩�����u�������v�Ɖ]���܂��i�ē�����P�O�Q�A�����W�P�A����U�O�j
����ɑ��āA�킪���ŗL�͂ƂȂ����̂́u�������ʊW���v�ł��B�������ʊW���́A���Ԃ���ʓI�Ɋώ@���āA��ʐl�̌o������̐�s���������݂���ꍇ�ɂ́A
���̌�s��������������̂��ʏ킾�ƍl����ꍇ�ɁA�Y�@��̈��ʊW��F�߂錩���ł��B
�i�Q�j�u�������v�̒��x
�u�������ۂ��v�Ƃ������f���̂͋ɂ߂ăt�@�W�[�ł����A���ʂ̔������u�ُ�v�u���悻�H�L�v�u����߂ċ��R�I�v�ł���ꍇ�Ɉ��ʊW���ے肳���Ƃ��܂��B
�i�u�o����ʏ�ł���v�c���P�V�S�A�u����߂ċ��R�I�Ȃ��̂������v����P�S�Q�j
�i�R�j���������f�̍\��
�������ʊW���ɂ��A�s�ׂƌ��ʂƂ̊Ԃɑ������ʊW������Ɖ]���邽�߂ɂ́A�@�s���̂ƁA�A�s�ׂ��猋�ʂɎ�����ʌo�߂̑������̑o���ɂ���
���������F�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���܂��B
�@�u�s�ׂ̑������v�́A�s�ׂ̌��ʂɑ���댯�������O���f���邱�Ƃɂ���Ċm�F����܂��L�`�̑������j�B�u�L�`�̑������v�́A���s�s�ה��f�Əd�Ȃ�ꍇ�������Ƃ���܂��B
�A�u���ʌo�߂̑������v�́A�s�ׂ̊댯������̓I�Ȉ��ʌo�߂�ʂ��Č��ʂ֎����������ǂ����Ƃ����댯�̎����̔��f�Ɉˋ����Ă��܂��i���`�̑������j
�y����Q�O�z
���ŏf����R�����Ǝv���āA�f����X�ɍs�������Ƃ���A�{���ɗ��������ďf�������S�����B
���̏ꍇ�A�X�ɍs������s�ׂɂ͏f���̎��ɑ���댯���͂Ȃ��A�L�`�̑����������@����̂ŁA�E�l�����ɂ��Ȃ�܂���B
�������A���̂悤�ȑ��������f�̍\���́A��ŏq�ׂ�q�ϓI�A���_�Ɏ��ʂ���邱�ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�@�L�`�̑������́A�u�����ꂴ��댯�̑n�o�v�̖��ł���A
���O���f�ɂ����s�s�א��̖��ł���A�A���`�̑������́A�u�댯�̎����v�̖��ł���A���㔻�f�ɂ����ʊW�̖��Ɉʒu�Â����܂��B
�i�S�j���f���̖��
��ϐ��A�q�ϐ��A�ܒ����̑����́A���ł͒��������c�_�ł��̂ŁA�ȗ����܂��B�e���̋��ȏ��Ŋm�F���Ă����Ă��������B
�Q�@�������ʊW���̖��_�[�u�������ʊW���̊�@�v
�i�P�j�͂��߂�
����̗���ɂ��ẮA��{�I�ɏ������ł���Ƃ��A�������ł���Ƃ��A����ɂ́A�q�ϓI�A���_�ł���Ƃ����_�҂����܂����A����E�������A�������ʊW�����̗p
������̂ł͂Ȃ����Ƃ����͖��炩�ł��B
����E�������������ʊW�����̗p�ł��Ȃ��̂́A�Ƃ��Ɂu�s��̎���ɂ��Ă̔��f�\�����s���m�ł���v�Ƃ����_�ɂ���܂��B
�i�Q�j�s��̎���
�s��̎���A���Ȃ킿�A��ݎ���ɂ��ẮA�ܒ������q�ϐ����A�s�����玖���\������Ƃ������f���s�����Ƃł͈�v���Ă���A�������ʊW���ɂ����Ă�
��ݎ���ɑ���\���\���̗L�������ƂȂ�A��ݎ���ُ̈퐫�ɂ���Ĕ��f�����E����邱�ƂɂȂ�܂��B��ݎ���ُ�ł���A���f���Ɏ�荞�܂Ȃ�
���ʂƂȂ�܂����A���̌�̔��f�̍\���͕K���������炩�łȂ��̂ł��B���Ȃ킿�A���f���Ɏ�荞�܂�Ȃ��ꍇ�A�s���̊댯���݂̂ň��ʊW�����f�����
���܂��̂ł��B���f���Ɏ�荞�܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���̎����͑��݂��Ȃ����̂Ƃ��đ��������f���s���Ƃ������Ƃł���A����́A����E�����ɂƂ��č̗p
�����Ȃ��_�ł��傤�B
����𖾂炩�ɂ����̂��A����`�����Ɩ�Ԑ����P�������ł����A���Ԃ����܂����̂Ŏ���ɂ��܂��B
�����m�u�����́A�������ʊW�ɂ����Ēm���Ă����ׂ������̃��x���Ƃ��āA
��ꃌ�x���Ƃ��āA�������ʊW�̋q�ϐ��Ɛܒ����Ȃ����u�s�ׂ̊댯�̌������v
�̔��f�g�g�݂𗝉����āA��\�I�Ȏ���Ɂi������͖������āj�ꉞ���Ă͂߂�
���Ƃ��ł���B
���Ƃ������Ă�����i�����w�Y�@���_�̍l�����E�y���ݕ��x79�Łj�B
���u���@���I���������v�Ƃ́u����s�ׂɎ��ԓI�Ɍ㑱����O�E��
��������ω����A���m�̎��R�@���Ɋ�Â��Ă��̍s�ׂƕK�R�I�Ɍ������Ă���A�\���v���Y�����ʂƂ��Ď�����邩�ۂ��v�Ƃ������f����
�����Ȃ肱��Ȃ��ƌ����Ă��w���̓`���v���J���v�����낗
�����B
�����̑��c������
���@���I���������́A�O�������_�i�\���I���_�A�������猋�ʂւ̐��_�j�ł���A
�K�v���������́A���������_�i��ړI���_�A���ʂ��猴���ւ̐��_�j�ł���Ƃ���Ă����ˁB
�������A�Y�@���ȁB�V�˂ƃA�z�̏W���̂�����ȁB
��ɉ����i�ނ̂������͂Ȃ��B
���O�݂����ȓ����͂������Ɛ��_�Ȃɓ��@�����
���O�͖ϑz�Ɏ���������ʼn����g�̂��邱�Ƃ�����Ȃ���
�R���⍂���̌������J�ɑ���ᔻ�Ȃǂ́A�����܂ł܂����o����Ȃ�����Ȃ�
�p�N���邩���Ȃ�����
���n���q�炵�����ǁA��͂蕶�n���q�̎���͏I������ȁB�ςȂ̂��������B
�������ȁH
�_�C�r���O���ɑD�Ƃ͂������Ĉ�Ԋ댯����Ȃ��B
�L����T���ēǂ�ŗ~�������ǁA�_�C�o�[���������ʂɏo�������ӂ�
���Ȃ������ߎ��ɂ��Ɩ���ߎ��v���e�^�őߕ߁A�Ƃ���
����s��ׂɂ��ߎ��Ƃ���Ȃ��́H�������邩�H
�ߎ��̋��������ƂȂ邯��ǂ��A�C��̃_�C�r���O�ɂ����āA�D�Ƃ͂���邱�Ƃ͍ő�̊댯������A
�D���̉ߎ��͓��R�����������Ȃ����ȁB
�D�̕��ł͊C���̃_�C�o�[�̈ʒu���c�����Ă����Ȃ́HGPS�Ƃ���
�c�����ĂȂ��Ȃ琅�ʂɏo���_�C�o�[�̎��ӂɋ��Ȃ��������N�\��
�Ȃ��Ǝv����
����͑D�͒�~���Ă��ă_�C�o�[���s���ċA���Ă�����Ǝv���Ă�
��������_�C�r���O�������ƂȂ����ǁA
�D���_�C�o�[�̂ǂ��炩���g�ŗ����ꂽ�낤�B
�s�ލ������Ǝv����
�C���X�g���N�^�[�͖S���Ȃ����������F�������Ă�����H
�C���X�g���N�^�[2�l�͎�u���ƈꏏ�ɊC�ɐ����Ă����Ǝv����B
���Ƃ�����A�����҂��Ď����ׂ��Ȃ̂͑D���݂̂ɂȂ��Ȃ����ȁH
�ł����ڂɊĎ����ׂ��Ȃ̂̓C���X�g���N�^�[���낤��
�C���X�g���N�^�[��1���S���Ȃ��Ă�ł���B
���ꂪ�s�\�Ȗ{���ɂ����ẮA�D���������҂̐�����������r���I�n�ʂɂ�����
�Ƃ������Ƃ���ˁB
�D�̏ォ��C���̃_�C�o�[�����̐�����r���I�Ɉ�����Ȃ�ĂȂ�
����͒P�Ȃ錋�ʐӔC�̌�������
���Ȃ��Ȃ��Ȃ����H�ߕ߂��炳���ׂ�����Ȃ������Ǝv��
�O��̑����ł��B
I����A�y�S�I�P�T�����z�i�����Q�N�P�P���Q�O���F����`�����j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�O�c�����͖{������x�����闧��i�q�ϓI�������ʊW���j����A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�O�c�Q�O�O�Łj
�@�@�i�C�j���ʊ�ɂ�鉣�łɂ�莀���ƂȂ�ɏ\���Ȕ]���̏o���������A�p�ނɂ��\�s�͊����������𑁂߂�e����^������
�@�@�@�Ƃǂ܂�Ƃ̌��R�̔F���O��Ƃ������A�퍐�l�̍s�ׂɑ����錋�ʔ����̊m���͑傫���A�i���j�`�̎��ޒu��Ɉӎ���
�@�@�@�����ĕ��u���ꂽ�҂ɂ���Ȃ��Q����������\�����Ȃ��Ƃ͂������A�i�n�j��ݎ���̌��ʂւ̊�^����ΓI�Ȃ���
�@�@�@�Ƃ܂ł͂����Ȃ��̂ŁA���ʊW��F�߂����f�́A�s�����ł͂Ȃ��Ǝv����B
����ɑ��āA���������́A�������ʊW����ᔻ���闧�ꂩ��A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�����P�Q�T�Łj
�@�@�@�������ʊW���̔��f�g�g�݂ɂ��Ȃ�A��O�҂ɂ��̈ӂ̖\�s�̉���ُ͈�Ȏ��ԂƂ��킴����A���߂�ꂽ���S
�@�@�@�Ƃ̊W�ł͈��ʊW��ے肷�邱�ƂɂȂ�̂��A���邢�́A��P�\�s�ɂ���Ēv�������������Ă��邱�Ƃ���A��������
�@�@�@�W���m�肷��̂��͖��炩�ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�@�@���̂悤�ɁA�������ʊW���́A��̓I�ȉ�ݎ���f��ꂩ�珜������A���ʌo�߂���ь��ʔ����̑ԗl���ǂ̒��x�܂�
�@�@�u���ۉ��v����̂��A�o���I�ʏ퐫���ǂ̂悤�ɔ��f����̂��Ƃ����_�ɂ��āA����߂ĕs���m�Ȃ̂ł���B
���X�����́q����r�������ēǂ�ł݂Ă��������B
���ɁAJ����A�y�S�I�P�R�����z�i�����S�N�P�Q���P�V���F��Ԑ����P�������j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�{����ɂ��āA�O�c�����́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�O�c�Q�O�T�Łj
�@�@�@��Q�ғ��̕s�K�ȑΉ�����ʓI�ɍl��������̂ł���A��ݎ���ُ̈퐫���������A�������퍐�l�̍s�ׂ���U�����ꂽ
�@�@�@���̂ł���ȏ�A�A�ӂ͔F�߂��悤�B
�܂��A���������́A�������ʊW����ᔻ���闧�ꂩ��A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i�����P�Q�U�Łj
�@�@�@�ō��ق́A�b�̉ߎ��s�ׂƎ��S���ʂƂ̊Ԃɑ�O�҂���є�Q�҂̕s�K�ȍs������݂������Ƃɂ��āA�����̍s�ׂ����ʂ�
�@�@�@����������댯���������̂ł���A�܂��A��݂����ߎ��s�ׂ��A�퍐�l����u�U���v���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ���
�@�@�@���ʊW���F�߂���Ɣ��������i�Ɩ���ߎ��v���߁j�B���̏ꍇ�ɁA��ݎ���\���\�ł��������ۂ��Ƃ����������ʊW��
�@�@�@�̔��f�g�g�݂͍̗p����Ă��Ȃ��̂ł���B
�R�@�q�ϓI�A���_
�i�P�j�Ӂ@�`
�q�ϓI�A���_�Ƃ́u�s�҂ɂ���Ď�N���ꂽ���ʂ́A�s�҂������ꂴ��댯��n�o���A�댯���\���v���I���ʂ̒��Ɏ����������A
���A���̊댯���\���v���̎˒��͈͂ɂƂǂ܂������ɂ̂݁A�s�҂̂��킴�Ƃ��āA�q�ϓI�ɋA���ł���v�i���N�V���j�Ƃ���
���_�ł��B
���Ȃ킿�A���ʂ̎�N�Ƃ������ʐ����f�Ɉ��������A���ʂ̋A���Ƃ����K�͓I�E���l�I���f���s���킯�ł��B
�q�ϓI�A���_�ɂ��A�@�����ꂴ��댯�̑n�o�A�A�댯�̎����A�B�\���v���̎˒��͈́A�Ƃ������f���s���܂��B
�B�͕�����ɂ����Ǝv���܂��̂Ŏ���ōl���Ă݂܂��傤�B
�y����Q�P�z
������A��]�����Q�҂��������E�����B
�y����Q�Q�z
�\�s������ɏ��Q�킹���Ƃ���A��Q�҂����ǂ���Ɏ��E�����B
������ł́A�댯�̎������F�߂��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂����A��Q�҂̎����I�ȍs�ׁA���Ȃ킿�A��Q�҂Ɏ��ȓ��Ӑ���
�F�߂���Ƃ��āA�����߁E���Q�v���߂̍\���v���̎˒��͈͂���E���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B
�i�Q�j����ɂ�����q�ϓI�A���_
����̗���́A�댯�̎����q�댯�Ƃ��̌������j�Ƃ����q�ϓI�A���_�̘g�g�݂��̗p���Ă���ƌ��_�Â��邱�Ƃ��ł��܂��B
�u�댯�̎����i�댯�Ƃ��̌������j�v�̉��ʊ�͎��̂Ƃ���ł��B
�@�s�ׂɂ�錋�ʔ����̊댯�i���ʂɑ���e���́j�̑傫��
�A�s�ׂƉ�݂������̎���̊W�i�x�z�A���p�A�U���A�����Ȃǁj���l�����������I�댯�x�̏C��
�B�s�ׂ̊댯�̎����i�e���́j������瑼�̎���̉e���͂ɂ���ĎՒf�����Ƃ����邩�ǂ���
�ȏ�܂��āA�y�P�O�����z�i�F���������j�A�y�P�P�����z�i�������H�N�������j�A
�y�P�Q�����z�i�ĕ�瀓��������j�A�y�P�S�����z�i�g�����N�ċ֒v�������j��ǂ��
�݂Ă��������B
�ȏ�ŁA���ʊW�_���I���܂��B
���́A�s��הƘ_�ł��B
�P�@�͂��߂�
���ẮA�s��ׂ́u���v�ł���A���������u�s�ׁv�Ɖ]����̂��Ƃ��A�u������L�͐����Ȃ��v����s��ׂ̌����͔͂ے肳���Ƃ��A
����ɂ́A�s��הƏ����͍ߌY�@���`�Ɉᔽ����i���V���Y�u�s��ׂ̍\���v�L����w���o�_�p�P�T���P���S�R�ŁA���{�W�T�ŁA�Ȃ�
��c�P�S�P�Łj�Ƃ����c�_������܂������A���݂ł́A���͈̔͂ŕs��הƂ����������Ƃ������ƂŊw���̑���̈�v���݂Ă��܂��B
���͂��̗��_�\���i���������j�ł��B
�Q�@��`���̔�������
�i�P�j�`���I�O����
����܂ł̒ʐ��́A�@�@�߁A�A�_��A�B�𗝁i���K���s�s�ׁj�������Ă��܂����i��˂P�T�R�A��J�P�R�V�j
�@�Ƃ��ẮA���@�W�Q�O���Ɋ�Â��e���҂̊Ō�`���A�A�Ƃ��ẮA�q���̕ۈ���ϑ����ꂽ�ۈ�m�̕ی�`���A�B�Ƃ��ẮA�����
����������̎�����m��Ȃ����߂ɍ���Ɋׂ葹�Q���邨���ꂪ����Ƃ��́A���̎�������ɍ��m����`���A���������܂��B
�i�Q�j��s�s�א��[�����`���w�s�^���s��הƂ̗��_�x�i�P�X�V�X�N�j
�s��הƂ́A���ƂȂ�s��ȑO�ɁA�@�v�N�Q�Ɍ��������ʂ̗��������ݒ肵���ꍇ�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���̂��߂ɂ́A�̈ӁE�ߎ�
�Ɋ�Â���s�s�ׂ̑��݂��K�v�ł���A������ŏ\���ł���Ƃ��錩���ł��B
�i�R�j������̈����[�x�����O�w�s��הƘ_�x�i�P�X�V�W�N�j
�@�@�v�̈ێ�������}��s�ׁi���ʏ����s�ׁj�̊J�n
�A���̂悤�ȍs�ׂ̔����E�p����
�B�@�v�ی�ɂ��Ă̔r�����̊m��
�i�S�j�r���I�x�z�̈搫���[���c�T�V�u�s��הƘ_�v�Y�@���_�̌���I�W�J�i���_�j�T�i�P�X�X�U�N�j
��ׂƕs��ׂ̓����l����S�ۂ���v�f���A���ʂւƌ��������ʌo�߂���̓I�E�����I�Ɏx�z�����_�ɋ��߁A�s��҂́A���Ȃ̈ӎv��
�u������̔r���I�x�z�v��ݒ肵�����ƁA�܂��A���Ȃ̈ӎv�ɂ��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����㌋�ʂ��x�z����n�ʂ����������Ƃ���A���
���ׂ��Ƃ����K�͓I�v�f���l�����邱�Ƃɂ���āA��`�������̍��������߂錩���ł��B
�����c���́A�x�����W���������̂ł����A���܂��������_���͌���Ă��炷�A�s��הƘ_�̍ō���Ƃ���Ă��܂��B
�ɂ�������āA�Q�����˂�Ŗ��f���p���܂��肾���A����Ȃ̂��������킯���Ȃ��B
�Y�@�w�҂��ă}�W�L�`���肾�ȁB�w��@�\���Ă��Ȃ��̂��H
���Ȃ���p����Ăă����^�B�������ȁB
��͂葁�c�̊w�҂͑��̎���Ƃ̓��x�����Ⴂ������ȁB
�s��הƂ̏��������́i�P�j�Ɓi�Q�j�|�i�S�j������ɕ���ł���̂͂���������ˁH
�i�T�j�������[�O�c�P�R�X��
�@�@���ʔ����̊댯�ɏd��Ȋ댯��^�������i��s�s�ׁj
�A�@�댯���R���g���[��������n�ʂɂ����i�댯�̈����j
�B�@���Y���ʂ̖h�~�ɕK�v�ȍ�ׂ��\��
�C�@���Ɍ��ʖh�~�ɉ\�Ȏ҂��ǂꂾ�����݂����̂�
�D�@�@�߂�_�Ɋ�Â��A�s�҂Ɣ�Q�҂̊W
�E�@���̊֗^�҂Ƃ̋A�ӂ̔z��
�i�U�j�@�\�I���[�R���Q�R�S�ŁA�����P�T�Q��
�@�v�ړI�ɕی삷�ׂ��ꍇ�ƁA�ԐړI�ɕی삷�ׂ��ꍇ�Ƃɕ����A��`�����A�댯��Ԃɂ���@�v��ی삷�ׂ��`���i�@�v�ی�`���j
�Ɩ@�v���댯�ɂ��炷�댯�����Ǘ����ׂ��`���i�댯���Ǘ��`���j�Ƃɓ��錩���ł��B
�R�@���@��
�ȏ�̌����܂��Ĕ�����݂Ă݂܂��傤�B
K����A�y�S�I�S�����z�i�������N�P�Q���P�T���j�́i�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�@�@�����Łu�\������v�Ƃ����\���́A�~���̉\�������ɍ����قƂ�Nj~���ł����Ƃ�����|�ł����āA�P�O�O�����W�O���Ȃ����X�O��
�@�@�Ƃ����m���̈Ӗ��ŏq�ׂ�ꂽ���̂ł͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B
���ɁAL����A���Ă͏��X���G�ł����A�y�U�����z�i�����P�V�N�V���S���F�V���N�e�B�p�b�g�����j�́i�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B���̔���ɂ��ẮA����A�R���搶�́w�V���Ⴉ�猩���Y�@�v�R�P�ňȉ���ǂ�ł��������B
�S�@���@��
�i�P�j���ɂ��ẮA�����̌`���I�����������Ă��A�����ɂ��ꂪ�Y�@��̍�`���ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��Ƃ����ᔻ���\�ł��B�Ⴆ�A����@���
�~��`���ᔽ�߂�����������Ƃ����āA���ꂪ�����ɎE�l�߁i�P�X�X���j��ی�ӔC�҈���v���߁i�Q�P�W���j�̐������킯�ł͂���܂���B
�i�Q�j���ɂ��A�P����瀂������̍ۂɎE�ӂ��������ꍇ�ɂ́A�����ɎE�l�߂̐������F�߂��Ă��܂��Ƃ����s���Ȍ��_�ɂȂ�܂��B
�i�R�j���ɂ��ẮA������̈����Ȃ��Ƃ��A�e�q�W�Ƃ������Ƃ���A�ˑ����������邱�Ƃ�����Ƃ����ᔻ���\�ł��B
�i�S�j���ɂ��ẮA�Ⴆ�A�M�ꂩ���Ă���q���A���̐e�̂ق����l��������C���Ȃ����Ă���Ƃ����ꍇ�ɁA�u�r���I�x�z�v�͑����Ȃ����䂦�ɁA
�N�ɂ��s��הƂ��������Ȃ����ƂɂȂ�A�Ó��Ƃ͉]���܂���B
�T�y���@���z
�������āA���́i�U�j���́u�@�\�I���v���x�����܂��B
�u�@�v�ی�`���v�̉��ʊ�Ƃ��ẮA�@�K�͓I�ی�W�A�A�C�ӓI�E���x�I�ی�W�A�B�@�\�I�ی�W�Ɋ�Â���`��������A
�u�댯���Ǘ��`���v�̉��ʊ�Ƃ��ẮA�@�댯�ȕ��E�ݔ��ɑ���Ǘ��`���A�A��O�҂̊댯�s�ׂɑ���Ǘ��`���A�B��s�̊댯�n�o�s�ׂɊ�Â�
��`���A�C�p���I�ی�@�\�Ɋ�Â��Ǘ��`��������܂��B
���̗ތ^���͊�{�I�ɑÓ��ł���A���ᕪ�͂̎��_�ƂȂ�Ǝv���܂��B
���̓_�������Ȃ��Ƃ܂������낤�B
����A���̍����̒��Ȃ��B��̐����Ȃ��B
�������́i�U�j���́u�@�\�I���v���x�����܂��B
�������Ȃ��B
�ȏ��J�Y�@���݂Ƀ��x�����Ⴂ�B�ǂ��̌Y�@�w�҂��m��ǁA
���݂̊w��̃��x���̒Ⴓ����Ă���̂��������B���̌Y�@�w�҂����x�����Ⴂ�̂��肾���A
�����������Ȃ̂������Ă��邩��Ȃ��B�z���g��ʑw�ȊO�͕��̏W�܂肾�ȁB
�i�P�j�̌`�����Ɓi�Q�j�ȍ~�̎����������ɕ��ׂ�̂͒[�I�Ɍ����Č�肾�낤�B
�P�@�͂��߂�
��@���Ɋւ��鏔���i�����h�q�_�A�ً}���_�A��Q�҂̓��Ӂj�A�\���v���Ɋւ��鏔���i���ʊW�_�A�s��הƘ_�j
�ɑ����āA�ӔC�Ɋւ��鏔�������グ�邱�Ƃɂ��܂����A�ŏ��Ɍ̈ӂ̖��ɂ��āu�����̍���v�ɂ��ďq�ׂ���
�Ǝv���܂��B
�u�����̍���v�Ƃ́A�s�҂̔F�����������Ǝ������ꂽ�����Ƃ��قȂ�ꍇ���]���A�����Ŏ������ꂽ�\���v���Y������
�ɂ��Č̈ӂ��F�߂��邩�����ƂȂ�܂��B
�y����Q�R�z
X���AA��_���Ĕ��C�����Ƃ���A�e�ۂ����ė\�z�O��B�����S�������B
���̂悤�ɁA�F�������q�̂Ƃ͈قȂ�q�̂ɐN�Q���������ꍇ���u���@�̍���v�Ɖ]���܂��B
�y����Q�S�z
X���AA���Ǝv���Ĕ��C�����Ƃ���A���͂����B�ł���AB�����S�����B
���̂悤�ɁA�F�������N�Q�q�̂̑����ɂ��Ă̍���i�l�Ⴂ�j���u�q�̂̍���v�Ɖ]���܂��B
�q�̂̍���ɂ��ẮA�w���͈�v���āAB�ɑ���̈ӂ��m�肵�Ă��܂��B���Ȃ킿�AB�ɑ���E�l�����߂��������܂��B
�Q�@�@��I�������Ƌ�̓I������
M����A�y�S�I�S�O�����z�i���a�T�R�N�V���Q�W���F�т傤�����e�����z�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�j��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B���̎����ɂ́A��ŏq�ׂ�u�̈ӂ̌��v�̖����܂܂�Ă���̂ł����A���̂悤�ɁA�F��������
���������Ƃ��\���v���͈͓̔��ɂ����ĕ������Ă���ꍇ�ɂ͎��������ɂ��Č̈ӂ�F�߂錩�����u�@��I�������v�Ɖ]���܂��B
�i�u���̈ӔƐ��v�Ƃ��āA�c���R�O�S���R�U�A����P�Q�Q�A��J�P�V�P�A�O�c�Q�V�R�A�ъ��l�Q�T�R�A����Q�P�S�A�����P�W�V�D
�@�u��̈ӔƐ��v�Ƃ����A��˂P�X�Q�A���c�P�Q�O���W�A����Q�W�P�A�����i��j�Q�Q�W�A�쑺�Q�P�R���P�A���v�ԂP�R�O�j
���̌�������́AX��B�ɑ���E�l�����߂��������܂��B
����ɑ��āA�q�̂̍���ɂ��Ă͎��������ɂ��Č̈ӂ�F�߂邪�A�F���E�\�������̂Ƃ͈قȂ�q�̂ɐN�Q�����������@�̍���̏ꍇ�ɂ́A
���������ɂ��Č̈ӂ�F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��闧����u��̓I�������v�Ɖ]���܂��B
�i����P�O�S�A���R�R�U�Q�A�����X�R�W�A����Q�S�P�A���c�P�U�Q�A�]���Q�O�U�A�R���Q�O�S�A���c�Q�O�V�A�x���P�O�V�A��c�R�P�O�A�R���R�Q�R�A
�@���{�P�X�U�A�����Q�P�V�j
���̌�������́AA�ɑ���E�l�����߂�B�ɑ���ߎ��v���߂��������܂��B
�@�@�y�����z
�R�@�@��I�������̌���
�@��I�������́A���@�̍���ɂ����ẮA�_���Ă��Ȃ����������ʂ��������q�̂Ɍ̈ӂ�F�߂܂��B
���̍����́AX��A�Ƃ����u�l�v���E�����Ƃ���B�Ƃ����u�l�v���E�����̂�����A�\�ۂƎ����̊Ԃɏd�v�ȍ���͂Ȃ��Ƃ������̂ł��B
�܂��A�s�҂́A�\���v���̂����œ���̕]�����鎖����F������A���Y�s�ׂ����s�Ɉڂ��Ă悢���Ƃ����u�K�̖͂��v�ɒ��ʂ���̂ł��邩��A
�������������ɂ��āu���ړI�Ȕ��K�͓I�l�i�ԓx�v�i�c���Q�X�W�j�Ȃ����u���ړI�Ȕ��K�͓I�Ȉӎv�����v�i��J�P�V�P�j��F�߂�ׂ��ł���Ƃ��܂��B
�������A����̕]�����鎖����F������A�Ȃ����������ʂ̎����ɂ��Ē��ړI�Ȑl�i�ԓx�Ȃ����ӎv������F�߂�ׂ��Ȃ̂��́A��������Ă��܂���B
�����ł́A�̈ӊT�O�́A�s���ɒ��ۉ�����Ă��܂��B���K�͓I�l�i�ԓx�Ȃ����ӎv�����́A�����܂œ����_���Ă���A�Ɍ�����ꂽ���̂ł���A���̌���ł̂݁A
�@�v�N�Q���������悤�Ƃ���ӎv���Ӗ�����u�̈Ӂv�Ƃ��ĈӖ��������܂��B
���̐����O��Ƃ���K�͘_�́A��̓I�@�v�N�Q�Ƃ̊W�ɂ�����K�͂������ɂ߂čs�ז����l�I�Ȃ��̂ŁA�������u�ӔC��`�v�̊ϓ_����݂Ă��A�P��
�K�͈ᔽ������������琶��������̌��ʂɂ͂��ׂČ̈ӐӔC���ׂ����Ƃ������ʐӔC�I�Ȍ����ł����ĕs���ł��B
�S�@��̓I�������̌���
��̓I���������ł��ᔻ����Ă���_�́A�q�̂̍���ƕ��@�̍���̏����̑���ł��i���Ȃ킿�A�O�҂ł͌̈ӂ��m�肳��A��҂ł͌̈ӂ��ے肳��܂��j
�y����Q�T�z
X���A��A���E�����Ƃ��āAA�̎Ԃɔ��e���d�|�����Ƃ���A����A�̍�B���Ԃɏ���Ĕ��������B
���̂悤�ȏꍇ�ɂ́AA��_�����Ƃ������ʂ��猩��Ε��@�̍���ł���A�����Ԃɏ��l���E�Q�������ł���A���ꂪA�ł͂Ȃ�B�ł������Ƃ����_��
������q�̂̍���ł����āA����Η��҂��������܂��B
���̎���ɂ��āA�R�������́A�q�̂̍���ł���Ƃ��Ă��܂��i�R���R�R�Q�j
�@�@X�́AA�̍s����P�ɗ\�����Ď��s�s�ׂ��s�����̂ł���A�܂��A���̎��s�s�ׂ͎��s���Ă��炸�A�������e����������Ƃ��ɍ��Ȃɍ����Ă���̂́A
�@�@A�ł���Ǝv���Ă����Ƃ���A�����ɂ�B�ł������Ƃ����ɂ����Ȃ�����A�q�̂̍���ł���B
�F������l���Ă݂Ă��������B
�@�@�y�����z
�T�@�̈ӂ̌�
�y����Q�U�z
X�́AA���E�����Ƃ��āAA�݂̂Ȃ炸B�����E�Q���Ă��܂����B
�@��I�������ɂ��AA�����B�ɑ���E�l�������Q��������i�A���A�ϔO�I�����j���ƂɂȂ�܂����A
�u��l�E�����Ǝv���Ă���̂ɎE�l�߂����������̂͂��������ł͂Ȃ����A�̈ӂɂ���������̂ł͂Ȃ����v
�Ƃ����ᔻ���������܂����i���열��w�ƍߘ_�̏����i��j���_�x�i�P�X�W�P�N�j�U�V�Łj
����ɑ��āA�@��I�������̐w�c�́A���̔ᔻ������ĂP�̌̈ӔƂ̐����̂ݔF�߂�u��̈ӔƐ��v��
�����̌̈ӔƂ̐������m�肵�Ă��s���ł͂Ȃ��A�ϔO�I�����̋K��͂��̂悤�Ȏ�|���܂ނƂ���u���̈ӔƐ��v
�ɕ�����܂����B
���́A�u�̈ӂ̌��v�̖��́A�@��I�������ŗL�̖��ł͂���܂���B
A���E�����Ǝv���Đl�Ⴂ��B���E�����Ƃ����q�̂̍���̏ꍇ�AB�E�l�����݂̂Ȃ炸�BA�E�l�����̐��������ɂȂ邩��ł��B
�T�@���Ƃ̍���
N����A���W�����̎���Q�V��ǂ�ł��������B
�y����Q�V�z�i���[�[�����U�[�������j
���U�[���͎����̎g�p�l���[�[�ɋ��K���^�̖̂��ƂŁA���̎����ɐX�̒���ʂ�V�����[�x�̎E�Q�����������B
���[�[�́A���̎����ɒʂ肩�������j���ˎE�������A����̓n�[�j�b�V���Ƃ����ʐl�ł������B
����́A�h�C�c�̌Â�����ł��B�܂��A���Ǝ҃��[�[�̍���͋q�̂̍���ł���A�E�l��������������_�͖�肠��܂���B
����ɑ��āA�����҃��U�[���̍ߐӂɂ��Ă͌�����������Ă��܂��B
�@��I�������̗��ꂩ��́A�u�l�v�̎E�Q���������āu�l�v�����S�����ȏ�A�E�l�����������F�߂���͓̂��R�ł��B
��̓I�������̗��ꂩ������l�̌��_���̂錩��������܂��i����R�W�V�j
�R�������́A��̓I�������̗��ꂩ��A�q�̂̍��낾�Ƃ��i�R���R�R�R�j�A���c�����́A���@�̍��낾�Ƃ��܂��i���c�Q�P�S�j
���@�̍��낾�Ƃ���ƁA�h�C�c�Y�@�R�O���̂悤�ȋ��������̏����K��������Ȃ��킪���̏ꍇ�A���U�[���̍ߐӂ́A
A�E�Q�ɂ��Ă͕s���ƂȂ�AB�E�Q�ɂ��Ă͉ߎ��v���߂���������ɂƂǂ܂�܂��B
�ȏ�ŁA��P�P�u[���@�̍���]���I���܂��B
���f���p���܂���Ȃ�B�L�`�K�C����B
�P�@���̏���
����́u�����̍���v�̂����A�N�Q���������q�̂ɍ���͂Ȃ����A�N�Q�Ɏ�����ʌo�߂ɍ��낪����u���ʊW�̍���v�ɂ��Č����������܂��B
���Ȃ킿�A�s�҂��F�����Ă������ʌo�߂ƌ����̈��ʌo�߂��قȂ�ꍇ�A�����ɔ��������\���v���Y�������ɂ��Č̈ӂ̐������m�肷�邱��
���ł���̂��A�Ƃ������ł��B
���W�����̎�������Ă��������B
�y����Q�W�z�i���F�a����j
X�́AA��n���Ŏh�E���悤�Ƃ������A�����菝�킹���Ɏ~�܂����Ƃ���AA�͎��͌��F�a���҂ł��������߂ɏo�����ʂŎ��S�����B
�y����Q�X�z�i���r����j
X�́AA��M�����������ŋ�����˂����Ƃ������AA�͐��ʂɌ����������A���r�ɓ��������˂������S�����B
�y����R�O�z�i�R����j
X�́AA���ˎE���悤�ƌ��e�˂������A���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ���AA�͒e�ۂ�����邽�߂ɔ�ёނ��A�w��̊R����ė����Ď��S�����B
�y����R�P�z�i�n�ُ��a�U�Q�N�P�O���P�T���[�����Ɓj
�q�����̊T�v�r
�s�s�K�X�̕��o�ɂ��q���A��ɖ����S�����悤�Ƃ��Đ����Ȃ������B
�q���@�|�r
�s�s�K�X�͓V�R�K�X�ł���i�����炭�s�҂��\�����Ă����j���Ŏ��̊댯�͂Ȃ����A�K�X�������̂Ȃ����_�f���R�ǂ̊댯�͂���������A�E�l��������������B
�y����R�Q�z�i�������ُ��a�T�R�N�X���Q�P���[�ߎ��Ɓj
�q�����̊T�v�r
�K�X�R�����̏�����Y�ꂽ���߂ɁA�ߐڂ����x�j���ɒ����ĉЂɂȂ����B
�q���@�|�r
�����l�����Ă����x�j���ւ̒��ڒ��ł͂Ȃ��A�R�������~���̃������ނɒ����A�K�X�z�[�X��`����ăx�j���ɒ�����Ƃ��������̌o�߂��\�\�łȂ��Ă��A
�x�j���ւ̒����\���\�ł�����܂�Ȃ��B
���F�e���͕����̖{���I�Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ��ȁB
�����Ă����̃����b�g���Ȃ����A���w�҃X���Ŋw��̎i��҂ɂ��Ă̔�排����܂ł���B
�����Ȃ��Ă���ƁA�Y�@�w�҂̂����炭�F�߂��ĂȂ��A�z�ȉ��ʑw�̊w�҂�
�Q�����˂�ɏ������݂��Ă���\���͍����B�܂�A�Y�@�w�҂͂Q�ɉ����������B
��ʑw�͓V�˂����A���ʑw�Ȃǂ̓z���g�A�z�̑����Ȃ낤�ȁB
http://www.youtube.com/watch?v=CIXNj-xajOA
http://www.youtube.com/watch?v=m9hVzkhzP_0
http://www.youtube.com/watch?v=qSHaq3I6I1s
http://www.youtube.com/watch?v=pVcJ4MQkth8
�Q�@�w�@��
�i�P�j�@�ʁ@��
����̌��ʂɌ�����ꂽ���ʌo�߂̑���́A�\���v���I�]���̏�ŏd�v�ł͂Ȃ��A����̍\���v���I���ʂɌ�����ꂽ�̈ӂ�����A
���ۂɐ��������ʌo�߂��������ʊW�Ȃ����q�ϓI�A���W���̘g���ɂ���ȏ�A���ۂɐ������\���v���Y�������ɂ��Ă̌̈ӂ�
�m�肷�邱�Ƃ��ł���B�\���v���I�]���̏�ŏd�v�Ȃ̂́A���Y�̈��ʌo�߂��������ʊW���[�������̂ł���Ƃ����_�ɂ���A
�����ɂ����Ȃ���ʌo�߂�H�������͏d�v�ł͂Ȃ��[���ꂪ�ʐ��ł��i���̂悤�Ȍ�������b�t�������̂Ƃ��āA�����w�ƍߘ_��
�W�J�T�v�i�P�X�W�X�N�j�Q�Q�V�ňȉ��A�Q�R�R�ňȉ��B���ɁA�ؑ��Q�Q�S�A������Q�V�O�A�c���Q�X�W�A��˂P�X�R�A�����Q�O�Q�A
�R���Q�P�Q�A���c�Q�P�P�j
�ȏ�̌����ɂ��A�s�҂Ɍ̈ӂ�����A�����̈��ʌo�߂������Ȉ��ʊW�̘g���ɂ���ꍇ�ɂ́A�̈ӂ̐������ے肳��邱�Ƃ�
�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A���F�a����B���r����A�R���Ⴂ����̏ꍇ�ł����Ă��A�̈ӊ����Ƃ̐������m�肳��邱�ƂɂȂ�܂��B
�i�Q�j�̈Ӕے��
�w���ɂ����ẮA���ʊW�̍���̎���ɂ����āB�̈ӂ̐�����ے肵�悤�Ƃ��錩�����L�͂Ɏ咣����Ă��܂��B
�@������Y�w�Y�@�ɂ�������ʊW�̗��_�v�i�P�X�V�V�N�j�Q�P�R�ňȉ�
���ʊW�_�Ƃ��Ă͏��������x�����Ȃ���A�Ȃ��A���ʊW�̍������Ƃ��Č̈ӂ�ے肵�悤�Ƃ��錩���ł��B
�̈ӂ̗��_�Ƃ��Ė@��I���������̂�̂ł�����悻�s�\�ł����A��̓I��������O��Ƃ���Ȃ�A�m����
�̈ӂ̐�����ے肷�邱�Ƃ��ł��܂��B
����������ł͈��ʊW�̍���̏ꍇ�A���悻�̈ӂ̐������m�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�����ŁA�\���������ʌo�߂ƌ����̈��ʌo�߂̕s��v���ǂ̒��x����Ό̈ӐӔC��₢���邩�Ƃ����c�_��
����������Ȃ��Ȃ�̂ł����A�����ŏo������́A�������ʊW���̗̍p�i�u�̈ӐӔC�͌o������\��
��������ʊW�����E�Ƃ���v����E�O�o�Q�Q�S�Łj�ɂȂ炴��܂���B
���̌����ɑ��ẮA�u���ւ���ǂ��������������ʊW���𗠌����炱������E�э��܂��Ă���v�Ƃ���
�ᔻ���\�ł��B
�@�@�y�����z
�Y�@���_�i�u�`�āj�@��P�Q�u�@���ʊW�̍���i�R�j
�A���c���E��ːm�E�Βk�Y�@���_�i�P�X�W�U�N�j�P�R�U�ňȉ�
�������ʊW������і@��I�������̗���ɗ����A�Ȃ����ʊW�̍������Ƃ��āA�̈Ӕے�̗��_�I�\�����m�肵�悤�Ƃ��錩���ł��B
���̌����́u�̈Ӎs�ׂ��甭���������ʂƌ̈Ӎs�ׂƂ̊Ԃɑ��������ʊW���������ꍇ�ł��A�s�҂̔F���E�\���������ʂ̌o�߂Ƌ�̓I��
�����������ʂ̌o�߂Ƃ̊Ԃ́y�s��v���������͈̔͂��Ă���ꍇ�z�ɂ́A���ʂɑ���̈ӂ͎��@�����Ƃ��Ă��܂��i�O�o�E�Βk�P�S�P��[���c]�j
�������A�s�҂ɓ��Y�q�̂�N�Q����̈ӂ��F�߂��A�����̈��ʌo�߂��������ʊW�Ɖ]������ꍇ�ɂ́u�s�҂����O�ɗ\�������Ƃ���ƁA���ۂ�
���ʊW�̌o�߂Ƃ��A�������ʊW�̊Ԃŕ������Ă���v����̈ӂ�����i�O�o�E�Βk�P�S�T��[���]�̂ł��B
����ɂ�������炸�u�s��v���������͈̔͂��Ă���v�Ɖ]���Ƃ��A���悻���̂悤�Ȃ��Ƃ����蓾��Ƃ���Ȃ�A�������ʊW��������̓I��
����\�肳��Ă���Ɖ]�킴��܂��A���̂��悤�ȁu�������v�͈̔́E��͋ɂ߂ĞB���Ȃ��̂ŁA���������̗��_�I�����͕s���ł��B
�B��c�ǁu�̈ӂɂ�����q�̂̓��肨��сw���x�̓���Ɋւ����l�@�i�O�j�v�@�w�����T�W���P�P���U�U�ňȉ�
���Y�̈��ʊW�̍��낪���ʂɑ���̈ӂ�j�p���A���ʋA�ӂ�W������̂������́u�K�͓I�v�Ȋ�ɏ]���Ĕ��f���悤�Ƃ��錩���ł��B
���̂悤�ȁu�K�͓I�v��Ƃ��č̗p����Ă���̂́A�u�s�҂��F�������A�s�ׂ̌����I�댯�����A��̓I�ԗl�ɂ����錋�ʂ̒��Ɏ����������v�Ƃ������̂ł��B
���̌����́A���r����̂悤�ȏꍇ�A���ˎ��͋�����˂����Ƃ��s�ׂ̊댯�����������̑ԗl�܂��̓o���G�[�V�����ɂ������A���̊댯���͔̂F������Ă���
�̂ł��邩��A���ʂ̋A�ӂ͍m�肵����Ƃ��܂��B
�C��؍��l�u�u���ʊW�̍���ɂ��āv�{���@���I�v�P���P�W�X�ňȉ�
���̌����́A�̈ӔƏ����̈Ӌ`���A���Ȃ̍s�ׂɂ���Ė@�v�N�Q���ʂ���������Ƃ������Ƃ�\�����Ă���s�҂��A
�Y���ɂ���ē��@�Â��邱��ɂ��A���ʔ����̗\���̂Ȃ��s�ׁA���Ȃ킿�A�̈ӂ̂Ȃ��s�ׂɓ������Ƃɋ��߁A
��������A���ʗ\���̂Ȃ��s�ׂ��s���Ă����ʂ����������ꍇ�ɂ͌̈ӐӔC���m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��܂��B
��������F�a����ɂ��Ă݂�ƁA�����菝�킹���Ƃ��������̎��ۂ́A����ɂ��i���F�a�Ƃ���������
�m��Ȃ��j�s�҂Ɍ��ʂ̗\�����^�����Ȃ��ꍇ�ł��邩��A���̏ꍇ�Ɍ̈ӐӔC���m�肷�邱�Ƃ͂��������ł���
�Ƃ���܂��B
�@�@�y�����z
�Y�@���_�i�u�`�āj�@��P�Q�u�@���ʊW�̍���i�S�j
�i�R�j���ʊW�̍��떳�p�_
���ʊW�̍��떳�p�_�́A���R���m�́u���ʊW�̍���̖��Ƃ́A���ǁA���̌o�߂��������ʊW�͈͓̔����ǂ����Ƃ������ƁA
���������Ĉ��ʊW�_�Ɠ���ɋA���A����_�Ƃ��ē��ʂɘ_��������̂͑����Ȃ��v�Ƃ����w�E��Ƃ��܂��i���R�R�U�S�ŁA�P�X�W�Q�N�j
�O�c�E��J�������́A���ʊW�̔F���͌̈ӂɂƂ��ĕs�v�ł���Ƃ������ꂩ��A���ʊW�̍��떳�p�_���܂��B
�y�O�c�Q�V�S�z
�d�v�ȍ��납�ۂ��́A���ǁA���ʌo�߂��������ʊW�͈͓̔��ɂ��邩�ۂ��Ō��肳���ȏ�A���̔��f��͋q�ϓI�Ȉ��ʊW�_�Ɠ���ɋA���A
�Ɨ��ɘ_����Ӗ��͏��Ȃ��B
�y��J�P�V�R�z
�]���A�����i���r����E���F�a����j�͎����̍���̖��Ƃ��āA�̈ӂ̐��ۂɂ��Ę_�����Ă������A���ʌo�H�̋�̓I�F���͌̈ӂ̐����ɂƂ���
�s�v�ł���ƍl�����邩��A���̍���͌̈ӂɂƂ��ďd�v�łȂ��A�ނ�����ʊW�̖��Ƃ��ĉ������ׂ��ł���B
�܂��A�R�������́A�q�ϓI�A���_�̗��ꂩ��A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
�y�R���R�S�W�z
���ʊW�̍��떳�p�_�́A���ʌo�߂̍���̏ꍇ�A���͍���_�͖��ł͂Ȃ��A�q�ϓI�A���_�i�������ʊW�_�j�Ŗ��͉�������Ǝ咣����B
�Ȃ��Ȃ�A�����E���������߂�̂͋q�ϓI�A���ł����āB���ʌo�߂̍���̏ꍇ�A�������ʂɑ���̈ӂ����݂��邱�Ƃ͋^�����Ȃ�����ł���B
�q�ϓI�ɔ����������ʌo�߂��A�q�ϓI�ɋA�ӂ�����͈͓��ɂ��邩����A�s�҂́A�̈ӁE�����̐ӔC���̂ł���B
�����A�i�R�j���ɗ^���܂��B
�ȏ�ŁA��P�Q�u{���ʊW�̍���}���I���܂��B
�@���⋳�������ُ̈�Ȏ����Ԃ�͍��҂̐S�̋��т���B
������o�J�ȋ����ł�����Ȃ��Ƃ킴�킴���Ȃ��B
�C�F�����B
�y�����Ă����ł͂Ȃ���
���ꂪ�Y�@�w�҂��L�`�K�C�����Ă������Ƃ��낤��
���w�҃X���Ŋw��̎i��҂��ǂ��̂����̌���Ă���̂�
�w�҂��~�Ղ��Ă��邱�Ƃ͊m���B
���يۏo���Ȃ̂́A�F�߂��ĂȂ����炾�낤������
�F�B�ł̘b�Â����Œ��������A���̗F�B�̐e�̗F�B���c�Ȃٌ�m�̗����Ă�������x���Ă���ۂ��B
�킩��Ȃ������A�ЂƂ̌g�тŋ����Ă܂ł��ĉ����������Ă�炩���Ă���ۂ��B
�z���Ƃ��ǂ����킩��Ȃ����A�������̓d�b���z�[���y�[�W���Ȃ��炵���B�Â��Ƃ������Ă�����A�T�����炵�����B�d�b����Ⴄ�Ƃ������������B�܂��A���T�蒆�炵�����A���̖��O�������������Ŋm�M�ȗL���Ȏ������������Ăق����B
�m���w�D�y�C���^�[�@���������x�ƌ����炵���B���O����A����Ȃ�ɂ͋C��t�����B�z���Ƃ��m��ǁc
�ȏ�A�F�B�̘b����
���ʊW�̍���̃o���G�[�V�����Ƃ��āu�E�F�[�o�[�̊T���I�̈Ӂv�Ɓu���������\���v���̎����v�����グ�܂����A
����Ǝ���̓h�C�c�̂̔���E�w���������āA���ڂ����_�������Ǝv���܂��B
�P�@�͂��߂�
N����A�y�S�I�P�U�����z�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B�L��������܂����B�����J�i�����蕶���X���X���Ɠǂ߂�悤�ɂ��Ă��������B
���̂悤�ɁA�s�҂͎��Ȃ̑�P�s�ׂɂ�茋�ʂ��������ƍl���Ă������A���ۂɂ͑�Q�s�ׂɂ�茋�ʂ����������Ƃ����ꍇ���w���āu�E�F�[�o�[�̊T���I�̈Ӂv�ƌĂт܂��B
���N�V���̒�`�ɂ��Ɓu�s�҂���P�̍s�ׂɂ���Č��ʂ��������Ǝv�������A���ۂɂ́A�s�҂̕\�ۂɂ��S���łɂ��̑O�Ɋ����ɒB�����s�ׂ̉B���ɖ𗧂ɂ����Ȃ�
��Q�̍s�ׂɂ���Ă͂��߂Č��ʂ��������A�Ƃ����Q�s�ׂ̎��یo�߁v�ł��B
�E�F�[�o�[���g�̒�`�ɂ��Ɓu�T���I�̈ӂƂ́A�ƍ߂̌��ӂ��A��v�Ȍ��ʂ�ڂ��������̍s�ׁA�����̎�i�A���邢�͍s�ו��������A����ɂ���āA�ړI�Ƃ��Ă����P�̔ƍ߂�
�����Ă���ꍇ�v�ł��B
�Q�@�h�C�c�ɂ�����c�_
�i�P�j���@��
�q�f�r���@�U�V,�Q�T�W[�Q�T�X]
�@�@�퍐�l�����͋������āA�E�l�̌̈ӂł`�w�l�ɏP��������A�|�ꂽ�`�������̂ƌ�M�����퍐�l�炪�A�`���ɓ�������A�M���������Ƃ������ĂŁA�퍐�l�����ɖd�E�߂̊�����F�߂܂����B
�l�c�q�@�P�X�T�Q,�P�U
�@�@�퍐�l�����܂ꂽ����̎����̎q����R�s�ׂ��s�Ȃ�����ɁA�q���������̂ƌ�M���āA�����ւڂɓ�������A���̌��ʒ������������Ƃ������ĂŁA���ۂ̈��ʌo�߂ƍs�҂��F��
�@�@���Ă������ʌo�߂̊Ԃ̐H���Ⴂ�͏d�v�łȂ��Ƃ��āA�퍐�l�ɎE�l�߂�F�߂܂����B
�a�f�g�r���@�P�S,�P�X�R
�@�@�퍐�l�͎E�l�̖��K�̌̈ӂ������ė���Ɉ�t�̗ʂ̍����Q�҂a�w�l�̌��ɉ������B�a�������Ȃ��Ȃ����̂ŁA�퍐�l�͂a�������̂Ǝv���A�a��역�߂ɓ������ꂽ�B�Ƃ��낪���ۂɂ́A
�@�@�a�͂܂�����ł��炸�A�역�߂̒��Ŏ��S�����B�A�M�ʏ�ٔ����́u�F�肳�ꂽ�����ɂ��A���R�ٔ������̈Ӗ������ł͂Ȃ��A������F�߂����Ƃ͐����ł���v�Ɣ������܂����B
�i�Q�j�w�@��
�w���́A�Q�ɕ������B
�@����̈�ʓI�ȍl�����Ɠ������A�E�F�[�o�[�̊T���I�̈ӂ̎�������ʊW�̍���Ƃ��Ď�舵���A���_�I�ɂ́A���ʌo�߂̈�E�́A�ʏ퐫�͈͓̔��ɂ���Ƃ��錩��
�i�o�E�}���AH.�}�C���[�A�C�F�V�F�b�N�A���N�V���j
�A��Q�҂̎��ڂɎ�N������Q�s�ׂ̓Ɨ�����F�߁A��Q�s�ׂɂ�����s���E�l�̌̈ӂ��F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�E�l�����Ɖߎ��v�������������Ȃ��Ƃ��錩��
�iM.E.�}�C���[�A�t�����N�A�}�C���F���g�j
H.�}�C���[�́A�@�̗��ꂩ��A��Q�s�ׂ��̈ӂɏo�����̂łȂ��ȏ�A����́A��P�̌̈Ӎs�ׂ̈��ʐ����Ւf����Ɨ��̍s�ׂ��肦���A�P�ɒ��Ԍ����ɂ����Ȃ��Ƃ��āA
���ʊW�̍���̖��Ƃ��āA��P�̌̈Ӎs�ׂ̐ӔC��_���ׂ��ł���A�Ƃ��܂��B
�}�C���F���g�́A�A�̗��ꂩ��A�s�҂����炽�Ȉӎv������Ȃ������ȏ�A�����ɂ͓��ӓI�ɍs�������̂����݂���̂ł���A�������甭���������ʂ����ʓI�ɂ���
�ȑO�̑�P�s�ׂɋA�ӂ����߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��A��P�s�ׂɂ�関���A��Q�s�ׂɂ��ߎ������݂̂����ɂȂ�ɂ����Ȃ��A�Ƃ��܂��B
����ɑ��āA�C�F�V�F�b�N�́A�@�̗��ꂩ��A�s�Ҏ��g�����ӎ��̂����Ɏ��Ȃ̍s�ׂ��������铹��ɂȂ��Ă���悤�ȂƂ��́A���S�ɋq�ϓI�A���̘g���ɂ���̂�
����A��E���Ă���Ƃ̕]�����s�҂̗L���ɋ��߂��邱�Ƃ͌����ĂȂ��A�Ɣᔻ���Ă��܂��B
���N�V�����A�T���I�̈ӂ̏ꍇ�A�E�l�̈ӂɂ���ĕ���ꂽ�s�҂̑�P�s�ׂ̑����Ȍ��ʂƂ��āA��Q�҂̎����ނɁu�A���v�����̂ł���A���̌��ʂ��Ȃ��s�҂�
�v��̎����Ƃ݂������A����͌̈ӂւ̋A���ɂƂ��Ă��\���Ȃ��̂ł���A�Ƃ��܂��B
�R�@�킪���ɂ�����c�_
�킪���ɂ����Ă��A�h�C�c�̊w���̔��f�ł���B���E�D���̂ق��A���܂��܂Ȋw�����咣����Ă��܂��B
�@�E�F�[�o�[�̊T���I�̈ӂ��m�肷����i�A���Q�U�O�j
�A�E�F�[�o�[�ɗ����������A�E�l�����Ɖߎ��v���̕����߂�F�߂���i���c�Q�S�P�j
�B���ʊW�̍���̖��ɊҌ����A�������ʊW�͔F�߂���Ƃ��A�E�l������߂Ƃ����
�i�ؑ��Q�Q�T�A���c�P�P�X�A��˂P�X�S�A�x���P�P�T�A�тQ�U�T�A�R���Q�P�S�j
�C���������ʊW�̍���̖��Ƃ��邪�A��P�s�ׂ̊댯���̌��ʂւ̎�����₢�A���ʊW���ے肳���ꍇ��F�߂���i�����X�U�R�A��c�P�W�T�j
�D�s�҂̐V���ȍs�ׂ̉�����d�����A��P�s�ׂɂ��ĎE�l�����A��Q�s�ׂɂ��ĉߎ��v����F�߂��
�i���P�V�W�A���R�E�T���Q�U�S�A����Q�U�S�A�]���P�W�W�A�쑺�Q�O�O�A��ؖΎk�P�O�S�j
�E�������̗��ꂩ��A�D�Ɠ������E�l�����Ɖߎ��v����F�߂���i����E���ʊW�̗��_�Q�R�T�j
�F���ʊW�̍���̖��ł͂Ȃ��A�������ʊW���̂��̖̂��Ƃ��A���ʂƂ��ĎE�l�����Ƃ�����i��J�P�U�P�A�O�c�Q�O�X�j
�G���������ʊW�̍���͉��ۖ��ł���Ƃ��A�q�ϓI�A���_�̗��ꂩ��A���ʂƂ��ĎE�l�����Ƃ�����i�R���R�T�U�j
�H�����ɂ����Č̈ӂ���s�א��i����P�R�T�j
�u�v�W�ɂ��邱�Ƃ��܂��������ׂ����낤�B
�Q�l�܂łɁA���c�L�����́u�\��O�̌��ʎ�N�v�u�\���̌��ʎ�N�v�ƌď̂��Ă���B
�L�`�K�C�Y�@�w�ҁB
���O�̕����L�`�K�C�����Ă��ƂɋC�Â��S��������Y
�S�@���@��
��ʂ���ƁA�E�l������ߐ��i�@�A�B�A�F�A�G�A�H�j�ƎE�l�����߁{�ߎ��v���ߐ��i�D�A�E�j�ɕ�����܂��B
�܂��A��P�s�ׂƑ�Q�s�ׂ��ēƗ��ɕ]�����ׂ����A���������ʂ��P�s�ׂɋA��������ׂ����A�̑I�������ɂȂ�܂��B
��씎�m�́A�D���̗��ꂩ��u��Q�̌̈ӂ���P�̌̈ӂƋ��ɎE�l�̌̈ӂɕ������Ƃ����̂͋�̓I�����̘c�Ȃł���v�Ƃ���i���P�V�W�j�A
���씎�m���u�E�ӂƎ��̈���[�����́A���̂ł͂Ȃ��������[�̂Q�̔F����O��Ƃ��Ȃ���A�O�҂̌̈ӂɂ��ƂÂ���A�̌o�߂Ƃ��āA���R��
��҂ɂ܂ł���т��邩�́A���Ȃ����K�v������v�Ƃ���܂��i����Q�U�S�j
����ɑ��āA�R�������́A�B���̗��ꂩ��A�u�@����������P�s�ׂɂ�铪���i���Q�҂̎��S�ɕ����I�Ɋ�^���Ă���A�A��P�s�ׂ̐Ղ�
��Q�s�ׁi�s�҂̔F���ɂ��Ύ��̈���s�ׂł���A��Q�҂̎��ɂ��Ă͉ߎ�������ɂ����Ȃ��j���s�Ȃ��邱�Ƃ͏\�����肤�邱�Ƃ�����A
��P�s�ׂ̊댯������Q�҂̎��Ɍ����������Ƃ������Ƃ��ł���v�Ƃ���܂��i�R���Q�P�S�j
�ߎ��s�ׂ̉�݂ɂ���đ������ʊW�Ȃ����댯�̎������ے肳���Ƃ���A���܂�ɂ����ʋA���͈̔͂������Ȃ肷����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
����ɁA��Q�s�ׂ́A�s�҂̔F���ł͎��̈���i�̈ӔƁj�|���́i���́j����[�ł������̂ɁA�Ȃɂ䂦�ߎ��ƂƂ����̂����炩�ł���܂���B
�E�l�����Ɖߎ��v���Ƃ���D���i�y�чD���j�͂Ƃ蓾�܂���B
���ɁA���ʂ��P�s�ׂɋA��������Ƃ��āA���ʊW�̍���̖��Ƃ��Ď�舵���̂��A����Ƃ����ʊW���̂��̖̂��Ƃ���̂����A����܂��B
���c���m�́A�B���̗��ꂩ��u�b�̍s�ׂƉ��̎��S�Ƃ̊Ԃɂ́A�������ʊW�̑��݂�F�߂邱�Ƃ��ł��邩��A�i��ɂ�鎀�S�ƍ����z����
��鎀�S�Ƃ̊ԕs��v�A���Ȃ킿�A���ʊW�̍���́A�̈ӊ����Ɛ����ɉe�����Ȃ��v�Ƃ���܂��i���c�P�P�X�j
���c���m�́A���ʊW�_�Őܒ��I�������ʊW�����Ƃ�A����_�ł͖@��I���������Ƃ��܂��B�����ŁA�s�҂̗\���������ʂ̌o�߂ƌ�����
���ʂ̌o�߂Ƃ��������ʊW�͈͓̔��ŕ������Ă���A�̈ӂ�F�߂��܂��B
���̌����ɑ��ẮA�������ʊW�̗L���ɂ���Č̈ӂ̗L�������܂邱�ƂɂȂ�A���ʊW�̒i�K�Ŗ��͂��łɉ�������邩��A���߂�
���ʊW�̍����_����Ӗ��͂Ȃ��A�Ƃ����ᔻ���\�ł��B
���ʊW�̍������Ƃ���B���i�y�чC���j�͂Ƃ蓾�܂���B
�ȏ�ɂ��A�������ʊW���̂��̖̂��Ƃ���F���A�y�ыq�ϓI�A���_�̗��ꂩ��u���ʊW�̍��떳�p�_�v�i�R���R�S�W�j���咣����G�����Ó����Ǝv���܂��B
��Ӎs�ׂ͑�P�s�ׂł���A�s�҂͎E�l�����߂ƂȂ�܂��B
�ȏ�ŁA��P�R�u�y�E�F�[�o�[�̊T���I�̈Ӂz���I���܂��B
����́u���������\���v���̎����v�ł��B
�K�[���t�����h(1980�N��)
http://www.youtube.com/watch?v=q5lBF4Tn95k
�K�[���t�����h(1990�N��)
http://www.youtube.com/watch?v=bzEnenrQLIQ
�P�@�͂��߂�
O����A�y�S�I�U�S�����z�i�����P�U�N�R���Q�Q���F�N�����z�����E�l�����j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B���������́q����r���A��Ŋe���ǂ�ł݂Ă��������B
���̂悤�ɁA�u�E�F�[�o�[�̊T���I�̈Ӂv�Ƃ͋t�ɁA�s�҂͗��ۂ��Ă������Ȃ̑�Q�s�ׂɂ�茋�ʂ������悤�Ƃ��Ă������A
���ۂɂ͎��Ȃ̑�P�s�ׂɂ�茋�ʂ��������ꍇ���u���������\���v���̎����v�Ȃ����u�����������ʂ̔����v�Ɖ]���܂��B
���N�V���̒�`�ɂ��u�s�҂̕\�ۂɂ��A��Q�s�ׂɂ���Ă͂��߂Č��ʂ���N�����͂��ł������ɂ�������炸�A
�w��������b�Â����P�s�ׁx�ɂ���Ă��łɍs�҂����ʂ���N���Ă��܂����ꍇ�v�ł��B
�Q�@�h�C�c�ɂ�����c�_
�i�P�j���@��
RGDS��R�@�P�X�R�X,�P�V�V
�@�@�s�҂���Q�҂��E�Q����O�ɁA�Ƃ肠�������łɂ���Ď��_�����悤�Ƃ������A����ɂ���Ă��łɔ�Q�҂��E���Ă��܂����B
BGH GA�@�P�X�T�T,�P�Q�R
�@�@�����̏��Y�ɒ�R�����Q�҂��A�������琶��������g�ݍ����ł��łɎ��S���Ă��܂����B
����́A������ɂ��Ă��A��{���I�Ȉ��ʊW����̈�E�ł���Ƃ��āA�E�l������F�߂Ă��܂����A���s�̒����ے肵�A
�\���s�ׂł���Ƃ������̔���͏d�v�ł��B
BGH�@NS��Z �Q�O�O�Q,�R�O�X
�@�@�퍐�l�́A�Ȃ����_��������A�����Ԃ̃g�����N�ɏ悹�ĕʂ̏ꏊ�ɉ^�сA�����ŎE�Q���悤�Ƃ��ăg�����N�ɏ悹���Ƃ���A
�@�@���S���Ă��܂����B�A�M�ٔ����́A��P�s�ׂƑ�Q�s�ׂƂ̊ԂɁu����Ȃ�{���I�Ȓ��ԍ������݂��Ȃ���Ȃ�v���A
�@�u�傫�ȏꏊ�I�E���ԓI�Ԋu������v�Ƃ������R����A���s�̒����ے肵�܂����B
�i�Q�j�w�@��
�w���́A�Q�ɕ�����܂��B
�@����Ɠ��l�A��{���I�Ȉ��ʊW����̈�E�ł���Ƃ��āA�E�l������F�߂錩��
�i�}�E���b�n���c�B�v�t�A�V���g���[���V�F���P���N���[�}�[�A���h���t�B�A�V���g���[�e�����F���g�A���N�V���j
�A�����݂̂�F�߁A�ꍇ�ɂ���Ă͉ߎ��ɂ�錋�ʎ�N�Ƃ̐��߁i�ϔO�I�����j���m�肵����Ƃ��錩��
�i�V�����[�_�[�A�w���c�x���N�A���V���J�A�Ȃ��A���H���^�[�A���R�u�X�j
���N�V���́A�@���̗��ꂩ��A���ʂ����Ȃ��Ƃ������s�ׂɂ���Ĉ����N�������Ƃ������Ƃ�O��ɁA��E�́A
�q�ϓI�ɕ]������A�Ȃ��s�v��̎����Ƃ݂���Ƃ��āA�E�l������F�߂܂��B
�A���̍����́A�������Ȃ��ƍs�҂��璆�~�̉\�������X�ɒD���Ă��܂��Ƃ������Ƃł����A���N�V���́u����������葹�Ȃ���
���ׂĒ��~�̉\����D���Ă��܂��Ƃ���A���ʂ̔������܂��ɂ����Ȃ肤��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ɣᔻ���Ă��܂��B
�R�@�킪���ɂ�����c�_
���̖��ɂ��ẮA���łɐ�O�ɂ����āA��씎�m���u���R�Ɋ����v�̉��ʎ���Ƃ��āA
�u��w���s�X�g���ŎE�����Ƃ��Ē͂ݍ����ċ���ԂɁA��w�̎w���s�X�g���̈����ɐG��e�ۂ�
��яo����w���E�����v�Ƃ����ݗ��p�ӂ��Ă������Ƃ����ڂ���܂��B���m�́u�s�҂ɂƂ���
�d�v�Ȃ͖̂ړI���������邱�Ƃł���A�ړI��B�����i�͎��͂ǂ��ł��悢�B���̈Ӗ��ɂ�����
����͌Y�@��d�v�Ȃ�ʓ_�ɑ����A�]���ĎE�l�̌̈ӂ�F�߂Ă悢�v�Ƃ���܂����B
���āA���݂̊w�����ʂ���ƁA�̈ӊ����Ƃ�F�߂錩���i�@�A�A�A�C�A�D�j�Ɩ����Ɖߎ��Ƃ�F�߂�
�����i�B�A�E�A�F�j�ɕ�����܂����A�ו�����Ǝ��̂Ƃ���ł��B
�@���ʊW�̍���̖��ɊҌ����A�������ʊW�͔F�߂���Ƃ��A�E�l�����߂Ƃ�����i��˂P�X�S�A���c�P�Q�O�j
�A�������̗��ꂩ��A�@�Ɠ��������ʊW�̍���Ƃ��ĎE�l�����߂Ƃ�����i����Q�Q�S�j
�B���������ʊW�̍���Ƃ��Ȃ���A�E�l������ے肵�ĎE�l�����Ɖߎ��v���Ƃ�����i�x���Q�Q�T�A���B�E�S�I�T�łV�V�Łj
�C��P�s�ׂƑ�Q�s�ׂƂ��u�ڒ������ڂɊ֘A����v���̂ł���A��P�s����
�u��A�̎E�Q�s�ׂ̔F���v��F�߁A�̈ӊ����ƂƂ�����i�O�c�Q�O�X�j
�D�q�ϓI�A���_�̗��ꂩ��u���ԓI�E�ꏊ�I�ɂ����ڂ�����A�̍s�ׁv���J�n�����u�댯�n�o�s�ׁv�͔F�߂��A
�@���ʌo�߂̈�E���{���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA�̈ӊ����Ƃ�F�߂���i�R���R�U�P�j
�E�����̈ӂ͖����̈ӂƂ͈قȂ�Ƃ��āA�E�l�����߂Ɖߎ��v���߂�F�߂���i����Q�S�W�j
�F�k�y�֎~�_�̗��ꂩ��A�̈ӊ����Ƃ�ے肵�A�E�l�����߂Ƃ�����i�R���[��q�j
�G�s�҂ɂ́A�\���̍s�ׂ����F�߂��Ȃ��Ƃ��āA�E�l�\���߂Ɖߎ��v���Ƃ�����i��c�R�V�V�j
�S�@���@��
���ʊW�̍���ɊҌ����錩�����s���ł��邱�Ƃ́u�E�F�[�o�[�̊T���I�̈Ӂv�ł��łɏq�ׂ܂����B
���������āA�@�A�A�A�B���͂Ƃ蓾�܂���B
���싳���́A�E���̗��ꂩ��u�`���C�₳���Ă���iR�����ŁA�܂��`�̓����_�ʼn��ł����Ƃ���A
�`�͂��̂܂��S���Ă��܂����Ƃ����悤�ȁw���܂������ʎ�N�x�̏ꍇ�ɂ́A�����������ʂɑ���
�̈ӂ��m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ��A�s�҂̎�ςƋq�ϓI�ɔ����������ʂƂ́A�������ʂ�
�͈͂ŕ������Ă���B�������s�҂ɂ́A���̉��ōs�ׂɂ���Č��ʂ������悤�Ƃ���Ӑ}�͂Ȃ��̂ł���A
���ʂ���������ӎv�̂Ȃ��s�ׂ��猋�ʂ����������Ƃ��Ă��̈ӔƂ�F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B����́A���Y�̍s�ׂ�
�����s�ׂł��邩�A�\���s�ׂɂƂǂ܂��Ă������Ƃ͖��W�ł���B�E�̗�ʼn��ōs�ׂ����ɎE�l�̎��s�̒���
�ł���Ȃ�ΎE�l�����߂Ɖߎ��v���߂Ƃ��A�\���ł���Ȃ�ΎE�l�\���߂Ɖߎ��v���߂Ƃ��A���ꂼ�ꐬ������v
�Əq�ׂĂ��܂����A��i�̋L�q�́u���������\���v���̎����v�̗���������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
��Ƀ��N�V���̒�`�����p�����悤�ɁA�u���������\���v���̎����v�Ƃ́u�w��������b�Â����P�s�ׁx�ɂ����
�s�҂����łɌ��ʂ���N�����Ă��܂����ꍇ�v���]���̂ł��B
�N�����z�������z���������s�ׂ�\���s�ׂƂ���G���ɑ��Ă��A�����ᔻ���Ó����܂��B
�R�������́A�F���̗��ꂩ��u�s�Ҏ��g�ɂ�錋�ʎ�N�s�ׁi��Q�s�ׁj�𖢂������ɗ��ۂ��Ă����1�s�ׂ̒i�K��
�i�̈Ӂj�����Ƃ̍\���v���Y���s�ׁi���s�s�ׁj���m�肷��̂͑Ó��łȂ��A�����܂ł���Q�s�ׁi�@�v�N�Q��N�s�ׁj��
�����Ƃ̍\���v���Y���s�ׁi���s�s�ׁj�ł���ȏ�A������s�����Ƃ���S�ł͂Ȃ����ۂ��Ă����P�s�ׂ̒i�K�ł́A
�����Ƃ̍\���v���O�̍s�ׂ��s���Ă���F�������Ȃ����߁A�����Ƃ̌̈ӂ͂Ȃ��v�Ƃ���܂��i�w�V���Ⴉ�猩���Y�@�x�W�X�Łj
�R�������́u�k�y�֎~�_�v�̖�萫�ɂ��Ắu�����ɂ����Ď��R�ȍs�ׁv�̉ӏ��ŏq�ׂ܂��B
�{�����ł́A���_������s�ׁi��P�s�ׁj�ƓM��������s�ׁi��Q�s�ׁj�́A���ԓI�ɂ��ꏊ�I�ɂ����ڂ��Ă��܂��B
�{������u��P�s�ׂ͑�Q�s�ׂ��m�����e�Ղɍs�����߂ɕK�v�s���Ȃ��̂ł������v���ƁA�u��P�s�ׂƑ�Q�s��
�Ƃ̎��ԓI�ꏊ�I�ڒ����v�𗝗R�ɋ����Ă��܂��B
���������āA��P�s�ׂ���Ӎs�ׂł���A�s�҂͌̈ӊ����ƂƂȂ�܂��B
�ȏ�ŁA��P�S�u�y���������\���v���̎����z���I���܂��B
����́A���ۓI�����̍���ł��B
�z���g�͂��Ȃ��ȁA�Y�@�X�����炢�����B����قǂ̍r�炵������̂́B�������w�҂Ƃ�������Ă��B
Sch/Sch��28�łɂ́C�V���g���[�̒P�Ǝ��M�����͂Ȃ����ǁB
�����Ō��T��ǂ�ł��Ȃ��̂ɁC�����������炾�߂ł���B
�������C�V���g���[���V�F���P���N���[�}�[�Ȃ�Ĉ��p���@���߂Č�����B
>>716
����ȏڍׂȊw�����ށA���߂Č�����B
�u�����v�̈ꌾ�ɐs����B
�P�@�͂��߂�
�O��܂ŏq�ׂ��u�q�̂̍���v�u���@�̍���v�u���ʊW�̍���v�͓���\���v�����̍���ł���A�u��̓I�����̍���v��
�Ă��̂ɑ��A�قȂ�\���v���Ɍׂ������u���ۓI�����̍���v���Ăт܂��B
P����A���W�����y����R�R�z�i���a�T�S�N�R���Q�V���F�w���C�����A�����j��(�����̊T�v�r�Ɓi����v�|�r��ǂ�ł��������B
�i�����̊T�v�r
�A�����������ł���o�����܂�A������ӎv�ŗA�����i�ł���w���C����A�������B
�i����v�|�r
���߂́A���̖ړI�����o�����܂����̍��ق����邾���ŁA���̗]�̔ƍߍ\���v���v�f�͓���ł���A���̖@��Y������ł���
�Ƃ���A�O�L�̂悤�Ȗ���Ɗo�����܂̗ގ����ɂ��݂�ƁB���̏ꍇ�A���߂̍\���v���͑S��
�d�Ȃ荇���Ă�����̂Ƃ݂�̂������ł��邩��A������o�����܂ƌ�F��������́A���������ʂł��閃��A���̍߂ɂ��Ă�
�̈ӂ�j�p������̂ł͂Ȃ��B
�S�I�ɍڂ��Ă��Ȃ��̂��s�v�c�Ȏ����ł����A�w���ɂ����Ă��A����̂悤�Ȏ����I�ȈӖ��ɂ�����\���v���̕�������Ƃ���
�u�@��I�������v�Ȃ����u�\���v���I�������v���ʐ��I�Ȓn�ʂ��߂Ă��܂��B
�Q�@�w�@��
�i�P�j�@��I�������i�c���j
�@��I�������́A�\�ۂ��ꂽ�����ƌ����̎����Ƃ�����̍\���v�����ɂ������ŁA�̈ӂ�F�߂�̂ł��邩��A���ۓI�����̍���ɂ��ẮA
�����Ƃ��Č̈ӂ�j�p������̂Ƃ��܂��B�������A�Ⴆ�A�Ɩ��㉡�̂̌̈ӂŎ��s�s�ׂɏo�����A�P�����̍߂����������ɂƂǂ܂����ꍇ�A
�P�����̍߂̌̈ӂ��j�p����A�P�����̗̂̌̈ӂ͂Ȃ��������̂ɕs���ƂȂ�Ƃ����͕̂s�����ł��B
�����ŁA�@��I���������A�قȂ�\���v���Ɍׂ���낪�˂Ɍ̈ӂ�j�p����̂ł͂Ȃ��A���͈͓̔��ŁA���낪�d�v�łȂ��ꍇ��F�߂Ă��܂��B
�i�Q�j�\���v���I������
�@���i�������i����j
����́A�d�Ȃ荇����F�߂�͈͂��u�Y�̉��d���R�̂�������A�t�Ɍ��y���R����������A���Y�Ƃ̂Ȃ��ŔF���Ǝ����ɂ�������������������v
�Ɍ��肵�A�d�Ȃ荇���̌��x���u�@�������̊W�ɗ������v�Ɍ��낤�Ƃ��錩���ł��B
���̌����ɑ��ẮA�����͈̔͂���������Ƃ����ᔻ������܂��i�c���j
�A�`���I�E�����I�������i�R�������̖����ɂ��j
�\���v���̏d�Ȃ荇�����x���A�\���v���������I�Ɍ`���I�ɏd�Ȃ荇���ꍇ�Ƃ��A����Ɏ����I�ɏd�Ȃ荇���ꍇ���܂ނ��̂Ƃ��܂��B
����ɂ��A�E�l�Ə����E�l�A�����Ƌ����E�l�Ȃǂɏd�Ȃ荇�����F�߂��܂��B
�B�����I�����i�ʐ��j
�\���v���̏d�Ȃ荇�����u�ی�@�v�̋��ʐ�����э\���v���I�s�ׂ̋��ʐ��v�i��ˁj�ɔF�߂錩�����]���܂��B
�y�����z�͂��̐��Ɏ^�����܂��B
�B�����I���������i����j
�@�j��̍\���v��������I�ɑ��̍\���v�����ۂ��Ă���ꍇ
�A�j�\���v���̊O���I����̂���ꍇ
���̌����́A���Q�Ǝ��̑���ɂ��Ă�������F�߂邱�Ƃ���A�����͈̔͂��������g�傳��邪�A�@�v���قɂ��邱�Ƃ���ᔻ����Ă��܂��i��J�j
�i�Q�j�ߎ��������i�����j
�{���́A�@��I�������͈͓̔��ŁA�F�����������Ɣ������������Ƃ��ƍ߂Ƃ��ėގ��̐��i��L����ꍇ�ɂ́A�̈ӂ̑j�p��F�߂�ׂ��łȂ��Ƃ��āA
��ʐl���قړ��Ӌ`�ƍl����悤�Ȗ@�v�N�Q�Ɍ�����ꂽ���̂ł���A�@�v�N�Q�̕��@�ɑ������Ⴊ�����Ă��A������F�߂闧��ł��B
�{���ɂ��A���̈���Ɛ��̈���ɂ́A�������F�߂�܂��B
�i�S�j�s�@�E�ӔC�������i����j
���̐��́A����R�R�̎��Ă̏ꍇ�A�w���C���Ɗo�����܂Ƃ͕������قȂ�ȏ�A�w���C���A���߂Ɗo�����ܗA���߂̍\���v���͕������Ă��炸�A
���̏ꍇ�A�}��E�ʐ��̂悤�ɍ\���v���̕������m�肷��̂́A�\���v���T�O�̎��E�s�ׂł���ƁA�\���v��������ᔻ���܂��B
�����āA�̈ӂ̓��e�Ƃ��č\���v�����Y�������̔F����v������������킪���̌Y�@�̉��߂Ƃ��ẮA���Y�̍\���v�����K�肷��
�s�@�E�ӔC���e�̔F��������Ό̈ӂ�F�߂邱�Ƃ��ł���Ƃ��āA���ǁA����E�ʐ����̂錈�_���̂͐��F���܂��B
�i�S)�����I�̈Ә_�i�O�c�j
���̌����́u�\���v�������̓��A�ǂ͈̔͂��ǂ̒��x�F������Ό̈Ӕ��\�ɂȂ�̂����̈Ә_�̋�̓I�ۑ�v�ł���Ƃ��āu�̈ӔƂ���������ɂ́A
�}�O�ƍߍ\���v���̎�v�����̔F���A�܂蓖�Y�\���v���̎����I��@�̔F���A��ʐl�Ȃ瓖�Y�ƍߗތ^�̗\�肷���@����F�������邾���̔F�����K�v
�ł���A������ő����v�Ƃ��܂��B
����R�R�Ŕ��Ⴊ����A���߂̐�����F�߂��͖̂���A���߂̌̈ӔƂ̐����ɖ���̔F���͕K�������K�v�Ȃ��Ƃ���܂��B
����́A�ߎ��Ƃł��B
�ɂȂ낤�ȁB�_�������Ȃ���ȂN�r�ɂ��Ă�����B
���{�����⏬�яy�����̖��ӎ��i�̈ӂƉߎ��̈ꌳ�_���_���j�����f����Ă���̂��H
�p�Ƃ������
�������Ă��Ȃ��B���̃X������Ɠ������킗
�Y�@�w�҂ɍ��݂̂���O�U�҉�wwwww
����̂����ň�u�ЂƂ肪��l�Ɍ�����w
�܂��Ƃ�����B
�|�[����B
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/lic/1378728604/l50
�P�@�͂��߂�
�u�ߎ��Ɓv�Ƃ́u�߂�Ƃ��ӎv���Ȃ��v�ƍߍs�ׂł���A�u�@���ɓ��ʂ̒�߂�����ꍇ�v�Ɍ����ď������܂��i�R�W���P���j
�����Łu�ߎ��v�Ƃ́u�s���Ӂv���Ӗ����܂��B���́u�s���Ӂv�Ƃ͉����������āA��q�̂Ƃ���w���ɑ���������܂��B
�Q�@�ߎ��\���_
�i�P�j�\���v���v�f�Ƃ��Ẳߎ�
�����A�ߎ��Ƃ́A�ӔC�̖��ł���B�̈ӂƕ��ԐӔC�����Ȃ����ӔC�`���ł���Ɖ�����܂����y���ߎ��_�z
�������ŋ߂ł́A�ߎ��Ƃ͍\���v���̖��ł���A�Ƃ��錩�����ʐ��ƂȂ��Ă��܂��y�V�ߎ��_�z
�\���v�����A�l�X�̈ӎv����̎w�j�ƂȂ�K�͂ł���Ƃ���A�K�v�Ȓ��ӂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�\���v���v�f�łȂ���Ȃ�Ȃ�
�Ƃ��ꂽ�̂ł��B
�������āA�̈ӂ���ϓI��@�v�f�悵�č\���v���v�f�Ƃ��ꂽ�悤�ɁA�ߎ����\���v���v�f�Ƃ���܂����B
�i�Q�j���ߎ��_�̏C��
�����ŁA�킪���̉ߎ��_�ɂ����ėL�͂ɏ������Ă���̂́A�C�����ߎ��_�ł��B
����͉ߎ��\���v�����u�����I�ŋ�����Ȃ��댯�v�̊ϓ_������肵�悤�Ƃ�����̂ł��B
�y�����z�v���A��q�̂Ƃ���A���̌������x�����܂��B
�R�@���ߎ��_
���ߎ��_�Ƃ́A�ߎ���ӔC�̎����ɂ����Ă̂ݘ_���A��@���܂ł́A�@�v�N�Q�̔����ƈ��ʊW�̑��݂ɂ���ď[���������̂Ƃ��錩���ł��B
�i�����P�P�P�A����Q�T�T�A�R���E���T���P�T�U�ňȉ��A�x���P�Q�P�A���c�Q�U�P�A��c�X�T�j
���̍l�����̔w�i�ɂ́A�ߎ���s���ӁA���킿�ӎv�ْ̋��̌��@�Ƃ���u�S���I�ߎ��_�v��
��@���̖{����@�v�N�Q�̎�N�ɂ����Ƃ���u���ʖ����l�_�u�v������܂��B
�����ł́u�\���\���v���ߎ��̒��S�Ɉʒu�Â����܂��B
�S�@�V�ߎ��_
�V�ߎ��_�́A�ߎ���ӔC�̖��ł���݂̂Ȃ炸�A��@���Ȃ����\���v���Y�����̖��ł���Ƒ����A�S����Ԃ̉ߎ��݂̂Ȃ炸�A
���̍s�ׂ̑��ʂɂ����ڂ��܂��i�c���R�R�R�A���c�P�Q�T�A��˂Q�P�U�A���c�P�Q�V�A��[�P�X�R�j
���Ȃ킿�u�����x�̂���s�ׁv�ɂ���Č��ʂ������Ƃ����ꍇ�ɂ݈̂�@�����m�肵�܂��i��㐳���E�ߎ��Ƃ̍\���i�P�X�T�W�j�T�P�ňȉ��j
���̂悤�ȔF�����L�܂����̂́u�ړI�I�s�ט_�v�̌��тł���A���̌����́u�s�ז����l�^�v�ߎ��Ƙ_�Ɖ]���܂��B
���Ӌ`���ᔽ�̑��ۂ́A�ތ^�I�Ɂu�Љ����K�v�Ƃ���钍�Ӌ`���v�ɔ��������ǂ����ɂ���Ĕ��f����܂��B
�T�@�C�����ߎ��_
����́A�ߎ��T�O��ӔC�_�ɂ�����u�\���\���v����сu���ʉ���\���v�ɋ��߂Ȃ���A�\���v���Y��������ш�@���ɂ�����
�ߎ��s�ׂɂ��A���ʔ����́u�����I�ŋ�����Ȃ��댯�v���������s�ׂɌ��肷�錩���ł��i����P�X�R�A���R�R�W�O�j
���̌����́A�ߎ��Ƃɂ����āA�u�s�ׂ̊댯���v�Ȃ����u�댯�̌������v��v�����܂��B
�T�@�\���\��
�i�P�j�ӔC�ߎ��Ƃ��Ă̗\���\��
�\���v���i�K�ł́u�댯�Ƃ��̑n�o�v������A�ߎ��Ƃ��������܂��B
�������{���̉ߎ��́A�ӔC�v�f�Ƃ��ĐӔC�̒i�K�Ɉʒu�Â����܂��B
�i�Q�j�\���\���̑Ώ�
Q����A�y�S�I�T�U�����z�i�D�y���ُ��a�T�P�N�R���P�W���F�k��d�C���X�����j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�{�������q�ׂĂ���Ƃ���A�ߎ��Ƃ́A�����̈��ʌo�߂̊�{�I�����̗\�����\�łȂ���Ȃ�܂���B
���ɁAR����A�y�T�P�����z�i�������N�R���P�S���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�y�����z���q�ׂ�A��̓I�������ɂ��A�\���v���Y�����́A�@�v��̂��Ƃɔ��f����܂�����A
�q�̂̑��݂�F���ł��Ȃ�����A���Y�@�v�ɑ���̈ӁE�ߎ��ӔC�킹�邱�Ƃ͂ł����A�{�����ł́AA�AB�̓����
������\���ł��Ȃ�����A�ߎ��Ƃ̐����͍m��ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��B
S����A�y�T�Q�����z�i�����P�Q�N�Q�O���F����g���l�������j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�R���搶�́q����r���e����œǂ�ł����Ă��������B
�i�R�j����I���f
���ʂ̋�̓I�\���\�����������邽�߂Ɂu����I���f�v���p������ꍇ���A����܂��B
T{����A���W�����́y����P�T�z��ǂ�ł��������B
BGHS���@�P�P�C�P�i�g���[�������j
�����Ԃ��A�K���ǂ���̂P���̊Ԋu�łł͂Ȃ��A�V�T�p�̊Ԋu�Œǂ��z�����g���b�N�̉^�]��́A���]�ԉ^�]�҂������Ă��ăg���b�N
�̕��Ƀn���h����������߂Ɏ��S���̂��N�������ꍇ�A��Q�҂������F���ł��Ȃ������Ȃ�A���̒��x�̊Ԋu�ł̒ǂ��z����
���R�ɗL�߂Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��B�V�T�p����x�̊Ԋu�ł̒ǂ��z���͓��풃�ю��ł���A����Œʏ�͎��̂͐����Ȃ�����ł���B
�i�댯�������Ȃ��j
��������C�����ߎ��_�Ɉʒu�Â��Ă���_�ɂ��āA
�Ð�L�F�w�Y���ߎ��_�����x�i�������j178�łɂ��ƁA
�u�����ŁA���씎�m�́A�ߎ��s�ׂ́u�����I�ŋ�����Ȃ��댯�v�̖����A�\���v���Y�����̋c�_�̈��
�ʒu�Â��邱�Ƃ�������߁A�u�����I�댯�����͗\���\���ł���A�ӔC�v�f�ł����ϓI��
�{�l�̗\���\���Ƃ����v�f�̗L���f����ꍇ�̈�̃v���Z�X�ɂ����Ȃ��v�Ǝ咣�����
�������B�v�Ƃ���Ă��邯�ǁA���̓_�ɂ��Ă͂ǂ��H
�Q�ƁA���열��u�ߎ��ɂ��Ă̓�A�O�̖��v�w��㐳�����m�җ�j��@�Y���@�w�̏����i���j�x300��
�u�{�����ł́AA�AB�̓���̎��������\�����ł��Ȃ�����A�ߎ��Ƃ̐����͍m��ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��B�v
�Ƃ��邯�ǁA��̓I�@�蕄����������u�\���\���v������Ήߎ��Ƃ̐����͍m��ł����ˁH
�V�@���ʗ\���`���H
�V�ߎ��_�́A�u�\���\���v�̑O��Ƃ��āA�u���ʗ\���`���v���܂����A
�R�������́A����ɑ��āA�s���ᔻ�������Ă��܂��i�R�����T���P�U�P�Łj
�@�u���ʗ\���`���v�́A���ꎩ�̂��Ɨ������u�`���v�ł͂Ȃ��B�`�����A���s
�@�@�������ʂ́u���ʂ̗\���v���Ȃ킿�u�̈Ӂv�ł���A���d���]������A
�@�@���d����������邩��ł���B���s����Ƃ��d���ӔC������u�`���v
�@�@�ȂǂƂ������̂̓i���Z���X�ł���B
�W�@���ʉ���`��
�悭�A�u���ʉ���`���v���ߎ��Ƃ̋q�ϓI���Ӌ`���ł���Ƃ���邱�Ƃ�����܂����A
����͌̈ӔƁE�s��הƂ��܂߂����ׂĂ̔ƍ߂ɋ��ʂ̋`���ł���A�q�ϓI�A����
�v���Ɋ܂܂����A�̂ł��i�����P�P�R�R�A����Q�T�X�A�]���E�Y�@�ɂ�����
���s�E�댯�E����i�P�X�X�P�j�T�X�ŁE�ъ��l�E�Y�@�̌���I�ۑ�i�P�X�X�P�j
�S�V�ŁA���{�Q�P�W�Łj
�����Ƃ��A�ߔN�A���ߎ��_�̗��ꂩ����A�ӔC�v�f�Ƃ��Ă̗\���\�������ł͂Ȃ��A
����ȊO�̗v�f�ɂ���ĉߎ��Ƃ̐����͈͂��悷��K�v������Ƃ������ӎ�
�����炩�ɂ���܂����i���ܗ��u�ߎ��Ɓi���j�v�@�w�����Q�V�U���i�Q�O�O�R�j�S�P�ňȉ��j
�Ȃ��A�ŋ߂̌����Ƃ���
�@���_�I�ɔƍ߂̃v���g�^�C�v�͉ߎ��Ƃł���Ƃ��āA�ߎ��ӔC�𒆐S�Ƃ���̌n�Ɋ�Â��ƍߘ_��W�J����
���ь����Y�w�Y�@�I�A�Ӂ[�t�B�i���X���X�E�q�ϓI�A���_�E���ʖ����l�_�x�i�Q�O�O�V�j�P�ňȉ�
�A�ߎ��Ƃ��̈ӔƂ̃A�i���W�[�Ƃ��Đ�������Ƃ����g�g�݂ɂ�炸�A���Ӌ`���̋�̓I���e�̊m����@��
�M���̌����̂ɂ�钍�Ӌ`�����Ə������ꍇ�𖾂炩�ɂ���
�������u�Y���ߎ��ƐM���̌����̌n���I�l�@�Ƃ��̌���I�Ӌ`�v
�i������w�@�ȑ�w�@���[�V���r���[�S���i�Q�O�O�X�j�P�V�R�ňȉ��j
������܂��B
�@�ɂ��ẮA���܂�ɂ��a�V�i�R�y���j�N�X�I�]���j�ł��邱�Ƃ���
�ے�I�]���������悤�ł��i�j
�X�@�s��ׂɂ��s�ׁ[�u�Y���������ӔC�v
�����A�̔����鎞�_�ɂ����āA�l�̎����Ɏ��邨����̂��錇�ׂ��\���\��
�ꍇ�ɂ́A�̔����́A���i���s��ɏo���A����҂ɒ�o���邽�߂̍s�ׂ��ߎ�
�s�ׂƂ݂邱�Ƃ��ł��܂��B
�w����A���̂悤�Ȍ��א��i�̉���`������`���Ƃ݂邱�Ƃ́A
�@���ʌo�߂ɑ��鎖���I�Ȕr���I�x�z��L�����
�i�k������q�u��Q�G�C�Y�R�����ɂ�����Y���ߎ��_�v�@�w�����Q�T�W���i�Q�O�O�Q�j�S�V�ňȉ���
�A�ł������I�Ɍ��ʉ��[�u���Ȃ������
�i���ڐ����u�Y���������ӔC�ɂ�����s��הƂ̈Ӌ`�ƓW�J�v���C�V�R�O���i�Q�O�O�X�j�Q�R�Œ��R�Q
�ɍ�`�������錩���ɂ����čm�肳��܂���7.
�P�O�@�����ꂽ�댯
�V�ߎ��_�̗��ꂩ��̉ߎ�����_�Ƃ��āu�����ꂽ�댯�v�Ɓu�M���̌����v������܂��B
�@�@�����̎Љ�ɂ����ẮA���Ƃ��A�z�R���H��̌o�c�Ƃ��A�����Ԃ�
�@�@�q��@�Ȃǂ̍����x��ʋ@�ւ̉^�]�E���c�̂悤�ɁA���ꎩ�́A�l��
�@�@�����E�g�́E���Y���e��̖@�v��N�Q����댯�����܂�ł��邪�A
�@�@�����̐������ێ������ɁA�s���ȈӖ��������̂����Ȃ��Ȃ��B
�@�@������L���֎~����Ƃ��́A�ߑ�I�Љ���͐��藧���Ȃ��ł��낤�B
�@�@���������āA����炪�A���ƁE�Љ�I�ϗ��K�͂ɏƂ炵�đ����Ɩڂ����
�@�@�͈͓��ōs�������A�@�v�N�Q�����̂ł����Ă��A�@�I�ɋ��e����A
�@�@�K�@�ƔF�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ���u�����ꂽ�댯�v�Ƃ����B
�@�i��˂R�T�V�Łj
���́u�����ꂽ�댯�v�̖@���ɑ��Ắu�s�ׂ��������ƂȂ��@�v�N�Q�̎�N��������邱�ƂɂȂ�̂��v
�Ƃ����R�������̉s���ᔻ������܂��i���T���W�T�Łj
�@�@
�ӂ��͌��ʉ���\���Ƃ��̍��ڂň�����Ȃ��́H
�Y�@�w�҂̏������݂��������ȁB�_���������ɂQ�����˂邩��B�z���}�L�`�K�C���ȁB
�P�P�@�M���̌���
U����A�y�S�I�T�R�����z�i���a�S�Q�N�P�O���P�R���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B�Ԃ��^�]���Ȃ��l�ɂ͕�����ɂ������Ⴞ�Ǝv���܂����A
���S�m�F��ӂ���X�߂Ƃ����_���d�v�ł��B
���̂悤�ɁA�M���̌����Ƃ́u�s�҂�����s�ׂ��Ȃ��ɂ������āA��Q�҂��邢��
��O�҂��K�ȍs�������邱�Ƃ�M������̂������ȏꍇ�ɂ́A���Ƃ����̔�Q��
���邢�͑�O�҂̕s�K�ȍs���ɂ���Č��ʂ����������Ƃ��Ă��A�s�҂͂����
���ĐӔC��Ȃ��v�Ƃ����������]���܂��i�����t�v�w��ʎ��̂ƐM���̌����x�P�S�Łj
���̌����́A���ߎ��_���邢�͏C�����ߎ��_�̗��ꂩ���
�@7�ߎ��s�ׂɗv�������u�����I�Ȋ댯���v�̗v�����I�ɕ\�������́i����P�X�V�j
�A��ʓI�\���\���Ƃ������ۓI���f�����̉����邽�߂̎v�l��̊�i�]���P�W�W�j
�Ƃ��đ������Ă��܂��B
�@
�ȏ�ŁA�ߎ��Ƙ_���I���܂��B
�ӔC�_�̏d�v�_�_�Ƃ��āu�����ɂ����Ď��R�ȍs�ׁv������̂ł����A
�����g�A�l�������ł܂��Ă��Ȃ����Ƃ���u�`�͏Ȃ��܂��B���������āA�����ɂ͏o�܂���i�j
�����ƁE�s�\�Ƃ͗������e�ՂȂ��Ƃ���ȗ����܂��B�e���A�����̋��ȏ��Ŏ��K���Ă��������B
�s�\�Ƃł͎R�������d�v�ł��B
����́A���~�Ƃ������܂��B
�E�ߎ��̕W���ɂ��ĐG��Ȃ��́H
�E�\���\���̒��x�E��̓I���e�ɂ��ĐG��Ȃ��́H������뜜�����ɂ��Ă��X���[���Ă邵�B
���̕���_���͕s���ɂ��ēǂ�łȂ��B
���_�T�͏��a�T�O�N�ŁA���җ�i���j�͏��a�T�W�N����ˁB
���̊Ԃɍl�������ς�����Ƃ������Ƃ��ȁH
���������A�ǂ�ł݂܂��B�L��B
>>743
�{�����ł́A�P�R�A�Q�R�Ƃ��A�퍐�l��A�EB�̓���̎�����F�����Ă��Ȃ�����
�Ƃ��������F������Ă���̂����B
>>748
�������ɁA���ʉ���\���̖��Ƃ��Ĉ����̂����ʂ��ˁB
���́A�ߎ��Ƃ������ɂ������Ă͏��{�����̋��ȏ����Q�l�ɂ����̂���
���{�搶���u�g���[���[�����v�Ɓu��t�����v��\���\���Ő������Ă���̂�
��������̂܂ܓ��P���Ă��܂����B
�P�@���~�Ƃ̈Ӌ`
�����Ƃ̒��ł��u���Ȃ̈ӎv�ɂ��ƍ߂𒆎~�����Ƃ��v�i�S�R��A���j�𒆎~�ƂȂ������~�����Ƃ����B
����ɑ��āA���Ȃ̈ӎv�ɂ��Ȃ������́A��Q�����Ƃ����B���̌��ʂ́A��Q�����ɂ��ẮA�Y��
�C�ӓI���y�ł���̂ɑ��A���~�Ƃ́A�K���Y�����y����A�܂��͖Ə������i�K�v�I���Ɓj
�Q�@���~�Ƃ̖@�I���i
�i�P�j�Y���������[�ؑ��R�U�X�A����P�R�Q�A�����m�u�R�T�U
�@�����ւ́u��߂�̂��߂̉����̋��v�igoldene Brucke zum Ruckzug)���˂���Ƃ����Ӌ`�����B
�y�����m�u�R�T�W�z
�������̗��ꂩ��́A���~�Ƃ́A���ʔ����̖h�~��ړI�Ƃ��āA���s�̒���ɂ���Ĕ����������ʔ����̊댯�������
���~�s�ׂɂ���ď��ł����邱�Ƃ����サ�A���~�s�ׂ��s�����҂ɁA�Y�̌��ƂƂ����J�܂�^����K��Ɨ��������B
�i�Q�j�댯���Ő��[�R���Q�W�O
�y�R���Q�W�O�z
�u���Ȃ̈ӎv�ɂ��v���~�ɂ��A�����̋�̓I�댯�����ł����Ƃ��ɁA���̂��Ƃɑ���J�܂Ƃ��āA�Y�̕K�v�I����
�Ƃ������T��^���邱�Ƃɂ���āA�ƍ߂̒��~�ɂ���̓I��Q�@�v�̋~����}�낤�Ƃ��鐭���I�Ӌ`��L������̂ł���B
>>�ے�I�]���������悤�ł�
���O�����쎩���ŃR�o�P���Ƃ������ăo�J�ɂ��Ă��邾�����낤���AR
�������ߎ��Ƙ_�͑S�R�Ȃ��ĂȂ���
���������A���O�����E�E�E�E�i���d������
�ߎ��̕W���ɂ��Ę_���ĂȂ����A�Ǘ��ēߎ��ɂ��G��Ă��Ȃ��B
�Ȃ��V�ߎ��_���Ɩ��Ȃ̂��A�̈ӂƉߎ���I�ɍl����Ƃ������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��B
���{�����́u�ߎ��Ƙ_�̌���I�ۑ�v�̖��ӎ��ɂ��G���ׂ����낤�B
�i�R�j��@�������[����R�R�S�A���c�Q�R�Q�A��J�R�W�S�A�x���Q�S�Q
��ϓI��@�v�f��F�߂錩������́A�C�ӂ̒��~�ɂ���Ă��̎�ϓI��@�v�f�����ł������A�@
�v��̊댯�����r�����邱�Ƃɂ���Ĉ�@������������B
�y��J�R�W�S�z
����Ɍ̈ӂ�������A���邢�݂͂����猋�ʂ̔�����h�~�����ꍇ�́A���ʔ����̌����I�댯
����эs�ׂ̔��Љ�I������������I�Ɍ�����������̂Ƃ��āA��@��������������B
�i�S�j�ӔC�������[�q��R�U�P�A�{�{�P�W�S�A�A���R�Q�S�A���Q�P�R�A�c���R�U�Q�A���R�S�R�Q���S�A����R�O�V�A�O�c�P�U�W�A�]���Q�T�R�A���c�Q�X�T
�ƍs�̌��Ӂi�̈Ӂj�̎���I�ȓP�s�҂̋K�͈ӎ��Ƃ��Ă͂��炭���Ƃɂ���āA�s�ׂɑ���ӔC����������B
�y�O�c�P�U�W�z
���Ȃ̈ӎv�Ŏv���Ƃǂ܂����ȏ�ӔC���y���Ȃ����ƍl����ӔC���������Ó��ł���B
����̈ӎv�ɂ��v���Ƃǂ܂����s�҂ɂ��ẮA�����̋K�͈ӎ�����݂Ĕ��͎�܂�Ƃ����悤�B
�y���c�Q�X�T�z�k�@��ʌY���R���l
���~�Ƃɂ�����Y�̌��Ƃ́A�ӔC�̑��ʂ���̖����Ƃɂ�����ʌY����̖@�艻�ł���B
�i�T�j��@�E�ӔC�������[������R�Q�R�A��[�S�Q�U�A��c�S�Q�S
�y��c�S�Q�S�z
���~�Ƃ́A���~�s�ׁi�s�ӎv�Ɋ�Â����~�s�ׁj����ь��ʂ̕s�����Ƃ�����@�������̗v���ƁA�C�Ӑ��Ƃ����ӔC�����̗v���̗����������Ă͂��߂Đ�������B
�i�U�j�������[��˂Q�T�W�A���Q�U�Q�A�q�P�R�U�j
�{�߂́A���~�Ƃ̐��i�ɂ��āA�ȏ�̏������̂��ׂĂ𑍍����ė������ׂ����̂Ƃ���B�A
��c���V�ߎ��_�Ȃ狖���ꂽ�댯�Ȃ�ĊT�O�K�v�˂���ƍs���Ă������Ƃɂ͐G��Ȃ��̂��H
�i�V�j���I�ӔC�������[�R���V�T�R
�y�R���U�W�W�z
���~�Ƃ̏ꍇ�A�Y�̖Ə��́A���I�ӔC�̌��������̍����ł���B����́A�����I�ɁA���~�����҂ɑ��āA�@�����ւ̋A�҂̕Ƃ��ČY�̖Ə����s���A�@�ւ̐M���������߂悤�Ƃ���ړI�ɏ]�������̂ł���B
�i�W�j�����������[�����R�W
�y�����R�W�Q�z
�\���v���Y�����E��@���i�j�p�j�E�ӔC�i�j�p�j�Ƃ����O�̃J�e�S���[�̂ق��Ɂu�����i�j�p�E�����j�v�Ƃ����J�e�S���[��݂��A���~�Ƃ��A���́u�����v�̌������R�Ƃ��Ĉʒu�Â���B
�i�X�j�������������[��ؖΎk�P�X�X
�y��ؖΎk�P�X�X�z
�K�͓I�]���Ƃ����_�ŁA�����Ƃ́u��@���v�E�u�L�Ӑ��v���������A����̒��~�s�ׂɂ���ĕω�����킯�ł͂Ȃ��B�P�ɂ��́u�������v���A����̒��~�s�ׂɂ���ĕϓ�����ɂ����Ȃ��̂ł���B
�L�`�K�C�̕�ɂ��˂��B��͂�F�߂��Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ⴄ�̂��ȁB���킢������
�R�@���@��
�܂��A�\���v���Y�����A��@���i�j�p�j�A�ӔC�i�j�p�j�̂ق��ɁA�u�����v��u�������v�Ƃ����J�e�S���[��݂���i�W�j���Ɓq�X�r���͂Ƃ蓾�܂���B
�����ᔻ�́A�ӔC�̈���Ƃ��āu���I�ӔC�v��F�߂�i�V�j���ɂ��Ó����܂��B
�i�R�j���ɂ́A���~�Ƃ��F�߂��邽�߂ɂ́A���~�s�ׂ��u���Ȃ̈ӎv�ɂ��v���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ����܂������ł��Ȃ��A
�Ƃ����v���I�Ȍ��ׂ�����܂��B
�i�S�j���̖��_�́A���̌����ɂ��A�s�҂ɒ��~�s�ׂ̏\���Ȉӎv���F�߂���ΐӔC�������m�肵����͂��ł��邪�A���s�@��́A
�P�ɒ��~�s�ӎv������A���ꂪ�����������Ƃ��Ă��A�q�ϓI�Ɂu�ƍ߂𒆎~�����v�Ɖ]���Ȃ���Β��~�Ƃ̐������m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����߁A
���s�@�̉��߂Ƃ��đS�ʓI�Ɏ���邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł��B
�i�Q�j���̖��_�́A�ƍߘ_�ɂ����Ă������������ƔF�߂�ꂽ�u�������ʂ̊댯�v���A
�s�҂̒��~�s�ׂɂ���ĉ��̎���I�ɏ��ł���̂�����������Ă��Ȃ����Ƃł��B
�i�P�j���́A���~�Ƃ̓��ʂ̎戵���̑��ݍ����ƂȂ蓾�Ă��A�ƍߐ����v���ɑ������������̘_��������ɂ������A
���~�Ƃ̐��ۂ̖��m�Ȋ��������Ƃ��ł��܂���i���V�^���u���~�Ɓv�Y�@�̑��_�i�Q�O�O�V�j�S�T�Łj
�i�U�j���̂悤�ȑ������́A�ƍߘ_�̒i�K�I�\������ѕ��͓I�v�l�̕����ł����āA�S�̒��ϓI�v�l�ɂȂ���
���̂ł����āA�s���ł���Ɖ]�킴��܂���B
�������āA�i�T�j�����c��܂��B
��ʂ̔ƍ߂ɂ��āA��@�ƐӔC�Ƃ����Q�̐����v�����l���邱�Ƃ��A
�@�v�ی�Ƃ����Y�@�̖ړI�ɏƂ炵�č����I�ł���̂ł���A���~�Ƃ�
���Ă��A��@�ƐӔC�Ƃ����Q�̖ʂɂ����ėv����藧���邱�Ƃ�
�����I�Ȃ͂��ł��B
��@�ƐӔC�������Ă͂��߂Ĕƍ߂ƂȂ�悤�ɁA��@�����ƐӔC������������
�͂��߂Ē��~�ƂƂ����u�}�C�i�X�ƍ߁v���������܂��B
���~�Ƃ̖@�I���i�̖��́A���~�Ƃ̐��ۂ̉����ɒ��ږ𗧂��̂ł͂���܂��A
�Y�@�ɂ������@�ƐӔC���l����ɂ������Ċ��D�̃e�[�}�ł��B
�F������A������x�l���Ă݂Ă��������B
�R�u�ƍ߂𒆎~�����v�Ƃ����v��
�i�P�j���~�s�ׂ̋q�ϓI�v��
��P�̒��~�s�ׂ̋q�ϓI�v���́A���~�s�ׂ̑ԗl�̌���̂��߂ɁA�Ւf���Ȃ����
���ʂ��������Ă��܂��댯��Ԃ��������Ă��邩�ǂ����ł��B
�܂��A�u��ׁv�ɂ�錋�ʖh�~�s�ׂ̗v���́A���ʂ�h�~����ɑ���s�ׂ��s������
�ɐs���܂��B
�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�s�ׂ̑��s�́u�s��ׁv���u���~�s�ׁv�ƂȂ邽�߂̗v���ł��B
���~�s�ׂƂȂ�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�C�Ӑ��̔��f�Ɏ��邱�ƂȂ��A��Q�����ƂȂ�܂��B
�@�s�ׂ̌p����
���~�����ׂ��s�ׂ́A���łɍs��ꂽ���s�s�ׂ̕����ƌp�����������̂łȂ���Ȃ�܂���B
�p���������邩�ǂ����́A�����I�E�K�͓I���f�ł��B���������āA���ԓI�E�ꏊ�I�E�\���v���I�E
�s�בԗl��́u�P�ꐫ�v���F�肳��Ȃ���Ȃ�܂���B
�Ⴆ�A�R�[�q�[�ɓŖ���������ēŎE�����݂����A���肪�R�[�q�[�����ڂ��Ă��܂��Ď��s�����̂ŁA
�V���ɓŖ����肵�A�����Ăѓ��l�̎�i�ŎE�Q�����݂悤�Ƃ������A���̌v�����������ꍇ�A
�P��ڂ̍s�ׂ́A���łɏ�Q�����ł���A���~�s�ׂƂ͉]���܂���B
�A�s�ׂ̑��s�\��
���~�ƂȂ�ׂ��s�ׂ̂Ƃ��ɁA�s�҂��s�ׂ�e�Ղɑ��s���������ǂ������A
���̗v���ł��B �s�ׂ̑��s�\���̔��f�́A�s���̏���q�ϓI�ɔ��f����܂��B
���������āA�s�҂́A��ϓI�ɂ́A�P���̒e�ۂŎE�Q�������ł��������A
�q�ϓI�ɁA�Q���̒e�ۂ����U����Ă����ꍇ�ɂ́A�q�ϓI�ɔ��f����ƁA
���s�\���͍m�肳��܂��B���̏ꍇ�ɁA�u���~�ӎv�v���������Ƃ����邩
�ǂ����́A���~�s�ׂ̎�ϓI�v���Ƃ����ʂ̖��ł��B
�i�Q�j���~�s�ׂ̎�ϓI�v��
���~�s�ׂƉ]�����邽�߂ɂ́A�u���~�ӎv�v���Ȃ킿�A���ʉ���ӎv�̂���
�s�ׂłȂ���Ȃ�܂���B�]���A���~�ӎv�̖��́A�u�C�Ӑ��v�i���Ȃ̈ӎv�ɂ��j
�̖��ƍ�������A�������̂܂ܘ_�����Ă��܂������A���҂͕ʂ̗v���ł��B
�@
�Ⴆ�A�s�҂��A�Q���ŎE�Q���悤�Ƃ��ĂP���ڂC�������A���ꂪ
�S���ɖ������A��Q�҂����S�������ƌ�M���āA�Q���ڂ������Ȃ������ꍇ�A
�u���~�����v�Ɖ]����ł��傤���B�q�ϓI��i�̓_�ł́A���s�\���͂���܂��B
�������A�s�҂ɂ́A���ʉ���ӎv���Ȃ��A���~�ӎv���������Ƃ͉]���Ȃ��̂ŁA
���~�s�ׂ͔F�߂��Ȃ��Ɖ]���ׂ��ł��B
�i�R�j���ʂ̔�����h�~����ɑ���ׂ����~�s�ׁ[�^���ȓw��
V����A�y�S�I�U�X�����z�i�������ُ��a�U�P�N�R���U���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
���ɁAW����A�y�S�I�V�P�����z�i��㍂�ُ��a�S�S�N�P�O���P�V���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
���̂悤�ɁA�ʐ��E����́A���~�s�ׂ����ʔ����h�~�̂��߂́y�^���ȓw�́z��v�����Ă��܂��B
�i���F�]���Q�T�T�Łu�ϋɓI�w�́v�j
�^������v������Ƃ��Ă��A�ϗ��I�]���Ƃ͐藣���āA�����A�^�Ɍ��ʂ̔�����h�~����悤
�ӗ~�������ǂ�������ɂ��ׂ��ł��B
���́u�^���ȓw�́v�̗v���ɂ��ẮA���Ƃ��ƌ��ʔ����̈��ʗ͂��Ȃ������ꍇ�ɖ��ƂȂ�܂��B
���Ȃ킿�A�@���Ƃ��ƈ��ʗ͂��Ȃ����߁A�܂��́A�A�ʂ̌������猋�ʂ��������Ȃ������ꍇ�A
���~�Ƃ��F�߂��邩�����ƂȂ�܂��B
�@
�@���Ƃ��ƌ��ʂ̔����Ɏ�����ݗ͂̂Ȃ����s�s�ׂł������ꍇ
���������ϋɓI���ʖh�~�s�ׂ͕K�v�łȂ��A�s�ׂ̑��s���������悩�����̂ł�����A
���薢���Ƃ��Ē��~�����͐��������܂��B
���������āA�v���ʂɒB���Ȃ��Ŗ�𓊗^������A��ō܂�^����Ȃǂ̐ϋɓI���ʖh�~�s��
���s�����Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ϋɓI���ʖh�~�s�ׂƌ��ʂ̕s�����Ƃ̊Ԃɂ́A���ʊW��
����܂��A���Ƃ��ƐϋɓI���ʖh�~�s�ׂ�K�v�Ƃ��Ȃ�����ł������̂ł�����A���s�s�ׂ�
���s��f�O�����ۂɔC�ӂ̒��~�s�ׂ��\��Ă���Β��~�ƂƂȂ蓾��Ɖ]���ׂ��ł��B
�h�C�c�Y�@�Q�S���P����i�́A�̏ꍇ��O���ɒu���āA���̂悤�ɋK�肵�Ă��܂��B
�� 24 Rücktritt
(1) Wegen Versuchs wird nicht bestraft, wer freiwillig die weitere Ausführung
der Tat aufgibt oder deren Vollendung verhindert. Wird die Tat ohne Zutun des
Zurücktretenden nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig
und ernsthaft bemüht, die Vollendung zu verhindern.
(2) Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wird wegen Versuchs nicht bestraft,
wer freiwillig die Vollendung verhindert. Jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit
sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern,
wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren
Tatbeitrag begangen wird.
�A���~�s�ׂƂ͕ʂ̌�����������Č��ʂ̔�����j�~�����ꍇ
��@����������́A�P�ɂ������ʔ����h�~�s�ׂɂ���čs���l�����邾���ł͂Ȃ��A
���ꂪ���ʂ̕s�����̌����ƂȂ邱�Ƃɂ���Č��ʖ����l�����j�~�������ƂɂȂ�A
�S�̂Ƃ��Ĉ�@������������̂ŁA���ʂ̕s�����Ƃ̂́u���ʊW�̑��݁v��v������
�����ɂȂ���܂��i����P�W�V�A������R�Q�U�A�A���R�R�Q�A���Q�U�S�A��J�R�X�O�j
�������A�s�ז����l�݂̂ł���@������F�߂邱�Ƃ��ł���̂ŁA��@�����������
���ʊW��K�v�Ƃ��Ȃ��Ƃ������������������܂��i�ؑ��R�U�W�A���c�Q�R�U�A��˂Q�U�R�A��[�S�W�O�j
�ӔC��������
�i�c���R�U�U���P�O�A����R�R�V�A�q�P�S�T�A�]���Q�T�U�A�O�c�P�V�U�j
�R�u���Ȃ̈ӎv�ɂ��v�̗v��
�i�P�j��ϐ��[�c���R�U�R�A���c�Q�R�S�A�]���Q�T�U�A�x���Q�S�S�A���v�ԂR�Q�U�A
�@�@�@�@�@�@�@��c�S�R�X�A�����R�W�W�A�����m�u�R�U�T�A�����R�Q�V�A��ؖΎk�Q�O�R
�O���I��Q���A�s�҂̕\�ۂ�ʂ��ē����I���@�ɋ����I�e����^�������A�����łȂ�������
�ɂ���ʂ��錩���ł��B
���̐��̈Ӗ��ɂ�����u�C�Ӑ��v�́A�u�t�����N�̌����v�ɂ���ĕ\����܂��B
�@�@Ich will nicht zum Ziele kommen,selbst wenn ich es konnte.
�@�@Ich kann nicht zum Ziele kommen,selbst wenn ich es wollte.
�y�����z���A���̐��ɗ^���܂��B
�@
�i�Q�j�q�ϐ��[�O�c�P�V�O
�O���I��Q�̕\�ۂ��ʏ�l�Ɂu�ł��Ȃ��v�Ɗ������������ǂ����ł͂Ȃ��A
�ʏ�l�ɂ���ł��u���s���悤�v�Ǝv�킹�����ǂ�������ɂ��܂��B
--------------------------------------------------------------------------
�i�R�j�����ϐ��[�{�{�P�W�S�A������R�Q�R�A�A�c�P�R�X�A���Q�P�R�A���R�S�R�T�A���c�Q�X�X
����A�����݁A�����A����A�s�����̉��l�ے�I�ӎv��K�v�Ƃ�����ł��B
�ȏ�ŁA���~�Ƃ��I���܂��B
�����ԁA���X��Ɛ肵�Ĉ��������B
�����܂ŏ����Ă����Ę_�_���ȗ�����Ȃ�B
�{�u�ł́A�����Ƃ��ĊԐڐ��Ɣے���ɗ����A�u���ƂȂ����Ɓv��F�߂闧�ꂩ��A�������q�ׂ����Ǝv���܂��B
�P�i�Ԑځj���ƂƋ��Ƃ̋��
�i�P�j�`���I�q�ϐ��[��ːm�E�Ԑڐ��Ƃ̌����i�P�X�T�W�j�P�Q�R�ňȉ��A��[���E���Ƙ_�����i�Q�O�O�P�j�T�V��
�\���v���̍s�L�q����Ƃ��āA�\���v���ɋL�q���ꂽ�s�ׂ����S�ɏ[�����҂݂̂𐳔ƂƂ��܂��B
�܂�A�Ԑڐ��Ƃ̐��Ɛ��́A���ڐ��Ƃ̂���ƈقȂ�Ȃ����s�s�א��ɂ���Ƃ��錩���ł��B
�w��҂Ɂu���s�̈ӎv�v������A���������̗U�v�s�ׂ��u�\���v�������̌����I�댯���v�����_�ŁA���ڐ��ƂƈقȂ�Ȃ��Ƃ��܂��B
�i�Q�j�����I�q�ϐ��i�R���V�X�R�j
�`���I�q�ϐ��ɁA�s��^�̊댯���̒��x�Ƃ��������I�ϓ_��t�������܂��B
�������A��̓I�ɂ́A�̈ӔƂɂ�������s�s�ׂƉߎ��Ƃɂ�������s�s�ׂƂł́A��A���̓��e���قȂ���̂Ƃ��܂��B
�i�R�j��ϐ��i�g���I���ƊT�O�̗���j
���Ǝ҂Ƃ́u���Ǝ҈ӎv�v�������Ĉ��ʓI�s��^���Ȃ��A���Ǝ҂Ƃ́u���Ǝ҈ӎv�v�����ɂ����Ȃ��Ƃ��܂��B
�i�S�j�s�x�z���[���{�����E�u�s�x�z�v�Ɛ��Ɨ��_�i�Q�O�O�O�j�A��c�ǁE�Y�@���_�̗��_�\���i�Q�O�O�T�j�Q�X�V�ŁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ə�����E�̌n�I���Ƙ_�ƌY���s�@�_�i�Q�O�O�T�j
���ƂƂ́A�s�ׂ��x�z����ҁA�܂�s���ۂ��蒆�Ɏ��߁A�s�ׂɏo��ׂ����ۂ��A�ǂ̂悤�ɍs�ׂ���ׂ��������肵�A
�\���v���̎����ɍۂ��āu���ۂ̒��S�I�Ȑl���v�ł���҂Ƃ��܂��B
�i�T�j�K�͓I��Q���[�A�c�d���E���Ƃ̊�{���i�P�X�T�Q�j�X�T�ŁA���`���E�Ԑڐ��Ɓi�P�X�U�R�j�P�R�S��
�험�p�҂ɋK�͓I��Q������ꍇ�ɂ́A�w��҂͐��ƂƂȂ�Ȃ��Ƃ��������ł��B
�u�K�͓I��Q�v�Ƃ́A�Y�@�̗��ꂩ�猩�āA���ʂ�\�����邱�Ƃ��ł��A�������
���Ƃ��ł����ƕ]�������s�ׂ��Ӗ����܂��B
�i�U�j�����I������[���c����Y�u�Ԑڐ��ƂƋ������Ɓv�_�R�ËH�i�P�j�S�S�X��
�s�҂��P�Ɛ��ƂƂȂ�̂́A���ʂڎx�z���Ă����ꍇ�ł���A����́A
�@�s�҂���Q�q�̂ɁA���̂܂ܕ��u����A���ɐ��������ʂ�������悤�Ȋ댯��ݒ肵���ꍇ�i�����I�x�z�j
�A���ɐ��������ʂɂ��āA�����I�Ɍ��肵�Ă��Ȃ��험�p�҂̍s�ׂ���Č��ʂ��������ꍇ�i�S���I�x�z�j
�̂����ꂩ�̗v�����K�v���Ƃ��܂��B
�i�V�j�|�y�����z
�i�Q�j������o�����A�i�T�j�������������܂��B
�Ԑڐ��Ƃ̗��_�I�����́A�܂�Ƃ���A���ڐ��ƂƓ����悤�ɁA���s�s�א����F�߂�꓾��_�ɑ��݂��܂��B
�Ԑڐ��Ƃ��A���ڐ��ƂƓ������A�e�{���̍\���v�����[�����邱�Ƃ�v������̂ł���A������s������
�]���邩�ǂ��������Ȃ̂ł��B
�Q�@�Ԑڐ��ƕs�v��
�i�P�j�s�v���̍���
���ƓƗ������E�g���I���ƊT�O����́A�Ԑڐ��Ƃ��s�v�Ƃ����͖̂ܘ_�ł����A�Ԑڐ��Ɩ��p�_�Ȃ�������_�́A
������N���̘_�҂�����L�͂ɏ������Ă��܂��B
����́A���ƌŗL�Ɛ����т��A�ߖ��Ɨ����̗���ɗ��ĂA�Ԑڐ��ƂƂ����T�O�͂����ĕK�v�łȂ��Ȃ�Ƃ������̂ł��B
�[�A�c�d���E���Ƙ_��̏����i�P�X�W�T�j�Q�P�ŁA������R�S�T�E�R�T�W�D���E�Ԑڐ��ƂP�R�W�A���R�S�V�S
�����̍����Â��̃��x����O�J���x����������
�i�Q�j�s�v���ɑ���ᔻ
���̂悤�ȊԐڐ��Ɩ��p�_�̓W�J�́A���Ƃ��A���ƊT�O�̒o�ɂ�h���A�����͈̔͂����肵�悤�Ƃ���_�ɂ���܂��B
�������A���̂悤�Ȍ����ɑ��ẮA�ߔN�A��Ƃ��č�����N���̗��ꂩ��A�������ᔻ�����т����Ă��܂��B�E
�y�R�����E���T���Y�@���_�i�P�X�X�W�j�Q�R�X�Łz
�i�Ԑڐ��Ƃ̔ے���咣�̗L�͂ȓ��@�Ƃ��Ă���j������N���́A�i�Ƃ��ĉ��I�ł��肤�邽�߁j�K�͓I��Q�ƂȂ肤���g���҂�
���p�ɂ��ĊԐڐ��Ƃ̐�����ے肷�錋�ʁA���Ƃ��ΐg���Ƃ̋����̐������m�肷�邱�Ƃɂ��������̂邱�ƂɂȂ�̂ł���B
�������A����ɑ��ẮA�u���ƂȂ����Ɓv���m�肷�邱�ƁA���Ȃ킿�u�l���������Ĕƍ߂����s�������v�Ƃ����Ȃ��ɂ�������炸����
�̐������m�肵�A�u���Ƃ�����v�Ƃ����Ȃ��ɂ�������炸�]�Ƃ̐������m�肷��̂́A���s�@�̗\�肷�鋳���E�̊T�O����E����
���ƂɂȂ�Ƃ���ᔻ���\�ł���B
�y��c�E���_�\���R�P�U�Łz
�킪���ɂ����Ĉꕔ�ŗL�͂Ɏ咣����Ă����g���I���Ƙ_�͏�����N���̗���ɂق��Ȃ�Ȃ��B�������ɁA���̌����̎咣����悤�ɁA
���Ǝ҂ɂƂ��@�Ȏ��ԁi���ƕs�@�j�������邱�Ƃ����Ƃ̏��������̒��j�����ł͂���B�����A���Ə����̌���̂��߂ɂ́A
���ƕs�@�̏]���I��N�A���������āA���ƕs�@�Ƃ̊W�ł̍ߖ��]�����i����ь̈ӂւ̏]�����j���K�v�ł���A�����ے肷��
�g���I���Ƙ_�͋��Ə����͈̔͂���Ȃ��̂Ƃ��Ă��܂������ꂪ����B
�G���^�[�L�[�@�����Ă�p���ڂɂ�����w
PC���S�䂵���Ȃ�����ȁB
�Љ�l�Ȃ������B�ނ���w�҂͂���ȂɎ����ĂȂ��ł��傤����
�w�҂���IT�Ƃ��قƂ�ǒm���l���������Ȃ�����
�s�x�z���͋q�ϖʂ��l���ł���Ǝv�����H
���Ƌ��Ƃ̋�ʂɍs�x�z�����̂�A
���ڎ��s�`�Ԃڐ��ƁA
�������s�`�Ԃ��������ƁA
�Ԑڎ��s�`�Ԃ��Ԑڐ��ƂƂ���̂��Ȗ��B
�Ȃ��A�����ɂ��Ԑڎ��s��
�Ԑڐ��Ƃ̓��ʗތ^�Ƃ��Ă̋����ƂƂ��A�����I�ɓ�d�̐��Ƃƍl����B
�@�@�@�@�@(�cɂ�^��" �;;;;;;,,,.. �T�@�@�@�@�@�j �� �i
�@�@�@�@�@);;; �S�;;;;...__,,�@�@�j;;;;;;;; �S�@�@�@�@�j �� �i
�@�@�@�@�@i:::) ` ;;�[--�`�@�q;;;;;;;::;;; i�@�@�@�j �� �i
�@�@�@ i�@i::/ �@ ^:::::::..�@i�@ ,ll/�i ;; l�@�@ �j /�@�i
�@�@�@ i�@l �S�R''�@�@�@�@߁@�@ )�j�;; /�@ �j ���@�i
�@�@i�@|�@ | i���`i,�@�@�@�@ (_�^i;;; |�@�@�j !!�@�i
�@�@|�@|�@ ! �M��]'"�@�@�@ �^�@�@�U:l�@�@�� (��
�@�@i�@l|�@ ! "�P �@,,,. �^,;�@�@�@ �i�@�@�@�@�@�@|l
�@�@|�@|i�@ �S��--;�]'�@,;;�@,;�@�@�@Ё@||i�@il�@�@ i|
�@�@|�@ll�@ �Q|�c"�@ ,'�@;�@�^'�P�O�P''''�_�@�@||
�i�R�j�u���ƂȂ����Ɓv�̘_��
���̂悤�Ȕᔻ�ɑ��ẮA�u���ƂȂ����Ɓv�v���A�������Y�@���_��ٕ̈��ł��邩�ɂ��āA�_���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�����m�̏����i���`���E�Y�@��̏����S�S�X�Łj
���ƂƂ͑��̎҂̏��ׂ������Ȃ̍s�ׂ̈��ʓI�o�߂Ƃ��Ă���ɕ�ۂ��邱�ƁA���̈Ӗ��ł͑��̎҂ƍs�ׁE�����E���ʊW��
�������邱�Ƃɂ���Đ������A���̂������́u���̎҂̍s�ׁv�����ƂƂ����ƔۂƁA����̍\���v���ɊY������ƔۂƂ́A����
�҂ɂƂ��Ă͏d�v�����A���ƂɂƂ��Ă͊S����Ƃ���ł͂Ȃ������̂ł���B
�A�쑺�����̏����i�쑺���E�����Ƃ̌����i�P�X�W�S�j�R�Q�P�Łj
���Ƃ́A���Ȃ��Ƃ����炩�̈Ӗ��ň�@�ȍ\���v���ɊY������s�ׂ̈ꕔ�̋����Ȃ������p�ɂ���Ċe���̔ƍ߂��������ׂ�����
�ƍl����ׂ��ł���B������Ƃ��́A�E�̂悤�ȍs�ׂɏ]�����āi�������Ƃ��܂߂āj���Ƃ���������Ɠ����Ɋe���̔ƍ߂̎�����
�ԗl�ɉ����ċ��Ƃ���������Ɖ����ׂ��ł��邩��A���ƎҊԂɐ�������ߖ����ʈقł��肤�邵�A���Ƃ̂Ȃ����Ƃ�F�߂邱�Ƃɂ�
����x��͂Ȃ����̂ƍl����B
�B���R���m�̏����i���R�S�V�V�Œ��S�j
�������d��Ƃ���A�g����ړI�������s�ׂ������I�Ȑ��Ɓi���ۂɂ͏]�Ƃ܂��͕s���j�Ƃ��āA����ւ̋������݂Ƃ߂�
���ƂɂȂ�ł��낤���A���̕����`���I�ȊԐڐ��Ɛ������Â�������A�������ɑ��������������ł͂Ȃ������Ǝv����B
�C���c���m�̏����i���c�Q�X�P�j
�Ԑڐ��Ƃ�F�߂�ׂ��ꍇ�����肦�悤���A�ʏ�͋����Ƃɂ����Ȃ��ƍl����ׂ��łł͂���܂����B��g���҂́A�u�g���v��������
�������Ƃ���A�@����u���Ɓv���肦�Ȃ��Ƃ��������ł����āA������u���Ɓv�Ƃ��Ă̎��i���Ƃ��A�������̍ȂƂ��Ă̎ӂ��
�����̌��j�������Ă���Ƃ����Ă��������Ȃ��ł��낤����A������̐��Ɓi�@����̛Ɓj�Ƌ����Ƃ̊W��F�߂邱�Ƃ́A
�K�������A���s�@�ɔ�������̂ł͂Ȃ��Ǝv����B
�i�S�j�R�������̌����i�R���W�Q�Q�j
�U�T���P���́A�u�Ɛl�̐g���ɂ���č\�����ׂ��ƍߍs�ׂɉ��������Ƃ��́A�g���̂Ȃ��҂ł����Ă��A���ƂƂ���v
�ƋK�肷��B����́A�^���g���Ƃ���u�ƍߍs�ׁv�Ɋ֗^�����҂͋��Ƃł���Ƃ����|�ł���B�u�ƍߍs�ׁv�Ƃ́A
���Ƃ݂̂łȂ����Ƃ����܂ށB�Y�@�́A�u���Ɓv�Ȃ����u���s�s�ׁv��\���Ƃ��́A���̂悤�ȕ�����p����i�U�O���`�U�Q���Q�Ɓj
�ɂ�������炸�A�U�T���P�����A�u�ƍߍs�ׁv�Ƃ���������p���Ă���̂́A���Ƃ݂̂Ȃ炸�A���Ƃ����܂܂����|������ł���B
���̂悤�ɂ��āA�^���g���Ƃɂ����Ĕ�g���҂𗘗p�����g���҂́A��g���҂��Ƃ����u�ƍߍs�ׁv���s�����̂ŁA����ɏ]��
���āu�����Ɓv����������B��g���҂̕��́A���p�҂���g���҂̋����ɏ]�����ěƂ���������̂ł���B
�i�T�j�y�����z
�悭�߂Ă݂�ƁA�U�P���P���́u�w�l�x���������Ĕƍ߂����s�������ҁv�ł���A�u�w���Ɓx���������Ĕƍ߂����s�������ҁv
�ł͂Ȃ��B�U�Q���P���i�j�́u�w���Ɓx������ҁv�ł���A���@�҂́A���炩�ɁA�u�l�v�Ɓu���Ɓv�ɈӖ��̈Ⴂ���������Ă���
�ƍl������B
�u�l�v�Ƃ́A�K�������u���Ɓv�ł���K�v�͂Ȃ��B�i������́j�u�Ɓv�ł��悢���A���邢�͉��炩�̗��R�ŕs���̎҂ł��悢
�ꍇ������ł��낤�B
�u���ƂȂ����Ɓv�͔F�߂���B�ہA���̍\�������A�����Ɂu�K�͓I�v�ɊԐڐ��Ƃ�F�߂�������Ԃɑ����Ă���B
�����ƛ̈Ⴂ����A�Ⴂ�������Ă���̂ŁA�l�Ɛ��Ƃ������ċ�ʂ��Ă����
�l����̂͂���������ˁB����ρA�N���ق��ˁB
���ق��悗����R
���ƂƂ���ȊO���s�x�z���̗L��
���s�`�Ԃŋ��Ɛ��f����B
�����������B����
���@���Ƌ��Ƃ̋�ʂɍs�x�z�����̂�A
���Ƌ��Ƃ̋�ʂɍs�x�z�����̂�A���Ƃ̔ƍ߂�
1 �ƍߋ������ƍs������
�������Ƃ́A�����u�����v����̂ł��傤���B
�u�����v�̔ƍ߂���������ƍl���錩�����u�i���S�j�ƍߋ������v�Ƃ����A���s�s�ׂ̎�ނ��قȂ��Ă�
�s�ׁE�����E���ʉߒ�����������悢�Ƃ��錩�����u�s�������v�Ƃ����܂��B
���݂ł́A���S�ƍߋ������͎p�������A�\���v���̏d�Ȃ荇���͈͓��ŋ������Ƃ�F�߂�u�����I�ƍߋ������v
�i�c���R�X�O�A���c�Q�U�V�A��˂Q�W�Q�A��J�S�O�Q�A���v�ԂR�X�X�A��c�S�U�U�j�Ɓu�s�������v
�i�A�c�P�T�Q�A������R�T�O�A���Q�P�X�A���R�S�T�P�A�쑺�R�W�U�A�����P�R�U�R�A�O�c�S�W�R�A���c�R�W�V�A
�R���R�O�Q�j���Η����Ă��܂��B
A����A�y�S�I�X�P�����z�i���a�T�S�N�S���P�R���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�����I�ƍߋ������ɂ��AX��Y�̍ߐӂɂ��A�E�l�߂̋������Ƃ��������AX�͂R�W���Q���ɂ�菝�Q�v����
�͈̔͂ʼnȌY�����Ƃ��錩���i�����������I�ƍߋ������j�ƁA���Q�v���߂̋������Ƃ���������Ƃ��錩��
�i���炩�������I�ƍߋ������j�Ƃ�����܂��B
�{����́A�u�����������I�ƍߋ������v�m�ɔے肵�܂������A�u���炩�������I�ƍߋ������v���̗p
�����̂��A�u�s�������v���̗p�����̂��͖��炩�ł���܂���ł����B
���������̒��ŁA�ō��ق͑O�ɐG�ꂽ�y�S�I�U�����z�i�����P�V�N�V���S���F�V���N�e�B�p�b�g�����j
�ŁA�u���炩�������I�ƍߋ������v���̗p���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B���̓_�ł͊w���̕]���͈�v
����̂ł����A�O�c�����P�l���u�s�������v���̗p�������̂��v�Ɗ撣���Ă��܂���
�������ė������ꂽ�u���炩�������I�ƍߋ������v�́A���͂�u�s�������v�ƍ����Ȃ��A�X�P����
�ł́uX�ɂ͏��Q�v���߂̋������Ƃ��AY�ɂ͎E�l�߂̋������Ƃ���������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���씎�m�́A�������P�X�V�T�N�u������I�ƍߋ������ƌĂԂ��Ƃ��ł��悤�B�������Ƃ���ƁA����
���_�́A�s�������Ƃ��������Ȃ����ƂɂȂ�v�i����R�U�T�j�Ɗ��j���Ă����܂����B�����I�ƍߋ�����
���̂��J�������A�[�I�ɁuA�̐ޓ��AB�̋������ꂼ��ɂ��Ĕƍ߂̋�����F�߂�ׂ��ł���v��
�q�ׂĂ��܂��i��J�S�O�Q�j
�Q�@�������Ƃ̐����v��
�i�P�j�������s�̈ӎv
�@�ƍߋ������ɂ�闝��
�������s�̈ӎv�i���������̈ӎv�j�́A�Q�l�ȏ�̎҂��������Ď��s�s�ׂ��s�����Ƃ���ӎv�A���Ȃ킿�A
�s�ғ��m�����ꂼ��̍s�ׂ��y���p�������A��[�������āz�ړI�𐋂��悤�Ƃ���ӎv���]���܂��B
�i��˂Q�X�P�A��J�S�O�X�j
�s�ґo���ɋ������s�̈ӎv�y�ӎv�̘A���z���K�v�Ƃ���܂��i�c���R�X�P�j
�A�s�������ɂ�闝���@
���Ȃ̍s�ׂ����l�̍s�ׂƁu���ʓI�Ɍ������Ĕƍ߂���N����Ƃ��������̗\���Ȃ����\���\���v
���]���܂��i�A�c�P�U�X�j
���̋��������̈ӎv�́A�ӎv�̑��ݘA�����Ӗ�������̂ł͂���܂���B���Ȃ킿�A�Q�l�ȏ�̎҂ɑ��݂�
�Ƃ��ɑ��݂���K�v�͂���܂���B�ڂ����́u�ЖʓI�������Ɓv�̍��ŏq�ׂ܂��B
�i�Q�j�������s�̎���
�Q�l�ȏ�̎҂��������Ă��ꂼ��̔ƍ߂̎��s�s�ׂ��s�����Ƃ��K�v�ł��B�u�������āv�Ƃ́A���l�̍s�ׂ�
���ʓI�e�����y�ڂ����Ƃ��Ӗ����܂��B���̂悤�Ȉ��ʓI�e���́u�����I�e���v�Ɍ��炸�u�S���I�e���v�ł�
�\���܂���B
�������ƂƂ���邽�߂ɂ́A���Ȃ��Ƃ����ꂼ��̍s�ׂ��A���s�s�ׂ̈ꕔ���Ȃ����̂łȂ���Ȃ�܂���B
���s�s�ׂ̈ꕔ�݂̂S�����ɂ����Ȃ��Ƃ��Ă��A���̎҂̎��s���A������[���A���Y�s�҂̎��s��
�A���������A�S�̂Ƃ��Ď��s�s�ׂƂȂ�܂��B
���̂悤�ɁA���s�s�ׂ̈ꕔ�̕��S�ɂ���đS�̓I�s�ׂ̐ӔC�����Ƃ��u�ꕔ�s�ׂ̑S�̐ӔC�̌����v��
�]���܂��B
�R�@�ЖʓI��������
�]���́A�ƍߋ��������ے�A�s���������m��Ƃ����}�����Ó����Ă��܂������A
�ŋ߂ł́A�ƍߋ������E�s���������킸�A�ے�����L�͂ɂȂ��Ă��܂��B
����ɂ��ẮA�e���̋��ȏ��Ŏ��K���Ă��������B
�S�@���p�I��������
�m����E�ے���E���Ԑ�������܂����A����Ɋւ���ō��ٔ���͂���܂���B
�e���̋��ȏ��Ɓy�S�I�W�R�����z�y�W�S�����z�Ŏ��K���Ă��������B
�T�@�ߎ��̋�������
����ɂ��Ă��������e�Ղł�����A�e���̋��ȏ��Ɓy�S�I�W�P�����z��
���K�����������B
�u�ً}�撲���v�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����͂��̕ӂŁB
���u�ł́A�������Ƃ̗ތ^�̂Ȃ��ł��ł��d�v�ȋ��d�������Ƃ����グ�܂��B
�@�@
�u�����`���̋����ᔽ�v�����ł����Ȃ�m���ɊȒP�����ǁB
�ō��ق̃z�[���y�[�W�ŒT�������q�b�g���Ȃ��B�N�����������Ăق����B
�T���N�X�B�����ǂ�ł݂�B
���d�������Ƃɂ��ẮA���ߌY�@�W�P�T�ňȉ��Ɍ̓��c����Y�����̏ڍׂȕ��͂�����܂����A
�{�u�ł́A���d�������Ɣے���ɗ����āA�������q�ׂ����Ǝv���܂��B
�P�@���@��
B����A�y�S�I�V�T�����z�i���a�R�R�N�T���Q�W���F���n�����j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�{�����́A
�@���d�҂́i�����j���Ɛ����A���l�̍s�ׂ�����Ύ��Ȃ̎�i�Ƃ��čs�����Ƃ����A�����ӎv��̐��Ƃ͈����
�@�悵���_���ɂ���čm�肵�����ƁA
�A�i�ז@��A���d���߂ƂȂ�ׂ������ł���A���i�ȏؖ��̑ΏۂƂȂ邱�ƁA
�̂Q�_�ɂ����ďd�v�ȈӋ`��L���܂��B
����C����A�y�S�I�V�U�����z�i�����P�T�N�T���P���F�X���b�g�����z�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r
��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�{����́A
�@�����W�ɂ���ẮA������u�d�c�v���Ȃ���Ȃ��Ƃ��A���d�������Ƃ�F�߂邱�Ƃ��ł���ꍇ�����邱�ƁA
�A���d���َ��̂��̂ł������ꍇ�����邱�ƁA
�������_�ɏd�v�ȈӋ`������܂��B
�@
�Q�@�w�@���@
�i�P�j�����ӎv��̐��[����^��Y
�߂�Ƃ����߂ɋ��Ǝ҂����S��̉����āA�����ӎv��̂Ƃ������l�I�c�̂��`�������A���̍\�����̒N����
�ƍ߂̎��s�s�ׂ��s���A����́A���̋����̂ɋA�������B�������A���݂̌Y�����l��ΏۂƂ��Ă��邽�߁A
���̐ӔC�́A���@��A�g���̊����ɂ��đg�����S�����ӔC���̂Ɠ��l�ɁA�����̂��`�������e�l�S����
����U����A����́A�����ӎv��̌`���Ɋ֗^�����҂͊F�������ƂƂȂ�B
�i�Q�j�Ԑڐ��Ɨގ����[���؉p�Y�E���I��@���̗��_�i�P�X�U�V�j�R�Q�S�ňȉ�
�Q�l�ȏ�̎҂��ƍߐ��s�ɂ��č��ӂɒB�����ꍇ�A���̂Q�l�̍s�����݂��Ƃ��́A�Ԑڐ��Ƃɂ����闘�p�W
�ɑΔ䂷�ׂ����̂������Ɍ��o�����Ƃ��\�ł���B���d�҂��A���l�ƍ��ӂ̏㋤�����đ��݂ɗ��p��������
���ʂ����������Ƃ����Ӗ��ŁA�����̎��s�������҂ƔF�߂邱�Ƃ��\�ƂȂ�B
�i�R�j�c�����[���a�T�V�N�V���P�U���̒c���ӌ�
�L�͂ȋ��d�������Ɣے�_�҂ł������c�����m�́A�ō��ٔ�������A�y�S�I�V�W�����z���_�@�Ƃ��čm�����
���݂���܂����B
�{�l�������҂Ɏ��s�s�ׂ�������ɂ��Ď����̎v���悤�ɍs�������{�l���g�����̔ƍߎ����̎�̂ƂȂ���
���̂Ƃ�����悤�Ȃ����ɂ́A���p���ꂽ�����҂����s�s�҂Ƃ��Đ��ƂƂȂ�̂͂������ł��邪�A
���s�s�ׂ��������{�l���A��{�I�\���v���Y�������̋��������҂Ƃ��āA�������ƂƂȂ���̂Ƃ����ׂ��ł���B
�i�S�j��ː��i�D�z�x�z�������Ɛ��j�|��˂R�O�V��
���s��S�����Ȃ����d�҂��A�Љ�ϔO��A���s�S���҂ɑ��Ĉ��|�I�ȗD�z�I�n�ʂɗ����A���s�S���҂ɋ���
�S���I�S����^���Ď��s�ɂ����点�Ă���ꍇ�ɂ́A�K�͓I�ϓ_���狤�����s������Ƃ�������B
��w�Ŏd�����ɁA�ꐶ�����Q�����˂�Ƀ��X���Ă���Ă̂�
�ǂ����Ǝv�����ǁA���Ɩ��ID���ς���Ă�Ƃ����邩��A���ƂɋA���Ă�
�\�����������B
�i�T�j������[����R�X�W�ȉ�
���̐��Ǝ҂̐S����ʂ��ĊԐڂɔƍ߂̐��s�ɑ傫�Ȏ����I�������ʂ�������
���������ƂƂ��邽�߂ɁA��ϓI�v�f�Ƌq�ϓI�v�f���狤�d�������Ƃ̓��e��
���m�ɂ��A���肵�Ă������Ƃ��錩���ł��B
���m�́u����͖@����̉����Ă䂭���̂ł���A�w���͂��̂��߂̎Q�l�ӌ���
�����Ȃ��v�Ƃ̔F������u���d�������Ɨt�̊T�O�́A����Ίm�����������
�Ȃ��Ă���v�u�������Ƃ��������ŁA�ǂ̒��x�܂ʼn��߂ɂ���Č���ł���
�ł��낤���Ƃ��������݂��������A���@�ɂ��C���ɂ�������l�������̂�
�킪���̖@����̕��̂�����ɂق��Ȃ�Ȃ��v�Ɗw����ᔻ���܂����B
���ؔ��m�̌l��`�I�w���ւ̓]���A�c�����m�̉����A�����ď�̂悤�ȕ���
���m�̖���N���āA�w���ł́A�m�����O��Ƃ�����ŁA��̓I�ɑÓ���
�����͈͂��悻���Ƃ����������������ƂȂ�܂����B
����́A���c���A������A���c����������܂��B
�S�����쎩���̓���l���ł��邱�Ƃ͖��炩�B
��J�搶�������ȕ����Ăǂ����H
�i�U�j���c���i�����s�������Ƙ_�F�d�v�Ȗ������j�|���E����Ê�i��j�R�V�T��
�ƍ߂̎����ɂ����Ď��s�̕��S�ɕC�G���A�܂��́A����ɏ�����قǂ́y�d�v�Ȗ����z ���ʂ������ƔF�߂���ꍇ�ɋ������Ƃ�F�߂܂��B
�\���v�������ɂƂ��ďd�v�Ȉ��ʓI��^������������Ƃ�F�߂܂��B
�y�ᔻ�z
�@�j�������d�v�Ȗ������ʂ����Ă���̂ł���A�d�v�Ȗ������ۂ��ł́A�������ƂƋ�������ʂł��Ȃ��B
�A�j�d�v�Ȗ������ۂ��̔��f���A���ʂ̎���̑����t�ʂɂ���Č��܂�̂ł́A�����͈͂��s���m�ƂȂ�B
�i�V�j������[���E�u�ߎ��Ƃ̋������Ƙ_�i�Q�j�v�@��117��12���i�Q�O�O�S�j�P�U�X�U��
��L�̂悤�ȁu�d�v�Ȗ������v�ɑ���ᔻ���ӎ����āA
�@�݂������̋��Ǝ҂ɑ��Ĉ��ʓI�e����^����Ƃ����Ӗ��ł̑o�����I�Ȉ��ʓI�e���͂�v�����A�����Ƃ̋�ʂ͂���ōs���A
�@�[�i�@�j�̔ᔻ�ɑΉ�
�A�d�v�Ȗ����̊T�O�m�����ׂ��A������A���O�I�Ɍ��Ċ����\���v���ɊY��������s�ׂ��s�����ꍇ��
�@���ʂƂ̉���I�����W������ꍇ�ɂ̂ݔF�߂�[�i�A�j�̔ᔻ�ɑΉ�
�Ƃ����������咣����Ă��܂��B
�i�W)���c���[���ߌY�@�W�Q�X��
�@�w��҂��A���d�ɐϋɓI�ɎQ������ȂǁA���s�s�ғ��ƐS���I�ɋ������т��Ă���A���s�s�ׂ��w��҂ɂƂ��Ă�
�u�����̂��́v�ƕ]���ł���ꍇ���A���邢�́A
�A�w��҂̍s�ׂ����Y�ƍs�ɂƂ��ĕK�v�s���ȈӖ��������Ă����ꍇ
�́A�����ꂩ������F�߂���A�������ƂƂ��ׂ��ł���Ƃ��܂��B
�������Ƃ�P�Ɛ��ƂƂ̃A�i���W�[�Ő������邩�A�������ƌŗL�̋A�Ӗ@���Ƃ��Đ������邩
�Ƃ����Η�����������Ɛ������Ȃ��ƁB
�R�@���d�������Ɣے���@
�i�P�j���d�������Ƙ_�̔w�i
��Ō����悤�ɁA���d�������Ƙ_�̎����I�����̈�ɂ́A���ƊW�ɂ����āu�d�v�Ȗ����v�i�����E�ƍߎ��s�s�ט_�R�R�X�Łj���ʂ������҂𐳔ƂƂ��ׂ����Ƃ���
�����I�l�@������܂��B����́A�����Ƌ�̓I�ɉ]���u�����d���_�v�ł��B�����́A�u���Ƃ̌Y���Ȃ���v�̂ł�����A���s�s�ׂɏo�Ȃ������w��҂������Ƃ��ď���
���邱�Ƃɂ���Ă��A���ƂƓ����Y���Ȃ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�������A�������o�Ƃ��ẮA���s�҂̔w��ɍT���鍕���E�ƍ߂̒��S�l���𐳔ƂƂ������Ƃ����v��������܂��i�ēc�E�ƍ߂Ɖ��I�]���Q�O�T�Łj�B���s�҂̔w���
�ƍߌv��𗧈Ă��A�w�߂��o���A�w���E�ē���啨�́A���`�I�Ɏ��s�҂����d�v�Ȗ������ʂ����̂ł���A����������Ƃ���ƁA���s���Ǝ҂Ɠ����A���邢�́A
������d���Y���Ȃ���̂�����ł��邩��i����S�O�O�Łj�A�u��Ɓv�Ƃ������ׂ��w��҂��A�u���Ɓv�Ƃ��ׂ����Ƃ����̂ł��B
�i�Q�j�ے���̘_��
�@�U�O���́u�������Ĕƍ߂����s�����ҁv���������ƂƂ��Ă��邪�A����́A���s�s�ׂ�����s�����҂݂̂��������ƂƂȂ�Ƃ�����|�Ɨ������ׂ����ƁB
�A���d�������Ƃ�ے肷��̂����@�҈ӎv�ł��������ƁB
�B�m����́A�����ɔ��������߂ŁA�ߌY�@���`�ɔ����邱�ƁB
�i�R�j���@��
�w���ɂ�����ے���́A���܂����������̂�����܂��B
�i�����R�T�P�A�A�c�P�V�P�A���Q�T�T�A����R�R�W�A���c�Q�V�T�A�g��Q�T�T�A���R�S�U�V�A���c�Q�X�X�A��c�S�P�X�A�]���Q�W�R�A�R���W�V�V�j
���s�������Ƃ̌`���I���m���̊m�ۂ́A�ߑ�Y�@�̑匴�����ێ�����d�v�ۑ�ł����āA������`�����̘g�����z������ՂȎ������ɂ���āA
�@������ׂ��ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B
�P�@���Ƃ̏�������
�i�P�j�Ӂ@�`
���Ƃ̏���������_����Ӌ`�́A
�@�K�v�I����
�A�g���Ƃ̋���
�B�����̋���
�C�P�O�R���E�P�O�S���ɑ��l���ւ�����ꍇ
�D��Q�ғI����ɂ���҂̉���
�ɁA����I���_��^���邱�Ƃɂ���܂��B
�i�Q�j�ӔC���Ƙ_�E�s�@���Ƙ_�E���ʓI���Ƙ_
�@�ӔC���Ƙ_
�ӔC���Ƙ_�́A�ɒ[�]��������O��Ƃ��A���ƍs�ׂ̎˒��́A���Ƃ�ӔC�̂���ƍߍs�ׂɗU�v�������Ƃł���Ƃ��錩���ł��B
���݂ł́A���̌������̂�w���͖w�nj�������܂��A��˂Q�X�O�ŁA��J�S�O�O�ł́A�i�s�ז����l�^�j�s�@���Ƙ_�Ƃ��āA
���̌������p���ł���Ƃ����w�E������܂��i���ߌY�@�W�O�V�Łk���c�l�j
�A�s�@���Ƙ_
�s�@���Ƙ_�́A���Ǝ҂��u��@�ȍs�ׁv�ւƗU�v������A���Ǝ҂��x������_�ɁA�������������߂܂��A�����]�������̂��ƂŁA
���ƕs�@�̍����Ƌ��Ƃ̂���Ƃ͍��{�I�ɈقȂ���̂Ɖ����܂��B�킪���ł́A���̌����́A�ߖ��]�������ɌŎ��������A
���ƌ��ʂ̎�N�����A���Ƃ́u���s�s�ׂ̎�N�v�ŋ��Ƃ̎˒��͐s����Ƃ��錩���Ɍ���Ă��܂��B
��̓I�ɂ́A���Ƃ��u�C�����ꂽ�\���v���v�ɊY������Ƃ��錩���i�c���R�V�R�A��˂Q�W�P�j�A�Ȃ���������N�����̂��
���̂��錩���i��J�S�O�O�j������ɑ����܂��B
�B���ʓI���Ƙ_�@
���ʓI���Ƙ_�Ƃ́A���ƂƋ��Ƃ̍ߎ��E����������{���I�ɓ����ƍl���錩���ł��B���̊w���́A�Y�@�̔C���͖@�v�̕ی�ł���A
���Ə��������̈���Ƃ��āA���Ƃ�ʂ��ĊԐړI�Ɍ��ʂ���N���邱�Ƃ����Ƃ̏��������ł���Ƃ��܂��B
�i�R�j���ʓI���Ƙ_�����̑Η�
�@�C����N��
�i�R�j���ʓI���Ƙ_�����̑Η�
�@�C����N���i���ƕs�@��N���F�h�C�c�̒ʐ��j
���Ǝ҂����������̂́A���Ƃ̍s�ׂ�U�v�E���i��������ł���A���Ƃ́A���ځA���ƌ��ʂ���N����̂ł͂Ȃ��A
���ƍs�ׂ�U�v�E���i���邱�Ƃɂ���ĊԐړI�Ɏ�N����Ƃ��錩���ł��B
�킪���ɂ����Ă��A��@�̘A�ѐ����������A��N����W�Ԃ���
�i�R�j���ʓI���Ƙ_�����̑Η�
�@�C����N���i���ƕs�@��N���F�h�C�c�̒ʐ��j
���Ǝ҂����������̂́A���Ƃ̍s�ׂ�U�v�E���i��������ł���A���Ƃ́A���ځA���ƌ��ʂ���N����̂ł͂Ȃ��A
���ƍs�ׂ�U�v�E���i���邱�Ƃɂ���ĊԐړI�Ɏ�N����Ƃ��錩���ł��B
�킪���ɂ����Ă��A��@�̘A�ѐ����������A��N����W�Ԃ��錩���́A�h�C�c�̏C����N���������ʓI�_�@��
�d�����܂����A�ꉞ�A���̐��ɑ�����Ɖ]���Ă悢�Ǝv���܂��i����R�T�S�A�����E�@�w�����P�P�S���V�R�Łj
�������A���̌����́A�s�@���Ƙ_�̗���ɑ��Ȃ�Ȃ��Ƃ����w�E������܂��i��c�S�W�Q�A�����R�V�P�j
�A������N���i�I�s�@��N���j
���̌����́A��N���ɂ͗����܂����A���ƂƋ��Ƃ̈�@�̘A�ѐ����A�C����N���̂悤�Ɍ��i�ɂ͉������A
��@�̑��ΐ������m�肵�A���ƓƎ��̕s�@�Ɛ��Ƃ̕s�@�̓_�I�ȕs�@�̍����Â����s���܂��B
���̐��́A�@
�@�j���ƂƋ��Ƃ̍ߖ��Ɨ��������͈̔͂ōm�肷����́[�������v�E���Ƒ̌n�Ƌ��Ɨ��_�i�P�X�W�W�j�P�U�U��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��z�`�v�E���Ƙ_�čl�i�P�X�W�X�j�P�W�P��
�A�j�ŏ��]���������̂�Ȃ���A�܂������ߖ��]������ے肷��킯�ł͂Ȃ����́[���c�R�W�W�A�O�c�S�U�U�A�����m�u�R�W�O
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c����Y�u�K�@�s�ׂ𗘗p�����@�s�ׁv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����T�T���i�Q�O�O�O�j�R�O��
�B�j������N���Ɍ���Ȃ��߂Â����A�����]���������ێ����u���Ƃɂ���@�ȍ\���v���̎����v��v���������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�R�����E���T���Q�S�R��
�ȂǑ��푽�l�ł��B
�ق��ɁA��c�����i��c�S�W�P�j�A���������i�����R�V�P�j��������N�����x�����Ă��܂��B
�@
�B������N��
������N���́A�O��Ƃ��āA�s�������E�ߖ��Ɨ��������̂�A���S�ȋ��ƌŗL�Ɛ����咣���܂��B�����Ȃ�Ӗ��ł��A���Ƃ̈�@���ɏ]�����āA
���ƍs�ׂ���@����тт�킯�ł͂Ȃ��Ƃ��܂��i������R�R�Q�A�A�c�P�T�Q�A���Q�Q�O�A���R�S�S�S�j
�܂��A�����I�ɁA���ƍs�ׂ́A�\���v���Y���s�ׂł��邱�Ƃ�v���Ȃ��A�܂�A�ŏ��]��������ے肵�܂��i������E���Ɨ��_�̌����i�P�X�W�V�j
�U�X�ŁE�P�P�T�ŁA�A�c�d���E���Ƃ̊�{���i�P�X�T�Q�j�P�O�V�ŁA���`���E�Y�@��̏����i�P�X�X�P�j�S�V�W�Łj
����ɂ��A�@�ߎ��함����̋��������I�ł���A�A��t�̉ߎ��閧�R�������������Ō�t�����I�ƂȂ�܂��B
�C�R�����i���I�s�@�]�������F�R���W�O�W�j
�i�����́j������N�����C�����āA���Ƃ̏����͐��Ƃ́u���I�s�@�v�ɏ]������Ƃ��܂��B
�܂�A�A���Ƃ̍\���v���Y�����͕s�v�Ƃ�����̂́u���ƌ��ʂ���@�ł��邱�Ƃ́A���Ɛ����̑O��ƂȂ�v�Ƃ��܂��B
�y�����z������Ɏ^���ł��B
����ɂ��A�@�ߎ��함����̎���ł́A�험�p�҂ɂ͉��I�ȋK�͓I��Q���Ȃ��A���p�҂͊Ԑڐ��ƂƂȂ�A�A�ł́A�Ō�t�ɐg�����Ȃ��A
�閧�R���߂́i�Ԑځj���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA�s���ƂȂ�܂��B
�u�`����҂������ɍl�������������̉ߒ����w���Ɍ��������Ȃ�B
�����Ɣ�����ڂ��������Ă��Ȃ��ƁA�w������͌����������⎑�i�����ɑΉ��ł��Ȃ����낤�B
�ǂ����w�Ҏ��g�����C���Ȃ����Ȃ��B
�Q�@���Ə]����
�������́A���Ə����𐧖�v�f�Ƃ��āA�]������F�߂Ă��܂��i���Ƃ̌��萫�j
�]�����ɂ́A�@���s�]�����A�A�v�f�]�����A�B�ߖ��]�����A�C�̈ӂւ̏]����������܂��B
�i�P�j���s�]����
���s�Ɨ������Ƃ́A���Ƃ̏����́A���Ƃ̎��s�̒����҂��ƂȂ��A���ƍs�ׂ��s����Ή\�ɂȂ�Ƃ�������
�ł���A���ĐV�h�̘_�҂ɂ���Ď咣����܂������i�q��i���j�U�V�V�A�ؑ��R�X�S�j�A�����ł́A���Ƃ̏����́A
���Ƃ����s�s�ׂɏo����ɂ͂��߂ĉ\�ɂȂ�Ƃ�����s�]������������ł��B
�i�Q�j�v�f�]����
�v�f�]�����ɂ��ẮAM.E.�}�C���[�̂S�̏]���`���i�@�`�C�j���L���ł��B
�@�֒��]���������\���v���Y�����{��@���{�ӔC�{��������
�{���́A���Ƃ̏�����������d���y���R�����Ƃɉe�����y�ڂ��Ȃ��Ƃ��Ă��錻�s�Y�@�̑ԓx�i�Q�S�S���R���A
�Q�T�V���Q���A�U�T���Q���j�Ɩ������Ă���A�̂蓾�܂���B
�A�ɒ[�]���������\���v���Y�����{��@���{�ӔC
�{���́A�U�P���́u�ƍ߁v�̗����Ƃ��čł����R�ł��邱�Ƃ���A��O�́A���̐����ʐ��ł����B�������A�Ⴆ�A
�P�R�̎q���̔ƍߍs�ׂ𗘗p�����ꍇ�ɂ́A���Ƃ��������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�����s���Ƃ���킯�ɂ�
�����Ȃ��̂ŁA���̏ꍇ�A���Ȃ苭���ɁA�Ԑڐ��Ƃł���Ƃ����\�����̂��܂����B�������A���Ȃ̍s�ׂ�
�ƍߓI�Ӗ��������㗝�����Ă���P�R�̎q�����A���S�Ɂu����v�Ɖ]����̂��Ƃ����ᔻ������܂����B
�B�����]���������\���v���Y�����{��@��
�����ŁA���݂̒ʐ��́A�����]�������ł��B
�i�c���R�W�S�A���c�Q�T�Vf�A��˂Q�W�V�A���c�R�O�U�A��[�T�R�Q�A�тS�Q�T�A�R���R�P�Q�A��c�S�S�P�j
���̐��ɂ��A�U�P���̕������ߏ�A�u�ƍ߁v�ł͂Ȃ��u���s�s�ׁv�ɏ]������Α����Ƃ��܂��B
�܂��A�����I�ɂ́A�u��@�͘A�ѓI�ɁA�ӔC�͌ʓI�Ɂv�Ƃ����l����������܂��B
�C�ŏ��]���������\���v���Y�����@
�ŋ߂ł́A���ƊW�ɂ������@�̑��ΐ���F�߂闧�ꂩ��A�ŏ��]���������L�͉����Ă��܂��i�O�c�S�U�W�A�Ȃ�����R�T�W�D��J�S�O�V�A�����m�u�R�V�W�j
D����A�y�S�I�W�X�����z�i�����S�N�U���T���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq����v�|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�{�����͉ߏ�h�q�Ɋւ��鎖�Ăł����A����ʉ����Đ����h�q�ɉ��p���邱�Ƃ��ł��܂��B�m���ɁA����̖h�q�҂ɂƂ��ċ}���ȏł��邪�A�����ɋ}��
�łȂ��ꍇ�͗e�Ղɍl�����܂��B�A�ڍׂ́A���䋳���́q����r��ǂ�ł��������B
�D�v�f�]�������p�_
�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA������N���͍ŏ��]��������ے肵�܂��i������E�����U�X�ŁA�A�c�E��{���P�O�V�ŁA���E�����S�V�W�Łj
���������āA�u���ƂȂ����Ɓv��F�߂܂��B
�E���I�s�@�]������
������O�ɏq�ׂ��悤�ɁA�ŏ��]������ے肷�邪�A���Ƃ̏����́A���Ƃ́u���I�s�@�v�ɏ]������Ƃ��������ł��B
�R�������̒i�R���W�O�W�j�ɂȂ���̂ł����A���R���m���x�����Ă����܂��i���R�E�T���Q�P�T�Łk��ʈ�@�]�������l�j
����́A���Ƃ̍\���v���Y�����͕s�v�ł����A���ʖ����l�_�I���n����A���Ƃ���@�ł��邱�Ƃ͑O��ƂȂ�Ƃ��������ł��B
���������āA�u���ƂȂ����Ɓv��F�߂�͈͂́A�D���������܂�܂��B
�R�@�ߖ��]����
���Q�����������Ƃ���A���s�҂��E�l��Ƃ��Ă��܂����Ƃ����ꍇ�A�ƍߋ������E�s���������킸�A�����҂ɂ͏��Q�v����������������Ƃ������Ƃ͈�ʂɏ��F����Ă��܂��B
�܂�A���ƂƋ��ƂƂł͍ߖ����قȂ��Ă��悢�̂ł��i�ߖ��Ɨ������j
�S�@�̈ӂւ̏]����
�ʐ��́A���Ə����ɂ�����A�̈ӂւ̏]������v�����܂��B
���W�����́y����P�U�z�����Ă��������B
�@��tX���A�E�ӂ������ēŕ��̓��������ˊ���Ō�tY�ɓn���Ă��������A�ɒ��˂��邱�Ƃ𖽂��A����A�����Ȃ������AY�͕s�K�Ȓ��˂ł��邱�ƂɋC�Â������B
�AX���A�o�����܂̏�p��A���E�Q���悤�Ƃ��āA�o�����܂ƋU���ēŕ�����n���A�m�炸�ɒ��˂���A�����S�������B
�����̎���i��c�����̐ݗ�ł��j�ł́A�̈ӂւ̏]�������m�肷��ʐ��ɂ��A�E�l�̌̈ӂ����������ƍs�҂����݂��Ȃ��̂ŁA�u�E�l�̋����v�ƌĂѓ��錋�ʎ�N��
�W���F�߂�ꂸ�A�w���X�������ƂƂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA�Ԑڐ��ƂƂ����ׂ��ł���Ƃ���܂��B
�������A���̂悤�Ȍ����ɂ͏��{�����̉s�����_������܂��i���{�Q�W�U�Łj
�H���A
�ʐ��́A���Ƃ̐����ɂ͐��Ƃ̌̈ӂ�v����Ƃ��錚�O���Ƃ�B�������A�����҂����ƂɌ̈ӂ��������ƌ�z���A���������Ƃ��̈ӂȂ��Ŕƍߌ��ʂ������N�������ꍇ�ɂ́A
�قƂ�ǂ̊w�����A���ƂɌ̈ӂ��Ȃ��Ă������Ƃ̐�����F�߂�B���Ƃ��A�c�����m�́A�u�����Ƃ͐l�ɔƍߎ��s�̌��ӂ����߂邱�Ƃł���B���������ĉߎ��Ƃ̋���
�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��v�i�c���E�S�O�R�Łj�Ɩ������Ȃ���A��̂悤�ȏꍇ�ɂ́u�����炭�A�����̌��x�ŐӔC������ׂ��ł��낤�v�i�c���E�S�Q�X�Łj�Ƃ���B
�܂�A�u�����Ƃ̐����ɂ́A�q�ϓI�ɐ��Ǝ҂ɔƍ߂����s������悢�̂ł����āA�̈ӂ����������ۂ��͏d������Ă��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���B
�̈ӂւ̏]�����͔ے肳���ׂ��ł��傤�B
�Ԃ��Ă����̂́u�Y��Ȃ��łق����v�Ƃ������t�ł����\�B
��http://www.greenpeace.org/japan/remember/
�������̂Ŕ�Q���������̕��X�Ɂu�������ɂł��邱�Ƃ́H�v�Ƃ����������Ƃ���A
�Ԃ��Ă����̂́u�Y��Ȃ��łق����v�Ƃ������t�ł����\�B
��http://www.greenpeace.org/japan/remember/
�������̂Ŕ�Q���������̕��X�Ɂu�������ɂł��邱�Ƃ́H�v�Ƃ����������Ƃ���A
�Ԃ��Ă����̂́u�Y��Ȃ��łق����v�Ƃ������t�ł����\�B
��http://www.greenpeace.org/japan/remember/
���{�������c���]���`���̒�`�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ���������Ă�B
http://proftanuki.jugem.cc/?eid=39
�R�@���@��
�i�P�j�K�v�I����
E����A�y�S�I�X�X�����z�i���a�S�R�N�P�Q���Q�S���j�́q�����̊T�v�r�Ɓq���|�r��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�@���@�҈ӎv���[���a�T�Q�N�R���P�U���̒c���⑫�ӌ�
����ƍ߂���������ɂ��ē��R�\�z����A�ނ���A���̂��߂Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ��֗^�s�ׂɂ��āA
�������������K�肪�Ȃ��ȏ�A������A�֗^�������̉��I�ȋ����E�Ƃ��ď������邱�Ƃ́A
�����Ƃ��āA�@�̈Ӑ}���Ȃ��Ƃ���ł���A�Ƃ��܂��B
���������āA�ϋɓI�Ȋ֗^�������ꍇ�ɂ́A���̌����̗�O�Ƃ��āA���ƂƂ��ď��������A�Ƃ��܂��B
�A�������[���열��E�ƍߘ_�̏����i��j�i�P�X�W�P�j�P�W�W��
���Y�����K�肪�A�֗^�s�ׂ��s�����u��Q�҂̕ی�v��ړI�Ƃ��Ă���ꍇ�ɂ́A�s��
�ł���Ƃ��܂��B���̗��ꂩ��́A�ٌ�m�@�V�Q���Ɉᔽ�����ي����̈˗��҂́A�\����
�ٌ슈�������Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł͔�Q�҂ł�����A�s���ł���Ɛ�������܂��B
�A���̕����A���ʓI���Ƙ_�ɉ������l�������Ɖ]���܂��B
�i�Q�j�����̋���
�u�����Ƃ̌̈Ӂv�ɂ��ẮA
�@���Ȃ̋����s�ׂɂ���Ĕ틳���҂�����̔ƍ߂�Ƃ����Ƃ����ӂ��A���̎��s�s�ׂɏo�邱�Ƃ����̈ӎv�̓��e�Ƃ��邱�Ƃ��Ӗ�����Ƃ����
�i�c���S�O�U�A��˂R�P�O�A���Q�X�W�A��J�S�R�R�A��[�T�U�Q�j��
�A�����s�ׂɂ��ƂÂ��Ĕ틳���҂���{�I�\���v������������ӎv�����v����Ƃ����
�i�ؑ��S�P�S�A���Q�T�U�A���R�S�V�R�A���c�Q�W�P�A�R���W�X�R�A�����m�u�R�W�S�A�����S�S�U�A�����R�V�R�j
�ɕ�����܂��B
���������āA�͂��߂��疢���ɏI��点��ӎv�ŋ��������u�����̋����v�́A�@������́A�����߂̋�������������̂ɑ��A
�A������͕s���ƂȂ�܂��B
�P�Ɛ��Ƃ̏ꍇ�ɁA�����ɏI��点��̈ӂ́A�̈ӂƂ͉]���Ȃ��悤�ɁA�����ł������Ƃ̋q�ϓI�ȍ\���v�������ƌ��ʂ�
��N�ɂ܂ŋy��ł��Ȃ��̂ł�����A�����̌̈ӂ́A�̈ӂƂ͂����܂���B
���������āA�A�����Ó����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�u���Ƃ������ƂŔ�������̂ɁA�����Ƃ��s���Ȃ̂͂��������v�Ǝv������́A�ӔC���Ƙ_�@�ł��Ă��Ȃ�����ł��B
�i�����m�u�R�W�S�ŎQ�Ɓj
�u�����̋����v�͋��Ƃ̏��������_�̎����ł��B
��J�������A������N�����̂�Ǝ��̂���Ȃ���A���ۂɂ͇@�����̂�̂ł�����A�s�@���Ƙ_�ł���Ɖ]�킴��܂���B
��J�����́A���S�Ɏ��ȗ���������Ă��܂��B���̂��Ƃ͑����̘_�҂��w�E���Ă��܂��B
�S�@��@��
�i�P�j�̈��ʊW
�y����P�V�z
X���A�ޓ���Y��A��̍�����n���AY�������p����A��ɐN���������AY�͍������Ȃ��Ƃ��J���p���p������
���K���X���������肵�ĐN���ޓ��𐋂��Ă�����������Ȃ��i���������̐���j
F����A�y�S�I�W�W�����z�i�������ٕ����Q�N�Q���Q�P���F����Ώ��E�������j��ǂ�ł��������B
�L��������܂����B
�w���́A�R�ɕ�����܂��B
�@���s�s�ב��i���i��˂R�Q�S�A��J�S�S�Q�A��[�T�T�Q�j
�{���́A�s�ׂƐ��Ƃ̎��s�s�ׂƂ̊Ԃɕ����I�܂��͐S���I�Ɏ��s�s�ׂ����i���ꂽ�Ƃ����Ӗ��ł�
���ʊW������Α����Ƃ��錩���ł��B
�{���́A�s�@���Ƙ_�̗��ꂩ�珥�����A�Ƃ̎˒��́A���ƂɎ��s�s�ׂ��s�킵�߂邱�Ƃɐs����Ƃ���
��������b�Ƃ��܂��B
�A���i�I���ʊW���i�h�C�c�̔���G����R�W�P�A�ؑ��S�Q�P�A���R�O�P�A���c�T�V�u�̈��ʊW�v
�@�w�Z�~�i�[�R�Q�Q���Q�S�ňȉ��A�����`���E����Y�@�_���k�T�l�R�S�P�ŁA�O�c�T�P�W�A�����m�u�R�V�Q�j
�{���́A�̏ꍇ�ɂ́A���ʊW�_�ɂ���������W�_���C�����A���ƌ��ʂ��̂��̂Ɗ��S�ȏ����W��
�K�v�łȂ��A�����e�ՂȂ炵�߂�悢�Ƃ��܂��B
�Ⴆ�A�ޓ������ӂ��Ă���҂ɌR���n�����҂́A���̛s�ׂ��Ȃ��Ă����ƌ��ʂ͐����Ă����������ꂸ�A
���S�ȏ����W�͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���ƌ��ʂ̎������u���i���A�e�Ղɂ����v�Ƃ������ʊW�͂���Ƃ��܂��B
�B���ƌ��ʎ�N���i�R���h��E�Y�@�ɂ�����q�ϓI�A���̗��_�Q�R�R�ŁE�Q�W�P�ŁA
��z�`�v�E���Ƃ̏��������P�V�Q�ŁA�]���ЕF�E����Y�@�_���k�T�l�R�S�Q�Łj
�{���́A���ʓI���Ƙ_�ɗ��r���A�Ƃ��A���Ƃ⋳���ƂƓ��l�ɁA���ƌ��ʂ���N���邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ�����ł��B
�@���́A�s�@���Ƙ_����̋A���ł���A�̂蓾�܂���B�A�����A��̓I����
���l����ƁA�@���Ɠ���ɋA�����ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�������āA���ƌ��ʂ̎�N�Ƃ����_���ێ�����B�����Ó��ł���Ɖ]���܂��B
�����A���̐����̂�ꍇ�A�u�s�ׂȂ���Ό��ʔ����Ȃ��v�Ƃ���������
�K�pl�ł��Ȃ��_�������ɉ������邩�����ƂȂ�܂��B
���̓_�ɂ��A�R���f�B�e�B�I�����ɑウ�č��@���I�����������̗p���A���Y
�s�ׂɂ���āA�@�v��Ԃ̈������邢�͖@�v�N�Q�̗e�Չ��Ƃ����`�ŁA
���ʂ���̓I�ɕύX���ꂽ���ۂ��A�Ƃ������f���Ó��ł���Ǝv���܂��B
�i�Q�j�����I�s�ׂɂ���
�Z���N�����s�����Ǝ҂ɁA����ƒm��Ȃ���h���C�o�[��̔������������̓X�����A�Z���N���̍ߐӂ����邩�H�Ƃ������ł��B
�ŋ߂ł́AWinny���������Ԃ̒��ڂ𗁂т܂����B
G����A���W�����́y����P�X�z�i�����Q�R�N�P�Q���P�X���j��ǂ�ł��������B
�q�����̊T�v�r
�퍐�l���A�t�@�C�����L�\�t�g�ł���Winny���J�����A���̉��ǂ��J��Ԃ��Ȃ��珇���E�F�u�T�C�g��ł�������J���A�C���^�[�l�b�g��
�ʂ��ĕs���葽���̎҂ɒ��Ă������A�������肵�����ƂQ���������p���Ē��쌠�@�ᔽ�̔ƍs���s�����B
Winny�̊J���҂��AWinny�̌��J�E�s�ׂ����쌠�@�ᔽ�̛s�ׂɂ�����Ƃ��ċN�i���ꂽ�B
�q����v�|�r
�@�퍐�l�́AWinny�����J�E����ɓ�����A�E�F�u�T�C�g��Ɉ�@�ȃt�@�C���̂��������Ȃ��悤���߂钍�ӏ���t�L������A
�@�J���X���b�h��ɂ����̎|�̏������݂������肵�āA�펞�A���p�҂ɑ��AWinny�쌠�N�Q�̂��߂ɗ��p���邱�Ƃ��Ȃ��悤
�@�x���������B
�A�����̓_���l������ƁA���܂��A�퍐�l�ɂ����āA�{��Winny�����J�E�����ꍇ�ɁA��O�I�Ƃ͂����Ȃ��͈͂̎҂������
�@���쌠�N�Q�ɗ��p����W�R�����������Ƃ�F���E�F�e���Ă����Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ͍���ł���B
�B�ȏ�ɂ��A�퍐�l�́A���쌠�@�ᔽ�߂̛Ƃ̌̈ӂ������ƌ��킴����A�퍐�l�ɂ����쌠�@�ᔽ�߂̛Ƃ�
�@�������Ȃ��B
�@
�@���������u�����I�s�ׂɂ��v�P�H�@�w�Q�V���Q�O�R�ňȉ�
�Ɩ��̒ʏ퐫�ɂ���āA�ʏ�s�ׂ𐋍s���ׂ����Ƃ���u�K�͓I�ȍs�ח\���v
���͂��炫�A���֎~����s�K�͂���ނ���B
�A���c����Y�E���ƁE���Ƙ_�̊�b���_�R�T�X�ňȉ�
�N���ޓ����v�悵�Ă���̂����܂��ܒm�������������A���̎҂Ƀh���C�o�[
��̔������ꍇ�ɂ́A�ߗׂ̓X�œ��l�̃h���C�o�[��������ꍇ�ɂ́A����I
��������l���ɓ����ƁA���Y�h���C�o�[�̔̔��́A���Ƃ̔ƍs�̊댯��
���߂Ă��Ȃ��Ƃ��āA��ے肷��B
�B�ȓc���u����I�s�ׂƏ]�Ɓv�@�w�V��P�P�P���R���P�S�P�ňȉ�
�m��I�̈ӂ��Ȃ킿�ƍߌv���m���čs��ꂽ�s�ׂɂ��Ă͉�����
�m�肵�A���K�̌̈ӂɂ��ƍߌv���m��Ȃ��ōs�����ꍇ�ɂ͔ے肷��B
�C�R���h��u�����I�s�ׂɂ��̉����v�֑�@�w�_�W�T�U���P���R�S�ňȉ�
�����I�s�ׂ̎�ނɂ���ėތ^�����A����ɉ������q�ϓI�A���_�ɂ�����
���}����ׂ��ł���B
�@�ɂ��ẮA�Ɩ��̒ʏ퐫�͈̔͂��s���m�ł���A���̋�̓I�v�����W�J
����Ă��Ȃ��A�A�ɂ��ẮA����I������̍l���́A��ʓI�ɋA�����f
�ɂ����Ă͋�����Ȃ��Ƃ���ׂ��ł���A�B�ɂ��Ă��̈ӂ̎�ނɂ����
�̍������_����Ă��Ȃ��A�Ƃ����ᔻ���\�ł��B
���̖��́A���ʓI���Ƙ_�ɂ��A���ƌŗL�̕s�@���e���ǂ̂悤�ɗ���
���邩�A�Ƃ������ł��B���̏ꍇ�A�u�ƍߓI�ȈӖ��A�ցv�i���N�V���j�́A
�u������Ȃ��댯�̑n�o�v���ۂ��Ƃ����q�ϓI�A���_�̖��Ƃ��Ĉʒu�Â���
���Ƃ��ł��A���̔��f��Ƃ��Ắu���Ȃ̍s�ׂ��A���Ƃ̔ƍߌv��Ȃ���
�ƍߍs�ׂɊ�{�I�ɓK������悤�ɁA���ʂɌ`���������Ɓv�i���ƍs�ׂƂ�
���ʂȌ����j���K�v�ƂȂ�܂��i�����S�T�R�Łj�B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A
���Ƃƛ����́u�A�ъW�v�i�V���[�}���j�ɂ���ƔF�߂��A�s��
�ɔƍߓI�ȈӖ��A�ւ��F�߂��܂��B
���������āA��{�I�ɂ́A�C�����Ó��ł���Ǝv���܂��B
���Ƙ_�̏d�v�e�[�}�u���ƂƐg���v�ɂ��Ă͏���������܂����A�����
���ẮA�U�T���P���͐^���g���ƂɊւ���K��A�Q���͕s�^���g���Ƃ�
�ւ���K��ł���Ƃ��锻��E�ʐ����������Ă����Ώ\���ł��B
�u���Ƃ���̗��E�v�ɂ��ẮA�S�I�łR���������グ���Ă��܂����A
���ʓI���Ƙ_�ʼn����ł�����ł��B�e���A���K���Ă��������B
����́A�ŏ��ɕۗ����Ă������u�\���v���_�v�ɂ��ďq�ׂ����Ǝv���܂��B
>���ẮA�U�T���P���͐^���g���ƂɊւ���K��A�Q���͕s�^���g���Ƃ�
>�ւ���K��ł���Ƃ��锻��E�ʐ����������Ă����Ώ\���ł��B
�������[�[�[�[�[�[�[�[�[�[�[��
�ނ��� >>840 ���@���I�����������̗p�̂����肱���A
���ʊW�_��ʂōu�`��O��Ƃ��āA
���@���I�����������̗p���闘�_�Ƃ���
��������Α���B
�_�ːV��NEXT 3��14��(��)16��38���z�M
�@�P�X�X�V�N�W���A�_�ˎs������̃z�e���Ŏw��\�͒c�R���g�̍ō������A����E��g�g���������i�U�P�j���Ǝ��Ȉ�t�����i�U�X�j�����ˎE�����Ƃ��āA
�E�l�Əe���@�ᔽ�̍߂ɖ��ꂽ�w��\�͒c�����i���U�j�̌������A���Ð��q�퍐�i�T�V�j�̍ٔ����ٔ��̔����������P�S���A�_�˒n�قŊJ���ꂽ�B
�{��p��ٔ����́A���Y�ʂ薳�������������n�����B
�@���Ô퍐�͎��s�ƂS�l������Ŏw�������Ƃ���A������P�U�N�ɂ킽���ē��S�B��N�U���A��ʌ��ŕ��Ɍ��x�ɑߕ߂��ꂽ�B
�@�����Ō��@���́u���s�Ƃ�����̗���ŁA�d�v�Ȗ������ʂ������v�Ǝ咣�B�ٌ쑤�́u�g�����̖��߂ɏ]�킴��Ȃ������v
�@�Ƃ��Ē����P�U�N�����߂Ă����B
�P�@�͂��߂�
�\���v���Ƃ́A���@�҂��ݒ肵���ƍ߂̗ތ^�i�J�^���O�j�ł��B
�Ⴆ�A�E�l�߁i�P�X�X���j�̍\���v���́u�l���E�����ҁv�ł��B
�����ɂ́A�s�ׂ̎�́i�ҁj�A�s�ׁi�l���E�����j�A�s�ׂ̋q�́i�l�j���L�q����Ă��܂��B
�����Ƃ��A�ƍ\���v���͂��قȂ�܂��B�����炱���A�Q�O�Q���́A���E�����߁A���E�߁A
�����E�l�߁A�����E�l�߂Ƃ����S�̍\���v�����܂ݓ��܂����A�������s�W�Q�߁i�X�T���j�́u�E���s�ׂ̓K�@���v
�̂悤�Ɂu�����ꂴ��\���v���v�f�v�����݂��܂��B
�Q�@�킪���ɂ�����j�I�W�J
�킪���̍\���v���_�́A���a�̂͂��߁A���쐴��Y�Ƒ��K�C�ɂ���ăh�C�c����A������܂����B
���씎�m�́A�\���v�����s�ׂ̈�@����ތ^���������̂ł���Ɠ����ɁA�s�҂̓��`�I�ӔC����
�ތ^���������̂ł���Ƃ��܂����i�ƍߍ\���v���̗��_�i�P�X�T�R�j�P�W�ňȉ��j�B����ɔ��m�́A
�\���v���ɏd�v�ȌY���i�ז@�I�@�\��F�߁A������Y���i�ׂɂ�����w���`�ۂł���Ƃ��܂����B
���m�̌����́A�c���d���́u��^���v�i�c���P�P�W�Łj�Ɍp������A�����A�킪���̒ʐ��ƂȂ��Ă��܂��B
�����A��씎�m�̍\���v�����_�ɂ́A�O���ʂ��Ă��Ȃ�̕ϑJ���݂��܂��i��˂P�Q�P�Łj
���Ȃ킿�A�����́A�}�C���[�̗���ɏ]��ꂽ�̂ł����A��ɁA�x�[�����O�̎w���`�ۂƂ��Ă̍\���v���T�O���̗p����A
����ɁA�ӔN�ɂ́A���c�K�[���̈�@�ތ^�Ƃ��Ă̍\���v����_�����܂����B
������́ATatbestand���u�ƍߗތ^�v�Ɩ܂������A���̊�{�I���i���u���I��@�ތ^�v�Ƃ��i�Y�@�ɂ������@���̗��_�i�P�X�V�S�j�P�Q�R�ňȉ��j
��@�ތ^�ł���Ƃ���܂����B�����āA���I��@�ތ^�ƈ�@�j�p���R�Ƃ́A�����^�Ɨ�O�^�̊W�ɂ���Ƃ��܂����B�܂��A�ƍߗތ^�́A���I��@�ތ^
�ł���݂̂Ȃ炸�A���I�ӔC��тт��s�ׂ̗ތ^�ł�����Ƃ��܂����B
�����ł́A�x�[�����O�̗�������އ@�s�חތ^���A�A���c�K�[�����̗�������އA��@�ތ^���A
�����āA���쁁�c���̗�������އB��@�E�L�ӗތ^�����咣����Ă��܂��B
�R�@�\���v���̋@�\
�\���v���ɋ��߂���ł��d�v�ȋ@�\�́A�@�ߌY�@���`�@�\�i�ۏ�@�\�j�ł��傤�B�����ƍ߂ʼn����ƍ߂łȂ�����������Ȃ��̂ł́A
��X�͓��X���S���ĕ�炷���Ƃ��ł��܂���B���ɏd�v�Ȃ̂́A �@�Ƃ��֘A���āA�A�ƍߌʉ��@�\�ł��B���̋@�\�Ȃ����ẮA�Y�@�e�_
�͐��藧�����܂���B
���̑��A�B��@����@�\�A�C�̈ӂ̑Ώۂ������̈ӋK���@�\�A�D�Y���i�ז@�R�R�T���P���́u�߂ƂȂ�ׂ������v�������Y���i�ז@�I�@�\
�Ȃǂ�����܂��B
�S�@�\���v���ƈ�@���Ƃ̊W
�i�P�j�s�חތ^���i���c�X�P�A�]���U�T�j
���̌����́A��{�I�Ƀx�[�����O�̉��l�����I�\���v���̎v�z���x��������̂ł���A�\���v���͐ӔC�݂̂Ȃ炸��@��������B�R�ƕ������A
������`���I�E���l�����I�ɂ����ς�s�ׂ̗ތ^�Ƃ��闧��ł��B
���̌����́A�\���v���̘_���I�ȈӖ��ł̈�@�E�ӔC����@�\��ے肵�A������̐���݂̂�F�߂܂��B���������āA��@�j�p���R�̑���
�̔��f�ł͕s�\���ł���A����ɐϋɓI�Ȉ�@���f���K�v�Ƃ���邱�ƂɂȂ�܂��B
�s�חތ^���ɂ��A�\���v�����`���I�E�����I�ɔc������錋�ʁA�\���v���Y�����̎˒��͈͂��L���Ȃ�A�������čߌY�@���`�Ɉᔽ����
�\���������Ȃ�ƂƂ��ɁA�K�͓I�\���v���̏ꍇ�A�����I�E���l�I���f���s���ł��邪�̂ɁA�x�����邱�Ƃ͂ł��܂���B
�i�Q�j��@�ތ^��
�@��@�s�חތ^���i����X�X�A���c�U�X�A�����P�X�Q�A�R���R�O�j
�\���v���́A��@�s�ׂ̗ތ^�ł��邪�A��@�����f�ɂ����ė�O�I�Ɉ�@�����j�p����邱�Ƃ����肤����̂Ƃ��錩���ł��B
���̌����́A��Ƃ��Ď�ϓI�\���v���v�f��F�߂Ȃ����ꂩ�珥�����܂��B
���̌����́A�\���v���̋@�\�̒��ŁA�C�̈ӋK���@�\������߂ďd�����錋�ʁi�R���R�S�Łj�A�ł��d�v�ȇ@�ߌY�@���`�@�\�A�A�ƍߌʉ��@�\��
�]���ɂ���Ƃ�����_�������Ă��܂��B
�܂��A�ӔC�̗ތ^����F�߂Ȃ����̗��ꂩ��́A�u�E�l�E���Q�v���E�ߎ��v���͍\���v���͓������v�i����X�W�j�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�������
�Ɏ�������łȂ��A�����̈�ʂ̏펯�������������Ă���Ƃ����ᔻ���\�ł��B
�A���ɓI�\���v���v�f�̗��_�i���E��z�h�q�_�P�X�ňȉ��A��c�X�Q�j
���̐��́A�����h�q�Ȃǂ̐��������R���A���ꂪ�s���݂ł���A�\���v�����[������Ƃ����Ӗ���
���ɓI�\���v���v�f�ł���Ƃ��܂��B���������āA���̌�������́A�ƍߘ_�̌n�́A�\���v���ƈ�@��
����̉������u�ތ^�I�s�@�v�ƐӔC�̓�i�K���琬�藧���ƂɂȂ�A�O�i�K�ƍߗ��_�͕�������܂��B
���̐��̎��_�́A����_�̉����ɂ���܂��B
���Ȃ킿�A�i�R�j���ł́A�Ⴆ�A��z�h�q�ɂ��E�l�̏ꍇ�A�\���v���I�̈ӂ͔F�߂��邪�A�ӔC
�v�f�Ƃ��Ă̌̈ӂ��ے肳��A�ߎ��v���߂��������邱�ƂɂȂ�B�������A�\���v���Y�����A��@����
�i�K�܂ł́A�E�l�߂̍\���v���A��@���ɓ�����Ȃ���A�ӔC�̒i�K�œˑR�ɁA�ߎ��v���߂̐ӔC�����
�ɂȂ�͕̂s�s���ł���B������x�A�\���v���̒i�K�ɖ߂��Ă��A���̒i�K�ł́A�̈ӂ����邩��A�ߎ�
�v���߂̍\���v���ɂ͓����炸�A���ǁA������u�u�[���������ہv�i��[�R�W�O�j�������ĕs�s����
���邪�A���ɓI�\���v���v�f�̗��_���̂邱�Ƃɂ���ĉ����ł���Ƃ����̂ł��B
�������A������̉����́A�O�i�K�ƍߗ��_�̌n���������������ł��\�ł���Ƃ���i�Ⴆ�A�R��
�P�X�T�A�����m�u�S�P�j�A�����I���f�Ɨ�O�I���f�Ƃ������͓I�v�l���̂ĂĂ܂ŁA���̗��_���x������
���Ƃ͂ł��܂���B
�B�\���v���̈�@���ւ̉������i�ē�����V�P�A�����P�R�R�j
�\���v���Y�����́A�K�͈ᔽ���Ƃ��Ă̈�@������e�I�Ɏ��������̂ł���A�ƍ߂̊T�O�̒��ł́A
�Ɨ��̊T�O�v�f���Ȃ����ƂȂ��A��@���Ƃ����T�O�v�f�̓����Ř_������ׂ����̂Ƃ��錩���ł��B
�������A��@�s�חތ^�ł���\���v���ƈ�@�]�����̂��̂Ƃ́A�T�O�㖾�m�ɋ�ʂ����ׂ����̂ł��B
�@
�@
�i�R�j��@�E�L�ӗތ^��
�@��@�E�L�ӗތ^���i����E�ƍߍ\���v���P�X�ŁA�c���P�P�W�A��˂P�Q�Q�A���V�S�A��J�X�V�A�O�c�S�V�A�����W�U�A�����m�u�R�T�j
���̐��́A�\���v���́A��@�s�חތ^�݂̂Ȃ炠���A�L�Ӎs�חތ^�ł�����Ƃ��������ł��B
���������āA�\���v���ɊY������A��@�ł��邱�Ƃ݂̂Ȃ炸�A�L�ӂł��邱�Ƃ������肳���Ƃ��܂��B
���̐��́A�@�ߌY�@���`�@�\�A�A�ƍߌʉ��@�\�͂����܂����A�̈ӂ��\���v���Ɋ܂܂�錋�ʁA�C�̈ӋK���@�\�͉ʂ������܂���B
�A�̈ӂ̑̌n�I�n��
�@�j�\���v������@�ތ^�Ɖ����闧�ꂩ��A�̈ӁE�ߎ���ӔC�v�f�Ɖ����č\���v���Ɋ܂܂�Ȃ��Ƃ��錩���i�R���R�S�j
�A�j�̈ӁE�ߎ�����@�v�f�Ɖ����č\���v���Ɋ܂߂錩���i��c�P�T�R�j
�B�j�\���v������@�E�L�ӗތ^�Ɖ����闧�ꂩ��A�̈ӁE�ߎ���ӔC�v�f�Ƃ��č\���v���Ɋ܂߂錩���i�O�c�S�V�A�����m�u�S�O�j
�A�j�B�j�ɂ���ĔF�߂���̈ӂ��A�Ƃ��Ɂu�\���v���I�̈Ӂv�ƌĂт܂��B
�i�S�j���I��@�ތ^�Ɖ��I�ӔC�ތ^�i������P�W�R�E�Q�Q�V�A���R�P�Q�X�Œ��S�A���c�u�\���v���̊T�O�v���_�k��R�Łl�P�T�ŁA�Ȃ������T�P�j
�ƍ߂����I�Ȉ�@�s�ׁE�L�Ӎs�ׂ̗ތ^�ł���ȏ�A�\���v�������R�Ɉ�@�\���v���ƐӔC�\���v�����g�ݍ��킳�ꂽ
��@�E�L�Ӎs�ׂłȂ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
���̏ꍇ�A�̈ӁE�ߎ������I�ȐӔC��ތ^��������̂ł�����A�ӔC�\���v���̗v�f�Ɖ����ׂ��ł��B
�����āA�ƍߘ_�̔F�菇���Ƃ��ẮA
���I��@�ތ^�Y�����ˈ�@�j�p�ˉ��I�ӔC�ތ^�Y�����ːӔC�j�p
�Ƃ����\�����̂邱�ƂɂȂ�܂��B
�y�����z������ɏ]���܂��B
���̌������̂邱�Ƃ̃����b�g�Ƃ��ẮA�\���v���Ɋ��҂����@�\�A���Ȃ킿�A�@�ߌY�@���`�@�\�A�A�ƍߌʉ��@�\�A�B��@����@�\�A
�C�̈ӋK���@�\�A�D�Y���i�ז@�I�@�\��S�ď[�������Ƃ��ł��邱�ƁA�\���v���I�̈ӂ�F�߂�K�v���Ȃ�����u�u�[���������ہv�������
���Ƃ��ł��邱�ƁA���������܂��B
�ȏ�ŁA�Y�@���_�i�u�`�āj���I�����܂��B
�����ԁA�X����Ɛ肵�Ĉ��������B
�����ɂ����Ď��R�ȍs�ׂ́H
�l�͌��݁A�ďA�E�Ɍ����Ċ撣���Ă���j�ł���
���_�Ȃɒʂ��Ă��苎�N�̔N�����������܂Ȃ��Ă����悤�ɂȂ�܂����B
�ŁA�]�@����ۂɏЉ��������ĖႢ�܂������Ȃ�ď����Ă��邩�������Ȃ�J���Ă��܂��c�����̐f�f��(�s����Q)�͕������Ă��܂�����
���܂ł̌o�߂������Ă��钆�œ��e���قȂ鎖�������Ă���܂����B
�Z���̓��@������܂�����(�y�x�̏Ǐ�̕�����̉���a���ł�)
�܂��A�F�X�L��܂������l������I�ɊŌ�m����⑼�̊��҂���ɖ��f���������悤��
��ۂ�^���鎖��������Ă����̂ł��B�M�����Ă����S����Ȃ����Ɏc�O�ȋC�����ɂȂ�܂����B
�l�����g���J���ēǂ̂͗ǂ��Ȃ��ł����ǁc�B
���@���Ă��鎞�ɑ��̊��҂���u���̐搶�͌�����肢�B
���X���̂��w���w�������肷���ˁB�v
�ƌ����Ă܂����B�l�����܂ɂ��̐搶�͕ς���Ă�ȂƎv�����͂���܂������c�B
���Ȃ݂Ɋ��ƗL���Ȑ搶�ł��B
�]�@��̐搶�Ɉ�����ۂ�^���Ă��܂��̂��D�ɗ����܂���B
�l�̂悤�Ȑl�Ԃ͐M������Ȃ��Ǝv���܂����c�Ȃ������ł��B
���������~�����Ƃ����_�ʑ��Ƃ��ł͂Ȃ��A�Љ������������ė~�����ł���
��������J���������o���Ă��܂����c�B
�l�͊��҂Ƃ�������ʼn��������Ă��s���ł��傤���c
�܂��A���v��������ƕς��ȂƎv���������\����܂��B
���݂܂���A�w���������̂Œ����A�ʕ����炵�܂����B
�X���������A�}�W���X����Ɩ����ł��B
��t�̍ٗʓ��̍s�ׂ�����B
�ꌩ���Ȃ��ɂƂ��ĕs���Ɍ����鎖���ł�������L�����邱�Ƃɂ���ĉ�����Ă��Ȃ��̂��߂ɂȂ�B
����
�����F�e�͂ǂ�������B����
�������B
���Ƃ���ߎ��Ƃ��������邽�߁A�c���E���삩��ǂݕԂ��Ă���̂���
����P�X�R�łɎ��̈�߂��������B
�ߎ��s�ׂ́A�P�Ɍ��ʂɑ��Ĉ��ʊW������Ƃ��������̍s�ׂł͂Ȃ��A
���ʔ����́u�����I�ŋ�����Ȃ��댯�v���������s�ׂł���A�����
�y�댯�̌������z�Ƃ��Č��ʂ����������Ƃ�����������̂��Ǝv����B
�u�댯�̌������v�Ƃ����t���[�Y�́A�����炭���ӎ��I�Ɏg�����̂ł��낤��
�����ӎ��I�Ɏg�����Ƃ���Ί댯�̌��������̎n�c�͕��삾�Ƃ������ƂɂȂ�B
���ޖ��߁B
�S���L�`�K�C�L�^�[�I
�Ⴄ�ł��傤��B
http://jbbs.livedoor.jp/study/11831/
���_�����҂���B
�ŋ߂̋��ȏ��i�����E�����E�����j�ł́A�܂��܂��s�ӎv�_���蒅���Ă���B
�Ⴆ�A�����P�O�X�ŁB�@
�@�@�l���F���Ǝv���ďe�̑_�������Ĉ��������������Ƃ��Ă���ꍇ�ɂ́A
�@�@�E�l�̌̈ӂ͂Ȃ����A�q�̂ɑ���댯�͎E�l�̌̈ӂ�����ꍇ�Ɠ��l��
�@�@���݂��Ă���B�܂�A���̏ꍇ�ɁA�W�I�ƂȂ��Ă���l�̐����ɑ���
�@�@�댯�����E���Ă���̂́A�E�l�̌̈ӂł͂Ȃ��A�_�������Ĉ�������
�@�@�������Ƃ���s�ӎv�Ȃ̂ł���B
�������A����P�Q�U�ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ����B
�@�@�l���E�����Ƃ��āA�s�X�g���Łu�_���������v�Ƃ��́A���łɎE�l��
�@�@������F�߂邱�Ƃ��ł���ł��낤���A���̏ꍇ�ɂ́A����Ɂu������
�@�@�������v�Ƃ������̍s�ׂ��Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́u��̍s�ׂ�
�@�@�ړI�Ƃ����v���̂ł���A���̖ړI�͎�ϓI��@�v�f���Ƃ�����B
�܂�A�s�ӎv�����Ƃ�����ʂł́A�]������F�߂��Ă����u�ړI�v
����ϓI��@�v�f�Ƃ���Α���A�����čs�ӎv�Ƃ����T�O��ݒ肷��K�v��
�Ȃ��B
�@
�L���āu�s�ӎv�v�Ƃ��čs�ט_�i���ʊW�_�j�ň������B
�����₷���͂ǂ���H
���������ϓI��@�v�f�Ƃ��Ă���B
���ʊW�_�ň������͒m��Ȃ��B
�Ȃ��ʂɂ�₱�����̌n�ɂȂ肻������
�w�҂�������w
�����Ȃ�B�̌n�I�ɋ^�`�������B
���씎�m�́A�s�ׁ[�\���v���Y�����[��@�[�ӔC�̑̌n���̂�A�s�ט_��
�s�ӎv��_����B
���R�����́u�s�҂̎�ϖʂɂ��댯���̔��f�ɉe�����y�ڂ�����v�f������
���A����́A�̈ӂ̗L���ł͂Ȃ��A�s�ׂ̑����Ƃ��Ă̍s�ӎv�̓��e�ł���v
�Əq�ׂĂ���i�N���[�Y�A�b�v�Y�@���_�P�U�Łj
����E���R�������s�ӎv����ϓI��@�v�f�ƈʒu�Â��Ă��镔����
���p�ł��Ȃ��H
�v�f�̈�v�ł���i����Q�U�Łj
�u�s�ӎv�́A�̈ӔƂɂ��ߎ��Ƃɂ����ʂ̗v�f�ł���A��ϓI��@�v�f�ł���v
�i�̈ӂƈ�@���̈ӎ��P�U�O�Łj
�����A���ʊW�_�Ɗ��ʏ��������̂̓~�X���B
�Ƃ͂����A�s�ט_�ł����_����ꍇ�ǂ���������̂��낤�B
��ϓI�v�f����@���Ȃ����\���v���܂ők�点�邱�Ƃ́A�\���v������@�ތ^
�܂��͈�@�E�L�ӗތ^�Ɖ����邱�Ƃɂ���ď��߂ĉ\�ƂȂ�B
�������A�k���͍̂\���v���܂łł����āA�s�ׂ܂ők�邱�Ƃ́i���씎�m
�͕ʂƂ��āj�A��ʂ̍\���v���_��O��Ƃ������s�\�ł���B
�s�ׂ̒i�K�ň�@����_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���̂悤�Ȕᔻ��������邽�߂ɂ́u�s�ӎv�v�͍s�ׂ̗v�f�ł͂Ȃ��A�\��
�v���ɑ�����u���s�s�ׁv�̗v�f�ł���Ƃ���̂���Ăł��邪�A���R������
�u���s�s�ׁv�T�O��ے肵�Ă�����i�N���[�Y�A�b�v�P�Q�ňȉ��j
���̂悤�ɍl����Ɓu�s�ӎv�v�͈�@���ɑ������ϓI�v�f�Ɖ�����ق��Ȃ��B
�������A����́u�s�ӎv�́A�s�ׂ̑����ł���v�Ƃ��鍂�R�����̑�O��Ɩ�������B
�T���N�X
���쎁�̌����͍s�ӎv����ϓI��@�v�f�̍\���v�f�ƌ��Ă���̂ɑ���
���R���͕�������(�ƌ������ނ���O��v��)�ƌ��Ă���悤����
����l�͓����p���ʂ̈Ӗ��Ɏg���Ă���̂�������Ȃ�
���ɍ��R���̌����͉ߎ��Ƃ̏ꍇ�����܂ޓ_�ƂĂ������
���肪�Ƃ��A
��������ƍs�ӎv�͗L�ӓI�s�ׂ̈ӎv�̗v�f�̂ЂƂł���Ƃ����m�F���A
��@�]�����\���v�����邢�͈�@���i�K�ł���̂��悳�������B
�S�R�������Ȃ��B���s�s�ׂƍs�ׂ͈Ⴄ����ȁB
�s�ׂ͈�@����тт�ꍇ������A�ттȂ��ꍇ�����邩���
>>877�̓A�z�ȍs�ז����l�_�҂Ȃ낤�Ȃ�
�u���������Ɛl�吙�v�Ƃ��o����ǁB
V2C��JaneXeno����
���̃X����
169 �F�����ٔ�F2014/03/25(��) 13:05:16.83 ID:???>>167
�������������c�ƂȂ�H
�Ŏ~�܂����܂܂Ȃ��ǁB
http://nozomi.2ch.sc/shihou/
���X�V�ł���H
�ꗗ���X�V���Ă݂�
��u�����@�ꗗ�@�X�V
�ł������O�O����
�ǂ������肪�Ƃ��B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�u���̎ז��ɂȂ邩��@�w�ł���Ă���v
�Ƃ����������������̂ŁA���̂Ƃ��肱�����̃X��������グ�悤��B
�N����������������B
(���x���ۂ��ł͂Ȃ��Ĥ�i�@�����Ƃ͂���Ă�(��������������)����
�������ł��ׂ����Ƃł͂Ȃ��ƌ����������������Ȃ��ǂ�)
�]������
��\���s�\�ȉ�ݎ���͔��f���ɒu���Ȃ���
�����碂��̍s���̂��炻�̌��ʂ���������̂���������f�����
����͂܂袑������̘g���Ɏ��܂��Ă��邩����̘g���邩��Ƃ������Ƃ���
���႟�ǂ�ȏꍇ�ɑ������̘g����̂��ƌ�������
����͢��ݎ���̌��ʂɑ���e���͂��傫���ꍇ��ł���
�ƌ����Ă邾�����Ǝv�����ǂˡ
�^�ۂ͂Ƃ���������Ţ�_��������Ȃ̂��悭������Ȃ�����ˡ
��U����f��ꂩ��O����ƌ������ȏ�ͤ
����悻���݂��Ȃ����̂Ƃ��Ėڂ��ނ�Ȃ�������Ȃ���Ƃ����Ӗ��ł���Τ
�����Ȃ̂�������Ȃ����
���Ȃ��Ƃ��]�����̎g�������Ƥ����f���ɒu����Ƃ����̂ͤ
�댯�̎����̌o�߂ɐϋɓI�Ɏ�荞�ނƂ������Ƃł����Ĥ
��������W���鎖��Ƃ��čl�����邱�Ƃ͕ʘ_�Ȃ�Ȃ��̂��ˡ
��������t�̎g�����̎^�ۂ͂Ƃ������A���������g�������Ƃ���Τ
�ʂɢ�_��������ƌ�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ͎v�����
�O�̂��ߌ����Ă����Ƥ�ʂɑ]�����̌�������������ł͂Ȃ��Ĥ
���ȏ��ʂɓǂ߂����Ȃ�Ȃ��̂��ȂƑf�p�Ɏv�������̂��Ƃł��
�댯���̒��x�Ɖ�ݎ���̊�^�x�Ƃ̑��֊W�Ō��܂�A�Ƃ��������ł������ȁH
���ݎ���s�ׂ���U�����ꂽ�����̂悤�Ɍo������\���\�ȏꍇ�ͤ
����f���ɂ����đ��������f���s���邽�ߤ�E�E�E
(�s�ׂ̊댯����)�Ⴂ�ꍇ�ł����Ă����ʌo�߂̑������͍m�肳���
�Ƃ������Ƃ�����B
�܂褢�s��(����)�̊댯�����Ⴍ����ݎ���̊�^�x��������ꍇ�ł����Ă�
��ݎ���\���\�Ȃ��̂ł���Τ�����̍s�ׂ�������炳�ꂽ���̂Ƃ����邩��
�������̘g���Ȃ�(�����̍s�ׂ̊댯�̎���)�Ƃ�����Ƃ������Ƃ���Ȃ����ȁB
���̓_�͎R�����Ǝ��Ă�̂�������Ȃ��B
��s�ׂ̊댯���������ģ���ݎ���̊�^�x����������Ƃ��͢���������裁B
��s�ׂ̊댯�����Ⴍ�ģ���ݎ���̊�^�x���傫����Ƃ��͢�������Ȃ���B
���̌���łͤ��s�ׂ̊댯���̒��x�Ɖ�ݎ���̊�^�x�Ƃ̑��֊W�Ō��܂�
�ƌ����Ă������̂�������Ȃ��B
�����(�\���s�\�ȏꍇ��)
��s�ׂ̊댯���������ģ���ݎ���̊�^�x���傫����Ƃ��͢�������Ȃ�����ˁB
����Ƃ��Ģ�ĕ��Ђ�������������������Ă�B
>>234
>�ꌾ���������A����17�N�O�̘_���Ƃ���Ɋ�Â��M�a�̔ᔻ����U���ɂ���
>���݂̋��ȏ���f���ɓǂ�ł݂��炢����Ȃ����Ƃ͎v�����ǁB
�w�Y�@�ɂ����錋�ʋA���̗��_�x�i�Q�O�P�Q�N�j�S�Q�łƏ����Ƃ��M���̎��ۂ�������������ȁB
�]���́A�͂������œ����ɏ��������{�_�����u�M�҂̑������ʊW�_�Ɋւ���l�����������Ƃ��ڍׂɘ_�����A
�{���̒��j�I�Ș_���ł���v�ƕ]���Ă���B
�P�V�N�O�̘_��������F�����Ă���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�]������ς���A�]���͂P�V�N�O����u���Ă��Ȃ��Ƃ������ƁB
�\���s�\�ȏꍇ�����A���ȏ��̓ǂݕ��Ƃ��Ă�>>899���������낤�ˁB
�������A�]���́A���ʋA���̗��_�S�R�łł́A
�@�@�����A�����Ȃ�ƁA�\���s�\�ł���Ƃ��Ă������f��ꂩ��r������������Ăє��f���Ɏ�荞�ށA
�@�@�Ƃ���������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^��Ɉ������邱�ƂɂȂ�B
�Ǝ��⎩�����Ă���̂���i���_�Ƃ��Ė����͂Ȃ��Ƃ���̂����j
�I�C���͂�͂薵�����Ă���Ƃ����l�����Ȃ��̂ŁA>>203�̏������݂������B
���ł����̍l���͕ς��Ȃ��B
> �@�@�����A�����Ȃ�ƁA�\���s�\�ł���Ƃ��Ă������f��ꂩ��r������������Ăє��f���Ɏ�荞�ށA
> �@�@�Ƃ���������Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^��Ɉ������邱�ƂɂȂ�B
>�Ǝ��⎩�����Ă���̂���i���_�Ƃ��Ė����͂Ȃ��Ƃ���̂����j
�����Ȃ̂����B
�ǂ������������Ȃ̂��C�ɂȂ邪��@�����Γǂ�ł݂܂��
�݊������A����I���Ă��ꂽ���Ă��Ƃ���ˁB
��������͔F�߂�Ƃ��Ĥ�ł͂�����ƌ��������̂ͤ
��\���s�\�ł���Ƃ��Ĕ��f��ꂩ��r�����������
�Ăє��f���Ɏ�荞�ނ̂͘_�������ł͂Ȃ�����Ƃ����̂�
�]���̢���⣂ł����Ģ���_�Ƃ��Ė����͂Ȃ���Ǝ������Ă���Ȃ��
���̢������̓��e�ɐ����͂��Ȃ����Ƃ�_���Ȃ���Τ
���Ǥ�]�����g�̢���⣕��������Ȃ̎咣���̂悤�ɂȂ����Ă邾����
�����i�W�͂��Ȃ��ł͂Ȃ�����Ƃ͎v�����ǂˡ��
��������������ۂ��������͂悹��B
���������̌��ݓI�ȋc�_����������B
�������̃X���ƈ���Ďז�������Ȃ�����A���ݓI�ȋc�_�����҂ł���B
�N������N�����������B
�����D�_�̋ɂ݂��ȁB
����͂Ƃ������A��c�E���_�\�����W�R�̎��̈�߂������ł��Ȃ��B
�u�ӔC�v�f���i���ʖ����l�_�j�͌��i�̈Ӑ��ɒ�������v
�̈ӂ������ς�ӔC�v�f�Ƃ��Ĉʒu�Â���u�ӔC�v�f���v�̑�\�I�_�҂͎R������
�R���͐����ӔC�����̂�B
�܂��A���ʖ����l�_�Ō��i�̈Ӑ����̂�̂́A�m�����A���R�E��c�݂̂ł���B
��c�́u��@�v�f���v�i�̈ӂ������ς��@�v�f�Ƃ��錩���j�Ɓu�ӔC�v�f���v��
�Δ���������邠�܂�A�w���̕��z�̊m�F��ӂ����̂ł͂Ȃ����B
�f���ɓǂ߂�����ˁHw
�ǂ����̂��ꂩ�݂�����w
���_�\���W�R�Ŏ��ӂ�ǂ�ł݂����A�������ɁA��c���������闝�O�^��
���ۂ̊w�����z�͘������Ă�ˁB
�͂����肷���ĕM����������Ȃ�����
>>909
��c�E���_�\���W�Q�Œ��Q�͏��{�����i�̈Ӑ��ɐ����Ă��邪�A����͌��B
�������ɁA���{�P�W�R�ł͌��i�̈Ӑ��ɑ���ᔻ�͗��R���Ȃ��Ƃ��Ă����
�ٌ삵�Ă��邪�A�P�W�S�łŁu���s�@�̉��߂Ƃ��Ă��v�u�_���I�ɂ��v�����ӔC��
���̂邵���Ȃ��Ƃ��Ă���B
�w�����p�����m�ŐM�p�ł���̂́A�R���A��c�E�u�`�Y�@�w�A���������B
��J�͌�肪�����̂ŗv���ӁB
���ʖ����l�ł���������Ȃ�����������̂ɁB
�S�������B�Ⴆ�A���_�\�����R�E���S�̎��̈�߁B
�u���ʖ����l�_���x����̂́A�Y�@�Ɠ����͋�ʂ����ׂ��ł���A�Y�@�I
���f����ϗ��I�l���͔r�������ׂ����Ƃ���v�z�ł���B��ŏq�ׂ�悤��
���ꂶ�����͐����ȍl�����ł���Ǝv����B�Ƃ��낪�A�_�҂́A���̐�����
�l��������A�����ɑ���s����̒Ƃ����@�\����@���f�ɋ��߂Ă�
�Ȃ�Ȃ��A����͌Y�@�Ɠ����̍����������炷�Ƃ����咣���̂ł���B
����͂܂��ɋ����ׂ��咣�ł��낤�v
�����̂͂������̕��ł���B�u�_�ҁv�Ƃ͒N���B�N������Ȏ咣�����Ă���̂��B
�S�������ĕs���ł���B
�u�������ƌ�������߂Ĕᔻ����v�i����j�̗ނ��ł���B
�Œ������̓i�`�X�Y�@��������Ƒ������Ă��炶��Ȃ����ȁB
���ʖ����l�_�͂��ꎩ�̃i�`�X�Y�@(�S�̎�`�Y�@)�ւ̃A���`�e�[�[������
���炽�߂đ�������K�v���͏��Ȃ����ǁA�\�ʓI�ɂł��ގ��̎咣�𗧂Ă�
�Ȃ�K�{���Ǝv�����B
���邢�͂���Ă�̂��ȁH������܂蕶�������ĂȂ�����ȁE�E�E
���p���������ɓI�\���v���̗��_�̎咣�Ɍ����Ă����B
>>914
�S�̎�`�Y�@�Ȃ�i�`�X�Y�@�����łȂ��\�r�G�g�Y�@�����ȁA
��������S�̎�`�ɍs���������B
>�͂����肷���ĕM����������Ȃ�����
���ɂ����_�\���W�T�y�[�W�B
�u�ӔC�����K�͓I��ʗ\�h�_�ł���s�ז����l�_�̕ʏ̂ɂق��Ȃ�Ȃ��v
�܂��A�Q�X�W�y�[�W�B
�u�s�x�z���Ƃ́A�s�҂Ɍ̈ӂ��̂Ă����K�͈ᔽ����߂����邱�Ƃɂ��
�@�v��ی삵�悤�Ƃ���Y�@���_�A���Ȃ킿�s�ז����l�_�̋��Ƙ_�ɂ�����
�ʏ̂ɂق��Ȃ�Ȃ��v
���R�搶�́A�\�r�G�g�Y�@���牽���w�낤�H
��J�͊w���̈��p�Ɍ���Ă���ӏ���������Ă��ƁH
�ǂ����H
���������ď�������Ȃ����A�Ⴆ�T�Œ��R�u����T�E�P�Łv
�Ȃ�قǁB�m�F���܂����B����͈��p�~�X�ł����ˁH��
���T�ɂ��������������Ċm�F���Ȃ������킯����ˁB
�܂��A���������ނ̂��̂Ȃ�A���Ƃ��Ă͋����邩�ȁB
���ރ~�X�̈�c�����߂͌y����
���������m�F����̂ł����H
�̂̎Q�l���ɃR�������^�[���`���Ŋ�{������̔������g����
�w�����ނ�����Ă��̂��������̂�B
�����B
���T�̓��Y�����������������[�h�őłB
�����Y�@�Ƃ����Q�l���̂��Ƃ͒m��Ȃ��������A���ʂƂ��Ă���Ǝ����悤�Ȃ��̂��o���オ��B
���̍�Ƃ�V������{�����o�ł���閈�ɍs���B
�����������ʂȍ�Ƃ������ォ��J��Ԃ��������ŃI�C���̓��F�e�ɂȂ�����
��J�̑��_�Ŋw���̐������Ԉ���Ă���ӏ����Ă���܂����ˁH
�y�[�W���̈��p�~�X�Ƃ�����Ȃ��āB
�U�O�Œ��W�u�R���E�U�V�Łv�|�R���͔���̖@������ے�
�W�V�Œ��R�|�ړI�I�s�ט_�҂̒��Ɉ�c�̖����Ȃ�
�P�P�X�Œ��R�S�u�O�c�E�R�W�Łv�|�O�c�Q�P�X�ł͕\���Ƃ�ے�
�P�W�Q�Œ��S�u�����E�Q�O�U�Łv�|�����Q�O�T�ł͊뜜����
�Q�W�U�Œ��T�R�u�R���E�S�W�R�Łv�|�R���͌����ɂ����Ĉ�@l�ȍs�ׂ̗��_���̂�Ȃ�
�R�R�W�Œ��W�u���c�E�Q�S�Q�Łv�A�R�R�X�Œ��P�Q�u���c�E�Q�S�O�Łv�|���c�Q�Q�T�ł͐����ӔC��
���X
�v���I�Ȃ̂́u������N�����ł��Ó��ł���v�i�S�O�O�Łj�Ƃ��Ȃ���A�����̋��������I�Ƃ��Ă���_�i�S�R�S�Łj
�����͏C����N���Ȃ����s�@���Ƙ_�ł���A����̐��̈ʒu�Â�������Ă���i�R���W�O�T�ŁA�����S�P�R�Œ��T�S�Q�Ɓj
������N���͐��Ƃ̈�@���Ƌ��Ƃ̈�@���̑o���Ɏ��������邩��A
���_���ǂ���ɂ��]�т����Ȃ��́H
�����疢���̋��������I�Ƃ��Ă��v���I�Ƃ͌����Ȃ��Ǝv�����B
���Ƃ̏��������_�̌���Ɖۑ�(��E��)
http://iyokan.lib.ehime-u.ac.jp/dspace/bitstream/iyokan/3744/1/AN00025020_2003_30_1-101.pdf
�\�͘_���ǂB�T���N�X�B
�u�m���ɁA��J�����́A������N���̗��ꂩ��A���Ƃ̎��s�s�ׂ̉�݂�
���Ɛ����̕s���̗v�f�Ƃ����Ɠ����ɁA���Ƃ̌̈ӂƂ��Ă͐��Ƃɂ��
���s�s�ׂ��s���邱�Ƃ̔F���ő����Ƃ���v
�@�@�@��
�������܂��ɖ��
�\�͋������g��������N�����ǂ̂悤�ɒ�`���Ă���̂��́i��E���j�ł�
�s���Ȃ̂ŁA�i��j���A�b�v���Ă���Ȃ����B
�T���N�X�B
�u��J�����́A��������N���Ɉʒu�Â��Ă��邪�A����ɑ��A���Ƃ��Β��R�����́A��^�����
�J�����̌����������̋����ɂ��ċ����Ƃ̐������m�肵�Ă���_�𑨂��āA�����̌�������N���Ɋ܂߂邱��
�͂ł��Ȃ��Ǝ咣�����B���R�����ɂ��ƁA��@���Ƙ_�i�s�@���Ƙ_�j�Ǝ�N���i���ʓI���Ƙ_�j�͖��m�ɋ��
����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�O�҂́A�\���v���ɊY�������@�ȍs�ׂ�U���܂��͑��i�����_�ɋ��Ƃ̏�������������
�錩���ł���̂ɑ��āA��҂́A���Ƃ����ƂƂƂ��Ɍ��ʂ���N�������Ƃ����Ƃ̏��������Ƃ��錩���������B
���̂悤�ɁA��N���Ƃ͖{���A�@�v�N�Q���ʂ̎�N�����Ƃ̖{���I�v�f�Ɖ����闧��ł��邩��A���̘_���I�A��
�Ƃ��āA���ʂ���N����ӎv�̂Ȃ������̋����͕s���ƂȂ�͂��ł���B��^���̘_�҂��J�����������̋���
�̉������m�肵�Ă���̂́A���Ƃ̖{����@�v�N�Q�i���ʖ����l�j�̎�N�ł͂Ȃ����Ƃ̎��s�s�ׁi�s�ז����l�j
�̎�N�Ɍ��Ă��邩��ł���A���̈Ӗ��ŁA�����̌����͎�N���ɂ͓����炸�A�ނ����N���Ƃ͋�ʂ��ꂽ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i44�j
���ł̈�@���Ƙ_�Ɉʒu�Â�����ׂ��ł���B�v
�t���ɉ����͂��Ă��邪�A�A�ԈႢ�Ȃ���J�ᔻ���Ȃ�
�����́A���R�����̎咣�����p�����ӏ��ł����āA
�\�͋����̎咣�ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����ȁH
�֘A���ɂ��A��J�����܂߁A���̐����_���I�ȋ������h��}��ׂ��A
����i�K�̈قȂ�\���Ƃ��čč\�����邱�Ƃɂ��w���̐���
������}���@���̗p����J�����_���I�����Ȃ����������邱�Ƃ�_���Ă����ˁB
�̂́A��J���ɔᔻ�I�������炵�����A�ŋ߂͉������Ă���Ǝv���̂�
���̘_���̎咣�����̂܂����̎咣���ǂ����͂킩��Ȃ��B
�����Â�����˂��B
���ۓI�ȉ�������đS���̘_�O���ˁB
���O�������ĂȂ�����H����
�����̂P�l�̎��쎩������
��͂�}���������ȁB�������ɂ�����������ł���̂ɂȂ���
�����[���e�[�}���ˁB
������ƒ��ׂĂ݂��B
���w������ˁ[���B
����Ƃ��P�Ȃ�r�炵�H
���̑�\�i������ˁB�ق��̊w�҂͉����Ă��B
�����V��ł���̂��H��
�s�ӎv�T�O�ɐG��Ă��Ȃ��̂́A�����A�сA���{�A�x���B
�t�ɐ����̈Ӑ��ȊO�ōs�ӎv�T�O��F�߂�҂́A�I�C�������ׂ����肢�Ȃ��B
�������Ă݂��>>938�̎w�E�͓������Ă���悤���B
���͂��̘_�����A�v�����B
�_�������Ȃ��ł���Ȃ��Ƃ��������Ă�Ȃ���
�����
�P�ɤ�s�ӎv�T�O���咣�����悤�ɂȂ����̂��ŋ߂̂��ƂŤ
���¤�ŋߌ��i�ӔC���͑Ó��łȂ��Ƃ��������ɂ��邾�����낤�B
���i�ӔC�����̖@���ʎx�����ł����Ă��s�ӎv�T�O���Ƃ邱�Ƃ͉\����ˁH
�����ӔC���͕���E���{�E���R�̂������Ŏ嗬�������ȁB
�ق��̊w�҂͗V��ł���낤�Ȃ�������
�Z���N���̋����ɂ�����̂ɔ���ŐG��ĂȂ����
>�����I��@�����Č��t�͕��������Ƃ��邯�ǁA�����I�댯���H
>����Ȃ��Ǝ咣���Ă���l����̂��Ȃ���
����Ȃ��ƌ������ɂ���K�v���Ȃ����A
�����I�댯�Ƃ������t����{�����̑��ɏ����Ă�l
���܂����Ȃ�
���L���Y�@�w�҂ɂ�
�ςȓz������Ƒ���ɂ���̂߂�ǂ���������A�܂Ƃ��Ȑl��
����Ăق����Ȃ���
�Y�@�͂���܂�m��ǁA�����I�댯���Ȃ�Č��t���g���Ă���w�҂��m���ȁB
�v�l���@�����Ă��邩��A���݂����Ǐ����ĂȂ��Ȃ�
���p���Ȃ�����ɉ��߂��ėi�삵�Ă��邵�ȁB����ȕ��X���K�v�Ȃ�����B
�ᔻ���Ă���l�Ԃ̂ق����ǂ����Ă������ゾ���ȁB
����ȂƂ���ŕ����ɂ��ݏ������Ɏi�@������
�����̂悤�ɌY�@���@�X�����ĂĈ��p���Ĕ��_���Ă݂�A�l�Ԃ̃N�Y
���������A�����I�댯���Ȃ�Č��t�ނ���
��J���Ƃ��Ĕ��_���Ă��邱�Ǝ��̂�����������ȁB
�C�܂������璴�L���Y�@�w�҂̊�{�������p�ł��Ȃ��낤
���������ނ��đ�J�Y�@�i�삵�Ă��܂������炗
��������āA��J�Y�@�i��Ɏg���Ȃ�Ăǂ������_�o���Ă���낤���B
����͙��ނ��ȁB��J�Ƃ��剺�����������Ă��Ȃ��ȏ�A
��J�Y�@�i��҂͂Q�����˂�ōD�������
��J�Y�@�i��̂��߂Ƀp�N���܂����Ď咣���Ă���̂��B
�����Ă邯�ǁc
���͑S���ǂ��Ǐ����Ă���l�͂��Ȃ������B
�_�����A��J�Y�@�̉��ł������p���ׂ��B
�����Ȃ�A��J�Y�@�i��҂͉R�����ƔF�肳����
���Ɖ��͑S���ڂ�ʂ��Ă��邩��A�����ƒf�����Ă����킗
����ł��̃X���Ɠ��������O���ق�݂����Ƃ��݂����Ɉ��p���Ă���͂�����ȁH������
�ł��Ȃ����R���Ƃ������Ƃ���ȁB
http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1399181913/
http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/shihou/1399282217/
�����I�댯�Ƃ������t�͂��邪�A���̖��O�ł���Ӗ��������S���Ⴄ���̂�����Ȃ��B
�܂������̖��̂ƊT�O�E���_�̖��̂�����������A�������Ǝ咣���Ă���̂ł͂Ȃ���ȁB
�n���Ȍ����҂��ۂ����ǁA�����܂Ŕn������Ȃ���ȁB��J�Y�@�i��҂��Ă̂͂�����
���Ɉ��p���Ă���J�Y�@��剺�_���ȊO����̈��p�Ȃ�A�p�N���ɂȂ邾�������ȁB
��J�Y�@�i��҂͓�������������������Ƃ������Ƃ��낤�B
�Ƃ���ŁA�����F�e�̏������݂��Ȃ��Ȃ����Ȃ������A�z���Ȃ�����
�Ɛ錾���Ď��Ƃ��J�n�������A�Ă̒�u�ǂ̋��ȏ��������ł����v�Ƃ�������
�����������B
������Ɩ��������A���[�N�G�i���䁁���с����c�����܁j��E�߂Ă������B
���R�͈ȉ��̂Ƃ���B
�@���c�E�R���剺�łŌł߂Ă���A�L�q�̃o���c�L�����Ȃ����ƁB
�A���ʊW�͏��сA���Ƙ_�͓��c�A�����h�q�͋��܂ȂǁA���̕���̑��l��
�@�����S���M���Ă��邱�ƁB
�B�w���Ɣ���̃o�����X���Ƃ�Ă��邱�ƁB
�C���w�҂ɂƂ��ĕs�v�Ȋw���̏o�T���ȗ�����Ă��邱�ƁB
�D�e�_�Ƃ̘A�g���Ƃ�Ă��邱�ƁB
�Ӗ��s����
�����A����ɂ��G��Ă���
���Ƃ�3�l�ɂ��Ă͐G��Ă����u�Ȃǁv�ŕЂÂ���Ȃ�
�����B�N�Ƃ͈Ⴄ�B
����̋Ɛт��ĉ��H
�悭�m��Ȃ����ǁB
CiNii �������lj������ӕ���Ȃ̂��������ȁB
�����邪�i�V�X�Œ��T�R�j�A�����_���u��Q�҂̍���ɂ��āv�_�˖@�w�N��
�i�P�X�W�T�N�j�̂Q�N�O�ɎR�����u��Q�҂̓��ӂɂ�����ӎv�̌����v�i��
��w�@�w�_�W�j�Ƃ����_���������Ă���B
������ƃt�F�A����Ȃ���ȁB
���e����������ˁ[����B�����B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B
�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B�Ђ�ڋC�F�����������������R�B