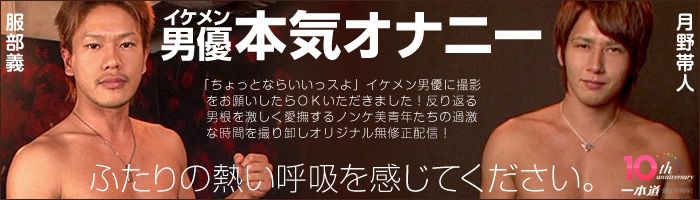【司馬遼太郎】 功名が辻 其の3
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/kin/1392835030/
【千代】功名が辻【一豊】
http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/kin/1348511932/
2006年 NHK大河ドラマ 「功名が辻」(大河通算45作目)
原作/司馬遼太郎<『功名が辻』ほかより>
脚本/大石静(『ふたりっ子』『オードリー』『アフリカの夜』『ハンドク!!!』など)
音楽/小六禮次郎(『秀吉』『さくら』『天うらら』『ちょっと待って、神様』など)
演出/尾崎充信(『ある日、嵐のように』『葵 徳川三代』『武蔵』など)ほか
制作統括/大加章雅(『こころ』『農家のヨメになりたい』『逃亡』など)
○関連ホームページ
放送前情報 http://www3.nhk.or.jp/drama/html_news_komyo.html
千代(山内一豊の妻)/永井杏→仲間由紀恵
山内一豊/途中慎吾→上川隆也
<一豊・千代の家族・家臣>
五藤吉兵衛/武田鉄矢
たき(吉兵衛の恋人)/細川ふみえ
五藤吉蔵/小倉久寛
祖父江新右衛門/前田吟
ふね(新右衛門の妻)/熊谷真実
祖父江新一郎(新右衛門の長男)/浜田学
法秀尼(一豊の母)/佐久間良子
山内康豊(一豊の弟)/古澤龍之→玉木宏
不破市之丞(千代の養父)/津川雅彦
きぬ(千代の養母)/多岐川裕美
若宮喜助(千代の実父)/宅麻伸
とも(千代の実母)/木村多江
よね(一豊・千代の娘)/皆川陽菜乃→森迫永依
<一豊・千代をめぐる人々>
望月六平太/香川照之
小りん(甲賀の忍び)/長澤まさみ
堀尾吉晴/生瀬勝久
いと(堀尾吉晴の妻)/三原じゅん子
中村一氏/田村淳
とし(中村一氏の妻)/乙葉
織田信長/舘ひろし
帰蝶→濃(信長の妻)/和久井映見
市(信長の妹、浅井長政・柴田勝家の妻)/大地真央
浅井長政/榎木孝明
茶々→淀(浅井長政・市の長女、豊臣秀吉の側室)/野口真緒→永作博美
柴田勝家/勝野洋
林通勝/苅谷俊介
佐久間信盛/俵木藤太
丹羽長秀/名高達男
足利義昭/三谷幸喜
今川義元/江守徹
明智光秀/坂東三津五郎
細川藤孝→細川幽斎/近藤正臣
細川忠興(藤孝の長男)/猪野学
玉→細川ガラシャ(光秀の娘、忠興の妻)/今泉野乃香→長谷川京子
木下藤吉郎→羽柴秀吉→豊臣秀吉/柄本明
寧々→北政所(秀吉の妻)/浅野ゆう子
旭(秀吉の妹、副田甚兵衛・徳川家康の妻)/松本明子
副田甚兵衛(旭の夫)/野口五郎
なか(秀吉の母)/菅井きん
治兵衛→羽柴秀次→豊臣秀次(秀吉の甥)/柴井伶太→成宮寛貴
竹中半兵衛/筒井道隆
前野将右衛門/石倉三郎
蜂須賀小六/高山善廣
福島正則/嵐広也
黒田官兵衛/斎藤洋介
前田利家/唐沢寿明
石田三成/中村橋之助
<家康をめぐる人々>
徳川家康/西田敏行
酒井忠次/森田順平
本多忠勝/高田延彦
井伊直政/篠井英介
宇喜多秀家/安田顕
小早川秀秋/阪本浩之
01月08日第01回『桶狭間』………………尾崎充信
01月15日第02回『決別の河』……………尾崎充信
01月22日第03回『運命の再会』…………加藤拓
01月29日第04回『炎の中の抱擁』………尾崎充信
02月05日第05回『新妻の誓い』…………尾崎充信
02月12日第06回『山内家旗揚げ』………加藤拓
02月19日第07回『妻の覚悟』……………加藤拓
02月26日第08回『命懸けの功名』………尾崎充信
03月05日第09回『初めての浮気』………尾崎充信
03月12日第10回『戦場に消えた夫』……加藤拓
03月19日第11回『仏法の敵』……………加藤拓
03月26日第12回『信玄の影』……………梛川善郎
04月02日第13回『小谷落城』……………尾崎充信
04月09日第14回『一番出世』……………加藤拓
04月16日第15回『妻対女』………………梛川善郎
04月23日第16回『長篠の悲劇』…………尾崎充信
04月30日第17回『新しきいのち』…………加藤拓
05月07日第18回『秀吉謀反』……………久保田充
05月14日第19回『天魔信長』……………梛川善郎
05月21日第20回『迷うが人』……………加藤拓
05月28日第21回『開運の馬』……………梛川善郎
06月04日第22回『光秀転落』……………尾崎充信
06月11日第23回『本能寺』………………尾崎充信
06月18日第24回『蝶の夢』………………梛川善郎
06月25日第25回『吉兵衛の恋』…………久保田充
07月09日第27回『落城の母娘』…………尾崎充信
07月16日第28回『出世脱落』……………梶原登城
07月23日第29回『家康恐るべし』…………加藤拓
07月30日第30回『一城の主』……………梛川善郎
08月06日第31回『この世の悲しみ』………大原拓
08月13日第32回『家康の花嫁』…………梶原登城
08月20日第33回『母の遺言』……………尾崎充信
08月27日第34回『聚楽第行幸』…………大原拓
09月03日第35回『北条攻め』……………加藤拓
09月10日第36回『豊臣の子』……………梶原登城
09月17日第37回『太閤対関白』…………久保田充
09月24日第38回『関白切腹』……………久保田充
10月01日第39回『秀吉死す』……………梛川善郎
10月08日第40回『三成暗殺』……………梛川善郎
10月15日第41回『大乱の予感』…………加藤拓
10月22日第42回『ガラシャの魂』…………加藤拓
10月29日第43回『決戦へ』………………尾崎充信
11月05日第44回『関ヶ原』………………尾崎充信
11月12日第45回『三成死すとも』………梛川善郎
11月19日第46回『土佐二十万石』………梛川善郎
11月26日第47回『種崎浜の悲劇』………加藤拓
12月03日第48回『功名の果て』…………加藤拓
12月10日第49回(最終回)『永遠の夫婦』…尾崎充信
原作
「功名が辻」 文春文庫 全4巻 各570円
その他題材となりそうな司馬作品
「国盗り物語」<3><4> 新潮文庫 740円,900円
「新史太閤記」<上><下> 新潮文庫 各660円
「播磨灘物語」<1>〜<4> 講談社文庫 各660円
「豊臣家の人々」 中公文庫 920円
「関ヶ原」<上><中><下> 新潮文庫 各740円(下巻は700円)
「戦雲の夢」 講談社文庫 680円
「城塞」<上><中><下> 新潮文庫 各780円(上巻は820円)
「女は遊べ物語」(「司馬遼太郎短篇全集」第4巻所収 文藝春秋 1,800円)
ガイド本
NHK大河ドラマストーリー「功名が辻」前編 日本放送出版協会 1,050円
功名が辻 2005年NHK大河ドラマ完全ガイドブック 東京ニュース通信社 980円
別冊ザテレビジョン NHK大河ドラマ「功名が辻」 角川書店 1,100円
時代考証担当 小和田哲夫氏による概説書
山内一豊と千代 日本放送出版協会 1,365円
賢妻・千代の理由 日本放送出版協会 1,470円
山内一豊 負け組からの立身出世学 PHP新書 798円
山内一豊のすべて 新人物往来社 2,940円
ageteon、sageteonなら、スレッドタイトルの末尾に[転載禁止]を表示
ageteoff、sageteoffなら、スレッドタイトルに[転載禁止]を表示しない
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Cinema/5784/taigadorama/cast/koumyougatuzi.html
とたんに一豊と千代がははーっと平伏して音楽がかぶりなか様大笑い
ほとんど水戸黄門じゃん!と笑ってみてしまった。
そして、朝日(旭)が長浜城にあがった場面のBGMが何となく哀しい曲調で
後の悲劇の発端が感じられて、気の毒に思ったよ。
功名では、秀吉の姉夫婦は出さないような展開だけど
姉夫婦とて良い思いをした反面、息子秀次を殺され・・・
分不相応に特別の出世をした秀吉をとりまく家族の悲劇だね。
山内一豊(2万石)は700の兵を率いて参陣。
なぜドラマではやらなかったのか。
目立った武功がないから豊臣政権の話をドラマでやったほうが視聴率取れると思ったんでしょ
ドラマでは一豊は参陣しなかったという設定。
一豊は北陸攻めの軍勢を長浜城で饗応。
竹中半兵衛が稲葉山城で千代と話をしていた場面のセットと同じではないかしら。
治部(治部大輔)
石田三成
治部(治部少輔)
もっと羽柴家の中での武将達の出世争いを描いてほしかったな。
六平太はまた回転してくれないものか。
そのあと北条征伐の山中城攻めで部下の渡辺勘兵衛の手柄もあって名を上げる。
(けど勘兵衛は中村に愛想付かして出奔しちゃうんだけど。)
出演させれば良かったのに。
後に因幡鳥取藩主池田光仲に仕え着座(鳥取藩での家老の呼称)池田知利(下池田)の客分となる。禄高100〜150石。
一清の子孫は藩主の陪臣として明治維新をむかえ、現当主・中村義和は千葉県に在住し、分家の中村忠文(中村家の会会長)は鳥取市で中村歯科医院を開業している。
ニコニコと山内家の風呂を借りに来る堀尾夫婦は、もう一組の山内夫婦って感じだね。
嫉妬し、一線を引きたがる中村一氏の気持ちも判るが、堀尾夫婦の生き方の方が得だよね。ストレスも溜まらないし。
松本明子の日焼けメイクや柄本のサル顔、
菅井の老けっぷりなどが良かっただけに違和感ばりばりです。
軍師は出陣の方角の吉凶判断等を行ったり、占い師の側面もあったという。
一豊の出世でギスギスしかかった関係を円満にした。
しかもあからさまにじゃなくて自然に…。
無理強い離婚も死別もともに経験。
仏とかあだ名ついているくらいだから。
中村一氏とは、対極にいる人物でちょうど真中に一豊が
いる感じでバランスとれていていい感じ。
実際にはこの3人仲良かったのかな?
最終的に、3人とも一緒に家康についたんだよね
千代が「錠前」にたとえた東から3つの城主だよねこの3人。
話の中盤で絡むし、ラストでも彼らの跡継ぎと一豊が絡むからいい伏線になる。
2人目の夫は無理矢理離婚させられ
ただ「農民でいたい」という以上に、
「行けば必ず良くないことが起きる」と、何かを感じ取っていたかのような抵抗ぶりだったし。
功名が辻では金八にしか見えない
息子が出世しても田畑を耕していたのは史実みたいだね
特に新右衛門は月代が違和感感じた
織田405万石>>武田130万石>>徳川48万石
最近知ったこと
小山会議の段階 淀君や大阪城の奉行たちから「石田三成がなんか不穏ですから、内府戻ってきてください」という書状が来てた。
それを発表したんだから、豊臣系も家康に従うのが当たり前だ罠(むしろ、真田が離脱したのが不思議)
↓
福島 池田達が上京開始
↓
石田が淀君、奉行衆、毛利を味方につけて 内府ちがいの状を発表
こういう時系列で考えれば、山内が言いだして、東海道諸侯が城を明け渡してたのは、徳川にとってすごくありがたかったんじゃないかと
もし明け渡してなければ、内府ちがいが来た段階で
話が違うんで通せませんというのが一人や二人いたかと
織田家、浅井家、豊臣家、徳川家の血が流れている
功名が辻=功名十字路
↓
功名の辻
↓
功名の十字路
↓
功名十字路
過去スレ読んで初めて知りました
お恥ずかしい限り
実在
実在
実在
実在
実在
実在
実在
拾(→ 湘南)
実在
実在か否か確認できない
>題名「功名が辻」の辻は「十字路、交差点、路上」という意味である。
> https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB
女性の嗜好
・信長:癒し系
・秀吉:ブランド志向
・家康:健康派タイプ
「豊臣秀次や堀尾吉晴、中村一氏という、これまであまり登場することのなかった人物が出てきて面白い」
「脚本家ががんばっている」と述べ、
また原作に関しては「小説と史実は異なるもの」として、「判断力がなければ戦国の世は生き残れず、やはり一豊はピカイチだった」と語っている。
作り話かと思っていたらネタ元があるんだな
へえ〜ソースがあるんだ
※ピンクラス、またはそれに準ずるの出演者のみ
津川雅彦、前田吟、近藤正臣、江守徹、山本圭、北村和夫、品川徹、津嘉山正種、佐久間良子、菅井きん
家康が織田信雄に「内府さま、内府さま」と言っているが
この時点で織田信雄は内大臣(内府)なのである。
織田信長
豊臣秀吉
織田信雄
豊臣秀次
徳川家康
豊臣秀頼
徳川秀忠
『徳川家康』で石川数正が秀吉に「ないふさま」と言っていたのは
そういうことだったのか、と納得
同様に
大御所=家康 家康=大御所 というわけでもない。
秀忠は将軍職を家光に渡して大御所となっているから。
そして天正11年(1583)
小牧長久手の前哨戦として、羽柴秀吉が滝川一益の居城・伊勢亀山城を攻撃した時、
この軍に従った一豊とともに真っ先に進み、大いに武功を表し、そして壮烈な討死をした。
時に32歳であった。
五藤吉兵衛には祖父江新右衛門といって、これも同じ一豊の家臣であり、年来の親友が有った。
吉兵衛が死んで、祖父江はこんな事を、人に語った
「私と吉兵衛の仲の良さというのは、親族以上のものだった。
あいつとはいつも、怒ることもなく、隠すこともなく、戦場に挑んでも共に励んだものだが、
私はいつも、吉兵衛に劣っていたよ。
今度の亀山城攻めの前の夜、私の陣に吉兵衛がやってきて、夜半過ぎまで軍物語をしていてな、
そこで、お互いの今までの手柄を数えてみたんだ。
自身で敵の首を獲ったこと、吉兵衛は26回。私は24回。
生け捕りをしたのは、吉兵衛が15人、私が11人。
敵の城に乗り込んだのは互いに6回。
敵と組み打ちをしたのは、吉兵衛が7回、私が9回であった。
吉兵衛はその時こう言った
『組み打ちはお主に負けたなあ。』
私は言ってやったんだ
『いいや、もう一つ勝っているものがあるぞ』
『それは何だ?』
『私のほうが5つ、歳が勝っている。』
お互いに大笑いしたものさ。
その夜は互いに酒を飲み、物語して別れたが、これを暇乞いにして、翌日、吉兵衛は討ち死にした。
私は、比翼の友(二羽の鳥が一体になって飛ぶように仲睦まじいこと)を失ってしまった!
もはや戦場に挑んでも勇む気持ちになれず、酒宴の席で楽しむ気持ちにもなれないのだ。」
そう、涙を流して語ったのだという
(土佐物語)
・大河ドラマ「秀吉」
・大河ドラマ「功名が辻」
市川山城守(市川信定)
山内一豊の長浜城主時代に仕えた。火矢の名手で小田原征伐では活躍し、一豊が遠江国掛川城に封じられた際、千石を領したという。
関ヶ原の戦いの直前、一豊は徳川家康に従い上杉景勝の討伐(会津征伐)に参加していたが、会津攻めに出陣した大名の家族を人質に取ろうとした大坂の石田三成の手から見性院(千代)を救うため、一豊の使者としてこの信定が派遣されている。
ドラマが史実のまんま
余所から入部してきた大名はただでさえ人手も足りなくなるので
地元の元家臣を大量に雇用するのが常であったが、
一領具足を中心とした旧長宗我部氏の武士の多くは新領主に反発し
土佐国内で多くの紛争を起こした。
これに対し一豊は重要なポストを外部からの人材で固め、
家康の敵であった長曽我部元親の遺臣らを桂浜の角力大会に招待しておいて
捕縛し73名を磔にしてRなど、あくまで武断措置を取ってこれに対応した。
この為一豊は常に領内で命を狙われる危険性があり、高知城の築城の際などには
6人の影武者と共に現地を視察した。
上士・郷士のしがらみが後の明治維新の原動力になったとはいえ、長宗我部遺臣にとっては非常に性質の悪い話。
高知城の築城の際などには一豊と同装束六人衆(野中玄蕃・市川大炊・柏原長宅(半右衛門)・乾宣光(七郎左衛門)・乾和三(猪助))
を影武者として共に現地を視察した(影武者の存在などは機密事項であったため通常記録には残らないが、一豊の場合には明記されている稀有な事例である)。
幕末の上士、郷士のしがらみはかなり別の話。
つーか幕末に上士に対抗した「土佐郷士」、とくに土佐勤王党の連中は長曽我部侍というより
新たに経済的に成功して郷士株を買った「新興武士」がその中心。
幕末、由緒正しい長曽我部以来の郷士は、実はほとんど上士についていた。
功名が辻が放送されていたとき
ブログに毎週感想をupしてた人が
「さて、今週の大河ドラマ・太閤記」って書いてた
天正8年(1580年)、山内一豊とその正室の見性院との長女として近江国で生まれる。名は『一豊公紀』には「與禰」と伝わる。
天正13年(1585年)に一豊が近江長浜城主となり、城内で暮らすが同年11月29日の天正大地震で城が全壊し、命を落とした。享年6と伝わる。
>天正13年(1585年)に一豊が近江長浜城主となり、城内で暮らすが同年11月29日の天正大地震で城が全壊し、命を落とした。
ドラマそのまんま
岩倉織田氏の家臣であった父を亡くし、仇敵である信長に仕官したそんな一豊のもとに、千代という美しい娘が嫁いできた。
婚礼の夜、千代の夢は伊右衛門が一国一城の主となることを約束し、木下藤吉郎秀吉の引きもあって、負傷や苦戦を重ねつつも、
千代の励ましもあって少しずつ出世の道を上って行き、信長の家臣ながら与力として秀吉に仕え、後に秀吉の家臣となる。
城下で駿馬を売る商人を見かけた一豊は、一旦は諦めたものの、
話を聞いた千代は秘蔵の小判を差し出してその馬を手に入れるよう促す。
その小判は、伯父である不和市之丞が、夫の大事な時に使うようにと千代に持たせたものだった。
一豊は日頃から、手柄を得るために分にそぐわない多くの家臣を(千代の入れ知恵で)抱えていたため自身は貧乏続きであり、
そんな自分に妻が秘密でへそくりを隠していた上、金を一方的にあてがわれる事に一時憤慨するが、千代の泣き落としにあって結局金を受け取って馬を買い、
その後の京都御馬揃えにて名声を博した。
五藤吉兵衛と共に、一豊の父盛豊のころから山内家のために尽くす。吉兵衛と大いにウマが合う。祖父江家も吉兵衛の五藤家と並んで、幕末まで山内家に仕える。
新右衛門と並ぶ、一豊の父盛豊のころからの郎党。機転が利き、一豊の牢人時代を助け、織田家仕官の後は新右衛門共々一豊の手足となって働き、亀山城攻めで討ち死にする。
明智光秀が自らの意思で決起して本能寺の変を起したという説の総称。単独犯行説や光秀主犯説、光秀単独謀反説など幾つか同義の言い方がある。
突発説(偶発説・油断説・機会説)
怨恨説(私憤説)
不安説(焦慮説、窮鼠説)
ノイローゼ説
内通露顕説
人間性不一致説
秀吉ライバル視説
功名が辻には少ないなー
柴田神社には勝家とお市が祭られているそうな
慶長のころのお話。
土佐の藩主、山内一豊が室戸岬の沖を航海中に突然の時化に襲われた。
船体が悲鳴を上げ、このままでは沈没してしまうと思われた・・・
まさにその時、何処からともなく一人の僧が現れ、巧みに船の舵を取り、船は無事に港へと辿り着くことができた。
一豊が礼を言おうと僧を探したが、すでに僧の姿はどこにもなかった。
近くの寺の僧であろうかと、一豊が探させると、なんと津照寺の御本尊が潮水で濡れているのが見つかった。
この寺の御本尊は地蔵菩薩であり、弘法大師が安置したと言われ、以来「舵取り地蔵」と呼ばれるようになった。
またこの地蔵菩薩は僧に身を変えて火事を村人に知らせ、火難を逃れたという物語もあり、
今でも「水難、火難よけ」の仏さまとして親しまれている。
演:松本元
信長を火縄銃で暗殺しようとした際に登場した。六平太の指示に従い、しぶしぶながら信長を威嚇射撃する。
京都はキリシタンの歴史も刻まれた街なのです
演:野口五郎
旭の夫。硬骨漢で、当初は「縁戚関係で出世した男と言われたくない」と旭を娶ることを拒否するも、
秀吉に説得されて意を翻した。
最初の夫・源助の死に暮れる旭を大事にし、旭は徐々に心を開いていった。寧々からはあまり評価されていない。
しかし旭が家康の元に嫁がせると命が下り、夫婦は突然引き裂かれる。
後に秀吉の離縁による出世話を一蹴して失踪するが、旭が病の床に就くと偶然再会した千代の手引きで再会し、
甚兵衛の書状を預かった針売りとして、旭に別れの言葉を告げた。
演:三浦春馬(幼少期:泉澤祐希)
幼名は拾(ひろい)。捨て子であったが一豊夫妻が養育する。
跡目を継がせようとするが、その件で「実子ではない」という理由から家臣たちの猛反対に遭い、
一豊夫妻が止む無く出家させ、僧になる。
その後、一豊が一領具足の頭目たちを謀殺したことに失望し、彼のもとを離れようとしていた千代のもとに現れ、「寛猛自在」という言葉について説いて千代を慰留した。
天正元年(1573年)織田信長の越前進攻の際に抗戦。殿を務め、刀禰坂の戦いで織田家臣山内一豊に挑まれ、重傷を負わすも逆に殺された。
首は織田家臣の大塩正貞が取り、一豊に渡したという。
弟も剛勇で知られたが、一旦は助太刀した兄を見捨てて退き、その戦いで戦死したという。
同合戦で織田方に討ち取られた武将の中にある三段崎六郎は勘右衛門かあるいはその弟と推定される。
なお、三段崎氏の子孫は後に医師・谷野一柏に弟子入りし、朝倉氏の滅亡後は、福井県で代々医業を生業としたという。
演:徳井優
山内家の小者。石田三成の挙兵を知らせる千代からの密書を一豊の元に届けた
堀尾忠氏(堀尾吉晴の子)が言うべき台詞を一豊が奪ってしまうんだよね
ユーモラスでした、
ロケをもっと多くすれば、視聴率はもっと上がったのにな
──150年に及ぶ戦国の世は終わった。
その戦いの日日を、
手に手を取って生き抜いた
千代と一豊の生涯も終わった。
それから今日まで、幾度も時代の扉は開き
変革の嵐は吹き荒れた。
そしてそのたびに、人々は心から平和を願った。
しかし、人の世に戦の尽きることはない──。
あの世で、
若い一豊と若い千代が再び出逢いました。
一豊は千代をおぶって、海辺を歩き出します。
永遠の夫婦。
新たなる二人三脚のはじまりです。
── 完 ──
祖父江徳心斎(医者)は架空の人物かもしれない
「この物語は、 乱世の片隅で命の瀬戸際に手と手を携えて生き抜き、
ついには土佐24万石の盟主にまで登りつめた山内一豊とその妻千代の物語である」
千代よりも一豊の名を先に言っているという。
>六平太の指示に従い、しぶしぶながら信長を威嚇射撃する。
六平太「言われたとおりにやらねば銭はやらん」
山内一豊公初所領之地
近江唐国四百石
ドラマにおける山内一豊の石高の推移
20石(仕官時、スタート)
50石(稲葉山城落城後)
200石(金ヶ崎で三段崎勘右衛門を討ち取った恩賞)
400石(第14回『一番出世』。小谷城落城後。150石の中村や堀尾をリード)
千石(時期不明。中村、堀尾は300石)
千300石(三木城落城後。山内、中村、堀尾同時。3人同格)
3千石(山崎の戦い後)
3千500石(時期不明)
3千800石(賤ヶ岳後。第28回『出世脱落』。中村は2万石、堀尾は1万7千石の大名)
2万石(小牧長久手後。身をていして秀次をかばった恩賞)
5万石or6万石(北条攻め後。中村は14万5千石、堀尾は12万石)
20万石(関ヶ原後)
演:宅麻伸
近江浅井氏の家臣であり千代の父。郷士だったが、戦で敵の鉄砲に当たり命を落とす。
御免そうらえ
NHK大河ドラマなどに携わった殺陣師の林邦史朗(はやし・くにしろう)さんが、膵臓(すいぞう)がんのため、29日に亡くなっていたことが31日、分かった。76歳だった。
林さんは東京都出身で、高校卒業後「劇団ひまわり」に所属して時代劇を学び、65年放送の大河ドラマ「太閤記」以降、「龍馬伝」「武蔵」や現在放送中の「花燃ゆ」など数多くの作品で殺陣師を務めてきた。
土佐の一両具足の頭領役(竹之内五左衛門)として、出演しました。
土佐弁が、けっこう難しかった。
江戸弁なら、大丈夫なんですけど。
あいみたがい【相身互い】
同じ境遇にあるものどうしが同情し,助け合うこと。また,そうした間柄。
人の世に戦のない時代はない。
ハイテク兵器が戦争の形を変えたように、
430年前、信長軍が見せた射撃戦は 戦の常識を一変させた。
3,000挺の鉄砲による大規模で組織的な射撃戦は
ヨーロッパでさえまだ行われていない。
実に、世界初のことであった。
戦国時代はまさしく革新の時代であった。
しかし、信長、秀吉、家康と受け継がれていった
天下統一の野望の下で、
おびただしい数の命も失われたのであった。
この物語は、
乱世の片隅で命の瀬戸際に手と手を携えて生き抜き、
ついには土佐24万石の盟主にまで登りつめた
山内一豊と その妻千代の物語である
当主の織田信長が危急存亡の時を迎えていました。
駿河国の今川義元が上洛すべく
大軍を引き連れてこの尾張に攻め込むのだそうです。
信長は密かに桶狭間山を下見します。
ゼイゼイと息を切らしながら後からついてくるのは藤吉郎です。
藤吉郎は後の豊臣秀吉となる人物で、当時はまだ25歳。
27歳の信長にガンバって仕えていますが、
演者の柄本 明さんは当時58歳。
あんな長距離を全速力で走らせては、
そりゃあ鬼のような形相になりますわな。
千代の父親も実在のモデルがいるとは
山岡荘八原作の大河「徳川家康」では光秀も三成もむごい扱いだった
よく乳を飲み、よく寝る子じゃった」と懐かしむ喜助に
『父ちゃん、それ何度も聞いた』と言ってしまえば、
感動シーンがメチャクチャになることうけあい。
勝家軍は5万もなかったはず
>3千500石(時期不明)
賤ヶ岳のとき3千500石
いま見てたら、台詞に出てきた
ドラマにおける山内一豊の石高の推移
20石(仕官時、スタート)
50石(稲葉山城落城後)
200石(金ヶ崎で三段崎勘右衛門を討ち取った恩賞)
400石(第14回『一番出世』。小谷城落城後。150石の中村や堀尾をリード)
千石(時期不明。中村、堀尾は300石)
千300石(三木城落城後。山内、中村、堀尾同時。3人同格)
3千石(山崎の戦い後)
3千500石(賤ヶ岳)
3千800石(賤ヶ岳後。第28回『出世脱落』。中村は2万石、堀尾は1万7千石の大名)
2万石(小牧長久手後。身をていして秀次をかばった恩賞)
5万石or6万石(北条攻め後。中村は14万5千石、堀尾は12万石)
20万石(関ヶ原後)
起源については、京都で発明されたとする説が有力であるが、
他にも、江戸時代に浮世絵師が作り始めた、同時代に大奥で使われ始めた、
戦国時代後期に山内一豊の妻である見性院によって発明された等々、
様々な異説・俗説がある。
いずれにしても、贈り物の包装紙として用いられた絵奉書(祝儀用書簡)が、
木版摺りの技術と結びついて量産化されるようになったものである。武家の女性は贈り物や菓子を包むことに千代紙を使った。
(大河ドラマのほうの「国盗り物語」は総集編しかない)
>真田太平記の「そのことよ」等のように印象的な台詞が
>功名が辻には少ないなー
そのことよw
このスレではロールプレイしようにも出来ない(使う台詞がない)
藤吉郎の斡旋で屋敷を与えられます。
ま、屋敷と言っても馬小屋なのですが(^ ^;;)
ようやく仕官がかなったので、
その報告も兼ねて一豊は母を訪ねます。
「信長!?」と法秀は思わず顔を引きつらせます。
そりゃそうです。
自分の夫を殺された相手ですからね。
しかし一豊は、信長に対する思いを母にぶつけます。
法秀は、一豊の仕官について
しぶしぶ承知するしかありませんでした。
そこへ戻ってきた千代。
千代の表情がパッと明るくなったのも束の間、
「お前、まだおったのか──」という
一豊の心ない……というかバカがつくほどの正直な……一言で
千代は美濃行きを決断します。
法秀に怒られて、一豊はしぶしぶ千代に謝りますが、
こうなっては千代も意地です。
「美濃へ発ちます」と己を曲げようとしません。
「子どもじゃのう」と呆れられて
「子どもではござりませぬ!」と売り言葉に買い言葉。
今やボタンを掛け違えたように
言葉を交わせば交わすほど会話にズレが生じます。
千代は反抗期ですかね(^ ^;;)
駄馬ですが、とても頼もしそうな馬です。
その藤吉郎を迎えての酒の席で、
明日か明後日に美濃攻めが始まることを知り
千代の身を案じて、慌てて法秀の庵に戻ります。
しかし、千代はすでに庵を出た後でした。
一豊は千代を追って美濃との国境に向かいますが、
千代はその境の川を渡っていました。
必死に止める一豊ですが、千代はもう心は変えられません。
美濃の人間として生きよ とは、亡き母の言葉です。
この河は、千代にとっては
美濃の人間になるための今までと決別する河であり、
織田の一員となった一豊にとっては、
渡りたくても渡れない 川幅以上に広く大きな河でした。
赤子を背負った女の案内で、
千代はようやく西美濃の不破家にたどり着きます。
姪にあたる千代が不憫で、不破市之丞ときぬ夫婦は
自分の娘として育てることにします。
「明日にも美濃攻めが始まる、と織田方が話していた」という
千代からの情報を受けて、慌てて登城することにします。
千代が言う通り、翌朝には織田軍が美濃へ攻め入りますが
準備を怠りなく進めていたために、
信長は陣を引き払って尾張へ戻っていきました。
千代の手柄と言うべきか?
でも、千代の胸中には一豊のことで占められていました。
「一豊さま……生きていてくだされ……」
織田を翻弄する素晴らしい軍師が斎藤方に現れます。
この半兵衛の策略は、
美濃攻めを諦めない織田軍を何度も窮地に陥れます。
藤吉郎は、このまま真っ正面から美濃稲葉山城を攻めたところで
今まで同様、勝てないのはすでに見越しております。
ゆえに、半兵衛に負けない知恵で戦を切り抜けます。
半兵衛と藤吉郎の知恵比べ!
半兵衛は藤吉郎を認め、藤吉郎は半兵衛を尊敬している。
そんなふたりが、あの河に偵察に来ます。
半兵衛は千代を連れて、藤吉郎は一豊を連れて。
河を挟んで、ではありますが、千代と一豊の久々の再会です。
一豊との別れのシーンが千代の脳裏を流れていきます。
天正元年(1573年)8月の朝倉氏との刀禰坂の戦いでは顔に重傷を負いながらも敵将三段崎勘右衛門を討ち取った。
この戦闘の際、一豊の頬に刺さったとされる矢は、矢を抜いた郎党の五藤為浄の子孫が家宝とし、
現在、高知県安芸市の歴史民俗資料館に所蔵されている。
浅井新八郎→前野長康→牧村政倫→山岡景隆→織田信長→豊臣秀吉→秀次→秀頼→徳川家康
「一豊&五藤吉兵衛&祖父江新右衛門&祖父江新一郎&堀尾&中村」の6人で退却し、
全員無事帰還というところがドラマらしい
・三方ヶ原の戦い
鶴翼の陣の負け
・関ヶ原の戦い
鶴翼の陣の負け
信玄本隊(鶴翼の陣)午前中苦戦す
尾張側から美濃を見るのは藤吉郎と山内一豊。
そして、美濃側から尾張を見るのは
竹中半兵衛と千代であります。
半兵衛は偵察を終えて屋敷に戻ろうとします。
千代は、向こう岸にいたのが一豊であると分かっていて、
後ろを振り返り、後ろを振り返り半兵衛についていきます。
永禄6(1563)年──。
千代は、一豊との出会いを半兵衛に話します。
その一豊は、向こう岸にいた騎馬の女人が気になる様子ですが
残念ながら、その女性が千代だとは気づいていないようです。
清洲城では、半兵衛の情報が披露されます。
19歳でありながら愚君の斎藤竜興を立派に支える男です。
「我が家中に半兵衛を凌ぐ者はおらぬのか」と
疑問を持った信長、ごもっともであります!
藤吉郎は、墨俣周辺を偵察した内容を元に、
美濃と尾張の中間に位置する墨俣に砦を築くことを主張。
藤吉郎はそこに3日で築いてみせると息巻き、
ニヤリとする信長はそれを許可します。
ちなみに墨俣は敵地なんですけど(^ ^;;)
組み立てやすいように寸法を揃えた丸太をいかだに組んで
木曽川上流から墨俣へ向かって流すという斬新なアイデアで
ちょうど3日目に墨俣に砦が完成します。
信長が墨俣砦を視察します。
そこで藤吉郎の働きを認め、禄高500石にし
幼名日吉から、“秀吉”という名を与えます。
薪を取ろうとして尻餅をつく ちょっとドジな千代ですが、
そんな千代を男がジッと見ています。
千代に迫るようにスタスタと近づくその男に、
「名を名乗りなさい!」と
のけぞろうとも身を守ろうともしない千代は
えらい度胸の据わった“男”です(笑)。
Kassyなら、後ずさりしてヒャア!と逃げますが(^ ^;;)
その男は、幼なじみの六平太であります。
千代を守ろうと兵士と切り結び
崖から落ちて気を失っていた六平太は、
甲賀の忍びに助けられたのだそうです。
千代は、六平太が忍びと聞いて
一豊の安否を確かめてもらうようにします。
行儀見習いに千代がご奉公しています。
六平太も庭師に化けて庭の枯れ木を掃いているのですが、
さすがは忍び、自分の存在を消すのが上手です。
千代が依頼した一豊情報を独り言のようにブツブツと伝えます。
一豊は今は墨俣にいて、今日、半兵衛調略のために
この菩提山城にくるかもしれない、とのことです。
「やまうち、ひできちろう、とよとよにござーる!」
六平太の情報通り、その日のうちに
秀吉が一豊を伴って訪問してきます。
秀吉たちに侍女たちがお茶を出します。
一豊にお茶を出したのは千代でして、
出しながら、こっそりと鉄砲玉を一豊に見せます。
ビックリして凝視する一豊に
千代はにっこり微笑み、下がっていきます。
半兵衛は、秀吉とともに来訪した男が
千代が「命の恩人」と語っていた一豊だと分かった上で、
秀吉と2人だけで話がしたいからと
一豊に席を外すように促します。
退出した一豊を、千代は廊下の端で待っていました。
あまりに大きく、美しく変わった千代を見て
一豊は言葉が出ません。
斎藤家重臣たちは大いに不安を感じていました。
一方、千代はご奉公先から暇を出されていました。
何が原因か分からないまま、
足が地に着かぬ心地で不破へ戻ってきます。
しかしそこで、養父・不破半之丞から
稲葉山城乗っ取りを聞かされるわけです。
前代未聞の稲葉山城乗っ取りを
たった16人で成し遂げた首謀者は……竹中半兵衛。
竜興が改心するなら城はそのまま返上し、
自らは隠居して学問を究めたいと言う半兵衛に
千代は納得がいきません。
竜興に代わって半兵衛が美濃を治めたら
この世から戦がなくなると信じていたのです。
改心した竜興は城を返上してもらいましたが、
半年後には、酒や女に耽る毎日に逆戻りしています。
市之丞も登城停止を食らっています。
こういう時だからこそ斎藤を立てねばと考えているようで、
「お前を織田には渡さぬ」と千代に言い聞かせます。
しかも“家中のしかるべき婿を探す”と言い出す始末。
あぁ、本人の気持ちとは裏腹に
一豊がどんどん遠ざかっていく……。
ワラをもつかむ思いで、千代は半兵衛に文をしたため
一豊との仲を取り持ってほしいとお願いしています。
忍びの六平太を使って
一豊の安否を調べさせ、半兵衛に文を出し、
軍師の半兵衛を使って自らの恋の成就をさせるとは、
公私混同もはなは……(以下略、笑!)
再び、秀吉が半兵衛を訪ねてきます。
しかし「信長は嫌いだ」と相手にしません。
六平太も千代の文を持って半兵衛を訪ねます。
半兵衛は千代からの文を読み、
六平太に千代を連れ出してくるように頼みます。
半兵衛から秀吉に「会いたい」という文が届きました。
「いよいよ落ちるぞ」と勇んで出かけた秀吉と一豊ですが──。
竹中半兵衛ら16人が稲葉山城を奪い取る。
>「やまうち、ひできちろう、とよとよにござーる!」
聞き取れないあれは「とよとよ」と言っていたのか
「とよとに」とか「とよとり」とか聞こえていた
・史実
織田信忠→溝口秀勝→山内一豊
・ドラマ
織田信忠→山内一豊
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%86%85%E5%BA%B7%E8%B1%8A
元亀3年(1572年)頃から織田信長の嫡男・織田信忠に仕えたが、
本能寺の変で信忠が明智光秀の襲撃によって自害したとき、
康豊は早々に逃げてしまったという。
その後は溝口秀勝に仕えたものの、兄・一豊の招聘に応じて山内家に帰参。その補佐に努めた。
(中略)
なお、山内家18代当主・山内豊秋は、康豊は兄より優れた人物だったと評した。
歴史街道 2015年10月号
特集して欲しい戦国武将は?
01位 織田信長
02位 真田幸村
03位 伊達政宗
04位 武田信玄
05位 明智光秀
06位 立花宗茂
07位 上杉謙信
07位 徳川家康
09位 豊臣秀吉
10位 石田三成
10位 加藤清正
10位 長宗我部元親
10位 毛利元就
>本能寺の変で信忠が明智光秀の襲撃によって自害したとき、
>康豊は早々に逃げてしまったという。
前田玄以が三法師を連れて二条御所から脱出したように
信忠も逃げればよかったのに。
織田政権に終止符を打った信忠の死…
>山内家18代当主・山内豊秋は、康豊は兄より優れた人物だったと評した。
康豊直系の子孫としては、康豊>一豊 なんでしょうね^^;
千代は縁談を受ける決意まで固めますが、
どうしても山内一豊への思いが断ち切れません。
今すぐに会いたい、会って話がしたい。
そんな思いを竹中半兵衛が骨折って叶えてくれます。
そうとは知らない一豊は
秀吉に連れられて半兵衛の庵にやって来ます。
よくよく話し合いされよ、と
半兵衛は一豊と千代を二人きりにしてあげます。
半兵衛はおのずと秀吉と二人きりになるわけですが、
秀吉に「あの二人は結ばれますか?」と聞いてみても
秀吉の眼中には半兵衛しかありません。
いやいや、そんな意味ではなくてね(^ ^;;)
本心では一豊とともに尾張へ帰りたい千代も
自分を育ててくれた美濃の不破家を裏切れない思いもあります。
一豊も、岩倉城時代からの家来を少ないながら抱える足軽の身、
武士を捨て、どこぞで田畑を耕す安穏な暮らしはできません。
そのベクトルはお互いに違う方向を指しています。
「死ぬな」と言われて、千代は大粒の涙を流します。
六平太とともに半兵衛の庵を去ってゆく千代の後ろ姿を
一豊は、半兵衛や秀吉とともに見送ります。
姿が見えなくなって、半兵衛は突然言い出します。
「私はいつ、信長殿に会えばよいのかな」
信長に会うために小牧城に出向きます。
ただし、信長の直参ではなく秀吉の配下としての組み入れです。
その上で、稲葉山城攻撃の段取りを半兵衛がつけます。
その段取りに沿った形で、市之丞は
きぬや千代とともに稲葉山城に入ることになりました。
稲葉山城がようやく落とせるか、と信長はワクワクしますが
なんだかんだで半年が過ぎ……。
業を煮やした信長に呼びつけられた半兵衛は
信長の前だからこそ「策はありませぬ」と言い張ります。
稲葉山城は山城ですので、
普通にかかれば二年三年経っても落とせない城です。
その策で城を落とすには、一豊の力が必要なのだとか。
呼ばれた一豊に、半兵衛は稲葉山城へ通じる裏道を教えます。
そして、千代を敵の刃から命を賭して守れと言うのです。
その案内役として、堀尾茂助がつけられます。
ちなみに茂助は後の堀尾吉晴でして、
一豊の親友として今後も渡り合っていきます。
織田軍に本丸に攻め込まれ、
観念した市之丞はきぬとともに果てるつもりです。
千代にはもう行くところがなく、亡き父母のところへ
養父母とともに運命を共にする覚悟です。
いち早く本丸に攻め入った一豊は
必死に千代を探しますが、なかなか見つかりません。
炎の中を、火の粉を避けながら奥に奥にと進みますが、
ある一室の前で足が止まります。
千代が長刀を手に、一豊に向かって構えています。
勢いで中へ飛び込んだ秀吉と一豊は
今まさに自害しようとしていた
市之丞ときぬから刀を奪います。
市之丞はあくまでも斎藤方として骨を埋めるつもりで
織田方には奪われたくないという気持ちがありますが、
秀吉の目的は、もはやそんなところにはありません。
──二人は好き合うているのだ!
市之丞にとって、初めて聞くことであります。
千代の口から「一豊殿をお慕い申しております」と
一豊を慕う気持ちが明らかにされますが、
一豊の「好いておりまする!」という突然の告白には、
市之丞ならずとも千代本人が
一番ビックリしているかもしれません。
こんな状況を見せられて、
秀吉は市之丞に二人の婚儀を迫ります。
子どものいない市之丞ときぬが、
わが子同然に慈しみ育ててきた千代です。
市之丞としては、
もはや反対する理由すらありません。
──当家、承知!
千代と一豊の気持ちが、通じました。
突然響き渡る「ありました!」の声。
嫁入りする千代のために、と
市之丞ときぬがせっせと貯金していたお金を発見しました。
10両あります。
全てが焼け、嫁入り道具には何の準備もできないながら
火から免れたこの10両だけを持たせてやります。
「千代のために使えというお天道様の思し召しじゃ!」
「貧しくとも、暮らし向きのことに使ってはなりませぬよ」
という養父母の言葉を胸に、
千代は有り難くいただくことにします。
永禄10(1567)年9月、美濃入りした信長に従って
50石取りになった一豊も尾張から移り住むことになりました。
そしていよいよ婚礼の日──。
そわそわして落ち着かない一豊に対し、
千代はいかにも堂々としていました。
そんな二人を見守り、祝う面々。
幸せそうな千代の姿です。
──────────
永禄10(1567)年9月、
織田信長が稲葉山城を落とし、岐阜城と改める。
山内一豊は義より利を選んだ^^;
ちょい役に宅麻伸起用とは豪華な
司馬遼太郎さんらしい
稲葉山城下で祝言を挙げた千代と山内一豊は
母・法秀尼らに歓迎されて夫婦になりました。
千代と一豊が出会って7年余、
千代は一豊に大きなわらじを履かせてもらったことも
傷の手当をしてくれたことも昨日のことのように思い出され、
夫婦になれた幸せでいっぱいでありますが、
そんな千代でも、一つだけ知りたいと思うことがあります。
「だんな様が、いつから千代を──愛おしいと?」
一豊の夢は「一国一城の主」ですが、
千代は「だんな様と二人で長生きすること」が夢です。
しかし一豊は武士ですので、死ぬこともある と言います。
現代とは違い、戦国の乱世にあって
命の生死の間をかいくぐって生きてきたことを考えると
恐らくはルンルン♪な結婚初夜であっても
伝えておかなければならないことなのかもしれません。
「名を残すような死に方をしようぞ」という一豊を
叩き起こす千代ですが……ダイジョウブです。
二人とも立派に名前を残しましたよ、いろんな意味で(笑)
先に起きて野菜を洗っている一豊の弟・康豊と法秀、
そこへ吉兵衛と新右衛門、一豊が起きてきますが、
千代の朝が遅すぎる、と康豊や吉兵衛は少しオカンムリです。
スヤスヤと眠っていた千代が目を覚まし、
隣に一豊の姿がないのを見て
慌てて着替え、表へ飛び出します。
ちなみに千代は、少し変わった小袖を着ています。
おおよそ、上から下まで同じような柄が一般的な小袖にあって
千代の着ける小袖は、ちと斬新なデザインです。
不破の家が焼けた時、焼けずに済んだ部分を縫い合わせたもので、
今で言うところのパッチワークでしょうか。
法秀は何度も頷き「おおらかでよい」などと
かなりのポジティプ発言が飛び出しますが、
細かい部分を気にしないのか、
自分を納得させようとしているのかは分かりません(笑)。
食事時、一豊は新右衛門に妻子を呼び寄せるように言います。
それには法秀や千代も賛同するのですが、
「お家はまだまだ50石にて」と新右衛門は固辞します。
堀尾茂助の妻・いとと 中村一氏の妻・としがやってきます。
いともとしも、千代のことが気になる様子です。
「燃え上がる稲葉山城の中で結ばれた二人ゆえ──」と
寧々は見事なまでのガールズトークで話を彩りますが、
朝餉の支度もせず、誰よりも遅くまでおおいびき。
朝寝坊する嫁はどんな嫁かと、すでに城下のウワサに。
いとやとしが現代に生きていたら、
まちがいなく芸能リポーターやってそうです。
……実に平和な戦国時代(笑)。
一豊を送り出した千代は
吉兵衛と新右衛門と田畑を耕していますが、
新右衛門の家族を呼び寄せる一件について
吉兵衛から大反対を食らいます。
50石では、一豊と千代と吉兵衛と新右衛門が
やっと食べていけるだけの量でしかありません。
そんな中、新右衛門の家族をどう養っていくのか?
貧乏だからこそ、一家力を合わせて頑張らねば!
3人より4人5人の方が楽しいし……と千代は力説。
しかしその実態は、妻が1人、子が7人──。
茂助や一氏らと相撲を取って汗を流しています。
一氏はなかなかのお調子者らしく、
大恋愛の末に夫婦となった一豊をからかいますが、
そんな棘ある一言に苛立ちを覚えた一豊との間を
「まぁまぁまぁ」と抑えるのが茂助の役回りです。
そうそう、茂助は
竹中半兵衛の命で稲葉山城の裏道を先導した男であり、
彼がいなければ一豊・千代夫婦はなかったかもしれません。
稲葉山城を岐阜城と改名した信長は
「天下布武」の名の下、まずは近江を攻めるつもりです。
近江攻めの危険性について
藤吉郎は半兵衛に愚痴を言いますが、
それには半兵衛も同調します。
仮に浅井を攻めれば、
越前の朝倉が浅井に味方して攻めかかってくるでしょう。
その間、岐阜を留守にしていれば、
このチャンスに武田が攻め込んでくるのは当然。
北近江の浅井氏と南近江の六角氏は犬猿の仲で、
どちらも織田と手を組みたいと考えているはずです。
秀吉は、浅井の内情を一豊に調査させます。
近江の知り合いがいるということを聞いて、
とりあえず市之丞に会いに行くことにします。
近江出身の千代は、一豊に鮒寿司をオススメします。
作り方から味まで鮒寿司情報をインプットしようとしますが、
「遊びに行くのではない!」と一蹴されます。
市之丞に簡単な近江情報を授けてもらい
そのつてを使って近江に入ろうとする一豊ですが、
一豊の、いかにも武士らしい格好を見て
「薬売りか何かの格好をなさってはどうかな?」
結局、薬売りの格好をすることになりました。
夫の不在の間、千代は吉兵衛に
山内家の旗印についての講義を受けています。
一豊の亡き父・盛豊が 最後の合戦で掲げていた旗印、
『丸三葉柏紋(まるにみつばがしわもん)』。
丹波での戦いの折、差物に柏の木の枝を使った盛豊は
味方が大勝利を収めて枝を見たところ柏の葉が三枚残っており、
「これは縁起よし」と『丸三葉柏紋』が定まったわけです。
千代の着る小袖の評判を聞きつけ、1着ねだったわけです。
一豊がもたらす情報を元に、藤吉郎は信長に進言します。
足利将軍家に忠勤励む六角に対し、
朝倉との結びつきが固いのは先代の浅井久政であって
当代の浅井長政はそんな父・久政と対立している分
浅井の方が与し易いわけです。
浅井と手を組めば朝倉の脅威は当分消えるでしょうし、
それに乗じて六角を倒せば京への道も開かれる。
おまけに長政は、六角の家来の娘と離縁しています。
信長は市を浅井へ嫁がせることにします。
市は無鉄砲に千代を訪れ、近江の話をせがみます。
近江は子供のころにしかいなかった土地ではありますが、
千代は市にわかりやすく、近江の魅力を伝えます。
近江の魅力もさることながら 千代の小袖にも着目した市は
寧々に作ってあげていたパッチワークを
「もらっていこう」と取り上げ、城に帰ってしまいます。
翌日、再びやって来た市は千代を誘って馬で遠乗りします。
広い草原で市が語ったのは、浅井へ嫁ぐことへの重圧、不安。
顔も見たことのない、性格も何も知らない男へ嫁ぐ
女の気持ちというのはどれほどのものか、計り知れません。
栄える城下町へ市を案内して曲芸士や猿回しで楽しませ、
自邸に戻ってささやかながら料理の手ほどきもします。
山内家では貧乏な暮らしゆえ
2つの枡をひっくり返してまな板代わりに使っているのですが、
「貧乏な暮らしはお屋形さまのせいではありません」という
フォローだけは忘れません。
お礼の意味合いがあったのか、
「城に戻ったら届けさせる。“なまいた”であったな」と
心遣いをいただくわけですが、
残念ながら間違った情報を持ち帰ります。
永遠に届かなそうな気配が(^ ^;;)
ともかく、市は行列を従えて近江へ向かいます。
一作品中の歴史イベントの数では功名が一位だよ
視聴率30%は確実だった
武田が兵を分散させてしまった
【武田軍】
武田信玄(8,000人)
武田信繁、武田義信、武田信廉、武田義勝、穴山信君、飯富昌景、内藤昌豊、諸角虎定、原昌胤、跡部勝資、今福善九郎、浅利信種、山本勘助
別働隊(12,000人)
高坂昌信、馬場信房、飯富虎昌、小山田信茂、甘利昌忠、真田幸隆、相木昌朝、芦田信守、小山田昌辰、小幡憲重
【上杉軍】
上杉謙信(13,000人)
一、佐久間信盛・信栄親子は天王寺城に五年間在城しながら何の功績もあげていない。世間では不審に思っており、
自分にも思い当たることがあり、口惜しい思いをしている。
一、信盛らの気持ちを推し量るに、石山本願寺を大敵と考え、戦もせず調略もせず、
ただ城の守りを堅めておれば、相手は坊主であることだし、何年かすればゆくゆくは信長の威光によって出ていくであろうと考えていたのか。
武者の道というものはそういうものではない。
勝敗の機を見極め一戦を遂げれば、信長にとっても佐久間親子にとっても本意なことであったのに、一方的な思慮で持久戦に固執し続けたことは分別もなく浅はかなことである。
羽柴秀吉の数カ国における働きも比類なし。
池田恒興は少禄の身であるが、花隈城を時間も掛けず攻略し天下に名誉を施した。
これを以て信盛も奮起し、一廉の働きをすべきであろう。
一、柴田勝家もこれらの働きを聞いて、越前一国を領有しながら手柄がなくては評判も悪かろうと気遣いし、
この春加賀へ侵攻し平定した。
一、戦いで期待通りの働きができないなら、人を使って謀略などをこらし、足りない所を信長に報告し意見を聞きに来るべきなのに、
五年間それすらないのは怠慢で、けしからぬことである。
今まで一度もそうした報告もないのにこうした書状を送ってくるというのは、
自分のくるしい立場をかわすため、あれこれ言い訳をしているのではないか。
一、信盛は家中に於いては特別な待遇を受けていたではないか。
三河・尾張・近江・大和・河内・和泉に、根来衆を加えれば紀伊にもと七ヶ国から与力をあたえられている。
これに自身の配下を加えれば、どう戦おうともこれほど落ち度を取ることはなかっただろう。
(以下略)
中村一氏「伊右衛門様は4百石、150石の我ら(中村・堀尾)とは違います」
信長←(夫婦)→濃姫←(恋愛感情)→光秀
祖父江新右衛門/前田吟
キャストが豪華
そのランキングを見ると歴史ゲーム^^;の影響もあると思う
演:石倉三郎
秀吉の家臣。蜂須賀小六と共に川並衆として活躍し、一豊兄弟元服に立ち会うなど一豊とは古くからの仲。豊臣秀次の失脚に連座して切腹した。
「功名は太閤記」って言われたんだろうなぁ
語り「いつ背くか分からない播磨の武将たち。秀吉軍は危機を迎えていた」
完全に太閤記です^^;
同じ架空の人物・望月六平太が最期まで描かれているのとは対照的。
>千300石(三木城落城後。山内、中村、堀尾同時。3人同格)
三木城城主・別所長治を説得した恩賞
「自らの命を犠牲にした(別所)長治は、今も三木の人々から慕われています」
その日以来、光秀は不眠症となり、眠れない日日が続く。
「明智光秀ノイローゼ説」も含む本能寺の変
怨恨説(私憤説)
不安説(焦慮説、窮鼠説)
ノイローゼ説
人間性不一致説
神格化阻止説
暴君討伐説
朝廷守護説
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%9F%E5%90%8D%E3%81%8C%E8%BE%BB#/media/File:Yamauchi_Katsutoyo_portrait.jpg
そこには無数の火薬があるわけですが、
勝家と市の遺骸を秀吉の手に渡さぬためであります。
その爆発の様子を秀吉の陣中から眺めていた茶々は
母・市と義父・勝家の辞世の句を詠み上げます。
さらぬだに うちぬるほどの
夏の夜の 別れを誘う
ほととぎすかな 市
夏の夜の 夢路はかなき
跡の名を 雲井にあげよ
山ほととぎす 勝家
3800石って言ったら、兵士90人くらい雇えるリッチな禄高。
3800石で95人(または114人)動員可能です
関ヶ原の戦いを「豊臣の家臣同士の争い」とせず
「豊臣対徳川の戦い」と位置付けていることだ
(大河ドラマ春日局も同様)
1960年代に各地方紙に連載された司馬遼太郎の歴史小説『功名が辻』において、一豊を支え、
ときに口うるさく叱咤する様は、まさに家の執事的な役回りで描かれていた。
2006年にNHK大河ドラマ化された時は武田鉄矢が演じた。
だが、幕末の志士で土佐出身の坂本龍馬をこよなく愛す武田は、
土佐藩・山内家が龍馬をはじめとする郷士を弾圧・差別したことから、山内家にゆかりのある人物に抵抗を感じて出演を拒否したものの、
NHKから山内一豊が土佐の大名になる前に戦死する人物だと説得され、出演に踏み切ったという。
演:石川さゆり
京都天竺屋の侍女。
出演時間5分ほど。
意識して見ていないと気付かないですね^^
http://hello.2ch.sc/test/read.cgi/sengoku/1436049039/l50
本能寺の変に興味のある方はお出でください
「功名が辻」における「本能寺の変」
怨恨説(私憤説)
不安説(焦慮説、窮鼠説)
ノイローゼ説
人間性不一致説
神格化阻止説
暴君討伐説
朝廷守護説
逸話・後世の創作が何気にドラマに入っているなー
豊臣200万石⇒65万石
史料的根拠は全くない^^;
徳川様接待不首尾のお怒り
近江坂本、丹波領地を召し上げ、出雲石見を切り取れとの冷たき御沙汰
丹波で、足の不自由な母を、見殺しにされた仕打ち
など、語り尽くせぬ恨みあれど
誤爆しました
関ヶ原1600 大坂冬陣1614
実子 での年齢 での年齢
於次丸秀勝 1574? 26 40
豊臣鶴松 1589 11 35
豊臣秀頼 1593 7 21
孫
豊臣国松 1608 − 6
求厭 1611? − 3
甥(姉の子)
豊臣秀次 1568 32 46
小吉秀勝 1569 31 45
豊臣秀保 1579 21 35
甥(秀長の子)
豊臣小一郎 1580? 20 34
養子
石松丸秀勝 1572? 28 42
小早川秀秋 1582 18 32
結城秀康 1574 26 40
池田長吉 1570 30 44
猶子
宇喜多秀家 1572 28 42
伊達秀宗 1591 9 23
秀長の養子
藤堂高吉 1579 21 35
秀次の子
豊臣仙千代丸1590 10 24
豊臣百丸 1591? 9 23
豊臣十丸 1592? 8 22
豊臣土丸 1593 7 21
「功名が辻」は「太閤記」ですから^^;
家康が信雄に「内府様」と言っている。
この言い方は正しい。
真田信繁(浪人);側室4人
「戦争は嫌い」「戦争をする人も嫌い」
という言動を言い放つわけです。
まあ、親を戦争で失ったわけだからそれくらいのトラウマは理解できる。
だけど、幼少時代まで描いてこの設定を引っ張りすぎだ。
つまり、結局のところ山内一豊を24万石の大名にまで育てる人が、
「戦争は嫌い」「戦争をする人も嫌い」
などと言い放つ
千代とデートしたり、16人で難攻不落な稲葉山城を攻略したり、
秀吉に好かれたり、一豊に「千代って知ってる?」と投掛けたりetc.
普段なら、柴田勝家など信長の重臣が墨俣城建設に失敗を重ね、
その失敗をチャンスと思っていた秀吉が、
「なら、オラが一夜で城を築いてみせますわ!!」
と言って、失敗した重臣たちからブーイングを受けつつも、上司の信長の
「やれるもんならやってみいや!!」
と言われ、実際にやってみせた、秀吉の有名な逸話。
でも、今作では、秀吉が墨俣城建設を提案して、何の反対もなく、
「オラが3日で作ってみせますわ!!」
っていう弱腰イベントに変更されていました。
1石=1両=10万円
千代が親父から貰ったのは10両だから、
10両=100万円
となるわけです。
で、一豊の今の給料は50石なので、
50石=500万円
みんながイメージしていた旭だった
関ヶ原(TBS)の朝日も好演
最悪
「徳川家康」(NHK大河)の朝日姫
上品過ぎて秀吉の妹という感じが全くなかった
「やはり側室をお持ちになられるでしょう?」
「千代だけおればよい」
「一豊さまぁ〜」
「お腹が・・・」
「ん? お腹が痛いのか?」
「お腹が減りました・・・お腹が空きました」
「何じゃと?」
「お腹が・・・お腹が空いたのでございます!!」
「お腹が空いた・・? ち、千代」
とほのぼの路線。
やはりこういうシーンが他の大河ドラマと違うところですね。
浅井勢内部では反信長派による襲撃をしようとする動きあり。
これが今後の浅井・朝倉同盟へと続いていくのであろう。
なかなか興味深い。
『留守を守る妻』そして『武士の妻』の存在感を示してくれた。
なかなかの好演技で涙を誘う展開は、さすがの一言。
「戦に出ている夫に私の死をお知らせくださりますな」
「戦場での心の乱れは、命に関わりまする」
「旦那様へのご奉公なりません」
「どうか、私のことは・・・・」
その息子がグレてしまい、千代(仲間由紀恵)に八つ当たりをする。
そして、実の父親新右衛門(前田吟)に対しても同様の態度で接する。
この子役の演技もなかなかのもので、同時に千代(仲間由紀恵)の演技も
かなりの感動をよぶものとなった。
さて、本編では三好氏を倒すために、また上洛することに・・・。
そして、これより長期出張生活が始まるのであった。
濃姫が安土城下を一人で歩くなんてあり得ない^^;
全く描かれていない
> 最悪
> 「徳川家康」(NHK大河)の朝日姫
> 上品過ぎて秀吉の妹という感じが全くなかった
主人公(家康)の正室が田舎娘丸出しではマズイから上品な女性にしたものと。
濃姫がばたっと倒れるシーンがわざっとらしい
演:小林正寛
旭の最初の夫。一豊夫妻の招きで、旭と共に長浜城下へ移る。
長篠の戦いに徴用され馬防柵を作ったが、
自分が作った柵を見に行ったところ武田軍の流れ矢が当たり戦死した。
その死は一豊らに衝撃を与え、「自分たちが戦場に送り出したから」だと責任を感じた一豊夫妻が自刃を試みようとするほどであった。
演:野口五郎
旭の夫。
硬骨漢で、当初は「縁戚関係で出世した男と言われたくない」と旭を娶ることを拒否するも、
秀吉に説得されて意を翻した。
最初の夫・源助の死に暮れる旭を大事にし、旭は徐々に心を開いていった。
寧々からはあまり評価されていない。
しかし旭が家康の元に嫁がせると命が下り、夫婦は突然引き裂かれる。
後に秀吉の離縁による出世話を一蹴して失踪するが、旭が病の床に就くと偶然再会した千代の手引きで再会し、甚兵衛の書状を預かった針売りとして、旭に別れの言葉を告げた。
演:生瀬勝久
通称は茂助(もすけ)。
信長の稲葉山城攻略の際に秀吉に山道を案内する。
やがて秀吉の家臣となって一豊の同僚となる。
一豊・一氏とは出世争いをするライバルではあったが温厚誠実な人柄で友情を保ち、
関ヶ原の戦いの後も一豊夫妻と交流があった。
演:田村淳
一豊の同僚。通称は孫平次、式部少輔。
己より出世していく一豊や吉晴に嫉妬し、二人をライバル視していく。
3人の中では一番智謀に長け、秀次事件では見事な処世で難を逃れた。
秀吉の死が秘匿されていることを看破した。関ヶ原の戦いの直前に病に侵され、弟を東軍に送り出した後病没。
これまでの大河ドラマ的な描き方とは一線を画した戦国物語を紡いだ。
たとえば、信長・濃姫・光秀の三角関係を本能寺の変の背景として描き、
従来の大河ドラマであれば1回丸々使うエピソードである本能寺の変を放送開始わずか15分で終結させ、
残り30分を事変によって揺れ動く人物たちの描写に費やした。
また次の回でも、秀吉が光秀を破った山崎の戦いが放送冒頭のアバンタイトルでの説明で済まされてしまっているなど、
合戦自体よりその前後の人間ドラマを重視する姿勢が見られた。
一豊が光秀の死を看取るなんてあり得ない^^;
『葵 徳川三代』では二代将軍徳川秀忠を演じていたことから、
「念願の家康役。夢が叶いました。ようやく本家本元という思いです。」とコメントしている。
>>267
「噂によれば御器量芳しからず」(葵徳川三代)
語り「恩顧か恩賞か、一豊の決断のときが近づいていた」
一豊は恩賞を選びました^^;
家康「あのおなご(淀)生かしてはおかぬわ」
小早川秀秋:宇喜多旧領 最悪
史実よりも酷く(残酷に)描いてどうする?^^;
本山一揆を鎮圧した山内一豊であったが、土佐国内には未だ多くの一揆の与党が隠れ潜んでいる
という情報が多く入ってきた。
参考
本山一揆勃発顛末
http://iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-7270.html
そこで一豊は謀をなし、国中に触れをだした
『浦戸において、相撲を取らせ一見すべし!上下によらず、望み次第にまかり出よ!』
これに、男伊達するほどの者は、我も我もと馳集まった。
見物の貴賎も群集しこれを見る。
相撲始まり、上下目を澄まして楽しんでいた
と、ここに、かねてから目付けを付けて監視してあった者達で、この場に来ていた者たちへ
捕手を向け、一揆の残党七〇余人を搦め捕り、種崎の浜にて磔とした。
この時、岡豊の城下、八幡村の名主は、これも一揆に組した者であったが、相撲の場に出向かず
用心の体で自宅に取り籠っていたが、ここにも若侍を差し向け生け捕りにして、同罪とされた。
これにより悪党どもも懲り、土佐は在所在所の山の奥まで、豊かに治まったのである。
(土佐物語)
例の浦戸相撲事件ですが、土佐物語では無差別に鉄砲を撃ちかけたわけではなく、
捕物で捕らえたという、印象で言えば、鉄砲に比べれば穏健なものになっています。
演:浜田学新右衛門の長男。
血気に逸りやすく、よく一豊らに助けられたり叱咤されたりする。
後に父から家督を譲り受ける。
一両具足の粛清の折、まだ生き残っていた一人によって思いがけぬ最期を遂げる。
一豊が偏諱を家臣に与えた際の訓みから「かつとよ」と考えられている。
永原 一照(ながはら かつあき)
林 一吉(はやし かつよし)
2006年(平成18年)の大河ドラマ『功名が辻』では、「かつとよ」「かずとよ」いずれの読みとするか製作サイドでも最後まで問題となったが、
山内家より「親しまれている名前で呼んでやってください」とのメッセージもあり、ドラマでは「やまうちかずとよ」と読むことになった。
追加
祖父江 一秀(そぶえ かつひで)
語り「秀吉は家康を屈服させようと様々な手を試みてきたが、此度、『独身家康』に目を付けた」
太閤記^^;
山内首藤一族ってのは仮冒?
287 : 人間七七四年
2015/12/17(木) 19:51:17.78 ID:YhmcBbK4
>>241
山内盛豊は岩倉織田家家老の上級武士、死に様も鮮やかだった。 祖父は織田家から偏諱をもらっていたような。
備前山内氏とかでも山内首藤氏なんだから土佐山内氏も同じでもおかしくはないよ。
嫁さんも名門梶原氏(梶原景時一族)の娘とかもらってたぐらいだから少なくとも下級武士ではない。
多分鎌倉の山内氏が全国で栄えたあと滅びた一族なんじゃないの
信長の安土城の場合は天“主”閣だった
乗り回しているので、信長に奪われるかと一瞬心配になった
秀吉:628万石
VS
家康:138万石
信雄:約100万石
福島正則(1561年 - 1624年)
加藤清正(1562年 - 1611年)
加藤嘉明(1563年 - 1631年)
脇坂安治(1554年 - 1626年)
平野長泰(1559年 - 1628年)
糟屋武則(1562年 - 1607年)
片桐且元(1556年 - 1615年)
7人というのは語呂合わせで、
『一柳家記』には「先懸之衆」として七本槍以外にも石田三成や大谷吉継、一柳直盛も含めた羽柴家所属の14人の若手武将が最前線で武功を挙げたと記録されている。
浅井万福丸イベント:お市の子ではないためにインパクトはイマイチ
重臣をはじめ多くの死傷者を出した武田軍の悲劇かと思いきや
源助の死
源助(げんすけ)
演:小林正寛
旭の最初の夫。一豊夫妻の招きで、旭と共に長浜城下へ移る。
長篠の戦いに徴用され馬防柵を作ったが、
自分が作った柵を見に行ったところ武田軍の流れ矢が当たり戦死した。
その死は一豊らに衝撃を与え、「自分たちが戦場に送り出したから」だと責任を感じた一豊夫妻が自刃を試みようとするほどであった。
信長の安土城が築かれつつあったある日のこと、京での馬ぞろえを前に、
城下で駿馬を売る商人を見かけた一豊は、一旦は諦めたものの、
話を聞いた千代は秘蔵の小判を差し出してその馬を手に入れるよう促す。
その小判は、伯父である不和市之丞が、夫の大事な時に使うようにと千代に持たせたものだった。
一豊は日頃から、手柄を得るために分にそぐわない多くの家臣を(千代の入れ知恵で)抱えていたため自身は貧乏続きであり、
そんな自分に妻が秘密でへそくりを隠していた上、金を一方的にあてがわれる事に一時憤慨するが、
千代の泣き落としにあって結局金を受け取って馬を買い、その後の京都御馬揃えにて名声を博した。
一豊にとって重要な「京都御馬揃え(パレード)」をやらなかったのは
予算の関係なのだろうか?
石川さゆりさんや野口五郎さんが出演していることに驚いた
語り「鶴松の死と跡目問題は秀吉の晩年を大きく狂わせていくことになる」
太閤記^^;
前野将右衛門は歴史好きにはたまらない存在だけどドラマにはあまり出てこないなー
演:石倉三郎
秀吉の家臣。
蜂須賀小六と共に川並衆として活躍し、一豊兄弟元服に立ち会うなど一豊とは古くからの仲。豊臣秀次の失脚に連座して切腹した。
前野景定(まえの かげさだ)
演:瀬川亮
将右衛門の子で豊臣秀次の家臣。
秀吉と秀次の仲が険悪になる中で、先手を打って決起しようとしたが失敗した。
天正13年(1585年)に一豊が近江長浜城主となり、城内で暮らすが同年11月29日の天正大地震で城が全壊し、命を落とした。享年6と伝わる。
・通説:門前で拾われ、一豊の養子
・異説:一豊の隠し子
豊臣秀次が跡継ぎ問題で切腹した文禄4年(1595年)頃に、養父・一豊の命令で家を離れて出家する。これは血筋でない彼に継がせるのは山内家にとって問題になると考えたとされる。
拾は京都で修行を積み湘南宗化となり、養父母から土佐国の吸江寺を与えられて住職となる。
かなり史実を意識したドラマ作りにしたんだな
東軍の合言葉「やまがやま、さいがさい」を大勢で大きな声で兵士たちが
何度も叫んでいるけど、西軍の間者に聞こえてしまいそう^^;
葵 徳川三代の合戦シーンが一部使われている^^;
小早川秀秋が東軍に寝返ってから、後方にあった山内隊は前進し、西軍の小西隊と戦ったそうな
黒田長政が三成に陣羽織をかける@関ヶ原(TBS)
山内一豊が三成に陣羽織をかける@功名が辻(NHK)
同じ司馬遼太郎さんの原作でこうも違うのか。
一豊は軍功により土佐国9万8千石を与えられた。その後、高直しにより20万2,600石を領した。
ドラマでは最初から20万石
200石〜1000石の武士の生活⇒大河ドラマ「功名が辻」
↓
軍奉行(重臣)
↓
寄親(有力家臣)
↓
寄子(同心)(有力農民)
↓
農民
>半農半武士の生活⇒大河ドラマ「武田信玄」
平三、平五かー。懐かしい
【豊臣家】もし秀頼が生まれなかったら
http://hanabi.2ch.sc/test/read.cgi/sengoku/1450777028/l50
時代劇板の方々もぜひご参加ください
秀次が跡継ぎとなり
秀次付きの一豊はさらに出世した
http://www.nhk.or.jp/michi/special/sp00011/#movie&open=sec3
秀次政権誕生ならば、山内一豊50万石はかたい
一豊、堀尾、中村、前野はみんな大大名
この作品が初だと思う
よねが地震で死ぬと前もって分かってしまうのがイマイチ
天正13年(1585年)に一豊が近江長浜城主となり、城内で暮らすが同年11月29日の天正大地震で城が全壊し、命を落とした。享年6と伝わる。
千代は縁談を受ける決意まで固めますが、
どうしても山内一豊への思いが断ち切れません。
今すぐに会いたい、会って話がしたい。
そんな思いを竹中半兵衛が骨折って叶えてくれます。
そうとは知らない一豊は
秀吉に連れられて半兵衛の庵にやって来ます。
よくよく話し合いされよ、と
半兵衛は一豊と千代を二人きりにしてあげます。
半兵衛はおのずと秀吉と二人きりになるわけですが、
秀吉に「あの二人は結ばれますか?」と聞いてみても
秀吉の眼中には半兵衛しかありません。
いやいや、そんな意味ではなくてね(^ ^;;)
本心では一豊とともに尾張へ帰りたい千代も
自分を育ててくれた美濃の不破家を裏切れない思いもあります。
一豊も、岩倉城時代からの家来を少ないながら抱える足軽の身、
武士を捨て、どこぞで田畑を耕す安穏な暮らしはできません。
そのベクトルはお互いに違う方向を指しています。
「死ぬな」と言われて、千代は大粒の涙を流します。
六平太とともに半兵衛の庵を去ってゆく千代の後ろ姿を
一豊は、半兵衛や秀吉とともに見送ります。
姿が見えなくなって、半兵衛は突然言い出します。
「私はいつ、信長殿に会えばよいのかな」
信長に会うために小牧城に出向きます。
ただし、信長の直参ではなく秀吉の配下としての組み入れです。
その上で、稲葉山城攻撃の段取りを半兵衛がつけます。
その段取りに沿った形で、市之丞は
きぬや千代とともに稲葉山城に入ることになりました。
稲葉山城がようやく落とせるか、と信長はワクワクしますが
なんだかんだで半年が過ぎ……。
業を煮やした信長に呼びつけられた半兵衛は
信長の前だからこそ「策はありませぬ」と言い張ります。
稲葉山城は山城ですので、
普通にかかれば二年三年経っても落とせない城です。
その策で城を落とすには、一豊の力が必要なのだとか。
呼ばれた一豊に、半兵衛は稲葉山城へ通じる裏道を教えます。
そして、千代を敵の刃から命を賭して守れと言うのです。
その案内役として、堀尾茂助がつけられます。
ちなみに茂助は後の堀尾吉晴でして、
一豊の親友として今後も渡り合っていきます。
織田軍に本丸に攻め込まれ、
観念した市之丞はきぬとともに果てるつもりです。
千代にはもう行くところがなく、亡き父母のところへ
養父母とともに運命を共にする覚悟です。
いち早く本丸に攻め入った一豊は
必死に千代を探しますが、なかなか見つかりません。
炎の中を、火の粉を避けながら奥に奥にと進みますが、
ある一室の前で足が止まります。
邪魔だ! と千代の長刀を簡単に払いのけ、
勢いで中へ飛び込んだ秀吉と一豊は
今まさに自害しようとしていた
市之丞ときぬから刀を奪います。
市之丞はあくまでも斎藤方として骨を埋めるつもりで
織田方には奪われたくないという気持ちがありますが、
秀吉の目的は、もはやそんなところにはありません。
──二人は好き合うているのだ!
市之丞にとって、初めて聞くことであります。
千代の口から「一豊殿をお慕い申しております」と
一豊を慕う気持ちが明らかにされますが、
一豊の「好いておりまする!」という突然の告白には、
市之丞ならずとも千代本人が
一番ビックリしているかもしれません。
こんな状況を見せられて、
秀吉は市之丞に二人の婚儀を迫ります。
子どものいない市之丞ときぬが、
わが子同然に慈しみ育ててきた千代です。
市之丞としては、
もはや反対する理由すらありません。
──当家、承知!
千代と一豊の気持ちが、通じました。
突然響き渡る「ありました!」の声。
嫁入りする千代のために、と
市之丞ときぬがせっせと貯金していたお金を発見しました。
10両あります。
全てが焼け、嫁入り道具には何の準備もできないながら
火から免れたこの10両だけを持たせてやります。
「千代のために使えというお天道様の思し召しじゃ!」
「貧しくとも、暮らし向きのことに使ってはなりませぬよ」
という養父母の言葉を胸に、
千代は有り難くいただくことにします。
永禄10(1567)年9月、美濃入りした信長に従って
50石取りになった一豊も尾張から移り住むことになりました。
そしていよいよ婚礼の日──。
そわそわして落ち着かない一豊に対し、
千代はいかにも堂々としていました。
そんな二人を見守り、祝う面々。
幸せそうな千代の姿です。
──────────
永禄10(1567)年9月、
織田信長が稲葉山城を落とし、岐阜城と改める。
稲葉山城下で祝言を挙げた千代と山内一豊は
母・法秀尼らに歓迎されて夫婦になりました。
千代と一豊が出会って7年余、
千代は一豊に大きなわらじを履かせてもらったことも
傷の手当をしてくれたことも昨日のことのように思い出され、
夫婦になれた幸せでいっぱいでありますが、
そんな千代でも、一つだけ知りたいと思うことがあります。
「だんな様が、いつから千代を──愛おしいと?」
一豊の夢は「一国一城の主」ですが、
千代は「だんな様と二人で長生きすること」が夢です。
しかし一豊は武士ですので、死ぬこともある と言います。
現代とは違い、戦国の乱世にあって
命の生死の間をかいくぐって生きてきたことを考えると
恐らくはルンルン♪な結婚初夜であっても
伝えておかなければならないことなのかもしれません。
「名を残すような死に方をしようぞ」という一豊を
叩き起こす千代ですが……ダイジョウブです。
二人とも立派に名前を残しましたよ、いろんな意味で。
先に起きて野菜を洗っている一豊の弟・康豊と法秀、
そこへ吉兵衛と新右衛門、一豊が起きてきますが、
千代の朝が遅すぎる、と康豊や吉兵衛は少しオカンムリです。
スヤスヤと眠っていた千代が目を覚まし、
隣に一豊の姿がないのを見て
慌てて着替え、表へ飛び出します。
ちなみに千代は、少し変わった小袖を着ています。
おおよそ、上から下まで同じような柄が一般的な小袖にあって
千代の着ける小袖は、ちと斬新なデザインです。
不破の家が焼けた時、焼けずに済んだ部分を縫い合わせたもので、
今で言うところのパッチワークでしょうか。
法秀は何度も頷き「おおらかでよい」などと
かなりのポジティプ発言が飛び出しますが、
細かい部分を気にしないのか、
自分を納得させようとしているのかは分かりません。
食事時、一豊は新右衛門に妻子を呼び寄せるように言います。
それには法秀や千代も賛同するのですが、
「お家はまだまだ50石にて」と新右衛門は固辞します。
堀尾茂助の妻・いとと 中村一氏の妻・としがやってきます。
いともとしも、千代のことが気になる様子です。
「燃え上がる稲葉山城の中で結ばれた二人ゆえ──」と
寧々は見事なまでのガールズトークで話を彩りますが、
朝餉の支度もせず、誰よりも遅くまでおおいびき。
朝寝坊する嫁はどんな嫁かと、すでに城下のウワサに。
いとやとしが現代に生きていたら、
まちがいなく芸能リポーターやってそうです。
……実に平和な戦国時代。
一豊を送り出した千代は
吉兵衛と新右衛門と田畑を耕していますが、
新右衛門の家族を呼び寄せる一件について
吉兵衛から大反対を食らいます。
50石では、一豊と千代と吉兵衛と新右衛門が
やっと食べていけるだけの量でしかありません。
そんな中、新右衛門の家族をどう養っていくのか?
貧乏だからこそ、一家力を合わせて頑張らねば!
3人より4人5人の方が楽しいし……と千代は力説。
しかしその実態は、妻が1人、子が7人──。
茂助や一氏らと相撲を取って汗を流しています。
一氏はなかなかのお調子者らしく、
大恋愛の末に夫婦となった一豊をからかいますが、
そんな棘ある一言に苛立ちを覚えた一豊との間を
「まぁまぁまぁ」と抑えるのが茂助の役回りです。
そうそう、茂助は
竹中半兵衛の命で稲葉山城の裏道を先導した男であり、
彼がいなければ一豊・千代夫婦はなかったかもしれません。
稲葉山城を岐阜城と改名した信長は
「天下布武」の名の下、まずは近江を攻めるつもりです。
近江攻めの危険性について
藤吉郎は半兵衛に愚痴を言いますが、
それには半兵衛も同調します。
仮に浅井を攻めれば、
越前の朝倉が浅井に味方して攻めかかってくるでしょう。
その間、岐阜を留守にしていれば、
このチャンスに武田が攻め込んでくるのは当然。
北近江の浅井氏と南近江の六角氏は犬猿の仲で、
どちらも織田と手を組みたいと考えているはずです。
秀吉は、浅井の内情を一豊に調査させます。
近江の知り合いがいるということを聞いて、
とりあえず市之丞に会いに行くことにします。
近江出身の千代は、一豊に鮒寿司をオススメします。
作り方から味まで鮒寿司情報をインプットしようとしますが、
「遊びに行くのではない!」と一蹴されます。
市之丞に簡単な近江情報を授けてもらい
そのつてを使って近江に入ろうとする一豊ですが、
一豊の、いかにも武士らしい格好を見て
「薬売りか何かの格好をなさってはどうかな?」
結局、薬売りの格好をすることになりました。
夫の不在の間、千代は吉兵衛に
山内家の旗印についての講義を受けています。
一豊の亡き父・盛豊が 最後の合戦で掲げていた旗印、
『丸三葉柏紋(まるにみつばがしわもん)』。
丹波での戦いの折、差物に柏の木の枝を使った盛豊は
味方が大勝利を収めて枝を見たところ柏の葉が三枚残っており、
「これは縁起よし」と『丸三葉柏紋』が定まったわけです。
そんな講義の最中にここへやってきたのは寧々であります。
千代の着る小袖の評判を聞きつけ、1着ねだったわけです。
足利将軍家に忠勤励む六角に対し、
朝倉との結びつきが固いのは先代の浅井久政であって
当代の浅井長政はそんな父・久政と対立している分
浅井の方が与し易いわけです。
浅井と手を組めば朝倉の脅威は当分消えるでしょうし、
それに乗じて六角を倒せば京への道も開かれる。
おまけに長政は、六角の家来の娘と離縁しています。
信長は市を浅井へ嫁がせることにします。
市は無鉄砲に千代を訪れ、近江の話をせがみます。
近江は子供のころにしかいなかった土地ではありますが、
千代は市にわかりやすく、近江の魅力を伝えます。
近江の魅力もさることながら 千代の小袖にも着目した市は
寧々に作ってあげていたパッチワークを
「もらっていこう」と取り上げ、城に帰ってしまいます。
翌日、再びやって来た市は千代を誘って馬で遠乗りします。
広い草原で市が語ったのは、浅井へ嫁ぐことへの重圧、不安。
顔も見たことのない、性格も何も知らない男へ嫁ぐ
女の気持ちというのはどれほどのものか、計り知れません。
栄える城下町へ市を案内して曲芸士や猿回しで楽しませ、
自邸に戻ってささやかながら料理の手ほどきもします。
山内家では貧乏な暮らしゆえ
2つの枡をひっくり返してまな板代わりに使っているのですが、
「貧乏な暮らしはお屋形さまのせいではありません」という
フォローだけは忘れません。
お礼の意味合いがあったのか、
「城に戻ったら届けさせる。“なまいた”であったな」と
心遣いをいただくわけですが、
残念ながら間違った情報を持ち帰ります。
永遠に届かなそうな気配が(^ ^;;)
ともかく、市は行列を従えて近江へ向かいます。
浅井長政の元へ輿入れした市を
父・浅井久政はじめ家臣たちは冷ややかに迎え入れます。
千代は、そんな市の身を案じつつも
近江調査から戻った山内一豊には
世の中の動きを見極めよとしゃもじ片手に力説します。
そこへ祖父江新右衛門が妻子を連れて戻ってきました。
目を離したスキに、あちこちで好き勝手に動き回る
落ち着きない子どもたちですが、
それでもこの親あってこの子ありという感じがします(^ ^)
妻・ふね、嫡男・新一郎と、
徳次郎、つる、うめ、かね、とみ、小三郎の1妻7子。
それに8番目がふねのお腹に、と聞くと
千代と一豊は「えっ!?」と目を大きく見開きます。
小三郎役のささの貴斗くんはプライベートでも実の兄弟で、
パパさんはあのワンシーン役者・笹野高史さんであります。
新右衛門一家を呼び寄せてからというもの、
山内家の生活は劇的に変わりました。
夜はあちこちでいびきが響き渡り、
子どもたちはゴロゴロと転がっていく有様。
「さぁさ、ご飯じゃぞ!」とお声がかかれば
あちこちから一目散に駆けてきて、お腹いっぱいに詰め込み放題。
アッという間にお米が尽きてしまいます。
越前国一乗谷・足利義昭御所──。
岐阜出立に先立ち、明智光秀が義昭に手をついて挨拶します。
上洛するのに織田信長を伴ったとあれば、
信長は狂喜するに違いありません。
光秀には、幕臣として無様なことがないように命じます。
そんな光秀を迎える側の織田家では、
信長が濃姫に「お主の従兄妹であったの」と言いますが、
濃姫は光秀が信長と合わないのでは? という危惧を持ちつつも、
従兄妹以上の“何か”を感じて複雑な表情を浮かべています。
信長は光秀に、美濃安八郡5000石を与えます。
さらに濃姫と庭で会わせてくれるという信長の計らいに甘え、
満開の桜の木のある庭へ出向きます。
濃姫の胸に去来するのは、織田に嫁ぐ直前の日のこと。
この時も同じような桜の木の前で、
光秀への思いを告白したことがあったわけです。
濃姫はあの日以来、笛を止めてしまったそうですが、
光秀との再会を祝い、久々に光秀と笛を共奏します。
吉兵衛のお代わり分の飯を見て、ゴクリと生唾を飲む千代です。
新右衛門一家を呼び寄せたきっかけは自分にあるからか
「胸が重いので」と自分の食事を浮かせて危機を凌いでいますが、
おかげで吉兵衛に懐妊を間違われてしまいます。
空腹でよろめく千代は水を飲んで腹を満たし……。
嫁入り時に養父母に持たされた10両を見つめます。
「貧しくとも、暮らし向きのことに使ってはなりませぬよ」
という養母の言葉が頭を離れず、目をつぶって箱を直します。
呉服屋に入り、近江ものの絹の白小袖を手放して金に替えます。
さらに、手作りの小袋や針山を市場に並べますが
さほどの金にはならず、何の足しにもなりません。
帰宅した一豊は、ぐったりした千代を発見しますが、
粥を作ってやろうにも、米や雑穀などが一切ありません。
そこで初めて、新右衛門一家を呼び寄せたことを後悔する一豊です。
一豊は山に分け入って猪を仕留め、鍋にしてみんなで食べます。
5000石をポンと与えたことで、信長による光秀の高評判は
織田家中でも相当なウワサになっています。
これからは信長のお気に入りとして光秀が筆頭になると見越して
「明智様の元で働きたいのう!」とだれ彼と言っていますが、
一豊は秀吉の元から離れるつもりはありません。
永禄11(1568)年7月25日、ついに義昭が岐阜入りします。
義昭を出迎えるにあたり、信長は光秀に礼法の指南を受けます。
そのイチイチに目くじらを立てますが、本番ではその通りに実践。
この2ヶ月のうちに上洛を果たし、征夷大将軍の座に との言葉に
さすがの義昭も慌てふためきます。
そんな名誉な仕事をする夫のために、
千代は『丸三葉柏紋』の旗指物をパッチワークで手作りします。
お家再興の御旗──。
一豊と吉兵衛、新右衛門、それに初陣の新一郎は
大家族が見守る中、出発していきます。
──────────
永禄11(1568)年8月5日、
織田信長が足利義昭を奉じて岐阜城を出発。
(途中で市に持って行かれるというハプニングはありましたが)
何とか出来上がりました。
いと、としにもお披露目です。
ちょうどそのころ、
祖父江新右衛門の子・徳次郎と小三郎が
一人の女の子をイジメていたのですが、
寧々のところから帰ってきた千代が偶然見とがめます。
たま、と名乗るその女の子こそ、後の細川ガラシャ。
千代は引っ越しでバタバタしている明智家へ赴き
たまを無事に帰します。
六角攻めの最中の木下藤吉郎は信長のお供で小谷城へ。
そこで浅井長政は義兄にあたる信長に頭を下げ、
気を良くした信長は「共に天下を」と声をかけています。
同じく手をついている市の頭には、別のことがありました。
対面を終えた市は、藤吉郎経由で参上した山内一豊に
千代に打ち掛けを作るように命じます。
そんな姿を、六平太が庭の影から見ていました。
「抜け道がある。万が一の時は信長を逃がせ」と
後に一豊と接触した六平太は忠告します。
藤吉郎はそれとなく「そろそろ……」と知らせますが、
信長としては今夜は小谷城に泊まるつもりのようです。
このチャンスを見計らって浅井久政らは信長を滅ぼす計画ですが、
それを長政は必死で食い止めます。
なすびを収穫している千代と新右衛門の娘らですが、
そこへ徳次郎が「母上が!」と駆け込んできます。
川で洗濯中に流産し、大量出血して倒れてしまったのです。
薬師も、もやは手の施しようがありません。
死期を悟ったふねは、子どもたちに遺言を残していきます。
しかし徳次郎に語りかける部分で、ついに力尽きます。
徳次郎は、母の死が引き金で荒くれます。
そんなことはつゆ知らず、新右衛門はふねのために
匂い袋か草履かと土産物を選んでいますが──。
上洛を果たしてくれた信長に
やれ副将軍だ、やれ管領だと褒美を与えようとしますが、
信長はそのいずれも拒否。
断り続けるのもアレなので、
堺・大津に代官を置くことの許しだけを得ます。
岐阜の山内家に無事に戻ってきた一豊らですが、
千代の出迎えがありません。
他所の畑から作物を盗んでは
「母上を返せ!」とわめき散らす徳次郎に、
千代は出迎えどころではないわけです。
今まで家族を顧みなかった
(というよりお家再興のために顧みれなかった)父が
今更ながら父親顔をしていることに徳次郎は納得がいかず、
世の中のすべてのことに不満を抱いています。
徳次郎のとげとげしいセリフにも驚愕する新右衛門は、
「お方さまに何と言う口の聞き方!」と
徳次郎を庭先に投げ出して刀を振り上げますが、
姉たちは徳次郎を庇って代わりに許しを請います。
千代も、新右衛門から徳次郎を逃がすのがやっとです。
──土砂降りの中、徳次郎が帰ってきません。
一豊と千代、吉兵衛、新一郎で
手分けして徳次郎を探しにいくことにしますが、
山の奥深くの洞穴で、千代が徳次郎を見つけます。
千代や一豊、それに家族みんなの介抱で徳次郎の看病をし
その甲斐あって、
熱にうなされていた徳次郎の意識がようやく戻ります。
永禄12(1569)年正月。
粉雪が舞い散る中、再び出兵していく父に
「ご武運を」と声をかける徳次郎の姿がありました。
──────────
永禄11(1568)年10月18日、
朝廷から将軍宣下を受けて足利義昭が第15代将軍に就任。
京を揺るがす事件が起こります。
将軍・足利義昭に不穏な動きありという情報が
木下藤吉郎の元に飛び込むわけです。
そのことを聞いた明智光秀は
「信長を見くびってはなりませぬ」と義昭に忠告しますが、
義昭は全然聞いていません。
報告を受けた岐阜城の信長は、
茶会を開かせ全国の諸大名を呼び寄せることにしますが、
三河の徳川家康には別の書状を送り、
越前の朝倉義景を討つ準備に入ります。
山内一豊は、岐阜に戻ったついでに家に戻り
また即座に信長から家康に当てた文を持って
三河へ発たねばなりません。
千代は、一豊の右手首にお守り代わりの布を巻き付けます。
千代も一豊のように右手首に布を巻き付けて家事に勤しみますが、
徳次郎がそれを見て不思議に思っているようです。
織田の使者として徳川家康と対面します。
文を受け取った家康は、それとなく信長の真意を探ろうと
一豊にあれこれ探りを入れますが、
一豊は知らぬ存ぜぬを通します。
4月、京を発った信長軍は越前朝倉攻めを開始します。
近江高島の信長本陣において、家康軍5,000が合流。
浅井長政は越前への援軍を送らないことにします。
これには浅井久政のみならず、家臣団も猛反発。
とはいえ、電光石火の織田軍はまたたく間に越前へ攻め入り、
越前側も織田軍に恐れをなしたか、
戦をしないまま開城降伏となりました。
とはいえ、城の明け渡しは古来からスムーズにはいかないもの。
それとなく竹中半兵衛は心配しております。
鉄砲隊は火縄に火をつけて それを絶やさぬようにしていまして、
それはそれでちと不穏な動きにも見えるわけですが、
どこからか聞こえた大砲らしき音に越前兵は腰砕け。
それを祖父江新一郎があざ笑い、越前兵との戦に持ち込みます。
弓の名手・三段崎勘右衛門に槍で応戦した一豊は、
至近距離から弓矢で射られ──。
一豊の元に駆けつけた新一郎は、その顔に腰を抜かします。
フガフガ……と一豊は吉兵衛に必死に訴えていますが、
顔を踏んで射られた矢を抜けと言いたいようです。
小谷城では、長政が信長に対して挙兵することにします。
長政から信長の元へ陣中見舞いが届けられますが、
これは無論、裏切りへの時間稼ぎ、見せかけであります。
六平太によって届けられます。
両方をしっかりと結ばれた袋の中には、無数の小豆。
小豆……小豆坂……。
信長は、最初こそ笑顔が絶えませんでしたが、
市の真意が伝わって、徐々に般若のような顔に変貌します。
「退き陣じゃあ!」
秀吉軍が殿(しんがり)と聞いて、
一豊は傷の手当中にも関わらず槍を持って戦に出ようとします。
吉兵衛も新右衛門も「そのお身体で」と止めますが、
ここで命が尽きるならそれまでであります。
包丁で指を軽く切ってしまった千代は不吉な気がして、
お百度参りで一豊の無事を祈願しています。
ただひたすらに、祈るばかりであります。
──────────
元亀元(1570)年4月26日、
越前の朝倉義景を攻撃し、金ヶ崎城の朝倉景恒を下す。
その裏切りを知った信長は、激怒しながらもひとまず撤退。
羽柴秀吉軍は殿(しんがり)として
撤収軍の最後に逃げることにします。
三段崎勘右衛門に受けた矢傷で
山内一豊は顔を包帯でぐるぐる巻きにされております。
竹中半兵衛は、痛み止めと熱冷ましの薬を一豊に飲ませます。
とはいえ、そんな悠長なことはしていられません。
今にも浅井軍が迫ってくる今、どうやって敵を食い止めるか。
足元おぼつかない一豊は、戸板に乗せられて陣を後にしますが
単独で走って逃げる足よりもおのずと遅くなり
敵兵に狙われやすくなります。
それを、五藤吉兵衛、祖父江新右衛門や
堀尾茂助、中村一氏らが果敢に守り、防いでいきます。
一豊は足手まといになっている責任を感じて
腹を斬って皆を逃がそうとしますが、
あれだけ自分のことしか考えていなかった一氏が
率先して一豊を担いで逃げます。
山内家に六平太が飛び込んできました。
浅井裏切り、信長敗走、秀吉軍は行方知れずと
ポイントだけをかいつまんで千代に伝えますが、
顔を射抜かれた一豊は生きて帰れないかもしれないと
覚悟をしておくように言います。
千代は半ば錯乱状態で、戦場に連れて行けとわめきます。
六平太は冷静に、しかし言葉を強めて祈れと説得します。
「お前の亭主に首を取られた者の家族も、祈ってるんだ」
千代は冷水を浴び続け、お百度参りも一心に行います。
ついに、一豊らが敵兵に囲まれてしまいました。
「ここがわしの死に場所じゃ」と
一豊は覚悟し、脇差しを首に当てますが、
その瞬間、発砲音が響き渡り
囲んでいた敵兵が次々に倒されていきます。
秀吉はもう少し前に進んだ林に身を潜めているらしく
家康は一豊を守るように自軍に下知をします。
家康軍に守られて、秀吉軍は無事に京へたどり着けました。
余談ながら、プライベートでもとてもとても仲のいい
武田鉄矢さんと西田敏行さんの大河ドラマでの共演は
意外ながらこのシーンが初めてであります。
収録前後のおふたりの雑談を聞きたかったなぁ(^ ^)
脱線、失礼──。
小谷城へ戻った長政は、市の出迎えを受けます。
父・浅井久政は、長政の出陣が遅れたことで
信長を討つチャンスをみすみす逃してしまったと猛烈に批判、
「磔にしてやりたいぐらいじゃ」と市にも捨て台詞を吐きます。
久政は影で、忍びに「信長を討て」と命じています。
命じられたのは──六平太です。
後から追いかけてきた秀吉と家康をねぎらいます。
庭で片膝ついている一豊にも声をかけますが、
三段崎を討ち取った大手柄を認め、知行200石に加増です。
それを一刻も早く千代に知らせたいと
祖父江新一郎が戻ることになります。
しかし、一氏は一豊の加増に不満タラタラです。
彼らが必死で守り抜いたおかげで一豊は無事に京へ戻り、
加増が叶ったわけです。
一氏としては、腑に落ちないところはあるでしょう。
お百度を踏み続けている千代のところに、
新一郎が戻ってきました。
新一郎の最初の言葉に生唾を飲んで覚悟する千代ですが、
思いもよらぬ言葉を聞かされます。
「戦場でのお働きにより、200石にご加増!」
生きているのね! と感激したのも束の間、
お百度の途中で口をきいてしまった、と(^ ^;;)
長雨の夕方、そこへ旅の途中の小娘がやってきました。
名は小りん。
聞けば、伯父を捜しているとのこと。
伯父がこの空也堂にいると聞いて雨の中やって来たそうですが、
残念ながら空也堂は別に移設しております。
この雨の中を無下に追い返すわけにもいかず、
ひとまずは堂の中に招き入れます。
男ばかりの環境であるため、一豊は
落ち着いたら早く出た方がいいと小りんに言いますが、
斬り傷によく聞く薬を置いていく代わりに、
私を一晩泊めてほしいと願い出ます。
一豊は断るつもりでおりましたが、
そこへ戻ってきた吉兵衛や新右衛門は
「殿さえよければのう」と満面の笑み。
結局は泊めることに。
新右衛門はイビキのマネをしつつ様子を窺っていますが、
吉兵衛は今夜は完全に寝入っております。
突然ホラ貝が吹かれ、陣ぶれが出されると
吉兵衛と新右衛門は外に駆け出していきますが、
「戦になったらもう会えない!」と
小りんは一豊に抱きつきます。
浅井との戦に行くわけではないこと、
岐阜へ千草峠越えして戻るであろうこと、
小りんに心配かけまいと、ペラペラと喋ってしまいます。
急いで陣中に向かう一豊ですが、
浅井の間者がうろついているから注意せよ とのお達しに
もしやと思って空也堂に戻ってみますが、
もう、小りんはおりませんでした。
他言はならぬ! と吉兵衛と新右衛門に厳命しますが、
「分かっておりまする、お方さまには──」と勘違い。
他言無用とは、間者に情報を漏らしてしまったことであります。
六平太に握り飯を分けてもらってガツガツと食べます。
そのかぶりつく様はやはり伊賀者っぽいです。
早速、織田軍が千草越えして岐阜へ戻るという情報を報告。
山内一豊が情報主だと知ると、千代のだんなということで
六平太としてはちと興味があります。
人柄のいい男、でも床上手じゃなかった という報告には、
さすがの六平太も「比べるな」とツッコミます(^ ^;;)
小りんは引き続き織田方に探りを入れ、
六平太は千草峠へ向かうことにします。
忍びに休む暇はありません。
千草峠を岐阜に向かう織田軍の一豊は
林の中に小りんの姿を認めます。
小りんは一豊にウィンクをして一豊を慌てさせます。
別の場所では、杉谷善住坊を雇った六平太が
信長を銃撃しようと狙っています。
でも一発で仕留めるのではなく、脅す程度です。
千代は、三段崎に受けた矢傷を開運の傷と言い
男前が上がられましたね、と一豊をねぎらいます。
その夜、夫婦の営みに励むふたりですが、
いつもの様子と違う一豊に、千代は気づきます。
そこで不憫に思ったか、黙っていられない一豊は
「京で……女子を抱いた」と千代に手をつきます。
千代は、一豊を見つめたまま微動だにしません。
──────────
元亀元(1570)年4月30日、
金ヶ崎の退き口で、織田信長が京へ逃げ延びる。
あまりのショックに、千代は一豊を質問攻めにしますが
それに一豊が一つ一つ誠実に答えれば答えるほど
事情を細かく話せば話すほど、話が明後日の方角へ。
「わしは好色漢じゃ!(-_-;)」
「いやでござります好色漢なんて!(T^T)」
「許せッ m(_ _)m」
「小りんなんて……おかしな名前ェ!(T△T)」
小りんとのことを千代に話してしまった一豊を
五藤吉兵衛と祖父江新右衛門はあきれ果て、
さんざんに責め立てます。
一方、千代はこういう時はどうすればいいかを寧々に相談します。
寧々は夫の浮気を「捨ておきなされ」と言います。
殿(しんがり)として命からがら逃げ帰った重責から解き放たれれば
男としては羽目を外したくなるもので、
夫の命があっただけでも良いと思わなければバチが当たると。
それでも分からない千代を、寧々は突き放します。
「では、お里の不破家へお帰りなされ」
千代は素っ気ない態度で接します。
吉兵衛はかなり気を使って
一豊の評判話で千代を喜ばせようとしますが
全くと言っていいほど反応しません。
千代の料理の腕を褒めますが、それもダメです。
翌朝、膨れっ面の千代は不破へ戻ります。
一豊の元には、一通の文が残されていました。
──御いとまたまはりたく候 千代
「そのようなささいなことで、戻ってくるではない!」
養父・不破市之丞は、千代を叱ります。
夫の浮気は一大事ですのに と千代は言いますが、
市之丞の言う一大事とは、浮気ごとにいちいち妻が実家に帰り
それによって心を乱された夫が戦場で命を失うことにあります。
それよりも、加増されたことで家臣を増やす必要がありますが
そのポイントを千代に教えます。
力の強い者、足の速い者、知恵の回る者、物覚えのよい者、
銭勘定のできる者、正直者などなど取り柄のある者を集める……。
千代はズバリ指摘してはいますが、
恐らくは一豊のことを言っているのでしょう(^ ^;;)
市之丞は千代に、とにかく明日戻れと言い聞かせます。
養母のきぬは、一豊のことが憎いと思うのなら
実家に戻ってきなさいとポンと背中を押してあげます。
千代が不在の間、
新右衛門の娘たちが変わって台所に立ってくれています。
一豊は千代を連れ戻そうと不破家へ向かおうとしますが、
それを新右衛門が留めます。
新右衛門の娘たちも
一豊が浮気したらしいとうすうす気づいているようで、
千代だ、小りんだ、間者だとクヨクヨする一豊を見ては
クスクスと笑っています。
千代は不破家から馬で急いで戻ってきますが、
すでに戦に行ったあとでした。
元亀元(1570)年6月27日。
浅井長政は小谷城を出発、姉川へ打って出ます。
河を挟んで北側の浅井・朝倉軍と南側の織田・徳川軍。
地形的には浅井・朝倉軍が有利ではあります。
三河からはるばる救援に来た徳川家康は
織田信長に後詰め(予備軍)を命じられますが、
それでは不服と朝倉軍への受け持ちに配置換えになります。
それを見た羽柴秀吉は悔しがります。
「お屋形様は最初から徳川殿を朝倉に当てるつもりじゃったな」
秀吉軍は3番隊、功名からはちと遠い軍隊です。
一豊は千代への申し訳なさを吹っ切るように
姉川へ飛び込んでいきますが、
銃声に驚いた馬が川の途中で急に立ち止まり、
騎乗の一豊がバランスを崩して川の中へ転落──。
水の中に落ちれば沈むだけです。
浅井軍は予想以上に強く、織田の2番隊3番隊にまで迫り
本陣へ攻めかかる勢いです。
それを逆転させたのは、浅井軍の脇腹を突いた家康でした。
無数の屍が浮かぶ川で、
吉兵衛と新右衛門は一豊を探します。
しかしそれらしい姿は見つからず。
岐阜へ戻った織田軍を迎えに出る千代ですが、
一豊の姿がありません。
戦の状況を茂助と一氏に詳しく聞く最中、
吉兵衛らも山内家へ戻ってきますが、
ふたりのお守りの布切れを見つけただけでした。
「それだけでは……まだ分かりませぬぞ!」
吉兵衛は千代を懸命に励まします。
いつもならこのお守りを一豊の手首に結ぶのに
今回は結んであげることができませんでした。
「バチが当たる」という寧々の言葉、
「そのようなささいなこと」という市之丞の言葉、
その意味が分かった気がしますが、時は既に遅かったわけです。
数日後。
秀吉の提案で、一豊の弔いをすることにしました。
そのあっけない判断に、吉兵衛や新右衛門
そして茂助までが反発しますが、
千代は、ただ黙ってそれを受け入れます。
千代は自分を責め続け、
法秀を前にして、髪を下ろすと言い出します。
今回の過ちを一豊に詫びながら、生きていこうというのです。
もし憎むとしたら、それは戦の世。
一豊の命を奪った戦を、乱世を憎む……。
法秀は、ただただ黙って千代を抱きしめます。
山内家に戻った千代は、力なく座っています。
吉兵衛と新右衛門、
ふたりの胸に去来するものは何だったのか。
まだ信長に仕える前、
仕官先を求めて諸国を放浪している3人が
不遇にもめげず、明日を目指していました。
新右衛門は脇差しを手に、吉兵衛は丸三葉柏紋を手にして
そんなことを振り返っています。
千代、わしは決して死なぬ。
千代、千代──。
そんな一豊の言葉が千代の胸を貫きます。
その言葉に呼び寄せられるように、
雨の中を駆け出していく千代。
幻聴?
いえ。
吉兵衛にも、新右衛門にも、
その声は確かに届いていました。
皆が夢中になって、
雨の中を声のする方へ駆けていきます。
「命、拾うたぞ……」
──────────
元亀元(1570)年6月27日、
姉川の戦いで、織田徳川軍と浅井朝倉軍が激突する。
小りんに助けられたことを告白します。
しかし今回は動揺することなく、
それはそれとして受け入れる千代は
この2ヶ月弱で大きく成長したのかもしれません。
「妾(そばめ)にしたい女子がおりましたら、お連れくださりませ」
そう言う千代に慌てる一豊ですが、
床に置いた布切れに足を滑らせます。
足を滑らせて、あんなにまでぶっ飛んだ人物は
(演技としても)初めて見ました(^ ^;;)
一豊が普段通りに出仕すると、
「このワシだけは、生きて帰ると信じておった!」と
秀吉は大手を広げて泣いて喜びます。
堀尾茂助も中村一氏も、どこかしらけムードですが。
浅井軍の動きを封じる役目として
秀吉軍は近江・小谷城近くの横山城に詰めています。
一豊は一気に攻めてはどうかと竹中半兵衛に持ちかけますが、
「功名を焦りなさるな」と逆になだめられます。
将軍・足利義昭の呼びかけに応じて三好軍が出兵し、
さらに浅井・朝倉・武田・毛利・本願寺・比叡山などが手を結んで
織田信長の包囲網を作り上げようとしている今、
横山城へ兵を割ける状態ではありません。
ある日、千代は寧々に頼み事があると呼び出されます。
秀吉の姉の子である治兵衛の教育係として
読み書きを教えてやってほしいというのです。
治兵衛はとても幼い男の子ですが、
やはり百姓の息子ということもあって
話し言葉は尾張のなまりが混じり、
あか抜けない感じがあります。
千代は読み書きを、
そして秀吉の提案で一豊は槍を教えることになります。
坂本へ向かい、比叡山延暦寺に立てこもり。
織田軍とにらみ合いが続きます。
雪が降り始めた頃、
明智光秀は京の二条御所に入って将軍義昭と対面します。
この雪では、兵粮が延暦寺に届きません。
ゆえに雪解けまでに軍は壊滅状態になる可能性もあります。
それを逆手に取って、光秀は
浅井と織田の和睦を仲介することを義昭に提案します。
浅井・朝倉に恩を売ることができ、
将軍としての威光を示すこともできます。
この和睦で、織田軍は久々に岐阜に戻ることができました。
元亀2(1571)年、再び近江へ侵攻した信長は
ついに比叡山攻めを決意。
しかし光秀がその下知に噛みつきます。
その様子を見て、他の武将の口はつぐんでしまいます。
9月12日、3万の軍勢を率いて比叡山に攻め入り
伽藍をことごとく焼き払います。
逃げ惑う僧たちに、光秀は一寸の情けもかけず
無残にも斬り殺されていきます。
堂に火をかけ、逃げてきた女・子どもたちにも
茂助や一氏、そして一豊も刀を振り上げますが
なかなか下ろすことはできません。
秀吉は「味方がやられておる!」と皆を移動させ、
そのスキに女・子どもたちを逃がしてやります。
この働きによって
光秀には滋賀5万石へ加増となりましたが
秀吉には何の加増もありませんでした。
戦いが終わり、一豊は千代の元に戻りますが
今回ほど後味の悪い戦いはありません。
濃姫も、そして一豊も
信長の本意が分からなくなっています。
──────────
元亀2(1571)年9月12日、
織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちする。
挨拶から習字、学問に至るまで一心に教え込みます。
治兵衛は将来的に人質として使われるそうで
本人はその意味すら分からずに
「人質! 人質!」と楽しそうに言っていますが、
そんな幼子を見て、千代は不憫でなりません。
ただ、習字も学問もどんどん吸収していきます。
横山城に入った羽柴秀吉は、浅井長政を攻めるべく
周辺の豪族の切り崩し工作に入っていますが、
宮部善祥坊の調略がうまく進んでいません。
秀吉は、竹中半兵衛が止めるのも聞かず
かつて半兵衛を調略したときのように
一人で調略に出かけていってしまいます。
秀吉を待つ間、山内一豊は半兵衛に
信長についてどう思うか思い切って尋ねます。
古いしきたりと戦っておられるのでしょう、と答える一方で
かつてない危機ゆえに畏れておられる、とも言います。
甲斐の武田信玄のことです。
半兵衛に言わせれば、そんな簡単な相手ではないそうです。
もし武田が上洛の兵を上げれば、信長はたちまち四面楚歌です。
秀吉が戻りました。
秀吉が人質として治兵衛を出すことを伝えれば、
宮部は逆に、自分の妹を人質に出して寝返りを約束します。
治兵衛は、人質として宮部の元へ送られることになりました。
千代はしっかり抱きしめ、治兵衛を送り出します。
元亀3(1572)年7月、信長は
浅井への備えとして虎御前山に砦を築きます。
そして10月、ついに信玄動く……。
陣中を探る怪しい女を見かけ、浅井側の間者ではないかと
祖父江新一郎が一豊の前に連れてきました。
小りんです。
どういうことかと問いつめます。
場合によっては斬らねばならないと脅しますが、
小りんは高らかに言って退けます。
「あんたに命の恩人は斬れないね」
10月22日の三方ヶ原の戦いで徳川家康は武田軍に大敗し
信玄の影がいよいよ信長の背後に迫っています。
明智光秀は、将軍足利義昭に
急いで京へ上るよう催促を受けます。
上洛した光秀は、細川藤孝に出家の決意を打ち明けられます。
名を細川幽斎とし、将軍の元から隠居するつもりのようです。
それも義昭の密事を知ってしまったからに他なりません。
密事……織田信長討伐であります。
義昭は信玄の出陣を心から喜び、
それに乗じて兵を上げるつもりのようです。
光秀は義昭をなだめようとしますが、
今更ながら遅すぎたようです。
そんな義昭を信長は鼻で笑いますが、
そこへ慌てて秀吉が駆け込んできます。
信玄が死の病で床についているとの情報です。
信長は、将軍義昭を討つのは今だと感じますが
そのまま討ち滅ぼせば信長の世間体に傷がつきます。
まずは弾劾状を送付して義昭が悪将軍であると世間に知らしめ
挙兵したところを討つ、という筋書きを描きます。
元亀4(1573)年4月、
挙兵した義昭は槙島城で信玄の上洛を待ちますが、
信玄死去の知らせをそこで受けます。
信長が将軍討伐の軍を差し向けたとの知らせを受け、
しかもその総大将が光秀と知って、目を回して卒倒。
織田軍は破竹の勢いでその日のうちに槙島城を落とし、
将軍義昭を京から追放してしまいます。
ここに、室町幕府は滅亡しました。
──────────
元亀4(1573)年7月18日、
将軍足利義昭が織田信長に降伏する。
一豊の出番がなかった
越前朝倉家も滅びると、小谷城の浅井長政は完全に孤立。
浅井家臣団も調略によって次々と織田方に寝返られていて
小谷城に残るはほんの少数であります。
小谷城を取り囲む織田軍。
その中に陣取る山内一豊の陣からは
降伏を勧める矢文が大量に射られ、
メガホンのようなものでも降伏を勧めます。
「こんなことをするより、一気に攻めた方が」と
祖父江新一郎は、その大きなメガホンを
よっこらしょと抱えながら言っていますが、
小谷城には織田信長の妹・お市の方がいるので
攻撃の判断を迷っているのかもしれません。
対する小谷城では、
届いた矢文で動揺を隠せなくなった兵士たち500ほどが
織田方へ駆け込んでいき、長政には諦めの表情が出ています。
父・浅井久政のつながりを遮断し
長政はますます孤立してしまいます。
羽柴秀吉は、市を助けたい一心で
『もし長政が速やかに城を明け渡せば、今回のことは不問に付し
織田の家臣として望む地に所領を与える』
という条件を信長に呑ませ、小谷へ向かいます。
しかしこの条件を、長政が承諾しません。
市と娘たちは道連れにしたくはありませんが、
嫡男・万福丸とともに自らは自刃して果てるつもりです。
長政からの依頼を受けて、秀吉は市を説得にかかります。
市も小谷で果てるつもりですが、
万福丸の命を守れるなら秀吉とともに城を出てもいいと譲歩。
そして夜、月夜の明かりをたよりに
秀吉らが子どもたちをおぶって、市とともに小谷から出ます。
市たちが織田陣中に到着するや否や、
信長は本丸総攻撃を命じます。
そしてすぐに火の手が上がり、
長政は自刃して果てます。
信長の下知に、秀吉は言葉を失いますが、
どこか覚悟ができていた部分もあります。
確かにこの乱世において、敗軍の将の嫡男を生かすことは
セオリーとしてはあり得ません。
平 清盛が源 義朝の子・頼朝を命を助けたばっかりに
後に挙兵され、平家滅亡してしまった話は有名です。
ただ、一豊は納得できません。
一豊自身も岩倉織田家家臣の嫡男でありながら
信長に命を助けられ、今に至ります。
ま、これは敗軍の将の嫡男というのと
敗軍の将の家臣の嫡男というのとで
次元の違う話ではあるのですが(^ ^;;)
それはそれとしても、もしRというのなら
あのまま小谷城に残して長政と運命を共にした方が
もしかしたらよかったのかもしれません。
秀吉は、自分の命令が聞けぬ一豊を
「謀反じゃ! 裏切りじゃ! 逆賊じゃ!」とわめき、
こういう重い任務を一豊に任せてしまいます。
一豊の号令で殺されてしまいます。
岐阜の千代の元に戻った一豊は、
ひとこと「疲れた……」とだけ言います。
市のために縫い上げたパッチワーク打ち掛けを
その直後に信長の命で市に届けた千代は、
そこで万福丸のことについて知るわけですが、
市の元を辞した千代が一豊に尋ねても
「仏門に入られた」と言ったっきり
顔は青ざめ、目も合わせようとしません。
しかし秘密を隠しきれない一豊は
千代にありのまま全てを話します。
いつも功名を挙げたいと
敵兵をさんざんに斬り倒してきた一豊が、
万福丸を殺せないというのはキレイごとだ。
相手が大人の武将なら殺せて、子どもなら不憫なのか。
秀吉に言われた手痛い一言です。
これからの自分の生き方を見失っています。
千代は、万福丸を磔にして殺害したことは何も言わず、
ただそのことを涙ながらに告白したことで
心の痛みを感じる殿様であってよかったと思っています。
今回の小谷攻めの功績で、
秀吉は小谷城と北近江三郡12万石を与えられます。
姓も、丹羽長秀の「羽」と柴田勝家の「柴」から羽柴とし、
羽柴筑前守秀吉と名乗ることになります。
そして一豊も近江唐国400石に所領を与えられます。
しかし、千代と一豊が隠し通すつもりだった
万福丸の死も、直に市に知れてしまいます。
天正2(1573)年正月。
信長は手をパンパンと叩き、杯を持って来させます。
杯にしてはちといびつな形をしていますが、実はそれは、
久政、長政、そして朝倉義景の髑髏(しゃれこうべ/どくろ)です。
驚きの家臣団に、ショックを隠しきれない市と濃姫。
柴田勝家・佐久間信盛の前には浅井長政、
林 通勝・丹羽長秀の前には浅井久政、
そして羽柴秀吉・明智光秀の前には朝倉義景。
狂気の信長を前に、秀吉は
かなり引きつった笑い声を出しつつ義景の杯を傾けます。
勝家らもそれを追って形ばかり笑ってはいますが、
光秀だけは苦々しい表情のまま。
光秀にとって義景は(元)主君でありますので
酒を注がれて、はい左様ですかと呑めるものではありません。
それを見咎めた信長の、光秀への折檻が始まりますが、
市がたまらず信長をたしなめ、
「汚らわしい!」と秀吉に捨て台詞を吐いて出て行きます。
──────────
天正元(1573)年9月1日
浅井長政が小谷城で自刃して果てる。
秀吉は小谷城から今浜に移り、
琵琶湖畔に築城して長浜と名を改めます。
それに伴って、一豊も千代の生まれ故郷の近くに屋敷を賜り
そこでの暮らしを始めます。
女中たちには屋敷内のお仕事があるから、と
千代は率先して風呂掃除。
「殿が笑い者になりまする」と五藤吉兵衛は苦々しい顔ですが、
千代はその手を止めようとしません。
庭では祖父江新右衛門が投げた薪を
息子の新一郎が受け取って薪割りしていますが、
庭に割った薪が転がっていないところを見ると、
まるで吉兵衛が見に来るまでサボっていたかのような印象です。
そこへ、お祝いを届ける堀尾茂助の妻・いとと
中村一氏の妻・としが酒樽を持ってお祝いに駆けつけますが、
茂助も一氏も未だ150石取りの身ゆえ、
どんな反応にも皮肉が垣間見えます。
これ見よがしに豪華な扇子をひらひらとさせるいとは
「金は天下の回りもの」と持論を展開しています。
新たな町作りのための建築現場では、一氏が茂助に
一豊の出世について愚痴を漏らしています。
資材をついつい落としてしまう人足に怒り心頭の一氏ですが、
そんな一氏を抑えて、穏やかに「気をつけろぉ〜」と言う茂助。
“落とさないように”気をつけろ、なのか
“一氏を起こらせないように”気をつけろ、なのか(^ ^;;)
一豊は竹中半兵衛の元を訪れます。
他の武将が各地で戦に明け暮れている現状で、
羽柴隊だけがこうしてのうのうと町作りをしていていいのかと
一豊は少し焦りを見せていますが、半兵衛は
「来たるべき時のためにお屋形様は秀吉様の兵を休ませているのだ」
と冷静に分析します。
来たるべき時……信玄亡き後の甲斐武田攻めです。
半兵衛の推測では、恐らくは毛利攻めは
明智光秀か秀吉のどちらかになるだろう、というわけです。
その後、茂助と一氏は一豊を見かけるわけですが、
一氏は黙って頭を下げ「猪右衛門さま」と皮肉丸出しです。
そんな一氏に、一豊は心の距離を感じずに入られません。
帰宅した一氏は、としが山内家の湯殿を借りたことを
カリカリと怒って奥方を泣かせておりますが、
一方で茂助は、いとが湯殿を借りたことも
「そうかぁ〜」と特段気にするところもありません。
寧々の元を辞した千代は、その帰りに
田に水をやる百姓のおばあさんを見かけ手伝います。
翌朝、そのおばあさんが山内屋敷を訪れ
昨日のお礼に、と野菜を置いていくわけですが、
一豊に千代を絶賛するおばあさんの
「ウチの寧々さだがね、日吉の嫁の」というセリフに
そのおばあさんが秀吉の母御前だと気づくわけです。
羽柴屋敷へ戻ったなかは、寧々さという立派な奥方がおりながら
数多くの女たちに手を出してきた秀吉に痛い平手打ち。
秀吉は寧々を睨みつけますが、寧々自身は何もしておらず困惑気味です。
秀吉は、家族みんなを長浜に呼び寄せますが、
妹の旭だけが尾張中村で百姓を続けています。
秀吉は何としても旭を長浜に連れてきたい考えのようで、
そんな秀吉の命を受け、一豊は説得に中村へ赴きます。
あ、ちなみに千代を伴っているのですが、
吉と出るか凶と出るか──。
旭は中村を出る気は毛頭ありません。
旭の夫・源助は虫一匹すら殺せない男で、
そんな男が武士になれるはずもないと考えていますが、
ただ一方で源助は、百姓という仕事もキライだと考えているようです。
千代は、旭の言い分も尤もだと言い出して
一豊と夫婦喧嘩を始めてしまいますが、
それを止めるように、が言います。
「わしらの者でもお城の仕事はあるんかいな?」
建築の作事仕事であれば得意で、自信があるそうです。
砦を築いたり城壁の修理をしたりできますし、
長浜の町作りをしている今、源助は
もしかしたら一番必要な人材かもしれません。
源助と旭は、ほどなくして長浜へ移ることになりました。
本人が自信を持って言うだけあって、
源助は生き生きと作事をこなしていきます。
しかも段取りがはかどるらしく、
半ば強引に長浜へ連れてきた一豊としても
安堵しているところですが、
一氏の皮肉めいた言葉と表情には、
一豊の心が晴れることがありません。
一豊が屋敷へ戻ると、茂助といとが屋敷を訪問していました。
「千代殿が、いつでも入りに来いと言うておったものでの」と
湯殿を借りに来たようです。
一豊は、そんな茂助の行動があまりに嬉しく
しばらくは言葉をなくしておりますが(^ ^;;)
それでも夫婦水入らずで入浴する茂助といとを
微笑ましく思っているようです。
湯殿のすき間から、茂助の
「極楽ごくらくぅ〜」という呑気な声が響いてきました。
祖父江新右衛門は、息子の新一郎に家督を譲り
自らは隠居して家族とともに暮らしたいと言い出します。
母を亡くした直後は問題行動が目立った徳次郎も
医者を志して京へ勉学に向かうそうです。
千代は、新右衛門は知恵者ゆえに
「わたくしの相談相手になってくだされ」と言って
新右衛門を喜ばせていますが、
ただ一人、五藤吉兵衛だけは不満顔です。
千代はそれとなく吉兵衛を気遣いますが、
吉兵衛には吉兵衛なりの奉公があるのだと思い至ります。
金ヶ崎の戦いの折の、
山内一豊の左ほおに突き刺さった矢じりを手に
「殿! まだまだ隠居はしませぬぞ!」と吠える吉兵衛。
その声は、すぐ隣にある屋敷の縁側で酒を呑む一豊には
しっかりと届いておりますが、
吉兵衛は話が長うていかん、と本音がポロリ。
尾張中村から強引に連れてきた、秀吉の義弟・源助も
本人が得意な作事仕事に携われて満足そうです。
評判もなかなかのもので、源助のおかげで
仕事が予定よりも5日も早く仕上がったのだとか。
秀吉は「でっきゃあ屋敷を与えてやるでよ!」と言いますが
秀吉の妹で源助の妻である旭は
母のなかと田を耕せさえすればいいと、高望みはしません。
一辺約20cmの板を、10mほど離れた場所から
鉄砲でバーンと射抜く男──六平太です。
鉄砲の名人との触れ込みでして
新一郎たちの前でその腕を披露する六平太ですが、
山内家にお召し抱えを、と言う新一郎に
「信用できぬなぁ」と吉兵衛は首を立てに振りません。
そこを通りかかった千代は
六平太の姿を見つけて動揺を隠しきれません。
千代は思い切って一豊に
六平太のことを相談してみることにします。
千代が言いあぐねている間に、夫婦の寝床を六平太が襲撃。
話の成り行きから、六平太は
山内家の食客としてしばらく居候することになります。
堀尾茂助が毎度ながら湯殿を借りに来ました。
どっぷりと風呂に浸かりながら、
茂助はムフフフと思い出し笑いしています。
妻のいともニコニコしておりまして、
話を聞けば、子どもを授かったのだそうです。
しかも中村一氏・とし夫婦のところも
時を同じくしてご懐妊とのことで(^ ^;;)
いとは千代にも何とか励んでもらおうとし、
妊娠しやすい身体になるには
山芋のネバネバが効果的! などと情報を吹き込みますが、
「まぁ……どうしましょ」と照れている千代は
いとが帰るや否や、教えられた通りにすぐ実践。
千代は逆に、いとやとしに一歩リードされています。
ちょっと焦っているのかもしれません。
しょんぼりとする千代を一豊は励まします。
千代の養父・不破市之丞が病の床についているとの報を受け
千代は馬を走らせて見舞いに行きます。
市之丞は、今や400石を抱えるようになった
山内家の跡継ぎのことを心配しています。
千代に子ができないのであれば、
一豊に妾(そばめ)を勧めるよう言います。
後から合流した一豊と一緒に、養母・きぬから話を聞きます。
市之丞・きぬ夫婦にも子がありませんが、
しきりに妾を勧めている市之丞は、
実は自分自身は妾を拒んだのだそうです。
子がない暮らし、妾を持たない暮らしは
市之丞やきぬは充分すぎるほど分かっていることです。
その経験を元に、千代に伝えたいことというのは
あるのかもしれません。
六平太のもとに小りんが参上──。
「お前が来ては話がややこしくなる、失せろ」と
六平太は追い払う手のしぐさをしますが、
愛しい男に会いに来た小りんは、出て行こうとしません。
翌朝、不破屋敷から戻った一豊と千代は
一礼をする六平太の後ろに小りんがいることに気づきます。
表向きは“六平太の妻・さと”ということになっていますが、
まぎれもなく小りんです。
吉兵衛も新右衛門も小りんに会っているので、
小りんとさとが同一人物であることが
千代にバレないように一豊と口裏を合わせます。
しかし、小りんはすぐにシッポを出します。
「わたくしが、殿の子を産みまする」と
子ができないと嘆く千代にそっと耳打ち。
千代は、心では拒絶したい一方で
それはそうかもしれない、と頭で理解しようとします。
それをいいことに、小りんは一豊に近づくわけですが、
小りんから逃げて来た一豊が戻ってくると、
千代は大粒の涙を流しています。
「旦那さまを……小りんには渡しませぬ」
嗚呼、すさまじき女の勘(^ ^;;)
──────────
山内一豊もその準備に余念がありませんが、
岐阜城に集まってはや3日、
未だに降る雨の中で待機が続きます。
その間、織田信長は羽柴秀吉と
馬防柵建設の打ち合わせをします。
その人足として、作事仕事の得意な源助に
“戦が始まる前までに”長篠から脱するという約束で
長篠へ来させるように一豊に命じます。
それには、妻・旭や義母・なか、
そして千代の大反対を食らいますが、
そんな千代をギロリと睨みつける寧々がいます(^ ^;;)
結局 源助は、義兄秀吉が頼りにするならと
皆を説得して長篠へ赴くことになるのですが、
寧々に睨まれていた千代は、別室にいる寧々の元へ赴きます。
旭を慮るあまり、秀吉をないがしろにした発言が
寧々の勘気に触れたようです。
しかも、源助を手放したくない旭を説得するために
千代を呼び寄せたのに、その反対のことをしでかしたわけです。
思ったことを口にするのは千代の魅力ではありますが、
「わが夫を難ずることは許しませぬッ」と
寧々に固く固くしぼられて、半ば放心状態で帰宅した千代。
岐阜を発った信長軍は、岡崎城で徳川家康軍と合流し
5月18日には長篠設楽原に到着。
「武田も、雨に負けるのか」
陣中に詰める六平太がポツリとこぼしています。
連れて来られた源助は、長雨の中
木を要領よく柵にする方法を適宜伝授して
皆の作業効率を上げています。
そんな源助のおかげで、柵は半日でできました。
源助のお役目は無事に終了したので、約束通り
できるだけ早く戦場から遠ざけて長浜に戻れるように
一豊は家臣を源助につけ、帰国の途につかせます。
翌朝、長篠では
濃いスモークがかかる方に
無数の鉄砲の銃口が向けられています。
武田騎馬隊が立ち向かって来、
信長は無言のまま指揮棒を振り下ろし
一帯に銃声が響きます。
倒される馬、落馬する人。
無数の兵士たちが倒れていきます。
入れ替わり立ち替わり柵の前に立ち
時を置かずして放たれます。
源助は、亡くなりました。
戦が始まる半日も前に秀吉の陣を発った源助は
長浜へ戻る途上、戦場で銃声が響いているのを聞き、
新しい戦をするという信長が、自らが組み立てた柵を
どのように活用するのかがとても興味津々で、
それを確かめに戦場に舞い戻ったわけです。
そこで、雨のように降り注ぐ流れ矢に
当たってしまいました。
後悔の念が千代を襲います。
この世に生まれいでた者は、死ぬまで生きねばならぬのだ。
命をつなぐことができる者は、つながねばならぬのだ──。
源助の死を千代に伝えた六平太は
千代のお腹に新しい命の存在を見抜きます。
やはりそのあたりの鋭さは
千代が小さい頃から見て来ただけあります。
長篠で大勝利を収めた織田軍が岐阜に戻ってきました。
しかし一豊の表情は晴れません。
一命に替えましても、と旭と約束した以上、
源助の死の責任を取って、腹を斬るつもりです。
立ち上がった一豊の手を掴み、
千代は自らの腹に当ててみせます。
「ここに、旦那さまのお子がおりまする!」
大事にいたせ と言い置いて、一豊は長浜城へ。
ついて来た千代とともに、責めを負って自害しようとします。
そこへ秀吉が駆けて来ます。
源助の柵は長篠の大勝利につながったこと、
源助はいわば一番手柄であること、
そして、秀吉や一豊らが源助を守り抜いてきたものの
結果的には救うことができなかったこと、
それを全て旭に打ち明け、詫び、
兄妹で抱き合って泣いて悲しみます。
一方で、秀吉に話をうやむやにされた
一豊と千代は屋敷に戻ります。
悲しみに打ちひしがれる旭を元気づけようと
秀吉はいろいろ方策を練りますが、
新しい女子を与えれば、とりあえずお前さまは
目の前の悲しみをお忘れになることができましょう?
そんな寧々の言葉に「……!!」となる秀吉。
その白羽の矢は、200石取りの副田甚兵衛に立ちますが
甚兵衛はその話を断ります。
不破家から、不破市之丞危篤の知らせが舞い込み、
一豊は馬で、千代は輿で不破家へ急ぎます。
もっともっと生きたい、と笑顔で話す市之丞は
「主君を選ぶは武将の知恵」と一豊に教えます。
しかし、千代の子を見たかった と漏らす市之丞に
千代は ややができましたと報告。
市之丞は大喜びして千代の手を握ります。
夫婦枕を並べて、朝を迎える幸せを大事にせい!
千代へ最後の教えを授けて、市之丞は翌朝
千代に看取られながら永久の旅へ。
──────────
天正3(1575)年5月21日
長篠の戦いで織田徳川連合軍が武田の騎馬隊を打ち破る。
桶狭間の戦い
【第2回】
戦勝に湧く清州城下に何気に光秀登場
木下藤吉郎と寧々の祝言
竹中半兵衛、織田軍を撃退す
【第3回】
木下藤吉郎、墨俣築城に成功
信長は藤吉郎を500石とし、「秀吉」という名前を与える
山内一豊、秀吉の与力となる
竹中半兵衛、たった16人で稲葉山城乗っ取りに成功(後に斎藤竜興に返却)
【第4回】
竹中半兵衛、秀吉の直臣(&軍師)となる
織田軍、堀尾茂助の案内で稲葉山城への裏道から進攻する
稲葉山城落城
不破市之丞、一豊と千代の婚儀に同意する
信長、家臣団を連れて美濃に引っ越し
一豊、50石取りとなる
一豊と千代祝言
【第5回】
稲葉山城を岐阜城と改めた信長は「天下布武」を印とする
お市、浅井長政に嫁ぐため岐阜を出発し、北近江・小谷城へ向かう
今や身重となった千代は、侍女たちに身体を支えられながら
山内屋敷内をゆっくりゆっくり歩いています。
そんな千代が座敷を見て「うわ!」とビックリ。
山内一豊の母・法秀と、千代の伯母(養母)・きぬが
生まれてくる子どものために
産着を無数に縫ってくれているのです。
子どもを法秀は、動いていればお産は軽いと
千代に“そぞろ歩き”を勧めますが、
今日は琵琶湖まですでに2往復しておりまして
それはよいことです、と法秀に褒められます。
一方で、中村一氏の妻・としが男子を産んだという知らせを
堀尾茂助の妻で同じく身重のいとがもたらしてくれまして、
私も負けてはいられませぬ! と言い置いて
さっさと屋敷に戻ってしまうのですが、
「騒々しいですね、勝つの負けるのと」
そんないとには手厳しいです。
成長した千代の腹に驚いています。
一豊は、羽柴秀吉から一字をもらって
「秀豊丸」という名に決めています。
ただ、産まれて来たのが
女の子だった時の名前は考えていないそうで、
千代は「よね」を提案します。
平凡な名前じゃの、と一豊はあっさり流しますが
平凡に生きられるほどの幸せはない! と母に一喝されます。
どうして一豊って、母親の前では一言多いのでしょうね(笑)。
秀吉の妹・旭の旦那候補である副田甚兵衛を呼び出した秀吉は
恐い顔で「上意である!」なんて言っていますが、
その実、そうでも言わねば甚兵衛が首を縦に振らないためで
手を握って、旭を頼む! と涙を流します。
涙まで流す人たらし具合に、寧々は驚きです。
秀吉が長浜に戻ることがないまま
甚兵衛は旭を娶ることになります。
秀吉と一豊は、竹中半兵衛の屋敷に見舞いに訪れます。
ひどく咳き込む半兵衛は、もはや先は長くはないと
最低でも十年間はかかるであろう中国攻めの極意を授けます。
中国攻めもそうですが、越後上杉をどうするか?
長篠合戦によって武田の力が弱まった今、
身軽になった上杉は織田を牽制するために
北国に攻撃を仕掛けるでしょう。
その北国には、柴田勝家がいるのですが──。
これからの織田家は、
柴田勝家と羽柴秀吉、それから明智光秀の
三つ巴の勢力争いになる とは六平太の見立てです。
その中で、一豊がどう動くかが最大のカギとなります。
それを千代にそっと教えたとき、千代は産気づきます。
法秀ときぬが見守る中、千代は女の子を産みます。
六平太から知らせを受けた一豊は
産まれたのが女の子と聞いて少し落胆気味ですが、
千代の申し出通り、よねと名付けることにします。
五藤吉兵衛や祖父江新一郎ら家臣たちに祝福を受け
顔を引きつらせたまま、その声に応じます。
天正5(1577)年4月。
久々に長浜に戻った一豊は、よねと出会います。
しかし未だ見たことのない一豊に何かを感じたのでしょうか、
一豊が抱きかかえた瞬間に大声で泣きわめくハプニング(笑)。
そして、明智光秀の妻・槙の方が
以前お世話になった千代を坂本城に招待したいと言っていて
その申し出を受けて夫婦そろって坂本城へ赴きます。
まだ山内家が貧乏の盛りだったころ、
祖父江徳次郎・小三郎兄弟にいじめられていた
玉を救ったのが縁ですが、
その玉もなんともキレイな美しい姫さまにおなりです。
勝家からの援軍を請う書状は、信長を突き動かします。
秀吉は、わざと援軍を送らずに上杉軍を近江まで引き寄せて、
近江で一気に叩き潰す策を提案しますが、
信長はその策に耳を貸しません。
信長は秀吉を援軍として向かわせることにします。
しかし、せっかく大挙して向かった陣から
出迎えがなかったと言いがかりをつけ、
「近江へ帰れ!」と叫んだ
勝家の言葉を待っていたかのように、
たちまち近江へ引っ込んでしまう秀吉に、
信長は激昂してしまいます。
織田信長の逆鱗に触れている羽柴秀吉。
その秀吉の下にいる山内一豊のことが気がかりな千代は
療養中の竹中半兵衛の屋敷を訪ねます。
半兵衛曰く、今回のことは秀吉一世一代の芝居だそうです。
信長に釈明すべく、お目通りが叶えば
秀吉の心中は必ずや信長に伝わるものと信じますが、
叶わぬ時は……疑い深い信長のことです。
即座に「秀吉謀反」とみなされても仕方ありません。
そんな半兵衛の不安が的中したか、
信長の目通りは許されませんでした。
しかも、沙汰あるまで長浜で閉門謹慎の命が下ります。
しょんぼりとしている秀吉に、
登城した半兵衛が何事か耳打ちします。
沈みかけた雰囲気を吹き飛ばすかのように
秀吉は寧々にも豪華な着物をまとうように指示し、
「百姓はしぶといでよォ、容易くは死なぬわ。は!」
猿楽の宴を盛大に開かせることにしますが、
豪華な料理が出されても、
誰一人として箸をつけようとはしません。
「無礼講じゃ!」という秀吉の声だけが
長浜城大広間に空しく響き渡ります。
そんな時、半兵衛が苦々しい表情で
このような宴を開いた秀吉が狂ったかと
信長に伝わる不安を口にしますが、
秀吉は、休み返上で長年働き続けた家臣たちを
この蟄居の間に労るために上様が与えてくれた休みだとし、
だからこそ遠慮なく呑めと言います。
そこでようやく箸を付ける家臣たち。
実はコレ、すべて半兵衛の知恵でありまして、
猿楽師たちも安土から呼び寄せた者たちです。
つまり、ああいう形で秀吉の思いを家臣に聞かせるフリをして
遠回しに猿楽師たちの耳に入れることによって、
信長に仕える猿楽師たちが信長に
秀吉の思いを代わって伝えさせることができるわけです。
秀吉はすばやく安土へ向かい、信長に閉門を解かれます。
秀吉は一豊を呼び出し、久秀がいる大和国信貴山城へ赴き
降伏の説得を命じられます。
イマイチ自身のない一豊ですが、秀吉は
久秀が所有し、信長が欲しがっている
「平蜘蛛の釜」をヒントに頭を使え、と送り出します。
しかし、その本音は──、
「槍ばかり振り回す武将は、いらぬのじゃ」
久秀を説得する一豊ですが、
信長という人物を知りすぎているためか
なかなか降伏に応じません。
一豊は、平蜘蛛の釜というカードを切り
釜を信長に献上することで、家臣のみならず
久秀の命も助けられるかもしれないと進言します。
その条件をようやく呑んだ久秀は、
家臣たちを城の外に出すために秀吉に兵を引いてもらい
それから平蜘蛛の釜を差し出しすことを約します。
場合によっては切腹して果てることも厭いません。
どちらかを持ち帰らねば信長を説得できず話は先に進まないわけで、
「そちはナメられておるぞ!」と激怒。
信長からの命令もあり、秀吉は比叡山と同じように
信貴山を焼き討ちにします。
城内の者たちはことごとく殺され、
それは女こどもたちも言うに及ばず。
平蜘蛛の釜に火薬を詰めた久秀は、
それに火を投じて爆死します。
上杉討伐がなかなか上手くいかない勝家をさんざんに責め立て、
丹波国を切り取るのに数年かかると言った明智光秀をバカにした信長は
中国10ヶ国侵攻の総大将を秀吉に命じます。
勝家らは秀吉に対してひがみを露(あらわ)にします。
長浜に戻った一豊を癒してくれるのは、
やはり千代とよねの存在です。
父の悩みとは関係なく、よねはすくすく育っています。
中国攻めを明日に控え、
千代は大きな杯になみなみと酒を注ぎ
一豊はそれに口をつけます。
勇んで長浜を発ったものの、
秀吉にとって中国攻めは難しい戦いになりました。
三木城の別所長治が毛利方へ寝返ったためで、
戦の長期化が予想されます。
槍を振り回す一豊の元に六平太が現れ
ポツリと一言言います。
「織田家を、見限りませぬか」
──────────
天正5(1577)年10月10日
織田軍に攻められた松永久秀が信貴山城で爆死。
好々爺の祖父江新右衛門が
一豊と千代の一粒種・よねにヤマブキの名前を教えています。
草花にもいのちが宿っているのだ、と。
しかし「いのちってなぁに?」と聞いて来たよねに
完全に答えに窮してしまってはおりますが(^ ^;;)
そんな暮らしの様子を、千代は
播磨三木城に戦で詰めている一豊に文で知らせています。
最近、屋敷に新右衛門そっくりのタヌキが庭先に現れて
腕組みをする様子がこれまた新右衛門そっくりだとあり、
“新太”と名付けたのだそうです。
そういった千代の文は、
なぜか五藤吉兵衛のツボにハマっておりまして、
千代が嫁いできたころの
千代に目くじらばかり立てる吉兵衛とは
かなり様子が変わってきています。
一時の癒しになっていることには違いありません。
もしかしたら、松永久秀のことで
一豊は再び道に迷っているのかもしれません。
人を殺めて天下を従え、その結果 泰平の世をもたらす。
このジレンマは、感じたのはおそらく一豊だけではないでしょう。
そんな時に言われた、
「織田家を、見限りませぬか」という六平太の一言。
お屋形さまも、筑前さまも裏切らぬ、とは言ったものの
ほんの少しだけ、迷いの原因となっていることも否定できません。
そのころ、織田信長は安土築城に向けて邁進中……。
その建設現場に呼び出された明智光秀は
愛娘・玉と 細川藤孝の嫡男・細川忠興との婚儀を命じられます。
信長は光秀に、早く丹波を切り従えて
毎朝毎朝安土に向かって手を合わせて拝めと言い出します。
秀吉は、自身を敬っていないために
中国攻めで苦戦しているのだと言いたげです。
安土城ができれば、松永久秀のような謀反を起こす人もなくなり
西国も帝も公家たちも信長にひざまづく……。
最近の、信長の考えがよく分かりません。
坂本城に戻った光秀は、玉を呼び出し
細川家へ嫁ぐ娘に懐剣をわたします。
もちろん、この刀を使わないことが一番ですが、
そのための守り刀だと説明しても、玉はいらぬと怖い顔。
「強情じゃのう」と父を呆れさせます。
ま、玉にとって忠興は幼なじみなので
知らない相手に嫁ぐよりは気が楽です。
忠興と玉との婚礼の儀が執り行われました。
10月・播磨の秀吉の陣屋で
すやすやと眠る一豊に六平太が襲いかかります。
襲うと言っても、いつものように重要な情報を持ってきたわけで、
後から羽交い締めにして騒がないように口を押さえつけただけです。
荒木村重が毛利に寝返ったとの知らせです。
織田は内から崩れてゆくと六平太の読み通りです。
長浜に戻って千代とよねを守るように言うと、
六平太はアッという間に消えてしまいました。
秀吉も村重寝返りの情報は掴んでいて、
中国の毛利と摂津の村重に
挟み撃ちに遭う危険性も出てきました。
村重の家来に、石山本願寺に兵粮米を売った不心得者がおり
信長が村重に申し開きをせよと呼び出し状を送りつけたわけです。
安土に上がれば殺されると思ったらしい村重は
信長を裏切って毛利方へ与したというらしいのです。
信長は、光秀の娘・ともが
荒木村重の息子に嫁いでいることに目をつけ
村重に申し開きをするよう光秀に説得させようとします。
村重の翻意あるときには、信長の許しが出る。
ただそのことを信じて、光秀も摂津へ──。
秀吉と一豊は、村重の居城・摂津有岡城に入ります。
村重に謀反されては、村重の身も危なく
挟み撃ちの危険にさらされる秀吉も危ないです。
村重は多少の後悔も感じつつ、もう後には引けないと
秀吉の説得に耳を貸そうとしません。
それでも秀吉は涙ながらに嘆願をし、
村重も気持ちだけ受け取ります。
そこへ、入れ替わりに到着した光秀です。
秀吉は自分の芝居にニヤリと笑い、光秀にあとは任せます。
クロージングってやつですか(^ ^;;)
村重は、秀吉のときとは違って光秀と2人きりで会います。
秀吉の猿芝居に反吐が出るところだった! と
秀吉の芝居は完全に読まれてしまっておりますが(笑)、
村重は、いくら有能な人物でも無用となれば捨てられる、
その現状が怖かったのだと光秀に吐露します。
そんな村重の訴えは、光秀の心を大きく揺さぶります。
説得、失敗──。
黒田官兵衛が再度説得に当たることにしますが、
有岡城に入った官兵衛の消息はすぐに途絶えてしまいます。
11月、官兵衛の帰りを待たずに
信長は3万の軍勢を率いて摂津有岡城を包囲。
しかし「窮鼠猫を噛む」のことわざ通り
村重の徹底抗戦で持久戦にもつれ込みます。
翌天正7(1579)年5月、ついに安土城天守が完成。
緊迫が張り巡らされた障子に真っ赤な漆塗りの床に
天然の美しさと人工の美しさの調和がとれた
とても素晴らしいものだと市は絶賛しますが、
村重が敗れれば、
有岡城将兵たちをまたも皆殺しにするであろう信長に、
濃は、この美しさは人の怨念の上に建っていると非難し
たまらずに天守から出て行ってしまいます。
咳が止まらず、吐血も量が増えてひどくなっています。
そのことを祖父江新一郎に知らされた千代は
居ても立ってもいられず播磨に向かおうとしますが、
戦場に女が踏み入れると、軍の士気に関わると新右衛門が止めます。
千代は半兵衛に感謝の気持ちと励まし、
長浜への無事の帰還を願う文を書きます。
それを一豊に読んでもらった半兵衛は
天下は信長には獲れないが、秀吉には獲れ
もっと長生きできればそれを楽しめたものを、と残念がります。
「生涯を通じて愛した女子は、千代殿でござった」
その言葉を最期に、ついに力尽きてしまいます。
──────────
天正7(1579)年6月13日、
肺の病気により竹中半兵衛が死去。
「おんな太閤記」でもここまでは描けなかった
黒田官兵衛の嫡男・松寿丸がいます。
「あの蝶は夫婦(めおと)かのう」と
飛ぶ二匹の蝶を見てよねに語りかけるのですが、
「めおとってなぁに?」と例の如く尋ねるよねに
きちんと答えてあげる、秀才ぶりを如何なく発揮しています。
8ヶ月前、荒木村重を説得すべく
摂津有岡城に入った官兵衛の人質、というわけです。
ただ、入城以来、すぐに何の音沙汰もなくなり
「元主君の小寺氏に呼応して毛利に寝返ったのでは?」だの
「説得が失敗し村重に斬られた」だの
推測ばかりが飛び交う羽柴秀吉の陣中ですが、
織田家譜代の家臣ではない官兵衛が
そこまで忠義を尽くすとは思えず、裏切り説が有力です。
でも、秀吉と一豊だけは官兵衛を信じるつもりです。
ただ、見せしめに松寿丸をRように
織田信長からの命令が下った時には、
かの秀吉もしぶしぶ従わざるを得ません。
長浜に戻った一豊に、千代は
「松寿丸は流行り病で亡くなりました」と遺髪を渡します。
一豊は、松寿丸を匿えば
それに加担した者と一族郎党は皆殺しにしてしまう
その信長の恐ろしさを知っているだけに 千代を咎めますが、
ただ、千代にもたらした六平太の情報では
村重説得に失敗した官兵衛は有岡城の獄に投ぜられていて、
未だ生きているとのこと。
村重に殺されなかったのは、
村重も官兵衛もキリシタンだったゆえです。
合点した一豊は、早く知らせねばと
遺髪を持ってそのまま三木城へ取って返します。
三木城に戻った一豊は、松寿丸の遺髪を秀吉に見せます。
松寿丸が生きていることもつい口を滑らせた一豊ですが、
秀吉は鋭い言葉を浴びせます。
「“消せ”という意味が分かっておらぬようだの」
殺せ、とは一言も言っていないのです。
泣きまねをしろ、と言うのです。
あまりのショックで泣き叫べば、そのウワサは安土まで聞こえ
松寿丸殺害をきっと信じてくれよう、というわけです。
人タラシたる秀吉の戦法は
こういったところから来ているのでしょうか。
裏切りはまず身内から、というわけで
一豊は秀吉軍団の前で大泣きして演じてみせます。
それどころか、刀を振り回して狂乱気味です。
何も知らない五藤吉兵衛は一豊を励まし、
何も知らない堀尾茂助あらため堀尾吉晴も同情をし、
何も知らない祖父江新一郎は涙すら浮かべています。
そんな一豊の様子を遠巻きに見つめる
前野将右衛門と蜂須賀小六も複雑な表情を浮かべています。
しかし有岡城を取り囲む事態は急展開を迎えます。
村重は家臣領民を見捨ててひとりで城を落ちたのです。
有岡城へなだれ込む秀吉軍。
城内にいた兵士や女こどもは皆殺しされました。
信長は、こんなに忠義に厚い官兵衛を疑い
松寿丸殺害をとても悔やんでおりまして、
官兵衛のためにと一豊に砂金を与えるのですが、
一豊は、自らの一存で松寿丸を匿っている事を打ち明けます。
信長の、真っ赤に目を腫らした涙目を初めて見ました(^ ^;;)
事態が好転しても、主命に背いたからには
何らかの処分を覚悟する一豊でしたが、
信長の「官兵衛に会わせてやれい!」という言葉で
許しを得たも同然であります。
「行けい」と言われて立ち去る一豊ですが、
与えられた砂金は持って行ったのでしょうか
置いていったのでしょうか。
有岡城の事態には関係なく
三木城の別所長治の抵抗はまだ続いていて、
秀吉軍は兵糧攻めにしています。
翌天正8(1580)年正月、長治が降伏を申し入れて
一豊らが三木城内に足を踏み入れてみると、
そこはまさに飢餓地獄であります。
長治ら主要の者たちは
腹を斬っていただくより他ありませんが、
もしそうなれば、城内に残った者たちには
指一本触れない約束にします。
城内の者たちに粥の炊き出しを行いますが、
その中に何故か小りんの姿が──。
小りんは長らくの兵糧攻めで目が見えなくなり
与えた粥も咽せて気を失ってしまいました。
小りんの姿に気づいた吉兵衛が助け出すのですが、
吉兵衛を追って来た一豊に、小りんは卑怯者呼ばわりします。
草も紙も木の皮も虫も馬も食いつくし、そんな地獄絵図と
刀や鉄砲で戦をするのとどこが違うンだ! と言われては、
一豊は「血を流さずに済んだ」と反論するのがやっとです。
これらの戦いで、一豊と吉晴、中村一氏は
揃って1,300石に加増されました。
明智光秀が、ぶらりと山内屋敷に立ち寄ります。
なんでも先日、病気がちの妻・槙に薬草を届けたそうで
そのお礼も兼ねてです。
一豊にとってみれば
千代は若干出過ぎたところがあって心配なのですが、
槙にとっては、岐阜城下に引っ越して来てからというもの
千代の世話になりっぱなしです。
日ごろ、軽々しく声をかけられる相手ではないだけに
一豊は、武士とは何ぞやと思い切って光秀に聞いてみます。
光秀曰く、その問いは誰しも考える事でしょう、と。
こんな素晴らしい武功を残す光秀はどうか気になるところですが、
その意外な返答に、一豊はある種の安堵感を覚えます。
「当たり前です」
晴れて畿内平定となりました。
すると信長は家臣団を集め、ある決断を下します。
林 通勝と佐久間信盛の両人を、織田家より追放する、というのです。
通勝の追放理由ですが、24年前のことが許せないからだそうです。
24年前とは……信長の弟・織田信行を担ぎ
信長を亡き者にしようと転覆を企てた事件のことであります。
ちなみにこの事件には柴田勝家も加担してはおりますが、
通勝と勝家はその後の働きが全く違います。
佐久間父子の追放理由は、
本願寺攻めで何の功績も残せなかったゆえです。
ただこれも、光秀や秀吉に比べれば全然足りず
何もやっていないのと同じ、というわけです。
通勝は、自分に味方して声を上げてくれる者が
一人もいないことに愕然とします。
──────────
天正8(1580)年1月17日、
三木城城主・別所長治とその一族が切腹し
1年10ヶ月ぶりに包囲が解かれる。
エイサ! エイサ! というかけ声と歌舞音曲に合わせて
無数の踊り手たちが派手に舞い、
周囲で見とれる民衆たちも踊り狂っています。
天正8(1580)年11月、安土城下──。
もともと祭り好きな千代は、いつの間にか
その踊り手たちの輪の中に入ってしまいます。
一豊は、祭りとなると居ても立ってもいられない千代を
軽く咎めますが、さほどは気にしていない様子です。
もしかしたら一豊は、信長が作った
活発な安土の市を見せたかったのかもしれません。
夫婦水入らずで、肩を並べて歩いていると
多数の武士たちが走っていきます。
何だろう?? と思っていると、
中村一氏が 馬市が立つことを教えてくれます。
馬市と聞いて一豊が元気になります。
置いてけぼりを食った千代は屋敷に戻りますが
膨れっ面のままで、五藤吉兵衛を困惑させています。
馬が多数居並ぶ中で、オーッと声を上げさせる名馬が登場します。
馬どころか、人さえも十戒のごとく道を開けるほどの
威厳を持った馬であります。
堀尾吉晴は、馬を引いて来た老商人に価格を聞いてみますが、
「情けない!」と一蹴。
馬を見れば自ずと値が分かるはず、というのです。
新たに羽柴秀吉の配下となった加藤清正の「4両!」
一氏の「5両!」という声に大笑いの老商人は、
その横で腕組みして眺めている一豊に
この馬の値をつけてもらうことにします。
「黄金……10両!」
一豊は、馬をてっぺんからすべて眺めて見て答えます。
昨日見た、龍のような名馬のことで放心状態の一豊です。
千代はその値を聞いてみますが、
「黄金10両じゃ!」と一豊に聞いて
千代は驚き、思いきり咽せてしまいます。
一豊は馬の値に驚いたから咽せたと思っていますが、
千代が驚いて咽せたのは、
馬の値が高かったからではありません。
頭痛で臥せっている濃姫に
織田信長が総見寺に詣でるように言います。
信長自身を祀る寺を安土に作ったわけです。
「たちどころに治ろうぞ」とニヤリと笑う信長は、
ちと不気味です。
濃は、「殿は、神でも仏でもありませぬ」と言いますが、
それでも信長は、徐々に発狂していきます。
後日、濃は明智光秀を安土城に呼び出します。
「殿のお召しにござりまするか?」という
奥方・槙の問いには、槙の視線を感じつつも
曖昧に返事する光秀です。
濃が心を許せるのは、光秀だけであります。
もし人生をやり直せるなら
光秀さまと……と考える濃ですが、
やり直せないのが人生であり、
「もし」と考えることすら
許されないことであると濃を諭します。
光秀は濃の気持ちを充分に感じてはいるのですが、
ケジメをつけるためにも「御免」と
言葉を残して行ってしまいます。
うん、と決意した千代は
馬で長浜城下の山内屋敷へ向かいます。
養父・不破市之丞と養母・きぬが用意してくれた
黄金の箱を取り出します。
一豊殿のお役に立てればよい。
今が、夫の大事と思う時にこの箱を開けよ──。
市之丞の言葉に従って、箱を開けます。
1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、
7枚、8枚、9枚……そして10枚。
黄金、10両。
千代は、その10両を持って安土へ取って返します。
その帰途、安土城の城下町で
足を挫いて歩けない女人を助けた千代は
山内屋敷へ連れていきます。
そこで包帯を巻き、手当をするわけですが、
この女人が信長の正室・濃であることは
千代は気づいていません。
やっぱり放心状態です。
そんな一豊に、千代は黄金10両を見せます。
「打ち出の小槌があったからにござります」と言いますが、
そんなことで騙される一豊ではありません。
追及すると、千代は悪びれもなく白状するのですが、
いくら市之丞の言いつけとはいえ、
それがまた男のプライドを深く傷つけるようで、
妻に見下されたと一豊は怒り、
そういう言い方をされて千代は泣き出してしまいます。
最近の一豊は、少し戦に疲れているように思え
妻としては、名馬にまたがって出陣する夫の姿を
もう一度見ることができたら、と願って揃えた10両です。
一豊は怒ったことを悔い、平身低頭 千代に謝り、
そして「今すぐ馬を買うてこよう!」と馬市へ向かいます。
濃は、一豊と千代のやり取りを立ち聞きしてしまったのですが
千代の行為・発言は、濃の心を晴れやかにしてくれました。
ここは、一豊が戻ってきて 自らの身分が明らかになる前に
屋敷から立ち去った方が賢明です。
信長からの突然の出仕命令が下ります。
信長は一豊が買った名馬を試し乗り。
馬には多少うるさい信長も大満足です。
黄金10両によって、
千代は山内一豊の名を天下に売った! と
信長の千代への評価もかなり高くなりました。
そして、その直後に通りかかった輿に
うまい具合に濃が乗っておりまして(笑)、
一豊は「お方さま!」と片膝を付き、
千代は「あっ!」と濃に指さします。
千代は、何が何だか分からないまま
片膝つかされますけど(^ ^;;)
濃は、助けてくれたお礼にと
一豊・千代夫妻に砂金を与えます。
帝の前で繰り広げられた馬揃えでますます名を高めた一豊は、
秀吉3万の兵に加わり、中国攻めに向かいます。
──────────
天正9(1581)年2月28日、
織田信長が正親町天皇ら公家衆の前で
馬揃えのパレードを行う。
山内一豊の妻・千代は筆まめで、
毎日のように一豊に手紙を送っています。
ただ、そのマメさもハンパないもので、
五藤吉兵衛、祖父江新一郎のみならず
黒田官兵衛相手にも文を送る有様であります。
堀尾吉晴の妻・いとや中村一氏の妻・としは
そんなマメさは私たちにはない、と諦め顔です。
高松城を囲む羽柴秀吉は、
城の攻撃方法について水攻めを提案します。
城の脇を流れる足守川を一旦せき止めてから土手を築き、
土手ができ次第、その堰を切って水を放流する。
反対側を流れる長野川でも同様、せき止めて土手を築き
土手ができたら堰を切って水を放流する。
しかも、間もなく梅雨入りしますので
絶好のチャンスかもしれません。
織田軍は甲斐の武田勝頼を攻撃し、ついに滅ぼします。
しかし武田の残党は恵林寺に逃げ込みますが、
織田信長は容赦なく焼き討ちを敢行。
国師として名高い快川紹喜和尚も炎に包まれて命を落とします。
細川藤孝らは、信長が持つ運の強さを神に例えて讃えますが、
「神ではないわ!」と光秀はつい声を荒げてしまいます。
藤孝ら各武将の協力や自分たちの骨折りがあって
今の織田の天下があるようなものだとフォローを入れます。
ただ、具合の悪いことに
その光秀の言葉は信長の耳に入ってしまいました。
「おのれが、いつどこで骨を折った?」と
信長は徐々に徐々に光秀を追いつめていきます。
その日以来、光秀は眠れない日日が続いています。
妻の槙は、それが武田滅亡によるものや
信長折檻によるものではなく、
武田攻めの前に濃から送られた文に
関係あるのではないかと考えています。
一豊に届けさせます。
秀吉の水攻めはとても効果があって、このままいけば
間違いなく降伏するであろう見通しではありますが、
水攻めの間、秀吉軍は待つばかりで何をすることもありません。
もし誰かがこの有様を信長に言いつけでもしたら、
秀吉の立場として危ないわけです。
ある日、信長は光秀を安土城に呼び出します。
朝廷から「関白」「太政大臣」「征夷大将軍」の
いずれか好きなものを選べと言ってきているらしく、
光秀ならどうするか、意見を求めたわけです。
信長は源氏ではなく平氏を名乗っているため、
平氏としての最高位・太政大臣に就くのがいいと進言。
ただ、信長の目指すところはソコではありません。
信長から見れば、朝廷からもらえることを
ありがたがる時代は終わりました。
それはつまり、もはや朝廷もいらず、と言うわけです。
「よがこの国の、王である」
信長は光秀に、徳川家康を安土に歓待した際の
接待役を申し付けます。
領地を与えない代わりに、
接待の厚さで長年の苦労に報いようとしたわけです。
一豊が秀吉の書状を携えて安土城入りを果たしたのは、
ちょうどそんな時でした。
家康に出した魚が腐っていると信長が言い出し、
接待役を下ろされて秀吉の援軍に回るように命じます。
出雲・石見を切り取り明智領とすることを許してくれますが、
近江・丹波という、今の光秀の領地は召し上げとなります。
光秀転落の瞬間です。
光秀は備中への出陣の途中で愛宕山へ登ります。
光秀は、信長が翌日
小勢を率いて上洛する情報はつかんでおりますが、
すれ違いざまに六平太が、更なる情報を教えてくれます。
「手勢はわずか、信忠軍も500ほど」
──時は今 天が下しる 五月かな
六平太は、そのまま長浜へ向かい
これから起こりえる変事を千代に伝えます。
──────────
天正10(1582)年5月28日、
明智光秀が愛宕権現に参篭し、連歌の会を催す。
織田信長は手勢を率いて上洛し、本能寺へ。
そのころ千代は、長浜城の寧々のもとへ
備中へ出陣する明智光秀に謀反の気配ありとの
六平太からの情報を持って急行します。
明智光秀が本能寺へ迫ってきました。
“光秀謀反”と聞いて、
濃姫は複雑な表情で森蘭丸を見据え
信長は高らかに笑っています。
信長軍と明智軍による銃撃戦です。
明智軍は明らかに信長の手勢のみを狙ってきますが、
信長らはそのまま相手していて
勝てるような数ではありません。
玉よけの竹組みを壊し、瓦を割り、そこを狙うことで
明智軍の被害を拡大させていきます。
濃姫が寺の中にいることを知りますが、
今となってはどうすることもできません。
濃姫が本能寺内に留まったことに信長も驚きますが、
濃姫らしい言葉で、信長は俄然やる気になります。
「あの世で会おうと仰せになれども、殿は地獄、私は極楽。
これでは死に別れにござります!」
濃姫は、笑う信長とともに敵兵を斬り倒していきますが、
無情にも信長の身体を幾多の銃弾が貫き、寺の奥へ運ばれます。
濃姫は、光秀の姿を認めます。
しばし見つめ合う二人です。
信長に嫁ぐ前まで、お互いに惹かれながらも
直接言葉に表すようなこともせず、今日まで来ました。
そんな濃姫は、光秀の目の前で
多くの銃弾を浴び、絶命。
光秀は信長の首にこだわりますが、
火の手が早く なかなか見つかりません。
六平太は、密書を安国寺恵瓊へ送ります。
京での出来事を秀吉に知らせる書状を送ります。
そして息子の嫁で、光秀の娘でもある玉に
本能寺での変事について事情を明かすのですが、
光秀に味方することだけは避けます。
玉は、己の無力さをひしひしと感じます。
備中では、静かな夜を迎えています。
満天の空を見上げて談笑する
山内一豊と五藤吉兵衛主従ですが、
そこへ六平太が放った密使が倒れ込みます。
密使は「これを安国寺恵瓊さまに」と
密書を吉兵衛に手渡しますが、
その密書には、本能寺で
信長が光秀に討たれた旨がつづられています。
にわかに信じられない羽柴秀吉ですが、
細川幽斎からの文が届いたこともあり
どうやら信長が亡くなったことは本当のようです。
毛利への使者を一切通さぬようにし、
同時に本能寺の変事が毛利に知れる前に
毛利と和睦を進めることにします。
備中高松城城主・清水宗治が腹を斬り
2日後、まだ信長の死を知らない
毛利軍が高松城から撤収してゆくのを見届けて、
後の世にまで伝わる
「中国大返し」のすさまじい強行軍で、
秀吉軍は6月11日には尼崎に達します。
明智家では、迫り来る秀吉軍の情報はそれなりに掴んでいます。
もともとは毛利攻めで動けないと予想していたのに
さっさと和睦を結んで上方へ迫り来ることだけは想定外でした。
山崎の地で秀吉軍を迎え撃ち、その闘いに勝ちさえすれば
各地の諸侯は光秀になびくことは必定で、
光秀としても、戦いは避けられまいと考えています。
6月13日、明智側からの攻撃で決戦の火蓋が切られます。
伊吹山中に身を寄せる寧々・なからを
千代は励まし、明るく避難生活を送ります。
信長の死で、千代と一豊を取り囲む環境は
大きく変わりつつあります。
──────────
天正10(1582)年6月2日、
明智光秀が反旗を翻し、京・本能寺で織田信長が滅びる。
備中高松からの思いがけない羽柴秀吉の
大返しのスピードに迎え撃つ態勢が整えられず、
山崎の戦いであっけなく敗れました。
小来栖の竹やぶの中を静かに逃げのびる光秀は
不意に農民らに襲撃されてしまいます。
そこへさしかかった山内一豊が光秀を救出(?)するのですが、
光秀は、一豊が自らの首を取りにきたと察します。
光秀の脳裏に浮かぶのは、愛娘・玉の可愛らしい姿や
よく支えてくれた妻・槙の笑顔、
秀吉の顔、信長の顔、
そして……桜の木の下で微笑む濃姫の姿です。
光秀が絶命し、ここで首を撮ればまさしく大手柄ですが
一豊は光秀を取り逃がしたことにし、
遺骸に指一本触れてはならないと厳命します。
光秀に頭を下げる一豊。
一豊らが救出し、長浜まで送り届けます。
一豊は、後の論功行賞で3,000石に加増され
長浜城城番の役目を担うことになりました。
城番という役目ながら、城主もほぼ同義であり
城持ち大名という夢が早くも叶って、夫婦で大喜びします。
一豊の母・法秀尼を長浜城に呼ぼうと説得に行きますが、
法秀は「自分ひとりのちからで生きていきたいのです」と
やんわりと断ります。
玉が嫁いだ細川家では、
細川幽斎が子の忠興に玉をRように命じます。
しかし、忠興には愛しの妻に
そんなことができようはずもありません。
ならば、と幽斎は
玉が軟禁されている座敷へ家臣たちを差し向けます。
これ以上、玉をかくまっていては
織田方に逆賊の誹りを免れないというわけです。
その方たち(家臣たち)こそ逆臣だと激怒し、玉を救出。
「ワシのために、子らのために生きよ、玉!」
忠興は、ほとぼりが冷めるまで
丹後の山奥に玉を幽閉することにします。
それだけが、玉を助ける唯一の方法のようです。
信長三男・織田信孝は
秀吉が信長の跡目を狙っている事実を市に告げ、
織田家のために働いてくれている柴田勝家に
「格」を与えたいと言い出します。
つまり、市に勝家に嫁ぐように言っているわけです。
織田家の跡目争いは、すでに始まっていました。
秀吉は、信長の嫡孫(信長嫡男・織田信忠の子)である
三法師に目をつけ、いろいろと世話を焼きます。
清洲城で織田家の跡目を決める評定が行われます。
秀吉は三法師、勝家は信孝を推挙しますが、
突然の腹痛で秀吉が中座します。
といっても、実は仮病なのですが。
丹羽長秀は、遠国の備中に出陣していながら
大返しを成し遂げて信長の仇を討った秀吉に分があると主張、
幽斎もそれに賛同します。
勝家も、遠国の越中におりましたが
なかなか思うように動けず、
仇討ちという観点からは一歩で遅れた感が否めません。
三法師の後見となった秀吉は、
織田家の実権を握ることに成功。
勝家に自分を嫁としてもらってくれるように言い
秀吉の天下取りを阻もうとします。
秀吉は、長浜城へ引っ越す準備で忙しい山内家へ赴き
手をついて謝罪します。
すなわち、勝家が長浜城をよこせと言い出したそうで
(言い出したのか、秀吉が譲歩したかは分かりませんが)
一豊の長浜城入りが叶わぬことになったのです。
一豊の固まった表情に、声をかけられない千代です。
──────────
天正10(1582)年6月27日、
清洲城で織田家跡継ぎを決める評定が行われる。
功名 22.6%
風林 19.8%
篤姫 21.4%
天地 24.7%
龍馬 22.6%
江 22.6%
清盛 17.2%
八重 18.1%
官兵衛 18%
花燃 15.8%
真田丸 18.3%
25.9% 義経
24.7% 天地人
23.3% 武蔵-MUSASHI-
22.6% 功名が辻
22.6% 龍馬伝
22.6% 江
21.4% 篤姫
20.3% 新選組!
19.8% 風林火山
18.3% 真田丸
18.1% 八重の桜
18.0% 軍師官兵衛
17.2% 平清盛
15.8% 花燃ゆ
史実と一致と知って驚いた
柴田勝家に再嫁するため、
越前北ノ庄城へ出発する市に呼び出しを受ける千代。
別れを言うために呼び出したわけですが、
市が感じる羽柴秀吉の人物像と
千代が描く秀吉の人物像とが全くの正反対で、
少々口ゲンカっぽくなってしまいます。
でも、そんな運命を受け入れながら別れる二人です。
長浜城をもらい損なった山内一豊と千代夫婦は
播州に知行は与えられていたものの、
山崎近辺に屋敷を賜っていました。
天下の形勢が徐々に秀吉に傾きつつある中、
千代は山内家の家来衆を更に多数雇うことにします。
その新メンバーたちに、五藤吉兵衛が
山内家家紋の由来について説明しようとするのですが、
侍女のたきが段差につまずいて吉兵衛の後ろに追突。
吉兵衛は顔を大きく歪ませて痛がります。
だんだんと演出がかってきておりまして、
更に話が長くなってきているのでやっかいです。
吉兵衛は延々と語りながら、最後列で話を聞いているたきが
目に涙を一杯に浮かべているのに気づきます。
10月15日、
秀吉は京の大徳寺にて信長の葬儀を盛大に催します。
喪主は、信長四男で秀吉の養子になっていた羽柴秀勝です。
それに対し、再婚したばかりの柴田勝家と市は
越前から参列はしませんでした。
それをきっかけに秀吉は、
柴田勝豊に譲り渡した長浜城攻略を開始します。
出陣前日、吉兵衛が厠へ入ったスキを見計らって
たきが吉兵衛のために新しく仕立てた袴を
数着置いていきます。
吉兵衛がたきに頼んで縫わせたものだと思っていましたが、
吉兵衛の口ぶりからそれは違うと分かると
たきの思惑に「ははぁん」と気づきます。
ただ、吉兵衛にとっては迷惑千万だそうで
(単に照れ隠しをしているだけだと思うのですけど(^ ^;;))
その袴をたきに返すように千代に頼みますが、
人の好意は素直に受けるべきだと
千代は途端に厳しい表情になります。
“男も女も一つになって戦うべし”と言っていたのは
吉兵衛ですが、その本人が実践できていませんね。
千代は「ワタクシの命です」と言い残し
呆れた表情でその場を離れますが、
主君の妻にそう言われてはさすがに逆らえず、
意地を張っていた吉兵衛は千代に片膝ついてしょんぼり。
吉兵衛はたきに袴を返そうとするのですが、
そのチャンスはなかなか巡りません。
それを母と自分とで何度も縫い直していたとのこと。
勝手に仕立てたことで、吉兵衛が迷惑がっているのは
何となく分かっているのですが、
父の姿を思い出させるそんな吉兵衛を見ると
たきとしては居ても立ってもいられなかったようです。
千代に「本当は、喜んでいると思いますよ」と声をかけられて
ちょっぴり嬉しく感じています。
山崎城を出発した秀吉軍は、近江を進んで佐和山城へ。
目指す長浜城から馬で走って1時間ほどの場所です。
ただ、すぐには攻撃は始めません。
先陣を任された一豊をはじめ、堀尾吉晴や中村一氏は
長浜城は長年暮らしてきた場所だけに
城内の道も弱点も知り尽くしているわけで、
軍隊の士気が落ちてしまう前に攻撃したいと主張しますが、
秀吉はあくまでも待つ構えです。
長浜城を取り戻した秀吉は
今度は信長三男の織田信孝が守る岐阜城を取り囲み、
信長嫡孫の三法師を取り返します。
勝家が思い描いた道筋が、雪を利用して
秀吉によって徐々に崩されていきます。
勝ち戦を治めて戻った吉兵衛は、
たきに仕立ててもらった袴の姿でたきに披露します。
ついでに、穴が空いたあの袴も繕ってほしいと
たきに頼んでいます。
侍女たちにこっそり覗き見られていることに
気がついた吉兵衛は、
恥ずかしさのあまり逃げるように立ち去りますが、
それもある意味スキップしているようにも見えます。
カタブツの人物が、こうも素直に振る舞うと
なぜに可愛らしく映るのでしょうかね。
柄にもないことを言い出しますが、
千代は、新一郎よりも先に吉兵衛からだと言います。
目をむき出しにして驚く一豊ですが、
恐らく、吉兵衛とたきが好き合っていることを知らないのは
一豊ただひとりではないかと(^ ^;;)
吉兵衛は58歳で、前妻と死別していますので
38歳のたきを後妻として迎えるとしても
許してくれるかもしれません。
前妻の形見である櫛を取り出して眺めていた吉兵衛は
一つの結論を導き出します。
「嫁は、要りませぬ」
たきは「五藤様が承知なら」と喜んで受けるつもりですが、
主君の命を守り通す役目の吉兵衛には、嫁は必要ないのです。
そんな話を、吉兵衛の部屋の近くで聞いてしまったたきは
暇をもらって実家へ帰ってしまいます。
思わず声を上げ、衝撃を受ける吉兵衛。
それを吉兵衛に渡し、素っ気ない表情で
たきが宇治にいることをそれとなく伝えます。
吉兵衛は居ても立ってもいられませんが、
雨が落ちる屋敷内をウロウロするばかりで
どうしていいかも分かっていません。
たきが繕った袴を胸に抱いて、自問自答を繰り返します。
──────────
天正10(1582)年10月15日、
京・大徳寺で、羽柴秀吉によって織田信長の葬儀が執り行われる。
柴田勝豊を味方に引き入れ
織田信孝を調略した羽柴秀吉の次なる目標は、
伊勢の滝川一益であります。
その伊勢攻めへの出立が近づいています。
せっかく千代がお膳立てをしたのに
五藤吉兵衛は引きこもって動きません。
伊勢攻めへ参加するつもりの祖父江新右衛門までやってきて
吉兵衛にたきと夫婦になれと後押ししますが、
それでも理屈を並べて動こうとしません。
“たきは、自ら身を引いた”と吉兵衛は思っていますが、
実は千代の策略で、吉兵衛にとって
たきがどれだけ大事な存在かを気づかせるために
わざわざ宇治へ離したのだそうです。
新右衛門はもう一度、吉兵衛を後押しします。
宇治──。
吉兵衛はたきが住んでいる家にやってきます。
野菜を洗うたきが、たまに見せる色っぽいしぐさに
ついついドキリとして見とれる吉兵衛は
犬に吠えられて小川に落ちてしまいます。
濡れてしまった吉兵衛の着物を干すたきは
吉兵衛に食事を出すなど、細やかな気遣いを見せます。
そんなたきに、ますます惹かれていった吉兵衛は
思いを抑えられず、たきに全てを告げます。
──たき殿、待っていてほしい。
戦が終われば、必ず迎えにくるで──
「あの陰気な女」から「たき」、そして「たき殿」へ
呼び方一つで、人の気持ちが分かるって不思議です。
2月9日、
秀吉軍75,000は滝川一益を討つべく伊勢路へ。
ただ、長い行軍で疲れたか
陣中で飯炊きの煙を上げてしまい
滝川軍はそのスキをついて攻撃を仕掛けます。
これが秀吉のひんしゅくを買ってしまいます。
吉兵衛は、たきのことで心にスキが生じ
陣中に乱れを呼んでしまったと己を責めます。
一豊も秀吉からの叱責を受け、少々ヘコんでおります。
でも、主君のために命を捨てて働く家臣たちには
こういう言葉がほしいもの、と吉兵衛は進言します。
わしこそそちに死に遅れはせぬわ。
わしとそちは主従ではあるが、しかし幼き頃からの親代わり。
ようここまで育ててくれた。
明日の合戦は我が武門興るか興らぬかの瀬戸際、
いわば……『功名が辻』である。
わしがRば、供養を頼む。
が、そちがRば供養し子々孫々重用し、
そちの働きに報いようぞ」
城壁の足場が出来上がり、よじ登っていこうとしますが
敵方に見つかり、矢や石を降らせて進むことができません。
吉兵衛は「ここが功名が辻じゃ!」と味方を鼓舞し
気合いで石垣を登っていきます。
陣中に乱れを呼び、
秀吉にひんしゅくを買った汚名をそそごうと
功名を焦っていたのかもしれません。
登りきった吉兵衛は、砦の屋根に槍を突き刺し、
その槍に巻き付けておいた山内の紋を下ろすことで
一番乗りの声を上げます。
すでに敵と斬り結ぶ吉兵衛の身が危ないです。
一豊も新右衛門も吉兵衛救出に向かいますが
何ぶん敵兵が多すぎて思うように動けません。
振りかざす刀が折れ、それでも応戦していましたが
ついに敵兵に囲まれた吉兵衛は串刺しにされます。
一豊は、前日に吉兵衛に教わった通りに
「天晴れ!」と吉兵衛の忠義を褒め讃えますが、
一国一城の主に……。
吉兵衛はつぶやき、にっこり微笑んで
一豊の胸で絶命します。
山内家に戻っていたたきは、
吉兵衛が戦死したことを知ります。
吉兵衛の亡きがらの懐から、たき宛の文が出てきて
千代はだまってそれをたきに手渡します。
千代は吉兵衛の名を連呼し、たきは泣き崩れます。
──────────
天正11(1583)年3月3日、
五藤吉兵衛が伊勢亀山城の戦いで城内一番乗りをし、討死。
三成が大谷吉継に協力を求める前の7月1日、秀家が豊国社で出陣式を早くも行っていることをその根拠とする。
なお、この出陣式に高台院(ねね)は側近の東殿局(大谷吉継の母)を代理として出席させており、ともに戦勝祈願を行っている。
これにより、高台院が東軍支持だったという俗説には疑問が提示されている。
「北政所周辺に西軍関係者が多い」
三成の娘(辰姫)が養女になっている
側近の東殿は大谷吉継の母である
一説には小西行長の母ワクサ(洗礼名:マグダレーナ)も側近である
「西軍寄りと見られる行動を取っている」
側近の孝蔵主が大津城開城の交渉にあたっている
甥である木下家の兄弟(小早川秀秋の兄弟)の多くが西軍として参加し領地を没収されている
「東軍諸将との関係が薄い」
『梵舜日記』(『舜旧記』)に高台院の大坂退去から関ヶ原の戦いの数年後まで高台院と福島正則らが面会したという記録が無い。
五藤吉兵衛が壮絶な討ち死にを遂げ、
彼の思い人であったたきは暇をもらい
山内家を離れることになりました。
千代は、吉兵衛が山内一豊のために死んだわけで
その妻として何度もたきに詫びますが、
たきは「このお屋敷で夢を見ることができました」と
静かに去ってゆきます。
たきの後ろ姿を見送る千代の顔に、笑顔はありませんでした。
一豊は、吉兵衛の遺髪を握りしめ
在りし日の姿を思い出しているようです。
二十年以上も前から
吉兵衛とともに一豊を支えた祖父江新右衛門も、
「あやつは果報者」と穏やかな表情で語りますが、
その子・祖父江新一郎は肩を揺らして泣いています。
咎めるつもりはさらさらないのですが、
新右衛門をなだめるつもりで振り返れば
もらい泣きしたか、新右衛門まで肩を揺らしています。
ある日、妙な男が山内家へ──。
千代の「よく訪ねてくれました」との言葉に
お久しゅうございます、と頭を下げているところを見ると
千代とは初対面ではないようです。
(でも、ドラマ初登場です)
この妙な男、討ち死にした五藤吉兵衛の弟で
五藤吉蔵と言います。
兄の死を期に、尾張黒田からやってきました。
もし自分の身に何かがあればたきのことを頼む、と
兄・吉兵衛の生前の便りにあり、
吉蔵は宇治の里に出向いたそうですが、
たきは自害して果てておりました。
たきは吉兵衛の形見を羽織り、
そしてその傍らには吉兵衛からの文がありました。
千代を励ますつもりで言葉をかけますが、
千代は、半ば強引にでも たきを
この館に置いておくべきだったと深く後悔します。
越前・北ノ庄城では
降り積もる雪を見て柴田勝家が焦りを見せ始めます。
勝家側の人間としていた滝川一益は羽柴秀吉にやられ、
養子の柴田勝豊も秀吉側へ寝返っているのです。
一方、近江・佐和山城では
そんな勝家の動きを収集しておりまして、
秀吉は勝家に対抗すべく出陣することにします。
やがて雪が解け。
両軍の睨み合いが続きます。
先に動いた方が負ける、と
秀吉も勝家も考えているからでしょう。
石田三成は、織田信孝を攻撃するために
陣を離れることを進言します。
秀吉が本陣に不在と知った勝家が
羽柴軍をつぶすべく動き出したのを確認して、
大返しをするという戦法です。
秀吉に指示を仰いだ一豊は
「んまぁ……わしについてまいれ」と
いてもいなくてもいいような扱いを受け、
三成には鼻で笑われたような感じで
あまり面白くありません。
さっそく陣を離れた秀吉のスキをついて
勝家軍の佐久間盛政が羽柴軍の砦を落とすことを提案しますが
動かぬことにこだわった勝家は賛同しません。
盛政は「大将不在の陣を叩くは、卵を割るよりも易し」と
勝家の決断を無視して羽柴軍攻撃へ。
それを聞いた秀吉は、
予定通りに大返しをすることにします。
賎ヶ岳に陣取った秀吉は勝家軍を叩き潰します。
勝家は命からがら北ノ庄城へ戻ってきます。
じき、秀吉軍が城を囲むでしょう。
勝家は市に、娘たちとともに
城を出て落ち延びるように命じますが、
市にその気はありません。
秀吉は北ノ庄城へ酒を届けさせ、
最後の宴を開かせます。
秀吉から市を救い出すように任務を命じられた一豊は
その宴の最中に市と面会、説得に当たりますが
結局、市は首を縦に振りませんでした。
城から落ち延びたのは、茶々・初・小督の3人の娘です。
秀吉は懐かしいと馴れ馴れしく近づきますが、
茶々の凛とした声で一喝されます。
「寄るな! 汚らわしい」
そこには無数の火薬があるわけですが、
勝家と市の遺骸を秀吉の手に渡さぬためであります。
その爆発の様子を秀吉の陣中から眺めていた茶々は
母・市と義父・勝家の辞世の句を詠み上げます。
さらぬだに うちぬるほどの
夏の夜の 別れを誘う
ほととぎすかな 市
夏の夜の 夢路はかなき
跡の名を 雲井にあげよ
山ほととぎす 勝家
茶々は母の形見である櫛を千代に差し出しますが、
同時に茶々は、千代に「手を貸せ」と言います。
秀吉の野望を打ち砕くため、だそうです。
とはいえ、千代にとって秀吉は夫の主君であり
茶々が望むような動きはできそうにありません。
すると茶々は、手のひらを返すように
千代を清洲から追い出してしまいます。
茶々との出会いが、千代の心をざわつかせていました。
──────────
天正11(1583)年4月24日、
賎ヶ岳の戦いで敗北した柴田勝家が
越前北ノ庄城で、妻・市とともに自刃して果てる。
一豊の腹に貫禄がついてきました。
それを千代が指摘すると、一豊はポンポンと腹を叩き
「もうすぐ城持ちじゃ」と笑顔です。
今回の亀山城攻めでは
家臣の五藤吉兵衛が一命をかけて一番乗りを果たし、
賎ヶ岳の戦いでは市の娘たちを救出したのは一豊です。
今考えれば、城持ち大名は一豊だけではなく
吉兵衛の夢でもありましたので、
吉兵衛に見せてあげたかったというのが心残りです。
一豊はさほど期待はしていないそぶりを見せますが
「城は……どこかのう?」と千代に聞いたりして
心の底ではどういう恩賞を賜るか、今からワクワクです。
天正11(1583)年6月5日。
近江坂本城で、賎ヶ岳合戦の論功行賞が行われました。
加藤清正・福島正則・片桐且元・脇坂安治ら
いわゆる“賎ヶ岳七本槍”のメンバーと、石田三成は
そろって3,000石に加増。
その中でも正則には働きがあったということで5,000石に加増。
これには一豊のみならず、七本槍メンバーも仰天です。
堀尾吉晴には17,000石に加増、若狭高浜城主となります。
そして、一豊には──。
わずか300石を加増、3,800石取りとなります。
これで、正則よりも格下ということになりました。
あまりの仕打ちに、固まってしまう一豊です。
「猪右衛門?」と吉晴は一豊を励まそうとしますが、
かつて一豊が出世頭だった時の自分たちの不甲斐なさを
イヤというほど味わっていただけに、
今日のところはそっとしておいてやれ、と言い置きます。
山内家へ戻った一豊の、意外にも苛ついた様子を見て
城持ち大名になれなかったのだな、と千代は推し量ります。
「徳川様に仕えるか」「浪人がよいか」と口走る一豊を
千代は豪快にガハハと笑い飛ばして
「お酒でしたわね」とわざと明るく振る舞います。
どういう言葉をかけてもらいたいのでしょうね。
とにかく、今の一豊には、どんな言葉をかけても
苛つきは取れそうにありません。
浪人になるなら、いっそ武士をやめて
草花をとり、商いをし、一豊とふたりで
ほそぼそと暮らしていきたいなどと千代は語ります。
ただ、一豊の夢が一国一城の主であることを結婚初夜に聞いて
妻である自分も同じ夢を追わなければと考えた千代は、
ことあるごとに“一国一城”“一国一城”と
一豊にプレッシャーをかけ続けてきた、その結末が
今の一豊の姿を生んだのだ、と千代は涙ながらに詫びます。
翌日から、一豊は出社拒否……もとい、登城拒否をします。
家で縄を結い、般若心境を写してみたりしますが
性根が拗ねているからか、何事もうまくいかず
余計にイライラが募ります。
そんな一豊の姿を、千代のみならず
愛娘のよねも心配そうに見守っています。
法秀にお知恵を拝借しようと、近江国の法秀尼の庵に出向きます。
一部始終を聞いた法秀は「いい歳をして」と息子にあきれ顔です。
若いながら、千代は出家まで考えているようで、
法秀は、自ら山崎に行って一豊に真意を聞き出すことにします。
今回の論功行賞で、不満の声がポツリポツリと出始めています。
特に清正は、七本槍のメンバーの中では
一番先に敵陣に突っ込んでいったはずだと主張していますが、
秀吉は黒田官兵衛に「棄て置け」と命じます。
それよりも、気になるのは一豊です。
特に不平不満の声が上がってきてはいませんが、
同期の一氏や吉晴と比較して300石のみの加増というのは
とてもとても少なすぎると、官兵衛から見ても思います。
秀吉は、家臣たちを試しているのだそうです。
恩賞の大きさだけでついてくる者、
秀吉を主君として仰ぎ 働く者。
これから先の大きな戦を前にして、
本当の家臣は誰かを見極めたいという気持ちがあるようです。
千代は突然「出家したい」と言い出します。
よねは、かわいそうですが尼寺へ送るつもりです。
そして、当然ながら一豊とは離別します。
そんな時、法秀が訪ねてきました。
今までの戦場で、多くの命を手にかけてきた一豊が
出家するというのはいい心がけであります。
法秀は千代に、剃髪の準備として
湯を持って来るように言いつけます。
途端に慌て出す一豊。
法秀が剃髪前の説法は必要ないと言うので
代わりに一豊が「それがしの話を聞いてくだされ」と頼みます。
一豊は、今まで秀吉の手足となって懸命に働いたからこそ
今の立派な秀吉の姿があるわけで、その自負があります。
しかし、新参者はいきなり3,000石で、
23年に渡って勤め上げてきた一豊が
わずかに3,800石というのは解せないし、あんまりです。
ただ、そういうことを秀吉には言っていません。
自分の恩賞が手薄である理由は、御法度ゆえに
直談判して聞いてはいないわけです。
「何か訳があるかと思えば……ただの愚痴か?」と
プリプリと腹を立てる一豊にあっさりと言ってのけます。
まさか愚痴の一言で済まされるとは思っていなかったためか
一豊にはさらに火に油を注ぐような結果になってしまいますが、
かつて、一豊の父(法秀の夫)である山内盛豊が
岩倉城で自害して果てた時の刀を取り出し、
一豊にこれで解脱するように言います。
母として、引導を渡そうとするのですが
千代がそれを強引に止めさせようとします。
ただ、そんなことでは決して止めない法秀。
千代は、もし一豊があの世へ逝くのなら
自分が先に逝ってお迎えする、と言って
カミソリを首に当てます。
親と子でもみ合いになりますが
千代の気持ちも法秀の教えもよく分かった、と
一豊が止めさせます。
「前を向いて、己の心と闘っていくしかないのです」
法秀は、一豊と千代の手を重ね合わせます。
──────────
天正11(1583)年6月5日、
賎ヶ岳の戦いの論功行賞が近江坂本城で行われる。
大坂城の築城を開始します。
姫路城へご機嫌伺いに赴いた千代は
秀吉に「一豊はくさっておろうのう」と言われ、
殿へのご恩、一日たりとも忘れたことはございません、と
模範解答的な返答で、秀吉や寧々を笑わせます。
その帰り、千代は廊下で若い武将とすれ違ったのですが、
千代の顔を覚えていたか、その武将は振り返り再会を喜びます。
かつて、調略のために養子に出されていた治兵衛であります。
千代の元を離れてから、治兵衛はあちこちに養子に出され
政略の嫁取りをさせられ、半ばうんざり気味の治兵衛です。
治兵衛、羽柴秀次であります。
翌 天正12(1584)年正月。
安土城で、織田家の後を継ぐ三法師の年賀挨拶が行われます。
しかし、織田の家臣たちはその後、
織田信雄への挨拶に出向いているそうです。
織田の家臣たちが挨拶にきてくれる中、秀吉だけが来ないとなれば
秀吉を畏れるようになり、家臣たちとともに徳川家康に加担する。
そうなれば、秀吉にとって信雄を討つ口実ができる……。
秀吉にとって、織田家はもはや無用のものであり
信雄が家康と手を組めば徳川を滅ぼすこともできるわけで、
一石二鳥なわけです。
一豊は、日本一律儀な家康が
秀吉と戦をする訳はないと考えていますが、
一氏や堀尾吉晴は「甘いのう」と言って
砂糖菓子をポリポリかじります。
千代も一氏らと同じことを思っていました。
ただ、一豊は政治的な考えを得意げに語る千代があまり好きではなく
ついつい夫婦喧嘩になってしまう訳ですが、
それを廊下で聞いていたよねは、
父が今度いつ戦に出て行くか分からない今、
一緒にいる間は「ケンカはおやめくださりませ」と
今にも泣きそうな顔です。
一豊は愛娘には甘いらしく、よねと千代に素直に謝ります。
という位を秀吉は家康に与え、それでも応じなければ
「従三位参議」(じゅさんみさんぎ)という
秀吉よりも高い位を与えます。
自分よりも高い位を与えれば
家康はお礼として動かざるを得ません。
そう見込んだはずでしたが、それでも家康は動きません。
礼状一つで事をすませ、決して頭を下げようとしないわけです。
そんな家康を、信雄が訪ねてきます。
信雄は秀吉憎しで固まっておりまして
家康が味方してくれれば勇気100倍です。
自分と同じように秀吉を憎いと考えている諸侯は
他にもたくさんいるはずで、
家康は、その武将たちの調略一切をすべて信雄に任せます。
ただ、信雄が帰った後
家康は信雄を「まことのうつけであるな」と評し
家臣たちと一緒に大笑いしています。
とはいえ、25,000の兵を持っている信雄はあなどれません。
徳川軍34,000と合わせれば、戦いようがあります。
両雄激突、小牧・長久手の戦いであります。
とはいえ、両軍はしばらく睨み合いが続きます。
「中入り」という、
戦場とはほど遠い相手方の本拠地を攻撃することで
相手を強引に動かそうとする戦法を主張する秀次ですが
それは賎ヶ岳の戦いの折にも
柴田勝家軍の佐久間盛重が立てた戦法でして、
その結果、柴田軍は敗北したのでした。
秀吉も、先に動いたら負けると考えていながら
今回は秀次の熱意に負けてやらせてみます。
しかし、家康による徹底した情報戦で
秀吉軍の中入り戦法もたちまち知るところとなっています。
「奇襲には奇襲を持って征す」と秀次軍に攻撃を仕掛けます。
秀次軍、総崩れ──。
秀吉は、帰陣した秀次に罵詈雑言の言葉を浴びせます。
陣が同じだった一豊は、叩き斬ろうとする秀吉から秀次を守り
秀吉に対して詫びの言葉を入れさせます。
秀吉による信雄調略が功を奏し、和睦に至ります。
結局、家康が戦をしたのは無駄骨ということになり、
「私はいったい何だったのでしょう」と(笑)。
7月、関白職に就いた秀吉は一豊を大坂城に召し出します。
子のない秀吉の跡取りとして
秀次は大事に育てていきたいところです。
そんな秀次を身をもって守り抜いた一豊の肩に
秀吉はポンと手をかけ……。
屋敷へ戻った一豊は、ほとんど放心状態です。
その異変にいち早く気づく千代ですが、
一豊の口から出たのは、意外な一言でした。
一気に20,000石に加増、これで城持ち大名です。
あまりに急なことで、千代はにわかには呑み込めません。
それが夢ではなくホントのことだと分かった時、
愛娘の前で抱き合って大喜びする千代と一豊でした。
──────────
天正12(1584)年4月9日
長久手の戦いで羽柴秀吉と徳川家康が戦う。
羽柴秀吉は関白となり、重臣の山内一豊も
長浜2万石の城主となっております。
そのお方さまとして廊下をしずしずと進む千代ですが、
着物が小袖から立派な仕立てのものに変わっていて
“2万石の城主の妻”らしくなってきました。
大広間では、一豊が家臣一同に
「皆のおかげじゃ」と声をかけます。
そして、吉兵衛の遺志を継ぐべく、その弟の五藤吉蔵が
新たに山内家重臣に加わることになりました。
千代は翌朝、一豊の母・法秀を迎えに庵へ行きますが、
法秀に同居の意思はありません。
ただ、一豊が一国一城の主となった今
気がかりなのは弟・山内康豊のことであります。
ただ、康豊は法秀にたびたび手紙を送っていて
浪々の身ながら、とりあえずは生きているそうです。
その宿老として、一豊・堀尾吉晴・中村一氏がつけられます。
一豊にとっては
秀次がまだ幼い頃に少しだけお世話したことがあり、
とても賢い頭脳の持ち主だと舌を巻いたものでしたが、
「なにゆえウツケになってしもうたのかの」と
秀吉は眉すら動かさず、ボソリとつぶやきます。
突然、康豊が長浜城を訪ねてきました。
一豊の身内だと主張してもなかなか信じてもらえず
捕らえられて千代の前に連れて来られたのですが、
千代が「康豊さま!?」と声を上げた瞬間、
主君の弟君 と家臣たちは驚愕する有様です。
康豊は、一豊と離ればなれになってからのことを
千代に語り聞かせます。
康豊は織田信忠の元にいて
本能寺の騒動に巻き込まれてしまいます。
その後、諸国をうろうろしていましたが、
あるとき足を踏み外し、崖から滑り落ちてしまいました。
丹後に送られていた妻の玉であります。
玉は人妻ながら、康豊の面倒を見てくれ
その大きな傷もみるみる癒えていきました。
「まだまだやり直せる道はある。素直に生きてみたら」と諭され、
一豊にすがってみようかと思い、長浜へ来たのだそうです。
法秀も一豊も、歓喜して康豊を迎えます。
康豊は玉の言葉を胸に、
山内家重臣として活躍することになります。
そして、玉も秀吉の計らいで謹慎を解かれ
宮津城へ戻っていきました。
秀吉の女狂いが始まったようです。
実は、越前北ノ庄城から救出された茶々を迎えた際
「寄るな! けがらわしい」と怒鳴られてから
茶々にゾッコンの秀吉は、
建築したばかりの大坂城の
金銀を散りばめた贅を極めた一室を茶々に与えます。
関白秀吉に取り立てられたとかで、
大蔵卿はそのお礼言上に茶々を訪問しますが、
お顔立ちは悪うござりまするが、お心は細やかで──と
秀吉を持ち上げた途端、茶々は顔色一つ変えずに言ってのけます。
「そちもサルの手に落ちたか」
秀吉が自分に近づくのは時間の問題、と
三成を呼びつけた茶々は
秀吉のお手がつく前に自分を奪ってほしいと三成に命じます。
秀吉は、佐々成政が出た後の
富山城受け取りに多数の兵を送り込みます。
そこで一豊に兵糧と宿割りを命じるのですが、
飯をどんどん炊いたおかげで、米蔵はすっからかんに。
呆気にとられる一豊に
「当分 戦はございませぬ。国主さま♪」とからかう千代とよね。
平和な時が過ぎていくかに見えました。
かわいらしく成長するよねは
松葉と木の葉で虫かごを作り、
その中にコオロギを捕まえて飼うつもりのようです。
山内康豊に、コオロギを捕まえたらかわいそうだと言われて
困惑顔のよねですが、
木の葉を器用な手つきでコオロギに作り替え
駕篭の中に入れてあげると、途端に表情が明るくなります。
どうやら、よねは康豊のことが好きになったようです。
「大きくなったら、叔父上の妻になりとうございます」と
千代の手を引き、コソッと告白するよねに
千代も幼い頃に一豊の妻になりたいと願ったことを話して
人に恋することは、心を豊かにすると諭します。
ただ、恋するメリットだけではなく
デメリットやリスクも合わせて話す千代は
いい母親かもしれませんね。
上洛を拒み続ける家康を説得するために
岡崎へ出向くように命じられます。
織田長益とともに岡崎へ乗り込んだ一豊ですが、
それでも説得に応じようとはしません。
それどころか「いつなりともお出ましあれ」と
ケンカを売る始末です。
天正13(1585)年11月29日──。
雷鳴轟き、鳥が泣きわめきながら方々へ飛び回っています。
黒い海が波立ち、不吉な印象の夜です。
よねはそんな夜がとても恐ろしく感じたらしく
城内見廻り中の千代の元に駆け寄ります。
千代は、見廻りが終わったら よねの枕元で
お伽草紙を読んであげましょう、と約束しますが
よねとしては、片時も離れたくありません。
火の用心の見廻りは、遊びではないのです。
少し厳しい声で言って、見廻りを続ける千代を
寂しそうに見送るよねでした。
千代が何かを感じて歩を止めると、
地鳴りがして、大きく揺れ始めます。
瓦が何十、何百枚と割れて落下します。
襖も次々に倒れてきます。
大きな揺れの中、千代は
ひとり戻っていったよねの名を叫びますが
その声もむなしく、崩れ落ちた天井の下敷きに──。
気を失っていた千代は、目を覚ますと
夢中になってよねを探します。
家臣たち、侍女たちも総出でがれきをかき分け
がれきの山からよねが見つかりますが、
よねは乳母に抱きかかえられたまますでに息なく。
「昨夜近江で大地震あり、よね姫さま、ご落命──」
馬上の一豊は、近江長浜からの急報を聞き
長益と康豊に後を任せて、自身は長浜へ急ぎます。
私が代わってやれば……と声を振り絞って泣きます。
よねを胸に抱き、千代は錯乱しています。
あの時、よねの言うように一緒に見廻りをしていたら。
よねをひとり残さずにそばにいさせていたなら。
こういったことにはならなかったはず……。
急ぎ帰城した一豊の顔を見て、
さらに声を上げて泣きわめきます。
一豊はよねの顔をそっと見ます。
今にも起き上がりそうな、
実に安らかな表情です。
大名になるという幸せの代わりに
天は我らからよねを奪ったのかの──。
一豊は低い声でうなります。
よねの葬儀が終わり。
長浜城修復のためにいったん京へ移り住んだ夫婦。
狂うほどに泣いた夫婦も徐々に落ち着きを取り戻しますが、
他人の子どもを見ると、やはりよねのことが思い出されて
胸が締め付けられるほどに痛みます。
よねと同じぐらいの年格好の娘に
よねのために仕立てたパッチワーク小袖を
プレゼントします。
そんな出来事があって、
この世の悲しみをどこにすがっていいか分からない千代は
南蛮寺へ引かれるように訪れてみます。
そこで玉と久々に再会するのですが、
玉は「力強く生きて参りましょう」と
愛娘を亡くしたばかりの千代を励まします。
──────────
天正13(1585)年11月29日
天正の大地震で長浜城が全壊し、
山内一豊の娘・よねらが遭難死。
一粒だね・よね姫を失った山内一豊と千代夫妻。
気落ちする千代を心配して、寧々がお見舞いに訪れますが
いつまでもくよくよしていては家臣たちに示しがつかない、と
千代は気持ちを奮い立たせています。
そして二人の話は、関白となった秀吉の内容へ。
表向きは平静を装っていながら、
水面下では敵対している徳川家康を懐柔するために
秀吉は、妹の旭を 「家康の正室」という名の人質として
送り込むことにします。
旭は、最初の夫であった源助とは
長篠合戦の柵作りに参加したことがきっかけで死別し、
次に嫁いだ副田甚兵衛と大坂城下でのんびりと暮らしています。
秀吉や寧々としては、
そんな旭を説得してほしいと千代に相談しにきたわけですが、
千代は、旭と甚兵衛のふたりを守りたいと強く思っています。
甚兵衛との仲を壊さぬためには、旭に長浜で身を隠してもらい
時間稼ぎするよりほかにはなさそうです。
しかし、時を同じくして秀吉から登城の命令が旭へ──。
「おらのために死んではならん」
旭は、自分を匿ったことで千代にお咎めが及ぶことを畏れ
登城する決意を固めます。
旭よりも先に大坂へ登城していた甚兵衛ですが、
秀吉は甚兵衛を5万石の大名にする代わりに
旭と離縁せよ、と迫ります。
「女房を5万石で売れと?」と反発する甚兵衛に
旭はすでに承知した話だと冷たく突き放します。
一方、図らずも甚兵衛を追いかける形になった旭には
寧々が同様の話をしています。
甚兵衛はすでに承知した話だと冷たく突き放します。
関白の妹はいらぬ、
賢妻と名高い千代が欲しい、と関白にご相談願いたい。
そう家康に言われ、一豊は言葉に窮します。
そんな生真面目すぎる一豊を見て、
家康はプッと吹き出します。
ただ、考えてみればそうですよね。
他人事だから「天下安寧のため」と言えるわけで
自分の妻を差し出せ、と言われては事情が異なります。
一豊は果たして、そこまで考えていたのか?
非常に疑問です。
一豊がいったん下がった後、家康は家臣たちと密談です。
「43……しじゅうさーん」と、家康は天を仰ぎながら
何度も何度も旭の年齢をつぶやいています。
旭にとって3度目の花嫁となる日、
旭は千代に甚兵衛宛の文を託します。
天正14(1586)年5月14日、ついに浜松着。
物珍しそうに一行を見守る町衆の中に、
複雑な面持ちで旭が乗った駕篭を見る
甚兵衛の姿がありました。
出迎えた家康は「仲良くしましょうぞ」と言って
旭をホッと安堵させますが、
もともとの目的であった、家康の上洛作戦は
この秀吉の懐柔策も失敗します。
秀吉は、寧々の顔を見て目を細めます。
「ま……まさかわたくしが!?」と寧々がのけぞった瞬間、
母のなかが、自らが人質になると名乗りを上げます。
思わぬ所からの援軍に、秀吉は大喜びです。
家康と旭のもとになかが到着したこともあって、
ついに家康が折れました。
10月26日、1万の軍勢を率いて
大坂・羽柴秀長の屋敷に入ります。
そこへ秀吉が飛び込んできます。
秀吉とは、長篠の戦いで直接会ってから
実に11年ぶりの再会となります。
秀吉は、翌日の対面の儀では
体裁上ふんぞり返った態度をとるが
どうかお気を悪くなさらず──と気を遣います。
その上で、気持ちは別でもいいので
諸大名の面々の前で自分に手をついて
頭を下げてほしい、と言うのです。
家康は、秀吉に充分理解を示します。
対面の儀では、すべて秀吉の
シナリオ通りに進んでおりましたが……、
家康は、アドリブで秀吉に返します。
「そのお召しの陣羽織、頂戴仕りとう存じまする」
それぞれの目から火花が散っていきますが、
家康のプレゼンが、いかにも家康らしいです。
我らが殿下のお側に侍りましたる上は
もはや陣羽織甲冑などご無用──。
秀吉は肝を冷やしながら、
しかし気持ちよく陣羽織を家康にかけてあげます。
──────────
天正14(1586)年10月27日
大坂城において徳川家康が豊臣秀吉に謁見し、
諸大名の前で臣従を誓う。
花燃ゆ、江とはえらい違いじゃのう。
豊臣秀吉は九州攻めのために大坂を出発しますが、
秀吉の重臣たる山内一豊は、
豊臣秀次の宿老として大坂留守居役であります。
それが不満なのだ、と弟の山内康豊は冷静に分析しますが、
康豊の主張は 一豊の気持ちをいちいち逆なでしていきます。
そんな兄弟を見て、千代は不安気です。
千代の話を聞いていた祖父江新右衛門は、
長浜の法秀尼に相談してみては? と
菓子をポリポリ食べながら言います。
千代としてはあまり心配をかけたくないのですが、
「心配するのも幸せなのです」と新右衛門に言われて
さっそく庵を訪ねてみます。
しかし、4〜5日前から法秀の体調が思わしくなく
床に臥せっていることを初めて知ります。
なんでも、一豊・康豊兄弟のことが気がかりで
お百度参りを雨の中に敢行したことが
体調悪化の原因だそうです。
千代は看病をすることにします。
堀尾吉晴や中村一氏、そして一豊・康豊と
町作りの談義をしています。
町作りにあたって、康豊は近江八幡の名物を作ることを提案。
おもしろい提案と笑いつつ、
秀次はそれを実行するように吉晴に指示します。
ただ、一豊は浮かぬ表情です。
急報を受け、一豊と康豊兄弟、そして新右衛門が
法秀尼の庵に急ぎます。
しかし、そこには母の亡きがらが。
「一豊、康豊、お互いの異なる性分を尊びなされよ。
考えの違うということは、実は素晴らしいことなのです。
山内家が間違った道を歩まぬよう、互いの意見を戦わせよ。
互いに学び合うことを忘れてはなりませぬ」
一豊は、康豊の意見を聞かなかったのは
自分の不徳だと反省します。
康豊も兄と同様に反省していますが、それよりも
兄弟のことを見通していた母の素晴らしさを
亡くしてみて初めて気づきます。
法秀に教えられ育てられた日日のことです。
「たくさん泣いてたんと食べるのじゃ」
「そなたが一豊の嫁になってくれたらと、
初めて会うた時から思っていました。
よう来てくれましたね、一豊のところに」
千代に看取られて、母上はさぞ幸せであったろう。
ありがたく思うぞ──。
一豊は、今までの千代の苦労をねぎらいます。
8月、九州平定を成した秀吉は大坂へ戻りますが、
ただ、キリシタンというものに畏れを抱いての帰還であります。
秀吉は即座に伴天連追放令を出しますが、
康豊は複雑な表情を浮かべています。
母の遺言のこともあり、康豊を山内家で重用するためには
康豊の嫁取りの話を進めていきたいところです。
本人の意思を確認する一豊ですが、
康豊の「はあ」という気のない返事では 少々気がかりです。
康豊としては手痛い一言であります。
そう、康豊は いつか自分を助けてくれた
細川忠興の妻・玉が好きなのです。
玉は洗礼を受けてガラシャとなっていますが、
秀吉の伴天連追放令は
ガラシャの生きる道を徐々に狭めていきます。
想ひ寝の 心御津に
通ふらむ 今宵逢ひみる
手まくらの夢
秀吉が茶々の寝所へ行くと言い出します。
「サルがいよいよ天下を獲りにきた」
それを知った茶々は石田三成を呼び出すわけですが、
茶々が言う“天下”とは、まさか自分自身のことだとは(^ ^;;)
動揺し、迷う茶々に、三成は
栄達のためには秀吉の想い人になるように勧めます。
茶々は何度も何度も三成に確認しますが、
茶々としては、秀吉から自分を奪ってほしいとさえ
思っているように見えます。
あすよりは 若菜摘まむと
しめし野に 昨日も今日も
雪は振りつつ
母・市から教わった歌を秀吉に披露し
最後の抵抗をする茶々ですが──。
翌朝。
山内屋敷の門を開けると、門の前には
生まれたばかりの赤子が棄てられていました。
「法秀さまのお導きかもしれぬ」
ひとまず、山内家で預かることにします。
──────────
天正15(1587)年6月19日
キリスト教宣教と南蛮貿易に関して
豊臣秀吉が禁制の文書を発令する。
屋敷の前に棄てられていた赤子を引き取り、
千代が養育しています。
愛娘・よねと、最愛の母・法秀を相次いで亡くし、
気力を奮い立たせて生きてきた千代は、
棄て児の養育で心の底から笑えるようになっています。
祖父江新右衛門は棄て児の養育には大反対ですが、
千代は特に意に介しておりません。
乳は、子をたくさん産んでいる祖父江新一郎の妻から
もらおうか、などと悠長に話をしています。
寧々は、「豊臣のため」と
早く子を産むように言葉をかけますが、
あくまでも茶々を“妾”として扱い、
秀吉の正妻としての自分との差をハッキリと示しておきます。
「上様の子を身ごもってこそ、初めて豊臣の女」と
茶々は子のない寧々に皮肉たっぷり。
寧々は冷静さを装いながらも、茶々のひとことが悔しくて
腹煮えくり返る思いで出て行きます。
石田三成と小西行長が加わってしばし歓談しています。
その帰り、京の町では
千代が拾った棄て児のことで話題騒然であります。
一豊は、世話をするのはいいが家督は継がせぬと
千代に言い聞かせますが、
今、この赤子が必要なのは生き延びること、と
千代は家督云々より世話が大事だと答えます。
ただ、今の一豊にとっては、棄て児のことよりも
聚楽第に天皇を招くお世話役を
仰せつかったことの方が一大事なのであります。
苦手な石田三成とともに事にあたることになりました。
一豊は蹴鞠の特訓をし、器の勉強をして努力しますが
千代からのアドバイスに従って
三成に教えを請おうと頭を下げます。
4月14日、5日間の日程で ついに天皇行幸が始まります。
臣下の邸宅に天皇が訪問するのは150年ぶりのことであります。
一豊はずる休みしますが(笑)、
ずる休みがバレた時はどんなお咎めがくだされるか……という
千代の言葉を聞いて、思い直して出席することにします。
ただこれは、各方面に暗い影を落としていきます。
寧々は「子を産めなかった自分が悪い」と己を責め続け、
糟糠の妻・寧々をどうすることもできないなかは泣き崩れ、
秀吉の後継者と目されていた秀次は、
今後の自分の行く末を不安視し出します。
吉晴の提案で、一豊を伴って
若君誕生のお祝いに真っ先に駆けつけることになりました。
その席上、秀吉は秀次の祝賀にウンウンと頷いておりますが、
秀吉は突然、秀次と一豊に問いかけます。
「このわしが亡き後、天下を誰が獲るか……言うてみ」
二人とも答えに窮しますが、
秀吉が考える人物は黒田官兵衛であります。
ちょうどその時、官兵衛は隠居願いを出すわけですが、
嫡男・黒田長政に家督を譲ることは認めたものの
秀吉は官兵衛の隠居だけは認めません。
官兵衛の力を削ぎ落とすためです。
隠居して、嫡男とともに反乱でもあげられたら
たまったものではありません。
そこで針商人とすれ違うのですが、
あの横顔は、紛れもなく副田甚兵衛であります。
──────────
天正16(1588)年4月14日
聚楽第に後陽成天皇が行幸。
すれ違った針商人が紛れもなく副田甚兵衛と気づいた千代。
甚兵衛が針の商いを始めた間に屋敷に立ち返り
旭に託された手紙を持ってきます。
甚兵衛は千代の姿を見て、一瞬たじろぎます。
旭は今、徳川家から豊臣家へ戻り
病気療養中で床に臥せっているのです。
千代としては、その現状を知っていてほしいわけですが
「旭なんて知らねぇなぁ」ととぼけ、慌てて立ち去ります。
しかし、千代から受け取った旭の手紙を隠れて読み
居ても立ってもいられなくなった甚兵衛は
千代の仲介で旭と対面することができました。
とはいっても、あくまでも甚兵衛を知る針商人という立場で
甚兵衛から預かった文を読み上げるためだけの役目でありますが、
その針商人が甚兵衛本人であることは、
寧々だけでなく旭本人も気づきます。
数奇な運命に翻弄された女の、最期でした。
天正18(1590)年2月17日。
小田原北条攻めに向けて一豊軍も近江八幡城を出発します。
戦いの直前、徳川家康が豊臣秀吉を裏切って
北条方へ味方するかもしれない、とのウワサがありましたが
それもどうにか収まり、
いよいよ戦の総仕上げです。
山の上から小田原城を見下ろせる場所に家康とともに立った秀吉は
関東八州を与える代わりに東海五州を召し上げるという話をします。
井伊直政は秀吉を叩き斬る勢いでしたが、
家康はそんな仕打ちでも忍耐を貫きます。
そのうち北条は秀吉に白旗を揚げ
秀吉軍の勝利で戦の幕を閉じました。
ただ、中村一氏は駿府14万5,000石、
堀尾吉晴は浜松に12万石なので、
そこまで格別に多いというわけでは(^ ^;;)
家康が関東八州240万石ということは、
天下の英雄を手なずけて
関東という牢に押し込めたと見ることもでき、
それを見張る役目として、一氏・吉晴、
そして一豊が加増されたのかもしれません。
なかなか大変な役目になりそうです。
天正19(1591)年1月、秀吉の弟・豊臣秀長が病没し
2月には秀吉の怒りを買った千 利休が切腹。
そして8月には──。
秀吉と淀の子・鶴松が亡くなります。
──────────
天正19(1591)年8月5日
豊臣鶴松が大坂城で病没、享年3。
豊臣秀吉の子・鶴松がわずか3歳で夭折し、
秀吉に近い人物だけを集めて
その葬儀がしめやかに執り行われますが、
秀吉の嘆き悲しみはいかばかりか……。
秀吉は泣き叫び、勢いで髷を落としますが
賎ヶ岳七本槍のメンバーは、秀吉に倣って
次々に髷を落としていきます。
呆気にとられる寧々と淀。
一方で、顔を見合わせ
慌てて立ち上がる山内一豊と中村一氏であります。
大坂城に戻った寧々は千代によるお悔やみの言葉を受けますが、
鶴松亡き今、秀吉の後継車争いが再び起きることは必定です。
その争いに不安を隠せない千代ですが、
その発端は石田三成にあると考えている寧々は
豊臣秀次の宿老たる一豊に「くれぐれもよろしく」と伝えるよう
千代に言い置きます。
鶴松に毒を盛っていたのだと声高に叫んでいます。
それを聞いた、淀の乳母・大蔵卿局は
「また吾子をお産みあそばしませ」と
冷静に淀に進言します。
てんこ盛りされた武将たちの髷の山──。
秀吉は「忠義の証を見せたわ」と満足げです。
ということは、勢いで髷を落としたのは
秀吉なりのパフォーマンスであったわけですね。
その上で、秀吉は宣言します。
「大明国に討ち入る!」
肥前名護屋城を拠点に、明国討ち入りの計画を進める秀吉は、
寧々の進言もあり、12月に秀次に関白職を譲ります。
兵糧武具の備えを万全に、えこひいきなく公平に──。
朝廷とは懇ろにし、よくご奉公せよ──。
秀次に対する秀吉の心配事はまだまだたくさんありますが。
そして秀吉自らは「太閤」と名乗ることになりました。
秀吉は淀を伴って肥前名護屋城へ。
そして秀次とともに居残りとなった一豊は
領地である掛川城を山内康豊に託して
京・聚楽第で秀次に仕えることになります。
秀次は、肥前名護屋城へ向かう家康の挨拶を受けますが、
武門・学問の両モンが揃ってこそ王道が開ける、との家康の言葉に
大きく頷き、我が意を得たりと満足げの秀次です。
ただ、共に笑う家康の心中は……どうなんでしょうねぇ?
秀次は、関白になったのを期に
幼少の頃にお世話になったお礼も兼ねて
千代に源氏物語写本を進呈します。
先ほどの家康の言葉にもあった通り
世を治めていくためには学問も必要だと考える秀次は、
秀吉にはそこが足りないと露骨に太閤批判を始めます。
千代はすっかり困惑顔です。
そのころ、肥前名護屋城では
5月3日に朝鮮の都を陥落させたことで
飲めや歌えやの大騒ぎであります。
即刻、明国討ち入りを止めさせよというなかに
秀吉に変わって、寧々が秀吉の胸中を説明します。
鶴松が亡くなって明国討ち入りなど
太閤も気が狂ったかと民衆ではもっぱらのウワサですが、
実は天下を平定したことで戦をする必要がなくなり、
それが元で秀吉から諸大名たちの心が離れていくのが心配で
「ウチの人は、死ぬまで戦はやめませぬ」というわけです。
戦のない世が来てほしいと願い、ついに天下平定がなったのに
更に戦を求めていかざるを得ない現実は、実に皮肉なものです。
庭のなすびを眺めながら、なかが亡くなったのは
それから間もなくのことです。
秀吉は肥前名護屋城から駆けつけますが
残念ながら臨終には間にあわず。
山内屋敷に、久々の六平太の訪問です。
千代に会うのは10年ぶりですが、
その間、しばらくは毛利に身を寄せ
海の向こうの明国に渡っていたそうです。
朝鮮の都を陥落させ、日本軍が緒戦突破できたのは
明国側に戦う意志がなかったためであり、
向こうが本気になって戦えば、
日本軍の全兵力を結集したところでとても叶わない。
「お前の亭主は秀次番でホント運がよかったなぁ」
その六平太の言葉に、千代は動揺を隠せません。
気持ちが落ち気味だった秀吉を狂喜させたのは、
大坂からの、淀懐妊の報でした。
そして8月、淀が再び男の子を産みます。
秀次は秀吉にお祝いの言上を述べますが、
豊臣を継ぐ者のひとりとして──という言葉に
秀吉は「うん、まぁ……そう急がんでもええ」と
後継の話に関しては言葉を濁しています。
関白秀次の立場は、次第に悪化していきます。
──────────
文禄2(1593)年8月3日
豊臣秀頼(拾)が大坂城で誕生。
祖父江新右衛門もあっけなく倒されるほど強くなりました。
ただ、山内一豊も新右衛門も侍女たちも拾を甘やかす中で、
千代だけは厳しく育てているせいか
千代を“怖い母上”と思っているようで、
「汗でも拭ってきなされ」という言葉にも
忠実に従うのみであります。
新右衛門は、拾が聡明な男子として育っていることに目を細め、
それはそれでとても頼もしく、嬉しいことなのですが、
改めて千代に忠告しておきます。
「殿のお跡目を、あの若君になさりたいとお考えではありますまいな」
豊臣家では、鶴松が亡くなって
豊臣秀次を後継者として指名した後の男子出生。
拾の誕生を誰もが予想だにしなかっただけに、
これからは「秀次派」と「反秀次派」に分裂する可能性が大です。
そういったお家騒動の元凶を抱えてはならぬ、と
新右衛門としては言いたいわけです。
2人に仕えているような一豊がどちらに味方をするのか
家臣として、とても気になるところでもあります。
……あ、そういえば千代に拾われた子も「拾」で
秀吉に生まれたのも「拾」なので、分かりづらいですね(^ ^;;)
ちなみにドラマでのスーパーでは、
前者は「山内家 拾」、後者は「豊臣家 拾」となっていましたが。
秀吉は“豊臣家の跡継ぎとして”拾に
天下一の大坂城を与えることにしますが、
寧々と淀はそれぞれの観点から大反対です。
無論、寧々は「豊臣家の跡継ぎは秀次だ」とし、
淀は鶴松が大坂城に取り上げられ、
そして亡くなってしまったことを根に持っているせいか
「私も拾も淀城が気に入っておりまする」と
大坂ゆきを固辞するわけです。
秀吉は、拾には大坂城、秀次には聚楽第、
そして秀吉自身は、新たに伏見に築く城に入るつもりです。
千代は、伏見に城を築くということは
秀吉は秀次のことを邪魔に考えている
心の表れのではないかと分析します。
……と言っても、新右衛門の見立てのままなんですが(笑)。
その上で、一豊に
伏見に屋敷を移して秀吉に味方するのか
このまま京に屋敷を構えて秀次に味方するのかを
考えておかねばならないと進言します。
そんなころ、朝鮮出兵に借り出されていた
前野将右衛門が山内屋敷を訪問します。
秀吉が足軽の頃からそばで見て来た将右衛門は
もはや秀吉には戦で苦しむ民衆の姿が見えていないと
鬱憤が溜まっている様子です。
そんなこともあってか「もう疲れた」と
将右衛門は隠居をして
息子に家督を継がせることにします。
返答を求められた秀次は「若君が元服なさいましたら」と
やんわりと先延ばしを目論みますが、
拾が元服したころの秀吉の年齢を考えると、秀吉は大激怒。
秀次の宿老たる一豊、堀尾吉晴と中村一氏は、
いち早く拾に関白職を継がせたいという秀吉の魂胆が分かり
今後どうしていくかを話し合います。
ただ、事態は急展開。
秀次に仕える2世家臣たちが、世継ぎは秀次だと
今こそ知らしめるべしとけしかけます。
ただ、それにのせられた秀次の言動も
今の秀吉の火に油を注ぐだけの無駄なものです。
秀次は酒食におぼれます。
秀吉に対面を願い出た一豊と千代でしたが、
その代わりに応対した石田三成には
あまり秀次に肩入れすると
秀吉の不興を買うだけと忠告されます。
伏見城が完成し、諸大名が次々に京から伏見へ屋敷を移すと
秀次はますます孤立していきます。
それに合わせて、秀次家臣団たちも徐々に分裂していきます。
それに対して千代も寧々も手の打ちようがありません。
豊臣家を二分するという最悪の結果を招く前に
一豊は三成と話し合いの場を設けます。
三成は秀次が関白職を返上するしかないと突き放しますが
一豊としては納得できません。
小姓に支えられながら廊下を歩く秀吉に遭遇する一豊。
「ワシにつくか秀次につくか、よう考えよ」という
転んだ拍子に言った秀吉の言葉に、
一豊の表情はいっぺんに変わります。
ちなみに、秀次に関するそのウワサを
淀の乳母・大蔵卿局が流していることは
三成はとうに分かっています。
「慎まれよ」と言う三成に、大蔵卿局はすっとぼけます。
太閤秀吉を討つべし! という主戦論者は、
謀反を起こす血判状を持って
秀次を三成や淀から守ってみせる! と意気込みます。
もはや一豊や千代でも、その流れを止められません。
前野将右衛門が捕らえられたという情報をもたらします。
謀反を起こそうとしている将右衛門の息子の責めを
将右衛門が負った形です。
いわゆる連座制で捕らえられたわけです。
どうやら、その血判状を入手した一氏が 秀吉に申し出たそうです。
六平太は思い悩んだ末、ひとつのアドバイスを授けます。
「力の強いものには……従うしかあるまい」
秀吉は一氏に、秀次を伏見へ出頭させるように一豊に伝えさせます。
もし応じなければ、一豊もその謀反に加担したものとみなすと
秀吉にしては厳しい要求であります。
豊臣秀次謀反の申し開きを伏見でするように
豊臣秀吉に出頭を命じられ、
秀次とともに秀吉の元に向かう一豊。
「最期の見送りになるやもしれぬ」という一豊に
千代は精一杯の励ましで夫を送り出します。
秀次を出迎えるために聚楽第に立ち寄った一豊ですが、
秀次家臣団たちは、こんな窮地であっても二分したままです。
「愚か者の名を残すのが男か、謀反人の名を残すのが男か」と
秀次に迫る木村常陸介と 前野将右衛門の息子・前野景定ですが、
秀次は態度を決めかねています。
主戦論者たちに囲まれた中で、一豊は
秀吉への申し開きを説得します。
出頭についてはしぶしぶ承知した秀次ですが、
数日間の猶予をもらうという言い分に
「即刻の申し開きでなければ」と食い下がる一豊。
一豊と祖父江新一郎に斬り掛かろうとします。
寸でのところで秀次が止めますが、
自分が秀吉の操り人形であるとともに
家臣たちにも操られている
現状が許せないのかもしれません。
関白としての最後の務めとして、
一豊の主張に沿って
このまま伏見へ申し開きに向かうことにします。
秀吉と対面した秀次は関白職を返上することを宣言しますが、
その上で、朝鮮出兵の取りやめを太閤秀吉に具申します。
秀吉は一瞬だけ怒りをあらわにしますが、
秀次に高野山謹慎を命じ、出て行きます。
血の気が引いていく秀次です。
秀吉の身内でさえなければ、尾張中村の百姓の子として
何事もない生涯を送ったであろう秀次は
7月15日、高野山青巌寺・柳の間で切腹します。
淀による 秀吉の耳へのささやきで
目障りな聚楽第の取り壊しと、
聚楽第に住んだ者たちの処罰が決まりました。
京・三条河原刑場で、秀次の妻子39名が惨殺されます。
心にも あらぬうらみは
ぬれぎぬの つまゆゑかヽる
身と成りにけり
秀次側室のお宮は、捕縛・護送されながら
辞世の句を歌い上げます。
すくすく育つ(山内家の)拾を見て、
一豊は「ゆくゆくは山内家の跡取りに」と
考えるようになってきています。
それを聞いて、千代は素直に嬉しいです。
そのころ、京に滞在している一豊に変わって
領国の掛川で町づくりに精を出しているのが
弟・山内康豊であります。
領主代理ではありますが、
領民の評判はなかなか上々だそうで。
立てようとしているのではないかというウワサが
そんな康豊の耳に入ります。
「よいではないか」と大して気にも止めない康豊ですが、
それを報告しに来た祖父江新一郎はとても心配です。
新一郎としては、康豊の子・国松を
山内家の跡取りにしたい考えですが、
国松はわずか2歳であります。
伏見の家臣たちがみな、国松を擁立しようと考えているなら
それもあり得ると康豊は答えはしますが、
五藤吉蔵は、拾でもよいと考えているようで
統一された考えではないようです。
一豊はあくまで拾を世継ぎにしたいようです。
千代も、拾が世継ぎになってくれればと願っていますが、
それが元で山内家が分裂してしまうようでは元も子もありません。
一豊は拾を座敷に呼び出し、仏門に入るように言い渡します。
今までの戦いで、自分のために家臣のために敵兵を斬り倒してきた
その弔いのためです。
「私が寺へ送られるのは、棄て児だからでござりまするか」
あくまでも武士になることにこだわる拾の言葉が、
一豊・千代夫婦の胸をズンと貫きます。
──そうです。
千代のか細い返答を聞いた瞬間、
拾の大きな目から大粒の涙があふれていきます。
最後の最後まで抵抗していた拾ですが、
しかし、ついに「かしこまりました」と
両手をついて、頭を下げます。
粉雪が舞い散る日、拾は出立します。
「父上、母上、お世話になりました」
頭を下げ、父母の方を振り向かずに出発していきました。
拾の名を呼ぶ千代の声が、
渇ききった辺りに響き渡ります。
──────────
文禄4(1595)年7月15日
関白・豊臣秀次が高野山青巌寺で切腹、享年28。
豊臣秀吉は、わずか4歳の拾を元服させ、
名を「豊臣秀頼」と改めさせます。
秀吉自身、生い先短いことを悟っていたのかもしれません。
秀吉は、秀頼に背くものは天罰を被ると脅しますが、
徳川家康や前田利家は、そのお披露目の場にいる者たちの
表情を窺って何も言葉を発しません。
政局はすでに、秀吉没後のことに推移しているようです。
と、そこで秀吉が不覚にも失禁してしまいます。
その場に居並ぶ者たちは
秀吉の死がまさに近いと感じ取ったのかもしれません。
利家は「若君、なんとした粗相を……」と
とっさに秀頼のせいにして
言葉を失って立ち尽くす秀吉に着替えを勧めます。
千代は、山内一豊の頭に白髪が生えてきたのを見て
お互いに年を取ったと感じています。
山内家は磐石にしておかねばならない。
そう主張する千代は、山内家のために一豊の子を望みます。
ただ、千代はもう高齢なので
若い女にタネを授けてほしいと願っているわけです。
若い女を見れば、それを得ようと考える。
それこそが「男の中の男」の本能だと。
一豊はムッとして、頑に拒否します。
さらには「いらぬと言うたわしは、
男の中の男ではないと申すか」とまで言い、
二人の主張は平行線に。
お互いがお互いを思って、相反することを主張する。
内容こそ違えど、今の世にも起こりえる難しいことです。
淀から夜伽を拒絶された秀吉は、
誰からも相手をされずに、ひとり廊下をよろめいて進んでいきます。
諸行無常を感じるのは私だけでしょうか。
この日から秀吉は急に体調を悪化させていきます。
一豊・千代と家臣たちは、久々に掛川へ戻ってきました。
この機会に、せっかく掛川まで来たのだからと、千代は
美濃の不破家で一人で暮らす養母のきぬのところへ向かいます。
その日の夜。
千代は、目をつけた美津という女子に
一豊の相手をするように命じていたらしく、
美津は、その言いつけ通りに一豊の元にやって来ます。
「殿様のおタネを頂戴いたせとの
お方さまよりのご下命でござりまする」
まだ諦めていなかったのか──。
一豊は大きくため息をつきます。
千代は養母・きぬと久々に再会します。
突然の千代の訪問に、何ぞあったかと心配しますが
何も言わない千代をそれとなく気遣います。
ただ、理性では“山内家のため”と分かっていても
心がついていかないのが千代です。
美津が一豊に抱かれている妄想をしてしまった千代は
「もうっ……旦那さま!」と口走りながら
庭に飛び出て、小枝で竹をつつきまくります。
きぬは、目を丸くしてビックリしています。
でも、何があったか事情を深く聞かず
「何かあったら、また訪ねてきなされ」とだけ言っておきます。
千代が伏見に戻って10日後、
一豊ら一行も掛川から伏見へ戻ってきました。
そして、その一行の中に美津もいます。
美津に、あの日のことをそれとなく聞いてみますと
美津に指一本触れることなく、
夜通しで美津の故郷の話や千代の話をしてくれたそうです。
責め立てればいいやらでよくは分かりませんが、
千代の感情としては、よかったのかもしれません。
「康豊の子・国松が元服し次第、山内家の跡取りといたす」
一豊は決心します。
秀吉の時代が、終わろうとしていました。
自分の死後、家康が天下を狙って動き出すでしょう。
秀吉はそう確信しています。
秀吉は家康と利家を枕元に呼び、
力を合わせて秀頼を支えてくれるように頭を下げます。
そして、石田三成にも後を託して、ついに力尽きます。
遺言により、喪は伏されます。
死を隠すために、秀吉の亡きがらは
三成の手配で裏門からこっそりと運び出されます。
賑やか好きな者の野辺送りにしては、
あまりに寂しいものでありました。
秀吉の死が、内々に家康の耳に入ってきました。
「長かったぁ……」
家康は、待ち望んだその時を涙ながらに喜びます。
──────────
慶長3(1598)年8月18日
豊臣秀吉が伏見城にて薨去、享年62。
その数ヶ月後、明国との講和が成立──。
福島正則、加藤清正、小西行長ら諸将たちは
7年間ずっと明に渡って戦に明け暮れる日日でありまして、
くたくたぼろぼろの姿で戻ってきますが、
石田三成は、秀吉に代わって
そんな彼らに「ご苦労でございました」とあっさり。
正則は「ご苦労の言葉しか言えぬのか!」と激怒します。
領国に戻って戦塵を落とせと言われても
長期間にわたる朝鮮出兵により、酒はおろか兵糧一粒すらなく、
そんな彼らに茶の湯でもてなそうという三成の言動は
彼らの心情にさらに油を注ぐ結果となってしまいます。
北政所(寧々)は秀吉没後に出家し、「高台院」となって
大坂城西の丸に居を移しております。
山内一豊・千代夫妻は、そんな高台院を訪問します。
しかしそこには先客があり、
その御仁はナント豊臣家大老・徳川家康であります。
今の豊臣家の内部がそれに従っているかを考えると
家康は、ちと疑問に感じています。
とはいえ、それ以後の家康自身も
六男・松平忠輝と伊達政宗の娘との婚姻を結ぶなどして
諸大名の囲い込みを始め、秀吉の遺訓に背いています。
三成は、そんな家康の動きを「目に余る」と苦々しく思い
家康も、三成を愚臣と思っています。
ふたりの亀裂は、徐々に広がっていきます。
家康は、合戦の支度(の真似事)にとりかかります。
家康を詰問するか弾劾するかで豊臣方がもたついている間に
家康の元には、三成に不満を持つ者たちが続々と集まり出します。
その数日後、一豊たちは武装する家康屋敷を訪問。
家康を大老職から引きずり下ろそうとするわけですが、
秀吉から「秀頼を守れ」という
遺言を受けた家康を大老職から引きずり下ろすことは、
その遺言に背くことになるのではないか? とへそを曲げます。
すごすご戻らざるをえなかったわけですが、
ここでもう一人、秀吉の遺言を受けた
大老・前田利家の登場を願うわけです。
ただ、豊臣方にとって不運だったのは
慶長4(1599)年閏3月3日、
頼みの綱の利家が病没したことであります。
秀頼の領地である越前府中6万石を与える、とそそのかされて
堀尾吉晴が徳川方に寝返りました。
吉晴は一豊に手をつき、一豊は吉晴を問いつめますが
「これからの時代は家康」と、苦しい心中を吐露します。
それでも一豊は寝返るつもりはありません。
そんな中、福島・加藤・細川・黒田軍が三成屋敷を急襲。
その知らせを受け、三成屋敷に先に入った一豊は三成を救出。
三成に被衣を被せ、一豊の先導で船着き場へ向かいますが、
明らかに怪しい2人がいるというのに
大して気にしない(あるいは気づかない)急襲軍は
とてもとても愚かです(笑)。
ただ、小西行長屋敷や宇喜多秀家屋敷も急襲軍に囲まれたとあって
万策尽きたりと一豊はため息をつきますが、
三成はとんでもないことを言い出します。
「いや、家康の屋敷にかけこむ」
千代は、これから大きな戦が始まると予見します。
一豊の一声で、山内家の運命が決まります。
決断を迫られる一豊──。
──────────
慶長4(1599)年閏3月3日
大老・前田利家が病没。
徳川家康に味方する堀尾吉晴が会いに来ます。
お互い、しっくりこない対面となりますが、
長期間、豊臣秀吉の下で働いてきた同志です。
言葉は交わさなくとも、
相手の気持ちは少しは分かるつもりです。
一豊・千代夫妻と吉晴・いと夫妻は
胸の病で床に臥せっている中村一氏を見舞います。
一氏は、徳川にはへつらわぬ! という立場です。
ただ、病に伏せる今の状況を考えると、
近いうちに息子に家督を譲ることも考えなければなりません。
家康は大坂城の淀と豊臣秀頼に対面します。
淀は、佐和山城に蟄居させられている石田三成を
大坂に呼び戻すことを提案しますが、それには返答を避け、
今は伏見城に詰める自分が
これからは大坂城で政を行うことを宣言します。
慶長5(1600)年正月。
諸大名たちは秀頼に年賀の挨拶を済ませると
そのまま大坂城の西の丸に移動し、家康にも挨拶。
「まことに残念だのう」と皮肉っぽく言います。
そのころ、景勝の重臣・直江山城守は佐和山城を訪れ
家康を倒す手だてを話し合っています。
大老職でありながら、秀頼への年賀の挨拶に訪れないのは
いろいろな疑いをもたれる原因になるため、速やかに大坂へ。
その書状だけを景勝のもとに送ります。
5月。
景勝からの返書が来ましたが、
家康を怒らせるに充分な内容でした。
激昂した家康は「上杉を討つ!」と大声で宣言。
ただこれは、家康の罠でありまして
景勝が単にその罠に引っかかっただけであります。
ともかく、これで戦の大義名分ができました。
形勢が少しずつ動き始めていますが、
一豊としては、態度を決めかねています。
焦らずに天下の形勢をじっくりと眺めて
今後を決めればいいと励まします。
考えたあげく、一豊は
小夜の中山で家康を饗応することにします。
山内康豊は「ご決意なされましたか!」と喜びますが、
一豊が決めたのは家康への饗応であって、
徳川の味方になることではありません。
「城は恐ろしい」
安心して饗応を受けられる寺に案内した一豊に感謝しながら
ふと漏らした言葉であります。
今までも諸大名からの歓待を受けた家康ではありますが、
城に案内されてきた家康は、
いつ襲われてもおかしくない城に案内されるのは
あまり好きではないわけです。
とそこへ、一氏が病を押してやって来ます。
一氏は、一豊の饗応中の訪問という無礼を詫び
後から駆けつけた家康には、息子・一忠をお供にと願い出ます。
中村家をつぶすことはできない、というわけです。
「功名を立てよ」という言葉を一豊に残して
1ヶ月後、一氏は亡くなります。
──────────
慶長5(1600)年7月17日
中村一氏が病没。
徳川家康に対する山内一豊の歓待は続いております。
一豊としても、かつて金ヶ崎の退き陣で
槍傷を負った自分を助けてくれた家康に
大恩を感じています。
それでも、と苦しい胸中を吐露する一豊に
家康は「どちらに味方しても一切怨みませぬ」と
優しく声をかけます。
家康と石田三成の溝が決定的になってきました。
佐和山城で、策を練りに練った石田三成が
満を持して大坂城へ乗り込みます。
千代は、山内家にいる者たち全員で
掛川城へ避難することにします。
すっかり耳が遠くなった祖父江新右衛門は
耳に手を当て「はっ?」と聞きかえしますが、
新右衛門殿こそ足手まとい、と小声でささやいた
吉蔵のセリフは、なぜかしっかり届いています。
「ワシを愚弄するか!」
三成がいま一番欲しいのは、
細川忠興の妻・玉(ガラシャ)であります。
徳川方に近づきつつある細川家を石田方に引き込むには
もはやそれしか方法がありません。
三成は、13ヶ条からなる家康への弾劾状を諸大名に送りつけ
だからこそ三成方に味方せよ、というものであります。
その弾劾状に、ついに三成発つか、と騒然となります。
山内家へも同様に弾劾状が届けられるわけですが、
千代は、その弾劾状は開封せず、
そのまま一豊に回送させることにします。
近江生まれで足の速いものを新右衛門が探した結果、
田中孫作という農民が選ばれました。
演者の徳井 優さんも、実はお隣のスタジオで収録していた
連続テレビ小説『純情きらり』に
「山長」の番頭・野木山与一役に出演中で、
大加章雅チーフプロデューサーが目をつけたんだそうです。
大河ドラマ『徳川慶喜』のプロローグ部分でも
黒船を見て慌てふためきながらも
大砲で反撃しようとする役人を演じておられて、
「あぁ、こんな人は多分いるな」と思わせる演技が素晴らしく、
かつそれを短時間でやってのける俳優さんは
そうなかなかいらっしゃらないのではないかと思います。
千代から一豊宛の文は笠のヒモに編み込んでおり、
それとは別に、三成からの書状を油紙に包んで
「編み込んだ方を先にお読みいただくように」と
孫作に託します。
「必ず!」と力強い返事をし、孫作は出発。
新右衛門は、千代を早く逃がしたいわけですが
その前にやらなければならないことがある、と
硬い表情の千代です。
やらなければならないこと、とは
細川ガラシャの説得であります。
しかし、石田方に囲まれた暁には
それなりの覚悟があるそうで、
説得工作は失敗に終わります。
そしてついに、
細川忠興邸は石田方に囲まれました。
屋敷には火がかけられます。
ガラシャはキリシタンなので自害できません。
小笠原少斎に懇願して胸を突かれ
「アーメン」の言葉を最期に絶命します。
波乱の生涯を送った細川ガラシャの凄絶な死は
諸侯の妻子を人質にとり、大坂城下を掌握せんとする
三成の計画に大きな一石を投じるものとなりました。
ちりぬべき
時知りてこそ 世の中の
花も花なれ 人も人なれ
その辞世の句を受け取った細川幽斎は
戦支度に取りかかります。
下総・諸川の一豊の陣に孫作が到着しました。
千代がヒモに仕込んだ中に、
一豊に宛てた千代からの文が入っております。
──届けました包みの中に
石田三成殿からの書状がそのまま入っています。
封を切らずに徳川様にお渡しなさいませ。
もし石田様にお味方なされるなら、
包みの封を切り、大坂へお帰りくださいませ──。
決断の時。
三成の義をとるか、家康の利をとるか
山内家の存続を考えれば、利をとるしかありません。
徳川方に味方することにします。
──────────
慶長5(1600)年7月17日
細川ガラシャが大坂玉造の細川忠興屋敷で胸を突かれて死去。
山内屋敷に、増田長盛が派遣されます。
しかし千代としては何度訪問されても
山内一豊の意向に従うのみであります。
「力づくでお連れ申す」という長盛に、千代も応戦。
多くのかがり火とわらを用意して
力づくで屋敷に火をかけようとします。
三成は、諸大名の屋敷を取り囲む兵を撤退させ
奥方人質の件もなかったことにします。
下野国小山の徳川家康の陣に一豊が現れます。
一豊は、まだ封を切っていない
三成からの書状をそのまま家康に渡します。
三成方の有り様を、封を切らずに徳川方に知らせることで
徳川への忠節を表し誓ったもので、千代の機転であります。
自陣に戻った一豊を、相談したいことがある、と
堀尾吉晴の子・堀尾忠氏が訪ねてきます。
「もし家康が上杉討伐から三成攻めに転じ西に向かうときは、
浜松の城を空にし、一切の兵を引き連れて従え」と。
吉晴の考えは見上げたものだと一豊は感心しています。
大坂城では、毛利輝元を筆頭に
安国寺恵瓊や吉川広家、小早川秀秋が秀頼に挨拶します。
輝元や恵瓊は三成方と分かっておりますが、
広家は徳川方に寝返る可能性があり、
秀秋にいたっては、未だ態度を明確にしていません。
そんな中、迎えた小山評定。
秀頼を擁する三成を背きがたいと考える諸将、
大坂に人質を置いている諸将は
今すぐ小山の陣を払って国元に帰られよ、と
井伊直政が言い出しますが、
はいそうですか、と陣を払う者などいようはずもなく
皆が徳川に忠義を誓います。
家康は、福島正則を先頭に西へ進軍し、
清洲城で待機させることにします。
その間、家康は江戸に立ち返り、
東国への備えを万全にして清洲で合流することに。
吉晴に教えられた言葉を言うようこっそり催促しますが、
若年の至りか、言い出す勇気がないのか
もじもじとしてためらっています。
“掛川の領地も兵士も徳川方へ献上する”と
一豊が代わって言うのですが、
忠氏にとってはとんびに油揚げをさらわれる形になり、
一豊も吉晴の言葉をそのまま奪い取ってしまったので、
両者の間に少しだけしこりが残ってしまったようです。
めいめい、清洲城に集まり出します。
ただ、当初は8月あたまに家康が清洲入りする予定であったのに
8月半ばになっても家康は江戸から動こうとしていません。
福島正則はしびれを切らして暴れ出しますが、
家康の思惑としては……。
豊臣恩顧の大名たちがコロリと家康に寝返ったため
予定からわざと遅らせて、
その大名たちがまたもコロリと三成方に寝返るかどうかを
試して見てみたいわけです。
挑発を受けた者たちは、戦を始めます。
家康が到着するまでは戦がないと見込んでいた
大垣城の三成方は、もろくも崩れてしまいます。
その様子を見て、家康はようやく重い腰をあげ
江戸を出発します。
尾張で合流した家康は、もはや城攻めは無用とし
三成討伐にかかります。
三成も、家康を迎え撃つべくその戦場を関ヶ原に設定。
「いざ、関ヶ原へ」
両軍の思惑が入り乱れる戦場へ、
ついに動き出します。
──────────
慶長5(1600)年7月25日
家康は会津征伐に従軍した諸大名を招集し、軍議を催す。
いわゆる「小山評定」。
しかし毛利一族は3つに分裂しております。
三成派の安国寺恵瓊、家康に近い吉川広家、
そして無派閥の小早川秀秋。
一方の徳川家康は小山で評定を開き、結束──。
慶長5(1600)年9月14日・関ヶ原の合戦前夜。
雨が降る中、多くの騎馬隊・兵士たちが進軍中です。
ちなみに東軍の合い言葉は「山が山、麾(さい)が麾」。
合戦を前に、一豊は兵士たちに訓示します。
祖父江新一郎は
兵士たちにその合い言葉を大声で伝えますが、
合い言葉というもの、敵に知れてはならないものだけに
何度も何度も復唱しても大丈夫なんですかねぇ?
……と、いらぬ心配をしてみました。
一豊は、今回の関ヶ原の戦いが生涯最後の戦となると思って
全力で戦うつもりでいます。
そういえば、若かりし頃から
ともに戦ってきた堀尾吉晴はすでに隠居し、
中村一氏はすでにこの世にはおりません。
『関ヶ原は美濃国不破郡(ふわぐん)にあり、
北に伊吹山系、南に鈴鹿山脈、
西に今須山、東に南宮山がそびえる
東西およそ4キロ四方の盆地である。
中山道が東西を走り、
その中央から北国街道と伊勢街道が分岐する、
日本のへそともいうべき交通の要衝であった』
葵バージョン
(語り(水戸光圀):中村梅雀さん)
『関ヶ原は美濃国不破郡(ふわのごおり)に位置し、
かつては不破の関がござり申した。
北に伊吹山系、南に鈴鹿山脈が裾野を広げ、
西に今須山、東に南宮山をひかえて、
東西約4キロ、南北約2キロの高原盆地でござる。
その中を中山道が貫通し、
東は木曽路、西は近江より京・大坂へ通じ、
中央の分岐点より西北へ北国街道、
東南へ伊勢街道と、文字通り交通の要衝でござった』
即座に西軍勝利を断言したといいます。
三成も、完成した布陣を眺めながら
「間違いなく勝った」と信じていたでしょう。
山内軍は、南宮山の毛利勢の見張り役として布陣しますが、
新一郎はその扱いに不服面であります。
ただ、一豊は直前まで徳川に味方するかどうかを迷っていたので
そんな者に重要な役回りをさせられないという家康の考えには
一豊自身、一応は納得しています。
大坂の屋敷では
千代が手を合わせて一豊の無事を祈っています。
しばらくは両軍睨み合いが続きますが
午前8時、ついに戦闘が開始──。
毛利勢の抑えとして布陣した山内軍ですが、
六平太の情報によると、
実際の毛利勢の抑えは徳川寄りの吉川広家であります。
抑えとしての意味がないと感じた一豊は家康に直談判し、
出陣することにします。
実際に戦をしているのはわずか3割ほどでありまして、
毛利、島津、小早川らは動こうとしません。
毛利勢は、先頭にいる吉川軍が動かないために
その山の上にいる毛利本体が動けず、
島津は「貴殿の配下ではなか!」と
三成の説得にも応じず日和見をきめこみ、
そして小早川秀秋は高台院の言葉が頭をよぎり、
三成が約束した関白の座も悪くはないと迷っています。
そんな秀秋を説得する六平太ですが、
演者の香川照之さんのデビュー作は
大河ドラマ『春日局』での小早川秀秋役でしたね(笑)。
ついでながら、東軍の陣に参じた秀秋が
家康と対面するシーンがありますが、
家康役の西田敏行さんと、秀秋役の阪本浩之さんは
大河ドラマ『八代将軍吉宗』で、
徳川吉宗役(阪本さんは青年時代)をなさりましたね。
それを言い出せば、三成役の中村橋之助さんと
一豊役の上川隆也さんは親子役だったわけで、
こういう、時代を経た運命を感じられるから
大河ドラマっておもしろいのです( ^ ^)/
ともかく、家康に大筒を放たれたことで
ビックリした秀秋は石田勢に雪崩を打って突撃。
これで東軍・西軍の形勢は逆転します。
大谷吉継軍全滅、石田三成軍壊滅、
小西行長軍・宇喜多秀家軍総崩れ。
島津義弘軍敗走。
戦が始まって6時間、大戦の決着はつきました。
戦のあと──。
東軍の陣にやってきた秀秋を
武将たちは冷ややかに見ています。
福島正則は「見事な裏切りっぷりじゃのう」と皮肉たっぷりですが、
秀秋としては、自らの行動を正当化したいわけです。
大谷軍など畏れるに足りず! と大きな口を叩きます。
その働きを褒め讃えた上で、顔色を変えずに次の課題を出します。
「佐和山も攻めてはくださらぬか?」
佐和山とは三成の居城・佐和山城のことであります。
目が泳ぐ秀秋です。
そんな必死な秀秋に攻められて、佐和山城はついに落城。
三成は逃亡を図りますが、田中吉政に捕らえられます。
──────────
慶長5(1600)年9月15日
美濃国不破郡で東軍と西軍が激突、
世にいう「関ヶ原の戦い」で東軍の徳川方が勝利を収める。
徳川家康の元に届けられました。
翌朝、家康の元に参じた東軍諸将たちは
縄にかけられた権力者三成の無様な姿を見るのですが、
福島正則は三成をあざ笑い、
細川忠興は 妻のガラシャのことで何か言いたげでしたが
何も言わずに目礼して立ち去ります。
ただ、誰と会おうと平静を装っていた三成は
小早川秀秋の姿を見た時には、
激怒をはるかに越えて怒り狂います。
山内一豊は、自らの陣羽織を三成に着せかけますが
三成は、一豊の妻・千代が淀に気に入られていることを知り
一豊・千代経由で淀へ遺言を伝えてほしいと願います。
『たとえ徳川家康を頼ろうとも
豊臣家と秀頼様をお守りなされよ』
関ヶ原を終えた後から、一豊は
戦に勝ちはしたものの
戦に対して空しさを感じずにはいられません。
そんな一豊に、千代はいつものセリフを言いますが、
今回はトーンも表情も何もかも違ったものでした。
敗れていった者たちへの供養なのか、
夫婦は涙を一杯に浮かべながら、舞い、謳います。
合戦で勝利を収めた家康に恐れをなした大蔵卿局は
三成に味方したことは間違いであったと認める詫び状を
家康に送るように淀に言います。
しかし、淀はこれに反発。
家康も三成も豊臣家の家臣であり、
家臣同士の争いにすぎないわけです。
世間を騒がせて申し訳ない、と
家康から詫びられることがあったとしても、
こちら側から詫びることは何らありません。
そんな強情を張る淀に、千代が対面を願い出ます。
三成の遺言を伝えるためです。
関ヶ原合戦から2週間が経過した9月27日、
東軍の諸将たちは大坂城の淀と秀頼に対面。
家康からの言上を受けながら、淀は
三成の遺志を受け継ぐことを決意します。
淀は諸将たちに、秀頼への忠義を誓わせます。
対面を終え、廊下を下がる家康は
扇を床に投げつけて悔しがります。
10月1日、小西行長・安国寺恵瓊とともに
京の町を引き回された石田三成は、
六条河原の刑場の露と消えました。
関ヶ原の戦いの論功行賞が始まりました。
じきに呼び出された一豊には、
土佐一国202,600石への大出世となりました。
「千代にもろうた国じゃ」と微笑んだ一豊は
天の五藤吉兵衛に向かって一国一城となったことを報告し、
みんなで祝杯をあげます。
その中には、三成からの書状を一豊に届けるという
大業を成し遂げた田中孫作も呼ばれています(^ ^)
しかし、一豊と千代には知らされていない事実が……。
──────────
慶長5(1600)年10月1日
石田三成が六条河原で斬首される。
朝餉の準備のために台所に集まっていた侍女たちは、
土佐という土地に縁もゆかりもないために
鬼のような男が住んでいる、とか
大きな大きな魚が泳いでいて、その上を船で進むのは怖いとか
ちと間違った情報ばかりが伝わっているようにも思えます。
一豊は「土佐二十万石」と筆でしたためてみて、
それだけの大名になったのだと感慨深げです。
今まで豊臣秀吉の下で不遇なときを過ごしてきただけに
家康に味方して、家康が一豊の器量を認めてくれて
二十万石の大名にしてくれたのだと鼻息が荒いです。
千代はそれを聞きながら
ちと有頂天になっている夫が心配です。
一豊は井伊直政のところに通い詰め、
土佐入国に関する段取りについての質問をぶつけます。
つまり、今まで土佐を治めてきた長宗我部盛親が
いなくなるという意味です。
直政によれば、盛親は
徳川家康に詫びを入れて死罪は免れたようですが、
なかなか諦めが悪いようです。
長宗我部家の家臣たちは
「盛親に土佐の半分でも分け与えねば
新領主たる一豊に戦を仕掛ける!」
など、いうことを聞かないとか。
一豊は、直政のアドバイスに従って
弟の山内康豊を土佐へ先乗りさせることにします。
京の高台院の庵へ、淀がやってきます。
天下人たる豊臣秀頼の許しなく、
関ヶ原で東軍として参加した諸将たちに、豊臣家の土地を
家康が勝手に分け与えていることに我慢ならない淀は、
高台院にも「関ヶ原は豊臣の家臣同士の戦い」などと
持論を展開しますが、
高台院は静かに、しかし確実に淀を突き放します。
康豊と祖父江新一郎が大坂を出発、土佐へ。
土佐沖に着いた一行は、しばし沖合で足止めを食らいます。
浜辺をみれば、土佐の一領具足たちが
康豊たちを入国させまいと抵抗しているわけです。
康豊は、それはそれは大きな大きなメガホン(?)で
その抵抗こそが
大坂で浪人中の盛親の命を危うくさせるものだと伝えますが、
一領具足のリーダーたる奥宮弥兵衛は
かまわず船に向けて発砲、康豊の肩に命中します。
康豊は新一郎に、長宗我部家の重臣たちを説得させ
盛親の命が大事ならば、
歯向かう一領具足たちを成敗せよとの命令を下し、
重臣たちはやむなくそれを実行します。
次々に倒されていく一領具足たち。
こうして康豊たちは、やっとの思いで
土佐浦戸城に入ることができましたが、
これでも完全に抵抗を抑えきれたわけではありません。
一豊と千代の前に六平太が現れます。
改めて、山内家に召し抱えてほしいというわけです。
表向きは、いろいろな家へ仕えてきた経緯がありますが、
それもこれも すべては一豊と山内家のためであり、
一豊は、もしかしたら六平太の尽力で
20万石の大名になれたのかもしれません。
千代に山内家への忠義を誓った上で、
六平太が山内家の仲間に加わることになりました。
一領具足たちを刺激しないように
山内家一行は浦戸城にこっそり入城します。
これから土佐を一豊が支配していくためには、
新しい政治を行っていく必要があります。
まずは手狭な浦戸城の代替となる城の建築に取りかかります。
川に囲まれた内側、という意味で河中山城と名付けます。
一領具足から武士の身分を取り上げることにします。
これは一領具足から反発を買うのは必至ですが、
「初めこそが肝心」と、六平太も折れる様子はありません。
一豊にとっては、問題山積の土佐入国です。
土佐の海を眺めている一豊と千代ですが、
突然銃声が響き渡り、千代がその場に倒れ込みます。
千代を呼ぶ一豊の叫び声だけが、あたりに響きます。
──────────
ひとまず小屋へ避難する山内一豊と千代ですが、
なおも発砲の手が緩むことはありません。
発砲したのは奥宮弥兵衛とその小娘で、
捕らえられた弥兵衛は、他の一領具足への見せしめのため
六平太の先導で 磔の刑に処されることになりました。
それでも収まらない一領具足へは、
容赦なく銃弾を浴びせ──。
六平太による独断は、さすがに
山内康豊や祖父江新一郎、五藤吉蔵らの反感をも買いますが、
長宗我部の残党狩りに手間取っていることで
徳川家康に難癖を付けられる前に、
何とか片づけておきたいという六平太の判断です。
築城の許可を得るために大坂城へ出向いた一豊は
「鎮圧にちと時間がかかりすぎるのう」という
家康からの一言に背中を後押しされ、
完全鎮圧を目指すことにします。
そして彼らが相撲好きであることを利用して
相撲選手権(?)で一箇所に集めることにします。
慶長6(1601)年3月・土佐 種崎浜。
土佐国安寧のための相撲大会、という触れ込みで
集まった勇猛果敢な強者たちが70人以上集まりました。
屋敷を歩き回る千代は、
家臣たちが鉄砲の手入れに勤しむ姿に一抹の不安を感じ
六平太を探しますが、どこにもいません。
一豊は、今から起こる悲劇から目を背けるように
建築中の河中山城(後の高知城)に千代を案内します。
相撲好きな一豊が相撲を見ないという部分も
千代には不可解に感じたようです。
女の勘は、なるほどするどい。
高揚するような、太鼓が激しく乱打される中で、
たくさんの銃が火を噴きます。
その銃声は、千代の耳にもしっかりと届いています。
千代が今まで見てきたものが、線でつながった瞬間でした。
一豊は千代を引き止めようとしますが、
千代は顔色を失い、音のする方へ向かいます。
さっきまで威勢のいい声が響いていた相撲場は、
たくさんの死体が転がる凄惨な場所へ変わっていました。
その改めに新一郎と六平太が立ち会っていましたが、
死んだフリをしていた具足に不意討ちを受け、
新一郎は命を落としてしまいます。
まぁ、新一郎のすぐ真後ろで尋常じゃない声が上がって
新一郎も一応は振り返って、姿を見ているのですが、
かなりの間でボーッと突っ立っているだけで
あっけなくやられてしまうのはとても不自然でして(^ ^;;)
何だか、後ろから突き刺されるのを待っている、
そう感じました。
相撲場に入った千代の前に広がる、地獄絵図。
六平太は「ワシの仕事は終わった」と言い、
千代の前で毒を呑んで自害します。
「お前が……好きだ」という遺言を残して。
これが新しい山内家のまつりごとですか!
新しい山内家のやり方ですか!
私が逆らえば私もRということですか!
さんざんな言葉を一豊に浴びせ、
ポツリとこぼします。
「お暇をいただきとうございます」
──────────
河中山城(こうちやまじょう・後の高知城)の建築であります。
当時の居城で、長宗我部氏の居城だった浦戸城は、
今では坂本龍馬の像が太平洋を臨んで立っている
かの桂浜近くにあり、
三方を海で囲まれているがゆえに守りに固く、
一豊は、高知中心部の周辺の町を活性化させるべく
江ノ口川と洲江川の間の平地部を選んで
城を建築させたわけです。
高知の末長い繁栄を願っての町づくりでありましたが、
一方では、新領主・一豊の入国に反発した
一領具足たちへの弾圧を強めていきました。
これにより、一豊の幼い頃から
仕えてきた祖父江新右衛門の子・新一郎と
陰ながら山内家を支えてきた六平太をも失います。
功名を立て、出世するということは
それはそれは名誉なことではあるのですが、
その一方で、その代償も大きく。
一豊と千代の新たな闘いははじまったばかりです。
千代は苦しい胸の内を抑えきれません。
一領具足を倒さなければならないという目的は
千代でも分かるのですが、
一豊を信じて集まってきた者たちを
だまし討ちするようなやり方に憤慨しているのです。
千代は、一豊の出世を双六のように楽しんできた節があり
だからこそ、幾多の苦難を乗り越えてここまでこれたのです。
その“あがり”がこういうことであったとは……。
もはや、一豊とともに並んで歩んでいくことはできないと
千代は山内家を出て、
今回の一件で命を落とした者たちを弔うことを決意します。
山内家で養われ、後に仏門に入れた拾を京から呼び寄せ
弔いをさせるからと一豊は食い下がりますが、
新一郎や六平太の葬儀が終わると、
千代は山内家を出て吸江庵で暮らし始めます。
拾が京からやってきました。
仏門に入って湘南と名乗る拾は、もう16歳。
湘南が読経する横で、千代は手を合わせる毎日です。
一方で、新たな頭痛の種は薩摩島津です。
上洛を促してもなかなか出てくる気配がありません。
島津を怒らせれば黒田如水と必ず手を結び
加藤清正とともに上方へ押し迫ってくるでしょう。
ただ逆に言えば、長宗我部や島津といった牙を抜けば
如水もそうそう動けず、当面は安泰です。
そんな如水が、家康に対面を願い出ています。
家康は、関ヶ原合戦の時の混乱に乗じて
北部九州を平定してしまった如水を詰問しますが、
如水は「平定したは上様のため」とのらりくらりと返答。
大の字になってゴロ〜ンと寝転がります。
家康も、笑うしかありません。
この、家康をバカにした如水の所業は
さすがの家康でも許せず、激怒。
井伊直政に、自らの遺骸を西に向けて葬るように厳命します。
新右衛門は穏やかに、
それとなく千代に戻ってくるようにお願いしますが、
千代としては聞く耳を持ちません。
そこへ、一豊倒れるの報。
慌てて城に帰った千代は一豊の手を握り
精一杯の励ましの言葉を一豊にかけてあげますが、
次の瞬間、一豊はムクッと起き上がります。
山内康豊、五藤吉蔵、そして新右衛門らと結託した
千代への“だまし討ち”です(^ ^;;)
一豊は、種崎浜の一件について
話を聞いてほしいと千代に手をつきます。
種崎浜事件の計画を事前に千代が知れば、
身を盾にしてでも止めたであろうことは
一豊でも容易に想像できます。
であっても、一豊は千代を幽閉してでも
種崎浜事件を決行せねばなりませんでした。
山内家は、徳川の一大名として土佐で安寧に過ごしたい。
そのためには、いち早く土佐を平定する必要があったし、
如水の動きが怪しい今、長宗我部の残党を滅ぼすことで
何としてもその動きを止めなければならなかったわけです。
種崎浜事件は、山内家にとってずっと汚点となるでしょうが、
あの事件があったからこそ、大乱を防げたのです。
生き残った一領具足たちには土地を開拓させ
その土地は末代に渡ってその者の土地とすること。
そして年に一度は種崎浜事件の弔いをすること。
慈悲深い政治を行っていくことを一豊は千代に約束します。
慶長8(1603)年2月。
京 高台院の屋敷で、千代は高台院から
家康が征夷大将軍に任ぜられることを聞きます。
一方で、大坂城にも家康の将軍宣下は聞こえておりまして、
淀が福島正則にさっそく噛みついています。
そして3月、一豊と千代は完成した河中山城へ移ります。
一豊は、六平太、新一郎、そして五藤吉兵衛に
天守に立つ姿を見せてやりたかったと言いますが、
千代もまったく同じことを考えていました。
そんなことを話しながら、穏やかな表情だった一豊は
直後、徐々に顔色が悪くなります。
そして──昏倒。
──────────
千姫と豊臣秀頼の婚儀が大坂城で盛大に執り行われます。
千姫は、徳川家康の三男・徳川秀忠と淀の妹・江の娘で
当時はまだ7歳。
11歳の秀頼とは、いわば従兄妹同士であります。
8月・河中山城。
左手が動かぬ、と倒れた山内一豊は
千代の献身的な介護を受けています。
槍働きをすることもないでしょう、と
千代は一豊を励ましますが、
槍働きにおいては天下一品の賞賛を受けてきた一豊も
左手が動かぬとあっては「もはや要なし」と気落ちし、
食も次第に細くなっていきます。
動かなくなった左手の代わりになる、と言い出した千代は
「だんな様の左手より、よく動くやもしれませぬぞぉ」と
千代はいつも以上の明るさで一豊を笑わせています。
そんな折、医学の道を極めるために家を出ていた
祖父江徳心斎が一豊の元へ戻ってきました。
小娘に乱暴をもしていた徳次郎の、
立派に成長した姿に一豊も千代も目を細めます。
その徳心斎の診立ては……血の滞り。
つまり、とっても軽い脳梗塞?
お庭先などを努めてお歩きになるのがよろしゅうございましょう!
と元気よくふるまう徳心斎ですが、
血の滞りが再び頭の中に溜まった場合は
命に関わることになると、山内康豊に打ち明けます。
慶長10(1605)年4月、家康は
征夷大将軍の座を嫡子・秀忠に譲ってしまいます。
将軍の座をあっけなく子に譲ったことで、
世間的には徳川の時代であることを見せつけたわけです。
この時、秀忠役を演じた中村梅雀さんは
大河ドラマにおいて家康役の西田敏行さんと
平成7年『八代将軍吉宗』以来二度目の親子役であります。
(西田さん:徳川吉宗役/梅雀さん:徳川家重役)
ついでながら、梅雀さんが秀忠役を演じるのは
昭和60年『真田太平記』以来二度目であります。
おどおど挨拶する秀忠に家康は舌打ちですが、
秀忠の征夷大将軍就任という祝賀の場には、
さすがに豊臣秀頼の姿はありませんでした。
その参賀から土佐に戻った一豊は、
山内康豊の子で一豊の養子・山内忠義に
徳川家康の養女との婚儀がまとまったのを機に、
家臣たちを前に 豊臣との縁を切ることを宣言します。
今後、豊臣と徳川の間で戦が起ころうとも
迷うことなく徳川の味方をするように言った一豊は
その直後、またも昏倒します。
徳心斎の言ったとおりのことになりました。
一豊の脳裏を横切るのは
金ヶ崎、姉川、長篠、そして関ヶ原などといった
戦いの日日であったかもしれません。
それは千代と出逢って夫婦となったことが
開運のはじまりだったともいえそうです。
川から上がり、全身ずぶ濡れで
足を負傷し、脅えた眼差しでこちらを見る千代に
傷の手当をし、草蛙を履かせてやった一豊。
それが夫婦の最初の出会いでした。
「千代は、一豊様をお慕い申しております!」
「千代殿を、好いておりまする!」
「千代は生きて、一豊様の妻になりとうございます!」
「生涯、大事にいたしまする!」
世の中の動きを見極めねば一国一城の主にはなれませぬ、と
しゃもじ片手に力説したかと思えば、
夫の背中を冷水で流し(^ ^;;)
夫の大事にと千代が貯め込んだ黄金10両を
一豊が握りしめて
名馬を買いに行ったこともありました。
どれも、まるで昨日のことのようです。
ゴクリと飲んだ一豊は、そのまま意識をなくします。
千代の横顔が、とても美しいです。
──翌朝。
一豊の隣で横になっていた千代は
一豊が冷たくなっているのに気づきます。
「だんなさまぁ!」
千代の叫び声が、空しく響き渡ります。
千代は落髪し、見性院となりました。
慶長11(1606)年の秋。
土佐を去った見性院は京の庵で暮らします。
見性院としては一線から退いたということで、
ある意味、世間とは隔たった暮らしをしているつもりですが、
否が応にも情報は耳に入ってくるものです。
家康は前々から秀頼に臣下の礼をとるように迫っていましたが、
淀がその都度 はねつけて拒否していました。
しかし家康は、今度ばかりはその拒否を認めようとしません。
認めなければ、戦です。
見性院は大坂城の淀のところへ赴きます。
二条城へ赴けば、主君が家臣に従ったも同じことと
淀はとても立腹しますが、
高台院や見性院の意見を聞き入れて
秀頼を二条城へ送ることにします。
家康から見れば、
秀頼は想像以上に“立派に”成長しすぎました。
それが逆に、豊臣家への危機感を募らせたと言っても
過言ではありません。
それからの家康は、あの手この手で淀を責め立てます。
慶長19(1614)年11月、大坂冬の陣勃発。
大坂城には、真田幸村や長宗我部盛親ら
関ヶ原の戦いで辛酸をなめた武将や浪人たちが集まり、
冬の陣に続く大坂夏の陣の二度に渡って
徳川軍を相手に捨て身の戦いを繰り広げます。
しかし運命は豊臣の味方はせず。
慶長20(1615)年5月8日、
淀は最後の最後まで“生”に執着しますが、
秀頼と一緒に、爆破された大坂城と運命をともにします。
その約1年後、病気によりついに力尽きます。
元和2(1616)年4月17日のことでした。
──だんなさま。
もう戦は終わりました。
乱世の末を、千代はだんなさまに代わって見届けました。
もう、この世に未練はありませぬ。
これより、戦で命を落とした者の魂を慰める旅に出ます。
“もうよい”とお思いになったら、千代を迎えにきてくださいませ。
だんなさまのおそばに、参りとうございまする──
見性院と一豊が初めて出会った、あの河原にも
旅の途中で立ち寄ります。
見性院の脳裏を横切るのは、
やはり一豊との最初の出逢いのシーンです。
その戦いの日日を、
手に手を取って生き抜いた
千代と一豊の生涯も終わった。
それから今日まで、幾度も時代の扉は開き
変革の嵐は吹き荒れた。
そしてそのたびに、人々は心から平和を願った。
しかし、人の世に戦の尽きることはない──。
あの世で、
若い一豊と若い千代が再び出逢いました。
一豊は千代をおぶって、海辺を歩き出します。
永遠の夫婦。
新たなる二人三脚のはじまりです。
── 完 ──
桶狭間の戦い
【第2回】
戦勝に湧く清州城下に何気に光秀登場
木下藤吉郎と寧々の祝言
竹中半兵衛、織田軍を撃退す
【第3回】
木下藤吉郎、墨俣築城に成功
信長は藤吉郎を500石とし、「秀吉」という名前を与える
山内一豊、秀吉の与力となる
竹中半兵衛、たった16人で稲葉山城乗っ取りに成功(後に斎藤竜興に返却)
【第4回】
竹中半兵衛、秀吉の直臣(&軍師)となる
織田軍、堀尾茂助の案内で稲葉山城への裏道から進攻する
稲葉山城落城
不破市之丞、一豊と千代の婚儀に同意する
信長、家臣団を連れて美濃に引っ越し
一豊、50石取りとなる
一豊と千代祝言
【第5回】
稲葉山城を岐阜城と改めた信長は「天下布武」を印とする
お市、浅井長政に嫁ぐため岐阜を出発し、北近江・小谷城へ向かう
浅井長政とお市の婚礼が盛大に行われた
(濃姫と光秀は従妹である、との設定)
幕臣として岐阜城にやって来た光秀に信長はぽ〜んと5千石与える
永禄11(1568)年7月25日、ついに足利義昭が岐阜に入った
一豊たちは六角攻めの先陣を命じられた
織田勢は総勢6万もの大軍
永禄11(1568)年8月5日、一豊と吉兵衛、新右衛門、それに初陣の新一郎は大家族が見守る中、出発
【第7回】
永禄11(1568)年10月18日、
朝廷から将軍宣下を受けて足利義昭が第15代将軍に就任。
上洛を果たしてくれた信長にやれ副将軍だ、やれ管領だと褒美を与えようとしますが、信長はそのいずれも拒否。
断り続けるのもアレなので、堺・大津に代官を置くことの許しだけを得ます。
越前の朝倉義景を攻撃し、金ヶ崎城の朝倉景恒を下す。
一豊、三段崎勘右衛門を討ち取る
市から信長への陣中見舞い
信長、退却を決意。秀吉軍がしんがりとなる
【第9回】
金ヶ崎の退き口
杉谷善住坊、信長を狙撃す
【第11回】
元亀2(1571)年9月12日、
信長が比叡山延暦寺を焼き討ちする。
三段崎を討ち取った手柄により、一豊、知行200石に加増
【第10回】
姉川の戦い
【第11回】
元亀2(1571)年9月12日、
織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちする。
【第12回】
元亀3(1572)年7月、信長は
浅井への備えとして虎御前山に砦を築く
三方ヶ原の戦いで徳川家康は武田軍に惨敗
信玄死去
足利義昭挙兵
室町幕府滅亡
天正元(1573)年9月1日
浅井長政が小谷城で自刃して果てる
お市と子供たち信長の陣へ行く
浅井万福丸、関ヶ原で磔刑
秀吉は小谷城と北近江三郡12万石を与えられる
姓も、丹羽長秀の「羽」と柴田勝家の「柴」から羽柴とし、
羽柴筑前守秀吉と名乗ることになる
一豊、近江唐国400石に所領を与えられる
浅井長政、久政、朝倉義景の髑髏(しゃれこうべ/どくろ)で信長たち酒を飲む
【第14回】
秀吉の妹・旭、尾張から長浜城へ移る
【第15回】
特記事項なし
【第16回】
天正3(1575)年5月21日
長篠の戦いで織田徳川連合軍が武田の騎馬隊を打ち破る。
千代の叔父・不破市之丞(不破重則)病死
【第17回】
千代、女の子(よね)を産む
秀吉軍、北陸戦線から無断撤退す
信長の逆鱗に触れた秀吉、連日祝宴を催す
松永久秀が謀反。秀吉軍は松永討伐に向かう
平蜘蛛の釜に火薬を詰めた久秀、 それに火を投じて爆死
信長、秀吉を中国征伐の総大将とす
三木城の別所長治が毛利方へ寝返る
【第19回】
明智光秀は愛娘・玉と 細川藤孝の嫡男・細川忠興との婚儀を信長から命じられる
忠興と玉との婚礼の儀
荒木村重が毛利に寝返る
秀吉、摂津有岡城に行き、村重を説得する
光秀、摂津有岡城に行き、村重を説得する
黒田官兵衛、摂津有岡城に行き、村重を説得しようとするが
捕らえられ有岡城内の牢に入れられる
安土城天守が完成
竹中半兵衛、三木城攻めの最中に陣没
黒田松寿丸イベント
信長は松寿丸を殺せと命令するが、松寿丸は密かにかくまわられる
黒田官兵衛が殺されなかったのは、村重も官兵衛もキリシタンだったから
荒木村重、有岡城から単身逃亡す
城内の黒田官兵衛救出される
信長、松寿丸が生きていたと知り、官兵衛に合わせてやれ、と命令す
兵糧攻めが続いている三木城の別所長治が降伏
長治と重臣たち切腹
1年10ヶ月ぶりに三木城の包囲が解かれる
石山本願寺が降伏、信長、畿内を平定す
信長、林通勝と佐久間信盛を織田家から追放す
一豊、千代に貰った黄金10両で馬を買う
【第22回】
秀吉、高松城水攻め開始
信長の武田攻めで、快川紹喜和尚焼死
光秀は備中への出陣の途中で愛宕山へ登る
【第23回】
本能寺の変
光秀の友・細川藤孝は頭を丸めて幽斎と名を改め京での出来事を秀吉に知らせる書状を送る
備中高松城城主・清水宗治切腹。秀吉「中国大返し」開始
【第24回】
山崎の戦い。光秀敗死
細川忠興、ほとぼりが冷めるまで丹後の山奥に玉を幽閉することにする
織田信孝はお市に柴田勝家に嫁ぐように言う
清洲会議
三法師の後見となった秀吉は、織田家の実権を握ることに成功
お市、柴田勝家に嫁ぐ
秀吉、京の大徳寺で信長の葬儀を盛大に催す
長浜城主・柴田勝豊、秀吉に寝返る(秀吉に降伏)
【第26回】
秀吉軍7万5千の大軍は滝川一益を討つべく伊勢路へ
五藤吉兵衛為浄が伊勢亀山城の戦いで城内一番乗りを果たし、討死
【第27回】
秀吉は勝家に対抗すべく出陣する
賤ヶ岳の戦い。柴田軍の佐久間盛政中入り失敗
秀吉軍、北ノ庄城を包囲
茶々・初・小督の3人の娘、城から救出される
勝家、お市自害
賎ヶ岳の戦いの論功行賞が近江坂本城で行われる
一豊にわずか300石を加増(一豊3千8百石取りとなる)
同僚の中村一氏は2万石に加増、岸和田城主となる
堀尾吉晴は1万7千石に加増、若狭高浜城主となる
【第29回】
秀吉は大坂城の築城を開始する
「正四位下 左近衛権中将」
という位を秀吉は家康に与え、それでも家康が上洛に応じないので
「従三位参議」という秀吉よりも高い位を家康に与えます
しかし、家康は礼状を寄越すのみ
小牧・長久手の戦い
中入り戦法を狙った秀次軍、総崩れ
一豊、長浜2万石に加増、城持ち大名となる
討死した五藤吉兵衛為浄の弟・五藤吉蔵為重、山内家の家老となる
秀吉、関白となる
秀次、叔父・秀吉の命で近江八幡城主となり、
その宿老として、一豊・堀尾吉晴・中村一氏がつけられる
放浪していた一豊の弟・康豊が長浜城へ来る
玉、秀吉の計らいで謹慎を解かれ、宮津城へ戻る
秀吉、大坂城の金銀を散りばめた贅を極めた一室を茶々に与える
【第31回】
天正13(1585)年11月29日
天正の大地震で長浜城が全壊し、山内一豊の娘・よねらが事故死
【第32回】
秀吉は、妹の旭を 「家康の正室」として送り込むことにする
旭の夫・副田甚兵衛、5万石を蹴り、浪人となる
大坂城を発った旭一行が浜松に到着
秀吉の母・なかも浜松へ行く
ついに折れた家康、大坂城に到着
陣羽織イベント
天正14年7月17日(1586年8月31日)
母・法秀尼、一豊・康豊兄弟の仲を案じながら死去
天正15(1587)年6月19日
キリスト教宣教と南蛮貿易に関して豊臣秀吉が禁制の文書を発令
玉は洗礼を受けてガラシャとなっているが、
秀吉の伴天連追放令は、ガラシャの生きる道を徐々に狭めてゆく
山内家屋敷の目の前に捨てられていた男の子を千代がひろい、
山内家で育てることにする
【第34回】
天正16(1588)年4月14日
聚楽第に後陽成天皇が行幸
秀吉は、次の天下人は黒田官兵衛であると座興で言う
小田原北条攻め
秀吉・家康の関東の連れしょん
一豊は遠江掛川5万石に加増
中村一氏は駿府14万5,000石、
堀尾吉晴は浜松に12万石
家康は関八州240万石
豊臣秀長が病没
天正19(1591)年8月5日
豊臣鶴松が大坂城で病没、享年3
【第36回】
肥前名護屋城を拠点に、明国討ち入りの計画を進める秀吉は、
寧々の進言もあり、秀次に関白職を譲る
文禄2(1593)年8月3日
豊臣秀頼(拾)が大坂城で誕生
関白秀次の立場は、次第に悪化してゆく
秀吉は中村一氏に、秀次を伏見へ出頭させるように一豊に伝える
もし応じなければ、一豊もその謀反に加担したものとみなすと秀吉にしては厳しい要求
【第38回】
秀吉と対面した秀次は関白職を返上することを宣言
その上で、朝鮮出兵の取りやめを太閤秀吉に具申
文禄4(1595)年7月15日
豊臣秀次が高野山青巌寺で切腹、享年28
京・三条河原刑場で、秀次の妻子39名が惨殺
棄て児・拾(のちの湘南宗化)、山内家から寺に送られる
【第39回】
豊臣秀吉は、わずか4歳の拾を元服させ、名を「豊臣秀頼」と改めさせる
「康豊の子・国松が元服し次第、山内家の跡取りといたす」と一豊は決心する
慶長3(1598)年8月18日
豊臣秀吉が伏見城にて薨去、享年62
【第40回】
慶長4(1599)年閏3月3日
大老・前田利家が病没
七将襲撃事件
慶長5(1600)年正月。
諸大名たちは秀頼に年賀の挨拶を済ませると
そのまま大坂城の西の丸に移動し、家康にも挨拶
一豊は小夜の中山で家康を饗応する
慶長5(1600)年7月17日
中村一氏が病没
【第42回】
石田三成、大坂城へ乗り込む
三成は、13ヶ条からなる家康への弾劾状を諸大名に送りつける
慶長5(1600)年7月17日
細川ガラシャが大坂玉造の細川忠興屋敷で胸を突かれて死去
一豊、利と義で悩んだ末、徳川方につくことを決断す
【第43回】
一豊は、まだ封を切っていない三成からの書状をそのまま家康に渡す
小山評定
一豊は「掛川の領地も城も徳川方へ献上する」と発言する
【第44回】
関ヶ原の戦い
吉宗とはざっと数えて13人被ってる。
いっその事脚本ジェームスにすればよかったのに。
千代の「内助の功」についての記録は
『山内家史料』の『一豊公記』や同時代の史料には出ていない。
ただ、新井白石の『藩翰譜』・室鳩巣『鳩巣小説』・湯浅常山『常山紀談』に登場するところから、
江戸中期にはこの逸話は成立していたと思われる。
慶長6年(1601年)に領地を掛川から土佐に移封となり浦戸城に入城する。
大幅な加増があり余所から入部してきた大名は、
ただでさえ人手も足りなくなるので地元の元家臣を大量に雇用するのが常であったが、
一豊は重要なポストを外部からの人材で固め、旧長宗我部遺臣を雇用するどころか敵視したので、
一領具足を中心とした旧長宗我部氏の武士の多くは新領主に反発し土佐国内で多くの紛争が起きた。
これに対し一豊は種崎浜での討伐などあくまで武断措置を取ってこれに対応した。
この為に命を狙われる危険性があり、築城の際などには5人の影武者と共に現地を視察した(影武者の存在などは機密事項であったため通常記録には残らないが、一豊の場合には明記されている稀有な事例)。
各地にくすぶりを残しこの課題は次代から幕末になるまで引き継がれ坂本龍馬などの人物が生まれることになる。
また、高知平野内の大高坂山に統治の中心拠点として高知城を築城し(奉行は関が原の戦いの後浪人となった百々綱家を招聘、慶長8年完成)、
城下町の整備を行った。また、このころに官位が従四位下土佐守に進んでいる。
慶長11年(1605年)高知城にて病死。享年61。法名は大通院殿心峯宗伝大居士。墓所は高知県高知市天神町の日輪山真如寺の山内家墓所や京都市右京区花園妙心寺町の正法山妙心寺大通院。
高知城には、騎馬姿で槍を持った銅像が存在する。
※日付=旧暦
1573年(天正元年)、近江国唐国(滋賀県虎姫町唐国)に400石を領す。
1577年(天正3年)、播磨国有年(兵庫県赤穂市有年)に700石を加増。時に、合計2700石領す(石高総計については異説あり)
1582年(天正10年)9月25日、播磨国印南郡(兵庫県南部地域)に500石を加増。
1583年(天正11年)8月1日、河内国禁野(大阪府枚方市禁野本町あたり)に361石を加増。
1584年(天正12年)9月、近江国長浜城主となって、5000石を領す。
1585年(天正13年)6月2日、若狭国高浜(福井県高浜町事代)城主となって19870石を領す。
8月、豊臣秀次の宿老となる。
閏8月21日、近江国長浜城主となって2万石を領す。
※1585年(天正13年)9月から1586年(天正14年)4月の間で正五位下対馬守に叙任(『一豊公記』)。
なお、豊臣家臣で一豊と同格の人物の多くの官位の人物は当時従五位下が多いため、
正五位下ではなく、従五位下の誤記ではないかとの説もある。
1594年(文禄3年)9月21日、伊勢国鈴鹿郡(三重県鈴鹿市)で1000石加増。
1595年(文禄4年)7月15日、遠江国内の豊臣秀次所有の蔵入地より8000石を加増。
1600年(慶長5年)11月、土佐国内9万8,000石(後の検地で20万2,600石)を領有する大名となる。
1603年(慶長8年)3月25日、従四位下に昇叙し、土佐守に転任する(『徳川実紀』)。
1605年(慶長10年)9月20日、卒去。
1919年(大正8年)11月15日、贈従三位。
信長の死後もそのまま秀吉の家臣として活躍した。
天正11年(1583年)の賤ケ岳の戦いでは、
その前哨である伊勢亀山城(三重県亀山市)攻めで一番乗りの手柄をあげている。
また、翌12年の小牧・長久手の戦いの参加の際には秀吉から命じられて家康を包囲するための付城(前線基地)構築に当たっている。
この後秀吉の甥・豊臣秀次の宿老となり、天正13年(1585年)には若狭国高浜城主、
まもなく近江長浜城主となり2万石を領した。
この時期に同じく秀次の宿老に列した中に田中吉政・堀尾吉晴・中村一氏・一柳直末らがいる。
なお、同年に起こった天正大地震によって一人娘の与祢姫を失った。
このころ従五位対馬守に任官。
まもなく遠江国掛川に5万1千石の所領を与えられた。
掛川では城の修築と城下町づくりを行い、
更に洪水の多かった大井川の堤防の建設や流路の変更を、
川向いを領する駿府城主・中村一氏とともに行っている。
また、朝鮮の役には他の秀次の宿老格であった諸大名と同じく出兵を免れたが、
軍船の建造や伏見城の普請などを担当して人夫を供出している。
文禄4年(1595年)には秀次が謀反の疑いで処刑され、
一豊と同じく秀次付き重臣であった渡瀬繁詮はこの事件に関わって秀次を弁護したために切腹させられた。
しかし、一豊は他の宿老の田中・中村・堀尾らとともに無関係の立場を貫き、連座を免れた。
このときに秀次の所領から8千石を加増されている。
家康の留守中に五奉行の石田三成らが挙兵すると、東軍に与している。
この最中、一豊は、下野国小山における軍議で諸将が東軍西軍への去就に迷う中、
真っ先に自分の居城である掛川城を家康に提供する旨を発言し、
その歓心を買っている。
この居城を提供する案は堀尾忠氏と事前に協議した際に堀尾が提案したものを盗んだといわれる(新井白石『藩翰譜』)。
ただし、東海道筋の他の大名である中村一氏が死の床にあり、
同じく忠氏の父堀尾吉晴も刺客に襲われて重傷を負うなど老練な世代が行動力を失っているなかで、
周辺の勢力が東軍につくよう一豊が積極的にとりまとめていたことは事実である。
三河国吉田城主の池田輝政などもこの時期、一豊とたびたび接触しており、なんらかの打ち合わせをしていると考えられる。
関ヶ原の戦い本戦では毛利・長宗我部軍などの押さえを担当し、
さしたる手柄はなかったものの、戦前の功績を高く評価され、
土佐国一国・9万8千石(太閤検地時に長宗我部氏が提出した石高、のちに山内氏自身の検地で20万2,600石余の石高を申告)を与えられた。
URL貼れないから
メーンズガーデン ってググってみて
※正しいサイト名は英語。
荒木村重は秀吉より先に茶会を許されていた
役者と演出や音楽はかなり良かった、
ホームドラマが多用された脚本に難があった作品なので
もし脚本がジェームスだったなら希代の名作だったろう。
平成6年(1994年)結成。
旧土佐藩に当たる高知市では、読みについては現・山内家(元侯爵)口伝(史料、系図、家臣に与えた偏諱も同様)により「やまうち かつとよ」である。
ジェームスだったら変に畏まった出来だっただろうから、大石で良かったわ
中国の動画サイト(youkuなど)で探すのがよろしいかと
当初、時代考証の小山田先生が「本能寺で信長は鉄砲使った記録は史料に無いから使わない」という意見を、
脚本家らは「その日鉄砲が本能寺に一挺も無いと書かれた史料は見たことありますか?」という意見があって、
結局銃撃戦が繰り広げられるシーンになったけど、あとで他の研究者やファンに散々叱られてトラウマになったんだって。
さすが「仏の堀尾」
平成以降の大河なら、同じ時代を扱っているコミカルホームドラマ大河として
「功名が辻」という作品があったが、こちらの方が時代のダイナミズムが描かれ
登場キャラの造形も面白く、各人物たちも生き生きと動き回っていた…正直、今の
真田丸と比べたらとても判り易く、それでいて歴史の流れが良く判る作りだった
関白になると関白諸大夫を周りに十二人置く慣例
偉くなると酒の相手も偉くしないと駄目なんだな
諸大夫十二人
中村式部少輔一氏 生駒雅楽頭政勝 小野木縫殿助重勝 尼子宮内少輔晴久
因幡兵庫助 柘植左京亮 津田大炊頭 福島左衛門大夫正則
石田治部少輔三成 大谷刑部少輔吉継 古田兵部少輔重恒 服部采女正
視聴率は落ちてたかもしれんが。
実に妖艶な演技で、素晴らしかった。
かわいいだけじゃない。
それ以来、僕の中で淀の基準は永作博美になってしまい、
なかなかそれを超える女優が現れない。次点で「江」の宮沢りえ。
「真田丸」の竹内結子はどうなるか?
静かに生涯を閉じられるようにと・・・』淀(NHK大河ドラマ功名が辻)
功名が辻とか独眼竜だと三成がそれに近いポジな感覚だけども。
でも、あの押し花はきりちゃんにフラグぶち折られたからなあ・・・。
秀次様が不穏。
「功名が辻」の時に山内一豊が初めて城主になった土地、
「江」の時に江の出身地
「天地人」の時に石田三成の出身地
「軍師官兵衛」の時に黒田氏発祥の地
と騒いでいた
国盗り物語・・・太地喜和子
黄金の日日・・・十朱幸代
おんな太閤記・・・佐久間良子
徳川家康・・・吉行和子
独眼竜政宗・・・八千草薫
春日局・・・香川京子
信長 KING OF ZIPANGU・・・中山美穂
秀吉・・・沢口靖子
葵徳川三代・・・草笛光子
利家とまつ・・・酒井法子
武蔵MUSASHI・・・小林由利
功名が辻・・・浅野ゆう子
天地人・・・富司純子
江・・・大竹しのぶ
軍師官兵衛・・・黒木瞳
真田丸・・・鈴木京香
島田正吾 『太閤記』テレビシリーズ・昭和40年
三島雅夫 『お吟さま』テレビシリーズ・昭和43年
志村 喬 『大坂城の女』テレビシリーズ・昭和45年
志村 喬 『お吟さま』映画・昭和53年
鶴田浩二 『黄金の日日』テレビシリーズ・昭和53年
内藤武敏 『おんな太閤記』テレビシリーズ・昭和56年
藤田まこと 『時代劇スペシャル 千利休とその妻たち』テレビ単発・昭和58年
池部 良 『独眼竜政宗』テレビシリーズ・昭和62年
三国連太郎 『利休』映画・平成元年
三船敏郎 『千利休 本覚坊遺文』映画・平成元年
田村高廣 『千利休 春を待つ雪間草のごとく』テレビ単発・平成2年
平幹二朗 『獅子を飼う 利休と秀吉』舞台・平成4年
伊藤孝雄 『信長』テレビシリーズ・平成4年
岸部一徳 『豊臣秀吉天下を獲る』テレビ単発・平成7年
米倉斉加年『影武者織田信長』テレビ単発・平成8年
仲代達矢 『秀吉』テレビシリーズ・平成8年
古谷一行 『利家とまつ 加賀百万石物語』テレビシリーズ・平成14年
林 与一 『大友宗麟〜心の王国を求めて〜』テレビ単発・平成16年
鈴木宗卓 『功名が辻』テレビシリーズ・平成18年
平幹二朗 『GOEMON』映画・平成21年
神山 繁 『天地人』テレビシリーズ・平成21年
小日向文世(声) 『歴史スペシャル 揺るぎなき先人〜千利休』テレビ単発・平成22年
石坂浩二 『江〜姫たちの戦国』テレビシリーズ・平成23年
市川海老蔵 『利休にたずねよ』映画・平成25年
大和田獏 『信長のシェフ』テレビシリーズ・平成25年
伊武雅刀 『軍師官兵衛』テレビシリーズ・平成26年
佐藤浩市 『花戦さ』映画・平成29年
2011年3月18日の会見で東電の小森常務は、こう発言したあと泣き崩れた。
食べて応援させられたのか?大塚アナから始まって麻央まで芸能人が次々に癌白血病心筋梗塞で倒れてゆく
ディーン・フジオカ、体調不良
元SOFT BALLET/現minus(-) の森岡賢が、心不全。6月3日死去。
俳優集団「D―BOYS」の高橋龍輝(23)引退 23歳の芸能人で、体調不良って・・・
『進撃の巨人』作画監督アニメーター杉崎由佳(享年26歳)5月28日死去。4月頃から、「頭が重たい」「歯が痛い」「服に血がめっちゃついているけど出血原因がわからん」
オノデキタ 今のYahoo画面。若い男性の骨折が1度に二つも掲載されている。
https://twitter.com/onodekita/status/720207084432699393
非御用学者 後々、健康被害が出たら、ウソを言った御用学者や政治家は、全員死刑だ。
https://twitter.com/Fibrodysplasia/status/363753995791114240
東 海アマ 副島隆彦・リチャードコ シミズ・中矢伸一・藤原直哉・鎌田實・江川紹子。全員、安全デマ吹聴に回った 。
https://twitter.com/tokai amada/status/592518352393764866
『放射能は安全です。福島の食べ物は安全です。』福島の中学生達が訴えていたのを見てゾッとした。
neko-aii 大人達に嘘を教え込まれ、自分達の命よりも 経済を優先されたと知った時、彼らはどれほど傷付き、未来に不安を持つのだろう
https://twitter.com/neko_aii/status/741970281774776321
千葉麗子 「科学的根拠も示さず福島には住めないなどと風評被害をまき散らしている」
名無し 食べて応援で人が何人死んだみたいな無茶苦茶なこと、福島県の人に対してよく言えるな…。見苦しい。
https://twitter.com/tok aiama/status/720726309240836097
リチャード輿水 「なぜ、福島が安全なのか、10月11日(日)のRK佐久講演を聞けば、全部、わかるよ。」
ベンジャミン フクシマが大変だ大変だって、あれはもうプロパガンダ、嘘八百なにもない。26分40秒〜
https://www.youtube.com/watch?v=KRd6O5bwN9M
1位:篤姫
2位:天地人
3位:功名が辻
初回視聴率トップ3
1位:天地人
2位:龍馬伝
3位:江
最終回トップ3
1位:篤姫
2位:功名が辻
3位:天地人
おんな太閤記と春日局
秀頼さんがラストに「母上の握りしめたその拳を開いて差し上げたかった」と言っていたのを思い出したんだけど、
確かに拳を握りしめ続けてる人は臨戦態勢だよなあっと。
ちゃんとそれが緩まる場所、人を得ている人は強いとは思う。
はるか昔に見た記憶のある大河ドラマはそういう印象ないんだけど本で読むと違うもんだ
悲しいなぁ
大河の主役で関ヶ原に参陣した武将は家康と一豊だけか。
↓
現実は高知包囲網で愛媛・香川・徳島に徳川親藩が配置され山内を囲んでた
『憲法改正国民投票法』、でググってみてください。
2017年10月22日(日)の国政選挙は、ぜひ投票に行きましょう。
平和は勝ち取るものです。お願い致します。☆☆
http://nhk2.2ch.sc/test/read.cgi/liveetv/1520131987/1-1000
耐震性はあっても、アメリカって高知県と同じで
過去の大津波の記録がないから、津波くるとヤバいんじゃない?
シアトル近郊は、地震と津波がくる湿地帯だからという理由で原住民住んでなかったはず。
高知県がヤバいのは長宗我部氏が滅ぼされた恨みで過去の津波記録を破棄したんだよね。
宇和島とか丸亀とか四国の城は津波を避けるために山城ばかりなのに、
山内一豊は津波なんて考えず海沿いに町を築いちゃった。
アメリカや高知に311並みの千年に一度の津波がくると、どこまで被害が及ぶかは未知数。
この前も功名が辻を横目で見てたんだが、長沢まさみが出てきて「わ〜い、切れ切れ〜♪」とはしゃぐシーンがあった
このシーンが無茶苦茶かわいかったんだが、これって何話のどのシーン?
グロ
25